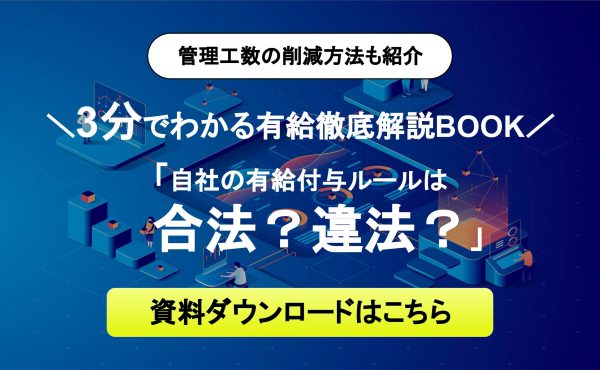有給休暇は条件を満たしたすべての従業員に対して、法定の日数分を付与しなければなりません。また、2019年4月に労働基準法が改正され、有給休暇の年5日取得が企業に義務付けられました。本記事では、有給休暇の発生要件や義務化で企業が対応すべきこと、日数の計算方法について詳しく解説していきます。
関連記事:有給休暇を使うと給料の金額は減る?金額の計算方法やパート・アルバイトの有給休暇について解説
関連記事:有給は実労働時間ではない!残業代に及ぶ影響を詳しく解説
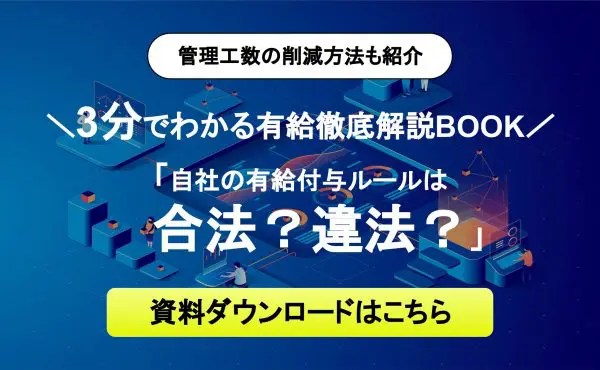
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 有給休暇とは

有給休暇(年次有給休暇)とは、従業員が心身の疲労を回復するために付与される、取得しても賃金が支給される休暇のことです。企業は、一定の要件を満たす従業員すべてに有給休暇を付与する義務があります。
まずは、基本的なルールや、法律に違反した際の罰則を振り返っておきましょう。
1-1. 有給休暇は法律で定められた従業員の権利
有給休暇は、労働基準法第39条によって以下のように定義されています。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。
企業は、一定の要件を満たす従業員に対して有給休暇を付与する義務を負います。従業員にとって、有給休暇の取得は当然の権利です。
有給休暇は、従業員の心身の回復やリフレッシュを目的としており、要件を満たした従業員に対し、継続勤務年数や週所定労働日数に応じた日数を付与しなくてはなりません。有給休暇は1日単位で取得するのが一般的ですが、半日単位での取得を認めている企業もあります。
また、労使協定を締結すれば、時間単位での取得も可能です。ただし、時間単位の取得は年5日までと決められています。なお、有給という名前の通り、休暇ですが賃金が支給されます。支給額の計算方法については「5. 有給休暇の金額の算出方法~6割の根拠とは~」で詳しく解説しますので参考にしてください。
1-2. 有給?有休?それとも年休?有給休暇の正しい意味と略し方とは?
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」で、その意味は、取得しても賃金が減額されない休暇です。
一般的に、年次有給休暇は有給休暇と呼ばれ、有給・有休・年休などと省略されます。それぞれの意味は以下の通りです。
| 意味 | |
| 有給 | 有給休暇の省略、給与があること |
| 有休 | 有給休暇の省略 |
| 年休 | 年次有給休暇の省略 |
上記から、有給休暇を省略する際は有給・有休・年休のいずれを使っても問題ないことがわかるでしょう。
「有給」は、有給休暇の省略以外にも「給与があること」を意味します。使用例としては、「有給の社外研修を受講する」のようになります。そのため、より正確性が高いのは「有休」「年休」ということになります。育児休暇を「育休」と省略するのと同じです。
有給休暇の略し方には決まりがありません。どのように省略するかは、企業の慣例に合わせるのがよいでしょう。
1-3. パート・アルバイトの従業員にも付与が必須
有給休暇の付与対象者は、正社員のみならず、パートやアルバイトの労働者も含みます。有給休暇の付与要件を満たしていれば、すべての従業員が有給休暇を取得する権利を有するので、パートやアルバイトの従業員だからといって有給休暇を付与しないのは違法となります。
有給休暇の付与要件は「 3. 発生要件と付与のタイミング」で詳しく解説しますのでチェックしておきましょう。
1-4. 管理監督者にも付与する必要がある
有給休暇は、管理監督者にも付与しなければなりません。
管理監督者には、残業手当や休日出勤手当を支給する必要がないため勘違いされがちですが、有給休暇については一般の従業員と同様に付与する必要があります。
1-5. 有給休暇の繰り越しと繰越日数の上限
週5日以上働いている労働者には、毎年10~20日の有給休暇が付与されます。この有給休暇は、もし使用しきれなかった場合でも、付与日から2年間は繰り越して利用することができます。
たとえば、2021年10月1日に付与された12日分の有給休暇のうち、5日間を使用した場合には、残り7日が翌年に繰り越されます。さらに、2022年10月1日に新たに14日分が付与されれば、翌年には最大で16日間の有給休暇を保持することが可能になります。
企業は、労働者が権利として持つ有給休暇を失効させることはできず、適切な管理が求められます。
関連記事:有給休暇の有効期限とは?基準日の統一や繰越のルールについて解説!
関連記事:有給は期限切れにより消滅する?気をつけたい未消化分の扱いについて
1-6. 有給休暇は原則買い取りができない
有給休暇の買い取りは原則禁止です。なぜなら、有給休暇の本来の目的は過重労働を避けるために有給で休める日を設けるということであり、それに反しているからです。
そのため、企業は有給休暇を買い取って働いてほしいなどと従業員に依頼はできず、従業員が希望したとしても、有給休暇を買い取って働かせるということはできません。
ただし、以下の有給休暇に関しては買い取りが認められていて、従業員からの申し出があれば、企業が任意で買い取ることができます。
- 2年間の有効期限が切れて消滅した有給休暇
- 退職する従業員が残している有給休暇
- 法定の日数以上付与した有給休暇
有給休暇の買い取りをする場合は、これら3つのケースに当てはまっているかを確認しましょう。
1-7. 有給休暇の法律に違反した場合の罰則
有給休暇は法律で定められた制度であるため、ルールを守らなければ、違法となり罰則が科される場合があります。
労働者の請求する時季に所定の有給休暇を与えなかった場合、有給休暇を付与すべき対象者に付与しない場合や、法律で定められた日数付与しない場合に罰則が科されます。
具体的には、違反した労働者1人につき6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が使用者に対して科されます。違反した労働者が多ければ多いほど罰金の金額は膨らむため、注意しましょう。
また、罰金などの負担以外にも、悪質な場合は企業名が公表されるなど、社会的信用を失うことも企業の大きな損失となります。
加えて、企業が有給休暇に関する法律を遵守しない場合、労働局からの指導や是正勧告が行われることもあります。このような勧告に従わない企業は、さらなる法的措置が取られる可能性もあるため、注意が必要です。
従業員の権利を守ることは、企業にとっても長期的な信頼関係の構築につながります。企業は労働者が安心して有給休暇を取得できる制度を整え、適切な管理を行うことが求められます。
2. 有給休暇の発生要件と付与のタイミング

有給休暇は以下2つの要件を満たしたすべての従業員に所定の日数が付与されます。
- 全労働日の8割以上出勤している
- 雇い入れから6カ月が経過している
この要件を満たしていれば、パートやアルバイトの従業員を含むすべての従業員に有給休暇を付与しなければなりません。
要件を満たした従業員にどのタイミングで有給休暇を付与するのかは次節で詳しく解説します。
関連記事:【図解】有給休暇の付与日数と付与のポイントをわかりやすく解説!
2-1. 初回の付与は雇い入れから半年後まで
有給休暇の付与要件を満たした従業員に有給休暇を初めて付与するタイミングは、雇い入れから半年後までの間です。労働基準法では、要件を満たし、有給休暇は雇い入れから6カ月経過した従業員に付与しなければならないと定められています。
ただし、6カ月よりも前に付与することは従業員にとって有利になる扱いのため、問題ありません。
有給休暇を何日付与しなければならないのかは次章でわかりやすく解説します。
3. 有給休暇付与日数の計算方法
 有給休暇の付与日数は従業員によって異なるため、日数の計算方法を確認しておきましょう。
有給休暇の付与日数は従業員によって異なるため、日数の計算方法を確認しておきましょう。
関連記事:有給休暇の有効期限とは?基準日の統一や繰越のルールについて解説!
関連記事:有給は期限切れにより消滅する?気をつけたい未消化分の扱いについて
3-1. 正社員は最低10日から年1日ずつ増える
フルタイムで働く正社員や契約社員の場合、入社後半年が経過した時点で10日の有給付与を付与します。
厳密には、「週の所定労働時間が30時間以上」「週の所定労働日数が5日以上」「年間の所定労働日数が217日以上」のいずれかに該当する従業員が10日付与の対象です。
また、有給休暇の日数は勤続年数に伴って、基準日を迎えるごとに以下のように増加します。
|
勤続年数(年) |
付与日数 |
|
0.5 |
10日 |
|
1.5 |
11日 |
|
2.5 |
12日 |
|
3.5 |
14日 |
|
4.5 |
16日 |
|
5.5 |
18日 |
|
6.5以上 |
20日 |
以上の付与日数を支給していなければ法律違反となり、罰則が科される可能性があります。有給休暇の付与要件を満たした従業員に正しい日数が支給されているかどうかを今一度確認しましょう。
3-2. アルバイトやパートは所定労働日数や時間によって変わる
週30時間未満や週4日以下勤務のアルバイトやパートにも、継続勤務年数や1年間の所定労働日数が条件を満たす場合は、有給休暇を付与しなければなりません。勤務時間や勤務日数が少ないパートやアルバイトの場合は、「比例付与」とよばれる方法で有給休暇の日数を算出します。
以下は、比例的に付与される有給休暇の日数です。
|
週の 所定労働日数 |
1年の 所定労働日数 |
勤続年数(年) |
||||||
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
||
|
4日 |
169~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
|
3日 |
121~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
|
2日 |
73~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
|
1日 |
48~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
比例付与の対象者についても、上記の表でわかるように勤続年数が長くなるにつれて、10日以上の有給が付与されることがあります。その場合は、有給休暇の年5日取得義務の対象となります。
年5日取得義務を守らないと、違法となり罰則が科される可能性があるため、パートやアルバイトのような短時間労働者であっても付与される有給休暇日数が何日か、一人ひとり正確に把握しておくことが必要です。
3-3. 有給休暇の最大日数は?
先述の通り、有給休暇は繰り越しが可能ですが、有効期限は2年間に限定されています。フルタイム勤務の場合と勤務時間や日数が少ない場合、両者の有給休暇の最大日数はどのようになるのでしょうか。
フルタイム勤務の場合
フルタイム勤務の場合、有給休暇の最大日数は35日です。「40日ではないの?」と思った方もいるかもしれませんが、10日以上の有給休暇を付与される従業員には、年5日間の取得義務が課されます。
勤続年数が6.5年以上のフルタイム従業員の場合、1年間で最大20日の有給休暇が付与されます。翌年もその翌年も、新たに最大20日の有給休暇が付与されますが、有効期限が2年間なので最大日数は40日となります。
しかし、これはあくまでも単純に計算した場合です。2019年4月に施行された有給休暇義務化により、1年で5日間の有給休暇を消化しなくてはなりません。つまり、新たに有給休暇が付与される前に有給休暇を5日消化していることになるので、有給休暇残日数は15日となります。翌年付与される最大20日分を追加し、有給休暇の最大日数は35日となります。
なかには有給休暇の有効期限を2年以上とする企業もあるでしょう。しかし、特別な規定がない場合は、35日以上の有給休暇を残している従業員がいないことを定期的に確認することが必要です。もし対象となる従業員がいる場合は、早めの取得を呼びかけ、有給休暇義務化に違反しないようにしましょう。
勤務時間や日数が少ない場合
勤務形態が異なっても、最大日数の考え方は変わりません。勤務時間や日数が少ない従業員の場合、1年間で付与される有給休暇の最大日数は15日です。
そのうち5日は期間内に取得することになるので、残日数は10日となります。翌年新たに15日の有給休暇が付与された場合、両方を合算した25日が最大日数となります。
4. 2019年4月から年5日間の有給休暇の取得が義務化

2019年4月から従来の有給休暇の法律に加えて、従業員に付与した有給休暇を確実に取得させることも企業に義務付けられました。
労働基準法の改正により、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、有給休暇が年10日以上付与されている従業員に年5日以上取得させることが義務付けられています。また、この義務化の対象となる従業員の有給休暇取得状況を「年次有給休暇管理簿」で管理することも新たに義務付けられました。
有給休暇自体は以前から存在する制度ですが、忙しい職場であるほど消化しづらく、適切に運用されていないケースも少なくありません。
こうした背景や働き方改革の推進において、ライフワークバランスの実現をするために有給休暇の取得が義務付けられました。2023年10月31日に厚生労働省が発表した資料では、有給休暇の取得率は62.1%で、昭和59年以降過去最高となっています。
また、有給休暇の取得義務化にあたって、有給休暇を年5日取得していない従業員に対して、企業が有給休暇の取得時季を指定して(年次有給休暇の時季指定義務)、年5日の有給休暇を確実に取得させなければならなくなりました。有給休暇の取得時季指定をする場合は、その旨をあらかじめ就業規則に定めておかなければなりません。
関連記事:年5日の年次有給休暇を正しく取得させるための注意点・ポイントをおさらい
関連記事:年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは
4-1. 有給休暇の取得義務化に違反した場合の罰則
従業員が年5日有給休暇を取得できなかった場合は、労働基準法違反になるため注意が必要です。6カ月以下の懲役、または、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科せられます。
有給休暇を取得できなかった従業員の人数が多いほど、罰金の金額も大きくなりますので、企業は計画的に取得できるような仕組み作りをする必要があるでしょう。
罰則を科されないためには、有給休暇取得義務のある対象者と有給休暇の付与日数を把握しておきましょう。
また、有給休暇の取得義務化にあたって、有給休暇の取得時季指定をする場合、就業規則にその旨を定めておかなければ、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金や罰則のほかにも企業名公表による社会的信用の低下などのリスクがあります。気づかないうちに法違反をしないために、有給休暇のルールを確認しておくことが重要です。当サイトでは、法律に則った有給休暇のルールを解説した資料を無料でお配りしています。自社の有給休暇の管理や付与ルールに問題がないか確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省
4-2. 年5日取得義務のある対象者
年5日の有給休暇取得義務のある対象者は、年10日以上の有給休暇を付与したすべての従業員です。ここでの従業員には、パートやアルバイトも含みます。
そのため、企業はどの従業員に何日有給休暇を付与し、何日取得できているかを随時確認しなければなりません。有給休暇を付与するタイミングと付与日数に関しては次章以降で詳しく解説します。
4-3. いつからいつまでに5日取得させる?
有給休暇の取得義務は1年間で5日以上と定められていますが、この1年とは有給休暇を付与したタイミングから1年間と数えます。有給休暇を付与した日を有給休暇の「基準日」といいます。
たとえば、4月1日に入社した従業員に10月1日、10日の有給休暇を付与した場合、10月1日が有給休暇の「基準日」となり、翌年の10月1日までに最低でも5日の有給休暇を取得させなければなりません。
有給休暇の年5日取得が義務付けられたことによって、企業はどの従業員にいつまでに5日取得させなければならないのかを把握しなければならなくなりました。
従業員一人ひとりの基準日が異なると、取得義務のある期間がバラバラになり、管理が煩雑になる場合があります。そのような場合は、基準日を前倒しして、すべての従業員の基準日を統一することも可能です。
ただし、基準日を後ろ倒しにして統一することは法律で禁止されているため、注意が必要です。
4-4. 年次有給休暇管理簿を作成する必要がある
有給休暇の取得義務化にともない、有給休暇管理簿を作成することが企業に義務付けられました。有給休暇管理簿は従業員ごとに作成し、5年間(当分の間は3年)保存しなければなりません。
有給休暇管理簿には、有給休暇の基準日、取得日数、取得時季を記載する必要があります。テンプレートなどを活用して作成を効率化しつつ、取得漏れがないようしっかりと管理しましょう。
5. 有給休暇の金額の算出方法 ~6割の根拠とは~

企業は、有給休暇を取得した従業員に対し、会社の規定に従って正しい金額を算出・支給しなくてはなりません。有給休暇を取得した従業員に対して支払う金額の算出方法は以下の3つです。
- 通常の賃金
- 平均賃金
- 標準報酬日額
それぞれの計算方法について詳しく見ていきましょう。
5-1. 通常の賃金
通常の賃金を支払う計算方法は、多くの企業で採用されている手法です。この場合、有給休暇の取得日数に関係なく、通常通りの給与計算・支給をおこないます。
特別な事務処理が必要ないので、担当者の負担が少ないのがメリットです。
5-2. 平均賃金
平均賃金とは、直近3カ月間に支払った給料額を元に、従業員の1日当たりの賃金を計算する方法です。以下の計算式によって求めます。
平均賃金の算出には休日を含むため、通常の賃金に比べ、支払額が減るのが特徴です。ただし、勤務日数が少ない従業員の場合は、以下の計算式でも金額を算出しなくてはなりません。
それぞれの計算式で求めた金額を比較し、高い金額を支給します。このことは、労働基準法の「平均賃金の最低保障」で定められています。
5-3. 標準報酬日額
標準日額報酬は、以下の計算式によって求められます。
計算式の母数となる「標準報酬月額」とは、健康保険料の決定の基礎となる仮の金額で、1~50等級に分けられます。健康保険に加入している企業は従業員の標準報酬月額を把握しているので、金額の算出はそれほど難しくありません。
ただし、健康保険に加入していない従業員については、この方法で計算できないため注意しましょう。
5-4. 「有給休暇の金額は6割」の根拠は「平均賃金の最低保障」による
「有給休暇の金額は6割」と聞いたことがあるかもしれません。これは、先程少し解説しましたが、労働基準法第39条によるものです。
この法律は、勤務日数が少ない従業員などの生活を守ることを目的としています。平均賃金によって有給休暇の賃金を算出するときは、前述の通り、2つの方法で算出された金額を比較し、高いほうを支給しなければなりません。
ただし、この規定が適用されるのは、有給休暇の金額を「平均賃金」としている企業に限られます。有給休暇の金額の算出方法は3つありますが、どの方法を選ぶかは企業の自由です。平均賃金を採用していない企業の場合、「6割」は影響しません。
なお、採用した算出方法は就業規則に記載しなくてはなりません。企業には、算出方法に従って正しく計算・支給する責任があります。
6. 有給休暇の取り方や注意点、ルール

有給休暇を付与したり、取得させたりするときは、以下のような点に注意しましょう。
6-1. 有給休暇の理由は無理に聞いてはいけない
有給休暇を申請する従業員に対し、取得理由を問う企業も少なくないでしょう。しかし、有給休暇は法律で定められている従業員の権利なので、本来なら理由を聞く必要はありません。
慣例などを理由に、有給休暇の取得理由を聞くこと自体は違法ではありませんが、理由を申告しない場合でも有給休暇を認める必要があります。また、理由を「私用のため」としている場合、それ以上の理由を聞くことはハラスメントになりかねないので注意が必要です。
理由を述べないから有給休暇を許可しない、というのは違法です。また、有給休暇の取得を渋ったり、取得できないように圧力をかけたりすることも権利に反します。
従業員の希望通りに有給休暇が取得できるよう、社内体制を整えていくようにシフト転換しましょう。
6-2. 従業員が希望する時季に取得させる
有給休暇を取得することは従業員の権利であるため、基本的には従業員が希望するタイミングで取得させなければなりません。従業員から申請があったときは、原則として取得を拒否できないため注意しましょう。
特に、会社の繁忙期にのタイミングで休むことが難しい場合は、事前に従業員とコミュニケーションを取って、取得時期の調整を行うことが重要です。 その際、どの時季が業務にとって特に忙しいのかを明確にし、従業員に理解してもらうことで、より円滑な協力を得ることができます。
ただし、従業員が休むことで事業の正常な運営が妨げられる場合に限っては、時季を変更することが可能です。この場合も、従業員に対して丁寧に事情を説明し、代替日を提案するなど配慮することが求められます。
企業側は、従業員が有給休暇を取得しやすい環境を整えるための施策を講じ、全体的な従業員の満足度向上を狙うことが重要です。
6-3. 就業規則に記載する必要がある
有給休暇に関する内容は絶対的必要記載事項であるため、しっかりと就業規則に明記しましょう。具体的には、付与日数や時季指定、時季変更権などについて記載する必要があります。
企業独自のルールを設定している場合も、明確に記載しておきましょう。
7. 有給休暇を積極的に取得させるための運用方法

これまで解説してきたように、有給休暇の年5日取得が企業に義務付けられています。本来であれば、従業員の希望するタイミングで有給休暇を自由に取得することが理想ですが、なかなか従業員が有給休暇を取得しない場合に企業はどのような対応をすべきなのでしょうか。
ここでは、企業が従業員に有給休暇を積極的に取得させる方法を2つ紹介します。
7-1. 計画年休制度を活用する
1つ目は、「計画年休」制度を活用することです。
計画年休とは、企業が従業員の有給休暇を会社全体・部署・グループ・個人単位で一斉に取得させることができる制度です。あらかじめ、労使協定で計画年休の導入について合意したうえで、就業規則に定めることで、有給休暇を計画的に取得させることができます。
ただし、計画年休を活用する場合は最低5日間、従業員が自由に取得できる有給休暇を残しておかなければなりません。
この制度を取り入れることで、繁忙期と閑散期を考慮した休暇取得が可能になり、業務のスムーズな運営を実現することができます。 また、計画年休の実施によって、従業員は事前に休暇を取得することが決まるため、計画的に生活やプライベートの準備を進めやすくなります。 このように、計画年休制度の活用は、企業と従業員の双方にメリットをもたらし、労働環境の改善につながります。
7-2. 特別休暇を支給する
2つ目は、従業員が有給休暇を取得した場合に、別途有給の特別休暇を支給することです。
有給休暇を取得することでメリットがある場合、従業員は積極的に有給休暇を取得しようと考えるでしょう。また、特別休暇を支給することで連続で休むことができるため、従業員のリフレッシュにもつながります。企業の人数や状況にもよりますが、従業員がなかなか有給休暇を取得しないという場合には有効な方法です。
このように年5日の有給休暇を取得していない従業員に取得を促すためには、まず、誰が有給休暇取得義務化の対象者で年5日取得できていないのかを把握しておく必要があります。
勤怠管理システムなどを用いて、従業員ごとの有給休暇日数や取得状況をリアルタイムで確認することで、取得義務化に対する違反を防ぎましょう。
8. 有給休暇の取得率を上げるメリット

有給休暇の取得により、人手不足や業務効率の低下などに陥るとして、有給休暇の取得推進をためらう企業も少なくないでしょう。しかし、従業員が有給休暇を取得することには、以下のようなメリットがあります。
- 従業員の健康維持につながる
- 従業員エンゲージメントが向上する
- 生産性向上や業績アップを期待できる
- 求職者の増加につながる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
8-1. 従業員の健康維持につながる
従業員の心身の健康を維持できることは、有給休暇の取得を促す大きなメリットです。業務量が多く仕事が忙しい場合、法定休日だけで体力を回復できるとは限りません。健康状態が悪化して、継続的に働いてもらえなくなる可能性もあるでしょう。
従業員の健康維持は企業の責任です。適切なタイミングで有給休暇を取得させ、ストレス解消や疲労の回復を図ってもらいましょう。
健康的な労働環境を実現するためには、企業側が積極的に休暇の取得を促す姿勢を持つことが不可欠です。 また、従業員が有給休暇を気軽に取得できる文化を醸成し、休暇を取りやすい雰囲気を作ることで、心身の健康をさらに促進することにつながります。 これにより、労働者は安心して労働に取り組むことができるため、企業全体の生産性向上にも寄与するでしょう。
8-2. 従業員エンゲージメントが向上する
有給休暇の取得によって、従業員は自分自身の時間を持つことができ、リフレッシュする機会が生まれます。
これにより、職場でのストレスや疲労感が軽減され、心身の健康が保たれます。
従業員が健康であればあるほど、自分の役割を果たすことに意欲を持ち、業務に対して前向きな姿勢を維持することができるのです。
このように、健康的な労働環境が整うことで、従業員はさらに高いエンゲージメントを持ち、企業の目標に対して積極的に貢献しようとするでしょう。
その結果、企業全体の生産性向上や業績向上も期待できると同時に、従業員の定着率を高める要因ともなります。
8-3. 生産性向上や業績アップを期待できる
生産性の向上や業績アップを期待できることも、有給休暇の取得を推進するメリットです。従業員が休むことで生産性が下がるのではないかと不安を感じるかもしれませんが、疲れた状態で働き続けてもよい結果は生まれないでしょう。
適度な休みを取ることで集中力を高め、業務効率のアップを図ることが大切です。
また、有給休暇を適切に取得することで、従業員のモチベーション向上や心の健康が促進され、その結果として企業全体のパフォーマンス向上にもつながります。 企業が有給休暇を推進することで、従業員は自らの健康や生活の質を維持しやすくなり、長期的に見ても持続可能な働き方が実現します。 このように、リフレッシュした従業員が休暇から戻ってくることで、業務に新たな視点や活力をもたらし、組織全体の生産性向上につながるのです。
8-4. 求職者の増加につながる
有給休暇の取得を重視するのは、雇用している従業員だけではありません。有給休暇の取得率が高ければ求職者の増加につながり、優秀な人材を確保できる可能性が高まります。
企業が働きやすい環境を提供し、有給休暇を自由に取得できる文化が評価されることで、求職者からも魅力的に見られます。
有給休暇取得率がまだそれほど高くない企業でも、ホームページに公表することでオープンな会社であることを印象付けられるでしょう。
また、具体的なデータや実績を示すことで、求職者に信頼感をもたらすことができます。企業によっては、有給休暇の取得実績をアピールポイントとして求人情報に盛り込むことで、潜在的な候補者の目を引くこともできます。
以上のように、有給休暇に対するネガティブなイメージを変え、有給休暇の取得を積極的に推進していくことが重要です。安心して休暇を取得できる企業文化を実現することは、従業員満足度や組織の活力を高めるだけでなく、結果として企業の成長と発展に寄与することになります。
9. 有給休暇の管理は適切におこなおう

有給休暇は、要件を満たしている全従業員に与えられる休暇です。働きやすい職場環境作りのために、年5日以上の取得が義務化されているため、企業は年次有給休暇管理簿で従業員一人ひとりの取得状況を管理する必要があります。
取得義務化の対象は、年10日以上の有給休暇が与えられる従業員のみです。有給休暇が取りづらい職場は、積極的に取得できるような取り組みをおこなっていくことが大切です。
また、勤続年数や所定労働時間によって付与日数は異なりますので、正しく付与されているか勤怠管理システムなどを活用し、把握しましょう。
関連記事:有給の前借りは可能!企業側が押さえておくべきポイントを解説
関連記事:年次有給休暇管理簿には作成・保存義務がある!記載事項や記入例をわかりやすく解説
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有給管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。