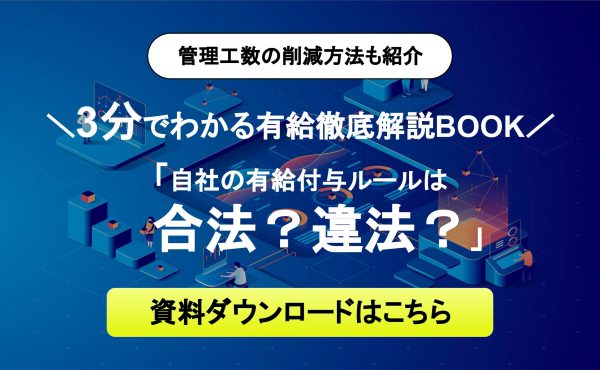企業は、有給休暇を取得しやすい環境整備に取り組む必要があります。その施策のひとつに有給休暇の時間単位付与が挙げられます。時間単位の有給休暇を導入することで、従業員の取得率向上を期待できるでしょう。
本記事では、時間単位の有給休暇について、導入方法や注意点もあわせて解説します。メリットやデメリットを理解して、時間単位での有給休暇を適切に活用しましょう。
関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説
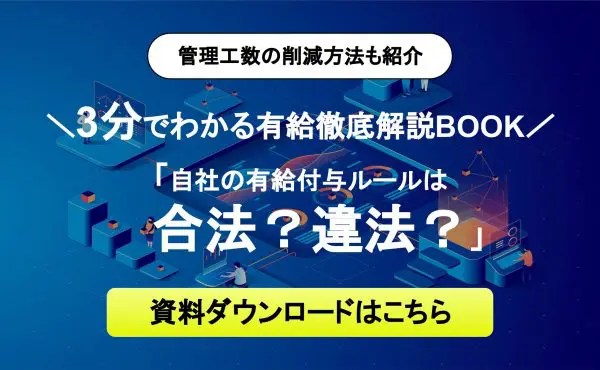
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有給管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 時間単位での有給休暇の付与とは

時間単位の有給休暇とは、通常1日や半日単位で取得する有給休暇を、時間単位で取得できる制度のことです。「時間単位の年次有給休暇」なので、「時間単位年休」とよばれることもあります。
時間単位の有給休暇を設けることは、義務化されていません。時間単位の有給休暇制度を導入するかどうかは、企業が自由に決定できます。
日本では有給取得率の低さが問題視されており、働き方改革の一環として、2010年の労働基準法改正から時間単位の有給休暇制度の導入を推進しています。
1時間や2時間など、半日に満たない細かい時間で有給を消化できるようにすれば、小さな用事にも使用でき、従来よりも有給が取りやすくなるでしょう。
企業がこの制度を導入するためには、就業規則に規定し、労使協定を結ばなければなりません。本章では、時間単位の有給休暇の運用ルールに関して詳しく解説します。
1-1. 時間単位で付与できる有給休暇の上限は5日
時間単位での有給休暇制度は有給休暇の積極的な取得を目的としていますが、有給休暇の本来の目的は、従業員の心身の回復です。そのため、付与日数のすべてを時間単位で消化することは認められていません。時間単位で付与できる上限時間は、1年間に合計5日分(比例付与対象者で付与される日が5日に満たない従業員は付与される日数の範囲内)です。5日以下(比例付与対象者で付与される日が5日に満たない従業員は付与される日数の範囲内)範囲であれば、各企業が自由に取得ルールを定めることができます。
たとえば、「前年度分の繰り越しがある場合には5日まで、繰り越しがない場合には3日まで」など、時間単位で取得できる時間数や日数に条件を設けることも可能です。
1年間に5日を超えて時間単位で有給休暇を与えることは違法となるため、注意しましょう。
1-2. 時間単位の有給休暇は繰り越しできる?
有給休暇には2年間の有効期限があるため、付与してから1年以内に使い切れなかった場合は、翌年度に繰り越すことができます。時間単位の有給休暇も同様です。
時間単位の有給休暇を繰り越す方法は2つあります。
- 残り時間を切り上げて1日にして翌年度の有給休暇に加える
- 残り時間をそのまま翌年度に繰り越す
いずれの方法でも構いませんが、時間単位年休を繰り越した場合、翌年分は前年度の繰り越し日数を含めて5日以内にしなくてはなりません。
たとえば、1年目に40時間(1日8時間×5日)の時間単位年休を付与して25時間を使用した場合、残りの15時間は翌年に繰り越されます。そして、翌年度においては、今回繰り越された15時間を含めて、5日以内の時間単位年休を付与しなくてはなりません。
時間単位年休を翌年に繰り越したからといって、5日の上限に繰越分を上乗せすることはできないので注意が必要です。なお、時間単位の有給休暇は1年で消滅するなど、労働者にとって不利になる規定は法律違反となります。
時間単位の有給休暇を設定する場合は、混乱を招かないために、繰り越しの扱いについても就業規則に規定しておきましょう。
関連記事:有給休暇日数の繰越とは?上限や計算方法などわかりやすい例を紹介
1-3. 時間単位の有給休暇における端数時間の計算方法
時間単位年休では、何時間が1日分にあてはまるのか定めておく必要があります。なぜなら、時間単位で取得する際の1日の労働時間の基準は、所定労働時間で決まるからです。
所定労働時間が8時間であれば「8時間の取得が1日分に相当」とできますが、所定労働時間が7時間30分や7時間45分のときは考え方が異なります。
1時間に達しない端数がある場合、時間単位年休制度では端数分を切り上げることがルールです。そのため、7時間30分など端数が出る場合は、8時間が有給休暇1日分にあたります。
反対に所定労働時間が8時間であるにもかかわらず、運用する際は7時間として扱うなど、実際の所定労働時間を下回ることはできません。
また、所定労働時間が日によって異なる場合は、1年間の平均所定労働時間から算出します。
1-4. 時間単位の有給休暇の賃金計算
賃金(給与)は、通常の有給休暇における1日あたりの賃金を所定労働時間で割って計算します。以下を例として考えてみましょう。
- 所定労働時間:8時間
- 1日あたりの通常賃金:12,000円
- 有給休暇の賃金:通常の賃金をもとに算出
上記の場合、「12,000(1日あたりの賃金) ÷ 8(所定労働時間)」という計算式になるため、1時間あたりの賃金は1,500円です。
たとえば、ある日の勤務で5時間労働し、残りの3時間は有給休暇を使った場合、以下のように考えます。
- 5 × 1,500 = 7,500円(5時間労働分)
- 3 × 1,500 = 4,500円(時間単位年休の3時間分)
有給休暇の賃金算出方法は法律で定められています。計算方法は複数あるため、自社に合った方法を就業規則で定めておく必要があるでしょう。
賃金算出方法を含めた企業の有給休暇に関するルールは、法律に則っている必要があります。法違反をしていた場合、罰則を科される可能性もあるため、法律に則った有給休暇のルールを正確に把握しておくことが大切です。
当サイトでは、有給休暇の基本ルールを1冊で理解できる資料を無料でお配りしています。自社の有給休暇に関するルールが適切か確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
1-5. 就業規則に記載する必要がある
時間単位の有給休暇を導入する際には、労使協定を結ぶ必要があります。そして就業規則に時間単位年休について記載しましょう。そして就業規則に時間単位年休について記載しましょう。就業規則には、労働条件や職場内のルールが定められており、具体的な内容を明記することで、従業員と企業間のトラブルを防ぐことができます。
年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)
(年次有給休暇の時間単位での付与)
第〇条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条(注)の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条(注)の年次有給休暇と同様とする。
2. 時間単位の有給休暇を導入するメリット
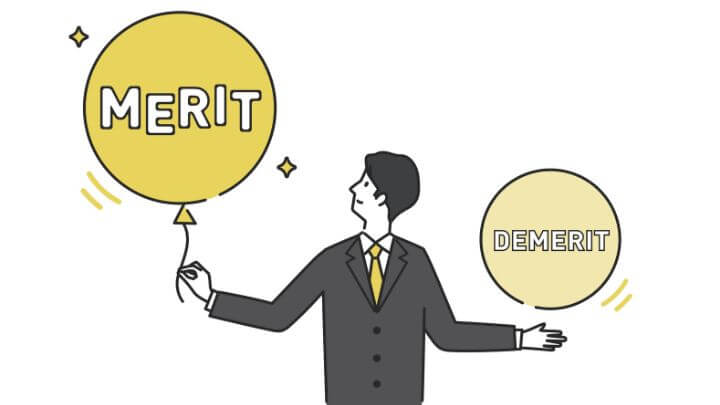
時間単位の有給休暇を導入することには、消化率が高まる、ワークライフバランスを確保できる、社会的なイメージが向上するなどのメリットがあります。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
2-1. 有給休暇の消化率が高まる
時間単位の有給休暇を導入すれば、有給休暇の取得率が高まるでしょう。時間単位での取得であれば、業務への影響も最小限に抑えられるため、休みづらかった人も取得しやすくなります。
たとえば、「数時間だけ病院に行くために抜けられたら」と思っている人にとっては、丸1日分の休みを取ることなく、仕事から離れることが可能です。
2-2. ワークライフバランスを確保できる
ワークライフバランスを確保しやすいことも、時間単位の有給休暇を導入するメリットのひとつです。時間単位の有給取得を認めれば、午前の数時間だけ休む、仕事の合間に中抜けするなど、従業員はより柔軟に働けるようになります。
これによって、各従業員は自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能になり、プライベートの時間を充実させることができます。
家事と仕事の両立も実現しやすくなり、特に子育て中の従業員や介護を担う従業員にとって、生活の質が向上します。こうした柔軟な働き方を導入することで、企業へのエンゲージメントを高め、長期的に働いてもらえるでしょう。
2-3. 社会的なイメージが向上する
時間単位の有給休暇を導入すれば、柔軟に休みを取得できる職場というアピールができ、社会的なイメージ向上にもつながります。ワークライフバランスを確保し、従業員の心身の健康を大切にしている職場であることが伝われば、就職したいと考える人も増えるでしょう。
その結果、採用活動がスムーズに進んだり、優秀な人材を確保したりすることにもつながります。
3. 時間単位の有給休暇を導入するデメリット
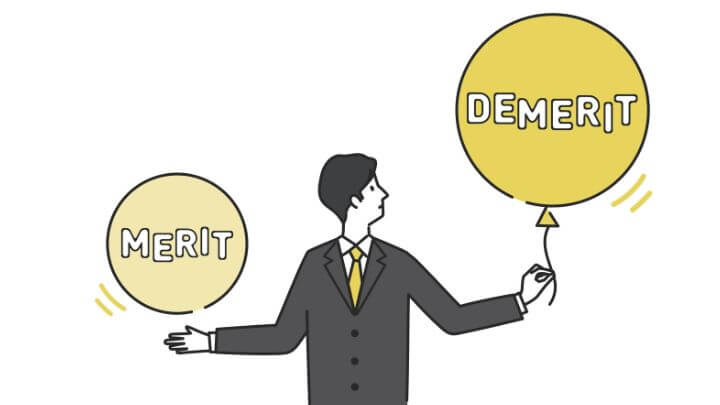
さまざまなメリットがある一方、時間単位の有給休暇を導入することには以下のようなデメリットもあります。
関連記事:時間単位の有給休暇のデメリット|時間単位の有給休暇とは?制度内容や導入方法を解説
3-1. 有給休暇の管理が複雑になり、手間がかかる
有給休暇の管理が複雑になることは、大きなデメリットです。時間単位の有給休暇を導入すると、日数だけではなく時間という細かい単位で管理しなければなりません。管理が複雑になり、担当者の負担が増えるのはもちろん、計算ミスなどが発生する可能性もあります。
時間単位の有給休暇を導入するなら、勤怠管理システムなどを活用して管理を効率化することが重要です。
3-2. 使いすぎると有給休暇の本来の目的に反するため制限がある
時間単位の有給休暇制度の導入によって、1日単位での有給休暇が取りづらくなってしまう可能性もあります。まとまった休暇を取得して休養してもらうという有給休暇本来の目的に反しないように時間単位年休については年5日以内となっているため注意しましょう。
また、時間単位での有給休暇取得は事業への影響が少ないため、時季変更権を行使しづらくなることは企業にとってのデメリットといえるでしょう。
関連記事:本来の有給休暇の目的が達成できなくなる|時間単位の有給休暇とは?制度内容や導入方法を解説
4. 時間単位の有給休暇を導入する方法

時間単位の年休制度を導入することは任意なので、取り入れなくても違法ではありません。しかし、導入するのであれば、ルールをしっかりと定める必要があります。
まずは、労使協定を結び、就業規則に記載しておく必要があります。労使協定で時間単位年休を導入する際に規定する内容があります。
|
必要項目 |
概要 |
|
時間単位年休付与の対象者 |
|
|
時間単位年休の利用可能日数 |
|
|
所定労働時間の扱い |
|
|
時間単位年休を付与する単位 |
|
|
賃金に関する内容 |
|
時間単位年休の導入には、労使協定の締結が必要です。締結の際も就業規則と同じように、対象者や取得可能日数などを書面で定めましょう。
変更した就業規則は、労働基準監督署長へ届け出る必要があります。労使協定の届出は必要ありません。また、就業規則の変更が完了したら、従業員に周知することを忘れないようにしましょう。
4-1. 労使協定の記載例
時間単位での年次有給休暇の取得に関するルールを労使協定に定める際は、下記のように記載しましょう。
(記載例)
時間単位の年次有給休暇に関する協定書
○○株式会社(以下「会社」という。)と○○株式会社労働組合は、時間単位の年次有給休暇に関し、次のとおり協定する。
(対象者)
第1条 すべての労働者を対象とする
(日数の上限)
第2条 時間単位年休を取得することができる日数は、1年につき5日以内とする。この5日には前年の時間単位年休の繰越し分を含めることとする。
時間単位年休を5日取得したために、前年から繰り越した1日未満の時間が取得できなかった場合は、この時間分は翌年度に繰越す。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 時間単位年休を取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
(1) 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者 6時間
(2) 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者 7時間
(3) 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者 8時間
(時間単位年休の取得単位)
第4条 時間単位年休を取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
(時間単位年休の取得手続)
第5条 時間単位年休の請求は、遅くとも前労働日の終業時刻までに「時間単位年休取得届」に必要事項を記載して、所属長に届け出るものとする。
(時間単位年休に支払われる賃金額)
第6条 時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(その他)
第7条 上記以外の事項については、就業規則第○条に定める事項と同様とする。
(協定の効力)
第8条 本協定は、令和●●年●●月●●日より効力を発する。
令和○○年○○月○○日
○○株式会社 代表取締役 ○○○○
○○株式会社労働組合 執行委員長 ○○○○
参考:年次有給休暇時間単位取得促進特設サイト|厚生労働省
参考:時間単位の年次有給休暇に関する労使協定例|愛媛労働局
5. 時間単位で有給休暇を取得させる際の注意点

時間単位の有給休暇を運用するうえでの注意点を確認しましょう。導入したことでトラブルが起きることがないよう、事前に理解しておくことが大切です。
5-1. 30分単位など、分単位での取得はできない
時間単位年休は、1時間や2時間など時間単位で取得することは可能ですが、15分や30分など分単位での取得はできません。
「時間単位」という制度の通り、1時間に達しない時間は法的に認められていないので、たとえ就業規則などで定めたとしても分単位での取得はできません。端数は1時間単位に切り上げて付与しましょう。
なお、1日に取得できる回数に決まりはありません。たとえば、午前に1時間、午後に1時間、合計2時間の有給を取得した場合も時間単位に該当するため、問題ありません。
5-2. 年5日以上の有給取得義務分として扱うことはできない
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与された従業員は年5日以上の有給取得が義務付けられています。
もし、時間単位での有給取得の合計取得時間が5日分になったとしても、取得が義務付けられている5日分の有給休暇を取得したとは見なされません。
有給休暇取得義務は、心身を休めるための休暇を増やすことが目的とされているので、時間単位で細分化して取得した有給休暇はこの条件を満たさないと判断されるためです。
時間単位の有給休暇を取得させる場合は、取得義務のある5日とは別で取らせなければならないことに注意しましょう。
関連記事:年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは
5-3. 計画年休で付与することはできない
時間単位の有給休暇は、計画年休で付与することはできません。計画年休とは、労使協定を結ぶことで、企業側が従業員の有給休暇取得日を指定する制度のことです。
有給休暇の取得を促す目的で計画年休を導入している企業も多いでしょう。しかし、時間単位の有給休暇は従業員からの申請によって付与すべきものであるため、企業側が取得日時を指定することはできません。
関連記事:計画年休との関係
5-4. 勤務時間がバラバラな場合は慎重に対応する
昨今、多くの企業にとって、パート・アルバイトなどの非正規従業員は大きな労働力となっています。しかし、非正規従業員の場合、従業員ごとにシフトが異なるため、時間単位年休の運用に支障が出るケースもあるようです。なかには、日によって労働時間が変わる従業員もいるため、時間単位の有給休暇は慎重に付与しなければなりません。
時間単位の有給休暇付与において、勤務時間がバラバラであることの問題点は、1日あたりの労働時間が固定されないことにより、付与する有給休暇の時間数が定まらない点です。
このような場合は、労使協定で1日の労働時間を明確にする必要があります。日によって労働時間数が異なる場合は、年間の所定労働時間をもとに1日あたりの労働時間数を決定しましょう。
また、複数の非正規雇用従業員がいる場合は、所定労働時間ごとに従業員をグループ分けすると管理しやすくなります。
フレックスタイム制を導入している場合は、必ず勤務しなければならない時間帯である「コアタイム」にのみ時間単位年休を適用する企業が多いようです。しかし、どの時間帯に対して時間単位年休を適用するかは企業次第なので、自由に勤務できる時間帯である「フレキシブルタイム」に設定しても問題ありません。
いずれにせよ、1日の所定労働時間が決まっていないフレックスタイム制の場合は、まず、1日分の有給休暇が何時間分に相当するのかを明確に設定することが重要です。
5-5. 1年の途中で労働時間が変更になった場合は、変動に比例した時間数に変更する
1年の途中で労働時間が変更になった場合、ポイントとなるのは、時間単位で取得できる有給休暇がどれくらい残っているかということです。時間単位年休が1日単位のものしか残っていない場合は、変更後の労働時間に合わせて1日あたりの有給休暇時間数も変動します。
問題は、1日単位に満たない時間単位の有給休暇が残っている場合です。この場合は、変更後の労働時間に比例して有給休暇の時間数も変更します。
たとえば、時間単位年休1日の労働時間数が8時間、付与日数が5日の場合で考えてみましょう。このうち、労働時間変更前に、1日と1時間を取得していたとすると、残りの時間単位年休3日と7時間になります。
では、労働時間を8時間から5時間に変更した場合はどう考えればよいのでしょうか。この場合の考え方は以下の通りです。
|
1日単位の有給休暇残日数 |
時間単位の有給休暇残日数 |
|
|
変更前 |
3日(1日あたりの時間数は8時間) |
7時間 |
|
変更後 |
3日(1日あたりの時間数は5時間) |
5時間 (7時間×8/5=4.375時間を切り上げる) |
このように、1日単位の時間単位年休が残っている場合は、変更後も1日あたりの時間数が変更になるだけです。一方、時間単位年休が時間単位で残っている場合は、労働時間が短くなるのに比例して時間数も変動します。なお、端数が生じた場合は切り上げになることを覚えておきましょう。
5-6. 時間単位の有給休暇は半日有給休暇と併用できる
時間単位の有給休暇は半休と併用できます。時間単位年休と有給休暇制度による半休取得はまったく別の制度であることが理由です。
そのため、半休を取得しても時間単位年休の日数や時間数が減ることはありません。
5-7. 早退・遅刻を時間単位の有給休暇による振り替えで認めるかは企業次第
従業員の遅刻・早退を時間単位年休で振り替えるか否かは企業の判断に委ねられます。事故や災害などの特別な理由に限って、振り替えを認める企業もあるようです。
ただし、振り替えを認める場合でも、会社側が自動的に振り替えることはできません。時間単位年休を含め、有給休暇の取得は、従業員からの申請があることが前提です。その申請に企業が同意することで初めて有給休暇の取得が成立することを覚えておきましょう。
5-8. 時間単位の有給の時季変更権の行使は認められにくい
企業は繁忙期や人員不足など、やむをえない事情がある場合には、時季変更権を行使して、有給休暇を申請した従業員の有給休暇の取得時季を変更することができます。
時間単位の有給休暇取得に関しても、同様に時季変更権は行使できますが、時間単位の有給休暇は半日や1日単位で取得した有給よりも業務に与える影響が小さいと考えられるため、合理的な説明をおこなうのが難しく、時季変更権の行使は難しい場合が多いでしょう。
5-9. 時間単位の有給休暇を導入する前に管理方法を見直す
時間単位の有給休暇を検討していても、管理が煩雑になることを理由に導入を先送りにする企業も少なくありません。
有給休暇が日単位であれば、残り日数が何日かを把握しておけば良いですが、時間単位で取得させた場合は、残り日数に合わせて残り時間も集計しなければなりません。
そのため、日単位で有給休暇を取得させるよりも、管理工数が発生します。
紙などで集計している場合、ヒューマンエラーも発生しやすくなるため、時間単位の有給休暇を導入する場合は管理方法の見直しが必要です。有給休暇を時間単位で取得しても、残り時間を自動集計してくれる勤怠管理システムなどを活用するとよいでしょう。
5-10. 時短勤務者も時間単位の有給休暇は取得できる
育児や介護などの理由から時短勤務をしている従業員はいますが、時短勤務者も時間単位での有給休暇を取得することが可能です。時短勤務者の場合は、通常の勤務者とは異なり、自身の所定労働時間を元に有給休暇の日数を計算します。
たとえば、8時間勤務の従業員が1時間短縮している場合、時間単位で取得できる有給休暇の上限は7時間×5日で35時間となります。
5-11. 中抜けを禁止することはできない
時間単位年休に関しては、中抜けを禁止することはできません。これは、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、有給休暇の制限が許可されるためです。
具体的には、取得できない時間帯を定めたり、所定労働時間の途中に取得したりといったことは認められません。
6. 時間単位の有給休暇制度を導入して柔軟な働き方に対応しよう

今回は、時間単位の有給休暇における基本を解説しました。時間単位年休は、1時間など細かい時間で有給休暇が取得できるので、短時間での用事や中抜けしたいときに利用できる便利な制度です。
しかし、有給休暇の管理が複雑になったり、1日単位での有給休暇が取得しづらくなったりする可能性があることは、デメリットとして把握しておきましょう。
また、時間単位年休の上限は年5日までであることや、有給休暇の取得義務の日数には含まれない点に注意する必要があります。
時間単位年休制度は、労使協定を締結して、就業規則に記載しておくと導入可能なので働きやすい労働環境の整備のためにも検討してみるとよいでしょう。
それと同時に事務作業の負担を軽減するために、勤怠管理システムの導入など、有給休暇の管理方法の見直しを進めることも大切です。
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しくおこなわれているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。