
有給休暇は、一定の期間勤めた従業員が、給与の心配をせずに休息を取れる制度です。自社の従業員に健康的に、生産性高く働いてもらううえでも、有給休暇について正しく理解することは非常に重要です。
本記事では、有給休暇を付与するタイミングや付与日数、有給休暇に関する疑問について解説します。また、2年目(2回目)以降の有給付与についても紹介します。
関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説
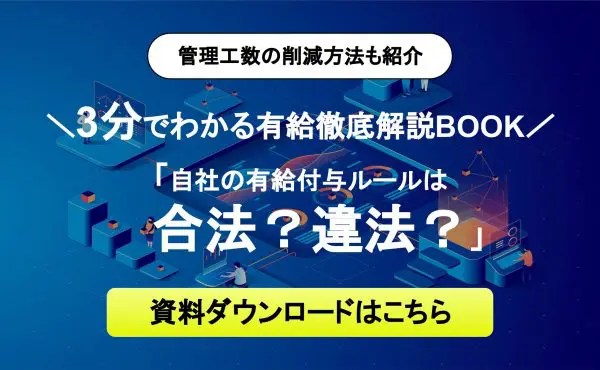
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから取得義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 有給休暇を付与するタイミングとは?

ここでは、有給休暇の付与条件を整理したうえで、有給休暇を付与するタイミングについて解説します。
1-1. 有給休暇の付与条件
有給休暇を付与するためには、下記の2つの条件を満たしている必要があります。
②その期間の出勤率が8割以上であること
この条件を満たしている従業員に対し、企業は有給休暇を付与しなくてはなりません。出勤率については、下記の通り、育児休暇や介護休暇など、実際には出勤していなくても出勤日に含めなくてはならない日もあるため注意しましょう。
・産前、産後の休業
・育児休業あるいは介護休業
・年次有給休暇を取得した日
・遅刻や早退の扱いとなった日
1-2. 有給休暇を付与するタイミングは付与条件を満たした日
有給休暇は、入社後6カ月以上経過しており、出勤率が8割を超えている従業員に付与されます。そのため、有給休暇を付与するタイミングは、これらの条件を満たした時点、すなわち入社後にちょうど6カ月を迎える時点です。
この付与条件を満たし、有給休暇が付与される日を「基準日」といいます。たとえば、4月1日に入社した従業員の基準日は6カ月後の10月1日となります。
1-3. 有給休暇は前倒し付与も可能
先述の通り、有給休暇の初回の付与日は入社日から半年後です。しかし、通常よりも早いタイミングに前倒しで有給休暇を付与しても問題ありません。
例えば、入社日に初回の有給休暇を付与することもできます。有給休暇の前倒し付与は、法律で定められたよりも従業員にとって利益となるからです。ただし、次の付与日は前倒しした付与日の1年後、もしくは、それより前にしなくてはならないので注意しましょう。
1-4. 有給休暇は毎年付与しても前年分を繰り越せる
1回目の有給休暇は入社から半年後に、その後は毎年付与します。有給休暇の有効期限は付与された日から2年間です。そのため、有給休暇は、毎年付与しても前年分を繰り越すことができます。
たとえば、入社半年後に10日間の有給休暇が付与されたケースで考えてみましょう。この場合、2回目の付与日までに1日も有給を取得しなくても、この10日間はそのまま繰り越して翌年分と合算できます。
有給休暇の有効期限は労働基準法で定められた最低基準です。有効期限を延ばすことはできますが、短縮することはできないので注意が必要です。
関連記事:有給休暇の繰越をわかりやすく解説!上限日数や計算方法を事例で紹介
1-5. 労働基準法で決められている有給休暇の最大日数
年次有給休暇の最大日数は、勤務年数に応じて決まります。労働基準法では、6年6ヵ月以上勤務した場合、最大で20日間の有給休暇が付与されます。
このうち、5日間は1年以内に取得させる義務があるため、次年度に繰り越せるのは15日間です。さらに、有効期限は2年間あるため、新たに発生した20日間と合わせると、最大で35日間の有給休暇を保有することが可能です。
2. 有給休暇を付与するタイミングは統一できる

結論、有給休暇を付与するタイミング(基準日)を統一することは可能です。基準日の統一には主に2つの場合があります。「年1回の基準日を設ける場合」と「年2回の基準日を設ける場合」です。
ただし、いずれの場合も従業員の不利益になる場合は違法と見なされるので注意しましょう。
ここからは、例を交えながら順番に解説します。
2-1. 年1回の基準日を設ける場合
仮に、毎年4月1日を基準日と設定します。この場合、4月1日に入社した従業員は入社した当日に有給休暇10日を付与されることになります。本来、4月1日入社の従業員は10月1日に有給休暇が付与されるので、基準日を統一しても従業員にとって不利益にはなりません。そのため、この場合の基準日統一は合法となります。
2-2. 年2回の基準日を設ける場合
仮に、毎年4月1日と10月1日を基準日と設定します。この場合、6月1日に入社した従業員は4カ月後の10月1日、7月1日に入社した従業員は3カ月後の10月1日に有給休暇が付与されます。この場合、本来よりも従業員が優遇されているので違法とはなりません。
2-3. 基準日を統一するメリット
中途採用を積極的におこなっている企業や、従業員を多く抱えている大企業などでは、有給休暇の付与タイミングが従業員によって異なるケースが頻発します。従業員一人ひとりの有給休暇の付与タイミングを適切に管理できなければ、有給休暇の付与漏れが生じる恐れがあります。
また、従業員ごとに基準日が異なると管理が煩雑になり、人事労務担当者の業務負荷につながるでしょう。
しかし、有給休暇の付与する基準日を統一することで、有給休暇の付与タイミングの管理が容易になります。そのため、有給休暇の付与漏れを防止し、適切に有給休暇の日数を管理することが可能です。
2-4. 基準日を統一する際の注意点
4月1日を基準日として年1回有給休暇を与える場合、6月1日に入社した従業員は翌年の4月1日になるまで有給休暇が付与されないことになります。法律に基づくと、本来は6カ月後の12月1日に有給休暇が付与されるはずなので、この場合は違法になります。そのため、初回は法定通りで、2回目の付与から基準日をあわせるなど、対策を講じる必要があります。
また、4月1日と10月1日を基準日として年2回のタイミングで有給休暇を付与する場合、4月1日、10月1日に入社した従業員は当日に有給休暇が付与されるのに対して、6月1日、12月1日に入社した従業員は4カ月後に有給休暇が付与されることになります。社内で不公平が生まれ、従業員の不満につながる恐れがあります。このような事態を防ぐために、従業員の入社月に応じて付与日数や基準日を調整するなどして、公平な労働環境を整えるよう努めましょう。
このように、年1回の基準日を設ける場合でも、年2回の基準日を設ける場合でも、従業員の不利益となってしまう場合は違法になるので注意が必要です。
関連記事:有給休暇の基準日とは?管理簿への記載が必須!統一するメリットや考え方を解説
3. 有給休暇付与日数の計算方法

ここでは、有給休暇付与日数の計算方法について解説します。
3-1. 正社員の場合
正社員などフルタイム労働者の場合、継続勤務年数に応じて有給休暇が付与されます。有給休暇の付与日数と継続勤務年数の関係は以下の通りです。
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
関連記事:有給休暇の付与日数の計算方法とは?付与条件や計算例、注意点についても紹介!
3-2. パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトなどの短時間労働者の場合、継続勤務年数や週の所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。有給休暇の付与日数と週の所定労働日数の関係は以下の通りです。
| 所定労働日数 | 勤続年数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間 | 年間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 |
2日 |
2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
なお、下記のいずれかに当てはまる場合は、正社員(フルタイム労働者)と同様の有給休暇の日数が付与されます。
- 週の所定労働日数が5日以上
- 週の所定労働時間が30時間以上
- 年間の所定労働日数が217日以上
このように、有給休暇を付与するタイミングも重要ですが、有給休暇を何日付与するのかも非常に大切です。
関連記事:アルバイト・パートにも必要な有給休暇|日数・賃金の計算方法
4. 有給休暇の取得に関する注意点

有給休暇には付与タイミングだけでなく、ほかにも注意点があります。ここでは、有給休暇の取得に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. 有給休暇は時間単位でも取得できる
有給休暇の本来の目的は、「労働者の心や体の疲労を回復し、労働力の維持培養を図るとともに、 ゆとりのある生活を実現する」です。そのため、1日単位で取得するのが当たり前とされてきました。
しかし、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革などを理由に、2010年4月の法改正で時間単位での取得が認められるようになりました。ただし、時間単位での取得には要件があります。
- 就業規則で時間単位での付与について定めていること
- 労使協定を締結していること
この要件を満たせば、時間単位での取得が可能です。ただし、時間単位で取得できるのは年5日までとなるので注意しましょう。
4-2. 有給休暇の消滅時効は2年
労働基準法により、有給休暇の消滅時効(有効期限)は2年と定められています。そのため、1年分の有給休暇の繰り越しは可能です。しかし、有給休暇の付与された日から2年過ぎると、有給休暇は消滅してしまいます。
たとえば、前年から繰越された有給休暇が10日、当年の有給休暇取得日数が8日の場合、当年に2日分の有給休暇が消滅してしまうことになります。有給休暇が消滅してしまわないよう、計画的に有給休暇を取得させることが大切です。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
関連記事:有給の消滅するはいつ?消滅分の計算方法や消滅を当たり前にしない対策を解説!
4-3. 有給休暇は繰越分と新規付与分のどちらから消化される?
有給休暇は原則として、古いものから順番に消化されます。そのため、繰越分と新規付与分では、繰越分から有給休暇は消化されます。
ただし、会社独自のルールとして、新規付与分から有給休暇を消化すると定めていることもできます。その場合、就業規則にきちんと明記し、従業員に周知することが大切です。
4-4. 有給休暇の買取は原則として不可
有給休暇の買取は原則として認められていません。ただし、下記のように、従業員が不利にならない範囲での買取は認められています。
- 法律で定められた日数を超える有給休暇
- 有効期限を過ぎた有給休暇
- 退職したときに残っている有給休暇
従業員の有給休暇を取得させることが難しいからといって、企業側が強制的に有給休暇を買い取ることはできないので注意が必要です。
関連記事:有給休暇の買取は違法?退職者の対応や計算方法、デメリットを解説!
4-5. 有給休暇の年5日取得義務化の厳守
2019年4日より、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されました。違反すると、罰金や懲役といったペナルティが課される恐れがあります。
なお、繰り越し分の有給休暇を5日取得させることでも、年5日取得の要件を満たすことができます。確実に有給休暇を取得させるために、時季指定をおこなうのも一つの手です。
関連記事:有給休暇の年5日取得義務化の対象者や取得できなかった場合の罰則を解説!
4-6. 有給休暇には時季指定権がある
先程少し触れましたが、有給休暇には「時季指定権」があります。これは、労働者自身が有給休暇をいつ取得するかを決められる権利です。
一方で、使用者には「時季変更権」があります。時季変更権とは、従業員が申請した有給休暇の日程を使用者が変更できる権利です。この権利は、有給休暇の取得により業務に支障が出る場合など、特別なときにのみ使用できます。
つまり、使用者は、基本的に従業員の希望通りに有給休暇を取得させなくてはなりません。そのため、日頃から従業員のスケジュールを正しく管理したり、業務調整などをおこなったりして、有給休暇が取得しやすい環境を整えて置く必要があるでしょう。
4-7. 有給休暇を取得させなかった場合の罰則とは
有給休暇を適切に取得させなかった場合、企業は罰則を受ける可能性があります。有給休暇において企業が罰則を受ける可能性がある主なケースは以下の3つです。
- 年5日の年次有給休暇を取得させなかった
- 時季指定権を行使する際に、就業規則での規定がない
- 従業員が時季指定権を行使できなかった
一例を紹介すると、年5日の年次有給休暇取得義務を果たせなかった場合は、罰則として30万円以下の罰金が適用される可能性があります。(労働基準法第39条7項に違反)
有給休暇の取得は従業員の権利で、法律でも定められています。罰則があるから取得させるのではなく、従業員の心身の健康維持に必要な制度であることを再認識し、できるだけ期限内に取得できるように配慮しましょう。
5. 有給休暇を付与するタイミングで「よくある疑問」

ここからは、有給休暇の付与するタイミングについて「よくある疑問」を解説します。
5-1. 2年目以降の有給休暇の付与タイミングは毎年同じでいいの?
入社日から半年後を基準日とする場合、2年目以降の有給休暇の付与日は、前年と同じです。入社日から半年後に1回目の有給休暇を付与し、2回目以降はその日から1年後、つまり入社後1年半が経過したタイミングで付与します。
1回目の有給休暇が10月1日に付与された場合、2回目以降は1年後の10月1日です。その後は毎年10月1日に付与することになるので、付与のタイミングを覚えてしまえばそれほど難しい管理にはならないでしょう。
ただし、入社日は従業員によって異なります。そのため、付与日を誤り、有給休暇を正しく付与できないケースも少なくありません。この問題を解決する対応策の一つが「基準日の統一」です。基準日を統一すれば、同じ日に全従業員に有給休暇を付与することになるので、付与を忘れるといったミスを防ぐことができます。
5-2. 従業員の退職が決まっている場合でも、有給休暇は通常通り付与すべき?
従業員の退職が予定されている場合であっても、有給休暇は通常通り付与する必要があります。有給休暇は法律に定められた「従業員の権利」であるため、企業がこれを侵害することができません。
従業員が退職予定の場合は、下記のような対処法をとり、計画的に有給休暇を消化させましょう。
・有給休暇の取得期間を踏まえたうえで、引継ぎをおこなう
・最終出勤日と有給取得時期の兼ね合いを考える
5-3. 派遣社員やパート・アルバイトに有給休暇を付与するタイミングは?
有給休暇を付与するタイミングは、フルタイム従業員も派遣社員やパート・アルバイトも同じです。勤務形態によって付与日数に差は生じますが、付与するタイミングは変わりません。
なお、派遣社員への有給休暇の付与は雇用主である派遣元企業がおこないます。派遣先企業は、派遣社員の有給休暇付与には一切関係しないので心配する必要ありません。
ただし、派遣社員から有給休暇を取得したいとの申し出があった場合は、可能な限り希望日に取得できるよう配慮しましょう。雇用形態の違いを理由に、有給休暇取得を認めないのは違法です。
5-4. 出勤率が8割未満の年は継続勤務年数に含めていいの?
有給休暇の付与条件の1つに「出勤率8割以上」があります。出勤率が8割に満たない場合、有給休暇を付与する必要はありません。
では、もし出勤率が8割に満たない年があった場合、その年は勤続年数に含まれないのでしょうか。答えは「勤続年数に含まれる」です。もし、誤って勤続年数にカウントしなかった場合、翌年以降に付与する有給休暇日数が本来付与すべき日数よりも少なくなってしまうので注意しましょう。
6. 有給休暇分の給与の計算方法

有給休暇分の給与の計算方法は3つあります。
| 計算方法の種類 | 概要や注意点 |
| 平均賃金をもとに計算する方法 |
|
| 通常賃金をもとに計算する方法 |
|
| 標準報酬月額をもとに計算する方法 |
|
いずれの方法で計算しても構いませんが、計算方法についてはあらかじめ就業規則などに定めておく必要があります。
7. 有給休暇の取得実態と効率的な管理方法

最後に、有給休暇の取得実態を紹介します。
合わせて、有給休暇を適切かつ効率的に管理する方法も紹介するので参考にしてみてください。
7-1. 有給休暇の取得率
「令和5年就労条件総合調査」によると、令和4年の1年間に企業が労働者に付与した有給休暇日数は平均17.6日となっています。そのうち、従業員が取得した有給日数は10.9日、取得率は62.1%でした。取得日数、取得率ともに過去最高となり、有給休暇が取得しやすい環境になりつつあるようです。
また、有給休暇の取得率は、企業の規模が大きいほど高い傾向にあることもわかっています。
繰り返しになりますが、有給休暇の取得は従業員の権利であるため、取得率100%となるのが望ましいと言えます。企業は、取得率が100%となるように、職場環境を整えたり従業員に働きかけたりしましょう。
有給休暇取得率アップのメリットとは
厚生労働省が公表している有給休暇取得率と、自社の取得率を比較してみたでしょうか?
有給休暇の取得率を向上させることは、企業に以下のようなメリットをもたらします。
- 従業員のエンゲージメントが向上し、仕事に対するモチベーションが上がる
- 従業員の仕事の質や生産性などが上がる
- 離職率の低下や人材採用によい影響がある
- 企業としてのイメージアップが期待できる
有給休暇の取得率を上げることは、従業員の仕事の意欲や企業の業績の向上につながるため、積極的に取得させましょう。特に、積極的な取得を促進することで、職場内のコミュニケーションが向上します。また、休暇を取得した従業員は心身の疲労回復が図られ、健康状態が改善されることにもつながります。
こうした効果は、結果的にチーム全体の士気アップや組織の活性化に貢献し、ひいては会社の成果や競争力を高める要因となります。
さらに、企業が有給休暇の取得を奨励することで、長期的に従業員の定着率が高まり、優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。
7-2. 有給休暇管理簿の作成義務
年次有給休暇管理簿とは、従業員の有給休暇の付与・取得状況などを管理するための帳簿です。使用者は、有給休暇を10日以上付与している全従業員の年次有給休暇管理簿を作成しなければなりません。
フォーマットは自由に決められますが、以下の3つの項目については必ず記載する必要があります。
- 付与日
- 付与日数
- 取得時期
上記に加え、従業員名や有給休暇の有効期限なども記載する必要が出てくるでしょう。有給休暇の付与や取得には、企業側の管理が必要不可欠です。
7-3. 有給休暇の付与タイミングを効率的に管理する方法
ルールを覚えてしまえば、有給休暇を付与するタイミングでミスをしたり、迷ったりすることはほとんどないでしょう。しかし、有給休暇の管理方法によっては、全従業員の付与日を把握・管理するのが困難というケースもあります。
付与するタイミングを誤ると、従業員の有給取得の妨げになるだけでなく、企業に対する不信感を招く恐れもあるので、慎重な対応が必要です。
有給休暇管理簿を紙ベースで管理している場合などは、付与するタイミングや付与日数を誤りやすくなるので注意しましょう。
最近では、エクセルテンプレートやアプリ、勤怠管理システムなど、有給休暇を効率的に管理できるさまざまなツールが簡単に手に入ります。特に勤怠管理システムは、有給休暇の付与タイミングだけでなく、休暇や遅刻・早退など、勤怠の一元管理が可能です。有給休暇の管理や勤怠管理の効率化を図ることが目的であれば、勤怠管理システムの導入をおすすめします。
関連記事:勤怠管理システムとは?特徴や活用メリット、システムをご紹介
8. 有給休暇を付与するタイミングを理解し、従業員が健康的に働ける職場へ!

本記事では、有給休暇を付与するタイミングや付与日数、有給休暇に関する疑問について解説しました。有給休暇について深く理解することは、知らないうちに労働基準法違反になるリスクを無くすことにつながります。
ただ、全従業員の有給休暇を管理することはかなりの負荷がかかります。有給休暇の付与タイミングを誤ると、有給休暇の取得を妨げ、従業員の権利を侵害する恐れがあります。
今回の記事を踏まえて、有給休暇について理解を深め、従業員が健康的に働ける職場づくりを心掛けましょう。それと同時に、有給休暇の管理方法を見直し、付与のタイミングや日数を正確に把握・管理できる方法を検討してみてはいかがでしょうか。







