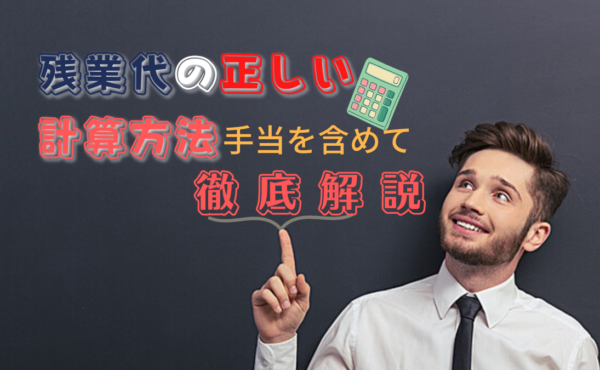
残業(時間外労働)をおこなわせた従業員に対しては、法律で定められた計算方法に従って残業代を支払わなければなりません。残業代を計算するには、1時間あたりの基礎賃金を算出したり、割増率を掛けたりしなければならず、計算が複雑になるケースもあります。
本記事では、残業代の正しい計算方法を給与形態や勤務体系ごとにわかりやすく解説します。
関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も
残業に対する割増賃金の支払いは労働基準法第37条で定められているため、適切に対応しなくてはなりません。
しかし、そもそもの割増賃金の計算方法や割増率の考え方に不安があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義や割増賃金の考え方・計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。
法律に則った適切な割増賃金の計算方法を確認したい方は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 残業の基準と割増率とは?
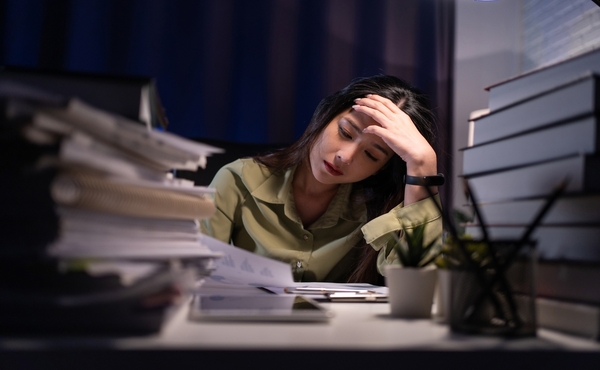
残業や割増率の意味を適切に把握することで、残業代の計算方法を正しく理解することができるようになります。ここでは、残業の基準や割増率について詳しく紹介します。
1-1. 残業に含まれる時間と含まれない時間
残業時間とは、事業者が定める所定労働時間を超えて働く時間を指します。残業時間に含まれる時間は、通常の労働時間に含まれる時間と同様です。労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれているかで判断します。
たとえば、下記の時間は労働時間や残業時間としてカウントしなければなりません。
- 朝礼や夕礼の時間
- 電話番・来客当番の時間
- 強制参加の研修の時間
- 制服・作業着の着用が義務付けられている場合の着替えの時間
- 始業前・終業後の掃除の時間
一方、下記の時間は残業時間に含まれません。
- 休憩時間
- 私用により外出した時間
- 遅刻や早退により勤務していない時間
- 有給休暇を取得している時間
このように、まずは労働時間の定義を正しく理解して、残業時間に該当する時間をきちんと把握できるようにしましょう。
関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!
1-2. 法定内残業と法定外残業の違い
残業には、法定内残業と法定外残業の2種類があります。
法定内残業とは、就業規則などで定められた所定労働時間を超えているものの、労働基準法における法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えていない残業のことです。たとえば、就業規則で1日の所定労働時間が6時間と決められていた場合、1時間の残業が発生しても合計の労働時間は7時間となり、法定労働時間内に収まります。
一方、法定外残業とは、労働基準法の法定労働時間を超えた残業のことです。法定外残業では、割増賃金を加えて賃金を支払うことが義務付けられています。たとえば、所定労働時間が午前9時~午後5時で休憩時間が1時間含まれている企業において、午後7時まで残業をした場合を考えてみましょう。
このケースの労働時間は、休憩時間を差し引くと9時間になります。法定労働時間を超えているのは1時間分となり、割増賃金を加えて賃金を支払わなければならないのは1時間のみです。しかし、所定労働時間を超えて働いた1時間についても、割増賃金は不要ですが残業代を支払う必要があります。
関連記事:法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説
1-3. 残業代に適用される割増率
残業代に適用される割増率は、下記の通りです。割増率については、労働基準法第37条により定められています。
|
残業区分 |
割増率 |
|
法定内残業 |
0% |
|
法定外残業(月60時間以内) |
25% |
|
法定外残業(月60時間超え) |
50% |
法定内残業の場合、割増率は適用されません。一方、法定外残業の場合、割増率25%を適用する必要があります。また、月60時間を超える法定外残業に対しては、割増率50%を適用しなければなりません。
このように残業代は通常の賃金よりも大きいため、人件費を抑え、従業員の健康を守るために、長時間労働を抑制する体制を整備することが大切です。
関連記事:残業の割増賃金とは?割増率の一覧を用いて割増計算方法も詳しく解説
1-4. 残業代と割増賃金の違い
残業代と割増賃金の違いについて、気になる人もいるかもしれません。割増賃金とは、「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」をおこなった場合に、通常の賃金に加えて支給される賃金のことです。それぞれの定義と割増率は、次の通りです。
|
種類 |
割増率 |
定義 |
|
時間外労働 |
25% |
法定労働時間を超えた労働に対して支払う |
|
時間外労働 |
50% |
月60時間を超えた分の時間外労働に対して支払う |
|
深夜労働 |
25% |
22時~翌5時の時間の労働に対して支払う |
|
休日労働 |
35% |
法定休日の労働に対して支払う |
一方、残業代の定義には、深夜労働や休日労働の割増賃金が含まれません。また、残業代には、法定労働時間を超えないが所定労働時間を超える労働時間に対する賃金も含まれます。
このように、残業代と割増賃金は同じ意味合いで用いられることもありますが、異なる意味をもつので正しく理解しておきましょう。
関連記事:休日出勤の割増賃金率は?労働基準法のルールと計算方法を解説
2. 残業代の計算式と計算手順

残業代の計算式は、次の通りです。
ここからは、残業代を正しく計算するための手順を紹介します。
2-1. 基礎賃金を算出する
残業代を計算するために、基礎賃金を計算する必要があります。基礎賃金とは、1時間あたりの賃金のことです。月給の場合、次の式により計算することが可能です。
※月平均所定労働時間 = 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月
なお、週給や日給、時間給、歩合制を採用している場合は、計算方法が異なります。ただし、計算方法は違っても、1時間あたりの基礎賃金を算出することに変わりはありません。
2-2. 対象となる残業時間を計算する
基礎賃金が算出できたら、その月に該当する残業時間を計算しましょう。残業代を正しく計算するために、下記の3つの残業時間を算出することが大切です。
- 所定労働時間を超えるけれど法定労働時間を超えない残業時間
- 法定労働時間を超える残業時間(月60時間以内)
- 法定労働時間を超える残業時間(月60時間超え)
なお、週40時間(法定労働時間)は、法定休日に労働した時間と1日8時間を超える労働時間を除いたうえで、1日8時間以下の労働時間の累積で考えます。たとえば、1日の所定労働時間が7時間、法定休日が日曜日の場合は、下記のように法定内残業時間と法定外残業時間が計算されます。
|
1週間 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
労働時間 |
0時間 |
7時間 |
7時間 |
7時間 |
10時間 |
8時間 |
7時間 |
|
週の累計 |
0時間 |
7時間 |
14時間 |
21時間 |
29時間 |
37時間 |
44時間 |
|
法定内残業時間 |
0時間 |
0時間 |
0時間 |
0時間 |
1時間 |
1時間 |
0時間 |
|
法定外残業時間 |
0時間 |
0時間 |
0時間 |
0時間 |
2時間 |
0時間 |
4時間 |
このように、土曜日の労働では1日の所定労働時間を超えていませんが、週の法定労働時間を4時間オーバーしているため、法定外残業時間は4時間と計算されます。
関連記事:労働時間の正しい計算方法とは?勤務時間との違いや残業代の計算の仕方も解説!
2-3. 割増率を掛けて残業代を算出する
基礎賃金と対象となる残業時間が出揃ったら、それぞれの残業時間に適した割増率を掛けることで、残業代を計算することができます。
当サイトがお配りしている無料ガイドブック「【残業ルールBOOK】残業時間の管理ルールと効果的な管理方法を解説!」では、法内残業や法外残業など残業の規定を図解しながらわかりやすく解説しています。 割増計算の基本的な部分から確認したいという方は、こちらから【残業ルールBOOK】ダウンロードして、是非ご活用ください。
3. 残業代の具体的な計算方法

残業代計算における注意点を理解したうえで、実際に残業代を計算してみましょう。ここでは、残業代の具体的な計算方法をケース別で紹介します。
3-1. 年俸制の場合
ここでは、年俸制の場合の残業代の計算方法を解説します。下記のケースを考えてみましょう。
- 年俸:360万円
- 1年間の所定労働日数:240日
- 1日の所定労働時間:8時間
- 残業時間:20時間
月平均所定労働時間は160時間(= 240日 × 8時間 ÷ 12ヵ月)と計算できます。また、年俸を月給に換算する場合、月給は30万円(= 360万円 ÷ 12ヵ月)と算出することが可能です。
以上から、基礎賃金は1,875円(= 30万 ÷ 160時間)と計算されます。時間外労働の割増率1.25を用いて、残業代は37,500円と算出することが可能です。
関連記事:年俸制を導入する際に知っておくべきこと|気になる疑問や注意点を解説
3-2. 月給制の場合
ここでは、月給制の場合の残業代の計算方法を解説します。下記のケースを考えてみましょう。
- 月給:30万円
- 1年間の所定労働日数:240日
- 1日の所定労働時間:8時間
- 残業時間:15時間
月平均所定労働時間は160時間(= 240日 × 8時間 ÷ 12ヵ月)と計算できるので、基礎賃金は1,875円(= 30万円 ÷ 160時間)と算出することが可能です。この場合の割増率は1.25が適用されます。
残業代の計算式に当てはめ、端数処理もおこなうと、残業代は35,156円(= 1,875円 × 1.25 × 15時間)と計算することができます。
3-3. 日給制の場合
日給制で働いている人の場合、所定労働時間を超えた分については、他の働き方と同様に残業代が発生します。下記のケースを想定して、その日の残業代を計算してみましょう。
- 日給:1万4,000円
- 1日の所定労働時間:7時間
- 残業:2時間
まずは月給制と同様、基礎賃金を算出しましょう。基礎賃金は2,000円(= 1万4000円 ÷ 7時間)と計算することができます。
1日の法定労働時間は8時間なので、残業時間のうち1時間分には割増賃金が適用されません。残りの1時間分には割増率1.25が適用され、割増賃金は2,500円(= 2,000円 × 1.25 × 1時間)と計算されます。そのため、残業代は4,500円(= 2,000円 + 2,500円)と算出することができます。
3-4. 時給制の場合
時給制も日給制のように、1時間あたりの給与が固定している給与形態です。下記のケースを想定して、その日の残業代を計算してみましょう。
- 時給:2,000円
- 1日の所定労働時間:8時間
- 残業:2時間
この場合の基礎賃金は時給2,000円が採用されます。残業代は5,000円(= 2,000円 × 1.25 × 2時間)と計算することが可能です。
3-5. 歩合制の場合
歩合給は「インセンティブ制」や「出来高払制」などともいわれる、個人の業績や成果に応じて給与を支払う形態です。労働基準法第27条により、賃金保障のため、従業員に対して完全歩合制をとることは認められておらず、歩合制を採用する場合は「固定給+歩合給」といった形での支払いとなります。
(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
ここからは、歩合制の場合の残業代の計算方法を解説します。下記のケースを考えてみましょう。
- 固定給:20万円
- 歩合給:9万円
- 1年間の所定労働日数:240日
- 1日の所定労働時間:8時間
- 残業:20時間
歩合制の残業代は、固定給と歩合給それぞれの残業代を算出し、両者を合計したものになります。固定給に対する残業代は、月給制と同じように計算しましょう。
歩合給に関しては「時間の延長により成果が上がった」という捉え方がされるため、すでに時間単価の給与が歩合給に含まれているとし、割増率「1.25」ではなく割増率「0.25」をかけた金額が残業代となります。
まずは固定給における残業代を計算しましょう。月平均所定労働時間は160時間(= 240日 × 8時間 ÷ 12ヵ月)になるので、固定給部分の基礎賃金は1,250円(= 20万円 ÷ 160時間)と計算できます。そのため、固定給に対する残業代は31,250円(= 1,250円 × 1.25 × 20時間)です。
一方、歩合給の基礎賃金は50円(= 9万円:歩合給 ÷ 180時間:1ヵ月の総労働時間)となります。歩合給に対する残業代は250円(= 50円 × 0.25 ×20時間)です。以上から、歩合制の残業代は31,500円と計算できます。
3-6. 月60時間を超える残業の場合
月60時間を超える残業が発生した場合は、どのように残業代が計算されるのでしょうか。下記のケースを考えてみましょう。
- 月給:50万円
- 1年間の所定労働日数:240日
- 1日の所定労働時間:8時間
- 残業:70時間
月平均所定労働時間は160時間(= 240日 × 8時間 ÷ 12ヵ月)と計算できるので、基礎賃金は3,125円(= 50万円 ÷ 160時間)と算出することが可能です。残業60時間までの割増率は1.25、残業60時間超えの割増率は1.50が適用されます。
以上より、残業代は281,250円(= 3,125円 × 1.25× 60時間 + 3,125円 × 1.50 × 10時間)と計算できます。
関連記事:残業が月60時間を超過すると割増賃金が増える?中小企業の猶予も解説
3-7. 残業と深夜労働が重なる場合
残業と深夜労働が重なるケースもあります。なお、休日労働には残業という定義がないので、重複する可能性はありません。時間外労働と深夜労働、深夜労働と休日労働が重なるケースにおける割増率は、次の表の通りです。
|
重複するケース |
割増率 |
|
残業(60時間以内)と深夜労働 |
50%(= 25% + 25%) |
|
残業(60時間超え)と深夜労働 |
75%(= 50% + 25%) |
|
深夜労働と休日労働 |
60%(= 25% + 35%) |
下記のケースを想定して、残業代を計算してみましょう。
- 月給:30万円
- 1年間の所定労働日数:240日
- 1日の所定労働時間:8時間
- 残業:30時間
- 夜勤:20時間
- 上記のうち残業と夜勤が重複する時間:10時間
基礎賃金は1,875円です。まずは夜勤に該当しない残業(割増率1.25)における残業代を計算しましょう。残業のみに該当する時間は20時間であるため、残業代は46,875円(= 1,875円 × 1.25 × 20時間)です。
次に残業と夜勤が重複したとき(割増率1.50)の残業代を計算しましょう。割増賃金は28,125円(= 1,875円 × 1.50 × 10時間)となります。そして、夜勤(割増率1.25)における割増賃金は23,437.5円(= 1,875円 × 1.25 × 10時間)です。
最後にすべてを合計し、端数処理すると、割増賃金(残業代を含む)は98,438円となります。
関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説
4. 残業代を計算する際の注意点

残業代を計算する際に、考慮しなければならない点がいくつかあります。ここでは、残業代を計算する際に注意すべき点について詳しく紹介します。
4-1. 残業代を計算する際に手当を除外する
残業代を計算するには、基礎賃金を求める必要があります。基礎賃金を算出する際は、原則として各種手当を含めなければなりません。しかし、下記の手当は除外する必要があります。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
なお、労働者の個人的な事情を加味したうえで、手当を除外するか判断します。たとえば、通勤手当でも、「全従業員に3万円支給」のように、従業員それぞれの状況に関係なく一律で支給する場合は、基礎賃金の計算に含めなければなりません。
また、上記に含まれていない手当についても、労働者一人ひとりの事情を加味して支給する手当は、基礎賃金の計算から除外することができます。このように、残業代を計算する際は、基礎賃金の計算に各種手当を含めるかどうか検討する必要があります。
関連記事:割増賃金の計算方法とは?除外する手当の取り扱いや具体例を紹介!
4-2. 残業代計算の端数処理に注意する
実際に残業代計算をおこなうと、端数が発生するケースもあります。事務処理の簡便化のために、認められている端数処理は、下記の通りです。
- 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
- 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
- 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2.と同様に処理すること
このように、従業員が不利にならないような範囲での端数処理は問題ありません。
関連記事:厚生労働省が定めた労働時間の端数処理ルールをわかりやすく解説!
4-3. 残業代の代わりに代替休暇の付与も検討できる
代替休暇とは、月60時間超えの時間外労働に対して割増賃金を支払う代わりに有給休暇を与える制度のことです。ただし、代替休暇を取得した場合でも、通常の時間外労働に対して適用される25%分の割増賃金は支払わなければなりません。代替休暇を付与することで、企業は残業代の削減、従業員は長時間労働の削減のメリットが得られます。
ただし、代替休暇制を導入するには、労使協定の締結が必要です。また、代替休暇を取得するかどうかは従業員の意思で決めることができます。そのため、残業代を減らしたいという理由で、強制的に代替休暇を取得させることはできません。このように、代替休暇は効果的な制度でありますが、導入する場合は注意点に気を付けましょう。
5. 残業代の勤務形態別における計算方法

現在ではさまざまな勤務形態が浸透してきており、それに伴って残業代の計算方法も変化します。ここでは、勤務形態別の残業代の計算方法について紹介しますのでチェックしておきましょう。
5-1. フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、3ヵ月以内で清算期間とその期間中の総労働時間を設定し、始業時間と終業時間は従業員が自由に設定できる制度のことです。フレックスタイム制の場合、ある日にだけ10時間働いたとしても、すぐに残業代が発生するわけではなく、清算期間内の法定労働時間の総枠を超えて労働した場合に、残業代の支払いをおこないます。
たとえば、清算期間を1週間とすれば、法定労働時間の総枠は40時間です。このとき、ある週に合計42時間働いた従業員がいた場合は、法定労働時間の総枠を2時間オーバーして働いているため、2時間分の残業代を支払うことになります。
関連記事:フレックスタイム制で残業代は減るの?残業時間や残業代の計算方法を解説!
5-2. 裁量労働制
裁量労働制とは、実労働時間を算定するのが不適当であると思われる業務に適用される勤務体系で、法律によって適用できる職種・業務が定められています。労使協定により、みなし労働時間が定められ、多く働いても少なく働いても、みなし労働時間働いたと見なされます。
ただし、みなし労働時間が法定労働時間を超える部分については、残業代を支払わなければなりません。たとえば、みなし労働時間が9時間であれば、法定労働時間の8時間を1時間超えているため、1時間分の残業代を基本給に組み込んで支払います。
関連記事:裁量労働制は残業代が出ない?計算方法や休日出勤・深夜労働についてわかりやすく解説!
5-3. みなし残業制(固定残業代制)
みなし残業制(固定残業代制)は、あらかじめどのくらいの残業が見込まれるか想定し、その分の残業代を基本給に含めて支払う方法です。
実際の残業時間が当初見込まれた残業時間を超えた分に関しては、超過分の残業代を支払います。一方、実際の残業時間が想定された残業時間に達しなかったとしても、足りない分の残業代を基本給から差し引くことはできません。
関連記事:「みなし残業」での違法を防ぐために|知っておきたい正しい運用方法
5-4. 変形労働時間制
変形労働時間制とは、平均労働時間が週40時間の枠内に収まっていれば、特定の日や週、月に法定労働時間を超えて働かせることができる制度です。
変形労働時間制では日・週・月のそれぞれで残業時間を算出します。具体的には、所定労働時間が法定労働時間よりも長い場合は、所定労働時間を超えた時間から、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合は、法定労働時間を超えた時間からが時間外労働としてカウントされ、残業代の支給が必要となります。
関連記事:変形労働時間制の残業時間の上限とは?残業代や割増賃金の計算方法も解説!
6. 残業代の請求権の時効

残業代を適切に支給していない場合、従業員から未払い分の賃金を請求される可能性があります。労働基準法第115条により、残業代の請求権の時効は5年間です。しかし、労働基準法第115条の賃金請求権の時効期間には、経過措置が設けられているため、当分の間は「5年間」でなく「3年間」が適用されます。とはいえ、経過措置はいつ終了するのか未定なので注意が必要です。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
たとえば、1時間あたりの残業代の割増分が250円の従業員100人に対して2年間(1ヵ月の平均勤務日数は20日)の未払いを続けた場合、もし従業員から請求を受けると、追加で1,200万円(= 250円 ×100人 ×20 日 × 24ヵ月)の人件費を支払う義務が生じます。支払義務のある金額が高額になれば、企業の経営に関わる問題にもなりかねないでしょう。
6-1. 残業代や残業時間を記録した書類を保存しておくことが必要
タイムカードや出勤簿など、残業代や残業時間に関する書類は、5年間(当面の間は3年間)保管しておかなければなりません。これは先ほど紹介した、残業代の請求権の時効が5年間であることと関係しています。
企業としては、未払いの残業代を請求される可能性に備え、関連する書類を保管しておく必要があるのです。労働時間を証明する記録がない場合、大きなトラブルに発展する可能性もあるため注意しましょう。
関連記事:労働基準法第109条の重要な書類の保存期間は何年?法改正や経過措置、違反した場合の罰則を解説!
7. 残業代の計算でよくある質問と注意点
 ここまで解説してきた通り、残業代の計算は単純ではありません。各企業が定める所定労働時間や時間外労働の時間などによっても左右されるため、担当者はあらかじめ残業に関する知識を身につけておくことが大切です。
ここまで解説してきた通り、残業代の計算は単純ではありません。各企業が定める所定労働時間や時間外労働の時間などによっても左右されるため、担当者はあらかじめ残業に関する知識を身につけておくことが大切です。
ここでは、残業代の計算においてよくある質問への回答を紹介します。
7-1. 管理職に残業代は発生しない?
管理監督者の場合は、労働基準法によって定められた労働時間や休憩、休日の適用が適用されないため、時間外労働や休日労働の割増手当が除外されることとなっています。しかし、深夜労働の割増手当は支給しなければなりません。
ただし、ここで注意したいのは、すべての管理職が管理監督者に該当するわけではないという点です。社内では管理職という立場であっても、管理監督者であるかどうかは以下のポイントが関係してきます。
|
ポイント |
内容 |
|
職務内容・責任・権限 |
|
|
勤務形態 |
|
|
待遇 |
|
これらに該当しない場合、管理監督者ではなく、いわゆる「名ばかり管理職」の可能性があるため、給与計算についても注意が必要です。
関連記事:労働基準法41条2号の管理監督者とは?管理職に対する残業代の支給についても解説!
7-2. 残業代を間違って支払ってしまった場合はどうする?
本来支払うべき残業代よりも少なく支払っていた場合は、対象となる従業員に説明をし、同意を得たうえで、翌月の給与で支給します。反対に、本来支払うべき残業代よりも多く支払っていた場合は、対象となる従業員に説明をしたうえで、翌月の給与から差額を差し引いて支給します。
雇用保険加入者の場合は、多く支払っている場合に雇用保険料も多く徴収されているため、支給項目の欄にマイナス金額を入れて処理する形になるでしょう。
7-3. 36協定を締結せずに残業をさせることはできない
そもそも従業員に法定労働時間を超えた残業を命じるためには、事前に36協定を締結しなければなりません。36協定を締結せずに残業を命じることは違法であるため注意しましょう。
また、36協定を締結した場合、残業時間の上限は週45時間・年360時間となります。臨時的な特別の事情がなければ、この上限を超えることはできません。
7-4. 固定残業代を支給する場合の注意点は?
固定残業代を支給する際は、固定残業代が何時間分の残業代になるのか明確にしておくことが必要です。また、基本給と固定残業代も明確に分けておかなければいけません。
固定残業時間を超えている場合は、追加残業代がきちんと支払われているかも確認しましょう。未払い残業代が発生している場合、後日従業員から請求される可能性があります。
関連記事:固定残業代とは?手当型と組込型の違いや就業規則・労働条件通知書への記載についてわかりやすく解説
7-5. 残業代の計算単位は?
基本的に残業代は1分単位で計算しなければいけません。たとえば、20時10分に退勤でタイムカードを打刻していたからといって、20時として切り捨てるようなことはできません。
ただし、月の総残業時間に関しては、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることが可能です。残業代を計算する際には、1円未満の端数が発生することもあるため、就業規則に「50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ」といった内容を定めておくとよいでしょう。
関連記事:勤怠管理を15分単位でおこなうのは違法!残業時間の切り捨てが許可されるケースも解説!
7-6. 残業代には上限がある?
36協定による時間外労働の上限は「月45時間、年360日」に定められています。とはいえ、業務を遂行するためには時間が足りないなどの理由から、一時的に法律の限度時間を超えて残業しなければならないケースもあるかもしれません。
このような場合、労使の協議をおこなって「特別条項付き36協定」を結ぶことによって例外的に残業時間の上限を超えることが可能です。なお、この場合の上限は「月100時間未満、年720時間以内」です。また、45時間を超える残業は1年で6ヵ月まで、休日出勤の時間を含めて2~6ヵ月の残業時間は平均80時間以内にしなければいけません。
つまり、残業時間にも上限があり、上限を超えて残業させると賃金を支払ったとしても労働基準法に違反することになるので気を付けましょう。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
8. 残業代の計算を効率化する方法

残業代の計算を効率化したい場合は、エクセルや勤怠管理システムを活用するのがおすすめです。
8-1. エクセルを活用する
費用をかけずに残業代の計算を効率化したい場合は、エクセルを活用するとよいでしょう。すでに会社のパソコンにインストールされていることも多く、使い慣れたツールであるので、気軽に導入できます。
労働時間や残業時間を計算する関数を設定しておけば、電卓で計算するような手間を省けます。ただし、入力ミスが発生すると正しい残業代を算出できないため注意しましょう。また、誰でも書き換えられる状態で管理すると、不正な改ざんなどが発生する可能性もあるので、アクセス制限を設定することも大切です。
8-2. 勤怠管理システムを導入する
従業員数が多い場合や多様な働き方を採用している場合は、残業代の計算に手間がかかるため、勤怠管理システムの導入がおすすめです。勤怠管理システムを活用すれば、日々の出退勤時刻を入力していくだけで、労働時間や残業時間を自動で集計し、簡単に残業代を計算できます。
また、法律改正に対応しやすいことも大きなメリットです。クラウド型の勤怠管理システムのなかには、定期的にアップデートされるものもあり、残業代の計算ルールが改正された場合でも自動で対応できます。
9. 残業代の計算方法の基本を知っておこう

今回は、残業代の計算方法や計算上の注意点などを解説しました。残業代の計算は少々複雑なものもあるため注意が必要ですが、正しく計算して支払わなければなりません。割増率や計算手順を間違えると、残業代が未払いの状態となり、労使間のトラブルが発生したり、法律違反として罰則を受けたりする可能性もあります。
社会的なイメージが悪化する可能性もあるため、従業員ごとの労働時間をしっかりと把握したうえで、正しく計算するようにしましょう。また、残業代を含む給与計算を効率化したい場合は、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。労働時間の管理から給与の算出までを自動化できるため、業務効率化を図りたい場合はぜひ導入を検討しましょう。









