
従業員の月の時間外労働が60時間を超えた場合、支払うべき割増賃金の比率は通常よりも高くなるため、トラブル防止のためにも正しい計算方法を知っておく必要があります。
今回は、月の時間外労働が60時間を超えてしまった場合の割増賃金について、割増率や賃金の計算方法を紹介します。また、60時間を超えないよう時間外労働を削減するための対策についても解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
これまで大企業のみに適用されていた月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%の規定が、2023年4月より中小企業にも適用されます。
しかし、「割増率が引きあがるのは知っているが、何を準備しておくべきかわからない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは割増賃金率の引き上げを含め、昨今の働き方改革による法改正で中小企業がとるべき対応をまとめた資料を無料で配布しております。
法律に則った勤怠管理をしていきたい方は、ぜひ下のボタンからダウンロードしてご活用ください。
目次
1. 割増賃金とは?

そもそも割増賃金とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超過した分の労働や休日労働などに対して、割増して支払う賃金のことです。割増率は、割増労働の種類によって異なっており、それぞれ労働基準法によって定められています。
ここでは、割増賃金率の一覧や、残業代と割増賃金の違いを詳しく紹介します。
1-1. 割増賃金率の一覧
割増賃金を支払わなければならないケースとして、下記の時間外労働、休日労働、深夜労働(夜勤)が挙げられます。
- 時間外労働:25%(※月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は後述)
- 休日労働(法定休日の労働):35%
- 深夜労働(22時~5時の深夜帯の労働):25%
割増賃金の適用が重複するケースもあります。たとえば、1日8時間以上の夜勤をおこなった場合、割増賃金は50%(= 時間外労働25% + 深夜労働25%)となり、法定休日に深夜労働をおこなった場合は60%(= 休日労働35% + 深夜労働25%)となります。
なお、所定休日(法定外休日)の労働に対しては、休日労働の割増賃金が適用されません。ただし、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働く場合や、22時から5時までの間に労働する場合、時間外労働や深夜労働の割増賃金は適用されるので注意が必要です。
1-2. 割増賃金と残業代の違い
残業代とは、残業手当や超過勤務手当とよばれることもあり、会社が取り決めている所定労働時間を超えて働く場合に支給する手当のことです。 そのため、残業代と割増賃金は意味が異なります。
たとえば、就業規則で所定労働時間を7時間と定めている企業を考えてみましょう。なお、週の法定労働時間については考慮しないこととします。この場合、1日7時間を超えて働くと残業代が発生します。ただし、1日7時間を超えても8時間以内であれば、法定労働時間を超えないため割増賃金を支給する必要はありません。
2. 時間外労働が月60時間を超えると割増賃金が増える
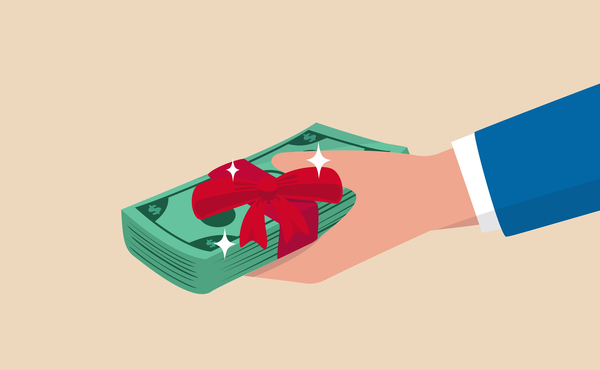
法定労働時間として労働基準法で定められた1日8時間、週40時間の上限を超えた時間外労働をおこなわせた場合には、25%以上の割増率で算出した賃金を支払う必要があります。
また、長時間残業による健康被害を防止するため、時間外労働が月60時間を超過した場合は割増率をさらに引き上げ、50%として割増賃金を支払う規定が設けられています。
中小企業に対しては適用の猶予期間が設けられていましたが、2023年3月31日で終了となり、2023年4月1日以降は企業の規模にかかわらず全ての企業に上記の規定が適用されています。以下、ポイントを詳しく解説します。
2-1. 割増賃金率を50%に引き上げる背景・目的とは?
月60時間を超過する時間外労働の割増賃金を50%にまで引き上げる目的としては、長時間の時間外労働を抑制することが挙げられます。厚生労働省は、割増賃金の引き上げには、長時間労働の常態化に加えて下記のような背景があったと公式資料に記載しています。
少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移しており、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。
割増賃金率が引き上げられることで、企業は60時間を超える残業時間を控えるようになり、総労働時間の削減が期待できるでしょう。また、従業員の残業時間の減少やワークライフバランスの向上も見込めます。
割増賃金率を上げることは多くの企業にとって負担にも見えますが、将来的に企業の利益となるメリットが多いといえるでしょう。2023年3月の猶予期間終了により、中小企業においても残業削減に向けて対策を講じ、業務の効率化を図ることでより働きやすい環境をつくることが求められています。
2-2. 割増賃金ではなく代替休暇を付与することもできる
60時間を超過した時間外労働の手当として、企業は割増賃金を支払うのではなく、該当金額分の代替休暇(有給)を付与することで対応することもできます。
ただし、代替休暇に替えられるのは、残業時間が60時間を超過すると同時に増加した割増率25%の割増賃金分のみです。仮に70時間の時間外労働をさせたのであれば、超過している10時間分について25%の割増賃金の支払いは通常通りおこないます。
つまり、従業員が代替休暇を取得した場合でも、60時間を超えた分の労働に対し、基本の時間外労働の割増賃金分(基礎賃金 × 1.25)を支払う必要はあるため注意しましょう。付与する代替休暇の時間数は、以下の計算式で算出できます。
代替休暇の時間数 = 60時間を超えた分の法定外残業時間数 × 換算率
※換算率 = 「代替休暇を取得しない場合の賃金の割増率50%」 – 「代替休暇取得した場合の賃金の割増率25%」
2-3. 中小企業に対する割増賃金の猶予期間はいつまで?
先述の通り、2010年より大企業では、すでに割増率の引き上げに関する規制は適用されています。中小企業については、業務体制の見直しや新しい人材の採用を短期間でおこなうことは難しいことから、しばらくの猶予期間が設けられていました。
しかし、適用の猶予期間は2023年3月31日で終了し、2023年4月1日以降は大企業と同様に60時間を超過した時間外労働には、さらに上乗せで手当を支給しなければならないことになっているので気を付けましょう。
2-4. パートやアルバイトも割増賃金の対象となる
正社員はもちろん、パート・アルバイトの従業員や契約社員なども割増賃金の対象となります。時間外労働・休日労働・深夜労働が発生した場合は、労働基準法に従って割増賃金を支払いましょう。
当然、時間外労働が60時間を超過した場合は、割増率が50%となります。雇用形態に関係なく、同様の扱いをする必要があるため注意しなければなりません。
2-5. 割増賃金を支払わない場合の罰則
適切な割増賃金を支払わない場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあります。また、労働基準監督署が企業に対して実態の確認を実施するケースもあるため、残業時間をしっかりと把握したうえで、適切な割増賃金を支払うようにしましょう。
割増賃金の未払いが発生すると、労使間のトラブルにつながるだけではなく、企業イメージの低下にもつながるので注意が必要です。
3. 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金

通常、時間外労働を命じる場合、使用者は従業員に対し、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。また、月の時間外労働が60時間を超えた従業員に対して、50%以上の割増率で算出した賃金を支払う必要があります。
さらに、月の時間外労働が60時間を超えた段階で、深夜労働や休日労働をおこなった場合には、以下で解説する通り、割増率を上乗せして賃金の支払いをおこないます。法律違反とならないよう、しっかりと対策をおこないましょう。
とはいえ、なにから対策をおこなえばよいのか分からないという方に向けて、当サイトでは「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」という無料のガイドブックをお配りしています。
法律の改正内容や、対応する際に管理するべき項目、効果的な管理方法についてわかりやすく解説しています。こちらから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」をダウンロードして、内容を照らし合わせながら法改正に対応しましょう。
3-1. 深夜の時間外労働(残業)に対する割増率
深夜労働の時間帯におこなった時間外労働で、1ヵ月60時間を超える時間外労働となった場合は、75%以上の割増率(時間外労働の割増率50%以上と深夜労働の割増率25%以上)で算出した賃金を支払います。
3-2. 休日の時間外労働(残業)に対する割増率
休日労働の時間帯に時間外労働をおこなう場合、すでに月60時間を超えた時間外労働をおこなっているときでも、通常の割増率(35%以上)の計算となります。
これは、休日労働と時間外労働が別の扱いとなることに基づきます。時間外労働は労働義務がある日に対して発生する割増賃金ですが、休日労働はもともと労働義務がない日の労働に対して発生する割増賃金であるため、同時に発生することはありません。
4. 時間外労働(残業)が月60時間を超えた際の割増賃金の計算方法
 ここでは、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金の計算方法を紹介します。
ここでは、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金の計算方法を紹介します。
「1ヵ月平均の所定労働時間を計算」「従業員1時間あたりの基礎賃金を計算」「割増賃金を計算」の3つのステップで説明していきます。
4-1. 1ヵ月平均の所定労働時間を計算
まず、従業員の1ヵ月平均の所定労働時間を算出します。1ヵ月平均の所定労働時間の算出方法は、以下の通りです。
4-2. 従業員の1時間あたりの基礎賃金を計算
次に、従業員の1時間あたりの基礎賃金額を計算します。月給制の場合を例とした計算式は、以下の通りです。
関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説
4-3. 割増賃金を計算
最後に割増賃金の計算をおこないます。
60時間までの時間外労働に対する割増賃金と、60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金では割増率が異なるため、それぞれを別で計算しましょう。
60時間までの時間外労働では割増率1.25倍を、60時間を超えた時間外労働では割増率1.5倍を適用します。
時間外労働60時間までの割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金額 × 1.25 × 60時間
時間外労働60時間超の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金額 × 1.5 × 超過時間
月給30万円で月の所定労働時間を150時間とし、残業時間70時間の従業員を例とする場合、1時間あたりの基礎賃金額と割増賃金は以下の通りです。
1時間あたりの基礎賃金額:300,000円 ÷ 150 = 2,000円
60時間までの割増賃金:2,000円 × 1.25 × 60 = 120,000円
60時間超の割増賃金:2,000円 × 1.5 × 10 = 30,000円
割増賃金合計:120,000円 + 30,000円 = 150,000円
関連記事:割増賃金の計算方法とは?除外する手当の取り扱いや具体例を紹介!
5. 割増賃金の引き上げへの対策

月60時間を超えた残業をおこなった場合の割増賃金率が50%に引き上げられたことを受け、どのように対応すればよいか不安に感じている人もいるかもしれません。
ここでは、割増賃金率の引き上げへの具体的な対策について詳しく紹介します。
5-1. 正確な時間外労働時間の把握
まずは正確な労働時間の把握を徹底しましょう。誰がどれくらいの時間働いているのかを把握することで、月60時間超の残業をしている従業員やその理由を可視化することができます。
一部の従業員に残業時間が偏っている場合は、業務量が適切でない可能性が高いため、同じ部署内の人に調節やフォローを促すなどの対策が必要です。一方、全体的に残業時間が多い場合は労働力が不足している可能性が高いので、アウトソーシングや新たに人材を募集することも手段の一つです。
5-2. 業務効率化による残業の抑制
月60時間を超える時間外労働に対するコストを抑えるためにも、業務の見直しをおこなうことが大切です。業務の無駄を見つけ、改善していくことで業務の効率化を期待できます。
業務をマニュアル化して誰でも同じ業務をおこなえるようにする、デジタル化できる部分はシステムを導入するなどの方法があります。
無駄を省くことで残業が少なくなるだけでなく、仕事に余裕が生まれ、従業員が余裕をもって業務に専念したり、新しい事業にチャレンジしたりすることもできるでしょう。
5-3. 代替休暇の活用
月60時間を超える時間外労働をおこなった労働者に、有給休暇を与えるのが代替休暇です。代替休暇は企業の一存で決定できるものでなく、利用するかしないかの決定権は従業員側にあります。
また、代替休暇制度を導入するには、事前に労使協定を締結する必要があるため注意しましょう。代替休暇の導入を検討する際には、労働者代表をはじめとする全従業員が納得できるルールを考えることが重要です。
5-4. 勤怠管理システムを整備する
紙のタイムカードで勤怠管理をおこなっている場合、時間外労働が月60時間を超えるかどうかで割増賃金率の適用を変更しなければならず、集計の負担が大きくなります。また、時間外労働の上限の基準を超えているかどうかは、集計時にしか把握できません。
法律にきちんと対応するためにも、勤怠管理システムを整備するのがおすすめです。勤怠管理システムを導入すれば、集計を自動化できるので、計算ミスや業務負担を削減することができます。また、従業員の労働時間をリアルタイムで可視化できるため、長時間労働をおこなっている従業員に対して注意を促すことも可能です。
5-5. 就業規則への追記
割増賃金を含む従業員の給与に関する情報は、就業規則に明記する必要があります。厚生労働省が公開している就業規則への記載例は、下記の通りです。
(割増賃金)
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。① 時間外労働60時間以下・・・・25%
② 時間外労働60時間超・・・・・50%
割増賃金率に関する記載を変更していない場合や、代替休暇・勤怠管理システムといった新しい制度を導入する場合は、今一度、就業規則を見直して適切に書き換えましょう。
5-6. 助成金を利用する
各種の助成金を活用しながら業務改善を進めることも重要です。厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金や業務改善助成金といった制度を整えています。
働き方改革推進支援助成金は、中小企業を対象とした助成金です。業務の生産性を向上させ、労働時間の短縮を図った際に、その費用の一部を助成してもらえます。
また業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資にかかった費用などの一部を助成してもらえる制度です。事業場内の最低賃金を一定以上引き上げたときに受給できます。
このような助成金を活用することで、費用負担を抑えながら業務改善や残業時間の削減を進められるでしょう。
参照:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省
6. 時間外労働が月60時間を超えないようにする対策

時間外労働を削減するため、次の6つの対策を検討してみましょう。
6-1. 勤怠管理システムを活用して時間外労働を管理する
従業員の労働時間をこれ以上増やさないためにも、どの従業員がどれくらいの残業をおこなっているか正しく把握することが大切です。
そのための手段としておすすめの方法が、先ほど紹介した勤怠管理システムの導入です。勤怠管理システムを活用することで、残業時間を正確かつリアルタイムに把握できるようになるため、時間外労働の原因の特定や対応施策の実行がスムーズに実施でき、時間外労働の削減に役立ちます。
6-2. ノー残業デーの社内ルール化
社内で「残業をしない日」として設定する「ノー残業デー」を作り、定時までに仕事を終わらせてしまう、というのも時間外労働を削減するために効果的な方法です。
また、ノー残業デーの導入で従業員が残業をしないために業務を効率化するきっかけをつかめば、他の日の残業時間も相乗的に減少させることができるでしょう。運用の際には社内ルール化をし、たとえ仕事が残っていた場合でも例外を認めないという姿勢で進めていくことが大切です。
関連記事:ノー残業デーの効果とは?メリット・デメリットや成功のコツをわかりやすく解説!
6-3. 残業申請の義務化
従業員が時間外労働をおこなう際には、従業員自身が残業の判断をするのではなく、あくまでも事前に申請したうえで残業を認める形をとりましょう。
管理職に残業申請をし、承認を受けないと残業できないというルールにすることで、不要な残業を削減することができます。また、従業員の過重労働の防止にもつながります。
6-4. 業務効率化を進める
時間外労働を削減するためには、社内全体で業務効率化を進めることが重要です。たとえば、無駄な業務を洗い出して改善する、業務の偏りを把握して人員配置を見直す、ITツールの導入によりDX化を推進するなどの対策が考えられます。
業務を効率化することで、時間外労働を削減できるだけではなく、仕事の質の向上や従業員のモチベーションアップも図れるでしょう。
6-5. アウトソーシングを検討する
業務の一部をアウトソーシングすることも、時間外労働を削減する対策の一つです。無理に社内で処理する必要のない業務を外部に委託すれば、従業員は重要なコア業務に専念できます。
委託するための費用はかかりますが、新たな従業員を雇用する必要はないため、採用コストや教育コストを抑えながら業務効率を向上させることが可能です。
6-6. 管理職が率先して残業を減らす
部下に時間外労働を減らすよう指示するだけではなく、管理職が率先して早く帰るように意識することも大切です。たとえば、管理職自身が業務フローの改善を図り、時間外労働を減らすよう努力するとよいでしょう。
また、ノー残業デーには管理職が率先して帰るなど、部署全体によい影響を与えるような行動をすることが重要です。
7. 月60時間を超える時間外労働に対して適切な割増賃金を支給しよう!

月60時間を超える時間外労働を従業員に命じる場合、通常の時間外労働の割増率を引き上げて割増賃金を支払う必要があります。
以前は大企業のみに適用されていたルールですが、2023年4月以降は全ての企業に適用範囲が拡大されているため、すぐに対策しなければなりません。賃金計算をする際には、正しい計算方法を確認し、未払いなどの支払いトラブルが発生しないよう注意しましょう。
また、基本的に月60時間を超える時間外労働は、決算期の処理など特別な事情がある場合のみに認められた例外です。日頃から可能な範囲で削減できるよう、勤怠管理システムの導入やノー残業デーの社内ルール化といった対策をとるようにしましょう。








