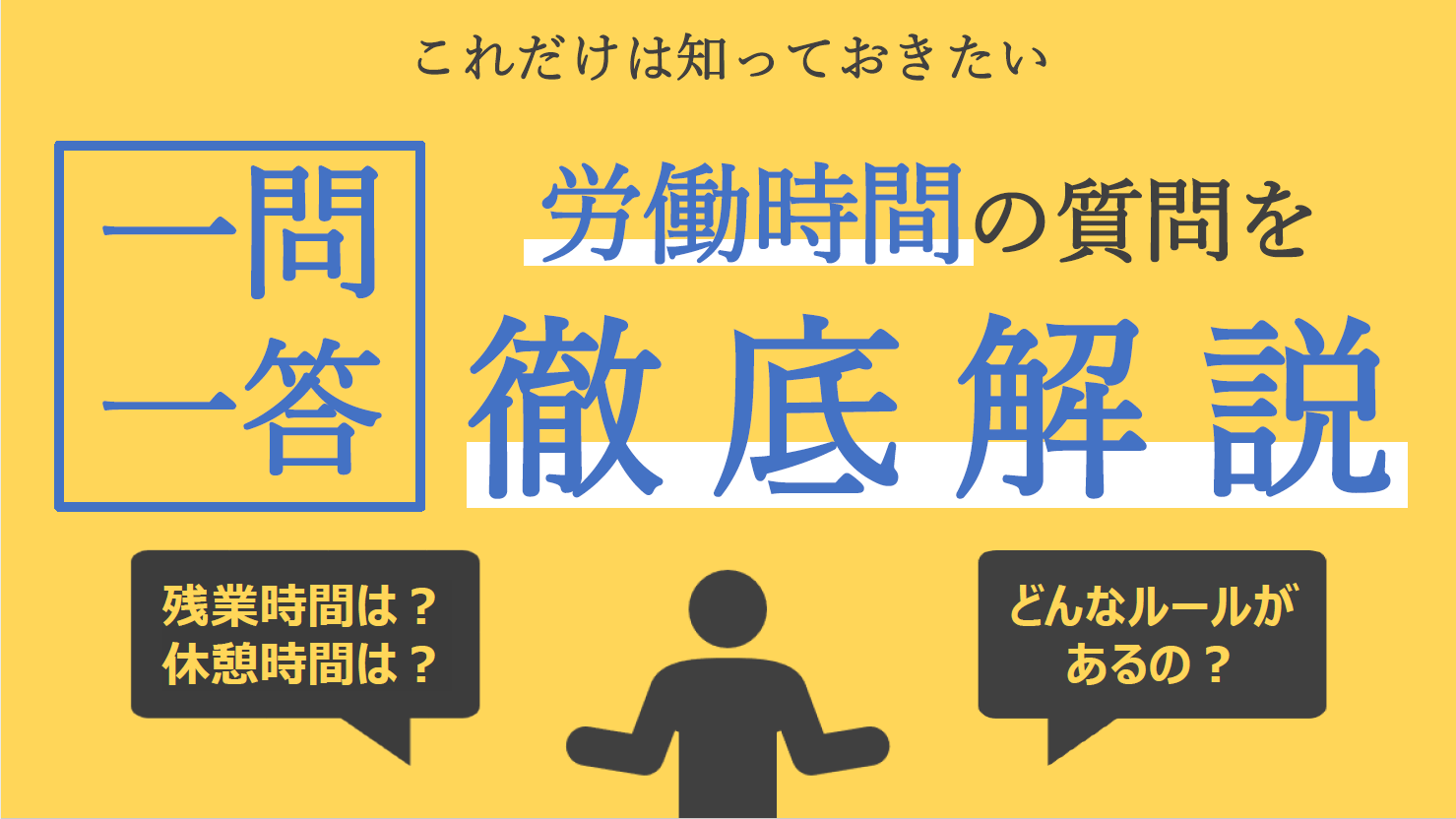労働時間の端数処理に関するトラブルの多さから、厚生労働省でもリーフレットを作成し、正しく端数処理をおこなうよう企業に呼びかけています。
たとえば、従業員に不利益となってしまう15分単位などの端数処理は、法律により禁じられています。労働基準法違反となり、罰則の対象となるため注意しましょう。
ただし時間外労働や月平均所定労働時間に関しては例外も存在するため、正しく把握することが重要です。本記事では労働時間や端数処理のルールや、例外について詳しく解説します。
労働時間でよくある質問を徹底解説
この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。
ジンジャーは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をご参考にください。
目次
1. 労働時間の把握とは

労働安全衛生法の改正により、労働時間の客観的把握や、長時間労働者に対して面接指導の対応が義務化されました。これまで労働時間の把握義務がなかった管理監督者も対象となります。
労働安全衛生規則に基づく労働時間の把握方法としては、タイムカードやパソコン、勤怠管理システムなどを用いた客観的な記録による打刻手段が該当します。適切な方法で労働時間を把握しないと、法律に違反してしまうだけではなく、正しい賃金を支給できなくなってしまうため注意しなければなりません。また、過重労働を防止し、従業員の心身の健康を維持するためにも労働時間管理を徹底しましょう。
2. 賃金支払いの5原則とは

労働基準法第24条には、賃金の支払いについて以下のような原則が記載されています。
- 通過で支払う
- 全額を支払う
- 従業員に直接支払う
- 毎月1回以上支払う
- 一定の期日を定めて支払う
上記は「賃金支払いの5原則」と呼ばれており、使用者はこのルールに従って労働時間に応じた賃金を支払う必要があります。「全額を支払う」というルールを守るためにも、使用者は端数を含めた労働時間を正確に把握しなければなりません。
2-1. 時間外労働に対しては割増賃金が発生する
同法第37条によると、「時間外労働や休日労働、深夜労働に対して割増賃金を支払わなければならない」と定められていることから、既定の割増率から正確な賃金を支払わなければいけません。いかなる場合においても、労働時間を正確に記録・管理し、1分単位で賃金を支払う義務が使用者にはあります。
3. 労働時間の端数は原則切り捨ててはいけない

労働時間の端数は正しく処理しなければなりません。ここでは、端数の正しい処理方法を紹介しますのでチェックしておきましょう。
3-1. 労働時間に端数が発生することはある?
労働時間管理における端数とは、1時間未満の数値のことです。1分、15分、30分などの端数が発生することはよくあるため、正しい処理方法を覚えておかなければなりません。
端数が発生しやすい場面としては、従業員が遅刻や早退をしたときが挙げられます。たとえば、始業時間に5分遅れた、終業時刻の40分前に早退した、といった場合は端数が発生するでしょう。
3-2. 労働時間の端数の切り捨ては原則NG
労働時間の端数処理については、会社独自のルールで勝手に処理して良いものではなく、法律によってルールが定められています。ルールに反した際は、労働基準法に違反したことになり、罰則が科せられる可能性がありますので、しっかり理解しておきましょう。
たとえば、労働時間が7時間15分の社員がいたとします。この社員の賃金計算をする際に、15分を切り捨て、7時間として労働時間を計算するのは労働基準法違反となります。
なぜなら前述の通り、労働基準法第24条で「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなくてはならない」(賃金全額払いの原則)とされているからです。厚生労働省でも、端数処理の大原則として「⼀律に賃⾦額、労働時間数に不⾜が⽣じる⽅法は不可」としています。[注1]
そのため、賃金計算をするうえでの労働時間は、1分単位で計算しなくてはなりません。
[注1]端数処理のソレダメ!|厚生労働省
3-3. 残業時間に関する端数処理
端数に関するルールは、時間外労働の計算であっても同じです。会社によっては15分単位などで時間を区切って、端数処理している所もあるでしょう。
しかし前述した通り、賃金全額払いの原則に反するため、時間外労働であっても端数処理することは認められていません。
ただし、端数を切り上げるのであれば、労働者が有利になるように計算することになるため違反にはなりません。たとえば、59分を切り上げて1時間として計算すると、労働者にとって賃金が増えることになるため、切り上げ処理は認められています。
3-4. 労働時間の端数処理について就業規則に記載しておく
労働時間の端数処理については、就業規則のなかに明記しておくことが重要です。労働者が有利になるように切り上げ処理をする場合であっても、会社全体で認識を共有できるよう、ルールを記載しておくとよいでしょう。
また前述の通り、端数処理は法律に従っておこなう必要があるため、就業規則に会社独自のルールを記載したからといって、すべてが認められるわけではありません。たとえば5分の遅刻を1時間の遅刻と見なすなど、法律に違反したルールは無効とされるため注意しましょう。
4. 端数処理で罰則を受けてしまうケース

例外を除いて、労働時間の端数の切り捨ては、原則することはできません。端数の切り捨てをした場合は、労働基準法に違反したことになり罰則が科せられます。
ここでは端数処理で罰則を受けてしまう具体的なケースを紹介するので、しっかりと確認しておきましょう。
4-1. 残業時間を15分単位で端数処理しているケース
残業時間を15分単位で区切り、残業代を計算している会社もなかにはあるでしょう。
たとえば、2時間14分の残業時間に対して、15分未満であることを理由に切り捨て、2時間で割増賃金を計算するのは、全額払いの原則に反することになります。
割増賃金の対象となる残業時間を端数処理して残業代の未払いが生じた際は、労働基準法第24条ならびに第37条の違反となるため、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。残業時間においても、基本的には1分単位で割増賃金計算をおこなわなくてはいけません。
4-2. 遅刻や早退の時間を端数処理しているケース
遅刻や早退など、実際に労務を提供しなかった時間がある場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則」によって、労務が提供されなかった時間については賃金を支払わなくても良いとされています。
ただし、この場合も労働時間の端数処理に注意が必要です。たとえば、所定労働時間が5時間の社員が50分遅刻した場合、実労働時間は4時間10分ですが、分単位を切り捨て4時間とすることはできません。労働基準法第24条の違反となり、30万円の罰金刑となる可能性があるため、注意しましょう。
基本的には遅刻や早退であっても、1分単位で労働時間を計算しなくてはいけません。
5. 労働時間の端数処理における例外

使用者が労働者の労働時間をまるめて端数処理をおこなうことは、労働者の不利益につながることから、原則認められていません。ただし、割増賃金計算や月平均所定労働時間などにおいては例外が存在します。
時間外労働や休日労働、深夜業にあたる労働時間の端数処理に関しては、以下3点が認められています。
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、丸2と同様に処理すること。
引用:Q10 残業手当の端数処理は、どのようにしたらよいですか。|鹿児島労働局
たとえば、1カ月の時間外労働の合計が19時間29分の場合は、30分未満であるため端数を切り捨て、19時間として労働時間を計算することができます。
同様に、1カ月の残業時間の合計が19時間31分であった場合は、30分以上であるため端数を切り上げて20時間としなくてはいけません。
5-1. 月平均所定労働時間の端数処理の方法
月平均所定労働時間とは、時間外手当の計算をする際に必要となり、下記計算式で求められます。
「月平均所定労働時間 =(1年の暦日数 - 年間休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12カ月」
月平均所定労働時間の端数処理に関しては、とくに法律で規定されていません。ただし労働者に不利益が及ばないよう、切り捨てすることが妥当とされています。
6. 労働時間の端数処理を正しくおこなわないリスク

労働時間の端数処理を正しくおこなわないことは、労働基準法違反による罰則を受ける以外にも、さまざまなリスクが潜んでいます。
ここでは、企業が受ける具体的なリスクについて解説します。
6-1. 未払い残業代の請求を受けることがある
賃金や割増賃金が正しく計算されずに支払われていると、不足分を未払いとして従業員から請求されるリスクがあります。場合によっては、民事訴訟に発展するケースもあるため注意が必要です。
令和2年3月に労働基準法の一部が改正されたことに伴い、賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長されました。ただし、経過措置として当面の間は3年となっています。未払い対象が複数人に及ぶ場合は、会社として大きな損失になりかねないでしょう。
6-2. 労働基準監督署から立ち入り調査が入る
会社が未払い賃金の支払いに応じないなどの理由で、従業員が労働基準監督署に相談をした場合、労働基準監督署から支払いの催促や立ち入り調査、事情聴取を求められることがあります。
また、場合によっては是正勧告書や指導票を交付され、期日までに是正報告書を提出しなくてはいけないケースも出てきます。労働基準監督署からの求めを拒否し続けた場合、書類送検されることもありますので注意しましょう。
6-3. 会社のイメージダウンとなる
未払い金のことが訴訟を通じてマスコミに知れ渡り、ブラック企業として報道されるようなことがあれば、会社のイメージダウンにつながってしまいます。顧客からの信頼を失うだけでなく、採用に影響を及ぼしたり、社員のモチベーション低下を引き起こしたりすることも想定されるでしょう。
7. 労働時間を切り捨てる端数処理は原則禁止!

今回は、労働時間管理における端数処理について解説しました。労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に基づき、労働時間を切り捨てる端数処理は、原則おこなってはいけないとされています。そのため、1分単位で正確に計算する必要があります。ただし、1カ月を通算で時間外労働を計算している場合は、この限りではありません。
端数を切り捨てて処理してしまった場合は、労働基準法の罰則が適用されるだけでなく、従業員からの未払い残業代の請求や労働基準監督署の立ち入り検査など、大きなトラブルに発展してしまう恐れもあります。
従業員はもとより、自社にとっての不利益とならないよう、労働時間は正しく計算しましょう。
労働時間でよくある質問を徹底解説
この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。
ジンジャーは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をご参考にください。