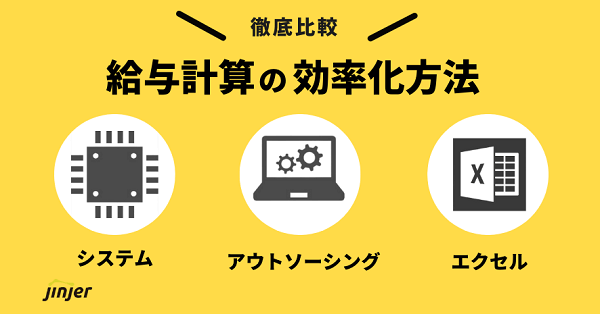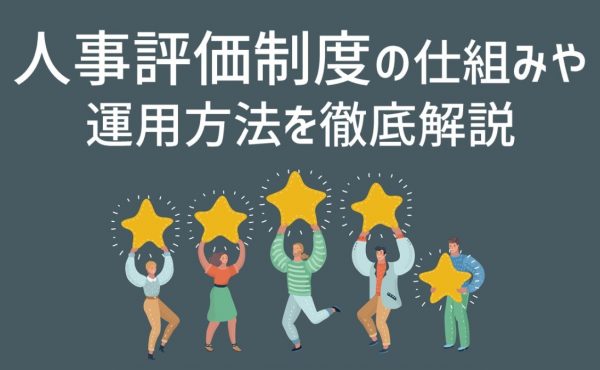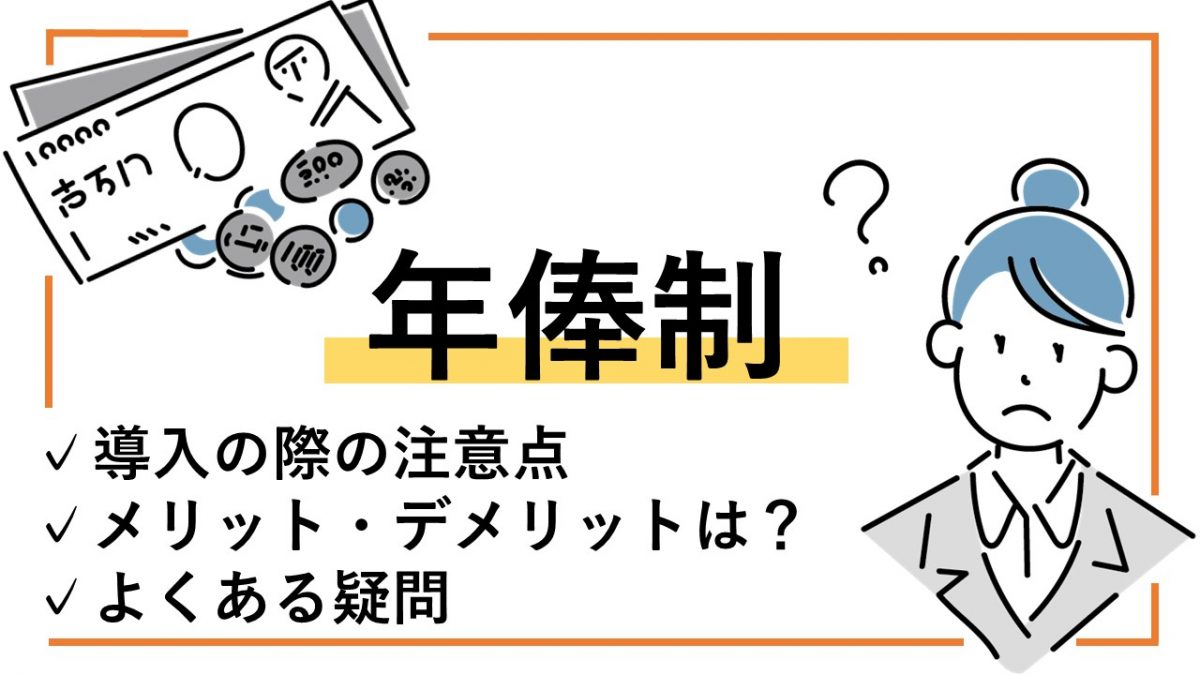
自社の給与体系を見直したいという方にとって、年俸制は一つの選択肢になり得ます。
しかし、平成26年に厚生労働省が実施した「就労条件総合調査」の結果によると、月給制を採用している企業は94%、年俸制を採用している企業は9.5%です。
外資系企業や一部ベンチャー企業では年俸制を採用しているケースが見られますが、なかなか日本に浸透しておらず、よく分からないと思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、年俸制導入を検討している企業の方、給与形態を見直したい方に向けて、年俸制の基本的な仕組みやメリット・デメリット、導入の際の注意点などをご紹介します。
給与計算の効率化方法を徹底比較!
給与計算は日々の勤怠管理でもれなく勤怠情報を収集した上で、一人一人計算していく必要があることに加え、ミスが許されない業務であるため、手間だと感じる方も多いでしょう。
「給与計算システムやアウトソーシングが便利なのはわかるけど、お金をかけてまで使う必要があるの?」という方に向け、当サイトでは給与計算システム・Excel・アウトソーシングのメリット・デメリットや、システムで給与計算がどのように効率化できるかをまとめた資料を無料で配布しております。
給与計算システム・Excel・アウトソーシングを比較検討したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1.年俸制の仕組み
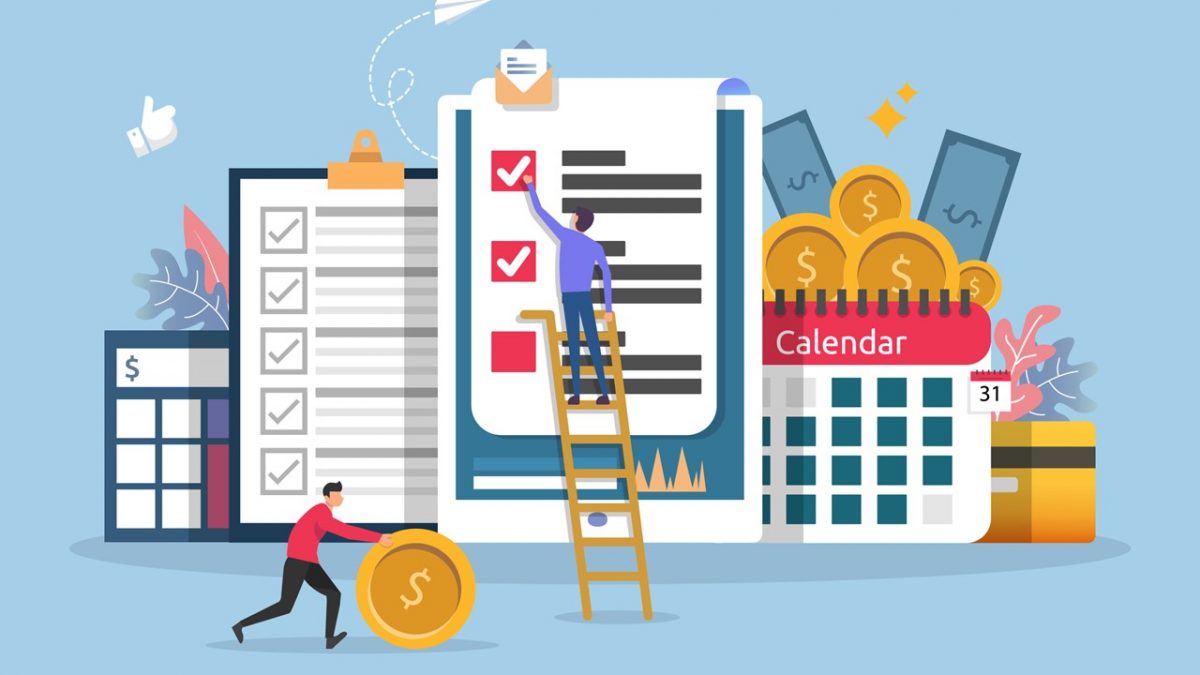
まずは、年俸制の基本についてご説明します。
1-1.年俸制とは何か
年俸制を一言で表すと、「1年単位で給与を算出する給与支払い制度」です。
労働基準法第24条では、毎月給料を支払う義務が定められているため、年間の金額を1か月ごとに分割して支払うことになります。
基本的に個人の能力に応じて翌年の給与を算出するため、年俸制は成果主義との相性が良いと言われています。
年俸額の決め方は企業によって異なり、
- あらかじめ賃金規定にルールや計算式が定められている場合
- 毎年経営者が年俸額を提示し、社員から了承を得ることで決定する場合
などがあります。
1-2.月給制と年俸制は何が違うのか
月給制と年俸制の違いは、給与額の決定が月単位なのか、年単位なのかです。それ以外に大きな違いはありません。
この違いは、1年の間に給与が変更できるか否かに影響しています。月給制は毎月給与を算出するため、業績が悪化したら給与を下げることができます。
しかし、年俸制の場合は年度の初めに年間の給与を定めているため、途中で変更ができません。
月給制は、勤続年数に応じて徐々に支給額が増えていくため、年功序列が基本のメンバーシップ型採用を導入している会社に向いています。大きく増減しない安定的な支給スタイルと月給制の相性が良いからです。
一方、ジョブ型採用の会社には、能力に応じて給与を大きく変更できる年俸制が適していると言えます。
2.年俸制のメリット・デメリット

ここでは、年俸制のメリット・デメリットを、会社側・従業員側に分けて4つずつご紹介します。
2-1.会社にとってのメリット・デメリット
メリット
- 年間の経営計画を立てやすい
年俸制の場合、年度の初めに人件費を決定させるため、長期的な経営計画が立てやすくなります。
- 社員のモチベーションアップにつながる
年俸制では、個人の成果や能力が翌年の給与に反映させやすいため、社員一人一人のモチベーション向上につながり、高いパフォーマンスを発揮させやすいと言えます。
デメリット
- 年度内に人件費を変更できない
万が一業績が悪化したり大きな損失があった場合、年俸制だと減額ができないため経営が苦しくなる可能性があります。
- 労働契約に手間がかかる場合がある
残業代や賞与の規定など、月給制以上に仕組みが複雑になり得るので、年俸制導入の際は従業員との契約作業に時間と手間がかかります。
2-2.従業員にとってのメリット・デメリット
メリット
- 評価が給与に反映されやすく、大幅な収入アップの可能性がある
自分が仕事を頑張れば、翌年の年収を上げることが可能です。年俸制の場合は、大きな成果を上げれば月給制の場合よりも大幅な収入アップが期待できます。
- 長期的なライフプランが立てやすい
年俸制だと年間で得る収入額が決定しているため、返済の計画など、あらゆる経済的なプランが立てやすくなります。
デメリット
- 成果を上げないと減額される可能性が高い
期待していたほどの成果を生み出せなかった場合、翌年の給与が減額される可能性があります。
- プレッシャーが大きい
成果がないと給与が減額されるかもしれないと思うことで、プレッシャーに感じ、不安や焦りにつながる場合があります。
年俸制は正当な評価制度があれば従業員の成果を反映させやすくモチベーションアップにつながります。
しかし、制度が整備されていないと、かえって従業員のモチベーションを低下させてしまう可能性があります。
年俸制を導入する際は、これらのメリットが機能するような制度を作ることが重要です。
3.年俸制に関するよくある疑問

ここからは、さらに詳しく年俸制を理解するために、よくある疑問に答えていきます。
3-1.賞与はどのように支払うのか
「年俸制はボーナスがない」と考える方は少なくないのではないでしょうか。しかし、支払いの制度によっては、賞与(ボーナス)の支払いも可能です。
一般的に、年俸制における給与の支払い方法は3つあります。
①12分割で賞与なし
年収を12で割って毎月支給するパターンでは、賞与はありません。
②14・16分割で賞与あり
年収を14で割る場合は、余った2か月分を年1回賞与として支給するのがスタンダードです。
16分割の場合は、余った4か月分を年2回に分けて支給することで賞与とみなすパターンが多いです。
③年俸額と別で賞与を支給
年収を12分割して支給するのとは別で、各個人の成果に応じてインセンティブを支給する方法もあります。この方式はとりわけ成果主義志向が強い会社に導入されていることが多いです。
3-2.欠勤控除はできるのか
年俸制の場合でも、従業員の欠勤や遅刻に応じた控除が可能です。
ただし、欠勤控除を有効にしたい場合は、事前に就業規則で具体的な決まりを明記しておく必要があります。
3-3.残業代はどう支払うのか
年俸制であっても、労働基準法第41条に規定する管理監督者などを除いて、労働基準法で定める労働時間を超えて労働させるときは時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
固定残業代を採用している場合は、決められた残業分の労働をおこなっても残業代を支払う必要はありませんが、それを超えた時間分に関しては、当然残業代が発生します。
3-4.退職・解雇の際はどうするのか
年度の途中で従業員が辞めてしまった場合は、働いていない期間の給与を支払う必要がありません。
賞与に関しては、在籍していた期間に応じて支払われることが基本です。
退職後のトラブルを防ぐためにも、退職や解雇時にはどのように賃金が算出されるのかをあらかじめ規定しておくことが大切です。
4.年俸制導入の際にすべきこと

ここまでで、年俸制導入の際にはトラブルを防ぐために、さまざまな取り決めをする必要があると分かりました。
それでは、実際に導入の際に何をすべきなのかご紹介します。
4-1.就業規則の改定
年俸制を新しく導入する場合、労働組合や個々の従業員と話し合いの上、就業規則を改正する必要があります。
残業代や賞与、欠勤控除や退職金についてなど、制度が曖昧にならないよう、すべて明記しましょう。
4-2.人事評価制度の見直し
年俸制の場合、年に1回しか給与改定のチャンスがありません。そのため、人事評価が正当におこなわれないと従業員の不満がたまり、パフォーマンス低下にもつながりかねません。
そのため、年俸制を導入する際には、どのように人事評価を実施するか明確化しておく必要があります。
人事評価に関しては、こちらの記事で種類や導入方法、運用についてなどを解説しています。ぜひご覧ください。
「【人事評価制度を徹底解説】評価基準の種類から導入方法、運用を成功させるポイントなどをご紹介」HR NOTE
https://hrnote.jp/contents/soshiki-jinjihyoka-20200323/
4-3.労働者との合意形成
先ほどご紹介した就業規則の改定・人事評価制度の見直しは、ただ人事担当者や経営者が決めれば良いのではなく、従業員との合意が必要になります。
どちらも制度を変える際にきちんと説明をし、不安を解消しておかなければ、後々トラブルになりかねません。丁寧な説明と合意形成を心がけましょう。
5.まとめ
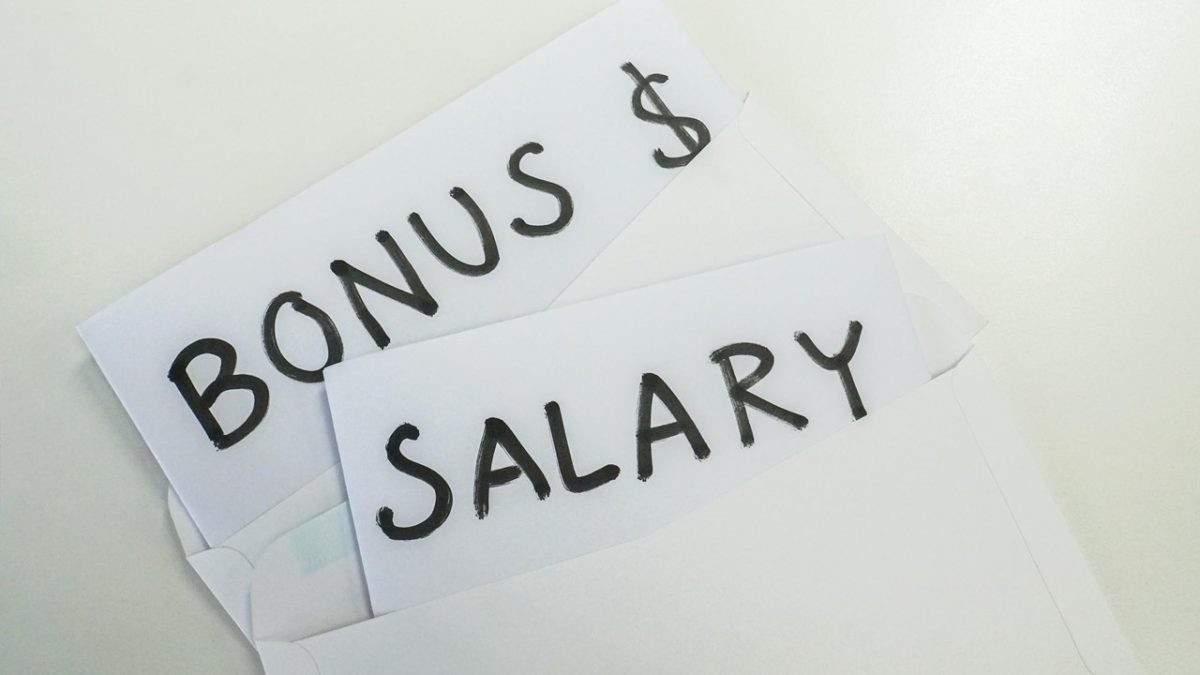
年俸制を導入した場合、適切に運用すれば、従業員にとっても企業にとっても大きなメリットが生まれます。
そのためには、十分な事前準備と入念な説明が不可欠です。
導入を迷っている方はぜひ本記事を参考に、自社にはどのような給与形態があっているのか考えてみてください。
給与計算の効率化方法を徹底比較!
給与計算は日々の勤怠管理でもれなく勤怠情報を収集した上で、一人一人計算していく必要があることに加え、ミスが許されない業務であるため、手間だと感じる方も多いでしょう。
「給与計算システムやアウトソーシングが便利なのはわかるけど、お金をかけてまで使う必要があるの?」という方に向け、当サイトでは給与計算システム・Excel・アウトソーシングのメリット・デメリットや、システムで給与計算がどのように効率化できるかをまとめた資料を無料で配布しております。
給与計算システム・Excel・アウトソーシングを比較検討したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。