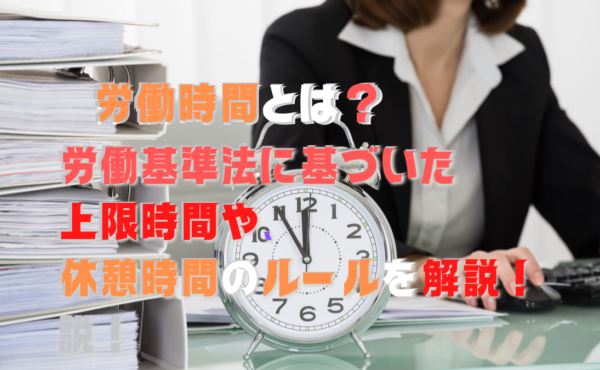
「労働時間」について理解するためには、法定労働時間や36協定、残業代計算など、幅広い内容を把握する必要があります。万が一、労働時間や残業代の計算を間違えてしまうと、従業員とのトラブルや法律違反につながるケースもあるため注意しましょう。
本記事では、労働時間の上限、計算方法、休憩時間などについて労働基準法に基づいて解説します。
目次
1. 労働時間の定義

ここでは、労働時間の定義と労働時間の種類について紹介します。
1-1. 労働時間とは?勤務時間・拘束時間との違い
「労働時間」とは、勤務時間から休憩時間を引いた時間のことです。
労働時間と混同されやすい「勤務時間」とは、従業員の始業時間~終業時間までを意味します。勤務時間のなかには、休憩時間は含まれますが、残業時間は含まれません。
また「拘束時間」とは、行動の自由が拘束されている時間を指します。一般的に休憩時間や残業時間も含まれるので注意しましょう。
労働時間は「労働者が使用者の指揮命令下にある時間」を指すため、休憩時間は含まれません。
労働時間に関する具体的な例は下記の通りです。
例)始業が9時30分、終業が17時30分で、間に1時間の休憩がある企業の場合
勤務時間:8時間(9時30分~17時30分)
労働時間:勤務時間(8時間)- 休憩時間(1時間)= 7時間
1-2. 所定労働時間と法定労働時間の違い
労働時間は「所定労働時間」と「法定労働時間」に分けられます。
所定労働時間とは、各企業の就業規則や雇用契約によって定められた労働時間のことです。一方で、法定労働時間とは労働基準法によって定められた労働時間の上限のことを指します。
ここまで労働時間の定義や「労働時間には所定労働時間と法定労働時間の2種類あること」について解説しました。36協定を締結していない状態で、法定労働時間を超えて従業員に労働させることは認められていないので、注意しましょう。
関連記事:「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いとは?定義や残業代計算について詳しく解説!
関連記事:月の労働時間上限とは?月平均所定労働時間や残代計算について解説!!
関連記事:1日の労働時間の基準や上限とは? 36協定や休憩時間のルールとあわせてご紹介!
1-3. 労働時間として認められる時間
労働時間の定義によれば、下記のような実際に業務に着手していない時間も労働時間に含まれます。
- 制服や作業着に着替える時間
- 強制参加の朝礼や終礼の時間
- 電話や来客対応のために待機している時間
- 始業前・終業後の準備や清掃時間
- 警備員や監視員の業務中における仮眠時間
- 会社に命じられて研修・セミナーを受ける時間
労働時間に含まれるかどうかは、従業員が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかによって判断することが大切です。
1-4. 労働時間として認められない時間
一方で、通勤するための時間や出張先への移動時間などは、一般的には労働時間に含まれません。使用者の指揮命令下に置かれているわけではないと判断できるからです。
ただし、移動中にも仕事を命じるなど、指揮命令下にあると見なされる場合は、労働時間と判断されることもあります。
2. 労働基準法における労働時間と休憩時間の関係性とは

ここでは、労働基準法に定められた休憩時間のルールについて解説します。
2-1. 休憩時間の原則
企業が従業員に休憩時間を付与する際は、下記の3つの原則を守る必要があります。
・分割付与の原則(休憩時間は分割してもよい)
・一斉付与の原則(休憩は一斉に取らせなければならない)
仮に「休憩はいらないので早く帰らせてほしい」という要望が従業員からあったとしても、途中付与の原則に違反するため応じてはいけません。また、付与する休憩時間は各従業員の労働時間によって変動します。ここからは「労働時間別に付与すべき休憩時間は何時間なのか」を解説します。
関連記事:休憩時間が取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介
関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き
2-2. 労働時間が6時間を超えて8時間未満の場合の休憩時間
労働時間が6時間を超えて8時間未満の場合は、従業員に少なくとも45分の休憩時間を付与する必要があります。「少なくとも45分」なので、従業員に1時間の休憩時間を付与していても問題ありません。
関連記事:6時間労働の休憩時間は何分?付与時のルールや労働時間管理の効率化について解説!
2-3. 労働時間が8時間を超える場合の休憩時間
従業員の1日の労働時間が8時間を超える場合、企業は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。労働基準法で定められているのは「8時間超えの場合」までなので、それ以降の労働時間に対して休憩時間を追加で付与する義務はありません。
つまり、1日10時間労働をおこなったとしても、1時間の休憩時間さえ与えれば、休憩時間の付与に関しては労働基準法違反にならないということです。また、「少なくとも1時間」であるため、昼休みに1時間、残業前に1時間のように、1日あたり1時間以上の休憩を与えても問題ありません。
2-4. 休憩時間を分割して付与することも可能
休憩時間は分割して付与することも可能です。1日の休憩時間が規定の時間に達していれば、45分・60分の休憩を分割しても問題ありません。
しかし、適切に休憩時間を付与しないと、労働基準法に違反するだけなく、従業員の生産性が下がる恐れもあります。休憩時間の重要性を再確認し、全従業員に適切に休憩時間が付与されていることを確認しましょう。
3. 労働時間の上限は法律によって定められている

労働基準法により、労働時間には上限が定められています。従業員に、上限を超える労働を強制することは認められていません。
ここでは、労働時間の年間・月間・1週間・1日あたりの上限と、法定労働時間を超える労働が必要な場合の対処法を解説します。
3-1. 1日・1週間あたりの労働時間の上限
労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間・週40時間に定めています。この規定を超える勤務、すなわち「残業」は原則として認められていません。
しかし、36協定の締結により、残業が法的に認められるようになります。
3-2. 36協定を締結したときの月間・年間の労働時間の上限
36協定とは「時間外・休日労働に関する協定」のことです。労使間で36協定を締結すると、「1日8時間・週40時間」を超えて従業員に労働させることができます。
しかし、36協定を締結したからといって、無制限に労働させられるわけではなく、法定労働時間を超えた時間外労働は「月45時間・年360時間まで」と定められています。また、時間外労働には割増賃金が発生するため、給与の計算には十分な注意が必要です。
もし、この「月45時間・年360時間」を超えて時間外労働をおこなう場合は、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
3-3. 特別条項付き36協定を締結したときの労働時間の上限
労使間で特別条項付き36協定を締結すると、「月100時間未満・年720時間」まで時間外労働をおこなうことができます。
2019年までは、「月100時間未満・年720時間」という上限が設けられていなかったため、特別条項付き36協定を締結すれば、実質、従業員を無制限に働かせることができました。しかし、長時間労働や過労死が社会的な問題となり、特別条項付き36協定を締結した場合でも、「月100時間未満・年720時間まで」という罰則付き上限規制が設けられました。
労働基準法では、特別条項付き36協定を定める場合には以下の項目を含めるように規定しています。
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・2~6カ月の時間外労働と休⽇労働の合計が平均月80時間以内
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6回まで
ここまで、労働時間の上限について解説しました。これらはあくまで「上限」であるため、少しでも時間外労働を減らせる労働環境づくりを心がけましょう。
関連記事:労働時間の上限とは?2024年建設業、運送業への法改正についても解説!
関連記事:労働時間を短縮するための取り組みとは?メリットデメリットや制度をご紹介!
3-4. 残業の上限規制適用に猶予がある業種
2019年4月から大企業に、2020年4月から中小企業に対して適用されている上限規制ですが、建設業や運送業など、一部の業種に関しては適用に猶予が設けられていました。これは業界全体の人手不足と勤務形態の複雑さに起因するものです。
ただし2024年4月以降は、建設業や運送業などでも残業時間の上限規制が適用されます。
いずれの業種でも、上限規制に違反すると罰則が科せられる可能性もあるため注意しましょう。この上限規制の発生は「2024年問題」とよばれ、各事業者は対応を迫られています。
関連記事:運送業労働時間の上限とは?超過するリスクや2024年問題についても詳しく紹介
関連記事:2024年から建設業の労働時間に上限規制が適用!今から準備できる対応とは?
4. 労働時間を超えて働く「時間外労働」とは?
時間外労働(残業)とは、所定労働時間を超えて働いた時間のことをいいます。たとえば、就業規則で労働時間が5時間と決められており7時間働いた場合は、2時間分が残業に相当します。
4-1. 法定外残業と法定内残業の違い
労働基準法の範囲内の残業を「法定内残業」、超える残業を「法定外残業」と呼びます。法定外残業とは、法定労働時間を超えた労働時間分のことです。
一方、法定内残業とは、所定労働時間を超えているが、法定労働時間以内の労働時間のことを指します。たとえば、1日7時間を所定労働時間としている場合、週の法定労働時間内(40時間以内)に収まることを前提に、1日7時間から8時間までの労働は法定内残業に該当します。
4-2. 残業代と割増賃金の違い
残業代と割増賃金は同じ意味合いで用いられることもありますが、異なる意味をもちます。
残業代とは、所定労働時間を超えて働く場合に支払われる賃金のことです。一方、割増賃金とは、時間外労働・休日労働・深夜労働の法定外労働をおこなった場合に、通常の賃金に上乗せして支払われる賃金のことです。
残業代は法定外残業だけでなく、法定内残業が発生した場合も生じます。一方、割増賃金は法定内残業の場合は発生しません。しかし、休日労働や深夜労働が発生した場合も支払う必要があります。また割増賃金は、通常の賃金に割増賃金率をかけて計算し、支払わなければなりません。
5. 労働時間の月平均はどれくらい?
 通常、他社の労働時間を知る機会はほとんどなく、自社の労働時間が多いのか少ないのかを判断するのは難しいでしょう。そこで参考にしたいのが、労働時間の平均です。
通常、他社の労働時間を知る機会はほとんどなく、自社の労働時間が多いのか少ないのかを判断するのは難しいでしょう。そこで参考にしたいのが、労働時間の平均です。
ここでは、厚生労働省の調査結果を参考に、労働時間の平均を解説します。
5-1. 最新の月間平均労働時間は160.0時間
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和6年2月の速報」によると、一般労働者の総実労働時間は160.0時間でした。総実労働時間とは、「所定内労働時間+所定外労働時間」のことです。
160.0時間の内訳は、所定内労働時間が146.3時間、所定外労働時間が13.7時間となっています。なお、出勤日数の平均は19.1日でした。これらの数値から、一般労働者の1日あたりの平均総実労働時間は約8.4時間となります。
5-2. 労働時間が月200時間は働かせすぎ?
では、月の労働時間が200時間に迫る場合、働かせすぎになるのでしょうか。
法定労働時間は「1日8時間・週40時間」と定められているため、1カ月を4週とすると月160時間の労働は法定内ということになります。36協定を締結していれば「月45時間・年間360時間」の時間外労働が可能であることから、月の労働時間が205時間程度であれば上限規制を超えないため、働かせすぎとはいえないでしょう。
ただし、月45時間の時間外労働は年6回までしか認められていないため、月200時間程度の労働が連続して発生したり、1年間に複数回発生したりする場合は注意が必要です。
また、この場合、従業員は毎日約2時間の残業をすることになります。そのため、従業員自身が働きすぎという認識を持っても不思議ではありません。
残業時間は働きやすさに直結します。月200時間労働は法的に問題ありませんが、従業員にとって心身の負担となることは間違いありません。そのため、企業は残業を極力減らすよう努める必要があります。
5-3. 年間労働時間も把握しよう
法定労働時間は「1日8時間・週40時間」と定められていますが、年間の法定労働時間は明確に示されていません。「1日8時間・週40時間」を守れば、労働基準法や36協定に違反することはありませんが、自社の労働環境について把握するうえで、年間の労働時間計算は非常に大切です。
年間労働時間は以下の通りです。
年間労働時間は、年間の法定労働時間と時間外労働時間を足したものになります。
【年間の法定労働時間の算出方法】
1年間を52週(365日÷7日≒52週)と仮定すると、法定労働時間は「週40時間」なので、
52週×40時間=2,080時間
1年間の法定労働時間は約2,080時間であることがわかります。
つまり、年間労働時間は以下の式で求めることができます。
年間労働時間=2,080時間+「年間の時間外労働の時間数」
ここまで、月間労働時間の平均や年間労働時間の算出方法について解説しました。ここからは労働時間の計算方法を解説します。給与額に関する重要な内容なので、きちんと確認して業務に活用しましょう。
関連記事:年間の労働時間の計算方法や上限とは?36協定や年間休日とあわせて解説!
6. 労働時間の計算方法
 給与計算には正しい労働時間の把握が必須ですが、計算方法を誤ってしまっては本末転倒です。これまでの内容を踏まえ、労働時間の正しい計算方法を習得しましょう。
給与計算には正しい労働時間の把握が必須ですが、計算方法を誤ってしまっては本末転倒です。これまでの内容を踏まえ、労働時間の正しい計算方法を習得しましょう。
6-1. 労働時間を計算する際の手順
|
計算手順 |
概要 |
|
|
1 |
日ごとの労働時間を求める |
「労働時間=勤務時間-休憩時間」で算出 |
|
2 |
日ごとの遅刻・早退時間を差し引く |
遅刻・早退時間をしている日がある場合は、その分の時間を差し引くか否かを決定し、必要に応じて労働時間から差し引く |
|
3 |
日ごとの法定内の残業時間を算出する |
法定内の残業時間とは、所定労働時間を超えて8時間以内におさまるもの |
|
4 |
日ごとの残業時間を算出する |
1日の法定労働時間である8時間を超えた時間のこと |
|
5 |
週ごとの法定内の残業時間を算出する |
週ごとの法定内残業時間とは、所定労働時間を超えて週40時間以内におさまるもの |
|
6 |
週ごとの残業時間を算出する |
1日間の法定労働時間である40時間を超えた時間のこと |
6-2. 法定労働時間を超過した場合の残業代の計算方法
法定労働時間を超過した場合、その時間に対して割増賃金が発生します。ここでは、割増賃金の種類や月平均所定労働時間の計算方法について整理しながら、残業代計算について解説します。
6-2-1. 割増賃金の種類
法定労働時間を超えた時間外労働のほか、深夜労働や休日労働に対しても割増賃金が発生します。ここでは、それぞれの種類や割増率について解説します。
▼時間外労働
時間外労働とは「法定労働時間を超えた労働」を指します。
割増率は25%です。
▼深夜労働
「午後10時から午前5時までの間の労働」を指します。
割増率は25%です。
▼休日労働
「法定休日における労働」を指します。
割増率は35%です。
また、事前に振替休日を取得してから法定休日(週1日もしくは月4日の休日のこと)に労働した場合、「休日労働」には該当しないため、賃金は発生しません。しかし、法定休日に労働させたあとに代休を取得した場合は、「休日労働」に該当するため、休日労働手当が発生します。間違いの起きやすいポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。
6-2-2. 月平均所定労働時間の計算方法
上記で解説した割増賃金の計算は、以下の計算式でおこないます。
上記の「1時間あたりの賃金」は以下の計算式でおこないます。
月給÷月平均所定労働時間
月平均所定労働時間とは、その名の通り、1カ月あたりの平均所定労働時間のことです。
月平均所定労働時間を算出する理由は、営業日数は月によって異なり、単月で計算してしまうと毎月1時間あたりの賃金が変動してしまうためです。
(※営業日が少ない月は1時間あたりの賃金が高くなり、営業日が多い月は1時間あたりの賃金が安くなる)
こういった事態を防ぐために、月平均所定労働時間を算出する必要があります。
月平均所定労働時間の算出方法は以下の通りです。
1時間あたりの賃金計算を例を交えて、下記で解説します。
例)年間休日が125日、一日の所定労働時間が8時間の従業員の場合
月平均所定労働時間=(365日-125日)×8時間÷12カ月=160時間
従業員の月給が20万円だとすると、
20万円(月給)÷160(月平均所定労働時間)=1,250円
となり、その従業員の1時間当たりの基礎賃金は1,250円であることがわかります。
関連記事:労働時間の適切な計算方法について|残業代計算についても詳しく解説!
7. 労働時間に関わる法律
ここでは、労働時間に関連する主な法律を紹介します。
7-1. 労働基準法
労働基準法とは、会社が最低限守らなければならない労働条件に関する法律です。労働契約、労働時間、賃金、休日、解雇など、労働条件に関するルールが定められています。
労働基準法は、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用される法律で、会社が違反した際には罰則の対象となります。
7-2. 労働契約法
労働契約法とは、会社と従業員との間で締結される労働契約に関するルールを定めた法律です。会社は労働契約法に基づき、従業員と適正な雇用契約を締結しなくてはなりません。
2012年に8月に改正され、主に、契約社員やパートなど有期契約労働者を対象とした「無期労働契約への転換」「雇止め法理の法定化」「不合理な労働条件の禁止」の3つのルールが新たに加わりました。
7-3. 働き方改革関連法
働き方改革関連法は、長時間労働の改善、柔軟な働き方や雇用形態によらない公正な扱いの実現を目的とし2019年4月に施行されました。
主に、労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法をはじめとして、パートタイム労働法・労働者派遣法などの8つの法律が改正されています。改正されたなかでも、「時間外労働の上限規制」「有給取得の義務化」「同一労働同一賃金ルール」については、確実に押さえておかなくてはなりません。
7-4. 労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、働き方改革関連法で改正された法律の一つで、労働者の安全や健康の確保、快適な職場環境をつくるべく制定された法律です。数多くの取り決めがありますが、とくに2019年4月より法改正がおこなわれた5項目には注意が必要です。
- 使用者は労働者の労働時間を客観的な方法により記録し、3年間保存する義務(現在は5年に改正)。
- 1週間あたり80時間以上働く長時間労働者に対して、医師による面接指導をおこなう制度。また1月あたり80時を超えた労働者に対して、速やかにその旨を通知する義務。
- 事業者と産業医・産業保健機能の連携の強化。
- 事業場が法令等を労働者に周知する内容や方法等の改正。
- 心身の状態に関する情報の取扱いの改正。
とくに長時間労働が発生しやすい企業に関しては、これらの項目の内容をしっかりと理解し、適切な対応をおこなう必要があります。
8. 働き方改革による労働時間への影響
働き方改革とは、少子高齢化に歯止めをかけ、誰もが活躍できる社会「一億総活躍社会」の実現を目的として策定されたものです。
労働者が各々の事情にあわせた多様で柔軟な働き方を実現し、長時間労働の是正や、雇用形態に関わらず公正な待遇の確保などに向けた措置を講じています。
働き方改革によって、勤怠管理において対応すべきことが新たに設けられたため、ひとつずつ確認していきましょう。
8-1. 労働時間の把握が義務化
健康管理をおこなう観点から、企業には従業員の労働時間を客観的に記録することが義務づけられています。
客観的な記録としては、タイムカード、ICカード、IDカード、パソコン入力といった記録が認められています。そのほか、使用者が始業・終業時刻を直接確認・記録しても問題ありません。
8-2. 管理監督者も注意が必要
管理監督者に関しては、労働時間の把握の義務はありませんでした。ただし法律改定後からは、管理監督や裁量労働制が適用される従業員に対しても、労働時間を適切な方法で把握する義務があります。
8-3. 労働時間の短縮促進の動き
長時間労働による健康被害や過労死の防止、働き方の多様化などさまざまな観点から、労働時間短縮に向けた動きは高まっています。
所定労働時間を短くし、勤務時間を減らす動きとして「ノー残業デーの設置」「有給休暇取得の促進」「勤務間インターバル制の導入」をおこなう企業も増加しています。
9. 労働時間に関して労働基準法違反になるケース
労働基準法に基づき、適切に労働時間を管理することが重要です。ここでは、労働基準法の違反でよくあるケースについて、罰則と合わせて詳しく紹介します。
9-1. 36協定を結んでいない残業
労使間で36協定を結ばず、従業員に法定時間外の残業をさせてしまった場合、6カ月以下の懲役または30万円の罰金が科せられます。
また、労使間で36協定を結んでいたとしても、あらかじめ決めた残業時間を超えて残業させた場合も、同様に処罰の対象とされます。
9-2. 休憩時間を与えない
使用者は、労働時間が6時間を超える時は45分、8時間を超える時は1時間の休憩を与えなくてはいけません。
休憩を与えなかった場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。なお、休憩時に電話番などさせた場合、休憩とは見なされませんので注意が必要です。
9-3. 休日・有給休暇を与えない
使用者は、従業員に必ず週1回以上の法定休日を与えなくてはなりません。これに違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられます。また、従業員へ特別な事情がなく有給休暇を認めなかった場合も、同じように処罰されます。
9-4. 就業規則の未作成・未掲示
従業員が10名以上の事業所では、必ず就業規則を作成して労働基準監督署へ届出しなくてはなりません。また、就業規則は従業員に周知させる義務もあります。
そのうえで、従業員を雇用する際は、雇用条件を明示しなければなりません。違反した場合には、30万円以下の罰金刑が科せられます。
10. 労働時間を調節する方法
企業の業種や従業員の状況に応じて勤務形態を変更することで、従業員の労働時間を調節し、人件費を削減することもできます。以下、代表的な調整方法を紹介しますのでチェックしておきましょう。
10-1. フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、3カ月以内の清算期間(多くは1カ月単位)で総労働時間を定めて、始業時刻・終業時刻を従業員自らに委ねる方法です。
ただし、フレックスタイム制であっても法定休日や法定労働時間の規則は適用されるため、法定の労働時間の総枠を超える分に対して割増賃金を支払ったり、週に1度の休日を設けたりする必要があります。
10-2. みなし労働時間制・裁量労働制
事業場外みなし労働時間制とは、事業場の外での業務など勤務状況の把握が難しい業務において、一定の時間分、勤務しているとみなして就業時間を規定し、賃金を支払う方法です。
裁量労働制は、始業時間や終業時間を従業員の裁量に委ね、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなし、賃金を支払う制度です。裁量労働制は、労働時間を規定することが難しいエンジニアや企画職など、一部業務に携わる従業員に対し適用されます。
また、裁量労働制には「専門型裁量労働制」と「企画型裁量労働制」の2種類があります。みなし労働時間制と似ている制度ですが、裁量労働制は一部の決められた業務にしか適用できない労働形態です。適用可能な職種は厚生労働省が定めているため、裁量労働制を検討する前に、適用可能な業務か確認しましょう。
10-3. 変形労働時間制
変形労働時間制とは、月や年の労働時間の平均が週40時間以内におさまる範囲内で、労働時間を月、週、日などで調整することができる制度です。繁忙期などにより勤務時間が増加しても時間外労働として扱う必要がなくなるため、閑散期と繁忙期が顕著な業種に適した労働形態といえます。
ただし、変形労働時間制でも、時間外労働の割増賃金を支払う必要があるため注意が必要です。
11. 労働時間に関する「よくある疑問」

ここでは、労働時間に関する「よくある疑問」について解説します。
11-1. 連続勤務は何日まで可能?
連続勤務は、最大で12日まで可能です。
企業が従業員に連続で勤務をおこなわせる場合は、下記の2つの原則を守る必要があります。
・変形労働時間制であれば月に計4日休日を設ける
そのため、週に1回の休日規定を設けている企業の場合であれば、1週目の最初と2週目の最後に休日を設けることで、最大12連勤が可能になります。
関連記事:連勤は何日までなら大丈夫?パートやアルバイトの場合や連勤の対策について解説!
11-2. 残業で労働時間8時間を超えた場合、別途休憩時間を付与すべき?
残業時間は労働時間に含まれるため、残業時間が加わることによって休憩時間が変動することもあります。
残業によって労働時間が8時間を超えたとしても、すでに従業員に1時間の休憩時間を与えていた場合は別途休憩時間を付与する必要はありません。
しかし、労働時間が6時間以上8時間未満の従業員の場合は、45分しか休憩時間を与えていないケースが多いため、別途15分の休憩時間を与える必要があります。
具体例は以下の通りです。
例)勤務時間が9時半~17時半で、1時間の残業をおこなった場合
元々、勤務時間が9時半〜17時半なので、所定労働時間は7時間15分となり、休憩は45分必要になります。
1時間の残業がおこなわれた場合、合計の所定労働時間が8時間15分となり、休憩時間は少なくとも1時間付与しなければなりません。すでに45分付与しているので、別途で15分の休憩を付与する必要があります。
関連記事:労基法違反?休憩時間について人事が知っておくべきこと
11-3. アルバイトの労働時間にも上限はある?
アルバイトやパート、契約社員などの労働形態にも、労働時間の上限は適用されます。時間外労働、深夜労働、休日労働に関しても、割増手当を与える必要があります。
ただし、派遣社員に限り、時間外労働をさせる際には派遣元と労働者の間で36協定を結ぶ必要があるため注意しましょう。
11-4. 遅刻・早退・中抜けなどはどのように対処する?
遅刻や早退などで所定労働時間から実労働時間が欠けた場合、賃金を控除しても問題ありません。控除をおこなうには、就業規則で控除のルールや計算方法を規定し、従業員に事前に周知することが必要です。
遅刻、早退、中抜けなどの場合は、1時間あたりの基礎賃金に所定労働時間から不足した分の時間数を掛け合わせて控除します。欠勤した場合は、月給を月平均所定労働日数で割って算出した1日あたりの賃金を欠勤日数分掛け合わせて控除する方法が一般的です。
関連記事:直行直帰の意味とは?労働時間の管理方法やメリット・デメリットについて解説!
関連記事:中抜けの意味とは?勤怠管理上の扱い方や注意点について解説!
11-5. 管理職には割増賃金を支払う必要はない?
社内で管理職とされる従業員が、労働基準法で定義される管理監督者に該当する場合は、時間外労働や休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
管理監督者とは下記の条件に該当する従業員のことを指します。
- 重要な職務内容を有している
- 重要な責任・権限を有している
- 勤務態様が労働時間等の規制になじまないようなものである
- 賃金等が地位にふさわしい待遇である
上記の条件が該当する管理監督者は、企業の経営に関わる業務を時間を問わずおこなう必要があるとして労働時間や休日の規定の適用が除外となります。
ただし、深夜労働に対する規定は適用されるため、深夜労働の割増賃金は支払わなければなりません。
関連記事:管理監督者の労働時間について適用や除外を合わせて詳しく解説
11-6. 移動時間や着替えは労働時間に含まれる?
一般的に、通勤時間や出張先への移動時間は労働時間に含まれません。ただし、例外もあり、移動時間を使用者の指揮命令下にあるとする企業の場合は、労働時間に含めることもあります。
着替えの時間を労働時間に含むか否かは、状況によって異なります。以下のようなケースに該当する場合は、着替えの時間を労働時間に含めなくてはなりません。
- 就業規則やマニュアルに記載がある
- 安全面・衛生面から着替えを必要としている
- 使用者が着替えを命じている(黙示の場合も)
- 使用者が更衣室を設けている
一方、労働時間に含まれないのは、着替えが従業員の理由によるものや、通勤時に制服の着用を認めているケースなどです。
なお、始業前の準備や終業後の片付け、会社命令による研修会への参加なども労働時間とみなされます。みなし労働時間は、使用者側と従業員側で認識が異なる可能性が高いため、しっかりと周知することが大切です。
11-7. 労働時間の1分単位計算はいつから?正しい端数処理の方法とは?
労働基準法の改定により、すでに、1分単位での労働時間の計算は運用が開始されています。就業規則で30分単位と規定していても、労働基準法が優先されるため、1分単位での計算が必要です。
なお、1分を超える単位で労働時間を計算した場合は違法となります。
また、労働時間の端数処理にも注意しなくてはなりません。労働時間における端数とは、「分」で示される部分のことで、四捨五入・切り上げ・切り捨てなどの方法で処理するのが一般的です。しかし、労働時間の計算は、原則1分単位となります。
ただし、時間外労働時間は端数処理が可能です。端数処理を切り捨てでおこなう場合、常に切り捨てのみで対応することはできません。
たとえば、1カ月の残業時間が30分に満たない場合に切り捨てをおこなうのであれば、30分以上の場合は1時間に切り上げることになります。
なお、企業が勝手に残業時間の切り捨てをおこなことは労働基準法に違反します。労働時間の端数処理の扱いは、労働局や労働基準法のガイドラインを参考にして決めましょう。
12. 労働時間に関する計算を効率化するツール

ここまで解説したとおり、労働時間に関する計算はどれも非常に複雑です。
ここでは、労働時間の計算を効率化するツールを3つ紹介しますので、うまく活用しましょう。
12-1. エクセル
表計算ツール「エクセル」を用いて労働時間管理をおこなう方法です。
実際に、労働時間計算に特化したテンプレートなども簡単に手に入れることができるので、多くの企業で利用されています。エクセルは労働時間計算だけでなく、給与計算にも使用することができるので非常に便利です。
ただ、エクセルに情報を入力するのは基本的に手作業で入力をおこなうため、入力ミスなどのリスクもあります。
12-2. Web上の計算ツール
Web上で公開されている無料計算ツールを用いて、労働時間計算をおこなう方法です。
基本的に無料で利用できるため、手軽に労働時間計算や給与計算を効率化したいときに向いています。
ただ、エクセルのように記録を残すことができないため、労働時間や給与に関する情報を別の媒体に記録する必要があります。また、エクセル同様に手作業で入力をおこなうため、入力ミスにも注意しましょう。
12-3. 勤怠管理システム
勤怠管理システムを導入して、労働時間計算をおこなう方法です。
勤怠管理システムを活用すれば、打刻・労働時間計算・記録を連動しておこなうことができるため、手作業による入力ミスの恐れが少ない点が魅力です。また、時間外労働ごとの割増率を設定しておけば、自動で残業代の計算をおこなえるため、人事担当者の負荷を大幅に減らすことができます。
さらに、スマートフォンやICカードなど、さまざまな方法で打刻できるため、リモートワークなどの柔軟な働き方に対応できる点も大きな魅力といえるでしょう。
関連記事:労働時間の管理は必須!上限時間や厚生労働省のガイドライン、効率化の方法を解説!
13. 労働時間を適切に管理し、従業員が働きやすい職場づくりを!

本記事では、労働時間の上限、計算方法、労働時間に関する疑問について解説しました。
労働時間を適切に把握するためには、さまざまな規定を守らなければならず、担当者にとって非常に大きな負担となります。
今回の記事の内容を踏まえて、労働時間を適切に管理し、従業員が働きやすい職場づくりを目指しましょう。
また、勤怠管理システムを導入するなど、労働時間を管理しやすい方法を検討することも大切です。








