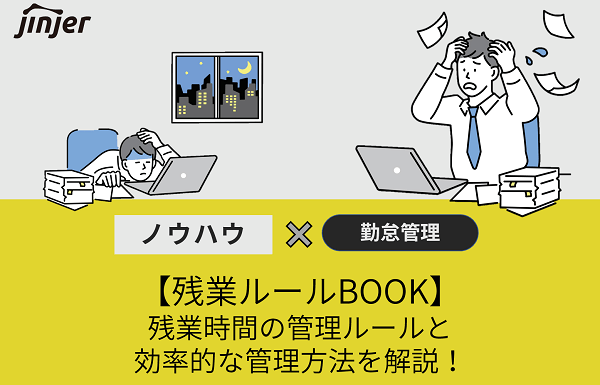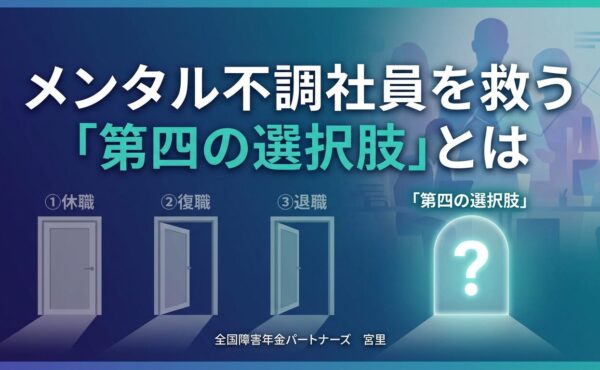残業にはいくつかの種類があり、割増賃金などの扱いもそれぞれ異なるため、基本的なルールや賃金の計算方法などを理解しておくことが重要です。残業についてしっかり理解していなければ、最悪違法になる可能性があるため注意しましょう。
今回は、残業に関するさまざまな制度や事例について紹介します。この記事を読むことで、残業に対する正しい知識をつけることができ、健全な企業経営を実現できるでしょう。
この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。
そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。
法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。
働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひ「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 残業とは

残業とは、就業規則で定められた労働時間を超過して働くことです。定時を超えて働くことや、週所定労働時間を超えて働くことも残業に含まれます。
また、残業は「法定内残業」と「法定外残業」の2つに大きく分けられます。それぞれの特徴は以下の通りです。
1-1. 法定内残業
法定内残業とは、労働基準法で定められている1日8時間・週40時間という法定労働時間内でおこなう残業のことです。法定労働時間については、労働基準法の第32条に記載されています。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
会社で定めている1日の所定労働時間が8時間未満、1週間で40時間未満である場合、所定労働時間を超えているものの、法定労働時間を超えていないときは、法定内残業に該当します。
1-2. 法定外残業
法定外残業とは、労働基準法で定められている1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて働くことです。法定内残業には割増賃金を支給する必要はありませんが、法定外残業には割増賃金の支払が法律で義務付けられています。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
このように残業には2つの種類があります。残業が法定内か法定外かによって割増賃金の支給義務が異なるため、従業員ごとの勤怠状況を正確に把握しておくことが重要です。
関連記事:法定内残業について割増賃金が必要ない場合や36協定などやさしく解説
2. 残業時間には上限規制がある

残業時間の上限は、法律によって決められています。また、残業を命じるためには、事前に36(サブロク)協定を締結しなければなりません。
ここでは、残業の上限規制について知っておくべきことを3つ紹介します。
2-1. 残業を命じるためには36協定の締結が必要
法定労働時間を超えた残業や法定休日における労働を命じるためには、事前に労使間で協定を締結しておくことが必要です。この協定は、以下のように労働基準法第36条に記載されていることから、36協定と呼ばれています。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
36協定を締結した際は、労働基準監督署長に届け出ることも忘れないようにしましょう。
2-2. 残業の上限は原則1カ月45時間・年360時間
36協定を結んだ場合でも、無制限に残業を命じられるわけではありません。残業を命じる場合の上限は「1カ月45時間・年間360時間以内」と定められています。
また、36協定で時間外労働の上限をこの時間よりも少なくしている場合は、その時間が上限となります。36協定を結んでいても、時間外労働には上限があるため注意しましょう。
2-3. 特別条項付き36協定を結んでも上限がある
臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項を設けることで「1カ月45時間・年間360時間」という上限を超えることができます。
特別条項とは、通常の36協定の上限内では時間外労働が収まらない臨時の事由がある場合、1カ月100時間未満、年間720時間以内まで残業させることが可能になる制度のことです。
ただし、45時間を超えて残業させることが許されているのは6カ月までとなっているほか、2~6カ月の残業時間の平均が80時間に収まるように調整しなければなりません。
2-4. 残業時間の上限規制に違反したときの罰則
残業時間の上限規制に違反した場合、6カ月以下の懲役や30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。たとえば、36協定を締結せずに残業を命じることや、特別条項を付けずに1カ月45時間・年間360時間という上限を超えることなどは違法です。
法律違反として罰則を受けないよう、上限規制についてしっかりと理解しておきましょう。
3. 残業代を計算する方法

残業代は、法定内残業か法定外残業かで計算方法が異なるため、しっかりと理解しておくことが大切です。ここでは、残業代の計算方法についてわかりやすく解説します。
関連記事:残業における深夜割増とは?割増率や計算方法を徹底解説
3-1. 残業代の基本的な計算方法
「法定内残業」か「法定外残業」かによって、残業代の計算方法は異なります。法定内残業の場合は、所定労働時間は超えているものの、法定労働時間を超えていないため、割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金で問題ありません。
法定外残業に関しては、法定労働時間を超えて労働をおこなっているため、通常の賃金に25%の割増率を加えて支払う必要があります。
たとえば、9~17時(休憩1時間)を所定労働時間としている企業で、従業員が9~22時まで働いた場合を考えてみましょう。
17〜18時の1時間分は法定内残業となり、割増賃金を支払う必要はありません。一方、18~22時の4時間に関しては法定労働時間である8時間を超えているため、法定外残業となり、25%増の賃金を支払う義務があります。
関連記事:法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説
3-2. 残業代の計算例
残業代は、「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間」で計算することができます。また、1時間当たりの賃金は、「1カ月の給与 ÷ 1カ月の労働時間」で求められます。
「1カ月の給与」については、交通費や家賃補助などの福利厚生は含まないようにしましょう。
加えて、1カ月の労働時間に関しては、単純に働いた各月の労働時間ではなく、月所定労働時間といわれるものを使用しなければなりません。
月所定労働時間は以下の計算式で求められます。
月平均所定労働時間 =(365 – 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12カ月
たとえば、月給30万円、年間休日が110日、諸手当なし、1日の所定労働時間数が9時〜18時(休憩1時間)の8時間の労働者が、1時間残業をおこなって9時〜19時で勤務した場合の残業代を計算してみましょう。
まず、月平均所労働時間は以下の通りです。
月平均所定労働時間 =(365 – 110)× 8 ÷ 12カ月 = 170
よって、1時間当たりの賃金は以下のように算出できます。
1時間当たりの賃金 = 300,000 ÷ 170 ≒ 1,764
最後に以下の計算式で、1時間あたりの割増賃金を算出しましょう。
1時間あたりの割増賃金 = 1,764×1.25 = 2,205
関連記事:残業代の正しい計算方法とは?給与形態・勤務体系別にわかりやすく解説!
関連記事:残業の割増賃金とは?割増率の一覧を用いて割増計算方法も詳しく解説
4. 残業代を計算する際の注意点

ここでは、残業代を計算する際の注意点を6つ解説します。
4-1. 有給休暇と残業を相殺することはできない
残業とは本来、従業員の労働時間が法定労働時間を超えた場合に、超過時間に応じて割増賃金を支払う必要があるため、有給休暇と同じ時間数であったとしても1時間の時給が異なります。そのため、残業代の代わりとして有給休暇を付与して相殺することはできません。
関連記事:残業の相殺は違法?代休やボーナスとの相殺は可能か解説
関連記事:有給の取得と影響してくる残業時間の計算について徹底解説
4-2. 固定残業代やみなし残業代でも、法定労働時間を超過した分は追加支払いが必要
原則として、固定残業代やみなし残業代を含んだ給与を渡している場合でも、指定した時間を超過した分は追加で給与を支払う必要があります。
追加で残業代を払う際の条件と割増率について紹介しておきます。
|
支払う条件 |
割増率 |
|
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)超えたとき |
25% |
|
時間外労働が60時間超えたとき |
50% |
固定残業代やみなし残業代を導入している企業でも、超過した分の給与を払わなければ違法になる可能性が高いため、支払うようにしましょう。
関連記事:固定残業代とは?手当型と組込型の違いや就業規則・労働条件通知書への記載についてわかりやすく解説
関連記事:「みなし残業」での違法をしないために|知らなければならない正しい運用方法
4-3. 深夜残業や休日労働の割増率に注意する
残業代を計算するときは、深夜残業や休日労働に対する割増率にも注意しなければなりません。深夜時間(22時〜5時)に労働させた場合の割増率は25%以上、法定休日に労働させた場合の割増率は35%以上です。
また、深夜時間に法定外残業を命じる場合は、それぞれの割増率が加算されて50%となります。条件が重なることで割増率が加算されるケースもあるため、計算時に注意しましょう。
4-4. 残業時間が60時間を超えた場合の割増率は50%
2023年3月31日までは、月60時間以上の残業に対する割増率は、大企業で50%、中小企業で25%とされていました。しかし、2023年4月1日以降は、大企業・中小企業ともに50%の割増率になります。
60時間を超える残業をさせることは従業員にとって負担が大きいため、このような措置が取られています。企業にとっても残業代の負担が大きくなるため、できる限り残業を減らすように努力しましょう。
参照:しっかりマスター 労働基準法|厚生労働省
関連記事:残業の割増率について中小企業が気をつけたいことを詳しく紹介
4-5. 残業時間は1分単位で管理する
残業時間を含む労働時間は、1分単位で正確に管理しなければなりません。労働基準法第24条によって、働いた分の賃金を全額支払うことが義務付けられているからです。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
残業時間を15分や30分単位で管理すると、同法に違反することになってしまいます。数分の残業だからといって切り捨てることはせず、1分単位で記録しましょう。
4-6. 着替えの時間が残業となるケースもある
状況によっては、着替えの時間も残業時間と見なされることがあります。そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことです。
よって、会社指定の制服に着替える必要がある場合などは、労働時間としてカウントしなければなりません。逆に、従業員の都合で着替える場合は、労働時間には該当しません。
5. 残業が発生する原因

ここまで残業時間の考え方や残業代の計算方法について解説してきましたが、そもそも残業は発生しないに越したことはありません。残業時間の削減で悩んでいる場合は、以下で紹介する残業の要因をチェックしておきましょう。
5-1. 人材不足による業務量の増加
社員数と業務量が釣り合っていないことで、残業が発生してしまうケースは多いです。労働人口の減少により、人手不足に苦しんでいる企業も多いでしょう。
求人を出しても、思うように応募者が集まらないこともよくあります。その結果、1人あたりの業務量が増加し、残業が発生しやすくなります。
5-2. 非効率な方法で仕事を進めている
非効率な方法で仕事を進めていると、当然、残業時間が長くなってしまいます。たとえば、目的が不明確な会議が多い、上司の押印をもらうために紙の申請書を回覧している、タイムカードの労働時間を手作業で集計している、といった場合は、仕事が定時で終わらなくなるケースも多いでしょう。
5-3. 残業代をもらって給与を上げたい
社員のなかには、残業代をもらって給与を上げたいという人もいます。日本では物価が年々上昇しつつも、給与はそれほど上がっていないため、生活の不安から残業している人がいるのも事実です。
簡単な仕事をあえてゆっくりと進め、残業代を多くもらおうとする従業員もいるかもしれません。
5-4. 長く働くことが美徳とされている
残業をして長く働くことが美徳とされていたり、残業によって上司の評価が上がったりするケースもあります。
実際に数十年前までは、企業側が残業している人は「頑張っている」「会社に尽くしている」などという評価をしていたこともあり、現在もそのような習慣が残っている企業もあります。
以上、残業が発生する要因を解説しました。このような要因を理解したうえで、自社に合った方法で残業を削減することが重要です。次章で残業を削減する方法を解説します。
6. 残業を削減する方法

残業が発生してしまう要因をふまえて、残業を削減するにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、残業を削減する方法について紹介します。
6-1. ノー残業デーを導入する
ノー残業デーを導入することで、その日だけは社員は残業をすることができなくなります。このようなルールを設けることで社員が業務時間内に仕事を終わらせようとし、業務効率が向上するようにさまざまな工夫をすることが期待できます。
また、ノー残業デーの日は、他の従業員に気を使うことなく退社できるため、従業員にとって早く帰る後ろめたさもありません。
しかし、業務内容は社員によって異なるため、固定の日でノー残業デーを作るのではなく、週に1回使用できるなどのほうが企業・社員のお互いにとって良い制度になるでしょう。
関連記事:ノー残業デーの効果とは?メリット・デメリットや成功のコツをわかりやすく解説!
6-2. 残業を事前申請制にする
残業の事前申請制を導入することで、社員は上司の許可がなければ残業ができなくなります。
これによって、上司は部下の残業を抑制できることに加えて、業務の進捗具合を把握することが可能になり、仕事量が適切でない場合は調整することもできます。
関連記事:残業申請制の運用ルールとは?申請書の項目やルール設定の流れを解説
6-3. 評価基準を改める
評価基準を改めることも残業を減らすための対策です。
たとえば、これまでは残業による長時間労働が評価基準であった企業が、これからは働いた時間ではなく、「どのような成果を出したかにする」ということです。
長く働くことが習慣化している企業や、美徳として考えられているような企業の場合、このような評価基準を改めることで、残業を削減することが可能になるでしょう。
6-4. 上司が定時に帰る
上司が定時に帰ることで、部下全員が残業規制に対して意識するようになります。
また、上司よりも早く帰りにくいといった社員がほとんどであるため、上司から積極的に帰るようにしましょう。
関連記事:残業が減らない理由とその対策|残業削減をする環境は自分で作る
6-5. 残業禁止のルールを設ける
残業禁止にするルールを設けることもひとつの方法です。残業をすることで、給料が稼げる仕組みの企業では、不必要に残業をしようとする従業員もいるかもしれません。そのような場合、残業禁止にすることで、生産性高く働かざるを得なくなります。
また、近年リモートワークが普及しましたが、リモートワークは労働の実態が把握しづらいなどということもあり、残業を申請制にしていたり、リモートワークでは残業を禁止にしたりしている企業などもあります。
残業禁止にするメリットには、不必要な残業代を支給しなくて良くなることや生産性の向上を意識して業務に取り組むようになることなどがあります。
ただし、このようなルールを設ける際には、業務量が適切であることが大前提となります。時間内にこなせない業務を与えて、残業も不可にするのは現実的でないうえに、従業員の精神面にも負荷になります。また、業務を持ち帰って残業したりすることは本末転倒です。
業務量を調整したり、人員の確保をしたりして、残業を減らせるよう企業側も取り組んでいきましょう。
7. 残業規制への対策法

残業削減に加え、そもそも残業には罰則付きの上限規制があるため、この上限を超えないように管理することが必要です。ここでは、残業規制への対策法について解説します。
関連記事:残業規制はいつから適用?労働基準法に違反したときの罰則を紹介
7-1. システムを導入して業務を効率化する
さまざまなシステムを導入することによって、人がこれまでしていた仕事をシステムに任せることが可能です。たとえば、給与管理システムや採用管理システムなどが挙げられます。
システムに任せることで業務が効率化し、残業規制を守りながら業務を進めることができるでしょう。
7-2. 業務を外注化する
業務の一部を外注することで、社員は勤務時間にコアとなる業務に集中することができ、残業をしなくて済むようになります。
ただし、外注すべき業務と社内でおこなうべき業務があります。まずは業務を分類したうえで、うまく外注していきながら、残業規制への対策をおこなっていきましょう。
7-3. 残業時間を適切に管理して可視化する
勤怠管理システムの導入によって残業時間を可視化することで、社員自身がどれだけ残業しているのか把握することができるようになります。これにより、残業時間に対する意識が芽生え、残業を削減するように努力するようになることが期待できるため、残業規制への対策に役立つでしょう。
関連記事:残業時間の適切な管理方法を企業が抱える課題とあわせて解説
関連記事:残業が多いと産業医面談が必要?長時間労働への対応を詳しく解説
8. 残業のルールを定めて適切に管理しよう

今回は、残業時間の上限規制や残業代の計算方法などについて解説しました。従業員に残業を命じるためには、事前に36協定を締結することが必要です。また、残業が発生した場合は、割増賃金を支給しなければなりません。36協定を締結せずに残業を命じたり、割増賃金を正しく支給しなかったりすると、法律違反として罰則を受けるため注意しましょう。
近年、残業に関しては、規制が厳しくなっています。日頃から残業が発生しないように人員の確保や生産性の向上を図っていくことは、従業員にも企業にもメリットがあります。残業規制への対策を万全な状態にして、健全な企業経営をおこなっていきましょう。