
どのような企業においても残業が発生することはあり、従業員が所定労働時間を超えて仕事をしなければならない状況は起こりえます。
しかし、残業申請ルールが決められていないと、従業員にも企業にも不利益が生じる恐れがあるため注意しましょう。
本記事では、残業の申請ルールを設けるメリットや導入方法について解説します。
関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も

残業時間の削減するにも、残業時間を管理するにも、まず残業時間を可視化することが大切です。 そもそも残業時間が各従業員でどれくらいあるのかが分からなければ、削減しなければならない残業時間数や、対象の従業員が誰かが分からないためです。
現在、残業時間を正確に把握できていないなら、勤怠管理システムを導入して残業時間を可視化することをおすすめします。 具体的な残業時間数が把握できるようになったことで、残業の多い従業員とそうでない従業員を比較して長時間労働の原因をつきとめ、残業時間を削減した事例もあります。
「システムで実際に効果があるのか知りたい」「システムではどう管理するのか知りたい」という方に向け、当サイトでは勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を例に、システムでは残業管理をどのように行えるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご確認ください。
目次
1. 残業申請制とは?必要性や申請書に記載する項目を紹介

残業申請制とは、その名の通り、残業をおこなうことについて従業員が申請することです。
本来、残業は緊急性の高い仕事が所定労働時間内に終わらなかった際、会社側が命令しておこなわせるものですが、納期などの都合上、従業員側から残業を申し出たいケースもあるでしょう。
何らかの業務が終わらなかった場合、従業員が残業することを申請してから業務を続ければ、どの程度残業がおこなわれているのか把握しやすくなります。
1-1. 残業申請の一般的な流れ
残業申請のルールは企業によって異なりますが、一般的には従業員が申請書を作成して提出し、上司や人事担当者が承認する、という流れで進められます。
紙の申請書ではなく、メールやチャットで残業の連絡をしたり、勤怠管理システムの機能を利用したりして申請する企業もあるでしょう。申請が承認されない場合、基本的に残業をすることはできません。
1-2. 残業申請書に書くべき項目
残業申請書には、以下のような項目を記載してもらいましょう。
- 残業日時
- 残業予定時間
- 残業理由
無駄な残業をさせないよう、理由を明確に記載させることが重要です。また、紙の申請書を使うと印刷や回覧の手間がかかるため、メールや勤怠管理システムを活用して承認フローを効率化するとよいでしょう。
1-3. 残業申請制を導入する企業が増えている理由
残業申請制を導入する大きな目的は、無駄な残業を減らし、残業代を削減することです。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が発生した場合、企業は通常の賃金に割増率をかけた割増賃金を支払わなければなりません。
自由に残業ができる状況では、仕事へのモチベーションが上がりにくいだけでなく、残業代をもらうことを目的として無駄に会社に残る従業員が増える可能性もあります。
そこで残業申請制を導入して、業務効率化を図りつつ、人件費を削減しようとする企業が増えてきたのです。
1-4. 残業申請制は違法?
残業申請制を導入することは、とくに違法ではありません。前述の通り、従業員の健康を守ることや残業代を削減することを目的として、導入している企業もあります。
ただし、従業員に対して残業申請を義務付けるためには、就業規則に明記しておくことが必要です。従業員は就業規則に従って働く必要があるので、合理的な理由もなくルールに違反した場合は、指導や注意をしたり、悪質な場合に懲戒処分を与えたりすることができます。
2. 残業申請のルールを設けるメリット
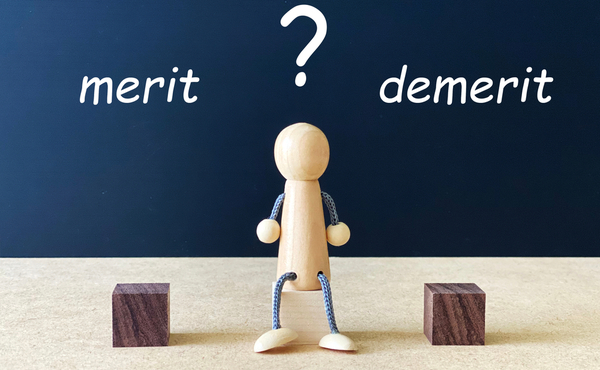
残業申請ルールを設けるメリットとしては、業務の効率化、従業員のメンタルヘルスの改善、残業時間の正確な把握などが挙げられます。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
2-1. 業務効率化の実現
業務効率化を実現できることは、残業申請ルールを設ける大きなメリットです。残業の申請ルールを導入すると、上司が部下の業務の状況を把握し、本当に残業が必要なのかを判断できます。
従業員がそれぞれの判断で残業をおこなえる環境では、不要な残業をおこなって残業代を稼ぐことが可能でしたが、申請ルールを設けることで、残業において本当に緊急度や重要度が高い業務に対してだけおこなわれるようになるでしょう。
さらに上司は、部下の能力や経験によって、より適切な業務の割り振りが可能となります。毎日のように残業を申請してくる部下がいる場合、スキルに見合わない業務内容になっている可能性を視野に入れ、業務量や内容の見直しも検討できるでしょう。
2-2. 従業員のメンタルヘルスの改善
残業の申請ルールが浸透すれば、従業員一人ひとりの業務状況を上司が把握しやすくなります。
結果として、長時間の残業をしている従業員が誰なのか、プロジェクトの進行が遅れている部分があるかなどをリアルタイムで知ることができるようになるでしょう。
上司が早期に改善策を講じられるので、コスト削減や業務効率化へとつなげ、プロジェクトが成功しやすくなります。それに加えて、長時間労働や業務へのストレスによって、心身に不調をきたす従業員を減らすことにもつながります。
2-3. 人件費の削減
無駄な残業を減らすことで、人件費の削減も図れます。自由に残業ができる環境では「生活残業」が横行している可能性もあるでしょう。生活残業とは、従業員が残業代によって生活費を稼ぐために、業務を意図的にゆっくりおこなうことです。
また、上司がまだ仕事をしている手前、帰りにくいという理由で部下が不要な残業をおこなっている場合もあります。残業を申請制にすることで、適切な業務でないと判断された場合、申請は承認されません。結果として無駄な残業が減り、人件費の大幅な削減につながります。
2-4. 残業時間を正確に把握可能
残業時間を正確に把握できることも、残業申請ルールを設けるメリットの一つです。正確な残業時間を把握しておかなければ、残業代を正しく支給することはできません。残業代を払い過ぎてしまったり、逆に未払いの残業代を請求されたりするケースもあるため、適切なルールを設定して残業時間を管理しましょう。
2-5. 残業時間の削減
残業申請ルールを設けることは、残業時間の削減にもつながります。残業の申請ルールが従業員の間に浸透してくると、残業は基本的にしないものという意識が生まれやすくなります。
就業時間内にすべての仕事を終わらせようとする従業員が増えれば、業務の効率化を実現できるでしょう。結果的に残業時間が少なくなり、会社が支払う残業代も節約できるのです。また、残業を申請制にすることで、残業管理が容易になります。
2019年の働き方改革関連法案の改正で、残業時間に上限規制が設けられたため、長時間の残業は罰則を受ける可能性があります。当サイトお配りしている「【残業ルールBOOK】残業時間の管理ルールと効果的な管理方法を解説!」というガイドブックでは残業時間の確認を効率的におこなう方法も詳しく解説しています。
先述した残業時間の上限もこれ一冊で確認することができるため、残業管理を適切におこないたい方はこちらから【残業ルールBOOK】をダウンロードしてご活用ください。
3. 残業申請のルールを設けるデメリット
 さまざまなメリットがある一方、残業の申請ルールを導入することにはデメリットもあります。
さまざまなメリットがある一方、残業の申請ルールを導入することにはデメリットもあります。
主に以下4つのデメリットがあることを覚えておきましょう。
3-1. 制度が形骸化する可能性
1つ目のデメリットは、制度の形骸化が起こりえることです。残業の申請ルールは、容易に形骸化する恐れがあります。
従業員が上司に対して残業の許可を求め、上司がその申請を承認するというプロセスをこなすだけになってしまえば、ただ単に残業をするための承認作業が増えることになってしまうでしょう。
残業の申請ルールを導入する際は、残業削減という本来の目的や重要性を従業員全員へ伝えておくことが大切です。
3-2. 残業代の未払い増加
残業申請ルールが正しく運用されなければ、残業代の未払いが増える恐れがあることもデメリットの一つです。
残業をなくすことだけに重きを置いてしまい、業務の効率化や適切な業務の割り振りがなされないでいると、結局は持ち帰り残業や申請しないサービス残業が増えることになります。
従業員だけでなく、上司などの管理職まで、全員が残業の申請ルールの正しい運用方法を理解しておくことが重要です。
3-3. 残業申請の手間が増える
残業申請の手間が増えることもデメリットといえるでしょう。申請書を作成したり承認したりするプロセスが発生するため、すぐに残業をスタートすることはできません。
残った業務を効率よく処理するためには、システム上で残業申請や承認をおこなえるツールを導入するなど、申請手続きを簡略化することが大切です。
3-4. 日中の業務が忙しくなる
残業申請制を導入すると、日中の業務が忙しくなる可能性もあります。残業をしにくくなることで仕事の生産性が高まる可能性もありますが、そもそもの業務量が多い場合は日中の業務が忙しくなりすぎ、従業員が負担を感じ、会社への不満へとつながるケースもあるでしょう。
残業申請制を導入するときは、従業員が抱えている業務量をしっかりと把握しておくことが重要です。
関連記事:残業禁止は計画的に|むやみな残業削減が招く新たな弊害とは?
4. 残業申請のルールを導入する方法
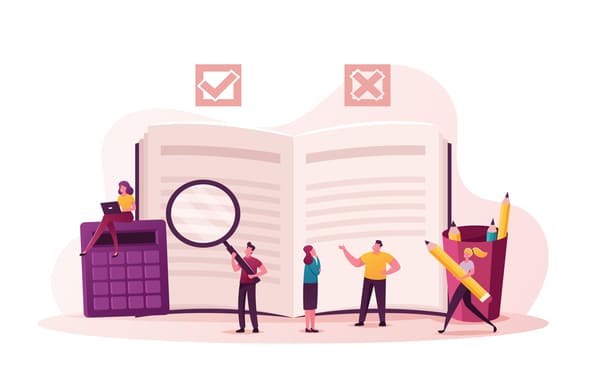
残業の申請ルールを導入する際には、いくつかのステップを踏むことが重要です。
残業の申請ルールをただ導入するだけでなく、上手に運用できるように順を追って見ていきましょう。
4-1. 残業申請ルールを就業規則に記載する
残業申請制を導入するにあたって、どのようなルールで運用をおこなうか制度の規定を作成して、就業規則に記載します。
どの時点で法的に見て残業になるのか、従業員がどのように残業を申請すればスムーズなのかなどを検討しながら規定を作成しましょう。
また、残業申請制では、従業員から上司に事前に残業申請書を提出させ、上司が許可を与える必要があります。残業申請をいつまでに提出させるのか、申請の承認者は誰にするのか、どのような基準で承認や却下をするのかといったポイントを定めましょう。承認者によってばらつきが出ないよう、承認する業務の具体例を決めておくことも大切です。
また、所定労働時間が7時間の企業であれば、従業員に1時間残業をさせても、法定労働時間の8時間のうちに収まる労働であるため、従業員に対して割増賃金を支払う必要はありません。申請が必要な残業に法定内残業も含むのか、法定外残業のみとするのかも決めておく必要があります。
会社や部門ごとの勤務形態もルールを作成する際の重要なポイントです。たとえば、外周りの営業担当者と、技術部門のエンジニアを同じ申請ルールで管理することは運用上難しいでしょう。会社や部門ごとのニーズに合わせて規定を作成する必要があります。
4-2. 残業申請書のフォーマットを作成する
規定を決めたら申請書のフォーマットを作成しましょう。申請書には下記のような項目を設定します。
- 残業予定時間
- 残業理由
- 上司の承認印
- 実際に残業をおこなった時間
- 上司の確認印
紙の申請書で提出させることもできますが、回収や差し戻しに手間がかかります。メールやシステムを用いるとスムーズに手続きがおこなえ、従業員の負担を減らして制度を運用できるでしょう。
4-3. 残業申請ルールのマニュアルを用意する
従業員への周知のために、残業申請に関するルールをまとめたマニュアルを用意しましょう。マニュアルは紙媒体よりも、エクセルやワードなどで作成して共有ファイルに入れておくことで、いつでも自由に確認できます。
申請・承認のルールに関することだけでなく、申請書の記入方法や管理方法についても明記しておくとよいでしょう。
理想は事前申請ですが、実際は緊急性のある急な業務もあるので、事後申請になる場合の例外対応についても規定しておくことが理想的です。このような事後申請の方法についてもマニュアルには詳しく記載しておきましょう。
4-4. 残業申請のルールを周知する
残業の申請ルールを定めたら、運用を開始する前に徹底的に周知することが重要です。
ルールを決めても周知されていなければ、運用がうまくいくことは決してありません。申請ルールを経営陣や管理職に伝えるだけでなく、従業員一人ひとりに説明する必要があるでしょう。
従業員一人ひとりが残業の申請ルールの重要性やメリットについて理解すれば、必然的に運用がスムーズにおこなわれるはずです。場合によっては、研修をおこなって申請ルールについて説明する機会を設けることが必要かもしれません。
ルールの周知は、導入前におこなえば十分というわけではありません。導入後も定期的にルールについて思い起こさせることが必要です。
4-5. 運用しながらルールを改善する
残業申請制を運用しながら、ルールを改善していくことも重要です。制度を導入したからといって、絶対にうまく運用できるとは限りません。
適切に運用されているかについても基準を設けてチェックすることで、より効果的な運用が可能となります。たとえば、同じような状況であるにもかかわらず、ある部署では残業が認められず、別の部署では残業が認められるといった事態が生じれば、従業員が不満を持つこともありえるでしょう。
残業申請を承認するかどうかの基準が曖昧だと、管理者の主観による判断になってしまいます。承認する基準を明文化したり、管理者向けの教育を実施したりして、ルールの統一や改善を図りましょう。
4-6. 勤怠管理システムの導入を検討する
紙の申請書を処理する手間がストレスになっている場合は、勤怠管理システムの導入を検討するとよいでしょう。一般的な勤怠管理システムには、オンラインで残業を申請・承認する機能が搭載されています。
紙の申請書を印刷したり、承認したりする手間を省けるため、残業申請制を効率よく運用できるでしょう。リモートワークを採用している企業や、外回りの従業員が多い企業にも最適です。
5. 残業申請制を導入する際の注意点

残業申請制は、残業をするために従業員に手間をかけさせることで、残業を減らす効果が期待される施策ですが、制度やルールの設定を誤ると期待した効果が得られず、従業員の不満につながる可能性もあります。
制度の導入で、かえって従業員の負担を増長させることのないように注意しましょう。残業申請制を導入するときの主な注意点は、以下の通りです。
5-1. 黙示的指示に注意
残業の申請ルールを導入する際、注意すべきなのが「黙示的指示」です。黙示的指示とは、上司から直接の指示がなくても、従業員が上司の意思に従って行動せざるを得ない状況にあることを指します。
残業の申請ルールを導入すると、申請にない残業がおこなわれたとしても、会社側は残業代を支払う必要はありません。会社側は従業員が申請せずにおこなった残業を把握することは困難だからです。
しかし、上司が従業員に対し、明らかに所定労働時間内に終わらないと考えられる業務を命じたり、残業せざるを得ないような高いノルマを設定したりする場合、黙示的指示があったと判断され、残業代を支払うよう裁判所から命じられることがあります。
裁判によって黙示的指示があったとみなされれば、いわゆる「ブラック企業」のレッテルを貼られたり、会社への就職希望者が減ったりする不利益を被ることになるでしょう。
そのため、残業の申請ルールを導入する際には、黙示的指示を与えることがないよう注意すべきです。
5-2. 残業申請をしない人への対処
申請にかかる手間が大きすぎたり、申請の承認条件が適切でなかったりすると、従業員が残業申請をせず、無許可で残業をおこなう可能性があります。
先述の通り、残業申請制の場合、残業許可がない残業に賃金を支払う必要は本来ありません。ただし、無許可の残業に対する未払い賃金を求めた実際の裁判における判例を見ると、黙示的指示が働いていると判断され、企業に対して未払いの残業代の支払いを命じられるケースが多いため、安易に残業を黙認することは危険です。
申請をせずに残業をしている従業員を把握した場合は、速やかに従業員に申請をしない理由の聞き取りをおこない、適切な指導や原因の解消をおこなうことが望ましいでしょう。
5-3. 持ち帰り残業が増えないように注意する
持ち帰り残業が増えないように注意することも大切です。残業申請の手続きが面倒、残業申請をすることで仕事が遅いと思われたくない、といった気持ちから、無断で仕事を持ち帰る従業員が増える可能性もあります。
従業員が自主的に仕事を持ち帰るだけでなく、上司が持ち帰りを指示する可能性もあるため、定期的にヒアリングを実施するなど、勤務状況を正確に把握しておくことが重要です。
5-4. 残業申請を却下するときのルールを明確にしておく
上司が必要でないと判断した場合、残業申請を却下することができます。先述の通り、判断基準が属人化しないよう、判断基準を明確にしておきましょう。
また、「無断での残業には給与を支払わない」とあらかじめ就業規則に規定しておくことで、却下された場合に無断で残業をおこなう従業員が発生することを防止できます。
5-5. 申請時間と実際の残業時間が合わなかったときの対応
残業を申請制にすると、残業をする理由や業務内容に加えて、残業の見込み時間を記入する場合があります。
たとえば、定時が17時の場合、2時間ほどで終わりそうだと予測したとします。その場合、17〜19時を残業として申請しますが「予測に反して長引いてしまった」もしくは「早く終わってしまった」ということも起こるでしょう。
そのようなとき、残業申請を差し戻して時間を変更するのか、追加申請が必要なのかなど、対応方法をあらかじめ考えておく必要があります。
5-6. 全ての部署でルールを守る
規模が大きく、部署が数多くある企業の場合、申請を承認する上司は1人ではないはずです。このようなとき「部署によって対応が違う」という問題が起こることが考えられます。
上司によって承認の甘さや厳しさに差が出ることのないよう、なるべく公平に判断されなければなりません。
「申請内容に目を通さずどのような申請も承認する上司」「承認が厳しく必要な残業もさせてくれない上司」は、どちらも問題です。前述した申請や承認のルールに沿った共通の対応がおこなわれなければ、導入の意味がありません。
申請を承認する立場にある上司には、事前に導入の目的や期待できる効果などを理解してもらい、ルール厳守を徹底しましょう。
6. 残業申請ルールはメリット・デメリットを理解して進めよう

今回は、残業申請制のメリット・デメリットや、導入する際のポイントなどを解説しました。残業申請ルールを導入すれば、残業を抑制したり、残業の発生状況を的確に把握したりすることが可能です。結果的に会社全体の残業が減るケースもあるため、従業員にとっても企業にとってもメリットがある制度といえるでしょう。
ただし、どれだけ効果を発揮するかは、事前の準備とルールの周知の徹底にかかっています。制度の導入によって、サービス残業や持ち帰り仕事が増えてしまっては意味がありません。残業申請制のメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで適切なルールを設定し、業務の効率化につなげましょう。

残業時間の削減するにも、残業時間を管理するにも、まず残業時間を可視化することが大切です。 そもそも残業時間が各従業員でどれくらいあるのかが分からなければ、削減しなければならない残業時間数や、対象の従業員が誰かが分からないためです。
現在、残業時間を正確に把握できていないなら、勤怠管理システムを導入して残業時間を可視化することをおすすめします。 具体的な残業時間数が把握できるようになったことで、残業の多い従業員とそうでない従業員を比較して長時間労働の原因をつきとめ、残業時間を削減した事例もあります。
「システムで実際に効果があるのか知りたい」「システムではどう管理するのか知りたい」という方に向け、当サイトでは勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を例に、システムでは残業管理をどのように行えるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご確認ください。








