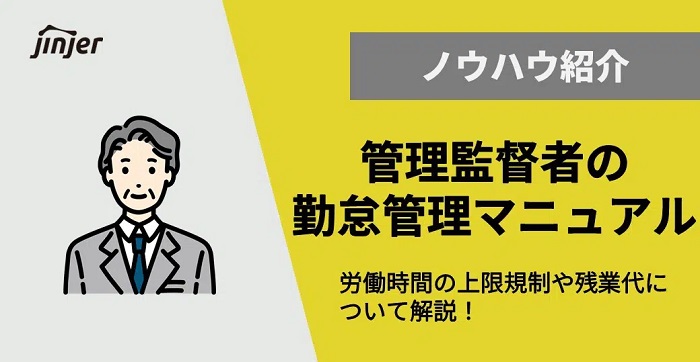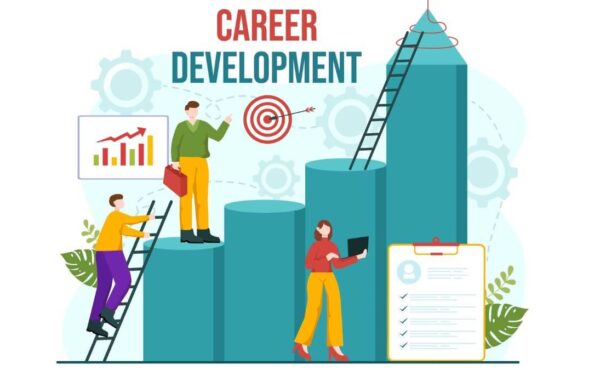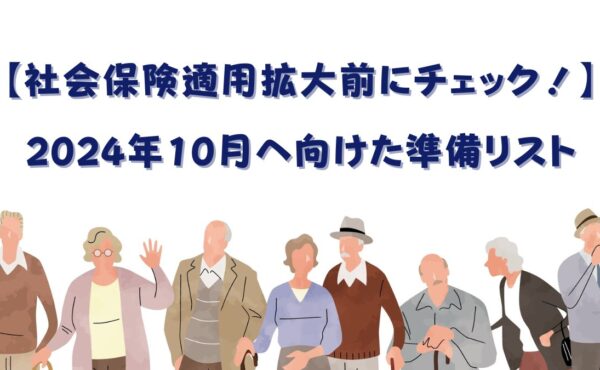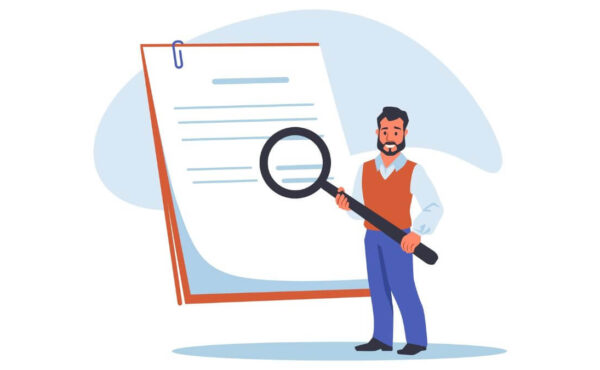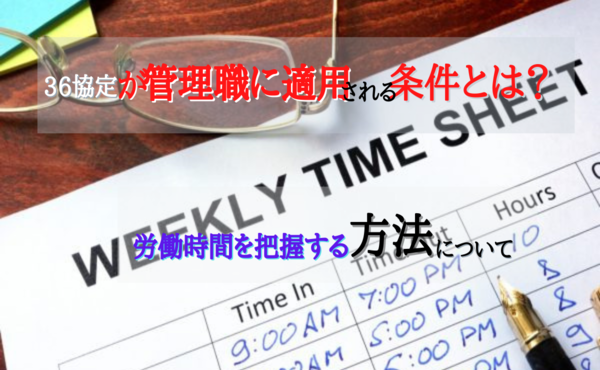
管理監督者には、労働基準法で規定された労働時間の制限が適用されないため、36協定を締結せずとも法定労働時間を超える時間外労働や休日労働が可能です。ただし、企業内で管理職にあたる者であっても、労働基準法で定められた管理監督者に該当しなければ、36協定の適用対象となります。今回は、36協定が適用される管理職の条件や、管理監督者の定義、労働時間を正確に把握する方法を解説します。
管理監督者に残業の上限規制は適用されませんが、労働時間の把握は管理監督者であってもしなくてはならないと、法改正で変更になりました。
この他にも、法律の定義にあった管理監督者でなければ、残業の上限超過や残業代未払いとして違法になってしまうなど、管理監督者の勤怠管理は注意すべきポイントがいくつかあります。
当サイトでは、「管理職の勤怠管理を法律に則っておこないたい」という方に向け、管理監督者の勤怠管理の方法やポイントについて、本記事の内容に補足事項を加えわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
管理職の勤怠管理に不安のある方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 36協定に関して管理監督者(管理職)は対象外?

36協定に関して管理監督者(管理職)は、原則として対象外です。36協定は、事業場で働くすべての人に、無条件で適用されるものではありません。「使用者と同等の立場」だと判断される管理職には、適用されないことがあります。ここでは、36協定とはどのような制度なのか、36協定の対象者について詳しく紹介します。
1-1. 36協定とは?
36協定とは、労働基準法第36条に基づいて、労使間で締結する労使協定のことを指します。労使間で36協定を締結することで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や法定休日(週1日もしくは4週4日)に働く休日労働が可能になります。ただし、36協定の時間外労働には罰則付きの上限があり、従業員に過酷な労働が課されないようになっています。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
1-2. 36協定の対象者
36協定が適用される対象者は、労働基準法において「労働者」に該当するすべての人です。労働基準法第9条で以下のように定められています。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
わかりやすくまとめると、労働者とは事業所に雇われていて、給与を受け取っている人のことです。そのため、正社員はもちろんですが、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員、契約社員などにも36協定が適用されます。ただし、次のような立場にある人は、36協定の対象外となるケースもあります。
- 管理監督者
- 育児・介護をしている従業員
- 妊産婦
- 18歳未満の年少者
なお、建設業や運送業など、2024年3月31日まで36協定の適用が猶予されている業種・業務もありました。しかし、2024年4月1日から、その猶予期間が終了し、36協定の適用が開始されているので注意が必要です。
関連記事:36協定の対象者は従業員全員?対象外となるケースについても解説
1-3. 36協定は管理監督者には適用されない!
労働基準法第41条により、「管理監督者」に該当する従業員に対しては、労働基準法で定められ労働時間や休憩、休日の制限を受けないため、36協定が適用されません。
ここで注意しなければならないのが、企業内で「管理職」とされている立場の者でも、そのすべてが法律で定義されている「管理監督者」に該当するわけではないということです。たとえ企業内で管理職という立場であっても、法的な管理監督者に該当しなければ、労働基準法で定められた労働時間の制限が適用され、それを超える時間外労働には36協定の締結が必要です。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(省略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)
(省略)
関連記事:労働基準法36条の36協定とは?労働時間の上限・締結方法をあわせて解説
2. 36協定の管理監督者に該当する4つの要件

法律で定義されている管理監督者とは、労働条件の決定をはじめ、労務管理の権限など、使用者(経営者)と同じ立場にある者のことです。一般的な「管理職」が役職名で判断されるのとは異なり、職務内容や勤務態様の実態、有する権限や責任、賃金や待遇といった4つのポイントを総合的に判断します。ここでは、36協定の管理監督者に該当する4つの要件について紹介します。
2-1. 経営に関わる重要な職務を任されている
36協定の管理監督者とみなされるには、経営者と一体的な立場にあり、経営に関わる重要な職務を任されている必要があります。課長や店長、リーダーといった役職で後輩の面倒を見る立場であったとしても、経営会議などに参加し、経営方針に関して経営者と同等の発言力がなければ、管理監督者とはいえません。
2-2. 経営者と同等の責任と権限を委ねられている
36協定の管理監督者と認められるためには、経営者と一体的な立場になければなりません。そのためには、経営者と同等の責任と権限を委ねられている必要があります。十分な権限が与えられていなければ、客観的にみると、通常の労働者と立場が変わりないと判断される可能性があります。このように、職務内容だけでなく、責任や権限も考慮して、管理監督者かどうかは判断されなければなりません。
2-3. 自分の裁量で働き方や労働時間を決められる
管理監督者は、時間に関係なく、経営の判断や対応をしなければならない場面があります。そのため、通常の労働者と同じ働き方をすることは難しいと考えられます。もしも自分で労働時間や休日、休憩などを管理する権限がなければ、通常の労働者と同じ規定が適用されるべきです。このように、自分で働き方や労働時間を責任をもって自由に管理できるかどうかも、管理監督者かどうか判断するためのポイントになります。
2-4. 相応しい待遇がなされている
「同一労働・同一賃金」という言葉が定着しつつあるように、経営者と一体的な立場にあり、経営に関わる職務を任されている場合、それ相応の待遇を与えられている必要があります。また、管理監督者になると、36協定が適用されないだけでなく、時間外労働や休日労働の割増賃金も支給されなくなります。場合によっては、通常の労働者よりも賃金が低くなってしまう恐れがあります。このような場合、一般従業員のように36協定を適用し、時間外労働や休日労働の手当が支給されるべきです。以上から、36協定の管理監督者とみなすのであれば、責任や職務内容、働き方を加味して、十分な待遇を与えている必要があります。
関連記事:労働基準法第41条第2号の「管理監督者」の意味や特徴を詳しく解説
3. 36協定における管理監督者の定義のポイント

36協定の管理監督者とみなすには、正しく要件を満たす必要があります。しかし、管理監督者や管理職という言葉は似ているため、間違って判断してしまうケースもあります。ここでは、36協定における管理監督者の定義のポイントについて詳しく紹介します。
3-1. 労組法の「監督的地位にある労働者」=管理監督者ではない
労働組合法第2条では、人事部課・労務部課など、職務上、人事や労務に関係する機密情報に触れる立場にいる労働者は、「監督的地位にある労働者」に該当するため非組合員と定義されています。しかし、労働組合法の「監督的地位にある労働者」にあたる者であっても、「管理監督者とみなされる4つの要件」を満たさなければ、労働基準法上の管理監督者には該当しないので注意が必要です。
(労働組合)
第二条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽいヽ触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
3-2. 管理職と管理監督者の違い
管理職と管理監督者の大きな違いは「労働基準法で認められるかどうか」です。管理監督者かどうかは、業務の実態に基づいて判断されます。一方で管理職は、企業が独自に決めた役職です。そのため、企業によって管理職とよぶ役職が違い、課長以上を管理職とよぶ場合もあれば、部長以上が管理職とされる場合もあります。
つまり、企業が管理職に就いている人を管理監督者として扱っていたとしても、実態が伴っていなければ法律上の管理監督者としては認められません。管理監督者は36協定の対象外になりますが、労働基準法上、管理監督者ではないけれど、企業の規定上、管理職となっている人は36協定の対象になります。その場合、当然、時間外労働の上限規制や割増賃金の対象にもなるので注意が必要です。
3-3. 一般労働者を管理的監督者として扱うのは労働基準法違反
小売業や飲食業など、複数のチェーン店を展開している企業の場合、店舗によっては少人数の正社員とパート・アルバイトで運営しているケースもあります。このような場合、店長である従業員が労働基準法上の管理監督者として扱われているにもかかわらず、相応の権限や責任、待遇を与えられていないことがあります。
労働基準法第41条第2号に基づく「管理監督者」に該当しない従業員を管理監督者として扱い、36協定を締結せずに時間外労働をさせる、割増賃金を支払わないといった行為は、労働基準法違反です。刑事裁判で罰金刑を科せられた事例もあるため、企業側は管理監督者の定義を把握し、適切な対応をする必要があります。
このように上記の条件に該当する労働者は「管理監督者」と扱われ、労働基準法の適用が一部除外されます。とはいえ、「管理監督者の労働時間において例外があることは知っているものの、細かい内容については把握できていない」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。本サイトでは、管理監督者における労働時間の規定や法律、また法律に沿った勤怠管理方法をわかりやすく解説した資料を無料で配布しています。 管理監督者の労働ルールや適切な勤怠管理方法を学びたい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
4. 36協定の管理監督者(管理職)に関する注意点

労働基準法上の管理監督者としてみなされる場合は、36協定の適用対象外となります。しかし、管理監督者でも適用される規定や36協定における注意点があります。ここでは、36協定の管理監督者(管理職)に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. 出向する場合は36協定の適用が変わる可能性あり
従業員が出向する場合、原則として出向先の36協定が適用されます。下記のように、出向元と出向先で立場が変わる場合、36協定の適用についても変わる可能性があるので注意が必要です。
|
出向元 |
出向先 |
36協定の取り扱い |
|
一般従業員 |
管理監督者 |
出向先が36協定を締結していても適用対象外 |
|
管理監督者 |
一般従業員 |
出向先が36協定を締結している場合、適用対象となる |
4-2. 管理監督者でも労働時間の管理は必要
企業には、従業員に対して、労働契約法第5条に基づいた安全配慮義務があります。安全配慮義務とは、従業員が身体の安全を確保したうえで働けるよう企業が配慮する義務で、管理監督者にも適用されます。そのため、たとえ管理監督者であっても、長時間労働によって健康を害することがないよう、労働時間を調整しなければなりません。
また、2019年4月に働き方改革関連法が施行されたことに伴い、労働安全衛生法が改正されました。労働安全衛生法第66条の8の面接指導の義務を果たすため、管理監督者の労働時間の把握が企業に義務付けられるようになっています。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(面接指導等)
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
関連記事:管理監督者の労働時間は上限なし?法律の適用範囲や労働時間の把握方法を解説
4-3. 深夜労働や有給休暇の規定は適用される
労働基準法の管理監督者に該当する場合、原則として、労働時間や休憩、休日の規定は適用されません。そのため、管理監督者が時間外労働や休日労働をおこなっても、それに応じた割増賃金の支給は不要です。しかし、深夜労働の規定は管理監督者にも適用されるので、22時~5時の間に労働をした場合、深夜労働の割増率(25%以上)を適用して割増賃金を支払う必要があります。また、年次有給休暇の規定も管理監督者に適用されます。1年に10日以上の有給休暇が付与されている場合、年5日の有給取得義務化の対象になるため注意が必要です。
関連記事:年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは
4-4. 管理監督者は過半数代表者になれない
労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者を選定したうえで、36協定を締結しなければなりません。労働基準法施行規則第6条の2により、管理監督者は過半数代表者になることができません。ただし、過半数代表者の選出にあたり、投票などに参加できる権利はあるので注意が必要です。
第六条の二 (両略)、法第三十六条第一項、(省略)に規定する労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(省略)
関連記事:36協定における労働者代表の選定方法やその条件を徹底解説
5. 36協定の管理監督者(管理職)におけるよくある質問

ここでは、36協定の管理監督者(管理職)におけるよくある質問に対する回答を紹介します。
5-1. 管理職しかいない事業所の36協定はどうなる?
管理職しかいない事業所の場合、すべての従業員が36協定の適用対象外となります。そのため、管離職のみの事業所の場合、36協定の締結は不要です。また、過半数代表者の選定の必要もありません。ただし、管理職が労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかきちんとチェックすることが大切です。
5-2. 「名ばかり管理職」とは?
「名ばかり管理職」とは、管理職の権限が十分にないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として扱われている労働者を指します。管理監督者に該当する場合、労働時間や休憩、休日の規定が適用されないので、原則として残業代などが支給されません。
労働基準法の管理監督者に当てはまるかどうかは、肩書や職位でなく、その労働者の立場や権限を基に判断されなければなりません。そのため、「名ばかり管理職」に該当する人には、36協定を適用し、残業代などをきちんと支給する必要があります。
関連記事:36協定違反によって科される罰則と違反しないためのチェック事項
5-3. 36協定は従業員人数何人から?
36協定は従業員の人数に関係ありません。時間外労働や休日労働をおこなわせる場合、36協定の締結および届出が必要です。ただし、管理監督者のみの事業所であれば、すべての人が36協定の適用を受けないので、時間外労働や休日労働が発生する場合でも、36協定の締結は不要です。なお、従業員の人数が関係する規定として、「就業規則の作成・届出」があります。従業員人数が10人以上の企業は、就業規則の作成および届出の義務があるので注意しましょう。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない
関連記事:就業規則の基礎知識|作成ルール・記載事項・注意点などを解説
6. 企業は管理職の労働時間を把握すべき!具体的な方法とは?

36協定の適用対象である管理職、法律上の管理監督者に該当する管理職、どちらの労働時間に関しても、企業側が正確に把握し、適切な勤怠管理をする必要があります。管理職の労働時間を把握するための方法としては、「紙のタイムカード」「PC・スマホのログや記録」「エクセル・スプレッドシート」などがありますが、より正確性と客観性を求めるのであれば、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
勤怠管理システムを活用すれば、PCやスマホを使って簡単に従業員の労働時間や休憩時間、時間外労働、休日労働などを記録し、自動集計することができます。これにより、リアルタイムで労働時間を把握し、過労になっていないかなど管理することが可能です。また、ヒューマンエラーによる集計ミスを減らし、正確に労働時間を管理することができます。
関連記事:勤怠管理システムとは?特徴や活用メリット、システムをご紹介
7. 勤怠管理システムで管理職の労働時間を正確に把握しよう

たとえ企業内で「管理職」であっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合、時間外労働・休日労働には36協定の締結が必要です。法律上の管理監督者に該当するかどうかの判断は、職務内容や権限、勤務形態、待遇などによっておこないます。管理職の労働時間を正確に把握するには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。従業員の労働時間や時間外労働などを自動集計できるので、正確で効率的な勤怠管理が可能になります。
管理監督者に残業の上限規制は適用されませんが、労働時間の把握は管理監督者であってもしなくてはならないと、法改正で変更になりました。
この他にも、法律の定義にあった管理監督者でなければ、残業の上限超過や残業代未払いとして違法になってしまうなど、管理監督者の勤怠管理は注意すべきポイントがいくつかあります。
当サイトでは、「管理職の勤怠管理を法律に則っておこないたい」という方に向け、管理監督者の勤怠管理の方法やポイントについて、本記事の内容に補足事項を加えわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
管理職の勤怠管理に不安のある方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。