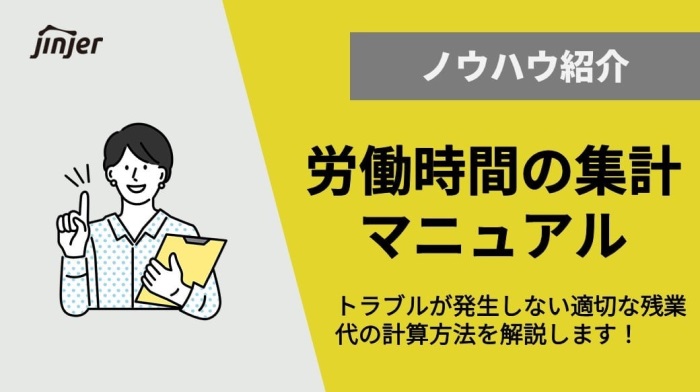勤怠は1分単位で計算するのが原則で、15分単位で切り上げ・切り捨てをして計算している場合は違法になります。労働基準法に違反すると、罰金などの罰則が課せられる恐れもあります。この記事では、15分単位での勤怠管理が違法になる理由と、正しい労働時間や残業時間の計算方法をわかりやすく解説します。また、15分単位の勤怠管理が認められるケースについても紹介します。
「打刻まるめの労働時間集計ってどうやるの?」「そもそも打刻まるめは問題ない?」という疑問をおもちではありませんか?
当サイトでは、打刻まるめをしている場合の労働時間の計算方法や、正しい残業代の計算方法、打刻まるめが違法となる場合について解説した資料を無料配布しております。
「打刻まるめでの正しい集計方をが知りたい」「自社の打刻運用に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 15分単位での勤怠管理は違法!

勤怠管理は1分単位で実施しなければならないため、15分単位で労働時間を計算するのは労働基準法違反となります。ここでは、打刻まるめの概要を説明したうえで、15分単位の勤怠管理が違法になる理由について詳しく紹介します。
1-1. 打刻まるめとは?
打刻まるめとは、始業時刻・終業時刻などの打刻情報の端数があった場合に、5分、15分、30分など、企業が定めた単位で切り上げや切り捨てをすることです。たとえば、15分単位で打刻まるめをしている会社の場合、「17時42分」の退勤は、「17時30分」の退勤として取り扱われます。
しかし、勤怠管理は、従業員の労働時間に基づきおこなわなければなりません。そのため、打刻時間の切り捨てや切り上げをして打刻情報を丸めるのは原則として認められていないため注意しましょう。
関連記事:打刻まるめとは?違法にならないためのルールやメリット・デメリットを解説!
1-2. 15分単位での勤怠管理が違法になる理由
労働基準法第24条「全額支払いの原則」により、1分単位での勤怠管理が義務付けられています。そのため、15分単位で切り上げや切り捨てをおこなっている企業は、労働基準法第24条に違反していることになります。
以前は15分単位での勤怠管理が一般的で、当たり前のように15分単位での残業代の切り捨てがなされていましたが、法改正がおこなわれた現在は1分単位での勤怠管理が原則です。会社の就業規則に15分単位で切り上げ・切り捨てといった内容が記載されている場合、原則として当該記載部分は労働契約の効力がなく無効になります。このように、15分単位で労働時間の切り上げや切り捨てをおこなう勤怠管理は原則として違法なので注意が必要です。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
関連記事:タイムカードの計算を15分単位で切り上げるのは違法?勤怠管理の注意点を解説!
1-3. 遅刻や早退時間の切り上げ(切り捨て)も違法
就業規則で決められた始業時間より3分ほど遅刻してきた従業員がいた場合、その従業員の始業時間を15分切り上げて勤怠管理をしているケースがあります。また、終業時間よりも10分ほど前に早退したため、15分切り捨てて勤怠管理をおこなっているケースもあるかもしれません。
しかし、労働基準法第24条によって1分単位での勤怠管理が義務付けられているので、遅刻や早退であったとしても労働時間の切り上げや切り捨ては違法となります。遅刻や早退であっても、1分単位で労働時間を計算することが大切です。
関連記事:勤怠計算を正しくする方法は?15分単位の計算の違法性も解説
2. 15分単位での勤怠管理をしていた場合の罰則とは?

15分単位で勤怠管理をしている場合、労働基準法に基づき罰則が課せられます。ここでは、15分単位での勤怠管理をおこなっていた場合の罰則の内容について詳しく紹介します。
2-1. 行政指導を受ける
勤怠管理を15分単位でおこなうのは違法です。しかし、いきなり刑事罰が課されるわけではありません。従業員からの申告などに基づき、労働基準監督署は企業が法律に違反していないか調査をおこないます。なお、調査には「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」といった種類があります。
15分単位や30分単位で労働時間を計算する勤怠管理を採用していた場合、労働基準監督署から是正指導や勧告を受ける可能性があります。その場合、勤怠管理を見直し、再度調査を受けるまでに、正しい方法に改善しましょう。
関連記事:勤怠管理の法律上のルールとは?違反した場合の罰則や効率のよい管理方法を解説!
2-2. 労働基準法に基づき罰則が課せられる
労働基準監督署からの指導を受けたにもかかわらず、15分単位の勤怠管理を見直さない場合、再調査を受けた際に労働基準法に基づく刑事罰が課せられます。この場合、労働基準法第120条に則り、30万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあるので注意しましょう。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一(省略)、第二十三条から第二十七条まで、(省略)
2-3. 企業名が公表される
罰金だけであればリスクが小さいと考えている人もいるかもしれません。労働基準法に違反すると、厚生労働省のホームページなどに企業名が公表されるリスクもあります。企業の信頼性を損ない、事業の継続に影響を及ぼす恐れもあるため、早期に勤怠管理を正しい方法に改善することが大切です。
2-4. 未払い賃金を請求される
15分単位・30分単位で勤怠管理をし、給与計算をおこなっていた場合、1分単位で正しい賃金が従業員に支払われていなかったことになります。そのため、従業員から未払い賃金を請求されたら、これに応じなければなりません。
また、賃金の支払いが遅れたことによる「遅延損害金」や、裁判所から会社に対する制裁としての「付加金」を上乗せして賃金を支払わなければならない可能性もあります。このように、15分単位での勤怠管理をおこなっている場合、さまざまな法的リスクがあるため、速やかに見直しをしましょう。
3. 15分単位の勤怠管理が認められるケース

勤怠管理は1分単位で実施しなければならないので、15分単位で勤怠を丸めるのは原則として違法です。しかし、例外として15分単位での打刻まるめが認められるケースもあります。ここでは、15分単位の勤怠管理が認められるケースについて詳しく紹介します。
3-1. タイムレコーダーと業務場所が離れている場合
タイムカードを使って勤怠管理をおこなっている企業も少なくないでしょう。打刻するためのタイムレコーダーと、実際に業務をする場所が離れている場合、打刻時間と実労働時間にズレが発生します。このような場合、打刻してから仕事をし始める時間や、仕事が終わってから打刻するまでの時間を15分単位などで丸めて計算している場合もあるかもしれません。
このような場合、労働時間よりも短くなるような打刻まるめは違法です。しかし、労働時間の切り捨てや切り上げの理由を客観的に証明できるのであれば、15分単位での打刻まるめが認められる可能性もあります。ただし、正確な勤怠管理のため、タイムレコーダーを現場の近くに設置できないか検討することが大切です。
3-2. 始業前の業務を申請制にしている場合
早く職場に着き、仕事をしていないにも関わらず打刻をしてしまうと、誤った勤怠管理や給与計算につながる可能性があります。始業時刻前の労働は発生することが予想されていない企業の場合、15分単位で打刻情報を切り上げても問題ないでしょう。
しかし、業務が発生している可能性もあるので、申請制などを採用すると、トラブルを未然に防止することができます。また、従業員が混乱しないよう、事前にルールを就業規則に明記してきちんと周知しておきましょう。
3-3. 労働者が有利になるような切り上げ(切り捨て)の場合
勤怠の15分単位の切り上げや切り捨てが問題になるのは、労働基準法に抵触する場合です。たとえば、18時18分に退勤した場合、従業員が有利になるよう15分単位で切り上げて、18時30分に退勤したことにしても問題ないでしょう。
しかし、このようなやり方を採用すると、実際よりも残業が多く発生していることになり、正確な勤怠管理ができません。また、実労働時間よりも多くの人件費がかかり、コストの負担も大きくなります。さらに、従業員によって不公平を生むと、企業に対する不満につながる恐れもあります。精度の高い勤怠管理や給与計算を実現するためにも、15分単位でなく、1分単位で勤怠管理がおこなえる体制を整備しましょう。
4. 正しい残業時間の計算方法

15分単位での勤怠管理は違法であり、1分単位での勤怠管理が原則です。これは残業時間に対しても適用されます。ここでは、正しい残業時間の計算方法を紹介します。
4-1. 労働時間の定義を把握する
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下で働いている時間を指します。そのため、次のような直接仕事に関係ないような時間も労働時間に含まれる可能性があります。
- 朝礼・終礼
- 仕事に必要な着替え
- 清掃・片付け
- 研修・セミナー
- 強制参加の社内イベント など
このような時間を切り捨てて勤怠管理をおこなっていたら違法になるので注意が必要です。また、労働基準法第32条には、法律で定められた労働時間の定義が記載されています。法定労働時間は1日8時間、1週40時間とされており、原則として、これを超えて従業員を働かせることはできません。また、労働時間は休憩時間を除いて考える点にも注意が必要です。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
4-2. 残業には「法定外労働」と「法定内残業」がある
労働時間には、残業時間も含まれます。残業は大きく「法定外残業」と「法定内残業」の2種類に分けられます。法定外残業とは、法定労働時間を超えた場合の残業を指します。法定外残業の場合、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払う必要があります。
一方、法定内残業とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えていないけれど、企業が就業規則などで定めた所定労働時間を超えて働いた分の残業を指します。法定内残業の場合、割増賃金は適用されず、1時間あたりの賃金を法定内残業の時間分支払えばよいとされています。主に1日の所定労働時間が8時間未満、もしくは週の所定労働時間が40時間未満の短時間勤務社員やパート従業員などの残業に適用されます。法定外残業と法定内残業の違いをまとめると、次の表の通りになります。
|
法定外残業 |
法定内残業 |
|
|
関連記事:法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説
4-3. 残業時間は1分刻みで給与計算する
賃金は、労働基準法第24条「全額支払いの原則」に則り支払わなければなりません。全額を支払うには、通常の労働時間だけでなく、残業時間も1分刻みで計算する必要があります。残業時間を15分単位で切り捨てて勤怠管理している場合は違法となり、30万円以下の罰金刑に処される可能性がある点に留意しましょう。
4-4. 残業代を1分単位で計算する方法
残業時間を1分単位で計算するために、まずは従業員の時給を調べましょう。アルバイトやパートなど時給制の従業員であれば、時給をそのまま残業代の計算に使用できます。月給制の場合、次の計算式を使って1時間あたりの基礎賃金を算出します。
基礎賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間数
※月平均所定労働時間数 = ( 年間の所定労働日数 – 年間休日数 ) × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月
このときに、1時間あたりの基礎賃金を計算する際の月給は、「手当などを除いた基本給のみで良いのでは」と思う人もいるかもしれません。しかし、手当を含めるか除外するかは、労働者の個人的事情を加味しているかどうかで判断します。基礎賃金が算出できたら、下記の計算式を利用して、残業代を計算します。
残業代 = 基礎賃金 × 残業時間 × 割増率
たとえば、基礎賃金(時給)2,000円、法定労働時間を超える残業時間20時間の場合、割増率1.25が適用され、残業代は50,000円(=2000円×20時間×1.25)と計算できます。正しく残業代を算出するため、この際の残業時間を1分単位で計算することが大切です。
関連記事:残業代の正しい計算方法とは?給与形態・勤務体系別にわかりやすく解説!
5. 残業時間の計算において注意すべきポイント

残業時間を計算する際には気を付けるべき点がいくつかあります。ここでは、残業時間の計算において注意すべきポイントについて詳しく紹介します。
5-1. 「時間外労働」の割増率は2種類ある
割増賃金は「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」に該当する場合に支払わなければなりません。時間外労働とは、いわゆる残業(法定外)のことです。法定労働時間を超える時間外労働に対して適用される割増率は、下記のように2種類あります。
|
種類 |
割増率 |
|
(法定内)時間外労働 |
なし |
|
(法定外)時間外労働(60時間以下) |
25%以上 |
|
(法定外)時間外労働(60時間超え) |
50%以上 |
このように、時間外労働60時間以下の割増率は25%以上、時間外労働60時間超えの割増率は50%以上が適用されます。そのため、残業時間を正しく計算したうえで、時間数に応じて割増率の適用を変える必要があります。正しく残業代が支払われない場合、従業員から残業代の未払い請求を受ける可能性があります。また、罰金や懲役といったペナルティが課される恐れもあるので、気を付けて勤怠管理や給与計算をおこないましょう。
関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も
5-2. 22時以降の残業には「深夜手当」も支給する必要がある
22時~翌5時の勤務や残業に対して深夜手当を支払うことが義務付けられています。そのため、22時以降の残業は、時間外労働の割増率に加えて、深夜労働の割増率25%も適用されます。
|
種類 |
割増率 |
|
深夜労働のみ |
25%以上 |
|
深夜労働 + 時間外労働(60時間以下) |
50%以上(= 25%以上 + 25%以上) |
|
深夜労働 + 時間外労働(60時間超え) |
75%以上(= 25%以上 + 50%以上) |
このように、夜勤が混じると残業代の計算が複雑になるので、手計算ではなく、ExcelやWeb上の残業代計算ツールを活用して、効率よく計算できるようにしておくことが大切です。勤怠管理システムの導入を検討してみるのもおすすめです。
関連記事:深夜労働は何時から何時まで?深夜時間帯の割増賃金の計算方法も詳しく解説!
5-3. 休日労働には残業が適用されない
休日労働とは、法定休日の労働のことです。法定休日に労働させる場合、休日労働の割増率35%以上が適用されます。ただし、休日労働には、残業の定義がないので、時間外労働の割増率は適用されません。しかし、深夜労働の割増率は適用されるため注意が必要です。
また、所定休日の労働には休日労働の割増賃金が適用されません。ただし、所定休日に残業をおこなった場合、時間外労働の割増賃金が発生する可能性もあるので気を付けましょう。
関連記事:休日出勤の定義とは?割増賃金の計算方法や強制・拒否できるかどうかも解説!
5-4. 管理監督者には残業が適用されない
労働基準法第41条に該当する労働者は、労働時間や休憩、休日の規定が適用されません。そのため、管理監督者は残業や休日出勤が適用されず、時間外労働や休日労働といった割増賃金の支給は不要です。ただし、管理監督者が夜勤をおこなった場合、深夜労働の割増賃金は適用されるので注意が必要です。
また、労働安全衛生法第66条の8の3に則り、使用者には、すべての従業員の労働時間を把握する義務があります。そのため、管理監督者の労働時間も、適正に管理しなければなりません。残業代が発生しないからといって、管理監督者の勤怠管理をしなくてもよいわけではないので留意しましょう。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
6. 残業時間の切り捨てが許可されるケース

原則として15分単位での勤怠管理は違法であり、残業時間も含め労働時間は1分単位で管理しなければなりません。しかし、なかには例外があります。ここでは、残業時間の切り捨てが許可されるケースについて詳しく紹介します。
6-1. 1ヵ月単位で残業時間を算出する場合
1ヵ月ごとに残業時間を算出している企業では、勤怠を締める際に残業時間の端数が30分未満であれば切り捨てることができます。これは、給与計算の手間を軽減することを目的として設けられた仕組みです。「労働基準法関係解釈例規について」では、下記のように定められています。
二 割増賃金計算における端数処理
次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(一)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
6-2. 残業時間の切り上げが求められる場合に注意が必要
1ヵ月ごとに残業時間を計算している場合、残業時間の端数が30分未満であれば切り捨てが可能です。しかし、端数が31分や40分など、30分を超えた場合は端数を1時間に切り上げて給与を計算する必要があります。「労働基準法関係解釈例規について」にも定められているため注意しましょう。
このように、1ヵ月ごとに残業時間を算出して給与を計算している会社では、残業時間の端数部分について切り捨てや切り上げといった端数処理が求められます。正確な給与の計算はできなくなりますが、その分勤怠管理の手間を省き、作業を簡易化することが可能です。
ここまで解説してきました通り、残業時間の計算は端数の切り上げが認められる場合や割増賃金が発生する場合などがあり、非常に複雑です。また、残業時間の計算を誤ってしまうと、法律違反や従業員とのトラブルにつながってしまうなど、残業時間の計算に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは残業時間に限らず、労働時間の集計についてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。端数の切り上げや割増賃金が発生する場合などの計算例も詳細に記載しているので、実際の業務のなかで不安になった際に、参考にしていただけます。労働時間の集計に不安を感じていらっしゃる方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
7. 残業時間の勤務形態に応じた考え方

ライフスタイルの多様化により「フレックスタイム制」「変形労働時間制」「裁量労働制」といった柔軟な働き方をする人も少しずつ増えています。ここでは、勤務形態に応じた残業時間の考え方について詳しく紹介します。
7-1. パートやアルバイト
パートやアルバイトも正社員と同様で「労働者」に該当するため、労働基準法の適用を受け、残業代や割増賃金を適切に支払う必要があります。ただし、パートやアルバイトで働く人は、「1日4時間勤務」「週20時間勤務」などのように、フルタイム労働者と比べると、勤務時間が短い傾向にあります。
時間外労働の割増賃金が生じるのは、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えてからです。しかし、所定労働時間を延長して働かせた時間に対しても、残業代を支払わなければならないので注意しましょう。
7-2. 変形労働時間制
変形労働時間制とは、繁忙期や閑散期のある場合に週・月・年単位で労働時間を調整できる制度のことです。たとえば、1ヵ月単位の変形労働時間制を導入する場合、1週目の労働時間を30時間にして、2週目の労働時間を50時間にするといったことができます。
2週目の労働時間は法定労働時間を超えていますが、1ヵ月単位の変形労働時間制の場合は対象期間を定めて労働時間を清算するので、その期間で法定労働時間を超えていなければ法的にも問題ありません。ただし、1日、1週、対象期間それぞれでみて残業時間をチェックしなければならないため、残業代の計算は煩雑になりやすいです。また、変形労働時間制を導入したからといって、15分単位で打刻まるめをするのは違法になるので、正しく勤怠管理をおこないましょう。
関連記事:変形労働時間制とは?残業の考え方や導入方法、注意点をわかりやすく解説
7-3. フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、一定期間についてあらかじめ決められた総労働時間の中で、従業員が自ら毎日の始業・終業時刻、労働時間を決められる制度です。フレックスタイム制では、あらかじめ労働すべき時間を定めた1ヵ月~3ヵ月の「清算期間」があり、清算期間において労働すべき時間を「総労働時間」といいます。総労働時間を超えて働いた時間が残業時間となります。
このように、フレックスタイム制では清算期間を単位として労働時間を管理するので、1日8時間、1週40時間の労働時間を超えても、ただちに残業時間とはならないことがあります。ただし、フレックスタイム制においても15分単位での勤怠管理は違法であり、1分単位で労働時間を計算することが大切です。
関連記事:フレックスタイム制とは?メリットやデメリット、目的と手続きを解説
7-4. 裁量労働制
裁量労働制とは、実際に働いた実労働時間でなく、あらかじめ決められた時間を労働したとみなす勤務体系の制度です。すべての職種で採用できるわけではありませんが、従業員は勤務時間の制限がなくなり、個人の裁量で毎日の始業・終業時刻などを管理することができます。
また、残業時間についても労働があったとみなす制度であるため、実際の残業時間に応じて残業代を支給する必要はありません。残業があったとみなしている固定の時間分のみ、残業代(固定残業代)を支払います。なお、裁量労働制であったとしても、22時以降の夜勤や休日出勤をおこなった場合は、その分の割増賃金を支払う必要があります。
裁量労働制ではみなし労働時間が採用されるからといって、打刻情報を15分単位などで丸めてよいわけではありません。裁量労働制を採用している従業員の健康を守るためにも、適切な方法で勤怠管理をおこないましょう。
関連記事:裁量労働制とは?適用職種や改正のポイントを簡単にわかりやすく解説!
8. 適切な勤怠管理を実施するためのポイント

勤怠管理を正しくおこなわないと、従業員とトラブルを生んだり、労働基準法違反により罰則が課せられたりする恐れがあります。ここでは、適切な勤怠管理を実施するためのポイントについて詳しく紹介します。
8-1. 残業が発生する場合は36協定の締結が必要
法定労働時間を超えた残業や、法定休日の労働が発生する場合、36協定の締結が必要です。36協定を結ばず、時間外労働や休日労働を従業員にさせたら違法になります。ただし、所定労働時間を超える残業のみ発生するのであれば、36協定を締結しなくても問題ありません。一度でも時間外労働や休日労働の発生が予想されるのであれば、あらかじめ36協定を結び、所轄の労働基準監督署に届出をしましょう。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
8-2. 勤怠管理のルールを就業規則に明示する
勤怠のルールを明確にしていない場合、打刻のやり方が従業員によって異なり、正しく勤怠管理や給与計算ができない可能性があります。また、従業員とのトラブルが発生し、業務負担が増える恐れもあります。
たとえば、タイムカードを修正・訂正する場合の書き方などの勤怠ルールを細かく就業規則で定めておくと、従業員は混乱することなく対応できます。このようにトラブルを回避するためにも、事前に勤怠管理のルールを定め、就業規則に記載して従業員に周知しておきましょう。また、時代や法改正にあわせて、定期的にルールを見直すことも大切です。
8-3. 勤怠管理システムを導入する
タイムカードやエクセル・スプレッドシートなどで勤怠管理をおこなっている場合、人的ミスが生じやすく、管理が煩雑になるため、業務負担の課題を感じている人もいるかもしれません。また、企業の規模が大きくなったり、変形労働時間制やフレックスタイム制など従業員の働き方が多様化したりするほど、勤怠管理の負担は大きくなります。
勤怠管理システムを導入すれば、出勤や退勤などの打刻・集計から給与の計算まで自動化して、ワンストップで管理することができます。また、従業員のICカードやスマホを使えば、不正打刻や打刻忘れを防ぎ、勤怠状況をリアルタイムで把握することが可能です。さらに、打刻情報はデータ化して管理できるので、効率よく1分単位の勤怠管理を実現することができます
関連記事:勤怠管理システムとは?特徴や活用メリット、システムをご紹介
9. 勤怠管理は1分単位の計算が原則!15分単位は違法になるので注意

勤怠管理を15分単位でおこなうのは違法です。労働基準法には「全額支払いの原則」が定められており、企業は1分単位での勤怠管理が義務付けられています。また、残業代にも「全額支払いの原則」は適用されるので、残業時間も1分単位で計算し、正確な残業代を支給しましょう。ただし、1ヵ月ごとに残業時間を算出している企業の場合、残業時間の切り捨てが許可されるケースや切り上げが求められるケースもあるため注意してください。
「打刻まるめの労働時間集計ってどうやるの?」「そもそも打刻まるめは問題ない?」という疑問をおもちではありませんか?
当サイトでは、打刻まるめをしている場合の労働時間の計算方法や、正しい残業代の計算方法、打刻まるめが違法となる場合について解説した資料を無料配布しております。
「打刻まるめでの正しい集計方をが知りたい」「自社の打刻運用に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。