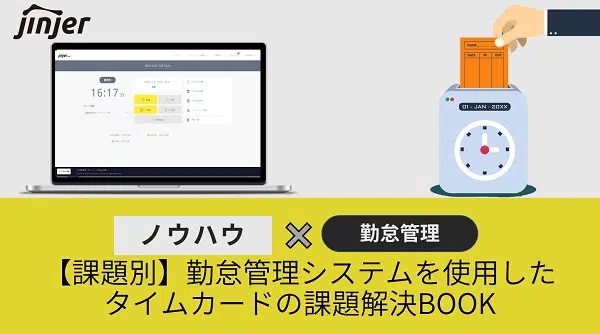従業員の勤怠情報をタイムカードで管理している企業は多いでしょう。
タイムカードであれば、紙の出勤簿に出勤・退勤時間を書くよりも効率的かつ正確に勤務時間を記録することができます。
この記事では、タイムカードの仕組みや使い方、メリット・デメリットを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしている場合、以下のような課題はないでしょうか。
・タイムカードの収集や打刻漏れ、ミスの確認に時間がかかる
・労働時間の集計に時間がかかる/ミスが発生しやすい
・労働時間をリアルタイムで把握できず、月末に集計するまで残業時間がわからない/気づいたら上限を超過していた
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムです。システムであれば工数・ミスを削減して労働時間の集計ができるほか、リアルタイムで労働時間が把握できるため、残業の上限規制など法律に則った管理を実現できます。
勤怠管理システムについて気になる方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. タイムカードとは?仕組みや使い方を解説!

タイムカードとは、従業員の出勤時間や退勤時間を記録する際に使用するカードのことです。
一般的なタイムカードは、1〜15日、16〜31日で打刻する面が分かれているので、タイムレコーダーを通して打刻する際は、日にちと裏表を確認するようにしましょう。
また、タイムカードは労働基準法により5年間保管しておくことが義務付けられていますので、しっかりと管理することが重要です。[注1]
[注1]労働基準法|e-Gov法令検索
関連記事:タイムカードの保存期間は5年!知っておきたいタイムカード保管方法
1-1. タイムカードはいつ押すべき?
タイムカードは基本的に、勤務開始時と勤務終了時に打刻するようにしましょう。労働時間は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを指します。
たとえば、9時の出社に対して10分前に出社したとしても、仕事に関係していないことをしているのであれば、タイムカードは押してはいけません。
仮に、10分前に出社し上司から仕事の依頼をされたときは、業務に取りかかる前にタイムカードを押しておきましょう。
しかし、打刻すべきかどうかを個人で決断するのは難しいため、社内ルールを事前に作っておくことで、従業員全員がどのタイミングでタイムカードを押すべきか明確にすることが重要です。
関連記事:タイムカードを押すタイミングはいつ?タイムカードに関する疑問を徹底解説!
関連記事:タイムカードの打刻ルールは決めるべき?|事例や浸透させるコツも!
1-2. タイムカードの目的
タイムカードは勤怠管理方法のひとつで、その意味や目的は以下の通りです。
- 勤怠情報を正しく把握するため
- 正しい賃金を支払うため
- 長時間労働を防止し、従業員の健康管理をおこなうため
- 年次有給休暇の付与・取得状況などを適正に管理するため
勤怠管理の第一歩は、労働時間を正しく記録することです。タイムカードによる勤怠管理は従業員を守るだけでなく、労働基準法などの法令を守ることにもつながっています。
1-3. タイムカードをはじめとする勤怠管理方法の要件とは?
タイムカードは多くの企業が使用している勤怠管理ツールですが、従業員の勤怠管理は必ずしもタイムカードでおこなう必要はありません。厚生労働省のガイドラインに則していれば、他の方法で勤怠管理をすることも可能です。
労働安全衛生法では、厚生労働省令で定める方法により、使用者が労働者の労働時間の状況を把握することを義務づけています。[注2]
ここでいう「厚生労働省令で定める方法」について、厚生労働省が定めたガイドラインでは、以下の要件を提示しています。[注3]
- 客観的な方法を基礎として確認し、適正に記録できるもの
- 必要に応じて、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録(残業命令書や残業報告書など)とをつき合わせて、確認・記録できること
以上の要件を満たす方法として、当該ガイドラインではタイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録などを挙げています。
つまり、企業はタイムカードをはじめ、上記の要件を満たす方法で従業員の労働時間を把握しなければなりません。
[注3]労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
1-4. タイムカードの設置場所
タイムカードとタイムレコーダーは、職場の出入口や廊下など、わかりやすい場所に設置するのが基本です。目につきにくい場所に設置すると、打刻忘れなどのミスが発生しやすくなります。ただし、あまりに人通りが多い場所に設置すると、打刻をするための行列が通行の妨げになるケースもあるため注意しましょう。
また、実際に作業をする場所の近くに設置することも大切です。作業場所から離れた位置に設置すると、打刻した時間と本来の労働時間に差が生じてしまいます。労働時間を正確に把握するためにも、作業場の近くでわかりやすい場所に設置しましょう。
2. タイムカードの種類

ここでは、さまざまな種類が存在するタイムカードを6つに分類し、それぞれの特徴について解説します。
2-1. 紙に時刻を記録するタイムカード
紙のタイムカードをタイムレコーダーに差し込むことで、タイムカードに時刻を印字するタイプです。ほかのタイプに比べてコストがかからないため、多くの中小企業で利用されています。昔から利用されていて馴染み深く感じている人が多い点も特徴といえるでしょう。
ただし、紙に印字されている記録をもとに集計する必要があるため、勤怠時間の集計に手間がかかるのが難点です。企業規模が大きいほど、紙のタイムカードの集計には大きな手間がかかります。
2-2. 集計機能付きのタイムカード
月の終わりに、実働時間や残業時間を自動的に集計するタイプです。紙に打刻するという基本的な機能は変わりませんが、月ごとの合計が自動算出されるため計算の手間が省けます。計算ミスなどのヒューマンエラーも防げるでしょう。
しかし、タイムレコーダーが対応している計算方法や項目は限られています。特殊な勤務体系で計算が複雑であれば、集計機能とは別に計算しなければなりません。
紙のタイムレコーダーのなかには、クラウドの勤怠管理システムとAPIで連携し、自動で集計をおこなうことができるものもあります。
2-3. USBに接続できるタイムカード
USBを利用して、タイムカードの記録をパソコンへ出力できるタイプです。記録の入力や計算を手作業でする手間が省けるうえに、集計ミスの発生を防げます。集計する件数が多いほど、その効果を発揮するでしょう。
このタイプは高性能ですが、打刻や計算の機能だけを持つものに比べてコストがかかります。そのため、勤怠管理を手作業でおこなっても問題がない少人数の企業の場合は、費用対効果は低くなる可能性があります。
2-4. ICカード対応のタイムカード
紙のタイムカードではなく、ICカードで打刻するタイプです。ICカードをカードリーダーにかざすことでパソコンにデータが送信・記録されます。従業員が持っている交通系のICカードや、セキュリティカードとして利用しているICカードを、紙のタイムカードの代わりに活用することが可能です。
このタイプのデメリットはコストの高さです。従業員がICカードを持っておらず、打刻用のICカードを新たに用意する場合は、各従業員に発行する必要があるため、新しい従業員が入るたびにカードを作成する費用がかかります。
また、タイムレコーダー本体も、ほかのタイプと比較すると高額です。コストが気になるのであれば、ほかのタイプを利用することも検討したほうがよいでしょう。
2-5. QRコードを使用するタイプ
従業員ごとに識別できるQRコードを発行して、スマートフォンやタブレットなどの端末で読み取ることで打刻するタイプです。QRコードは個別に管理するため、不正打刻を防止することができます。また、QRコードの記載されている紙を紛失した場合でも、簡単に再発行することが可能です。
ただし、従業員がスマートフォンやタブレットなどのITツールの操作に慣れていない場合、打刻の仕組みを理解したり、実際に運用をおこなったりするのに時間がかかる恐れがあります。
2-6. 生体認証を活用したタイプ
指紋や顔といった生体情報を使って認証をおこない、打刻するタイプです。紙のタイムカードでは紛失や不正打刻のリスクがありますが、生体認証を活用したタイプでは、これらのリスクを防止することが可能です。
ただし、指を怪我していたり、システムの反応が悪かったりすると、打刻に時間がかかる可能性もあります。また、他のタイプと比較すると、生体認証に対応したタイムレコーダーなどの機器を導入するために大きなコストがかかります。
3. タイムカードの集計方法とは

タイムカードの集計方法はさまざまです。
この章では、タイムカードの3つの集計方法について解説します。
関連記事:効率的なタイムカードの集計方法とは|人事・経理から個人管理まで
3-1. 電卓による手作業
タイムカードの集計は電卓を使用して手作業でおこなうことにより、高度なシステムを導入する費用を節約することができます。
しかし、集計に膨大な時間がかかり、計算ミスをする恐れもあるので、第三者による確認工数が必要となる可能性があります。逆に人件費がかさむ可能性もあるため、注意が必要です。
3-2. エクセルのテンプレートや関数の活用
タイムカード集計の際、エクセルのテンプレートや関数を活用すると、費用を抑えられるだけでなく、電卓よりも計算を効率的に進めることができます。
ただし、従業員が増加してくることによって、テンプレートや関数が複雑になるので注意しましょう。
関連記事:タイムカードの情報をエクセルで計算する方法|メリットや注意点も
3-3. 勤怠集計サイトの利用
勤怠集計サイトでは、従業員の「出社時間」「休憩時間」「退社時間」を入力するだけで、各従業員の勤務時間などを計算することができます。
勤怠集計サイトは無料で利用できますが、広告が掲載されているため、効率よく業務を進めたい場合は気を付けましょう。
スムーズな勤怠集計には、クラウドシステムの導入も有効です。人事や経理の担当者が、従業員の勤務状況をリアルタイムで確認できるため、違法な長時間労働を気づかないうちにおこなわせてしまうリスクを回避できます。
また、従業員各自がスマートフォンのアプリから打刻をおこなえるシステムもあり、双方にとって利便性が高いといえるでしょう。
関連記事:クラウド型タイムカードとは|無料から使える打刻システムをご紹介
関連記事:アプリ対応の勤怠管理システム8選|タイムカードに代わる勤怠管理手法の導入メリットとは
4. タイムカードのメリット

タイムカードには大きく4つのメリットがあります。
ここでは、それらのメリットについて紹介します。
4-1. 費用を抑えることができる
タイムカードによる勤怠管理にかかる費用は、「カード代」と「タイムレコーダーの購入費」だけです。システムなどを導入した際は、初期コストや運用費が莫大にかかりますが、タイムカードだと、そのような心配はありません。
また、紙のカードではなく、ICカードを使って打刻できるシステムもあります。ICカードを用いる打刻機には、各自の交通系ICカードを使った勤怠管理に対応しているものがあります。そのようなシステムを選定した場合には、カードの導入費用をかけずに、打刻のデバイスのみの費用で勤怠管理をおこなうことも可能です。
関連記事:タイムカードとICカードの違い|ICカードのメリット・デメリットも
4-2. 1分単位で記録できる
労働基準法における賃金全額払いの原則に則って、労働時間は1分単位で記録する必要があります。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
タイムカードは1分単位で労働時間を記録することが可能です。そのため、タイムカードでの勤怠管理は法律に違反することなく、従業員の細かい勤務時間を把握することができます。
4-3. 誰でも使いやすい
タイムカードは、カードをタイムレコーダーに差し込むだけなので、あまりシステムに詳しくない従業員でも簡単に利用することができます。
また、新しく入ってきた従業員に関しても、タイムカードを利用したことがある人が大半であるため、教育コストを削減できるでしょう。
4-4. 運用しやすい
運用しやすいこともタイムカードによる勤怠管理のメリットです。集計の手間はかかるものの、特別なスキルは必要ありません。
タイムカードに印字された時刻を見ながら労働時間を計算すればよいため、ITシステムが苦手な担当者でも無理なく作業できるでしょう。
5. タイムカードのデメリット
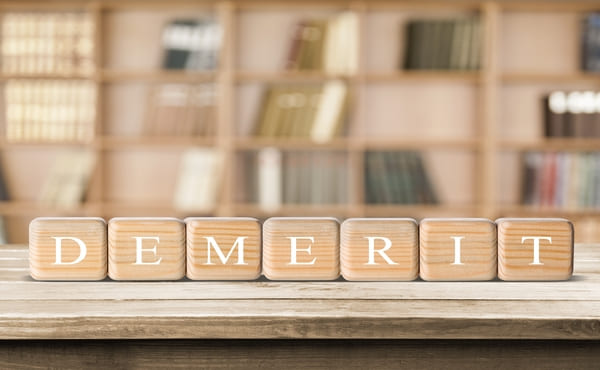
一方、タイムカードにはデメリットも存在しています。
メリットとデメリットを両方理解したうえで、自社の勤怠管理に適しているか判断するようにしましょう。
関連記事:タイムカード打刻のメリットより時代はペーパーレスの勤怠管理システム
5-1. 集計に時間がかかる
紙のタイムカードで勤怠管理をする場合、手作業で計算やデータ入力などをおこなうため、時間がかかります。全従業員分のデータをパソコンに移して計算するとなると、かなりの作業量になるでしょう。
また、続けて印字されている時刻は見間違いを起こしやすく、計算を間違えた場合は修正作業も必要です。タイムカードの集計に時間がかかれば、月末や締日前に残業が増えてしまう可能性が高く、人件費にも影響が出るでしょう。
5-2. 拠点が多いと郵送に手間がかかる
支社や支店など複数の拠点がある場合、最終的には本社にタイムカードを郵送するため手間がかかります。郵送には費用や時間もかかるため、大きなコストとなりかねません。
本社で勤務時間の集計をするには、ほかの拠点からタイムカードが届くのを待つことになります。もし郵送漏れなどのトラブルがあったときは対処に時間がかかり、給与計算が滞る原因となるでしょう。
5-3. 法律に合わせた運用に対応できない場合がある
「働き方改革関連法」が2019年より順次施行されたことで、企業には従業員の残業時間や年次有給休暇日数などをきちんと把握できる体制を構築することが求められています。[注4]
タイムカードを使った勤怠管理では、集計タイミングが基本的に月に1度なので、リアルタイムに残業時間や取得した有給休暇日数を管理するのが難しいです。そのため、月の途中で残業時間が上限を超えてしまっても気づけないことも多いでしょう。このように、タイムカードを使用する場合、法律に合わせた運用に対応できないケースがあります。
5-4. 第三者による不正打刻の可能性がある
タイムカードは従業員全員がわかる場所に設置されているという性質上、他の従業員が遅刻をしそうになったときに、誰かが代わりに打刻することも可能です。
また、誰がどれだけ働いているかなどを役職にかかわらず確認できてしまうので、従業員のプライバシー保護の観点ではあまり良い状態ではないといえます。
さらに、打刻は客観的な記録でなければならないとされています。出勤簿など、従業員が手書きで出退勤を申告する方法は客観性を保つことが難しく、不正にもつながるため注意が必要です。
関連記事:タイムカードの改ざんは違法!不正打刻や改ざんを防ぐ方法をご紹介
5-5. タイムレコーダーの設置場所を作らなければならない
タイムレコーダーを設置するためには、ある程度スペースを確保しておく必要があります。
また、タイムレコーダーは、故障していないか定期的にメンテナンスする必要もあるため、業務効率が落ちる可能性があります。
関連記事:タイムレコーダーの特徴・金額の比較まとめ|勤怠管理もIT化へ
5-6. 打刻漏れや記入ミスが起こる可能性もある
タイムカードの打刻は、出勤時に従業員が各自でおこないます。従業員の出勤が重なり、タイムレコーダーが混雑していると後回しにしまったり、単純に忘れていたりといった理由から打刻漏れが発生する可能性があります。
また、カードの差し込み位置が悪く、印字がずれたり、かすんだりしてしまうと正確な打刻時間がわかりません。記入ミスが発生していると、月末に担当者が集計する際に各従業員への確認作業が必要になり、給与計算がスムーズにおこなえない場合もあります。
関連記事:タイムカード押し忘れを減らす4つの対策|システム導入のメリット
関連記事:タイムカードの打刻ミスがあった場合の対処法|打刻漏れを防ぐ方法についても紹介!
6. タイムカード選びのポイント

ここでは、購入する前に知っておきたい、タイムカードおよびタイムレコーダーを選ぶポイントについて詳しく紹介します。
6-1. 自社の規模に合っているか
タイムカードが自社の規模に合っているかは、必ず確認したいポイントです。
従業員数が多いのに手作業が必要なタイムレコーダーを利用すると、管理者の負担が大きくなります。また、タイムカードを押すための台数が少ないと、打刻に時間がかかって打刻が形骸化する可能性もあります。
従業員の数を踏まえたうえで、いずれのタイプが自社にふさわしいのか、何台のタイムレコーダーが必要なのかを検討しましょう。
6-2. 使いやすいか
タイムカードの使いやすさは意外と重要です。タイムカードは毎日利用するものなので、打刻するたびにストレスがあると業務効率の低下にもつながってしまいます。タイムカードがレコーダーに差し込みやすいか、壁に取り付けることができるか、時刻が見やすいか、といった使いやすさを確認しましょう。
また、毎日利用する従業員からの視点だけでなく、集計をおこなう担当者から見た使いやすさも気に留めておいてください。
6-3. 必要な機能が搭載されているか
タイムカードを導入する際には、あらかじめ必要な機能を把握しておき、その機能が利用できるかどうかチェックしておきましょう。たとえば、休憩時間を複数回に分けて取っているなどの特殊な勤務形態をしている企業であれば、その形態に対応しているか必ず確認してください。
必要な機能が足りていない場合はタイムカードを買い直すか、対応していない部分を手作業で対応しなければなりません。どちらにしても無駄が生じるので、事前にチェックしてマイナスを避けましょう。
6-4. サポートは充実しているか
タイムカードで勤怠管理を実施するには、打刻機が必要です。停電や回線にトラブルが生じて、タイムレコーダーが故障してしまうケースもあるかもしれません。
まずは、トラブル時の対処方法をきちんと確認しておくことが大切です。また、ベンダーのサポート体制についても必ずチェックしておきましょう。24時間対応であったり、電話やチャットなど複数の問い合わせ方法に対応していたりするベンダーであれば、故障時も安心して対応することができます。
7. タイムカードの打刻ルール ~手書き・押し忘れ・ずれの対処法~

従業員にとっても管理者にとっても、タイムカードは手軽な勤怠管理方法ですが、タイムカードでの勤怠管理をおこなう際には下記のポイントに留意しておきましょう。
7-1. タイムカードは手書きではダメ?
タイムカードに手書きで記入しても違法ではありません。ただし、厚生労働省のガイドラインにある「客観的な記録」には該当しません。
手書きによるタイムカードは自己申告制に該当し、外回りの営業のように客観的な記録が難しい従業員に限り認められています。また、手書きによる申告は改ざんなどのリスクが高まるため、申告した勤務時間に誤りがないか上長が細かくチェックするなどの対応が必要です。
手書きのタイムカードで勤怠管理をおこなっている場合は、デジタル打刻のように客観性の高い管理方法の導入を検討しましょう。
関連記事:手書きのタイムカードを使うメリットや注意点を徹底解説
7-2. 休憩時間は打刻すべき?
休憩時間については、無理に打刻する必要はありません。従業員ごとの休憩時間は基本的に決められているため、始業時刻と終業時刻さえ把握できれば、休憩時間を差し引くことで労働時間を算出できます。
ただし、休憩をしっかりと取れているか確認したい場合や、長すぎる休憩を取っていないかチェックしたい場合などは、打刻するよう従業員へ指示するとよいでしょう。
7-3. タイムカードを押し忘れた場合の対処方法
タイムカードの押し忘れがあった場合はそのまま放置せず、すぐに対処します。対処の手順は以下の通りです。
- 該当従業員に、押し忘れのあった箇所の出勤・退勤時刻などを確認する
- 該当従業員の上長に報告し、従業員の申告した時刻で間違いないか確認する
- タイムカードを修正する
タイムカードの押し忘れがあった際に重要なのは、従業員が自ら修正できる仕組みを作らないことです。上長に報告・確認することで客観性が保たれ、正しい勤怠管理につながります。
なお、タイムカードを押し忘れたからといって欠勤・遅刻扱いにしたり、無給や罰金などのペナルティを科したりすることは原則違法です。タイムカードの押し忘れを理由に、勤務実績を無効することはできません。
タイムカードの押し忘れは修正などに手間がかかり、給与計算においてもミスが出やすくなります。打刻機の配置を見直したり、従業員に打刻の徹底を周知したりして、押し忘れが起こりにくい環境作りに努めましょう。
関連記事:タイムカードを押し忘れると?押し忘れの理由や対策を詳しく解説
7-4. タイムカードの時間がずれた場合の直し方
タイムカードの時間にずれが生じる原因は2つあります。1つは打刻機の不具合によるもの、もう1つは打刻のやり方によるものです。
打刻機の不具合が原因の場合は取扱説明書を見たり、メーカーに問い合わせたりすることで問題を解消できるでしょう。また、打刻機の時刻と職場内の時計の時刻がずれていると、打刻ミスが起こりやすくなります。打刻機の時刻と職場内の時計が一致しているか定期的に確認することも大切です。
一方、打刻のやり方が原因で時間のずれが生じるケースもあります。たとえば、打刻機の出勤・退勤のボタンを押し間違え、出勤時間の上に退勤時間が印字される二重打刻や、打刻が終わる前にタイムカードを引き抜いたことで印字がずれるケースなどがあります。
タイムカードの時間がずれた場合の直し方は以下の通りです。
- 時間がずれた箇所を確認し、正しい打刻時間が見えるかチェックする
- 正しい時刻が確認できない場合は、該当従業員に正しい打刻時間を確認する
- 該当従業員の上長に報告し、従業員の申告した時刻で間違いないか確認する
- タイムカードを手書きで修正する
タイムカードの時間にずれが生じると、確認や修正に手間がかかります。日頃注意していても完全に防げるミスではないので、タイムカード以外の勤怠管理方法を検討する必要があるかもしれません。
8. タイムカードの15分・30分など数分単位の切り捨ては違法?

原則として、労働時間は1分単位で計算することが義務付けられています。
労働時間を15分・30分など数分単位で切り捨てることは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反することになります。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
そのため、自社で定めているタイムカードのルールのなかに、15分・30分など、数分単位の労働時間を切り捨てるよう定めている場合は、今すぐタイムカードのルールを見直すようにしましょう。
関連記事:タイムカードの計算を15分単位で切り上げるのは違法?勤怠管理の注意点を解説!
8-1. 時間ぴったりの打刻は遅刻・早退になる?
始業・終業時間ぴったりにタイムカードを打刻しても、遅刻・早退にはなりません。ただし、業務の性質上、タイムカードの打刻直後に仕事を始めるのが難しい場合などは遅刻と見なすこともあるでしょう。
たとえば、製造業のようにタイムカードを打刻したあとに作業着に着替える必要がある場合や、打刻機と就業場所が離れているため移動時間がかかる場合などは、時間ぴったりに打刻しても遅刻扱いになる可能性があります。
始業・終業の取り扱いについては企業の判断に委ねられます。時間ぴったりの打刻が遅刻・早退になる場合は労使間で取り決めをおこない、就業規則に記載するなど特別な対応が必要です。
9. タイムカードを利用するときの注意点

タイムカードによる勤怠管理においては、以下のような点に注意しなければなりません。
9-1. 打刻漏れを防止する仕組みをつくる
打刻漏れは、タイムカードによる勤怠管理において発生しがちなミスのひとつです。打刻漏れや打刻忘れが頻発していると、集計時に確認する手間が増え、担当者の負担が大きくなってしまいます。正しい労働時間を把握できない可能性もあるため、打刻漏れを防止する仕組みをつくることが大切です。
具体的には、打刻したかどうかを従業員同士で確認する、ポスターを貼って打刻忘れに対する注意を促す、タイムレコーダーをわかりやすい位置に設置するなどの対策を検討するとよいでしょう。
9-2. 集計作業を効率化する
タイムカードの集計にはかなりの時間がかかるため、作業を効率化することが重要です。とくに紙のタイムカードの場合は、手作業で集計したりエクセルに転記したりする必要があるため、担当者がストレスを感じることも多いでしょう。
集計作業を効率化するためには、打刻データが自動的にパソコンへ転送されるシステムへ移行することなどがおすすめです。また、従業員数が多くなるとタイムカードによる勤怠管理が難しくなるため、勤怠管理システムを導入することも検討しましょう。
9-3. 不正打刻を防止する
タイムカードによる勤怠管理をおこなう場合は、不正打刻にも注意しなければなりません。たとえば退勤時刻にあえて打刻せず、あとで手書きで時刻を記入し、残業代を水増し請求するケースなどが考えられます。また、遅刻しそうなときに代理で打刻してもらう従業員もいるかもしれません。
このような不正打刻を防止するためには、生体認証による打刻方法を採用したり、手書きで修正するときのルールを設定したりすることが重要です。
10. タイムカードの代わりに導入が進む勤怠管理システム

リモートワークやフレックスタイム制など多様な働き方が進む現代において、タイムカードの代わりに勤怠管理システムを導入する企業が増えてきました。勤怠管理システムには、出退勤の記録や残業・休暇の管理、シフト作成などの機能が備わっています。
10-1. 勤怠管理システムの種類
勤怠管理システムには以下のような種類があります。
- クラウド型:オンライン上でシステムにログインして利用する
- オンプレミス型:社内にサーバーを設置してシステムを構築する
クラウド型の勤怠管理システムであれば、法改正時に自動的にアップデートされるため、自社で設定を変更する必要などはありません。また、パソコンやスマートフォンなどから打刻できるため、リモートワークや直行直帰にも対応できます。
一方のオンプレミス型は、社内で独自のシステムを構築するため、自由にカスタマイズすることが可能です。ただし、システム構築やメンテナンスに多額の費用がかかるため注意しましょう。
10-2. 勤怠管理システムのメリット
勤怠管理システムには、さまざまな機能が搭載されているため、勤怠管理に関する業務を大幅に効率化できます。従業員ごとの労働時間は自動的に集計されるため、タイムカードのように手作業で集計する必要はありません。
また、労働時間をリアルタイムで確認でき、法律による上限を超過しそうなときにアラートで知らせてくれるシステムもあるため、知らないうちに法律違反をしてしまうリスクを回避できるでしょう。
10-3. 勤怠管理システムのデメリット
勤怠管理システムを導入するまでには、ある程度の時間がかかります。まずは、どのシステムを導入するかを決定し、運用ルールを設定しなければなりません。また、導入費用やランニングコストも発生するため、予算に合っているか事前に確認しておきましょう。
関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介
11. タイムカードの選び方は会社の規模によって異なる|自社に合ったタイムカードを見つけよう

今回は、タイムカードの種類やメリット・デメリット、運用上の注意点などを解説しました。タイムカードの機能は「出退勤の記録のみ」や「労働時間の集計までできる」などさまざまです。そのため、自社の規模に合わせたタイムカードを利用するようにしてください。
また、タイムカードには従業員の個人情報も記載されるため、セキュリティー面にも気を付けましょう。タイムカードの勤怠管理に不安がある場合は、サポート体制が充実している会社から提供されているタイムカードを利用することをおすすめします。
関連記事:タイムカードがない職場は違法?知っておきたいタイムカードの必要性
タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしている場合、以下のような課題はないでしょうか。
・タイムカードの収集や打刻漏れ、ミスの確認に時間がかかる
・労働時間の集計に時間がかかる/ミスが発生しやすい
・労働時間をリアルタイムで把握できず、月末に集計するまで残業時間がわからない/気づいたら上限を超過していた
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムです。システムであれば工数・ミスを削減して労働時間の集計ができるほか、リアルタイムで労働時間が把握できるため、残業の上限規制など法律に則った管理を実現できます。
勤怠管理システムについて気になる方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。