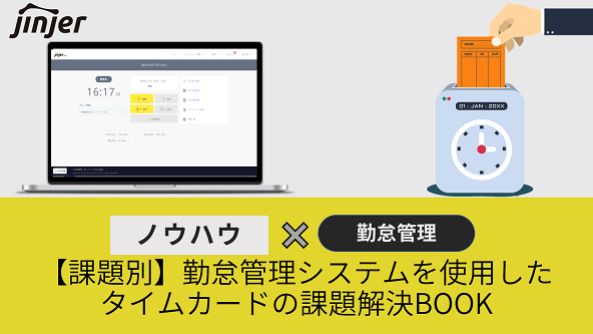こんにちは。社労士の小西広宣です。
今回はタイムカードの保管の重要性についてご紹介します。
タイムカードには保管期間が法律で定められており、違反すると処罰される可能性もあるため、正確に把握しておきましょう。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1.タイムカードの保管期間は原則5年!

労働基準法では、使用者(会社)に書類の保管義務を設けています。そのうち、労働時間を管理するための記録(タイムカード等)については、記録が完結してから5年間の保管義務があります。
ちなみに、2020年3月31日までタイムカードの保管期間は3年間でしたが、2020年4月1日の法改正により、5年間に変更になりました。
現在は法改正の経過措置として3年間の保存でも問題ないとされていますが、今後は先のことも見据えて5年間タイムカードを保管しておくと安心です。
また、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねる場合は7年間の保管が必要です。
この保管義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
※参考:労働基準法についてはこちらも! ▶︎労働基準法をもっと詳しく!勤怠管理に関する法的ポイントを解説
2.タイムカード保管の起算日はいつから

タイムカードの保管期間を正確に知るには、タイムカードを保管する起算日を把握する必要があります。
起算日について簡単に説明すると、期間を数え始める1日目を意味します。
従来まで、タイムカード保管の起算日は「最後の出勤日」など非常にあいまいなものでしたが、令和5年4月1日からは、タイムカード保管の起算日が明確になります。
改正労働基準法施行規則(令和5年4月1日施行)
第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
2 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
具体例として、令和2年4月1日〜30日までの1ヶ月分の記録について、給与の支払いが5月31日であれば、会社側は令和2年6月1日から令和7年5月31日までの5年間は保管する義務があります。
3.タイムカード保管の重要性

タイムカードを少なくとも法定期間内は保管しておくのは、会社自身を守るためにも重要です。
未払い残業代のトラブルが起きた時、保管しておいたタイムカードは、残業時間を算定するための重要な記録となります。実際、裁判でも保管しておくべき期間内のタイムカードを会社側が提示できなかったため、会社が敗訴したケースもあります。
スタジオツインク事件という裁判(東京地裁 平成23年10月25日判決)では、会社側が法定保管期間内のタイムカードを破棄していたため、労働者側が自ら記録していた勤務時間の記録を覆すだけの証拠を出すことができず、この部分については会社が敗訴しています。
このような例もあるため、法定保管期間内のタイムカードは、保管をしていつでも提示できるような状態にしておくことが大切です。
働き方改革という言葉が多く聴かれるようになり、タイムカードに限らず、法的リスクを回避することが一層重要な世の中になりました。
「無意識に労働基準法に反していることはないか」と不安を感じる方は、以下の資料で労働基準法について網羅的にわかりやすく解説しているのでぜひご活用ください。
【無料DL:『労働基準法改正』についてもっと詳しく】 ▶︎労働基準法総まとめBOOK|法改正から基本的な内容まで分かりやすく解説!
4.有効なタイムカードの保管方法

タイムカードといっても、物理的に打刻しているケースや、Webによる打刻、PCのログイン、ログアウトの時刻を勤務時間とするケースなどいろいろあると思います。
Webによる打刻や、PCのログイン、ログアウトの時刻を使う場合は、その記録をいつでも印刷しておける状態にしておけば大丈夫でしょう。
物理的に打刻しているケースでは、紙のカードが溜まってしまいますが、段ボールに入れて保管する、また可能であればスキャンなどでデータ化して保管するのも手です。
なお、紙のものを保管するときは、いつのタイムカードかがすぐにわかるようにしておくことが大切です。段ボールに入れて保管するのであれば、同じ期間のものをまとめて、段ボールの外側にいつのものかを書いておくべきですし、データ化する場合も、フォルダやファイル名でいつのものかが一目でわかるようにしておくことが求められます。
これは、労働時間の記録の提示を求められた際、スムーズに提示できるようにするためです。
データで勤怠情報を保存しておく場合は、シフト管理や給与計算、残業管理なども一括で効率化できる「勤怠管理システム」の導入も有効でしょう。
タイムカードで勤怠管理をすることとシステムを導入することの違いは、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
※参考:5分でわかる勤怠管理システムの全て!タイムカードとの違いを徹底解説!
5.アルバイト・派遣社員に対してもタイムカードの保管が必要?

結論、アルバイト・派遣社員など雇用形態を問わず、タイムカードは5年間保管する義務があります。
また、裁量労働制や管理監督者として働いている方に関しても保管の要件があります。
裁量労働制の方に関してはタイムカードの保管をする必要性があると厚生労働省が発表しています。
管理監督者ですが、管理監督者であっても勤怠管理の必要性はあるため、勤怠情報をタイムカードや出勤簿で管理しているのであれば、労働基準法第109条に則り保管しておくのが無難です。
6.会社自身を守るためにも

現在は、未払い残業代について労働者の権利意識も高まっています。退職した社員から未払い残業代を請求された際、感情的になって払いたくないという場合もあると思います。
しかし、一円も払いたくないと考えて法定保管期間内のタイムカードを破棄してしまうと、法律違反となるだけでなく、労働者側が自分でつけた記録に対して反証することができなくなるため、かえって会社にとって不利な結果となってしまいます。
現在「働き方改革」で残業についても規制を強化する方向で進んでいますので、最低限タイムカードを法定期間内は保管しておくようにしておきたいですね。
また、管理体制の整備にお悩みの方は、従業員の勤怠データをデータで保存しておける勤怠管理システムの導入も考えてみてはいかがでしょうか。
以下で国内ほぼ全ての勤怠管理システムについて解説していますので、具体的な機能や価格などを一度見てみることをおすすめします。
※参考:国内ほぼ全ての勤怠管理システムを網羅!料金・機能・メリット徹底比較|2022年最新版
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。