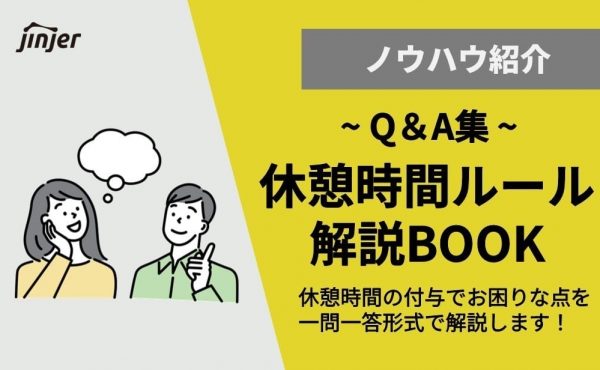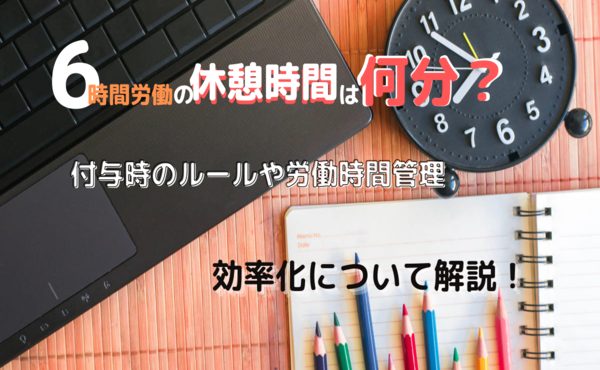 6時間勤務、8時間勤務などのように、労働時間に応じて付与すべき休憩時間は変わってきます。労働者に休憩時間を適切に付与することは、労働基準法に違反するリスクをなくすだけでなく、従業員の心身の健康を守ることにもつながります。本記事では、休憩時間が発生する基準や付与する際のルールについてわかりやすく解説します。
6時間勤務、8時間勤務などのように、労働時間に応じて付与すべき休憩時間は変わってきます。労働者に休憩時間を適切に付与することは、労働基準法に違反するリスクをなくすだけでなく、従業員の心身の健康を守ることにもつながります。本記事では、休憩時間が発生する基準や付与する際のルールについてわかりやすく解説します。
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の付与や管理について、よくある質問を一問一答形式で解説した無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」「確実に休憩を取らせたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 6時間勤務の休憩時間は必要?

勤務時間は会社によって異なります。ただし、一定以上の労働時間が生じる場合は、労働者に休憩を正しく付与しなければなりません。ここでは、6時間勤務の休憩時間は必要かどうかを労働基準法に基づきわかりやすく解説します。
1-1. 労働基準法に基づく休憩時間とは?
休憩時間とは、労働基準法第34条に定義されており、従業員が休息を取るため完全に業務から解放されることが保障された時間のことです。法律で定義されているため、労働者を雇用する企業は必ず遵守しなくてはなりません。
1-2. 労働時間と勤務時間の違い
休憩時間は労働時間が一定を超える場合に付与しなければなりません。労働時間とは、雇用主の指揮命令下で従業員が会社のために労働する時間を指します。労働基準法第32条「労働時間」の定義があるように、労働時間は休憩時間を除いて計算します。一方、勤務時間とは、一般的に就業規則や雇用契約書などに定められている始業時刻から終業時刻までの時間のことです。そのため、休憩時間があれば勤務時間に含めて考えます。このように、労働時間と勤務時間は似た意味を持ちますが、休憩時間を含むかどうかで違いがあるので正しく押さえておきましょう。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
1-3. 労働時間が6時間以内であれば休憩は不要
休憩時間の付与義務は1日の労働時間が6時間を超えてから発生します。そのため、労働時間が6時間以内であれば休憩時間を与えなくても問題ありません。
1-4. 労働時間が6時間超え8時間以内の場合は休憩45分が必要
労働基準法第32条により、1日の労働時間が6時間を超え8時間以内の場合、少なくとも45分の休憩時間を従業員に付与しなければなりません。最低でも45分なので、6時間半勤務の従業員に1時間の休憩時間を付与していても問題ありません。
1-5. 労働時間が8時間超えの場合は休憩1時間が必要
労働基準法第32条に基づき、1日の労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を労働者に与えなければなりません。労働基準法で定められているのは「8時間超えの場合」までなので、それ以降の労働時間に対する休憩時間の付与は義務付けられていません。そのため、たとえば10時間勤務や12時間勤務の従業員がいたとしても、1時間の休憩時間を与えていれば、法的に問題ないことになります。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:労働基準法第34条一部抜粋|e-Gov
2. 休憩時間に関する原則

休憩時間には細かい決まりがあります。ここでは、休憩時間を従業員に付与する際の原則について詳しく解説します。
2-1. 労働時間の途中に与える
労働基準法第34条により、休憩は労働時間の途中に与える必要があります。始業して最初の1時間や終業前の1時間に休憩を与えてはいけません。中には「早く帰りたいので休憩は不要」と考える従業員がいるかもしれません。しかし、労働時間の途中に与えなければ労働基準法違反となるため注意しましょう。
第三十四条 使用者は(省略)休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
2-2. 労働からの完全な解放
労働基準法第34条により、休憩時間中は労働から完全に解放させなければなりません。休憩時間とは、従業員が労働を中断し、自由に休息してもよい時間のことです。そのため、休憩時間中にもかかわらず、電話対応をさせるなど、休憩時間中に生じる半強制的な業務は労働基準法違反となるので注意が必要です。
(省略)休憩時間を自由に利用させなければならない
2-3. 休憩時間は分割してもよい
休憩時間は、分割して付与しても問題ありません。業種や業界によっては、休憩時間をまとめて取れないケースもあります。そのような場合、休憩時間を分割して付与することができます。たとえば、1時間の休憩が必要な場合に「30分×2回」という形で付与しても違反ではありません。ただし、あまりにも細かく休憩を分割して付与すると、「自由に休息を取る時間」とはいえず、労働基準法違反になる可能性があるので気を付けましょう。
2-4. 休憩は一斉に取らせなければならない
労働基準法第34条により、休憩は従業員に一斉に取らせなければなりません。ただし、あらかじめ労使協定を締結することで、一斉付与の原則を適用外とすることもできます。その場合、労働基準法施行規則第15条に基づき、労働者の範囲と休憩の与え方について協定する必要があります。なお、労働基準法施行規則第31条により、下記に該当する業界においては労使協定を結ばなくとも、一斉付与の原則を適用外とすることが可能です。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署
(省略)休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない(省略)
第十五条 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
第三十一条 法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
このように、休憩に関するルールは細かくあり、パートやアルバイトの従業員が多い企業など個別で休憩時間の管理が必要な企業では、休憩時間の管理も複雑になる場合があります。当サイトでは、法対応した正しい休憩時間の取らせ方について解説した資料を無料でお配りしています。よくある休憩時間の疑問についても解説しているので、自社の休憩の取らせ方に問題がないか確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
3. 勤務時間ごとの休憩時間の考え方

休憩時間は労働時間が6時間を超えて初めて付与されます。ここでは、勤務時間に応じて具体的にどのぐらい休憩時間を付与すればよいのか解説します。
3-1. 勤務時間5時間の場合
パート・アルバイトで働く人や派遣社員として労働している人などは、勤務時間を5時間と設定して働いている人も少なくないでしょう。休憩時間は労働時間が6時間を超える場合に付与義務が発生します。そのため、残業の可能性がほとんどない場合は、休憩時間を付与しなくても問題ありません。ただし、突発的な残業が必要になり、6時間勤務を超えて働く労働者が発生した場合、休憩時間を正しく付与させるよう、現場の責任者に周知しておきましょう。
3-2. 勤務時間6時間ちょうどの場合
勤務時間6時間ちょうどの場合、原則として休憩時間は付与しなくても問題ありません。ただし、労働時間が6時間1分になってしまった段階で、少なくとも45分の休憩を付与する義務が発生します。
たとえば、始業時刻が15時、終業時刻が21時の6時間勤務の労働者を考えてみましょう。21時ぴったりに仕事が終われば、休憩時間を付与しなくても問題ありません。しかし、21時に15分の残業が必要だと判断された場合、労働時間の途中に休憩を挟まなければならないので、21時から45分の休憩時間を取らせて、21時45分から15分の労働をさせ、22時に退勤させることになります。
このように、6時間勤務ちょうどに設定している場合、少しでも残業の可能性があれば、休憩時間の管理が煩雑になる恐れがあります。休憩時間の管理の煩雑さを回避するため、あらかじめ5時間半勤務に設定して休憩時間を付与しないことにしたり、6時間勤務ぴったりでも休憩時間45分の付与を原則にしたりするのも一つの手です。
3-3. 勤務時間8時間ちょうどの場合
休憩時間を除く勤務時間が8時間ちょうどの場合、休憩時間は45分付与すれば法律的に問題ありません。ただし、労働時間が8時間1分になった時点で、休憩時間を1時間付与しなければならない義務が生じます。45分と1時間に分けて休憩時間を管理すると、業務負担が増えるだけでなく、人的ミスなどにより意図せず労働基準法に違反する恐れもあります。
そのため、8時間ぴったりの労働を採用している場合でも、あらかじめ1時間の休憩時間を付与しておくこと望ましいです。なお、休憩時間は分割して付与できるので、まとまって1時間の休憩を確保するのが難しい場合、「15分×4回」「30分×2回」のように、分割して付与させる方法もあります。
3-4. 勤務時間10時間の場合
10時間勤務の場合、1時間の休憩時間を付与させることが原則です。なお、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の観点からも、連続した労働時間が8時間を超えないタイミングで休憩を取得させるのが望ましいです。また、10時間勤務の場合、法定労働時間をオーバーしているため、事前に36協定を締結が必要になることも押さえておきましょう。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
3-5. 勤務時間15時間の場合
8時間勤務した後に1時間休憩して6時間勤務させた場合、勤務時間が15時間になります。このような場合、追加で休憩時間が必要になるか判断に迷われる人もいるかもしれません。労働基準法上、労働時間は1日単位で考えるため、法律的には15時間勤務の場合も1時間の休憩を付与していれば問題ありません。
ただし、1日15時間の勤務となると、労働者に大きな負担がかかります。まずは労働時間を削減できないか対策を検討することが大切です。それでも15時間労働が生じる場合、1時間の休憩だけでなく、従業員の好きなタイミングに追加で休憩時間を取得できるような仕組みを構築しましょう。これにより、集中力の低下を防止し、長時間労働の削減にもつながります。
関連記事:1日の労働時間の基準や上限とは? 36協定や休憩時間のルールとあわせてご紹介!
4. 休憩時間に関する注意点

休憩時間には、時間数だけでなく、他にもさまざまな注意点があります。ここでは、休憩時間に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. 着替え時間や手待ち時間も労働時間に含まれる
労働者に付与すべき休憩時間は、労働時間に応じて変わってきます。休憩時間を適切に付与するには、労働時間の定義を正しく理解することが大切です。労働時間とは「使用者の指揮命令下で働く時間」を指します。そのため、業務に必要な着替え時間や手待ち時間も労働時間に含まれます。それ以外に、次のような直接業務をおこなっていなくとも、労働時間とみなされるケースがあります。
- 朝礼・終礼の時間
- 準備・後片付け
- 研修時間
- 昼休み中の電話対応
これらに該当しなくとも、使用者の指揮命令下に置かれている時間は、労働時間に含まれます。一方、自己啓発のための研修時間や、強制参加ではない朝のラジオ体操の時間は、労働時間に含まれません。このように、労働時間の定義を正しく把握したうえで、適切な休憩時間を付与することが重要です。
関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!
4-2. 休憩時間の付与義務の対象にならない人もいる
休憩時間の付与は原則として、雇用形態に関係なく、すべての従業員が対象になります。しかし、労働基準法第41条により、休憩時間の付与対象とならない人もいます。たとえば、管理監督者は休憩時間の規定の適用から除外されます。また、労働基準法施行規則第32条には、休憩時間を付与しなくもよい業種が明記されています。自社がそれらの業種に該当するかどうか一度チェックしてみることが大切です。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
関連記事:管理監督者の労働時間は上限なし?法律の適用範囲や労働時間の把握方法を解説
4-3. 休憩時間のルールは就業規則に明記する
労働基準法第89条により、労働者数10人以上の企業は就業規則の作成および届出の義務があります。就業規則には、休憩時間の内容も含めなければなりません。そのため、「何時間の休憩を付与するのか」「休憩時間の付与タイミングをどうするのか」など、具体的な休憩時間のルールを定め、就業規則に明記することが大切です。また、休憩時間のルールを就業規則に記載したら、従業員にきちんと周知するようにしましょう。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(省略)
5. 休憩時間を適切に付与しないと労働基準法による罰則あり

正しく休憩時間を従業員に付与しない場合、労働基準法第119条により「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性があります。また、労働基準法に違反した企業として、厚生労働省のホームページに会社名が公開されるリスクもあります。それだけでなく、従業員の健康に悪影響を及ぼし、労災事故につながる恐れもあります。
このように、休憩時間を正しく付与しないと、罰則だけでなく、企業の信頼性を損なうことにもつながります。法律をきちんと理解したうえで、正しく従業員に休憩時間を付与するようにしましょう。しかし、休憩を付与すべきか悩まれるケースもあるかもしれません。ここからは、休憩時間を付与しない場合、罰則となるケースについて紹介します。
5-1. やむを得ず休憩を付与できなかった場合は?
やむを得ず休憩を付与できないケースもあるかもしれません。この場合も労働基準法に違反していることに変わりありません。そのため、時間をずらしてでも、正しい休憩時間を付与することが大切です。なお、休憩時間を付与できなかった場合、その時間についても賃金を支給する必要があります。
5-2. 従業員から休憩はいらないと言われた場合は?
残業などにより休憩時間の付与義務が生じたけれど、従業員から早く帰りたいため休憩は要らないと言われるケースも少なくないでしょう。この場合、合意のうえで休憩を与えず、帰宅させたとしても、労働基準法違反となります。休憩時間を与えることは法律上の義務であることを労働者に伝え、原則に基づき、正しく休憩を取得させるようにしましょう。
関連記事:休憩時間が取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介
6. 休憩時間、労働時間管理を効率化するツール
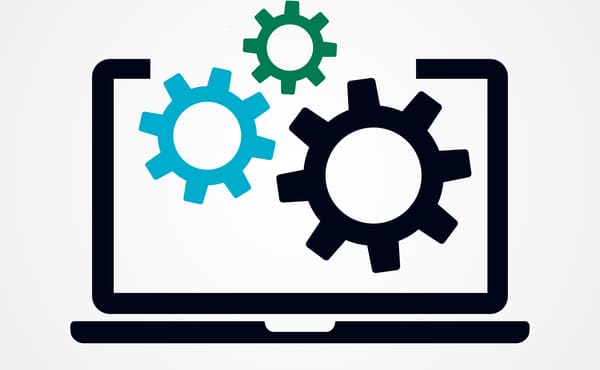
休憩時間に関する規則は複雑であり、気づかないうちに労働基準法に違反している可能性もあります。そのため、細心の注意を払い、勤怠管理をおこなうことが大切です。ここでは、休憩時間や労働時間の管理を効率化するためのツールについて詳しく紹介します。
6-1. エクセルやスプレッドシート
Excelやスプレッドシートといった表計算ソフトを用いることで、休憩時間や労働時間を効率よく管理することができます。表計算ソフトは、休憩時間や労働時間の計算だけでなく、給与計算にも使用することが可能です。従業員が使い慣れているため、手軽に導入できることから多くの企業で利用されています。
ただし、Excelやスプレッドシートに情報を入力するのは基本的に手作業になります。入力ミスが生じたり、関数・マクロにエラーが発生したりすると、適切に勤怠管理をおこなえない可能性があります。このようなメリット・デメリットから、従業員が少人数の場合は表計算ソフトを用いた勤怠管理でも問題ないかもしれません。
関連記事:勤怠管理をエクセルで!マクロや無料テンプレートについて解説
6-2. 勤怠管理システム
休憩時間や労働時間の管理を効率化するために、勤怠管理システムを導入するのも一つの手です。勤怠管理システムを活用すれば、打刻・計算・記録を連動しておこなえるので、手作業によるミスが発生しにくくなります。また、休憩時間が必要な場合に自動で通知できる機能もあるので、知らず知らずのうちに法令違反になることを防げます。ただし、勤怠管理システムを導入する場合、コストがかかります。まずは自社の目的を明確にし、複数のツールを比較したうえで、ニーズにあった勤怠管理システムを導入することが大切です。
関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介
7. 休憩時間に関するよくある疑問

ここでは、休憩時間に関するよくある疑問について紹介します。
7-1. パート・アルバイトや派遣社員にも休憩時間の付与義務はある?
休憩時間に関する規則は、正社員やパート・アルバイト、派遣社員などの雇用形態にかかわらず適用されます。そのため、パートやアルバイトであっても休憩時間を付与する必要があります。なお、個人事業主やフリーランスの場合、労働者でないので労働基準法が適用されないため、休憩時間の付与義務は生じません。
関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き
7-2. ダブルワークや副業の場合の休憩時間はどうなる?
近年では働き方改革の推進の影響もあり、ダブルワークや副業によって、2社以上で働く労働者も少なくないでしょう。労働基準法第38条により、原則として、2カ所以上の勤務先で働く場合は、その労働時間を通算しなければなりません。
たとえば、1日にA社で4時間、B社で3時間働いた場合、通算した労働時間は7時間になるので、休憩時間の付与が必要になると考えるかもしれません。しかし、労働時間は連続しているとみなされないので、休憩時間はその会社のみの労働時間で判断すれば問題ありません。この場合、A社とB社ともに労働時間が6時間を超えていないので、休憩の付与義務は生じません。このように、ダブルワークや副業の休憩に関するルールをきちんと理解しておきましょう。
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
7-3. 1日2回勤務した場合の休憩時間は?
ダブルワークや副業でなく、午前と午後で2回労働するなど、1日に1社で2回働くようなケースもあります。たとえば、1回目7時間、2回目7時間働く労働者がいた場合、休憩時間は2度付与すべきか迷われるかもしれません。労働基準法上、労働時間は1日単位で考えるのが原則です。そのため、この場合、1日に1時間以上の休憩を付与していれば問題ありません。ただし、長時間労働は従業員への健康に悪影響を及ぼすので、適切なタイミングで追加の休憩を付与することも検討しましょう。
7-4. 残業時間は労働時間に含まれる?
結論、残業時間は労働時間に含まれます。そのため、残業時間の有無によって休憩時間の長さが変動する可能性もあります。具体例は以下の通りです。
例)定時が9時半~17時半の企業(休憩時間:45分)
【残業がない場合】
定時が9:30~17:30の場合、勤務時間(※休憩時間を含まない)は8時間です。6時間を超えた段階で45分の休憩を与える必要があるので、労働時間は7時間15分となります。残業がない場合、労働時間が8時間を超えないため、追加の休憩時間は不要です。
【1時間の残業があった場合】
18:30まで1時間の残業がおこなわれた場合、勤務時間は9時間となります。45分の休憩だと労働時間は8時間15分となり、8時間を超えてしまうため、休憩時間は1時間付与しなければなりません。すでに45分付与しているので、別途で15分の休憩を付与しましょう。
関連記事:残業すると休憩時間が別途発生する?労働基準法によるルールを解説
7-5. 休憩時間にタイムカードの打刻は必要?
休憩時間にタイムカードの打刻は、原則として不要です。なぜなら、1日の勤務時間から付与する休憩時間を差し引けば、適切な労働時間を算出して勤怠管理・給与計算をおこなうことができるからです。ただし、従業員がきちんと休憩を取得しているか管理することは大切です。また、早退・遅刻などのイレギュラーが発生すると、休憩時間を正しく管理できなくなる恐れもあります。そのため、タイムカードに休憩時間を取得したタイミングと時間について記載してもらうのも一つの手です。
関連記事:タイムカードを押すタイミングはいつ?タイムカードに関する疑問を徹底解説!
8. 休憩時間の規則を把握し、健康的に働ける職場づくりを!
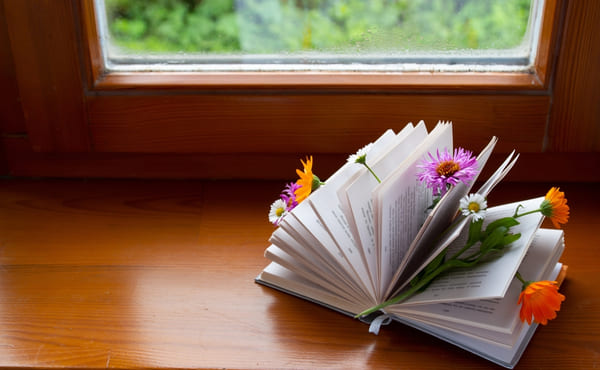
6時間勤務ちょうどであれば、休憩時間の付与は不要です。しかし、1分でも残業した時点で休憩時間の付与義務が生じます。そのため、残業時間を踏まえて、あらかじめ休憩時間のルールを整備し、就業規則に記載しておきましょう。勤務時間の異なる従業員が多い会社の場合、勤怠管理が煩雑になる可能性もあります。この機会に休憩時間を自動管理できる勤怠管理システムの導入も検討してみましょう。
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の付与や管理について、よくある質問を一問一答形式で解説した無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」「確実に休憩を取らせたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。