
日本では常に長時間労働が問題視されています。長時間労働は従業員の健康に悪影響を及ぼし、最悪の場合には過労死につながります。また、疲労の蓄積により、モチベーションや生産性が低下するケースも多いでしょう。こういった状況から、労働時間短縮を求める声が高まってきました。
本記事では、労働時間の短縮が推進されている背景や、労働時間短縮・年休促進支援コース、労働時間短縮を実現させるための取り組みについて解説します。
関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!
勤怠管理の原則や守らなければならない法律を知りたいという方に向け、当サイトでは勤怠管理の原則的な方法や働き方改革による労働基準法改正の内容を解説した資料を無料で配布しております。
どのように勤怠管理をすべきか具体的に解説しているため、「法律に則った勤怠管理の方法を確認したい」という方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。
目次
1. 労働時間の短縮とは

労働時間の短縮とは、会社の始業から終業までの休憩時間を除いた所定労働時間を短縮する取り組みのことです。
平成17年11月2日に、労働者の能力を有効に発揮させ、心身の健康維持、ワークライフバランスの確保、経済の発展を目的とした「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。現在は「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」へと改定された「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」も同法律に含まれます。
また2019年4月には「働き方改革関連法」が成立し、時間外労働の上限規制や、勤務間インターバル制度導入の努力義務などが新設され、労働時間の短縮に向けた動きは高まりをみせています。現在の労働基準法においては、1日8時間、週40時間の労働時間の上限はありますが、会社はこの範囲内であれば、自由に所定労働時間を設定することが可能です。
具体的に労働時間を短縮する方法として、所定労働時間の短縮以外に次のような方法もあります。
- ノー残業デーの導入
- 消灯時間の設定
- 有給休暇取得の促進
- フレックスタイム制の導入
1-1. 政府が推奨する働き方改革の狙い
国をあげて労働時間の短縮を推奨するようになった背景には、将来的な労働人口の減少があります。厚生労働省の調査では、15歳〜64歳の生産年齢人口は2020年の7,509万人から2070年には4,535万人まで減少すると予測されました。
このような予測があるなか、労働力不足を今後補っていくためには、育児や介護などの理由により働きたくても働けない人たちの社会進出を促していく必要があります。
そのためにも、労働時間の短縮や長時間労働の改善を図り、多様な働き方を促進させるワークライフバランスの実現をしていかなければならないのです。
1-2. 日本の労働時間の現状
厚生労働省の調査によると、2023年における男性の平均労働時間は週 41 時間程度、女性は週 32 時間程度でした。この数値は平均値であるため、長時間の残業をしている従業員も多く存在すると考えられます。
また、月末1週間の労働時間が60時間以上となっている人は、全体の約5%でした。忙しくなる時期に仕事が集中して、長時間労働を強いられるケースも多いといえるでしょう。
先進国のなかでも、日本は依然として長時間労働が発生しやすい国であるといえます。
1-3. 労働時間が長くなってしまう要因
長時間労働が発生する理由は企業によってさまざまですが、具体的には以下ような要因が考えられます。
- 従業員数が減少傾向にあるにもかかわらず仕事量が増えていること
- サービス残業や長時間労働をよしとする風潮が残っている
- 非効率な業務をすぐに改善する風土がない
- 裁量労働制を採用していることから限界まで働いてしまう
- 従業員の労働時間や業務量を把握できていない
自社にこのような特徴がある場合は、改善にむけて取り組む必要があるでしょう。
まず、従業員の労働時間や業務量を把握できていないのは問題です。労働時間を正しく把握できなければ、労働時間をどの程度短縮すべきなのか、無駄な業務がないかなどを洗い出すことができません。
また、従業員一人ひとりの業務量も適切に管理し、業務量に偏りが出ないようにすることも大切です。労働時間の短縮に取り組むためには、まずは労働時間の管理に問題がないことを確認しましょう。
1-4. 日本と欧米の労働に対する考え方の違い
欧米では、日本と比較すると長時間労働をよしとする文化がなく、生産性を重視する傾向にあります。日本の雇用慣行である終身雇用や年功序列に対し、欧米では成果主義であることから、ストレスがかかりやすいといった側面はあるでしょう。
一方で、サービス残業が発生しない企業や、早く仕事が終わればすぐに帰宅が可能である企業も多数存在しています。
1-5. 労働時間を短縮するさまざまな方法
労働時間を短縮する方法は、所定労働時間の調整だけではありません。所定労働時間を短縮しても、時間外労働が減らない、休日労働が増えた、ということでは本末転倒です。
労働時間の短縮に取り組む場合は、以下のような方法で総労働時間を減らすことも検討しましょう。
- ノー残業デーの導入:特定の日の残業を禁止し、定時で退社させる
- 有給休暇取得日の指定や取得促進:全社共通の有給休暇取得日を指定するなど
- 退館時刻の設定:特定の時間になったら館内の電気を強制的に消す
- フレックスタイム制の導入:特定の時間をコアタイムに設定し、それ以外の時間の勤務は従業員に任せる
なお、労働時間の短縮に向けた具体的な取組については、後ほど詳しく解説します。
2. 労働時間の短縮が推進されている背景

労働時間の短縮が推進されている背景としては、主に少子高齢化による労働人口の減少が挙げられます。ここでは、労働時間短縮が求められる背景について詳しく解説します。
2-1. 人手不足による長時間労働を改善するため
日本の少子高齢化問題は、企業における人材確保にも影響をもたらしています。労働人口の減少により、とくに中小企業における人材の確保は難航するケースが多く、日本経済に大きな損失を与えかねません。
また2019年以前は、特別条項付き36協定を締結すれば実質、無制限に従業員を労働させられるという状況が相まって、長時間労働や過労死が深刻な社会問題となりました。
こういった問題を是正するため、特別条項付き36協定を締結しても「時間外労働は月100時間、年720時間まで」と罰則付き上限規制が設けられました。以上のように、日本では徐々に労働時間を短縮させる動きが強まっています。
労働時間を短縮させるためには、普段から適切な勤怠管理をおこない、労働時間を正確に把握しておく必要があります。当サイトでは、法律に則った勤怠管理の原則方法について解説した資料を無料でお配りしています。法改正の内容とそれにあわせた勤怠管理の方法も解説しているため、適切な勤怠管理をおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
2-2. 日本の労働生産性向上のため
日本では労働人口の減少が深刻化していることから、労働生産性の向上が求められています。実際に日本の労働生産性はOECD加盟国36カ国のなかで20位前後に低迷しています。そういった状況を受けて、労働生産性の向上を求める風潮を日本全体で高めていくために、労働時間の短縮が推進されているのです。
3. 労働時間短縮のメリット

労働時間を短縮することには、ワーク・ライフ・バランスを実現できる、企業のイメージアップにつながるなどのメリットがあります。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
3-1. ワーク・ライフ・バランスの維持を実現できる
労働時間を短縮することで、ワーク・ライフ・バランスを維持できます。適度に休息を取り、プライベートを充実させることで、仕事へのモチベーションを維持することが可能です。
また、家族と過ごす時間や趣味を楽しむ時間を確保することで、従業員の心身の健康を保ち、仕事への集中力を高めることができるでしょう。
3-2. 定着率がアップする
従業員の定着率がアップすることも、労働時間短縮を図る大きなメリットです。仕事と生活の両立をしやすくなるため、子育てをしている女性であれば、家事や育児に割く時間をしっかり取ることができるでしょう。
他にも、資格取得やスキルアップのための勉強に時間を充てたり、趣味や遊びなどに時間を費やしたりなど、プライベートが充実することで従業員のモチベーション維持にもつながり、従業員の定着率アップを図ることができます。
3-3. 企業のイメージアップにつながる
労働時間の短縮は、企業のイメージアップにつながります。企業のイメージが刷新されることで、求人が増加し、人材不足を解決することができます。
長時間労働は主に人材不足が原因であるため、労働時間短縮に取り組むことで長時間労働の発生を根本的に解決することが可能です。また、従業員の定着率も上がるため、離職や採用などにかかる手間やコストも削減できるでしょう。
3-4. 業務効率化のアイデアが生まれる
労働時間の短縮を図ることで、業務効率化のアイデアが生まれることもあります。たとえば、ノー残業デーを設定すると、従業員は決められた時間内に仕事を終えられるよう、積極的に業務を効率化しようとします。
無駄な作業を省略したり、システムの活用によってスムーズ化したりするなど、業務改善に向けた取り組みも活性化するでしょう。
3-5. 人件費を削減できる
労働時間を短縮すれば、人件費を削減できます。残業が発生すると、企業は従業員に対して割増賃金を支払わなければなりません。通常よりも高い賃金を支払うことになるため、残業が増えるほど企業の負担も大きくなってしまいます。
残業を抑制すれば割増賃金の発生を防げるため、人件費を削減しつつ、新しい事業を展開したり職場環境を改善したりすることに費用を使えます。
4. 労働時間短縮のデメリット

さまざまなメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあるため注意しましょう。
4-1. 従業員の給与が減少する
労働時間を短縮することで、今まで支給されていた残業代が減少し、従業員の給与が下がる可能性もあります。収入が減ることに不満を感じる従業員もいるかもしれません。
なお、所定労働時間を短縮する場合は、給与を据え置きにするのが一般的です。もし、所定労働時間の短縮に伴って給与を減額する場合は、従業員にとって不利益な変更となるため、労使間での十分な協議が必要となります。
4-2. 仕事が納期までに終わらないリスクがある
労働時間短縮により、単に労働時間を減らすだけだと仕事が納期までに終わらない可能性があります。これにより、納期が遅れて売上が減少し、会社の資金繰りが困難になるなどの問題が生じるかもしれません。
そのため、労働時間短縮を取り入れる場合は、業務量や労働環境を見極めたうえで段階的に推進しましょう。
4-3. 社内間の意思疎通が悪くなる
労働時間の短縮によって懸念されるのは、社内間の意思疎通が悪くなることです。労働時間が短くなった分、効率的に業務をおこなわなければならなくなり、コミュニケーションを取る時間が十分取れなくなる恐れがあります。
コミュニケーション不足により、業務に支障をきたすような報告漏れや確認ミスが起きてしまう可能性もあるほか、社員のチームワークにも支障が出るかもしれません。
4-4. 仕事の質が低下する可能性がある
労働時間の短縮によって、仕事の質が低下する可能性もあります。短い時間で仕事を終える必要が出てくるため、どうしても雑な作業になってしまうケースもあるでしょう。
その結果、顧客満足度が低下したり、クレームが発生したりする可能性もあります。労働時間を短縮するときは、仕事の質を確保できるよう、バランスを考慮することが大切です。
4-5. 時短ハラスメントが発生する
労働時間を短縮するにあたり、企業として対策を講じずに、一方的に残業を禁止することを「時短ハラスメント」といいます。業務の効率化や仕組み化、適切な勤怠管理をおこなえない場合、残業代の不払いや法令違反、労働者への心身的負担につながりかねないため注意が必要です。
4-6. サービス残業や仕事の持ち帰りが増えてしまう
業務量が変わらないまま労働時間だけが短縮されれば、納期までに仕事が終わらないケースも出てくるでしょう。そのため、サービス残業をしたり、家に持ち帰って仕事をしたりする従業員が出てくる可能性があります。
これでは労働時間の短縮とはいえません。サービス残業や持ち帰りの仕事は時間の制限がないため、これまで以上に労働時間が増えてしまうリスクもあります。このような労働環境は従業員の負担となり、心身の健康に悪影響を及ぼすかもしれません。労働時間短縮の本来の目的を再確認し、見せかけではなく確実に労働時間が短縮できる体制を整えましょう。
ここまで、労働時間短縮が推進されている背景や助成金制度、メリット・デメリットについて解説してきました。建設業や運送業、医師業などの業界や職種においては長時間労働の文化が根強く、労働時間の短縮が難航しています。
これらの業界では、それぞれ労働時間短縮に向けさまざまな取り組みが実施されています。以下、医師業における労働時間短縮に向けた取り組みについて紹介します。
5. 医師に対する労働時間短縮計画とは?

ここからは、医師の労働時間短縮計画の概要について解説します。2024年から、全ての勤務医に時間外労働の上限規制が設けられました。
各病院では「年間960時間以下」のA水準を原則として、地域医療における必要性などの理由がある場合については「BあるいはB連携水準」として、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする場合については「C水準」として、年間1,860時間・月100時間未満の上限規制が適用されることが決定しています。
以下、医師労働時間短縮計画の提出に関する内容について解説しますので、チェックしておきましょう。
5-1. 計画提出が求められる医療機関
計画提出が求められる医療機関は以下の通りです。
・令和2年度~令和5年度までに、B・C水準の指定を受けていない状況下で年間時間外・休日時間数が960時間を超える医師がいる医療機関
・令和6年度以降は連携B・C水準の指定を受けている年間時間外・休日時間数が960時間を超える医師がいる医療機関
上記の通り、対象の医療機関は期間ごとに異なるため、注意が必要です。
5-2. 計画期間
令和5年度末までの計画期間は以下の通りです。
・計画始期:任意の日
・計画終期:令和6年3月末日
令和6年度以降の計画期間は以下の通りです。
・計画始期:令和6年4月1日
・計画終期:始期から5年を超えない範囲内で任意の日
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
また、労働短縮計画の提出後は実際に労働時間短縮に向けて取り組んでいく必要があるため、可能な限り早期の提出が望ましいとされています。
ここまで、医療労働時間短縮計画の提出が求められる医療機関と計画期間について紹介しました。
医療労働時間短縮計画の記載事項には「共通記載事項」と「任意記載事項」の2種類があります。以下、順番に紹介します。
5-3. 医療労働時間短縮計画の共通記載事項
共通記載事項には「労働時間」「労務管理・健康管理」「意識改革・啓発」の3つがあります。
5-3-1.労働時間
以下の全ての項目で、「前年度実績」「当年度目標」「計画期間終了後の目標」を記載する必要があります。
・ 年間の時間外・休日労働時間数の平均
・ 年間の時間外・休日労働時間数の最長
・ 年間の時間外・休日労働時間数 960 時間超~1,860 時間の人数・割合
・ 年間の時間外・休日労働時間数 1,860 時間超の人数・割合
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
また、目標値については自由に決めていいというものではなく、「医療労働時間短縮目標値ライン」を目安に設定しなければなりません。2035年度末の目標値である「年960時間」を着実に達成していけるよう、3年ごとの目標値を設定する必要があります。
「医療労働時間短縮目標値ライン」は以下の通りです。
2027 年:X-(X-960)/4
2030 年:X-2(X-960)/4
2033 年:X-3(X-960)/4
2036 年:9602024 年4月時点での時間外・休日労働時間数を年X時間として計算しま
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
例)時間外・休日労働時間数を年1200時間とした場合
2027年:1200 – (1200 – 960) ÷ 4 = 1,140時間
2030年:1200 – 2(1200 – 960) ÷ 4 = 1,080時間
2033年:1200 – 3(1200 – 960) ÷ 4 = 1,020時間
2036年:960時間
となり、上記の結果が各年の目標値になります。
5-3-2.労務管理・健康管理
以下の全ての項目で、「前年度実績」「当年度目標」「計画期間終了後の目標」を記載する必要があります。
・労働時間管理方法
・宿日直基準に沿った運用
・医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続き等
・労使の話し合い、36協定の締結
・衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
・追加的健康確保措置の実施
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
5-3-3.意識改革・啓発
以下の項目のうち、最低1つの取り組みにおいて、「前年度の取り組み実績」「当年度の取り組み目標」「計画期間中の取り組み目標」を記載する必要があります。
・管理者マネジメント研修
・働き方改革に関する医師の意識改革
・医療を受ける者やその家族等への医師の働き方改革に関する説明
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
意識改革・啓発とは、医師の労働時間短縮を進めるうえで、管理者や医師の労働時間に対する意識変革を目的とした活動です。医師の労働時間に対する意識変革を促すため、管理者や医師の労働時間に関する十分な説明をすることが求められていることが伺えます。
5-4. 医療労働時間短縮計画の任意記載事項
任意記載事項は以下の通りです。ただし任意記載事項は、各医療機関に勤務する職員の状況や提供している診療業務の内容などによって、実施できる可能性が大きく変わります。
そのため、下記の項目のうち1つの取り組みを選択し、「取り組み実績」「計画期間中の取り組み目標」を計画に記載するという方式が用いられています。
・タスク・シフト/シェア[注1]
・医師の業務の見直し
・その他の勤務環境改善
・副業・兼業を行う医師の労働時間の管理
・C-1水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化[注2]
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
[注1]タスク・シフト/シェアとは、現在医師が行っている業務を他職種がカバーすることで、医師がより専門的な業務に注力しやすくし、業務時間の短縮に繋げようとする取り組みのこと。
[注2]C-1水準とは、研修医向けに設けられた水準のことでプログラムに沿って基礎的な技能や能力を習得する際に適用されます。
ここまで、医師労働時間短縮計画の対象となる医療機関や、計画の記載事項や任意記載事項について解説しました。長時間労働に悩んでいる医療機関は、今回解説した計画を参考に、労働時間の短縮に取り組んでいきましょう。
しかし、長時間労働が問題視され、労働時間短縮への取り組みをしなければならないのは、医師だけではありません。企業ごとの規模によっても、労働時間は全く異なります。ここからは、とくに長時間労働が問題視されている「中小企業」に対する労働時間短縮を目指す取り組みについて解説します。
6. 労働時間を短縮する際の課題と対策

労働時間を短縮する際の課題となってくるのは、今までの業務を短縮された時間内で処理しなくてはいけないことです。また、それぞれの社員の業務内容が不透明なまま、上司が社員に労働時間の短縮を強要するジタハラ問題も課題の一つとして挙げられます。
他にも、就業時間内に仕事を終わらせることができずサービス残業をしたり、家に持ち帰ったりということも課題となってくるでしょう。こうした課題に対して、次のような対策を講じることが大切です。
6-1. 社員の業務内容を可視化する
労働時間の短縮をする前にまずやるべきことは、社員の業務内容と業務量を可視化することです。
社員一人ひとりが、どのような業務をどの程度こなしているかを見える化することで、業務の優先度をつけやすくなります。また、それぞれの業務量を把握することで、特定の社員に負担がかからないように業務を割り振りすることもできます。
6-2. システム導入やアウトソーシングを検討する
業務内容や業務量の調節が難しいようであれば、システムの導入や外部へのアウトソーシングを検討するのもよいでしょう。会計システムや労務管理システム、チャットツールやWeb会議システムなど、業務の効率化につながるシステムにはさまざまなものがあります。
導入費用などのコストはかかりますが、残業代といった人件費の削減が図れるため、長期的にみると会社にとってのメリットは大きいでしょう。
6-3. 長時間労働に対する社員の意識改革を図る
日本では、長時間働くことに対して「仕事ができる」というイメージが未だに色濃く残っており、仕事を早く終わらせて帰ることに抵抗を感じている社員も少なくありません。
労働時間の短縮を進めるにあたっては、こういった社員の長時間労働に対する意識改革を図っていかなくてはなりません。社内で啓蒙活動を進めるとともに、人事評価においても短時間で業務をこなせる能力を評価するようにしたほうがよいでしょう。
6-4. ノー残業デーを導入する
「ノー残業デー」とは、残業をせず、定時で帰る日を設定する取り組みです。ノー残業デーを設定することにより、定時に帰るために仕事を終わらせなくてはいけないという意識が生まれ、結果として従業員の生産性が上がり、残業時間の短縮につながります。
6-5. 消灯時刻を設定する
消灯時刻を設定することも労働時間短縮につながります。退社すべき時刻に社内の照明を消したり、パソコンの電源を落としたりと、物理的に働けない状態にすれば強制的に労働時間を短縮できるでしょう。ノー残業デーの導入と一緒に実施すると効果的です。
6-6. 管理職が早めに帰る
労働時間を短縮するためには、管理職が早めに帰ることも重要です。管理職が率先して労働時間短縮に努めなければ、部下の行動を促せないでしょう。仕事が終わったらすぐに帰る、積極的に有給休暇を取得するなど、休むことの重要性を示していくことが大切です。
6-7. 労働時間短縮・年休促進支援コースを申請する
働き方改革の推進を支援すべく、厚生労働省は令和2年度から「働き方改革推進支援助成金」の支給をしており、全3コースのなかの1つに「労働時間短縮・年休促進支援コース」が存在します。
一定要件を満たした事業者が、以下のいずれかの成果目標に向けた事業を実施する際に、達成状況にあわせて25万~150万円程度の助成金が支給されます。
- 36協定の時間外、休日労働時間を縮減させること
- 年次有給休暇の計画的付与と時間単位年休の規定を導入させること
- 指定する特別休暇のいずれか1つ以上を導入させること
6-8. 就労スケジュールの不確実性の対策には労務管理を工夫する
労働時間の短縮が業務上、簡単でない職種や業界も存在するでしょう。予期しない長時間残業の発生は、労働者の精神衛生上悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、ワークライフバランスにも支障をきたしやすいです。
労働量や心理的負担に見合う賃金を支払うほか、長期休暇を付与するなどの対策をとる必要があるでしょう。
6-9. 勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムの導入も業務時間の短縮につながります。勤怠管理や給与計算を紙やExcelでおこなっていると、打刻ミスがあった際の対応や集計作業、法改正への対応の際に、長時間労働が発生しがちです。勤怠管理システムを導入していると、勤怠情報を自動で記録し、法改正にも自動で対応できるため、大幅な労働時間短縮を実現することができます。
また、労働時間を短縮するためには、従業員一人ひとりの労働時間を正しく把握していなくてはなりません。勤怠管理システムなら、労働時間をリアルタイムで確認できるため、どの業務にどれくらいの工数がかかっているか把握できます。
労働時間の短縮は、すぐに成果を出そうとすると無理が生じてしまいます。勤怠管理システムで定期的に労働時間を確認しながら段階的に短縮すると、企業にとっても従業員にとっても負担が少なくて済みます。労働時間の短縮に取り組む場合は、まずは労働時間の管理方法を見直してみましょう。
7. 労働時間短縮の政策助成金「年休促進支援コース」とは?

先ほど紹介した「労働時間短縮・年休促進支援コース」とは働き方改革推進支援助成金の1つで、労働生産性の向上、労働時間短縮、有給休暇取得の促進に向け、労働環境整備に取り組む中小企業を支援する政策です。助成金の支給を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
ここからは、より具体的に「労働時間短縮・年休促進支援コース」について解説するので、参考にしてください。
7-1. 支給対象となる事業主
「労働時間短縮・年休促進支援コース」の支給対象となるのは、上記で述べた通り中小企業が当てはまります。以下の3つの基準を満たす中小企業が支給対象となるので注意しましょう。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること。
②交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
7-2. 支給対象となる取り組み
さまざまな取り組みが支給対象となりますが、総じて労務担当者に対する研修や労務用管理ソフトウェアの導入など、労働時間削減に関する取り組みが対象となります。
詳しい内容についてはこちらから確認することができます。
7-3. 成果目標の設定
成果目標の設定は選択式です。
以下の1~4のうちから1つ以上選択し、それを成果目標とし達成を目指します。
1:全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
4:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
引用:医師労働時間短縮計画作成ガイドライン一部抜粋|厚生労働省
7-4. 実施期間・申請期間・支給額について
実施期間や申請期間は以下の通りです。
・事業実施期間:2024年2月29日
・支給申請期限:2024年3月8日
支給額については、成果目標の達成度合いに応じて変動します。
期間は延長される可能性があるため、気になる方は随時チェックしておきましょう。詳しくは下記のリンクから参照してください。
働き方改革推進支援助成金 一部抜粋 |厚生労働省
「労働時間短縮・年休促進支援コース」を上手く活用して、自社の労働時間短縮を促進していきましょう。
8. 業務改善を進めて労働時間短縮を実現させよう!
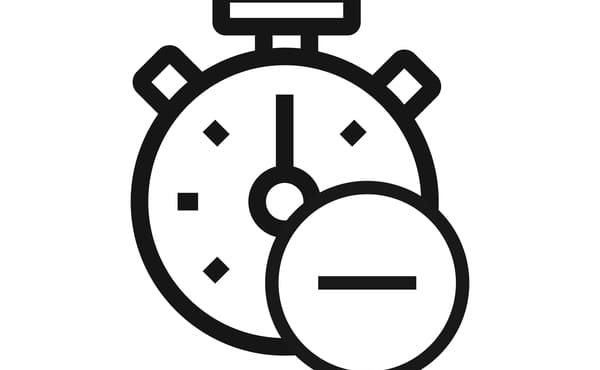
本記事では、労働時間の短縮が推進されている背景や、労働時間短縮を実現させるのための取り組みについて解説しました。
労働時間の短縮は、企業にとってメリットもデメリットもあります。しかし、企業が存続していくために回避できない課題でもあります。まずは、自社の労働環境や従業員の業務量を正しく把握し、可能な範囲で労働時間短縮に取り組みましょう。
そのためには、勤怠管理システムなどによる労働時間の正確な把握も重要です。労働時間短縮をスムーズに推進するために、ぜひ導入を検討してみてください。









