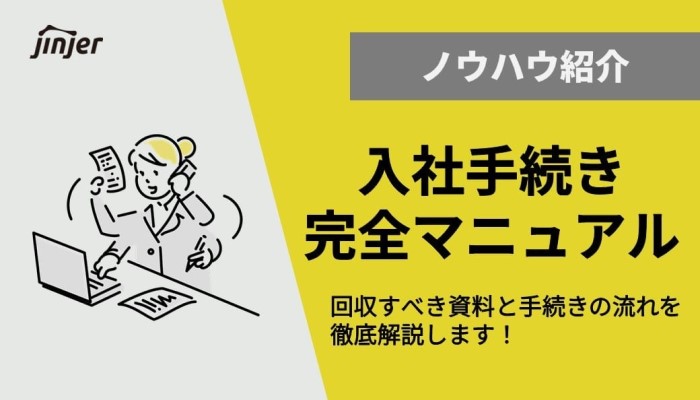入社手続きをするには、内定者に住民票や年金手帳、雇用保険被保険者証、マイナンバーなどの多くの書類を準備してもらわなくてはなりません。また、会社側も書類を集めた後、法定三帳簿の作成や保険・税金関係の手続きなど、さまざまな対応が求められます。新入社員が入社後に安心して仕事に取り掛かれるよう、入社手続きは迅速かつ適切におこなうことが大切です。今回は、企業側の入社前と入社後の入社手続きについてわかりやすく解説します。
入社手続きは社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など、対応しなくてはならない項目が多くあります。
そのため、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、遅れ等が発生してしまうと、該当の従業員に迷惑をかけてしまうだけでなく、会社への不信感を抱かせてしまうことに繋がりかねません。
そのため、確実に滞りなく入社手続きを進める必要があるでしょう。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
2024年4月からの労働条件明示ルールの変更にも対応しているので、この資料1つでチェックすることができます。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 【入社前】入社手続きのために会社側が準備すべき書類

入社手続きは、企業にとって新しい従業員を受け入れる際の重要な業務です。ここでは、入社前に入社手続きのため会社側が用意すべき書類について詳しく紹介します。
1-1. 労働条件通知書・雇用契約書
労働条件通知書とは、会社側と労働者の間で取り交わされる労働条件が具体的に記載された書類のことです。労働基準法第15条により、企業側は従業員に労働契約の締結の際に、労働条件を明示する義務があります。それを担うのが「労働条件通知書」です。
しかし、労働条件通知書は、会社側から労働者に一方的に交付する書類であり、労働者の合意があったかどうかを証拠として残すことができません。そこで、雇用契約書の交付をおこなうことも大切です。雇用契約書は、労働条件通知書と内容はほとんど変わりませんが、会社側と従業員の双方が合意したことを証明するため、押印・署名が必要になります。なお、労働条件通知書と雇用契約書の内容が変わらないのであれば、「労働条件通知書兼雇用契約書」として一つの書類にまとめることも可能です。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!
1-2. 扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書とは、給与を受け取る人(給与所得者)が扶養控除などの控除を受けるために必要になる書類です。提出期限は、その年にその会社で初めて給与を受ける日の前日までとなっています。そのため、入社前に準備しておき、スムーズに提出してもらうことが推奨されます。なお、扶養控除等(異動)申告書は1社にのみ提出できるので、2社以上に勤めている人は本業となる勤務先に提出してもらうようにしましょう。
1-3. 採用通知書(内定通知書)
採用通知書(内定通知書)とは、内定者に対して正式な採用の旨を通知する書類のことです。採用通知書の交付の義務はありません。しかし、採用通知書を交付することで、応募者は内定があったことを書面として把握でき、安心を促す効果が期待できます。なお、採用通知書の交付をおこなった後に、正当な理由もなく、内定・採用を取り消すのは違法となります。
関連記事:内定通知書とは?具体的な作成方法や書式・テンプレートをご紹介
1-4. 入社誓約書(入社承諾書)
入社誓約書(入社承諾書)とは、入社の意思を確認するための書類です。内定時に交付し、一定の期間までに押印・署名をしてもらって提出してもらうのが一般的です。ただし、入社誓約書(入社承諾書)の提出後も、一定の期限までであれば、入社を拒否できることも押さえておきましょう。たとえば、無期雇用の正社員採用の場合、入社日の2週間前までに入社辞退について会社へ伝えることで、入社を辞退することができます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2. 【入社前】入社手続きのために内定者に用意してもらう書類

入社手続きをスムーズにするため、会社側だけでなく、内定者にも入社前に用意してもらう必要のある書類があります。ここでは、入社前に入社手続きのため内定者に準備してもらう書類などについて詳しく紹介します。
2-1. 住民票記載事項証明書
入社する人の氏名や住所、生年月日、性別などの基本情報を正しく把握するため、住民票の写しや住民票記載事項証明書を求める企業もあります。なお、住民票記載事項証明書とは、それに記載された情報が、住民票に書かれている情報と相違ないことを証明するための書類です。間違った年齢や住所などの申告により、誤った手続きをしてしまったことで、罰則を受けるのは会社側です。正しく入社手続きをするためにも、住民票記載事項証明書を提出してもらうようにしましょう。しかし、個人情報保護の観点から、住民票記載事項証明書の提出を義務付ける場合、保存や管理に注意を払うことが大切です。
2-2. 基礎年金番号
基礎年金番号とは、年金加入記録を管理するための番号のことで、厚生年金保険の手続きをする際に必要となります。基礎年金番号は、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書により、確認することが可能です。なお、令和4年4月から「基礎年金番号通知書」により基礎年金番号は通知されることになっています。ただし、既に年金手帳が交付されている人には、基礎年金番号通知書が発行されないので注意が必要です。社会保険の入社手続きをスムーズにするためにも、入社前に基礎年金番号の確認できる書類などを用意してもらうようにしましょう。
2-3. 給与振込先の口座情報
給与を銀行振込によりおこなっている企業も少なくないでしょう。その場合、給与の振り込みをする前に、振込先を確認しておく必要があります。会社側で用紙した給与振込申請書に記入してもらう方法や、通帳・キャッシュカードの写しを提出してもらう方法などがあります。いずれにせよ内定者に準備してもらわなければならないので、早めに通知をおこなうようにしましょう。
2-4. マイナンバー
マイナンバーとは、行政の効率化や国民の利便性を高めることを目的とした、住民票を持つ日本国内のすべての住民に付与される個人番号のことです。社会保険や税金関係の手続きでマイナンバーは必要になります。マイナンバーは、個人番号通知カードやマイナンバーカード、住民票などにより確認することが可能です。ただし、マイナンバー法により、労働者は個人番号の提出を拒否できるので、その場合は無理に提出を求めることはできません。
関連記事:年末調整にマイナンバーは必要か?記入を拒否された場合についても解説!
2-5. 雇用保険被保険者証番号(対象者のみ)
雇用保険被保険者証番号は、雇用保険の手続きをするために必要になる番号のことです。雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者証などから確認することができます。ただし、新入社員の場合や、前職が公務員であった場合は、雇用保険に加入した経験がないため、雇用保険被保険者番号が与えられていない可能性もあります。その場合、提出してもらう必要はありません。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?必要なシーンや手続きのタイミング、再発行の方法を解説
2-6. 源泉徴収票(転職者のみ)
源泉徴収票は、年末調整を正しくおこなうため、その年の途中で転職してきた人に提出してもらう必要があります。源泉徴収票とは、その年にどのぐらいの収入があり、どのぐらいの所得税を支払ったのか確認するための書類です。なお、提出してもらう必要のある源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票」であり、「退職所得の源泉徴収票」は不要です。もしも提出を受けた場合、速やかに返却しましょう。
関連記事:年末調整後にもらう源泉徴収票とは?見方をわかりやすく解説
2-7. 退職証明書(転職者のみ)
退職証明書は、会社を退職した場合に発行される書類です。転職の場合、転職先が前の会社を本当に退職したかどうか確かめるため、提出を求めるケースもあります。なお、労働基準法第22条により、退職者が退職証明書を請求した場合、退職先は、遅滞なく交付する義務があるので注意が必要です。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
関連記事:離職証明書とは?退職証明書との違いや作成時の注意点を解説
2-8. 卒業証明書(学歴を確認する場合)
卒業証明書とは、高等学校や大学など、学校を卒業したことを正式に証明するための書類です。新卒入社の場合、まだ学校を卒業してないため、卒業見込証明書の提出が求められるケースもあります。卒業証明書(卒業見込証明書)を提出してもらわない場合、学歴詐称などにより、入社後、誤った待遇などを与えてしまう恐れがあります。そのため、学歴を重視している場合などは、内定者に卒業証明書(卒業見込証明書)を準備してもらうようにしましょう。
2-9. 資格証明書(資格が必要な業務に従事させる場合など)
資格証明書とは、その資格を取得していることを証明するための書類です。資格がなければ業務に携わることのできない仕事も少なくありません。たとえば、公認会計士や税理士、看護師、保育士、登録販売者などが挙げられます。また、会社独自の資格手当を支給する場合も、偽りの申告を防ぐため、資格証明書を提出してもらうようにしましょう。
2-10. 健康診断書(入社後に実施しない場合)
労働安全衛生規則第43条により、雇い入れ時の健康診断が義務付けられています。しかし、入社3カ月前までに自身で健康診断を受けている場合、健康診断書を提出してもらうことで、雇い入れ時の健康診断の対象外とすることができるかもしれません。このように、雇い入れ時の健康診断は義務であること、例外があることも押さえておきましょう。
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(省略)
2-11. その他の書類
その他にも、次のような書類が必要になるケースもあります。
- 身元保証書
- 従業員調書
- 個人情報保護に関する誓約書 など
入社手続きをスムーズに進めるため、法律に違反しないためにも、自社のニーズにあわせて、内定者に必要な書類を準備してもらいましょう。
関連記事:入社手続きに必要な書類一覧!手続きの流れや覚えておきたいポイント
3. 【入社前】入社前に済ませておくべき手続き

ここでは、入社前に済ませておくべき手続きについて詳しく紹介します。
3-1. 労働条件の合意を得る
入社手続きをスムーズに進めるため、まずは労働条件の合意を得ることが大切です。万が一、労働条件通知書と違った内容の業務などをさせた場合、会社側が罰則を受ける恐れがあります。入社前に労働条件通知書を発行するとともに、雇用契約書を交付し、労働条件に合意があった事実を証拠として残しておくことで、トラブルを未然に防止することが可能です。
関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!
3-2. 通勤手当を決定しておく
自動車や、電車やバスなどの公共交通機関を使って通勤する場合、会社に出社するための交通費がかかります。入社日より発生するので、それまでに通勤手当を計算しておく必要があります。通勤手当には非課税限度額があるなど、気を付けるべき点も多くあります。入社前に余裕をもって通勤手当に関する手続きを済ませましょう。
3-3. 制服や備品を貸与する
入社日から仕事を任せる企業もあるかもしれません。また、テレワークで仕事をおこなう場合、PCやスマホ、ネットワーク機器などが必要になります。そのような場合、事前に必要となる制服や備品を貸与しておくことで、入社後、スムーズに仕事に移ることが可能です。
4. 【入社前】入社手続きの手段と注意点

入社手続きには、さまざまな書類を用意・交付する必要があります。どのような手段・方法で手続きをおこなえばよいかわからないと疑問に感じる人もいるかもしれません。ここでは、入社手続きの手段と注意点について詳しく紹介します。
4-1. 直接来社してもらって対応する
入社手続きの一番簡単な手段として、内定者に直接来社してもらって対応する方法が挙げられます。直接来社してもらえば、対話して互いの疑問点・不明点を解消しながら、入社手続きを進めることができます。ただし、多くの人数を採用している場合、一人ひとりの内定者に対して直接対応するには、時間とコストがかかります。また、まだ入社していない内定者に負担がかかることも忘れてはいけません。
4-2. 郵送で手続きをする
入社手続きに必要な書類を郵送し、返送してもらうことで、入社手続きを進める方法もあります。具体的には、次の手順で実施します。
- 入社手続きで記入してもらう必要がある書類を準備する
- 返送用封筒と一緒に郵送する
- 内定者に記入および返送してもらう
郵送の場合、個人情報が外部に漏れる恐れがあります。また、書類が届いたのか直接わかりません。そのため、簡易書留郵便など、追跡可能な方法で郵送することが推奨されます。また、郵送する場合、封筒に「社名」「問い合わせ先」を必ず明記し、送付先の住所や氏名に間違いがないか確認してから郵送することが大切です。
4-3. メールやチャットで実施する
入社手続きは電子化して、メールやチャットなどで実施することも可能です。人事管理システムへのアクセス権限を付与し、入社手続きの書類をシステム上で提出してもらう方法もあります。入社手続きを電子化すれば、会社側と内定者双方の手間を減らすことが可能です。
ただし、PCやスマホといった端末やネット環境がなければ、メール・チャットやシステムを用いた方法で入社手続きをすることができません。あらかじめ内定者の所有物を確認し、入社手続きに必要になる備品を貸与しておきましょう。また、電子ツールの使い方もわかりやすいようマニュアルとしてまとめておくとよいでしょう。
関連記事:【完全版】入社手続きマニュアル!手順や必要書類、注意点を徹底解説!
4-4. メールで案内文を送付する際の注意点
メールで案内文を作成・送付する際は、「入社手続きのご案内」など、簡潔でありながら本文内容がわかるような件名をつけましょう。【重要】などと明記すると、よりわかりやすいでしょう。宛名には内定者の氏名をフルネームで、差出人には「会社名」「部署名」「担当者の氏名」を記載します。
メールの本文は挨拶からはじめ、「結果の通知」「内定式の日程・場所・時間」「必要書類提出のお願い」「提出期限」を明記します。なお、冒頭や文末に「拝啓」や「敬具」を記載する必要はありません。また、文章は長すぎず短すぎず、読みやすい長さを心がけることがポイントです。
関連記事:【例文つき】入社手続きメールの企業側の書き方・NG例を詳しく解説
5. 【入社後】入社後に会社側がすべき各種手続き
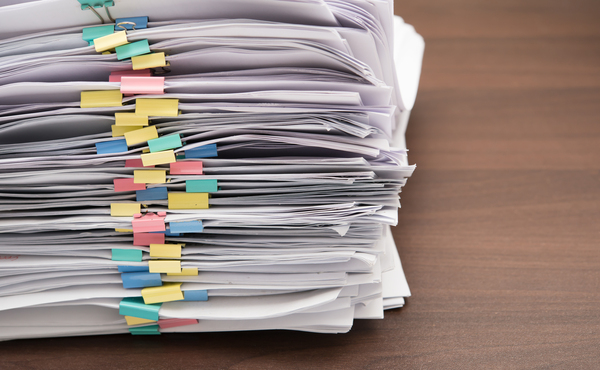 入社前だけでなく、入社後におこなう入社手続きもあります。ここでは、入社後に会社側がすべき各種手続きについて詳しく紹介します。
入社前だけでなく、入社後におこなう入社手続きもあります。ここでは、入社後に会社側がすべき各種手続きについて詳しく紹介します。
5-1. 法定三帳簿の作成
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つのことで、労働基準法によって会社に作成・保管することが義務付けられている書類です。
なお、労働者名簿とは、従業員の氏名や住所、生年月日など、個人情報を記載した書類のことです。資金台帳は、賃金計算期間や労働日数、労働時間数、基本給や手当などを記載した書類を指します。出勤簿とは、従業員の出勤日や出勤日数、労働時間数、出退勤の時刻などを記載した書類のことです。
このような法定三帳簿に加えて、労働関係に関する重要な書類は5年間の保存が義務付けられています。ただし、経過措置が設けられており、当面の間は3年間の保存で問題ありません。しかし、いつ経過措置が終了するのか未定なため、できる限り5年間保存するような体制を整備しましょう。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
関連記事:労働基準法第109条による「労働者名簿」とは?作成方法を解説
5-2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き
社会保険の加入条件(健康保険・厚生年金保険)を満たしている場合、その手続きが必要になります。なお、社会保険への加入が必要となる従業員の条件は以下の通りです。
|
対象者 |
加入条件 |
|
正社員などの一般労働者 |
所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上、かつ、契約期間が2カ月以上 |
|
パート・アルバイトなどの短時間労働者 |
・週の所定労働時間が20時間以上 ※上記5つをすべて満たしていることが加入の条件 |
なお、社会保険適用拡大の影響により、短時間労働者の場合、2024年10月から「従業員が51人以上の事業所」も対象になるので注意が必要です。社会保険に加入させるためには、資格取得届を日本年金機構や各種健康保険組合に届け出なければなりません。また、家族を扶養に入れる場合、健康保険被扶養者異動届や国民年金第3号被保険者届の記入・届出も必要になります。それぞれ期限が決まっているので、速やかに手続きをしましょう。
5-3. 雇用保険の加入手続き
雇用保険の加入条件を満たしている場合、雇用開始月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出し、資格取得手続きを済ませましょう。雇用保険の加入条件は次の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上継続して雇用される見込みがある
- 学生でない(例外あり)
手続きの際は、法定三帳簿や雇用契約書なども一緒に提出しなければならないケースがあります。資格取得手続きの完了後、ハローワークから送られてくる「雇用保険被保険者証」「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」は、従業員本人に渡します。なお、雇用保険被保険者証は重要な書類であるため、会社側で預かっているケースもあります。
関連記事:雇用保険の加入条件!手続き方法や注意点をわかりやすく解説
5-4. 労災保険の加入手続き
労災保険とは、通勤時におけるけがや業務中の負傷を補償するもので、正式名称は「労働者災害補償保険」です。雇用保険と合わせて労働保険と呼ばれます。従業員を1人でも雇用していれば加入の対象となります。大まかな手続きの流れは以下の通りです。
- 管轄の労働基準監督署へ出向いて保険関係成立届を提出する
- 概算保険料申告書を提出する
- 労働保険番号が発行されてことを確認する
- 「納入済通知書」を受け取って金融機関にて保険料を納付する
労働保険の資格取得対象者がいる場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークへ行き、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届とは?記入例や提出先を詳しく紹介
5-5. 税金に関する手続き
入社後、「所得税」と「住民税」の税金に関する手続きが必要になります。所得税については、内定者から提出してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとにして源泉徴収簿を作成します。年末の源泉徴収票発行を不備なくおこなうための手続きなので、滞りなく済ませましょう。
次に、住民税です。住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。普通徴収の場合は従業員本人が納税しますが、特別徴収の場合は会社が従業員の毎月の給与から本人に代わって住民税を納付します。中途入社した従業員が特別徴収での納税を希望する場合は、納税先の自治体に「給与所得者異動届書」を提出する必要があります。
6. 【入社後】入社後に安心して働けるように会社側が準備すべきこと

入社手続きを済ませた後は、従業員が気持ちよく働けるようサポートすることが大切です。ここでは、入社後に安心して働けるように会社側が準備すべきことについて詳しく紹介します。
6-1. 入社後の研修を整備しておく
入社後は慣れない環境のため、従業員は不安に感じてしまいます。まずは会社の方針や文化などを理解してもらうため、研修をおこなうのが一般的です。入社後の研修が適切でないと、従業員のモチベーションが下がり、生産性低下や早期離職につながる恐れがあります。入社手続きに加えて、入社後の研修についても、事前に整備しておきましょう。
6-2. 既存の社員に新しく従業員が入ることを周知する
新しく従業員が入る場合、PCやデスクの用意など、既存の社員にも負荷がかかります。いきなり新入社員が入ると、既存の従業員が上手く対応できず、トラブルにつながる可能性があります。入社後、スムーズに業務に取り掛かれるよう、既存の社員にどのような従業員が入るのかを周知しておくことが大切です。また、どのような準備が必要かもマニュアル化して、既存社員に伝えておくことが推奨されます。
6-3. 問い合わせ窓口を用意しておく
入社前後には、さまざまな手続きがあり、トラブルが生じることも少なくありません。疑問点や不明点があった際に、すぐに解決できるよう、あらかじめ専用の問い合わせ窓口を用意しておくことで、会社側と内定者ともに不安を減らし、スムーズに対応することができます。このような対応は、入社後の従業員のエンゲージメントにも影響を与えるため、丁寧に応対するようにしましょう。
6-4. 業務を効率化するため入社手続きのチェックリストを作成する
入社手続きは煩雑であり、時間や手間がかかります。また、期限がある手続きもあるので、慎重に対応しなければなりません。入社手続きの業務を効率化するためにも、自社の必要書類や手続きをチェックリストにしてまとめておくことが推奨されます。また、人的ミスを防いだり、迅速な情報共有をおこなったりするため、労務管理システムや人事管理システムといったITツールの導入も検討してみましょう。
7. 入社手続きでよくあるトラブルと対処法

ここでは、入社手続きでよくあるトラブルの事例とその対処法を紹介します。
7-1. 期日までに手続きが間に合わない
社会保険の手続きなどには期限があり、それに間に合わないケースも少なくありません。期日を過ぎてからの提出でも、内容がきちんとしていれば、受理してもらうことは可能です。しかし、追加書類を求められることがあり、事務処理の手間が増えるので注意してください。
企業として、手続きの遅れは好ましくありません。また、法律に則り罰則が課せられたり、社会的信用を損なったりする恐れもあります。このような事態を繰り返し起こさないためには、人事業務フローの見直しや人事管理システムの導入など、迅速かつ正確な入社手続きをおこなえるような対策を取ることが大切です。
7-2. 内定者から必要な書類を回収できない
入社手続きでは、内定者に提出を求める書類もあります。次のような書類は紛失などを理由に提出が遅れる可能性があります。
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳・基礎年金番号通知書
雇用保険被保険者証は、本人に前職の会社へ問い合わせてもらうか、ハローワークに行って本人確認書類と前職の企業名および住所が分かるものを提出すれば再交付が受けられます。年金手帳・基礎年金番号通知書は、本人による再交付手続きが必要です。再交付については日本年金機構のホームページを確認しましょう。
7-3. 外国人を雇用した場合の対応がわからない
労働者不足を理由に、外国人を雇用するケースも増えています。外国人の入社手続きには、以下のような書類が必要になります。
- 在留カード(国内居住者の場合)
- パスポート
- 卒業見込みまたは卒業証明書(留学生を雇用する場合)
- 職務経歴書
国外に住んでいる外国人を雇用する場合は、「ビザ申請」も必要です。国内に住んでいる外国人の場合は、必ず「在留カード」を確認し、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出しましょう。
このように入社手続きは対応すべき事項が多く、一連の流れをよく理解していなければ、手続きに時間がかかって書類提出の期日に遅れたり、漏れが発生したりしてしまいます。当サイトでは、入社手続きの流れとおこなうべきことが確認できるマニュアルを無料で配布しています。漏れや遅れが発生することなく入社手続きをおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードして、スムーズな入社手続きにお役立てください。
8. 会社側の入社手続きのやり方を理解してスムーズに対応しよう
 入社手続きには、法律で定められた書類の作成・管理ほか、各種保険や税金の手続き、備品支給など、細かい業務が必要です。とくに社会保険や雇用保険の加入手続きには期限があるため、迅速な対応が求められます。人事管理システムや労務管理システムといった便利なITツールを導入し、業務を効率化して入社手続きをよりスムーズにし、新たに入社する従業員が安心して仕事できる環境を整えましょう。
入社手続きには、法律で定められた書類の作成・管理ほか、各種保険や税金の手続き、備品支給など、細かい業務が必要です。とくに社会保険や雇用保険の加入手続きには期限があるため、迅速な対応が求められます。人事管理システムや労務管理システムといった便利なITツールを導入し、業務を効率化して入社手続きをよりスムーズにし、新たに入社する従業員が安心して仕事できる環境を整えましょう。
入社手続きは社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など、対応しなくてはならない項目が多くあります。
そのため、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、遅れ等が発生してしまうと、該当の従業員に迷惑をかけてしまうだけでなく、会社への不信感を抱かせてしまうことに繋がりかねません。
そのため、確実に滞りなく入社手続きを進める必要があるでしょう。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
2024年4月からの労働条件明示ルールの変更にも対応しているので、この資料1つでチェックすることができます。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。