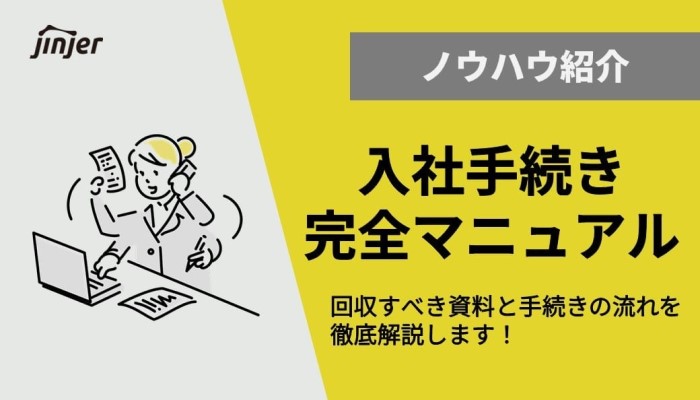入社手続きをマニュアル化するには、まず基本的な流れを把握することが大切です。必要書類の作成と採用内定者への送付、採用内定者に提出依頼していた必要書類の回収、法定三帳簿の作成、社会保険や雇用保険の加入手続き、税金関係の手続きなど、入社手続きには多くの書類の管理や届出・提出が必要です。今回は、人材採用後の入社手続きをマニュアル化したい方に向けて、基本的な処理の流れや注意点を解説します。
入社手続きは社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など、対応しなくてはならない項目が多くあります。
そのため、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、遅れ等が発生してしまうと、該当の従業員に迷惑をかけてしまうだけでなく、会社への不信感を抱かせてしまうことに繋がりかねません。
そのため、確実に滞りなく入社手続きを進める必要があるでしょう。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
2024年4月からの労働条件明示ルールの変更にも対応しているので、この資料1つでチェックすることができます。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 入社手続きの手順
 入社手続きをマニュアル化するには、基本的な流れを理解しておくことが大切です。ここでは、入社手続きの手順について詳しく紹介します。
入社手続きをマニュアル化するには、基本的な流れを理解しておくことが大切です。ここでは、入社手続きの手順について詳しく紹介します。
1-1. 必要書類を作成して送付する
まずは採用通知書(入社手続き案内)、入社承諾書、労働条件通知書、雇用契約書を作成しましょう。労働条件通知書は法律で交付が義務付けられているので注意しましょう。それぞれの書類のテンプレートを作っておくと、業務を効率化することができます。また、送付タイミングや注意点をまとめてマニュアル化しておくことで、入社手続きをスムーズにおこなうことが可能です。
1-2. 法定三帳簿を作成する
入社手続きに必要な書類を作成・送付し、返送してもらったら、その情報に基づき、法定三帳簿を作成する必要があります。法定三帳簿とは、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿のことで、労働基準法の定めにより、作成・保管が義務付けられています。それぞれの特徴や意義は以下の通りです。
|
帳簿の種類 |
説明 |
|
労働者名簿 |
従業員の氏名や年齢、住所やマイナンバーなどの個人情報を記載した名簿のこと |
|
賃金台帳 |
従業員の賃金額やその計算の基礎となる事項、賃金計算期間など、賃金に関する項目をまとめた書類のこと |
|
出勤簿 |
従業員の出勤日や労働日数、労働時間数などを記載した書類のこと |
労働基準法第109条により、法定三帳簿は5年間(ただし、当面の間は3年間)の保存が義務付けられています。労働基準法第120条により、違反した場合は30万円以下の罰則が課される可能性があります。法定三帳簿に関しても、記載事項やルールをまとめてマニュアル化しておきましょう。
(記録の保存)
第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
1-3. 社会保険の加入手続きをする
法定三帳簿を作成したら、従業員の労働条件を基に加入要件を確認したうえで、社会保険の加入手続きをおこないましょう。健康保険や厚生年金保険と雇用保険で加入条件が異なるので注意が必要です。
健康保険や厚生年金保険に加入させるためには、管轄の年金事務所と健康保険組合に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出します(協会けんぽの場合は年金事務所)。雇用保険に加入させるためには、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、手続きをおこないましょう。なお、法定三帳簿が必要になるケースもあるため、あらかじめ用意しておくとスムーズです。
関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識
1-4. 税金に関する手続きをする
社会保険の加入手続きが終わったら、所得税や住民税といった税金に関する手続きをおこなう必要があります。まずは所得税の手続きをします。入社の際に提出してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとに、源泉徴収簿を作成しましょう。前職を退職した年に再就職した従業員に関しては、前職の源泉徴収票の提出が必要になります。
住民税の納付方法には、自分で納める「普通徴収」と会社側が本人に代わって納める「特別徴収」の2種類があります。特別徴収の場合、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を所轄の市区町村に提出しなければなりません。
関連記事:所得税と住民税の違いは?税率や仕組みの違いをわかりやすく解説!
1-5. その他、実務の準備も整えておく
入社手続きというと、書類の作成・提出が優先される傾向にあります。しかし、入社予定の社員にとっては、これから自分がどのような環境で働くか不安に感じている人も多いです。万が一入社準備に不備があれば、モチベーション低下や早期離職につながる恐れもあります。
入社手続きの中には、新入社員を受け入れる環境の整備も含まれています。制服やデスクなどをはじめ、備品やメールアドレスの取得などの準備も忘れずにおこないましょう。また、入社当日の手続きがスムーズに進むよう段取りを確認したり、すぐに業務に移行できるような研修を準備したりするなど、部署の垣根を越えて社内で強力して新入社員を迎え入れましょう。
このように、入社手続きに加えて、新入社員を迎え入れる体制を整備することで、新しく入社する従業員は安心して働くことができるようになります。手続きのし忘れが生じないよう、あらかじめ手続きや準備すべきことをマニュアル化しておくようにしましょう。
関連記事:入社手続きに必要な書類一覧!手続きの流れや覚えておきたいポイント
2. 【入社前】入社手続きに必要な書類

入社手続きは煩雑であるため、マニュアル化してスムーズに対応できるようにすることが大切です。入社手続きの中には、入社前に済ませておくべきものもあります。ここでは、入社前に必要となる入社手続きの書類について詳しく紹介します。
2-1. 採用(内定)通知書
採用(内定)通知書とは、企業が採用者に対して雇用の承諾を伝えるための書類です。会社によっては書面ではなく、口頭やメールで通知する場合もあるようです。後でトラブルが生じないよう、記録に残るようにしておくことが大切です。なお、採用通知書は法律で定められた書類でないため、交付しなくても問題ありません。ただし、採用通知書を交付したのにもかかわらず、会社側の一方的な都合で入社を拒否するのは違法になるので注意が必要です。
関連記事:内定通知書とは?具体的な作成方法や書式・テンプレートをご紹介
2-2. 入社承諾書
入社承諾書とは、入社の意思確認をおこなうための書類です。採用(内定)通知書と一緒に送付し、入社承諾書のみ署名・捺印のうえ提出してもらいましょう。ただし、承諾のサインがあった入社承諾書に返送してもらっても、内定者は一定の期限までであれば、法的に問題なく入社を拒否することができます。そのため、承諾済みの入社承諾書を受け取ったからといって、会社側は慢心せず、入社まで丁寧に応対することを心がけましょう。
2-3. 労働条件通知書、雇用契約書
労働条件通知書とは、労働条件を記載した書類で、労働基準法第15条によって交付が義務付けられています。労働条件通知書を交付しない場合、違法になる恐れがあるので注意が必要です。記載事項に関しては法律で定められた事項を記載しましょう。一度テンプレートを作成し、マニュアル化しておくと作成・交付がスムーズになります。
なお、労働条件通知書を一方的に交付しただけでは、労働条件に合意があったことを証明できません。そこで、雇用契約書も交付するのが推奨されます。雇用契約書は労働条件通知書とほとんど内容が変わりません。しかし、押印・署名を必須にすることで、会社側と内定者が労働条件に合意したことを証明することができます。労働条件通知書と雇用契約書は「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚の書類としてまとめることも可能です。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!
3. 【入社後】入社手続きに必要な書類

入社手続きには、入社後に内定者に提出してもらったり、記載してもらったりする書類もあります。入社後に必要な書類も数多くあるため、スムーズに手続きを進めるため、マニュアル化しておきましょう。ここでは、入社後、入社手続きに必要な書類
3-1. 住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書とは、住民票に記載されている事項が正しいことを証明するための書類です。法定三帳簿を作成したり、社会保険・税金関係の手続きをしたりする際、新入社員の基本情報が必要になります。誤った手続きをしないためにも、住民票記載事項証明書を提出してもらいましょう。
3-2. 年金手帳(基礎年金番号通知書)
厚生年金保険に加入させるためには、資格取得届に「基礎年金番号」を記載して提出しなければなりません。基礎年金番号を確認するためには、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を提出してもらう必要があります。なお、2022年4月以降、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されるようになっています。従業員の年齢などに応じて、提出が必要になる書類が異なることも押さえておきましょう。
3-3. 扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書とは、給与に関して扶養控除などを受けるため提出が必要になります。提出期限は、その年の最初に給与の支払いがおこなわれる日の前日(中途入社の場合、就職後最初の給与の支払いがおこなわれる日の前日)までとされています。そのため、入社後、速やかに手続きをおこなうようにしましょう。
関連記事:【令和6年版】扶養控除等(異動)申告書とは?書き方を項目別に紹介
3-4. 給与振込先申請書
給与の振込を銀行口座を用いておこなっている会社も少なくないでしょう。このような場合、最初の給与振込を実施するまでに、振込先を確認しておく必要があります。そのため、入社後、給与振込先申請書を記入し、提出してもらいましょう。なお、振込先が間違っていると、正しく給与が支払われず、トラブルが生じる可能性があります。給与振込先申請書を提出してもらう際に、通帳やキャッシュカードを提示してもらったり、その写しも提出してもらったりして、振込先が正しいことをチェックしましょう。
3-5. マイナンバー
マイナンバーとは、行政の効率化や国民の利便性向上のため、住民票を有するすべての人に付与されている重複することのない個人番号のことです。社会保険や税金関係の手続きには、マイナンバーが必要になるケースがあります。マイナンバーは、「マイナンバーカード」「住民票の写し」「通知カード」などにより、確認することが可能です。ただし、マイナンバーは個人情報であり、提出を拒む労働者もいるかもしれません。その場合、強制することはできないので注意が必要です。
関連記事:年末調整にマイナンバーは必要か?記入を拒否された場合についても解説!
3-6. 雇用保険被保険者証(過去に雇用保険に加入していた場合)
雇用保険被保険者証とは、雇用保険の加入状況を証明するための書類です。新しく雇用保険の加入手続きをする場合、雇用保険被保険者番号が必要になります。ただし、前職が公務員であった場合や、初めて会社に勤める場合などは、雇用保険の加入履歴がないので、雇用保険被保険者証は交付されていません。そのような場合、新しく発行されるため、雇用保険被保険者証の提出は不要です。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?必要なシーンや手続きのタイミング、再発行の方法を解説
3-7. 源泉徴収票(その年に転職を行った場合)
その年に他の勤務先で給与を受け取ってから退職した場合、退職先から給与所得の源泉徴収票が退職者に発行されます。転職先はその内容を含めて年末調整をしなければならないため、前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。なお、退職所得の源泉徴収票は提出してもらわなくて問題ありません。
関連記事:年末調整後にもらう源泉徴収票とは?見方をわかりやすく解説
3-8. 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者資格取得届(扶養の手続きをする場合)
配偶者や子を社会保険(健康保険や厚生年金保険)の扶養とする場合、健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者資格取得届を記入し、提出してもらう必要があります。従業員から書類を提出してもらったら、会社側が日本年金機構もしくは各健康保険組合にその書類を提出しなければなりません。なお、扶養に該当するかどうか、きちんと確認したうえで、書類を提出するようにしましょう。
関連記事:健康保険被扶養者届とは?書き方や記入例、提出が必要なケースや添付書類を解説
3-9. その他必要書類
会社の環境や状況などによって、入社手続きに次のような書類が必要になるケースもあります。
- 身元保証書
- 健康診断書
- 資格免許証
- 合格証明書類
- 個人情報保護法に基づく誓約書 など
このように、入社手続きに必要な書類は企業によっても変わってきます。自社に必要になる書類をまとめ、スムーズに漏れなく手続きできるようマニュアルにまとめておきましょう。当サイトでは、入社手続きをする際に企業がすべきことを入社手続きの注意点とともにまとめた資料を配布しています。漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードして、お役立てください。
4. 入社手続きに必要な各機関への届出
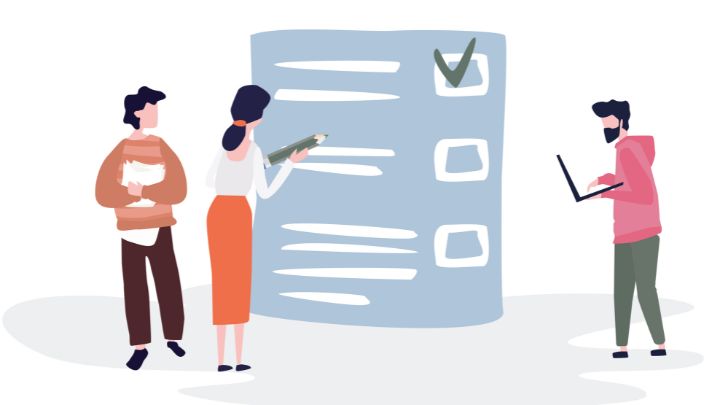
提出してもらった書類は内容に不備がないか、各機関へ届出をおこなう前にチェックをおこないます。書類に問題がないようであれば、各機関へ届出をおこないます。ここでは、入社手続きに必要な各機関への届出について詳しく紹介します。
4-1. 社会保険の加入手続き
社会保険の加入手続きは、従業員が入社した日から5日以内におこなわなくてはいけません。フルタイムの正社員は基本的に全員が社会保険の加入対象です。一方、パート・アルバイトなど短時間労働者は、以下の条件を満たす場合に加入が義務付けられています。
- 従業員数が101名以上の企業に所属している(2024年10月からは51名以上の企業に改正予定)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上
- 雇用契約期間が2か月超である
- 学生でない
社会保険の届出は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を作成のうえ、日本年金機構(管轄年金事務所)もしくは健康保険組合へ提出します。なお、扶養家族の加入申請もおこなう場合は「健康保険被扶養届」を、扶養している配偶者については「国民年金第3号被保険者資格取得届」も合わせて提出する必要があります。
関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識
4-2. 雇用保険の加入手続き
雇用保険の加入手続きについては、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に書類を提出しておこないます。なお、雇用保険への加入が義務付けられている従業員の条件は、原則として次の通りです。
- 同一の事業主で引き続き31日以上働く見込みがある
- 所定労働時間が週20時間以上である
- 学生でない(例外あり)
上記のすべての加入要件を満たしている場合、入社した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を作成して手続きをする必要があります。
関連記事:雇用保険の加入条件!手続き方法や注意点をわかりやすく解説
4-3. 税金の手続き
入社手続きには、所得税や住民税といった税金の手続きもあります。所得税の手続きについては、従業員より提出を受けた「扶養控除等(異動)申告書」を基に、源泉徴収簿を作成しましょう。
住民税の手続きに関しては、入社前の納付方法が「普通徴収」または「特別徴収」であったかにより異なります。普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収への切替申請書」を、未使用の住民税納付書または領収書と一緒に、従業員が居住する市区町村に所定の期日までに提出します(期日は市区町村によって異なりますので各自ご確認ください)。前職より続けて特別徴収にする場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出します。なお、新卒のように前年の所得が無い場合、手続きは不要となります。
5. 入社手続きで注意すべきポイント
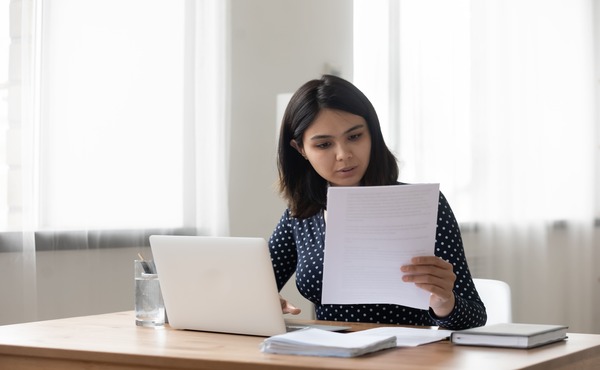
入社手続きには気を付けるべき点がいくつかあります。ここでは、入社手続きで注意すべきポイントについて詳しく紹介します。
5-1. 入社手続きの期限に従って優先順位を決めて進める
社会保険や雇用保険の加入手続きには、届出の提出期限が設けられています。期限を過ぎた場合、入社日から手続きをした日までの賃金台帳と出勤簿を提出しなければならなかったり、遅延理由書を作成して提出する必要があったりと、余計な手間がかかってしまいます。それぞれの期限をマニュアルにきちんと記載し、優先順位を決めて入社手続きをおこないましょう。
5-2. 手続きの内容によって提出先となる機関が異なる
入社手続きはその内容によって書類の提出先が異なります。事前に提出先を確認したり、処理担当者を担当制にしたりして、スムーズな手続きにつなげましょう。
社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入手続きでは、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を「日本年金機構(場合によっては、日本年金機構と健康保険組合)」に提出します。なお、従業員に配偶者や子どもがいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」、配偶者が「国民年金の第3号被保険者」に該当する場合は「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」も併せて提出しましょう。
雇用保険の加入手続きは、必要事項を記入した「雇用保険被保険者資格取得届」に法定三帳簿などの確認資料を添付し、所轄のハローワークに提出します。そして、住民税を特別徴収で納付する場合は、納付先の市町村に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
このように、手続きの期限だけでなく、提出先や添付書類などもマニュアルにまとめておくと、スムーズに手続きができるようになります。
5-3. 新入社員の個人情報の取り扱いに気を付ける
入社手続きには、従業員に個人情報を提供してもらう必要があります。場合によっては、従業員の家族の情報も知りうる可能性があるため、その重要性を認識したうえで業務に取り組みましょう。
知り得た情報が外部に漏れたり、悪用されたりした場合、企業の社会的信用を損なう恐れがあります。個人情報の管理方法についてもマニュアル化し、外部に漏洩しないよう注意しましょう。
5-4. 入社手続きを電子化して業務を効率化する
入社手続きにはさまざまな書類の準備が必要になり、細かい業務が多く発生します。また、従業員の個人情報を取り扱う重要な業務でもあるため、処理のミスを防がなくてはなりません。人事管理システムや労務管理システムといったITツールを導入することで、作業の一部を自動化し、業務を効率化することができます。また、人的ミスを防止することにもつながります。さらに、入社手続きをオンライン上で完結できるので、働き方改革を推進することも可能です。この機会に入社手続きを電子化できるような体制を整備してみるのもおすすめです。
関連記事:【入社手続き】会社側で必要な準備や書類は?保険の加入や税金の対処法を紹介
5-5. 既存の従業員への周知も忘れない
入社手続きでは、人事担当者や新入社員だけでなく、既存の従業員にも負担をかけることがあります。たとえば、部署配属になる新入社員のデスクやパソコンの準備・設定などが挙げられます。いきなり新入社員が配属されることになった場合、既存の従業員の負担が増え、トラブルにつながる恐れもあります。このように、既存社員の負担も考慮し、新入社員に対する準備などをマニュアル化して事前に伝達しておくと丁寧な対応だといえるでしょう。
6. 入社手続きをマニュアル化し、迅速かつ適切に対応しよう!

必要書類の準備や各機関への届出の提出など、入社手続きに関わる業務は多岐に渡ります。社会保険や雇用保険、税金関係の手続きが遅れてしまうと、従業員の生活に大きな影響を与えます。業務をマニュアル化・フロー化することで効率化を図り、書類の提出漏れや期限遅れを防ぐことが大切です。入社手続きに関する業務をより迅速に、適切に処理するには、電子化に対応したシステムの導入がおすすめです。
入社手続きは社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など、対応しなくてはならない項目が多くあります。
そのため、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、遅れ等が発生してしまうと、該当の従業員に迷惑をかけてしまうだけでなく、会社への不信感を抱かせてしまうことに繋がりかねません。
そのため、確実に滞りなく入社手続きを進める必要があるでしょう。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
2024年4月からの労働条件明示ルールの変更にも対応しているので、この資料1つでチェックすることができます。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。