
雇用保険は、労働者が失業した場合でも安心して暮らせるために設けられている制度ですが、働いているすべての人が加入できるというわけではありません。
自身が雇用保険に加入できるかどうかによって、万が一退職したり休職したりした際の生活の安定度には大きな差が生まれます。そのため、雇用保険への加入条件はきちんと把握しておく必要があります。
本記事では、雇用保険の加入条件や雇用形態ごとの違い、雇用保険が適用されないケースについて説明します。
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用保険とは?

ここでは、雇用保険の定義や、雇用形態によって加入条件は異なるのかについて詳しく紹介します。
1-1. 雇用保険の定義
雇用保険とは、失業した場合などに給付を実施し、労働者の生活・雇用の安定を図ることや、再就職をサポートすることを目的とした制度です。事業者は、雇用保険法により、対象要件を満たす労働者がいる場合、事業者および労働者の意思に関係なく、雇用保険に加入させる必要があります。
なお、雇用保険の失業等給付は、大きく下記の4つに分類されます。
|
失業等給付 |
説明 |
|
求職者給付 |
失業者の生活の安定を図ることに加え、求職活動を援助するための給付(基本手当や技能習得手当など) |
|
就職促進給付 |
失業者の再就職を援助・促進するための給付(就業手当や再就職手当など) |
|
教育訓練給付 |
労働者の主体的な能力向上やキャリアアップをサポートし、雇用の安定と再就職の促進するための給付(教育訓練給付金など) |
|
雇用継続給付 |
労働者の雇用継続を援助・促進するための給付(育児休業給付金や介護休業給付金など) |
また、雇用保険料は、事業主と労働者が負担します。雇用保険の場合、健康保険や厚生年金保険などと異なり、事業主が多く支払うようになっています。まずは雇用保険の仕組みについて正しく理解することが大切です。
関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!
1-2. 雇用形態によって加入条件は変わらない
雇用保険に加入するための条件に、雇用形態に関する内容のものは設けられていません。そのため、正社員や契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく、条件を満たせば、雇用保険に加入することができます。
このように「正社員だから加入できる」「アルバイトだから加入できない」といったように、制度が決められているわけではないので、企業は加入条件を満たしているすべての労働者を、雇用保険に加入させなければなりません。
2. 雇用保険の加入条件
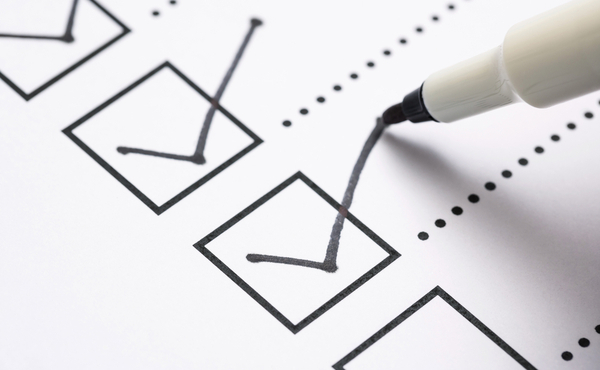
雇用保険に加入するためには、企業と労働者の双方が決められた条件を満たさなければなりません。ここでは、企業および労働者が満たすべき具体的な加入条件について紹介します。
2-1. 企業
企業は1人でも従業員を雇用している場合は、原則として雇用保険に加入しなければなりません(農林水産業の一部事業を営んでいる場合を除く)。
雇用保険への加入は任意ではなく強制なので、従業員を雇ったのであれば必ず期日までに雇用保険加入の手続きをおこなうことを心がけましょう。
2-2. 労働者
労働者は以下の条件を満たす場合に、雇用保険に加入することができます。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上雇用される見込みがあること(後述する日雇労働被保険者を除く)
- 学生でないこと(例外あり)
正社員の場合は、基本的に週の所定労働時間は20時間以上になります。契約社員やパート・アルバイトとして働いている人は、週の所定労働時間によって雇用保険に加入できるかどうかが変わります。なお「所定労働時間」に関しては、就業規則や雇用契約書に記載されている「通常の週に勤務すべき1週間の労働時間」が適用されます。たとえば、パートやアルバイトで「通常の週に勤務すべき1週間の労働時間」に「18時間」と記載されている場合、一時的に20時間以上働くケースがあっても、雇用保険の加入条件を満たしたことにはなりません。
「31日以上雇用される見込みがある」と判断されるのは、以下のような場合です。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
- 雇用契約に契約更新の規約がないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
学生は基本的に雇用保険の加入対象者とはなりません。しかし、定時制や夜間学校などに通う学生は、例外的に加入することができます。
2-3. 【補足】政府は雇用保険の加入条件の緩和を検討している
令和5年12月の第189回職業安定分科会雇用保険部会では、働き方や生活の在り方の多様化が進んでいることを踏まえ、雇用のセーフティネットの拡大に関して議論がおこなわれました。見直し内容として、週の所定労働時間の条件を「20時間以上」から「10時間以上」に変更することを検討しています。
正式に決定することになれば、雇用保険の加入条件を満たす労働者が増えることになります。そのため、企業における雇用保険加入手続きの負担が大きくなる可能性があります。今後の雇用保険の適用拡大に関する政府の動きについて随時チェックしておくことが大切です。
3. 雇用保険の被保険者の種類

雇用保険は、雇用形態によって加入条件が変わることはありません。しかし、年齢や業務内容・期間などに応じて、4つの種類に区分されます。ここでは、雇用保険の被保険者の種類について詳しく紹介します。
3-1. 一般被保険者
雇用保険の加入条件を満たしいる正社員や契約社員、パート・アルバイトなどで、「高年齢被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」に該当しない場合は、一般被保険者となります。
3-2. 高年齢被保険者
2017年1月の雇用保険の適用拡大により、年齢制限がなくなり、65歳以上の高齢者も雇用保険の適用対象となりました。雇用保険の加入条件を満たす65歳以上の労働者で、「短期雇用特例労働者」「日雇労働被保険者」に該当しない場合は、高年齢被保険者となります。なお、雇用保険に加入している64歳以下の労働者が65歳になったら、自動で高年齢被保険者に移行するので、特別な手続きは不要です。
3-3. 短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される労働者のうち、下記に該当しない場合は、短期雇用特例被保険者となります。
- 4カ月以内の期間を定めた雇用
- 週の所定労働時間が 30 時間未満
短期雇用特例日保険者が失業した場合、「特例一時金」が支給されます。なお、短期雇用特例被保険者が同じ勤務先で雇用される期間が1年以上になると、「一般被保険者」もしくは「高齢被保険者」になるので注意が必要です。
第三十八条 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 四箇月以内の期間を定めて雇用される者
二 一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
3-4. 日雇労働被保険者
日々雇用される労働者や、30日以内の期間を定めて雇用される労働者は、日雇労働被保険者となります。日雇労働被保険者が失業した場合、「日雇労働求職者給付金」が支給されます。
第四十二条 この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一 日々雇用される者
二 三十日以内の期間を定めて雇用される者
4. 雇用保険が適用されないケース

雇用保険が適用されないケースは、雇用保険の加入条件の裏側を考えれば分かります。つまり、以下のような条件を満たす場合には雇用保険は適用されません。
- 週の所定労働時間が20時間未満である
- 31日以上雇用される見込みがない
- 学生である(定時制や夜間学校などを除く)
ただし、雇用保険法第6条により、これまでに説明した雇用保険の加入条件を満たしているとしても、雇用保険が適用されないケースもあります。ここでは、雇用保険が適用されないケースについて詳しく紹介します。
4-1. 国・都道府県・市区町村の公務員およびこれらに準ずる事業に雇用されている
公務員は、雇用保険の対象外です。雇用保険は労働者が失業した場合でも安心して暮らせるための制度ですが、公務員は一般のサラリーマンと異なり、リストラにあったり勤務先が倒産してしまったりするリスクが非常に低いことが、雇用保険の適用除外理由として挙げられます。なお、公務員の場合は、雇用保険の失業手当の代わりに、退職手当が支給されます。
4-2. 季節的業務に関する短期雇用である
夏の海やキャンプ場、冬のスキー場やスケートリンクなど、季節限定で雇用される場合があります。このような場合は、短期特例被保険者に該当しなければ、雇用される期間が31日以上であっても、雇用保険の対象となりません。
ただし、もともと予定されていた期間を過ぎても雇用が継続し、そのまま仕事を続けることになった場合は、雇用保険の対象となるケースがあります。その場合の雇用保険加入期間は、長期雇用に切り替わったタイミングからとなります。
4-3. 船員保険の被保険者である
船員保険の被保険者は、原則として雇用保険の対象になりません。船員としての勤務は、一般的に働く場合の勤務体系と異なり、そのことを踏まえたうえでの賃金水準となっています。そのため、1年を通じて船員として雇用されない場合は雇用保険の適用除外となります。ただし、それ以外で1年以上の雇用が認められていれば、雇用保険の対象となるので注意が必要っです。
ここまで雇用保険の対象者を確認しましたが、対象となる場合どのような手続きをおこなうのかがよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて、当サイトでは雇用保険を含む社会保険手続きの方法を一冊にまとめた資料を無料でお配りしています。雇用保険手続きが正しくできているか不安な方はこちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご活用ください。
5. 雇用保険の加入手続きの方法

事業主が初めて加入条件を満たす従業員を雇用する場合、雇用保険に加入させる必要があります。まずは保険関係成立に関する手続きをすませましょう。その後、所轄のハローワークに「事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
新しく従業員を雇用する場合は、その都度、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出しなければなりません。なお、提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。提出方法には「郵送」「窓口持参」「オンライン」の3種類があります。
提出後、ハローワークから交付される「雇用保険被保険者証」は、事業主から本人に渡しましょう。
6. 雇用保険の加入における注意点

雇用保険の加入については多くの注意点があります。ここでは、雇用保険の加入に関して押さえておきたいポイントについて詳しく紹介します。
6-1. 雇用保険の加入条件から外れる場合
アルバイトやパートで働く人などは、途中で週の所定労働時間などの就業条件が変わるケースもあるかもしれません。これにより、雇用保険の加入条件を満たさなくなる従業員が発生することもあります。
このような場合、雇用保険脱退の手続きをおこなう必要があります。事業主は、従業員が雇用保険の加入条件を満たさなくなった日の翌日から10日以内に、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。
雇用保険の被保険者でなくなると、失業給付などを受けられなくなる恐れがあるので、きちんと従業員に周知することが大切です。
6-2. 雇用保険の二重加入に注意する
パートやアルバイトを掛け持ちしている人や、正社員で副業をおこなっている人などは、複数の会社で雇用保険の加入条件を満たすケースもあるかもしれません。しかし、雇用保険は同時に2つ加入することができません。
そのため、1つの会社のみ雇用保険の加入手続きをする必要があります。二重加入とならないよう、雇用保険に加入させる際は、ダブルワークしていないかどうかも確認するようにしましょう。
6-3. 雇用保険の加入義務を怠った場合には罰則がある
雇用保険法第7条により、雇用保険に加入させるのは、事業主の義務です。加入条件を満たすのに、雇用保険に加入させなかった場合には、雇用保険法第83条により、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課される恐れがあります。そのため、雇用保険の加入条件をきちんと把握したうえで、正しく加入手続きをおこないましょう。
第七条 事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
7. 雇用保険の加入条件は正確に把握しておく必要がある

労働者が決められた条件を満たす場合、企業はその労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
雇用保険への加入義務は雇用形態で決まるわけではないので、「正社員だから加入」「パートだから加入しなくてよい」というように判断するのでなく、それぞれの労働者に応じて適した判断をしなければなりません。
雇用保険が適用されないケースも細かく定められているので、それぞれの条件に関しては正確に把握しておきましょう。









