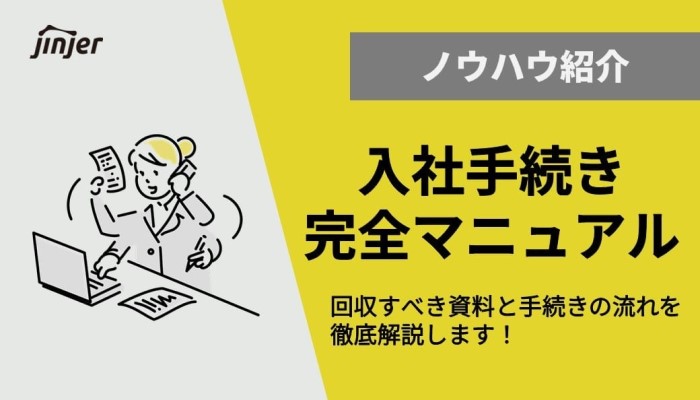入社手続きには、年金手帳や雇用保険被保険者証など、多くの必要書類が必要です。
入社手続きには、年金手帳や雇用保険被保険者証など、多くの必要書類が必要です。
また、社会保険や雇用保険など、届出の期限が設けられている加入手続きもあるため、適切で迅速な処理が求められます。
今回は、入社手続きに必要な書類一覧と手続きの流れ、メールや添え状などのルールを解説します。
関連記事:入社手続きで必要な書類や準備とは?案内方法や業務フローを紹介
入社手続きは社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など、対応しなくてはならない項目が多くあります。
そのため、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、遅れ等が発生してしまうと、該当の従業員に迷惑をかけてしまうだけでなく、会社への不信感を抱かせてしまうことに繋がりかねません。
そのため、確実に滞りなく入社手続きを進める必要があるでしょう。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
2024年4月からの労働条件明示ルールの変更にも対応しているので、この資料1つでチェックすることができます。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 入社手続きの必要書類

入社手続きの書類には、企業が準備するもの、採用内定者から提出してもらうもの、あるいはその両方が必要となるものの大きく3種類あります。
入社手続きをおこなう際は、必要書類の確認と合わせて、使用者と内定者のどちらが関与する書類なのかを書類別に確認しておくとよいでしょう。
1-1. 【共通】労働条件通知書
労働条件通知書とは、従業員を採用する際、会社が従業員に対して交付する労働条件を記載した書類です。
労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条により、使用者は労働者に労働条件通知書を交付することが義務付けられています。違反すると、罰金や懲役といった罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。
労働条件通知書は、労働契約を締結するタイミングで渡す必要があるため、内定日や入社日に必ず交付するようにしましょう。
1-2. 【共通】年金手帳(基礎年金番号)
厚生年金の加入手続きには、年金手帳に記載されている「基礎年金番号」が必要です。
年金手帳の保管は「本人」「企業」どちらでも構いません。従業員自身が保管する場合は、一度原本を提出してもらい、企業側がコピーを取ったのち返却します。企業が保管する場合は、従業員から原本を預かり、退職する際に返却します。
なお、2022年4月より年金手帳の交付が廃止されたため、初めて年金制度に加入する場合、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が発行されます。また、年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合は、手続きすることで、基礎年金番号通知書が再発行されることも覚えておきましょう。
1-3. 【共通】給与振込先の届書
従業員の給与振込先として、金融機関の口座番号を確認するために必要な書類です。企業が用意した届出に、指定金融機関の支店名・店番号・口座番号・口座の名義人など、必要事項を記入したうえで提出してもらいます。
給与振込先の情報がわかれば良いので、システムや第三者が閲覧できないアンケート機能などで提出してもらうことも可能です。企業によっては、通帳のコピーを提出してもらう場合もあります。
1-4. 【共通】源泉徴収票
前の職場を退職後、同じ年度に自社に中途採用された従業員や新卒採用の社員で入社する年の1月から入社月までにアルバイトなどで収入を得ていた人に対しては、年末調整のために源泉徴収票を提出してもらう必要があります。
源泉徴収票は、年間の給与の支払額と、それに対する所得税や復興特別所得税の税額を証明する書類です。正しい所得税額を再計算するためのものなので、必ず提出してもらいましょう。
前の職場を退職時に渡されているはずですが、もし受け取っていない、または紛失してしまったという場合は、前の職場に再発行してもらうよう伝えましょう。
1-5. 【共通】扶養控除等申告書
税金関係の手続きをおこなう際に必要です。配偶者や扶養家族の有無を確認し、源泉徴収する所得税を算出するために用います。企業側で扶養控除等申告書の用紙を用意し、採用内定者が必要事項を記入の上で提出してもらいます。
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類などの一定の書類を除き、押印を必要としないとされたため、扶養控除等申告書への押印は必須ではありません。
また、扶養控除等申告書は電子申請が可能なので、オンライン上で従業員に必要事項を記入してもらい、書類作成をすることも可能です。
扶養控除等申告書は採用内定者に配偶者や扶養家族がいない場合でも提出が必要なので、全員に提出してもらいましょう。
1-6. 【共通】マイナンバー
マイナンバーとは、住民票を持つ日本国内のすべての人に付与される12桁の番号です。社会保険加入や納税の手続きなどに、マイナンバーを記載する必要があり、事業主は適切に管理する義務があります。
マイナンバーは、マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票、個人番号通知書などで確認することが可能です。マイナンバーカードを取得している場合は両面のコピー、取得していない場合はマイナンバーを確認できる書類と本人確認書類(運転免許証など)のコピーを提出してもらいましょう。
1-7. 【中途】雇用保険被保険者証
中途採用の従業員で、以前雇用保険に加入経験がある場合は、雇用保険の資格取得手続きに「雇用保険被保険者番号」の確認が必要です。対象の中途社員には入社の際に雇用保険被保険者証を提出するように伝えましょう。
1-8. 【扶養家族がいる場合】健康保険被扶養者異動届
扶養家族がいる採用内定者の場合、社会保険の手続きに健康保険被扶養者異動届が必要です。届出書は企業が用意し、必要事項を記入したものを提出してもらいましょう。
こちらも電子申請を活用して紙のやり取りを減らすことができます。
2. 企業によっては提出が必要な書類
 企業によっては、次のような書類を提出してもらう必要があります。
企業によっては、次のような書類を提出してもらう必要があります。
2-1. 入社誓約書
企業が定めた就業規則や機密保持・守秘義務などを記載した契約書に、遵守を宣誓する証として署名捺印して提出してもらいます。なお、入社誓約書は法律で義務付けられている書類ではありません。
そのため、会社に入社誓約書を提出した後でも、内定辞退することは可能です。しかし、入社誓約書は、入社の意思確認として用いられることが多いため、入社を辞退する場合は入社誓約書の提出前に会社へ伝えるようにしましょう。
2-2. 雇用契約書
雇用契約書は、勤務時間や給与、休日など、労働条件について明記された書類です。契約を取り交わした証拠として、使用者(企業)と労働者(従業員)が署名捺印し、使用者が保管します。なお、法律で発行が義務付けられている「労働契約通知書」と兼用で、「労働条件通知書兼雇用契約書」として交付するケースもあります。
2-3. 住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書は、住民税に関する手続きをおこなう際に使用します。採用内定者の住所が履歴書と同じであることを確認します。住民票記載事項証明書は、自分の住んでいる市区町村の役所や、行政サービスの窓口で申請・発行することが可能です。
2-4. 身元保証書
従業員が故意や過失によって企業に損害を与えたとき、その賠償ができない場合、連帯して賠償責任を負う身元保証人が必要です。身元保証書は、その約束として、身元保証人の署名捺印をもらうために必要な書類です。
一般的には従業員の両親をたてることが多いですが、企業ごとに細かい条件を設けることも可能です。
2-5. 健康診断書
採用内定者の健康状態を把握するために、入社前3ヵ月以内、または入社後3ヵ月以内の健康診断書を提出してもらいます。
労働安全衛生法では、使用者(企業)が労働者(従業員)に対して「雇い入れ時の健康診断」を実施することが義務付けられています。
企業は健康診断をおこなう病院と日時を指定し、採用内定者に定められた検査項目を全て受けてもらう必要があります。
2-6. 従業員調書
従業員調書とは、人事管理をするための書類です。採用内定者の個人情報を記入して提出してもらいます。最近では提出を求める企業も少なくなり、履歴書が代用されることや人事管理システムなどで従業員情報を収集・管理する企業が増えています。
2-7. 卒業証明書・卒業見込証明書
卒業証明書(卒業見込証明書)とは、履歴書に記載されている学歴が正しいものかどうかを確認するため、主に新卒、第2新卒の採用内定者に提出してもらう書類です。卒業証明書・卒業見込証明書の取得方法は、所属している学校によって異なります。
2-8. 成績証明書
成績証明書とは、学校での履修科目や評価が記載された書類です。成績証明書は、卒業できるかどうかや内定者の人柄などを確認するために用いられます。成績証明書の取得方法も、卒業証明書と同様で、学校によって異なるので、所属する(していた)学校に確認してみましょう。
2-9. 免許・資格関連の証明書類
特定の免許や資格の取得を採用条件としている場合、または資格手当が発生する場合、免許や資格を保有していることを証明する書類を提出してもらいます。
2-10. 退職証明書
退職証明書とは、従業員が確かに退職したことを企業が証明する書類です。複数の会社に所属していないかを確認するため、退職証明書を求められるケースがあります。労働基準法第22条により、従業員が請求した場合、企業は退職証明書を交付しなければなりません。
3. 入社手続きはいつ何をする?企業が入社手続きをおこなう流れ
 入社手続きの基本的な流れは次のとおりです。
入社手続きの基本的な流れは次のとおりです。
- 入社日までに入社手続きの案内を郵送またはメールで通知する
- 入社日に必要書類を提出してもらう
- 雇用開始日から法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)を作成する
- 雇用開始から5日以内に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きをおこなう
- 雇用開始の翌月10日までに雇用保険の加入手続きをおこなう
- 特別徴収の場合は住民税の申告手続きをおこなう
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、労働基準法によって作成と保管(原則3年間)が義務付けられている書類で、「法定三帳簿」とよばれています。
新入社員を採用した際は、まずこれらの帳簿を必ず作成しましょう。
社会保険の加入条件を満たしている場合は、所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出し、社会保険の加入手続きをおこないます。
雇用保険の加入手続きは、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。いつでもどこでも提出できる電子申請を利用すると、ハローワークに出向かずとも社会保険加入手続きが可能になります。
また、中途入社した従業員が住民税の特別徴収を希望した場合は、納税先の市町村に「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を提出し、申告手続きをおこないましょう。このほかにもあわせておこなうべきことを確認しておくことで、スムーズに入社手続きをすることができます。当サイトでは、入社手続きの流れとおこなうべきことをまとめたマニュアルを無料で配布しています。
漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードして、ご活用ください。
3-1. 入社手続き書類を郵送する場合の対応
入社手続き書類を郵送によって送り、提出させる場合は、確実に届いたかどうかが確認できるように、郵便物を追跡できる簡易書留や特定記録郵便で送るようにしましょう。ただし、雇用保険被保険者証や年金手帳は重要な書類なので、郵送によるやりとりを避けて、出社時に提示してもらうようにします。
実際に郵送する際は、記入してもらう必要のある書類を準備し、返送用封筒とともに送ります。また、送付状(添え状・送り状)を同封することがマナーとされています。送付状には、書類を郵送する際の挨拶や、内容物がきちんと含まれているかの確認として使用されます。送付状には、下記の項目が記載されているかチェックしましょう。
- 日付
- 宛名
- 差出人情報
- 頭語・結語
- 本文
- 同封書類の名称と部数
書類が返送されたら、書類がそろっているかや署名・捺印の有無を確認することが大切です。
3-2. 入社手続き書類の書類をメールで依頼する場合の対応
入社手続き書類の送付をメールで依頼する場合には、「相手にとって理解しやすい文面」であることを意識しましょう。
メールには、「提出してほしい書類」「提出期限」「提出における注意事項」を必ず明記します。こちらが伝えたい内容を確実に伝えるために、以下のようなポイントに注意しましょう。
- 件名は明確かつ具体的にする
- 宛名・差出人を正しく記載する
- メールの冒頭は挨拶文やお礼文にする
- 採用結果を通知する
- 別記をわかりやすく記載する
- 結びの挨拶で締めくくる
5の「別記」とは、入社日や添付書類、入社日までに内定者が準備すべきことなどをまとめたものです。内定者が準備を進めやすいように必要書類を表などで整理し、注意するポイントや提出期限なども明確にしておきましょう。
入社手続きがスムーズに進まないと内定者が不安を感じ、入社をためらう可能性もあります。メールの文面や別記を工夫して丁寧にフォローし、入社への意欲を高めましょう。
また、疑問点があれば担当者に連絡できるように、連絡先や担当者の名前も記載するようにしましょう。
3-3. 入社手続き書類は電子化が可能
前述の通り、入社手続き書類は電子化することが可能です。2019年4月に紙での交付が法律で義務化されていた「労働条件通知書」の電子交付が解禁されたことによって、入社手続きに必要な書類は全て電子化が可能になりました。
健康保険・厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険などの申請手続きをオンライン上でおこなうことで、書類作成・管理にかかる時間や手間、郵送代、書類提出のために行政機関に出向くことなどを削減できます。
また、今までは人事書類が会社にあることで一般的に人事は難しいとされていたテレワークも人事書類の電子化によってしやすくなります。
電子申請で入社手続きに必要な書類を作成する方法をマニュアル化したものが厚生労働省のホームページでまとめて解説されているため、以下のリンクから確認してみてください。
また、人事管理システムの中には、従業員に登録してもらった情報から自動で書類を作成して電子申請までおこなうことができるものもあります。入社手続きの効率化をしたい企業は導入を検討してみると良いでしょう。
関連記事:人材採用後の入社手続きマニュアル!基本的な流れとおさえておくべき2つのポイント
4. 入社手続き書類でよくある失敗例やお悩みポイント

入社手続きに必要な書類を集める際に注意しなければならないのが、社会保険や雇用保険の手続きが書類の提出期限がある点です。「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」の提出期限は雇用開始から5日以内、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出期限は雇用した月の翌月10日までと定められています。
例えば、雇用保険の手続きが遅れて期限を過ぎてしまった場合、雇用を開始した日から手続きをおこなった日までの期間の賃金台帳と出勤簿と、遅延理由書を作成して提出しなければなりません。
手続きが遅れてしまうと余計な業務が増えるだけでなく、従業員の生活にも影響を与えてしまうため、迅速な対応が求められます。
4-1. 入社手続き書類に必要な印鑑の種類は?
入社手続き書類を作成する際、押印を求められることがあります。印鑑には、「実印」「銀行印」「認印」といった種類があります。そのため、どの印鑑を使用すれば悩まれる人もいるかもしれません。
結論として、基本的に「認印」を使用して問題はありません。ただし、企業によっては、印鑑が確かに本人のものであることを証明するため、印鑑証明書を求められるケースがあります。このような場合は「実印」が必要になるため注意が必要です。企業側は「実印」を求める場合、間違えないようきちんと周知することが大切です。
4-2. 入社手続き書類を提出する3つの方法
これまでに紹介した入社手続きの書類には3つの提出方法があります。
- 内定者が持っているものを原本のまま提出するもの
- 会社が指定する所定のフォーマットに必要事項を記入(捺印)して提出してもらうもの
- 内定者もしくは企業が原本をコピーして提出するもの
それぞれの書類の一例を紹介します。
| 入社手続きの書類の提出方法 | 書類の一例 |
| 内定者が持っているものを原本のまま提出するもの |
|
|
会社が指定する所定のフォーマットに 必要事項を記入(捺印)して提出してもらうもの |
|
| 内定者もしくは企業が原本をコピーして提出するもの |
|
原本のまま提出してもらう書類は手元にあればすぐに提出できますが、紛失しているケースも少なくありません。そのため、内定者が提出する書類は早めに通知し、期限内に不備なく提出してもらえるようにしましょう。
また、内定者に記載してもらってから提出してもらう書類は、記入ミスや漏れが起こりがちです。記入例などを添付しておくとスムーズに記入でき、提出後のチェックや差し戻しの手間も省けるでしょう。
4-3. 入社手続き書類に関するトラブルの対処法
入社手続きにおいて必要書類が揃わず、頭抱える担当者の方も少なくないでしょう。
必要書類が揃わない場合は、まずはその理由を確認し、いつまでに揃いそうかを確認しましょう。
ただ単に、内定者が用意し忘れていたというケースであればそれほど問題はありません。しかし、紛失などにより用意できていない場合は、前職や役所に依頼して書類を再発行してもらわなくてはなりません。再発行には時間がかかることもあるので、あらかじめ書類を紛失している場合の対処法も通知しておくとよいでしょう。
入社手続きの書類は、内定者を丁寧にサポートすることで揃いやすくなるので、社内のサポート体制を強化しておくことをおすすめします。
5. 必要書類や業務フローを把握し入社手続きをスピーディーに

入社手続きは、社会保険や雇用保険、税金関係の手続きなど、新入社員の生活にかかわる手続きが多いため、迅速かつ適切な対応が必要です。
しかし、手続きには必要な書類が多く、新卒採用時期などは多くの採用内定者の手続きに対応しなければならないため、担当者に大きな負担がかかるでしょう。
また、必要書類が揃わない、不備があるなどのケースも少なくないため、内定者へのサポート体制を整える必要もあります。
入社手続き業務を削減し、優秀な人材の採用や人事戦略策定などに時間を使うことができれば、企業の成長に繋がります。
入社手続きを適切に、スピーディーにおこなうには、必要書類や業務フローを把握し、提出期限がある手続きを優先的に処理しましょう。また、電子申請の利用や人事管理システムを導入することで、業務を効率化できるため、活用してみてはいかがでしょうか。
入社手続きは社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など、対応しなくてはならない項目が多くあります。
そのため、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、遅れ等が発生してしまうと、該当の従業員に迷惑をかけてしまうだけでなく、会社への不信感を抱かせてしまうことに繋がりかねません。
そのため、確実に滞りなく入社手続きを進める必要があるでしょう。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
2024年4月からの労働条件明示ルールの変更にも対応しているので、この資料1つでチェックすることができます。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きをおこないたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。