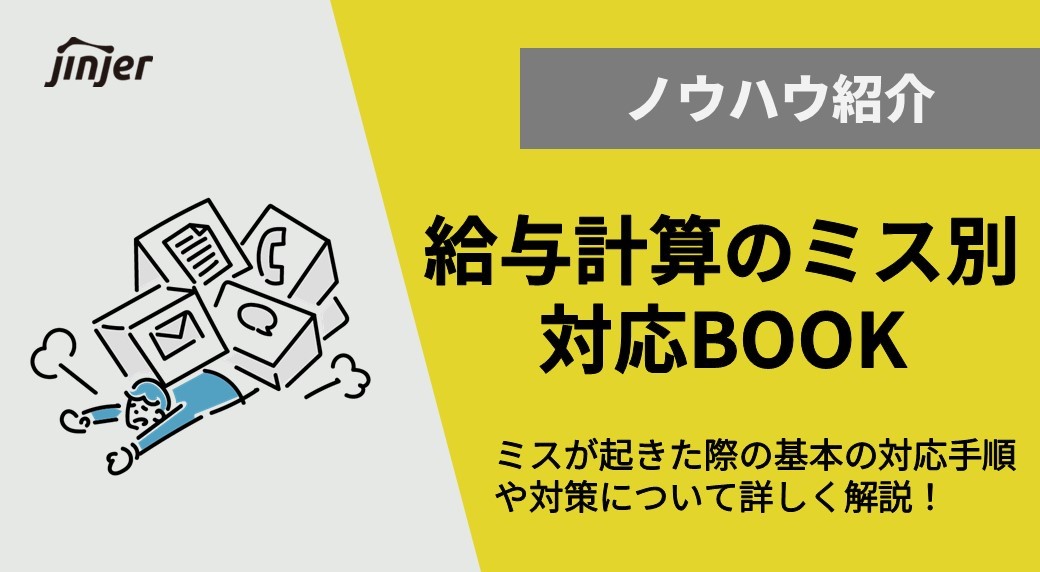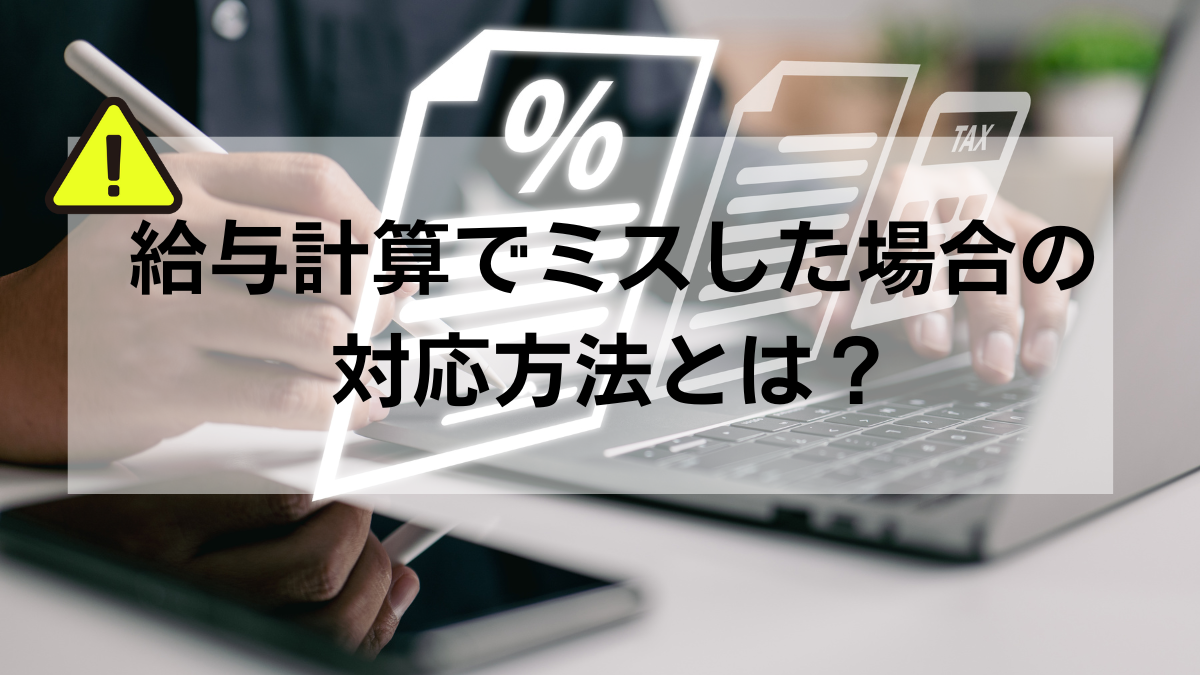
給与計算を実施するには、割増賃金や社会保険、源泉所得税といったさまざまな知識が必要になります。また、給与計算ミスは、些細なヒューマンエラーなどで起こることも多いです。そのため、人的ミスを防ぐための対策が必要となります。この記事では、給与計算ミスの原因や事例、間違いが発生してしまったときの対応と防止対策についてわかりやすく解説します。
給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。
当サイトでは、給与計算で生じるミスの対処方法を場合別に紹介した「給与計算のミス別対応BOOK」を無料で配布しております。
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・給与計算業務のチェックリストがほしい方
・給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
上記に当てはまるご担当者様は、「給与計算のミス別対応BOOK」をぜひご覧ください。
1. 給与計算ミスが起こったときの対応

給与計算にミスが発生してしまった場合には、誠意が伝わるようすみやかに謝罪をし、過不足分の給与の精算をおこないましょう。ここでは、具体的な対応フローについて解説します。
1-1. 発覚時点で本人に報告・謝罪する
給与計算のミスが発生したらまずおこなうべきなのが、対象者本人に通知し、謝罪することです。丁寧な通知や謝罪がなければ、信頼関係にも大きく影響を及ぼします。給与計算にミスが発覚した際に、メールなどにて事実を伝え、お詫びを入れることが重要です。お詫びメールの例文は、以下の通りです。
| 件名:【重要】給与計算の誤りについてのお詫び |
| 〇〇さん お疲れさまです。〇〇部の〇〇です。 先月の月分の給与支払いにつきまして、 (ミスの内容例) ・〇月〇日の休日労働手当の計算に誤りがありました。 ・〇月〇日の年次有給休暇を欠勤として扱ってしまい、給与が反映されていませんでした。 (対応策例) ・謹んでお詫び申し上げますとともに、差額に関しましては〇月分の給与支給にて調整いたします。 ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。 二度とこのようなことのないよう、給与計算の誤りを防止するべく体制を強化してまいりますので、何卒ご容赦のほどお願い申し上げます。 |
1-2. 給与明細を訂正する
給与計算ミスについて通知や謝罪をおこなったら、正しい給与明細を作成します。給与明細のどの部分にミスがあったのかを詳細に伝えることで、本人にも安心感が生まれます。所得税や保険料の徴収についても訂正しなければならないので、再度ミスが生じないよう、落ち着いて対応するようにしましょう。
関連記事:給与明細とは?必須項目と注意点、給与計算の流れを詳しく解説
1-3. 過不足を精算する
本人への謝罪と正しい給与明細の作成が終了したら、実際に過不足の精算をおこないます。なお、労働基準法第24条の「賃金支払いの5原則」に注意が必要です。給与が少なく支給されている場合、「全額払いの原則」に違反している可能性があります。できる限り給与計算ミスが発生した当月中に清算をおこなうことが望ましいです。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(省略)
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(省略)
関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介
1-4. 給与計算ミスにより追加支給が必要な場合
支給すべき給与に対して、支払った給与が不足していた場合、追加で本来支給すべき差額を支払う必要があります。不足額の精算には主に2つの対応方法があります。ここからは、それぞれの対応方法について解説します。
1-4-1. 当月に現金精算する
当月中に現金で不足分を支給することは可能です。ただし、不足額を支給することで「源泉所得税」や「雇用保険料」などの徴収額が増える可能性もあるため、これらの控除額も加味したうえで、追加支給する金額を計算しましょう。精算手順は、次のとおりです。
- 誤って支給した月分の給与計算をやり直す
- 誤って支給してしまった給与支出額を、計算し直した正しい給与額から差し引き、差額(不足額)を算出する
- 正しい給与明細と、現金で不足額を用意し、従業員に支給する
当月に不足額を精算する場合も、給与計算ミスが発覚した時点で従業員にきちんと周知するようにしましょう。
1-4-2. 翌月の給与にて精算する
翌月の給与支払いの際に、通常通りの支給額に加えて、前月分の不足額を追加して支給することで、不足分を清算することも可能です。ただし、「労使協定で定められている」「本人の合意を得ている」といった一定の要件を満たす必要があります。また、翌月の給与明細の項目には、調整金などとわかりやすく記載することが大切です。
1-4. 給与計算ミスにより返金が必要な場合
給与の計算ミスによって過剰に給与を支給してしまい、従業員から回収が必要となる場合もあるかもしれません。返金してもらうための手段として、主に2つの対応方法があります。ここからは、それぞれの対応方法について解説します。
1-5-1. 当月に過払い分を回収する
不足額を支給する場合と同様で、「源泉所得税」や「雇用保険料」への影響が考えられるため、控除額を考慮して過払い額を計算することが重要です。手順は以下の通りです。
- 誤って支給した月分の給与計算をやり直す
- 誤って支給してしまった給与支出額から、計算し直した正しい給与額を差し引き、差額(過払い分)を算出する
- 正しい給与明細を用意し、過払い額を従業員から回収する
当月中に過払い分を返金してもらう場合、支払方法や支払期日などをきちんと伝えることが大切です。また、振り込みの際に支払手数料がかかる場合は、基本的に会社負担となります。
1-5-2. 翌月の給与から控除する
翌月の給与から、過払い分の給与を控除する対応も可能です。翌月は通常の給与計算処理をおこない、給与明細の項目には過剰に支払っていた分の金額を「調整金」として、マイナス計上します。
1-6. 不足分の保険料の申請や追加納付
給与計算ミスにより、社会保険料の徴収額にも誤りが生じた場合、「翌月の同項目で精算する」「当月に精算する」「会社が負担する」の3つの対応方法があります。
翌月の同項目で精算する方法では、徴収額が不足していた場合は翌月の控除額に上乗せし、過剰に徴収していた場合は翌月の控除額から差し引きます。当月に精算する方法では、控除額に不足がある場合は追加で徴収し、過剰に徴収していた場合は返金します。会社が負担する方法では、個人負担の不足額は代わりに会社が負担し、「現物給与(課税対象)」として処理します。
関連記事:社会保険料とは?パートも加入対象?計算方法や注意点などをわかりやすく解説!
2. 給与計算ミスが発生したときの注意点

給与計算ミスが発生したら素早く対処することが大切です。ここでは、給与計算ミスが生じた場合の注意点について詳しく紹介します。
2-1. 違法となり罰則が課される恐れがある
給与計算ミスにより、労働基準法第24条「賃金支払いの5原則」に抵触すると、罰則を受ける可能性があります。労働基準法第120条により、労働基準法第24条に違反すると、30万円以下の罰金のペナルティが課せられます。罰則を受けないためにも、給与計算ミスに気づいたら法律に基づき素早く対処するようにしましょう。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第二十三条から第二十七条まで、(省略)の規定に違反した者
2-2. 過払い請求には時効がある
民法第166条により、給与計算ミスで賃金を支払い過ぎた場合、その事実があったときから10年もしくは、その事実に気づいたときから5年を経過すると、時効により権利が消滅します。また、労働基準法第115条により、給与未払いなどにより、従業員が賃金を請求できる権利の時効は5年です。ただし、経過措置が設けられており、当分の間は3年間とされています。
このように、過払い賃金や未払い賃金については時効が定められているので、正しく法律を理解したうえで、適切に対応するようにしましょう。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
2-3. 給与計算ミスによる遅延損害金とは?
遅延損害金とは、金銭の支払いが遅れた際に損害賠償として支払う賃金を指します。実際は従業員と会社の交渉によって差額のみの支払いでおさまることが多いです。しかし、遅延損害金が発生すれば、人件費の負担が大きくなります。そのため、給与計算ミスが発生しないよう、きちんと対策を講じることが大切です。
関連記事:給与計算でミスをしたら遅延損害金が発生する?対応・防止方法を紹介
3. 給与計算ミスのよくある原因

給与計算ミスが発生すると、罰則などの大きなリスクにつながる恐れがあります。なぜ給与計算ミスが発生してしまうのでしょうか。ここでは、給与計算ミスが発生する原因について詳しく紹介します。
3-1. 働き方の多様化
近年では働き方改革の影響もあり、多様な働き方が推進されています。正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなど、多様な雇用形態を採用している企業も少なくないでしょう。また、裁量労働制や変形労働時間制、フレックスタイム制などの柔軟な働き方を導入している企業も増えています。
このように、従業員のニーズにあわせて、さまざまな働き方を用意するのは、生産性を向上させたり、従業員満足度を高めたりするために有効的です。しかし、従業員一人ひとりの勤務形態にあわせて勤怠管理や給与計算をおこなわければならないので、給与計算ミスが発生しやすくなります。
関連記事:裁量労働制とは?残業代や適用職種をわかりやすく解説
3-2. 複数人での作業
1人で給与計算業務をしている場合、自分の思うように工夫したり、体系化したりしながら作業をおこなうことができます。しかし、複数人で給与計算業務をする場合、きちんと情報共有できていないと、勤怠や給与のデータに正しい情報が反映されず、給与計算ミスが生じてしまいます。複数人で給与計算をおこなう場合、ルールを明確化し、業務の属人化が発生しないよう注意が必要です。
3-3. アナログでの作業
給与計算を手作業でおこなっている企業も少なくないでしょう。紙のタイムカードを集計する際や、電卓で給与を算出する際に、ヒューマンエラーが生じ、給与計算ミスにつながるケースがよくあります。
アナログ作業で給与計算をおこなう場合、二重チェック体制などを設けて、ミスを見逃さないようにすることが大切です。近年では、勤怠管理システムや給与計算ソフトといったITツールが普及しています。これらのツールを活用すれば、勤怠管理から給与計算までを自動化できるので、人的ミスを防止することが可能です。
関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介
4. 給与計算ミスが発生しやすい事例

給与計算ミスを発生させないためにも、よく起こる給与計算ミスの事例を把握しておくことが大切です。ここでは、給与計算ミスは、具体的にどのような事例で発生しやすいのかを詳しく解説します。
4-1. 労働時間の集計ミス
残業代を正しく計算するには、労働時間や残業時間を正確に把握する必要があります。労働時間は1分単位で計算されなければなりません。また、着替えや朝礼・終礼などの時間も、原則として労働時間に含まれます。労働時間を15分・30分単位で計算してしまっている場合や、労働時間に該当する時間を除外している場合は、給与計算ミスが生じます。まずは法律に基づき、勤怠管理や給与計算のやり方を正しく把握することが大切です。
関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!
4-2. 割増賃金の計算ミス
時間外労働や休日労働、深夜労働が発生すると、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は、従業員ごとに割増賃金の基礎となる賃金を算出し、対象になる割増率と労働時間を掛けることで計算できます。
基礎賃金は、手当なども考慮して算出する必要があります。また、割増率は法定外労働の種類によって異なります。複数の割増労働が重なるケースもあります。このように、割増賃金を計算するまでには、さまざまな工程があるので、給与計算ミスにつながりやすいです。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
4-3. 社会保険料の反映ミス
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料は給与から控除して納付します。そのため、社会保険料の計算間違いも給与計算ミスにつながります。
社会保険料は種類によって、個人負担と会社負担の割合が異なります。また、保険料率も改正などによって変わることがあります。さらに、介護保険料は40歳から支払い義務が生じます。そのため、介護保険の加入タイミングで給与計算ミスが起こりやすいです。
このように、社会保険料の反映ミスが生じると、給与計算にもミスが発生します。給与計算ミスを生じさせないためにも、社会保険の加入条件や計算方法をきちんと把握しておくことが大切です。
4-4. 中途入社と中途退社による日割り計算ミス
中途で入社したり、退社したりする場合の日割り計算で、給与計算ミスが発生するケースもよくあります。多くの場合、入社や退社は月初めまたは月末ですが、月の途中で入社したり退社したりすることもあります。その場合、給与は日割りで計算しなければなりません。また、日割り計算の場合は除外となる手当がでてくるので、計算も複雑になります。なお、社会保険料(雇用保険料は日割り)の計算は、月割りになります。
関連記事:雇用保険料率の計算方法とは?端数処理や賞与の取り扱いについても解説!
4-5. 扶養人数変更の反映漏れ
「子どもが社会人になった」「配偶者の収入が増えた」などの理由で扶養人数が変更になったと、従業員から申し入れがあったら、給与計算にも反映しなければなりません。源泉所得税額は、扶養人数を考慮した源泉所得税表を基に計算します。そのため、扶養人数変更について給与計算に反映しなかった場合は、給与計算ミスにつながります。なお、扶養人数の変更があったタイミングで従業員から申し入れがなければ、扶養人数の変更については年末調整で対応することになります。
関連記事:所得税は毎月変わる?仕組みやチェック項目を詳しく紹介
4-6. 役職手当や昇給の反映漏れ
役職や職務に応じて、手当の有無や給与の変動が発生する従業員も多いでしょう。担当者への情報共有が漏れていたり、従業員データに反映されていなかったりする場合、給与計算ミスへとつながりやすいため注意が必要です。
5. 給与計算ミスを防止するための対策

ここでは、給与計算ミスを防止するための対策について詳しく紹介します。
5-1. 給与計算スケジュールを見直す
給与計算をおこなうときのスケジュールが短ければ短いほど、余裕がなくなりミスが発生しやすくなります。そのため、改めて給与計算のスケジュールを確認して、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
給与締めの日から支給日までの日数を20日程度に設定するのが目安です。20日未満の場合には、給与締めの日を前倒しにするなどの対応を取ることで、切迫したスケジュールを見直すことができます。
5-2. 給与計算ルールを整備する
給与計算をおこなう際のルールの整備も、ミスを減らすためには有効です。会社によってはさまざまな手当あり、基準や対象者を細かく定めている場合もあります。複雑なルールは理解しづらく、共有や引き継ぎをおこなうときにも時間がかかります。給与計算ルールは、できる限りシンプルにし、理解しやすくすることがミスを防止するためのポイントです。
また、ルール作りとともに、給与計算ミスが発生しやすい項目についてチェックリストを作成したり、ダブルチェックの体制を設けたりするのもミスを減らすための一つの手です。当サイトでは給与計算でミスが発生しやすい項目のチェックリストを無料配布しております。チェックリストとともによくある給与計算ミスとその対応方法、ミスを減らす方法についても解説しているため、給与計算ミスを減らしたい方はこちらから「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードしてご覧ください。
5-3. 勤怠管理システムや給与計算ソフトを導入する
アナログでの勤怠管理や給与計算をおこなっていると、集計・計算の過程でミスが発生しやすいです。勤怠管理システムや給与計算ソフトを導入すれば、勤怠管理から給与計算までを自動化することができます。給与計算ミスを防止するだけでなく、業務を効率化することも可能です。
ただし、ITツールを導入・運用するには、時間やコストがかかります。まずは自社の課題を洗い出し、目的を設定したうえで、ニーズにあったシステムを選定することが大切です。
関連記事:給与計算ソフトおすすめ18選!特徴を徹底比較|2024年完全版
5-4. アウトソーシングを実施する
正しく給与計算を実施するには、細かな作業と専門性が必要になります。そのため、給与計算ミスをなくすため、アウトソーシングするのも一つの手です。アウトソーシングを活用することで、自社の給与計算担当者の負担を減らすこともできます。ただし、アウトソーシングを利用する場合、コストがかかります。予算や目的を明確にし、自社のニーズにあった給与計算代行業者を選定することが大切です。
関連記事:給与計算代行・アウトソーシングのメリット・デメリット・特徴など24サービスを比較
6. 給与計算ミスの原因はさまざま!対策を考えよう

給与計算は、導入している雇用形態や勤務形態が多いほど煩雑になります。また、割増賃金や社会保険料の計算もしなければならないので、専門的な知識が必要になります。給与計算ミスを防止したいと考えている人は、勤怠管理システムや給与計算ソフトなどのITツールの導入を検討しましょう。
給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。
当サイトでは、給与計算で生じるミスの対処方法を場合別に紹介した「給与計算のミス別対応BOOK」を無料で配布しております。
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・給与計算業務のチェックリストがほしい方
・給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
上記に当てはまるご担当者様は、「給与計算のミス別対応BOOK」をぜひご覧ください。