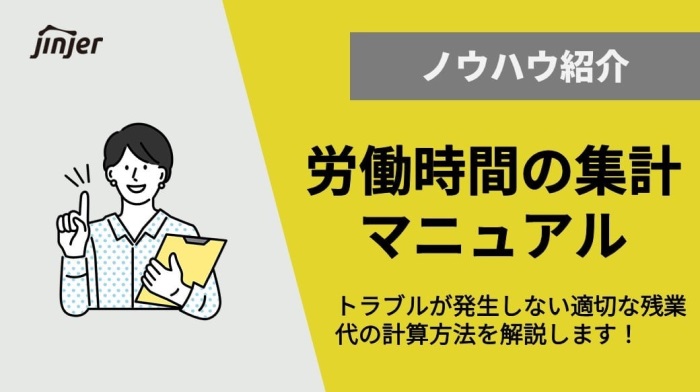法定労働時間を超えて働かせたり、休日・深夜に出勤させたりする場合は、その時間またはその日の労働について、割増賃金を支払うことが法律で義務づけられています。
割増賃金には状況に応じて複数の種類があるので、従業員に残業や休日出勤をさせる際は、割増賃金の種類と計算方法をよく理解しておきましょう。
今回は、割増賃金の種類や計算のポイント、従業員から割増賃金を請求された際に確認すべきことをまとめました。
労働時間の客観的で正確な管理ができていなければ、正しい残業代の計算ができず、未払いが発覚した場合には最悪、法律に違反する可能性があります。
当サイトでは、トラブルが発生しない適切な残業代の計算方法が知りたいという方に向けて、労働時間の集計マニュアルを無料配布しています。
「残業代の計算における打刻まるめが違法となるケースについて知りたい」
「自社の残業代の計算方法に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 割増賃金とは

割増賃金とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせる場合や、深夜・法定休日に働かせる場合に、割増して通常よりも多く支払う賃金のことです。
なぜ割増賃金が設けられているのでしょうか。また、割増賃金と残業代の違いについて気になる人もいるかもしれません。
ここでは、割増賃金の目的や、割増賃金と残業代の違いについて詳しく紹介します。
1-1. 割増賃金の目的
割増賃金の目的は、主に下記の2つです。
- 通常と異なる特別な労働(時間外労働・休日労働・深夜労働)をする労働者に対して補償をおこなう
- 使用者に対して経済的負荷を課すことで長時間労働といった過重労働を抑制する
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、人手不足から長時間労働が常態化している組織も少なくないです。従業員の健康と生活を守るために、割増賃金が設けられています。
1-2. 割増賃金と残業代の違い
割増賃金は、下記の3つのいずれかのケースに当てはまる場合に、法律に従って支払わなければなりません。
- 時間外労働(法定労働時間を超えて働かせる場合)
- 休日労働(法定休日に働かせる場合)
- 深夜労働(22時~5時の深夜に働かせる場合)
一方の残業代は、企業が就業規則などで独自で定める所定労働時間を超えて働かせる場合に支払う賃金のことです。割増賃金とは異なり、割増するかどうか、どの程度割増するかなどは企業が自由に決定できます。
たとえば、所定労働時間を7時間と設定している企業を考えてみましょう。週40時間を超えない範囲で、1日9時間勤務したとします。この場合、2時間分の残業代を支払う必要があります。
ただし、所定労働時間を超えるけれど、法定労働時間を超えない1時間分は割増賃金の支払いが不要です。残りの1時間は割増賃金を上乗せして給与を支払う必要があります。
このように、割増賃金と残業代は意味が重なるケースもありますが、異なる用語なので正しく理解しておきましょう。
1-3. 割増賃金について定めた法律
割増賃金については、労働基準法の第37条に記載されています。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
企業は同法に従い、割増賃金を正しく支給しなければなりません。なお、割増賃金率については後ほど詳しく解説します。
1-4. 割増賃金を支払わないことによる罰則
割増賃金を支払わないと、労働基準法の第119条により罰則を受ける可能性があります。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
上記の通り、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため、割増賃金は正しく支給しましょう。
2. 割増賃金には複数の種類がある

割増賃金は、状況に応じて大きく4つの種類に分類されます。ここでは、労働基準法をもとに、割増賃金の種類や割増率について解説します。
2-1. 時間外労働の割増賃金
時間外労働の割増賃金とは、労働基準法で定められた1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせた場合に支払う割増賃金のことです。なお、時間外労働の割増賃金率は25%以上と定められています。
時間外労働(残業)には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。法定内の時間外労働であれば、割増賃金は不要で、残業代のみ支払えば問題ありません。一方、法定外残業に該当する場合、割増賃金を上乗せした残業代を支払う必要があります。
2-2. 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金
時間外労働が月60時間を超えた場合、割増賃金率は50%以上となります。なお、中小企業に対しては2023年3月まで適用における猶予期間が設けられていました。
そのため、中小企業は猶予期間であれば、月60時間を超える時間外労働に該当する場合でも、割増率25%の適用で問題ありませんでした。しかし、2023年4月より中小企業にも適用が開始されたので、月60時間超残業に対してすべての企業が割増率50%を適用しなければなりません。
関連記事:残業が月60時間を超過すると割増賃金が増える?中小企業の猶予も解説
2-3. 深夜労働の割増賃金
深夜労働の割増賃金とは、夜勤をおこなわせた場合に支払う割増賃金のことです。なお、深夜労働の割増賃金率は25%以上と定められています。
労働基準法第37条4では、午後10時~翌午前5時(厚生労働大臣が必要と認める場合は午後11時~翌午前6時)までの労働を、深夜労働と定義しています。
2-4. 休日労働の割増賃金
休日労働の割増賃金とは、法定休日に労働者を働かせる場合に支払う割増賃金のことです。なお、休日労働の割増賃金率は35%以上と定められています。
労働基準法第35条に従い、使用者(4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者を除く)は労働者に対し、少なくとも週に1回の休日を与えなければなりません。これを法定休日といいます。休日労働は法定休日が対象であり、企業が独自で定める所定休日(法定外休日)は対象になりません。
たとえば、土日休みの週休2日制で、日曜日を法定休日としていた場合、土曜日の休日は企業が独自で定める所定休日となります。そのため、土曜日に休日出勤しても休日労働に対する割増賃金の適用は不要です。ただし、土曜日に法定外残業や夜勤をおこなった場合、時間外労働や深夜労働の割増賃金を適用する必要があります。
3. 割増賃金の計算方法とポイント

割増賃金の基本の計算式は、下記の通りです。
ここでは、割増賃金の具体的な計算方法や、割増賃金を計算するにあたって押さえておきたいポイントを解説していきます。
3-1. 割増賃金の基礎となる賃金を算出する
割増賃金を計算する際は、まず1時間あたりの賃金を算出する必要があります。1時間あたりの基礎賃金を、「割増賃金の算定基礎」「割増賃金の基礎となる賃金」とよぶこともあります。
月給制における基礎賃金の計算方法は以下の通りです。
※月平均所定労働時間 = ( 1年の日数 – 年間休日 ) × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月
基礎賃金を計算する際、一定の要件を満たす下記の手当は除外されるので注意が必要です。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説
3-2. 各種割増率の一覧
割増率は労働基準法第37条で規定されています。各条件における割増率は下記の通りです。
|
割増条件 |
割増率 |
|
時間外労働 |
25%(※月60時間を超えた場合は50%) |
|
深夜労働 |
25% |
|
休日労働 |
35% |
上記は定められた最低ラインであるため、上記を超える割増率であれば各社自由に設定することができます。
関連記事:割増賃金率の一覧を使って計算方法を徹底解説!割増率引き上げの条件とは?
3-3. 割増賃金の具体的な計算方法
ここでは、例を挙げて、割増賃金の具体的な計算方法を紹介します。割増賃金を計算する際のモデルは、次の通りです。
- 月給:40万円
- 1日の所定労働時間:8時間
- 1年の出勤日数:240日
- 手当:なし
- 時間外労働:80時間
- 深夜労働:0時間
- 休日労働:0時間
月平均所定労働時間
まずは、上記の式を使って月平均所定労働時間を算出しましょう。
月平均所定労働時間は、160時間であることがわかりました。
割増賃金の基礎となる賃金
次に、割増賃金の基礎となる賃金を算出します。先ほど求めた月平均所定労働時間(160時間)を使って、上記の式で計算しましょう。
割増賃金の基礎となる賃金は、2,500円であることがわかりました。
時間外労働に対する割増賃金
最後に、時間外労働に対する割増賃金を算出しましょう。時間外労働は合計80時間ですが、60時間分については25%の割増率が、20時間分については50%の割増率が適用されます。
この例の場合は、時間外労働に対して26万2,500円の割増賃金を支払う必要があります。
関連記事:割増賃金の計算方法を徹底解説!基礎賃金算出時の注意点とは?
3-4. 割増賃金の条件が重複した場合は割増率を引き上げて算出する
前述の通り、割増賃金にはいくつかの種類がありますが、所定の条件がそろえば複数の割増賃金が重複する場合もあります。割増賃金の条件が重複した場合は、下記のように割増率を引き上げて算出しなければなりません。
|
割増条件 |
割増率 |
|
時間外労働(月60時間以下)と深夜労働 |
50%(= 25% + 25%) |
|
時間外労働(月60時間超)と深夜労働 |
75%(= 55% + 25%) |
|
深夜労働と休日労働 |
60%(= 25% + 35%) |
なお、法定休日には法定労働時間の定義がないため、休日労働と時間外労働の割増率は重複しないので注意しましょう。
3-5. 割増賃金計算に関する端数処理
割増賃金の計算の際に端数が発生するケースもあります。下記のように、従業員が不利とならないような範囲で、事務を簡便にするものであれば、割増賃金の計算における端数処理は認められます。
- 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
- 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
- 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2.と同様に処理すること
上記の通り、1時間あたりの基礎賃金を算出する際や割増賃金を算出する際に、1円以下の端数が発生した場合は、50銭以上は切り上げ、50銭未満は切り捨てで計算します。
ただし、賃金は1分単位で算出して支払わなければなりません。15分単位・30分単位で丸めるのは違法となるので注意が必要です。
4. 割増賃金を適用する際に押さえておきたいポイント

割増賃金を適用する場合、注意しなければならない点がいくつかあります。ここでは、割増賃金を適用する際に押さえておきたいポイントを詳しく紹介します。
4-1. 「時間外労働」「休日労働」をさせるには36協定の締結が必要
法定労働時間を超えて働かせる場合や、休日出勤をさせる場合、36協定の締結が必要になります。36協定については、労働基準法の第36条に記載されています。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、36協定を結んだとしても、時間外労働の上限(月45時間・年360時間)があります。特別な事情がある場合、下記を満たす範囲で時間外労働の上限を延長させることが可能です。
- 時間外労働:年間720時間以内
- 時間外労働+休日労働 :月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内
- 月45時間超の時間外労働:年6回まで
特別条項付きの36協定を結ぶことで長時間労働が可能となりますが、残業や休日出勤が常態化すると、従業員の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。過重労働を抑制するため、適切に勤怠管理をおこなうことが大切です。
4-2. 給与形態によって割増賃金の計算は異なる
割増賃金の計算方法は、「月給」「週給」「日給」「時給」など、給与形態によって異なります。また、歩合制やみなし残業制、裁量労働制などを採用している場合、割増賃金の計算方法が変わるケースもあります。自社の給与計算の方法を適切に把握したうえで、法律に基づき、正しく割増賃金を計算することが大切です。
4-3. 割増賃金の代わりに代替休暇を付与できる
労働基準法第37条3では、月60時間を超える時間外労働をおこなった従業員に対し、割増賃金の代わりに有給休暇を付与できる代替休暇制度について定めています。
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
ただし、代替休暇制度を取り入れる場合、労使協定の締結が必要です。また、代替休暇を取得するかどうかは、従業員が選択できます。そのため、会社が割増賃金を支払いたくないからといって、従業員に代替休暇の取得を強制することはできません。
このように、代替休暇制度を上手く活用すれば、「従業員の健康促進」「コストの削減」といった労使ともにメリットを得られる可能性もありますが、注意点を正しく把握しておく必要があります。まずは代替休暇制度について正しく理解を深めましょう。
関連記事:残業が月60時間を超過すると割増賃金が増える?中小企業の猶予も解説
4-4. 管理監督者に時間外労働・休日労働の割増賃金を支払う必要はない
一般従業員と異なり、管理監督者に対して時間外労働・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり、重要な経営判断に関わる従業員のことです。管理監督者は、時間に関係なく重要な判断をおこなう必要があるため、労働基準法上の労働時間や休日などの規制を受けません。
ただし、管理監督者に該当するかどうかは、慎重に判断する必要があります。部長や所長といった肩書きがあったとしても、とくに経営に関わっていない場合などは、一般の従業員と同じ扱いとなり、割増賃金の支払いが必要です。なお、管理監督者であっても、深夜労働に対する割増賃金の支給はしなければならないので気を付けましょう。
4-5. 残業手当の一律支給には注意する
残業手当の一律支給には注意しましょう。面倒な残業代・割増賃金の計算を簡略化するために、実際の残業時間にかかわらず残業手当を一律支給する場合は、一定の基準を満たす必要があります。
まずは、残業手当を一律支給することについて、就業規則に明記しなければなりません。また、実際の残業時間から算出した残業代・割増賃金より残業手当が低い場合は、その不足分を支払う必要があります。
関連記事:固定残業代制度を正しく運用する3つのポイントを解説
4-6. パート・アルバイトも割増賃金の対象となる
割増賃金の対象となるのは、正社員だけではありません。パートやアルバイト、契約社員などについても割増賃金は発生します。時間外労働や休日労働、深夜労働が発生した場合は、正社員と同様の割増率で計算するようにしましょう。
5. 割増賃金を請求された際に確認すること

従業員から割増賃金を請求されたとき、確認すべきポイントは以下3つです。
- 月の労働時間が法定労働時間を超えているか
- 法定休日に出勤しているか
- 深夜帯に出勤しているか
いずれか1つ以上に該当する場合は、その労働時間に対して割増賃金を支払う必要があります。実際に未払いの割増賃金があることが確認されたら、速やかに未払い分を支給しなければなりません。
未払い分が発生していなかった場合は、ただ単に「未払分はありません」と伝えるだけでなく、なぜ割増賃金を請求しようと思ったのか、その理由を当該従業員にヒアリングしましょう。
そのうえで、割増賃金に対する誤解や思い違いが認められた場合は、割増賃金のルールについて丁寧に説明することが大切です。割増賃金のルールをしっかり周知しておけば、誤解からくる割増賃金の請求を未然に防ぐことができます。
5-1. 割増賃金の消滅時効は延長されている
割増賃金の未払いなどがあった際に、従業員は賃金を請求することができます。しかし、賃金請求の権利は、一定の期間が経過すると「時効」により消滅します。
これまでは、賃金の消滅時効は2年とされていました。しかし、2020年4月の民法改正により、賃金の消滅時効は5年(当面の間は3年)に変更されています。また、消滅時効を適用できないケースや、時効の更新を適用できるケースもあります。
割増賃金の消滅時効について正しく把握するとともに、計算間違いや支払ミスが生じないよう、適切な管理体制を整備することが大切です。
参照:未払賃金が請求できる期間などが延長されています|厚生労働省
6. 時間外労働・休日出勤・深夜労働には割増賃金を支払う必要がある

今回は、割増賃金の意味や計算方法、割増率について解説しました。法定労働時間を超えて残業させる場合や、法定休日および深夜帯に労働させる場合は、通常の労働時間または労働日の賃金に割増率を適用した割増賃金を支払う必要があります。
割増率は労働状況や給与形態によって異なるので、従業員ごとにいつ・どのような労働を・どのくらいおこなったのか、正確に把握しておくことが大切です。手書きの出勤簿や、エクセルを使った勤怠管理では誤入力やチェック漏れが発生しやすいので、打刻情報を自動で入力・管理できる勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。
労働時間の客観的で正確な管理ができていなければ、正しい残業代の計算ができず、未払いが発覚した場合には最悪、法律に違反する可能性があります。
当サイトでは、トラブルが発生しない適切な残業代の計算方法が知りたいという方に向けて、労働時間の集計マニュアルを無料配布しています。
「残業代の計算における打刻まるめが違法となるケースについて知りたい」
「自社の残業代の計算方法に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。