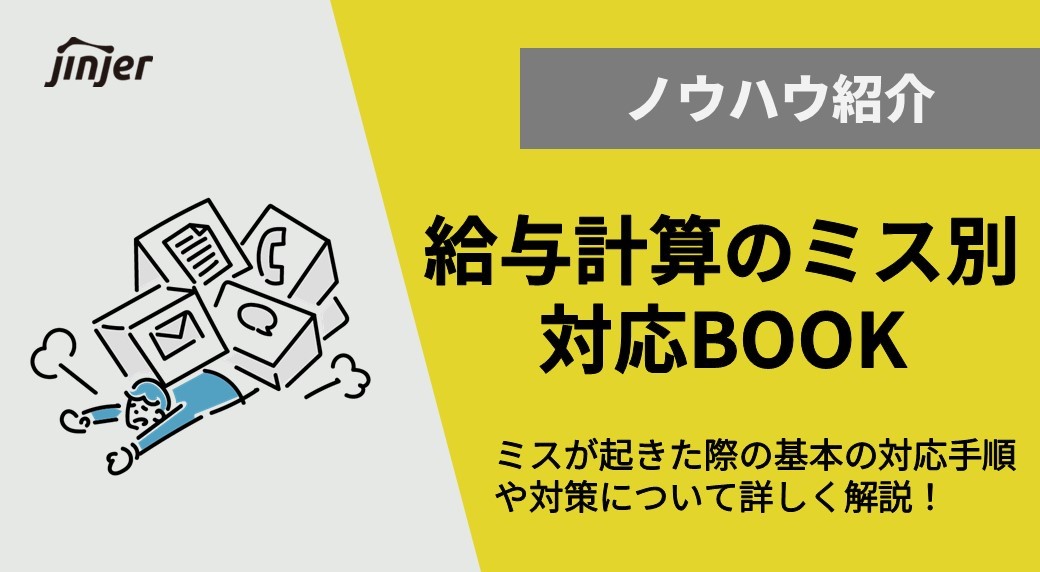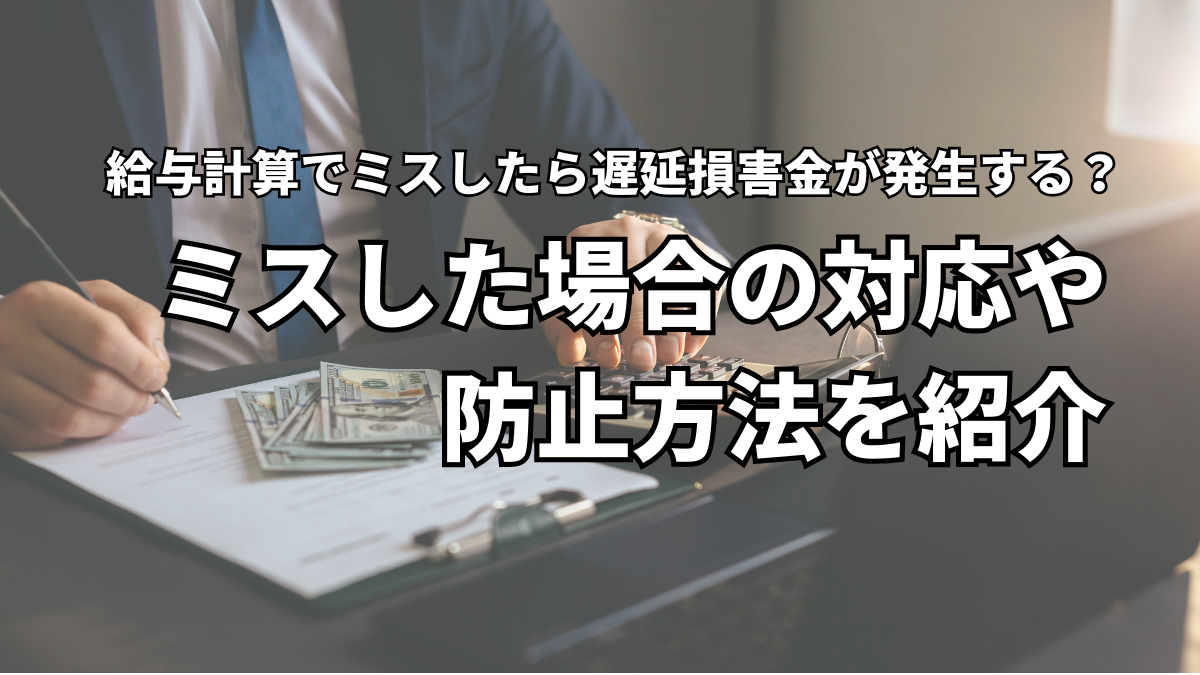
給与計算業務は、従業員と会社の信頼関係にも関わる業務ですから、ミスのないようにおこなわなければなりません。しかし、人間が作業する以上、ミスが起きてしまうこともあります。給与計算でミスしてしまった場合、遅延損害金は発生するのでしょうか?
今回は給与計算でミスが発生したとき、どうなってしまうのかを解説します。遅延損害金が発生するケースや発生した場合の対応方法も紹介しますので、給与計算をおこなう方は理解しておきましょう。
給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。
当サイトでは、給与計算で生じるミスの対処方法を場合別に紹介した「給与計算のミス別対応BOOK」を無料で配布しております。
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・給与計算業務のチェックリストがほしい方
・給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
上記に当てはまるご担当者様は、「給与計算のミス別対応BOOK」をぜひご覧ください。
目次
1. そもそも遅延損害金と付加金はいつ発生する?

そもそも遅延損害金や付加金とは、どのような場面で支払いが発生するのでしょうか。
遅延損害金や付加金とは、給与の計算ミスなどにより賃金に不足が合った際に、責任をとり本来の金額に追加して付与する利息などを指します。両者の違いについて、詳しく解説します。
1-1. 遅延損害金とは
「遅延損害金」とは、金銭の支払いが遅れた際に損害賠償として支払うお金のことです。
遅延損害金の支払いの強制力があるのは裁判所のみで、基本的には従業員と会社の交渉によって解決します。
給与が1日でも遅れたら債務不履行になってしまい、遅延損害金が発生します。
1-2. 付加金とは
「付加金」とは、賃金全般の未払いが発生しており、裁判で悪質であると判決が下った場合に、制裁措置として支払いを命じられる金額を指します。
付加金の金額に関しては、支払不足賃金分と同額の支払を命じられることがあります。
賃金全般とは、割増賃金や休業手当、有給休暇への給与、解雇予告手当などが含まれます。
1-3. 遅延損害金と付加金の時効は?請求期限について
遅延損害金の時効は、2020年4月の民法改正により5年に延長されました。(ただし経過措置により当分の間は3年)付加金も同様に、5年に延長されることが決定しています。
2. 給与計算でミスが発生するとどうなるのか

給与計算でミスが発生した場合、故意でなかったとしても給与の一部が未払いになっていたり不足している分があるのであれば労働基準法の賃金支払の原則に反しているとされ、法律違反になってしまいます。
速やかに対処して従業員も納得すれば大きな問題にはなりませんが、従業員が告発した場合、後から未払い分・不足分を支払っていたとしても労働基準監督署から勧告を受けたり、罰則を受けたりする可能性があります。また、立ち入り調査や未払い請求訴訟に対応しなければならないこともあるので、給与計算はミスがないようにしなくてはなりません。罰則を受ける場合は、賃金支払原則違反は30万円以下の罰金刑、割増賃金支払義務違反は30万円以下の罰金刑もしくは、6カ月以下の懲役刑が課されることもあります。
故意ではないミスでも発生するとこのような深刻な問題になってしまうことがあるため、ミスがないように十分注意しましょう。また、万が一ミスを起こしてしまった場合は、速やかに対処する必要があります。ミスの内容によって、どのように対応すればいいかを解説します。
2-1. 未払い分や不足分がある場合
給与計算のミスで問題となりやすいのは、未払い分がある場合や不足分がある場合です。従業員としては本来もらえるはずの給与がもらえていないことになりますから、過払いしてしまった場合よりもさらに誠実な対応が必要です。
未払い分や不足分がある場合、給与を支給してすぐにミスが発覚したら、従業員にお詫びして、当月中に支払いを求めるかどうかを確認してください。複数人に対してミスがあった場合は、一人ひとり確認して、それぞれの希望に合わせて対応します。従業員が翌月精算に同意した場合は、翌月の給与で未払い分・不足分を支払いましょう。
ただ、必ずしも給与支払いのすぐ後に未払い分・不足分が発覚するとは限りません。数週間後、翌月などに会社側が気付くことや、従業員が指摘することも多いです。その場合は当月中に支払いが難しいですから、しっかりお詫びして、できるだけ早く対応します。
未払い分・不足分があることで源泉所得税や雇用保険料が増える可能性もありますから、賃金台帳もきちんと修正します。
2-2. 過払いしてしまった場合
給与計算のミスによって給与を過払いしてしまった場合、翌月の給与支払いで精算するのは厳密にいうと労働基準法で定められている全額払いの原則に反していることになります。しかし過去の事例で、前月分の過払い分を翌月で精算しても、労働基準法第24条の違反とは認められないとされたケースがあるため、法令違反などの問題となることは少ないでしょう。
ただし、会社側が給与計算でミスしたにも関わらず、従業員に通知せず、勝手に精算してしまうとトラブルになる可能性があります。翌月精算する場合はあらかじめ従業員にその旨を伝えてお詫びした上で、精算するようにしましょう。
翌月の給与で精算できない場合は、給与計算ミスが発生した当月中に、過払い分の返金を現金にてしてもらいましょう。源泉所得税や雇用保険料が減る可能性もあるため、賃金台帳もきちんと訂正します。
3. 遅延損害金が発生した場合の対応方法

遅延損害金が発生した場合、どのように対応すべきなのかを解説します。従業員との信頼関係を損ねないためにも、抜けがないように気を付けて対応しましょう。
3-1. 未払い分・不足分と遅延損害金を計算する
未払い分・不足分があることがわかったら、速やかにその金額を計算します。そして、未払い分・不足分に対して損害遅延金がいくらになるのかも計算しましょう。
3-1-1. 遅延損害金の計算方法(退職前の場合)
本来給与を支払うべき日より給与の支払いが遅れた場合、遅延損害金を支払わなければなりません。遅延金は支払いが1日でも遅れると発生します。
遅延損害金の金額は未払い分・不足分に対して3%となります。2020年4月の法改正までは6%が法定利率でしたが、現在は変更になっているので注意してください。
損害遅延金の計算は、「不足分 × 0.03%(利率)× 遅延日数 ÷365日」です。
3-1-2. 遅延損害金の計算方法(退職後の場合)
退職後の遅延損害金の利率は、退職前から大幅に上回り、年14.6%と高額になる恐れがあります。民法419条の1項、賃金の支払の確保等に関する法律6条の1項、同施行令1条により確認ができます。
ただし、賃金支払確保法6条の2項には下記の規定があり、一部適用が除外されます。
前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。
3-2. 従業員へお詫びをする
給与計算ミスが発生したら、遅延損害金を支払う場合でも支払わない場合でも、すぐに本人にお詫びをします。わずかな額であったとしても適当に済ませてしまっては、会社への信頼を失くしてしまう可能性が高いです。
気付いた時点ですぐにお詫びをしましょう。またミスの内容やミスが起きてしまった理由もきちんと伝えます。未払い分・不足分の額とともに損害遅延金がいくらになるのかも伝えてください。
3-2-1. お詫び文の例
給与の計算ミスに対して謝罪をする際には、重要な給与に関わることであるため、ミスの内容や、対応策を簡潔かつ具体的に述べることが大切です。
以下、お詫び文の一例です。
| 給与計算の誤りについてのお詫び
○○様の○月度分の給与支払いにつきまして、下記の誤りが見つかりました。 (ミスの内容例) (対応策例) 今後同じようなミスを繰り返さぬよう、一層の注意を払い給与計算の処理をいたしますので、何卒ご容赦のほどお願い申し上げます。 |
3-3. できるだけ早く精算する
不足分を現金で支払う場合は、支払った際に従業員から領収書をもらってください。振り込みは即時受け取りが可能な場合のみ利用するようにしましょう。従業員が同意した場合は翌月の調整でも、労働基準法違反にはなりませんが、誠意を見せるという意味でも、できるだけ早く精算することをおすすめします。
3-4. 給与の支払い以外に発生することがある実務について
まず、給与の未払い・過払いが発生した場合、賃金台帳の変更が必要です。不足した事実、追加で支払った事実や金額、発生した経緯を記録することが求められます。
3-4-1. 社会保険料の対応
社会保険料に関しても、修正申請や追加納付が発生することがあります。
給与計算ミスが社会保険料の徴収額にも影響した場合、3つの対応方法があります。
- 翌月の同項目で精算する
徴収額が不足していた場合は翌月の控除額に上乗せし、過剰に徴収した分は翌月の控除額から差し引きましょう。
- 当月に現金精算する
控除額の不足分は追加で徴収し、過剰分は現金で返金します。ただしこの修正分は、給与データに反映することを忘れずにおこないましょう。
- 会社が負担する
個人負担が不足している分の額は、代わりに会社が負担し、「現物給与」として課税対象として処理する手段もあります。
4. 給与計算で発生しやすいミスとは

ここからは、給与計算でミスが発生しやすい事例について解説します。
給与を計算する際には、これらの間違いがないか確認をして、正しい給与を支給しましょう。
4-1. 割増賃金に漏れがある
割増率は、労働状況や労働時間によって変化するため、計算ミスや対応漏れがおきやすいでしょう。給与計算の際には、入念に確認しましょう。
4-2. 役職手当の反映に漏れがある
役職手当を支給する従業員や支給額は、あらかじめ明確に理解しておく必要があります。
役職が変更した後などは、適切に連携ができていないと対応漏れが発生しうるので、注意しましょう。
4-3. 扶養の反映に漏れがある
例えば「配偶者の収入が増加した」「子どもが社会人になった」など親族が扶養から外れた際に、給与から所得税の徴収額に変更が発生するため気を付けましょう。
反映に漏れがあった場合には、年末調整にて差し引きが可能です。
4-4. 40歳以降の介護保険料控除に漏れがある
40歳以降になると、新たに介護保険料が徴収されます。通常40歳となる前日が該当する月から、必要となります。また3年ごとに徴収金額も変更となるため、注意しましょう。
4-5. 退職者の社会保険料控除に誤りがある
月途中に退職した社員がいた場合、社会保険料は控除してはいけません。誤って差し引いてしまうと、のちに未払い金として請求される可能性もあるため、把握しておきましょう。
5. 給与計算のミスが発生する理由とは
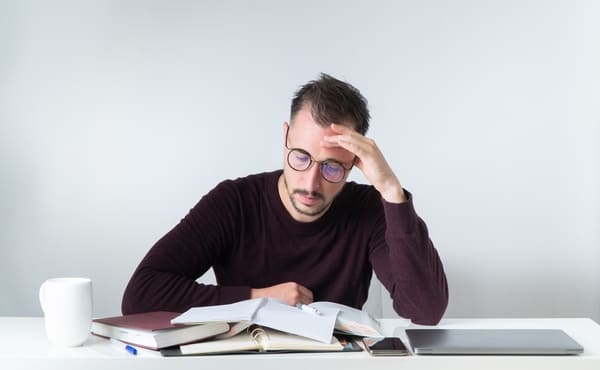
ここまで、給与計算でミスが発生しやすい事例について解説しました。ここからは、給与計算ミスの発生につながる3つの要因を紹介します。
5-1. 固定給の変更がある
従業員の昇格や降格、扶養家族の変更などによって、固定給が変わるタイミングは度々発生することがあります。固定給が変動すると、社会保険料の控除額も都度確認をする必要があり、対応が漏れてしまうことが給与計算ミスの要因となるケースも多いでしょう。
5-2. 給与を自動計算しない
手動で給与を計算すると、どうしても人為的ミスをなくすことは難しいでしょう。月末の集計作業や割増賃金、保険料の計算など多様な業務があるほか、従業員人数に比例して工数も増えてしまいます。
5-3. 勤怠管理が正しくおこなえていない
従業員の出退勤を記録する打刻データが正しく集計・管理できていない場合も、給与の計算ミスの要因となりやすいです。
例えば、昨今は働き方が多様化し、テレワークやフレックスタイム制度を取り入れる企業も増えてきました。出勤簿やタイムカードなどでの打刻は、修正の手間が発生しリアルタイムでの管理が不可能であるため、打刻漏れや修正ミスなどが発生することも多いです。
6. 給与計算ミスを防ぐ方法

給与計算ミスをして未払い分・不足分があっても、遅延損害金を支払うケースはそれほど多くはありません。ただ、給与計算ミスをするということ自体が、従業員の会社への信頼を大きく損なう原因になりますから、できるだけ給与計算ミスを防げるように対策を取りましょう。
6-1. マニュアル・チェック項目の作成
給与計算ミスを防ぐためには、給与計算のルールをしっかり把握し、できるだけシンプルにすることが重要です。
給与計算に関しては一つのケアレスミスが、のちの業務に大きく響いてしまったり、トラブルへと発展しうるため、少しでもミスを減らせるようチェックリストを作成することも有効な手段の一つでしょう。
当サイトでは給与計算でミスが発生しやすい項目のチェックリストを無料配布しております。チェックリストとともによくある給与計算ミスとその対応方法、ミスを減らす方法についても解説しているため、給与計算ミスを減らしたい方はこちらから「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードしてご覧ください。
6-2. 2人以上で最終確認する
小規模な企業の場合、1人で労務回りの業務を担当する方も多いでしょう。ただし従業員人数に応じて、工数が増えるため人為的ミスが発生する可能性は高まりやすいです。
可能な限りダブルチェックをおこなうようにして、ミスが発生した場合もいち早く気付けるような仕組み作りをおこないましょう。
6-3. 給与計算のタスク予定を見直す
給与計算のミスを防ぐために、スケジュールに余裕をもたせることは一つ重要な手段でしょう。例えば、「給与の締め日から給与支給日までの日数を増やすこと」や、「従業員にあらかじめ締め日までには打刻漏れがないよう打刻申請を徹底してもらう」なども余裕を持たせるために重要でしょう。
6-4. 給与計算システムを導入する
従業員の数が多いのであれば、外部に委託するのも一つの方法ですが、最近は給与計算システムで簡単に給与計算ができるようになっています。ミスも防げますし、作業の効率化も図れますので、導入を検討してみるのもおすすめです。
7. 給与計算ミスがあったら速やかに対応しよう

給与計算ミスはあるべきではありませんが、人間が作業をおこなう以上ミスを100%避けることはできません。給与計算ミスがあった場合は、損害遅延金の有無にかかわらず、できるだけ早く対応しましょう。
【監修者】小島 章彦(社会保険労務士)
給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。
当サイトでは、給与計算で生じるミスの対処方法を場合別に紹介した「給与計算のミス別対応BOOK」を無料で配布しております。
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・給与計算業務のチェックリストがほしい方
・給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
上記に当てはまるご担当者様は、「給与計算のミス別対応BOOK」をぜひご覧ください。