
雇用契約書がない場合、直ちに違法になるわけではありません。しかし、雇用契約書がないことで、さまざまなトラブルが起きやすくなります。この記事では、雇用契約書がないことは法的に問題がないかどうかをわかりやすく解説します。また、雇用契約書がないことによる会社側と労働者側のデメリットやリスクについても紹介します。
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。
当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。
雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 雇用契約書がないのは違法?
 労働契約が成立しているにもかかわらず雇用契約書がない場合、それは違法になるのでしょうか。ここでは、雇用契約書がないことの違法性や罰則について詳しく紹介します。
労働契約が成立しているにもかかわらず雇用契約書がない場合、それは違法になるのでしょうか。ここでは、雇用契約書がないことの違法性や罰則について詳しく紹介します。
1-1. 雇用契約書がないのは違法でない
雇用契約書がないこと自体は違法になりません。労働契約法第6条により、労働契約(雇用契約)は、労働者が労働すること、使用者がその労働の対価として賃金を支払うことについて、労使間で合意することで成立するとされています。
なお、民法第521条「契約自由の原則」により、法令で特段の定めがなければ、契約内容や契約方式などは当事者間で自由に決めることが可能です。そのため、雇用契約は口約束などの口頭でも、使用者と労働者の合意があれば成立することができます。このように、雇用契約書がなくても、労働契約を成立することは可能であり、そのこと自体は違法になりません。
(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
関連記事:雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや雛形などの書き方について徹底解説
1-2. 労働条件通知書がないのは違法
雇用契約書を交付しなくても違法になりませんが、労働条件通知書を交付しない場合は違法になります。労働基準法第15条により、労働条件通知書の書面での交付が法律で義務付けられています。労働条件通知書には、労使双方の合意の必要性まで定められていないため、会社から一方的に労働者に交付したとしても法律の要件を満たすことが可能です。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いやそれぞれの役目と必要な理由を解説
1-3. 雇用契約書がない場合の罰則
雇用契約書がないこと自体は違法でないため、法律に則り罰則が課せられることもありません。しかし、労働条件通知書がない場合は違法になり、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金のペナルティが課せられる恐れがあります。また、労働基準法に違反した企業として、会社名が厚生労働省のWebサイトなどに公表される可能性があり、社会的信用を損なうリスクもあるので気を付けましょう。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第十五条第一項若しくは第三項、(省略)の規定に違反した者
2. 雇用契約書の目的や役割

雇用契約書がないことに違法性はありませんが、雇用契約書を交付することには意味があります。ここでは、雇用契約書の目的や役割について詳しく紹介します。
2-1. 雇用条件を明確にする
雇用契約書には決まったフォーマットや記載事項がないため、必要に応じて法律を満たす範囲で労働条件を書き加えることもできます。労働条件通知書で労働条件の明示義務の要件を満たし、雇用契約書で雇用条件をより明確化することで、会社と労働者の両者にとって安心した労働環境の整備につなげることが可能です。このように、雇用契約書は、雇用条件を明確にするための役割があります。
2-2. 労働条件に合意があったことを証明する
雇用契約は口約束などの口頭でも成立しますが、後で「言った言わない」のトラブルが生じる恐れがあります。なお、労働条件通知書は、労働者に労働条件を明示できますが、同意が得られたことまで証明できません。雇用契約書は「契約書」という名が付くように、労使双方が労働条件に合意した証になります。労働条件に関してトラブルがあったら、雇用契約書を再確認することで、適切な対応を取ることが可能です。
2-3. 雇用に関するルールを社内に遵守させる
労働時間や休日、賃金、退職など、雇用に関するルールは法律で細かく定められています。しかし、現場の従業員などは、このようなルールを細部まで理解しているとは限りません。雇用契約書を交わし、使用する者と働く者が労働に関するルールをきちんと確認することで、法令を遵守した正しい雇用環境を作り出すことができます。このように、雇用契約書は雇用に関するルールを遵守させる目的で活用することも可能です。
3. 雇用契約書がないことによるデメリット【会社側】

雇用契約書がなくても違法になりませんが、会社側にさまざまなデメリットが生じます。ここでは、会社側の雇用契約書がないことによるデメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 労働条件に関するトラブルが起きたときに証拠がない
労働者から「聞いていた勤務時間と違う」「賃金の計算がおかしい」などの指摘をもらう可能性もあります。そのような場合、雇用契約書がなければ、労使双方で合意した労働条件を確認することができません。一方、雇用契約書があれば、その記載内容をもとに双方で話し合いを進めることができます。思い込みなどによる不要なトラブルを未然に防ぐためにも、雇用契約書を作成しておくと安心です。
3-2. 労働者からの信頼が得られない
雇用者側が、手間がかかることなどを理由に雇用契約書を作成していないだけの場合でも、労働者にとって雇用契約書がないことは「書面での契約がないなんて何か事情があるのではないか」「ブラック企業なのではないか」などの不安要素になりかねません。また、雇用契約書がないことを理由に内定を辞退する人がいないとも言い切れません。労働者に信頼や安心を与えるためにも、雇用契約書を交付することが推奨されます。
3-3. 試用期間や退職・解雇に関するルールが曖昧になる
試用期間を設定する場合、その際の労働条件も明示する必要があります。雇用契約書がない場合、試用期間のルールは就業規則に従うことになります。しかし、就業規則にも試用期間のルールが記載されていない場合、試用期間のない雇用の定めとみなされる恐れがあります。
また、退職や解雇に関するルールも、事前に労働条件として明示しなければなりません。正当な事由で労働者を解雇したとしても、雇用契約書がない場合、解雇理由を証明できず、不当解雇とされ解雇が無効になる可能性もあります。このように、雇用契約書は労働者だけでなく、会社を守る役割もあります。
関連記事:試用期間とは?設定する際の注意点やよくある質問・トラブルを紹介
3-4. 転勤や異動などの配置転換が違法になる可能性がある
転勤や異動などの配置転換は、業務遂行上の理由があれば可能です。2024年4月から労働条件明示ルール改正があり、就業場所や業務の変更範囲も労働条件として明示する義務が設けられました。雇用契約書がない場合、配置転換があるという労働条件に合意があったことを証明できず、労働者が拒否した場合、配置転換を実施できない恐れがあります。このような事態を招かないように、雇用契約書に配置転換の有無を記載したうえで、雇用契約を締結しましょう。
関連記事:配置転換とは?目的やメリット・デメリット、実施手順をわかりやすく解説!
3-5. 固定残業代制度が認められない恐れがある
残業代の計算を効率化したり、人件費を抑制したりするため、固定残業代制度を設けている企業もあるかもしれません。雇用契約書がなく、正しく固定残業代制度の仕組みを労働者に伝えていない場合、固定残業代が残業手当として認められず、別途残業代を支給しなければならなくなる恐れがあります。
「京都地裁平成28年9月30日判決、大阪高裁平成29年3月3日判決」の裁判事例では、就業規則で固定残業代制度の内容を記載しており、雇用契約書に残業手当が含まれると記載していた場合でも、固定残業代制度は認められず、未払い賃金を支払うよう命じられました。その理由として、雇用契約書には、残業手当が含まれる旨のみで、いくらが基本給で、いくらが何時間分の時間外等手当なのか明らかになっていなかったためです。
このように、固定残業代制度が正しく認められるためには、雇用契約書に基本給と固定残業代を明確に分けて記載し、その固定残業代は何時間分の残業代なのか金額もきちんと記載する必要があります。また、固定残業時間を超過した場合、その分の残業代は別途支給する旨も記載しておかなければなりません。
関連記事:固定残業代(みなし残業代)の計算方法とは?超過分の計算や違法となるケースも解説!
4. 雇用契約書がないことによるデメリット【労働者側】
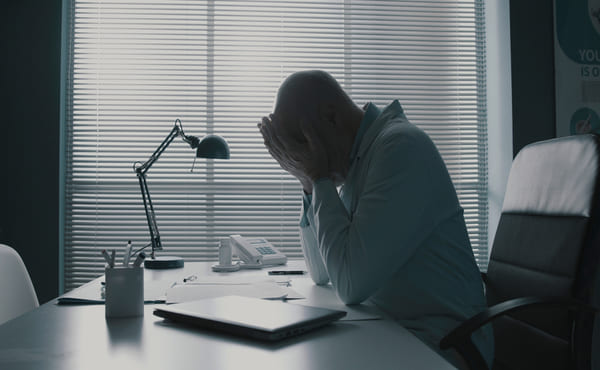
雇用契約書がない場合、会社側だけでなく、労働者側も不利益を被る可能性があります。ここでは、労働者側の雇用契約書がないことによるデメリットについて詳しく紹介します。
4-1. 求人票の内容と実際の労働条件が異なる可能性がある
求人票はあくまでも「見込みの労働条件」であり、求人票の内容と実際の労働条件が違っても、直ちに違法になるわけではありません。雇用契約書を交わさない場合、「面接の際に採用後の労働条件を提示しました」と言われれば、労働者は求人票の条件と実態が異なっていても、受け入れるしかない恐れがあります。このように、実際の労働条件を正しく把握するためにも、雇用契約書は重要な書類となります。
4-2. 実際の雇用主が誰だかわからない恐れがある
雇用契約書を交わすことで、そこに署名・捺印された者が雇用主として明確に判断できるようになります。しかし、雇用契約書がない場合、実際の雇用主が誰だか明らかにされないため、社会保険の加入義務や賃金の支払いなどにおいてトラブルを招く恐れがあります。
社会保険が完備されている大手企業に雇用されたと思っていたのに、実態は大手企業に所属している従業員(個人)によって雇用されていたという事例もあります。雇用主を明確にし、労働者に安心を与えるためにも、雇用契約書を交わすようにしましょう。
同労組によれば、同社では一部店舗の理髪師をQB本社(キュービーネットホールディングス株式会社)が雇用するのではなく、エリアマネージャーが雇用する形式をとることによって、本部が雇用責任を免れていたという。いわば、「社員が社員を雇用する」という異様な雇用形態を作り出していたわけである。実は、異様な雇用形態は近年さまざまな大手企業に広がりを見せており、背景には「脱法行為」の狙いがあることが指摘されている。
4-3. 有利な雇用契約を結んでいても就業規則が適用される可能性がある
雇用契約は口頭で成立させることもできます。しかし、口約束によって有利な労働条件で雇用契約を結んだ場合、それを証明できないため、就業規則で定められている労働条件が適用されてしまう恐れがあります。
たとえば、「1年目から有給休暇を20日付与する」と口頭で約束しても、実際は就業規則に従って10日しか付与されないことがあります。このような場合、雇用契約書があれば、その契約書を根拠に好条件での契約があったことを主張することでき、就業規則より有利な雇用条件を適用してもらうことができます。
5. 雇用契約書がない場合の整備の手順

雇用契約書を用意していない企業は、今すぐに交付できるよう準備すべきです。ここでは、雇用契約書がない場合の整備の手順について詳しく紹介します。
5-1. 必要になる雇用契約書の種類を把握する
正社員や契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態によって、労働条件は変わります。また、フレックスタイム制や変形労働時間制、裁量労働制など、働き方によっても雇用条件は変える必要があります。そのため、まずは自社に採用されている雇用形態や労働時間制度をチェックし、作成すべき雇用契約書の種類を確認しましょう。
5-2. 雇用契約書のひな形やテンプレートを手に入れる
雇用契約書のひな形やテンプレートは、インターネット上で取得することができます。しかし、ひな形・テンプレートは法律の要件を満たしていない可能性もあるので、ニーズに応じてそれをカスタマイズするようにしましょう。雇用契約書のひな形・テンプレートを活用することで、雇用契約書の作成を効率化することが可能です。
5-3. 雇用契約書の記載事項を整える
雇用契約書は法律で交付が義務付けられていないため、記載事項は自社のニーズにあわせてカスタマイズすることができます。一方、労働条件通知書は、労働基準法施行規則第5条によって記載事項が明確に定められています。そのため、雇用契約書にも、労働条件通知書に必須な記載事項を含めるようにしましょう。なお、記載すべき事項は、次の通りです。
| 記載する項目 | |
| 絶対的記載事項 |
|
| 相対的記載事項 |
|
相対的明示事項は、項目に該当する定めをした場合には必ず記載が必要となるものです。口頭での明示でも構いませんが、後でトラブルになる可能性があるため、できるだけ書面で明示するようにしましょう。なお、2024年4月1日から労働条件明示ルール変更に伴い、必要に応じて次の項目も記載しなければならないので注意が必要です。
- 就業場所・業務の変更の範囲(すべての労働者)
- 更新上限の有無と内容(有期契約労働者)
- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(有期契約労働者)
関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!
5-4. 雇用契約書に署名・捺印欄を必ず設ける
雇用契約書には、使用者と労働者が合意したことを証明するため、署名・捺印欄を必ず設けましょう。なお、民事訴訟法第228条により、当事者の署名もしくは押印のどちらかがあれば、その文書は真正に成立したとみなされるため、契約書を成立させるには必ずしも押印が必要というわけではないので正しく法律を理解しておきましょう。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。(省略)
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(省略)
5-5. 雇用契約書の交付方法や注意点を社内に周知する
雇用契約書のフォーマットが作成できたら、実際に運用する方法を明確にしましょう。電子交付する場合は、その注意点を明確にしておく必要があります。また、雇用契約書には保管期間も定められています。このように、雇用契約書の交付には気を付けるべき点が多くあるので、運用を開始する前に、あらかじめ従業員にルールを周知しておくことが大切です。
関連記事:雇用契約書の保管期間は5年!経過措置の内容やほかの書類についても紹介
6. 雇用契約書を作成・交付する際の注意点やポイント
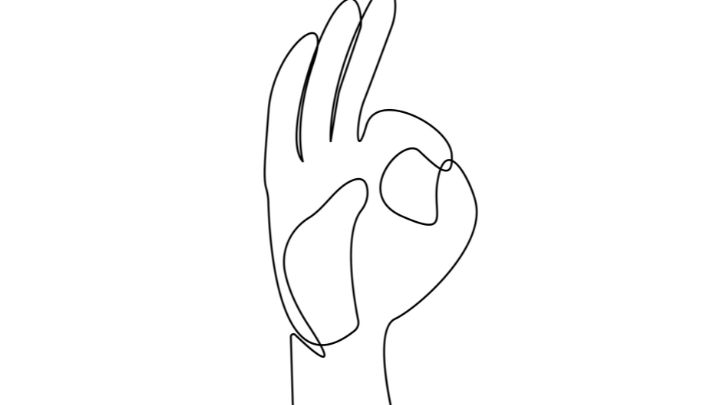
雇用契約書の作成や交付には気を付けるべき点がいくつかあります。ここでは、雇用契約書を作成・交付する際の注意点やポイントについて詳しく紹介します。
6-1. 雇用契約書に労働条件通知書を兼ねることも可能
雇用契約書と労働条件通知書の目的や役割は違いますが、内容がほとんど変わらないケースもよくあります。その場合、雇用契約書と労働条件通知書を兼用して、「雇用契約書兼労働条件通知書」として作成し、交付することも可能です。
ただし、雇用契約書兼労働条件通知書を交付する場合、法令で求められる記載事項を網羅し、署名・捺印欄を設ける必要があります。雇用契約書と労働条件通知書を1枚の書類にまとめることで、事務手続きの負担やコストを減らすことができます。
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説
6-2. 雇用契約書は電子化できる
雇用契約書は法律で交付が義務付けられていないため、以前から電子化することができました。また、2019年4月から労働条件通知書の電子交付が可能になったことで、雇用契約書兼労働条件通知書も電子化することができるようになっています。
ただし、労働条件通知書や雇用契約書兼労働条件通知書を電子化する場合、労働基準法施行規則第5条に則り、次のいずれもの要件を満たす必要があります。
- 労働者が希望していること
- 労働者本人のみを特定して送付すること
- 電子送付された記録を書面に出力できること
また、労働条件通知書や雇用契約書は、電子帳簿保存法の要件を満たさなければ、有効な書類として認められない恐れもあるので注意が必要です。労働条件通知書・雇用契約書を電子化すれば、郵送代や保管費用などのコストの削減や契約手続きの業務効率化が期待できます。
(省略)法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
関連記事:雇用契約書の電子化は合法?メリットや導入方法、労働条件通知書との違いも解説
6-3. 雇用契約書の交付タイミングを明確にしておく
雇用契約書の交付タイミングは明確に定められていませんが、雇用契約を締結する際に交付するのが一般的です。そのため、採用内定時や初出勤前、入社日に交付することが考えられます。実際に労働者を働かせる前に交付することを心掛けましょう。
なお、労働条件通知書の交付タイミングは、労働基準法第15条で「労働契約の締結に際し」と定められています。そのため、雇用契約書を用いて雇用契約を締結する際に、労働条件通知書も交付するようにしましょう。
6-4. 労働基準法や就業規則に満たない条件は無効になる
労働者保護の観点から労働契約法第12条、労働基準法第13条により、雇用契約書で労働基準法や就業規則に満たない労働条件を提示し、たとえ労働者の合意があっても、その条件は無効になり、労働基準法や就業規則の規定が優先されて適用されることになります。
たとえば、「賃金は2カ月に1回」と雇用契約書で定めがあっても、それは無効になり、労働基準法第24条に則り「賃金は毎月1回以上」支払わなければなりません。このように、法令に違反した雇用契約書の内容は無効になるため、労働基準法や就業規則を確認しながら、雇用契約書は作成するようにしましょう。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
6-5. 雇用契約書の内容を変更する場合は労働者の同意を得る
労働契約法第8条により、使用者と労働者の合意があれば、途中で労働条件を変更することができます。そのため、雇用契約書の内容を変更したい場合、労働者の同意を得ることで対応が可能です。従業員の同意が得られないのにもかかわらず、労働者が不利となるような雇用条件に変更するのは違法で無効になるため注意が必要です。なお、雇用契約書を変更する際は、新たな雇用契約書を作成するか、変更部分だけを抽出して「覚書」を作成するかのいずれかで対応することができます。。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
関連記事:雇用契約は途中で変更可能?拒否された場合や覚書のルールについても解説!
7. 雇用契約書がない場合によくある質問
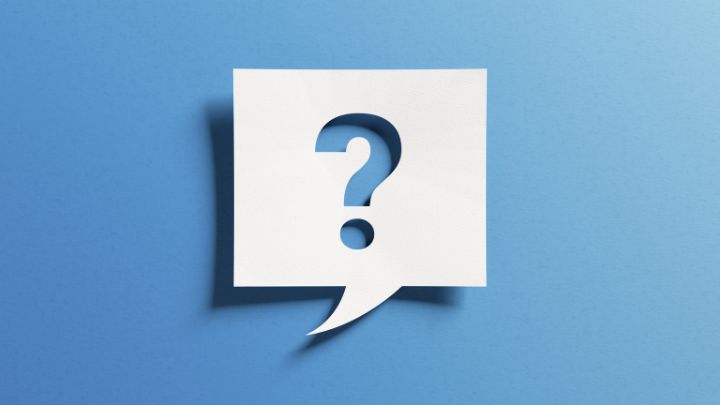
ここでは、雇用契約書がない場合によくある質問について詳しく紹介します。
7-1. パートやアルバイトの雇用契約書がないのは違法?
パートやアルバイトの雇用契約書がないことに関しても、違法ではありません。正社員の場合と同様、雇用契約書の交付について法律上義務はないので、使用者とパート・アルバイト双方の合意のもとであれば口約束でも労働契約は成立します。
ただし、労働条件通知書は作成して交付しなければなりません。加えて、パート・アルバイトのような短時間労働者や有期雇用労働者に対しては、パートタイム労働法第6条に基づき、次の項目を明示する義務があります。
- 退職金の有無
- 昇給の有無
- 賞与支給の有無
- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口
労働条件に関するトラブルを起こさないようにするため、パートやアルバイトなどの労働者に対しても、労働条件通知書だけでなく、雇用契約書も交わすようにしましょう。
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
関連記事:パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際に押さえておきたいポイント
7-2. 雇用契約書がない場合に労働条件を確認できる書類は?
雇用契約書がない場合、労働条件をチェックする際、どのように確認すればよいかわからない人もいるかもしれません。まずは交付されている労働条件通知書を確認しましょう。また、内定通知書や採用通知書などでも、労働条件を確認できるかもしれません。そのほかにも、就業規則も労働条件をチェックする際に有効的です。
7-3. 雇用契約書がない場合に労働者はいつでも退職できる?
退職については、憲法や民法、労働基準法によってルールが定められています。無期雇用労働者か有期雇用労働者か、契約期間がどれくらいかなどによって、退職のルールは異なります。そのため、雇用契約書がないからといって、労働者はいつでも退職できるわけではありません。
ただし、労働基準法第15条により、労働条件通知書や雇用契約書で明示した労働条件と、実際の労働内容が相違する場合、労働者は即時にその労働契約を解除することができます。また、会社側は就業のために労働者が住居を変更していた場合には、、退職後に帰郷のための旅費を負担しなければならない恐れもあるので注意が必要です。
第十五条 (省略)
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(省略)
関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介
8. 安心・快適な労働環境のためにも雇用契約書の作成・交付を徹底しよう!

雇用契約書に法的な交付義務はないため、雇用契約書がないこと自体に違法性はありません。しかし、雇用契約書がない場合、労使間で労働条件に合意があったことを証明することが難しいため、トラブルが起きやすくなります。雇用者と労働者の双方が安心して働ける環境を作るためにも、雇用契約書を作成・交付しましょう。
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。
当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。
雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









