
雇用契約書とは、企業が従業員を雇用する際に取り交わす契約書です。労働契約の成立を証明できる書類であるため、作成・保管することで労使トラブルの防止に役立ちます。この記事では、雇用契約書が持つ法的効力や労働条件通知書との違いについてわかりやすく解説します。また、雇用契約書の交付タイミングや書き方のポイントも紹介します。
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。
当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。
雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 雇用契約書とは?
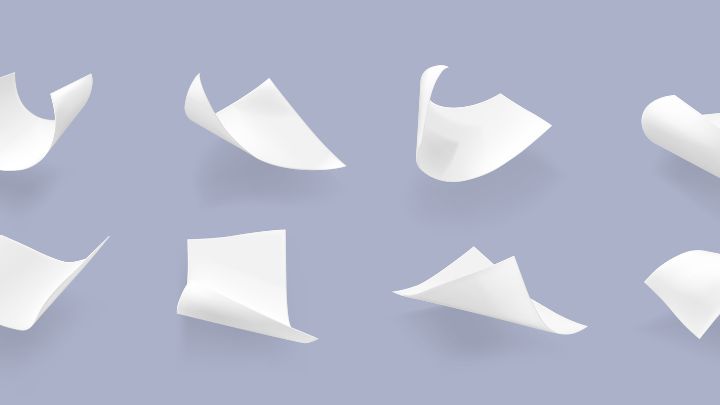
雇用契約書とは、給与や就業場所・時間など、使用者(企業)と従業員との労働契約を明らかにした契約書のことです。ここでは、雇用契約書の役割や必要性について詳しく紹介します。
1-1. 雇用契約とは?
雇用契約とは、民法623条に則り、労働者が労働に従事することと、雇用者がその労働に対し報酬を支払うことを約束した契約のことです。なお、雇用契約は、労働契約と言い換えられることもあります。雇用契約を結ぶことで、労働者は労働基準法や労働契約法などの法律によって守られるようになり、安心して働くことができます。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
1-2. 雇用契約書の役割
雇用契約は、使用者と労働者双方の合意があれば、口頭でも成立します。しかし、口約束だけでは証拠を残せないため、後で労働条件に関する違反があったときにそれを証明できず、当事者が不利になる可能性があります。そのため、労働時間や賃金、勤務地、業務内容などの雇用条件について、労使双方の合意があったことを証拠に残すため、雇用契約書は用いられます。
1-3. 雇用契約書がないのは違法?
雇用契約書は交付の義務が定められているわけではないため、作成しなくても違法になりません。しかし、使用者と労働者の間で労働条件に合意があったことを証拠として残しておかなければ、後々働き方や待遇などに問題が発生したときに、証拠を提示して適切に対応できない可能性があります。雇用契約書はなくても法律に違反することはありませんが、雇用条件に関するトラブルを未然に防ぐため、作成して交付することが望ましいです。
関連記事:雇用契約書がない場合の違法性は?生じるトラブルや整備の手順を紹介!
2. 雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書と間違われやすい書類に、「労働条件通知書」があります。両者の内容は似ていますが、交付義務や記載事項などに明確な違いがあります。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書の違いについて詳しく紹介します。
2-1. 法律で交付が義務付けられているか
雇用契約書は法律で交付が義務付けられていません。一方、労働条件通知書は、労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条に則り、原則として書面で交付することが法律で義務付けられています。そのため、労働条件通知書を交付しなかった場合、労働基準法により罰金などの罰則が課せられる恐れもあります。
なお、労働条件通知書は、労働者が希望した場合に限り、FAXやメールなどの電気通信を用いて交付することができます。ただし、特定の受信者宛てで送付すること(第三者が見られる場で公開しないこと)や、受信した労働者が出力して書面を作成できることなどの条件もあるため注意が必要です。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
(省略)
④ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法
2-2. 記載事項が定まっているか
雇用契約書は法律で交付が義務付けられていないので、その記載事項も定まっていません。そのため、自社のニーズにあわせて記載事項を自由に定めることができます。一方、労働条件通知書は交付義務があるように、労働基準法施行規則第5条によって含めなければならない記載事項が決まっています。
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(省略)
2-3. 署名・押印の必要性
雇用契約書は「契約書」という名が付くように、労使双方の約束を記載した私文書になります。民事訴訟法第228条により、当事者の署名もしくは押印があれば、雇用契約書が偽りなく、本物であることを証明することが可能です。そのため、雇用契約書には、署名・捺印欄を設ける必要があります。なお、法務省が公表している資料にもあるように、必ずしも押印が必要なわけではないので正しく契約の仕組みを理解しておきましょう。
一方、労働条件通知書は「通知書」であり、会社から労働者に対して一方的に労働条件を明示するために発行されます。そのため、署名・捺印欄は不要です。しかし、労働条件通知書を交付しただけでは、労働者からの同意を得た証拠にならないので注意しましょう。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。(省略)
4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する(省略)
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説
3. 雇用契約書はいつまでに交付する?

雇用契約書の交付タイミングがわからないという人もいるかもしれません。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書の交付タイミングについて詳しく紹介します。
3-1. 雇入れよりも前のタイミング
雇用契約書は、雇入れよりも前のタイミングで交付するのが好ましいです。しかし、実際には入社手続きをおこなうタイミングで作成・交付し、雇用契約を締結するケースが多いです。まれに、雇入れ後に労働条件の確認を目的に、雇用契約書を交付するケースがありますが、労働条件の適用事項が不明確で従業員の不安につながる恐れがあるため避けるようにしましょう。
一方、労働条件通知書は、労働基準法第15条により、労働契約(雇用契約)の締結と同じタイミングで交付するようことが義務付けられています。そのため、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結する前に、労働条件通知書を交付する必要があります。
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(省略)
3-2. 雇用契約書は労働条件通知書と兼用できる
雇用契約書と労働条件通知書はそれぞれ別々で交付するだけでなく、「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚の書類としてまとめて交付することもできます。雇用契約書と労働条件通知書の記載事項や内容が変わらないのであれば、労働条件通知書兼雇用契約書にまとめることで、手続きの負担を減らすことができます。ただし、労働条件通知書兼雇用契約書を交付する場合、労働条件通知書に記載しなければならない事項と、署名・捺印欄の両方を書類に含めなければならないので注意が必要です。
3-3. 雇用契約書は電子化して交付することも可能
雇用契約書は法的に交付が義務付けられた書類でないため、電子化して交付することもできます。また、2019年4月1日から、労働条件通知書も電子化して交付することができるようになりました。これにより、労働条件通知書兼雇用契約書も電子化して交付することが可能です。
雇用契約書や労働条件通知書を電子化すれば、印刷代や郵送代などのコストを減らしたり、送付・返送の負担を削減したりすることができます。ただし、電子化する場合は、電子帳簿保存法の「真実性」「可視性」の要件を満たせるようにすることが重要です。
関連記事:雇用契約書の電子化は合法?メリットや導入方法、労働条件通知書との違いも解説
4. 雇用契約書の記載事項

雇用契約書を作成する際は、記載すべき事項があります。なお、法律で記載事項が定められているのは労働条件通知書ですが、両者を兼ねた労働条件通知書兼雇用契約書を作成する企業も多いので、記載事項を正しく把握しておくことが大切です。ここでは、雇用契約書(労働条件通知書)の記載事項について詳しく紹介します。
4-1. 絶対的明示事項
労働条件通知書に必ず記載すべき事項を、絶対的明示事項とよびます。具体的な記載事項は、次の通りです。
- 労働契約期間
- 就業場所
- 従事する業務内容
- 始業時刻・終業時刻
- 休憩時間
- 休日・休暇
- 交替制勤務におけるルール
- 賃金に関する事項
- 退職や解雇に関する事項
2024年4月1日からの労働条件明示ルール改正に伴い、次の項目も必ず含めなければなりません。
- 就業場所の変更範囲
- 業務内容の変更範囲
また、有期雇用労働者に対しては、次の項目も必須事項に含まれるようになっています。
- 更新上限の有無とその内容
- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(※無期転換申込権が生じる契約更新のタイミングごとに明示)
なお、パートタイム労働法第6条、パートタイム労働法施行規則第2条に則り、パートやアルバイトなどで働く短時間労働者や有期雇用労働者に対しては、次の項目も絶対的明示事項に含まれます。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与(ボーナス)の有無
- 雇用管理の改善などに関する事項に関係する相談窓口
労働条件通知書に絶対的明示事項を含めていない場合、労働基準法などの法律違反となり、罰則が課せられる恐れもあるので気を付けましょう。労働条件通知書と雇用契約書を1枚にまとめる場合も、必ず絶対的明示事項を含めましょう。
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。(省略)引用:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(パートタイム労働法施行規則)第2条一部抜粋|e-Gov
関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!
4-2. 相対的明示事項
相対的明示事項とは、労働基準法施行規則第5条に記載されている絶対的明示事項以外の事項を指します。相対的明示事項も、その定めをしているのであれば必ず含めなければならないので注意が必要です。具体的な記載事項は、次の通りです。
- 昇給に関する事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時に支払われる賃金に関する事項
- 最低賃金
- 労働者が負担する食費や作業用品に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償や傷病扶助に関する事項
- 表彰や制裁に関する事項
- 休職に関する事項
相対的明示事項は、口頭で伝えても問題ないとされています。しかし、トラブルを防ぐためにも、相対的明示事項に当てはまる制度を取り入れている場合は、書面で交付したほうが良いでしょう。
③ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 ←絶対的明示事項
4-3. 法的効力を持たせるために必要な事項
雇用契約書は労働条件通知書のように明確な記載事項が定められているわけではありませんが、法的効力を持たせるために署名・捺印欄を設ける必要があります。また、法的に必要な明示事項以外にも、就業規則で定める重要な社内ルールを記載しておいてもよいかもしれません。
当サイトでは、明示事項に加えて、雇用契約の締結から解雇までのルールを取りまとめた資料を用意しています。雇用契約の手続きに置いて不安がある方はぜひこちらからダウンロードしてご確認ください。
5. 雇用契約書の書き方のポイント

労働条件を記載する際は必須事項を網羅し、なるべく細かく記載することが大切です。ここでは、雇用契約書を作成する際のポイントを解説します。
5-1. 手当がある場合は詳しく記載する
手当にはさまざまな種類があるため、手当名や金額、計算方法など詳細に記載しましょう。たとえば、通勤手当であれば、支給の有無だけでなく、実費なのか、上限を設けるのかについても記載することが大切です。支給額が変動する手当の場合は、「詳細は就業規則による」として、就業規則に支給額についてのルールを定めておくと良いでしょう。
5-2. 固定残業代を導入している場合は時間を記載する
固定残業代制度を導入している企業は、何時間分が固定残業代なのか、その時間が金額としていくらに相当するのかを明確に記載しておかなければなりません。固定残業時間を超える労働をおこなった場合は、別途残業代を支給することも忘れず記載しておきましょう。
5-3. 試用期間について記載する
試用期間を設けてから本採用する場合は、その期間や賃金について明記しましょう。とくに、試用期間と本採用後で賃金が異なる場合は、あらかじめその旨を記載しておくことが重要です。なお、試用期間と本採用後で大きく労働条件が異なる場合、試用期間終了後に改めて雇用契約を結んでも問題ありません。
関連記事:試用期間とは?設定する際の注意点やよくある質問・トラブルを紹介
5-4. 労働時間制を検討して明示する
昨今では働き方改革の影響もあり、裁量労働制やフレックスタイム制、みなし労働時間制、変形労働時間制など、さまざまな労働時間制が登場しています。しかし、通常とは異なる労働時間制を採用する場合、その内容についても記載しておくことが大切です。たとえば、フレックスタイム制を採用するのであれば、清算期間やコアタイム・フレキシブルタイムも明記しておきましょう。
5-5. 転勤や職種変更の可能性の有無を明らかにする
労働者の在職中に転勤や職種変更、人事異動などが必要になる可能性がある場合は、雇用契約書に明記しておきましょう。就業規則にその旨の記載があっても、雇用契約書に記載がなければ効果が認められず、転勤命令を出そうとしても受け入れられないリスクがあります。必要な人事異動ができなければ、新たに人材を確保するなどの対応が必要になり、手間やコストがかかるため、きちんと雇用契約書に明示しておくことが大切です。
5-6. 【注意】雇用契約書の雛形(テンプレート)を用いる場合
雇用契約書を作成する際に、インターネット上に提供されている雛形やテンプレートを使用する企業も少なくないでしょう。しかし、このような雛形・テンプレートのすべてが法令を遵守しているとは限りません。あくまでも一般的な雇用契約書をもとにした参考例にすぎないため、実際に雇用契約書を作成する際は法令をはじめ、自社の状況や従業員の雇用形態などに合わせて適宜修正を加え、適正な雇用契約書を作成しましょう。なお、厚生労働省では「労働条件通知書」の雛形が公開されているので、参考として目を通してみるとよいかもしれません。
関連記事:雇用契約書の書き方とは?記載すべき事項やパート・アルバイトのケースも紹介
6. 雇用契約書が持つ法的効力

雇用契約書は内容が法律に則っていれば法的効力を持ち、使用者と労働者はともにその内容に拘束されることになります。もしも使用者が雇用契約書の労働条件に違反した場合、労働者はその雇用契約を即時に解除することが可能です(労働基準法第15条)。また、使用者は労働基準法に則り、懲役や罰金といったペナルティが課せられる恐れもあるので注意しましょう。ここからは、雇用契約書の内容が労働基準法や就業規則に違反する場合にどうなるのかについて詳しく紹介します。
6-1. 労働基準法に違反する内容の場合
雇用契約書の内容が労働基準法に違反する場合、労働基準法第13条により、その部分は無効となり、労働基準法の定める基準が適用されることになります。つまり、法律で定める内容を下回るような労働者が大きく不利益を被る規定を雇用契約書に含めることはできません。
また、無効になった部分は、労働基準法の基準が適用されるので、使用者が自由に条件を決められるわけではありません。たとえば、時間外労働(月60時間以下)の割増率を10%と雇用契約書で定めている場合、労働基準法の基準である25%に満たないため、その規定は無効になり、割増率は25%が適用されることになります。
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
6-2. 就業規則に違反する内容の場合
雇用契約書の内容が就業規則に違反する場合、労働契約法第12条により、その部分は無効となり、就業規則の定める基準が適用されることになります。たとえば、雇用契約書で住宅手当をなしとする定めをしても、就業規則ですべての従業員に住宅手当を支給する定めをしていれば、必ず住宅手当を支給しなければなりません。
このように、労働基準法だけでなく、就業規則も雇用契約書に影響を及ぼします。雇用契約書を作成する際は、法律や就業規則を確認しながら違反しないように作ることが大切です。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
7. 【雇用形態別】雇用契約書を作成する際の注意点

ここでは、雇用形態別に雇用契約書を作成する際の注意点について詳しく紹介します。
7-1. 正社員
正社員とは、雇用期間を定めない無期雇用契約の従業員を指します。2024年4月1日から労働条件明示ルールが変更されたことに伴い、雇用契約書に就業場所や業務内容の変更範囲もきちんと明記することが大切です。変更範囲を記載していない場合、転勤や異動ができなくなる恐れもあるため注意が必要です。また、試用期間を設ける場合、その内容も細かく記載しておきましょう。
7-2. パートやアルバイト
正社員と違い、パートやアルバイトに対しては雇用契約書が不要と思われがちです。しかし、労働条件に関するトラブルを防ぐためにも、パートやアルバイトで働く従業員に対しても雇用契約書を交付するようにしましょう。
また、パート・アルバイトで働く人の雇用契約書には、昇給・退職金・賞与の有無や相談窓口など、パートタイム労働法で規定されている記載事項も含めることが大切です。また、社会保険や最低賃金などとの関係も考慮しながら雇用契約書を作成するようにしましょう。
関連記事:パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際に押さえておきたいポイント
7-3. 契約社員
契約社員とは、雇用期間に定めのある有期雇用契約の従業員を指します。契約社員に対しても、正社員と同様で、労働条件のトラブルを防止する目的で雇用契約書を交付することが大切です。
契約社員の場合、契約期間はいつからいつまでなのか、更新があるかどうかを明記しましょう。また、更新する可能性がある場合は、その更新の条件も具体的に記載することが重要です。契約期間や無期転換などに関しては法律でルールが定められているので、契約社員の雇用契約書を作成する際は違反しないよう注意しましょう。
7-4. 【注意】雇用契約書の保管期間は5年間!
労働基準法第109条により、雇用契約書の保管期間は5年間とされています。起算日は労働者の退職(死亡を含む)の日からです。雇用契約書を作成した日や、交付した日ではないので注意しましょう。なお、労働基準法第109条には経過措置が設けられており、当面の間は5年間でなく、3年間の保存でも問題ないとされています。しかし、経過措置はいつ終了するか未定なので、できる限り5年間保管するようにしましょう。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
8. 雇用契約書の内容を変更する際の注意点

ここでは、雇用契約書の内容を変更する際の注意点について詳しく紹介します。
8-1. 労働者にとって有利な労働条件に変更する場合
労働者にとって有利となる労働条件に変更する場合、就業規則の変更により対応することができます。これは就業規則で雇用契約を上回る水準の労働条件を定めれば、自動的に就業規則所定の労働条件が適用されるためです。
ただし、労働契約法第9条により、原則として、労働者が不利になるような就業規則の変更はできません。また、労働基準法第89条により、就業規則を変更した場合、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないので注意が必要です。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(省略)
8-2. 労働者にとって不利益な労働条件に変更する場合
労働契約法第8条により、使用者と労働者の合意があれば、労働条件を変更することができます。そのため、労働者にとって不利益な労働条件に変更する場合、労働者の合意を得たうえで、雇用契約を変更しましょう。雇用契約を途中変更する場合、「覚書を作成する」「新しく雇用契約書を作成する」といった方法で対応することができます。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
関連記事:雇用契約は途中で変更可能?拒否された場合や覚書のルールについても解説!
9. 雇用契約書を交わしてトラブルを未然に防ごう!

雇用契約書は、労働条件通知書と違い、交付義務について法律で定められていません。しかし、労働条件について労使双方が合意したという証拠を残すため、雇用契約書を作成することが推奨されます。雇用契約書には署名・捺印欄を設ける必要があるので注意しましょう。
なお、労働条件通知書と雇用契約書は兼用することもできます。その場合、必ず労働条件通知書の法律で定められている記載事項を含めなければなりません。また、2019年4月1日から労働条件通知書の電子化が解禁されているため、この機会に雇用契約書や労働条件通知書の電子化を検討してみるのもおすすめです。
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。
当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。
雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









