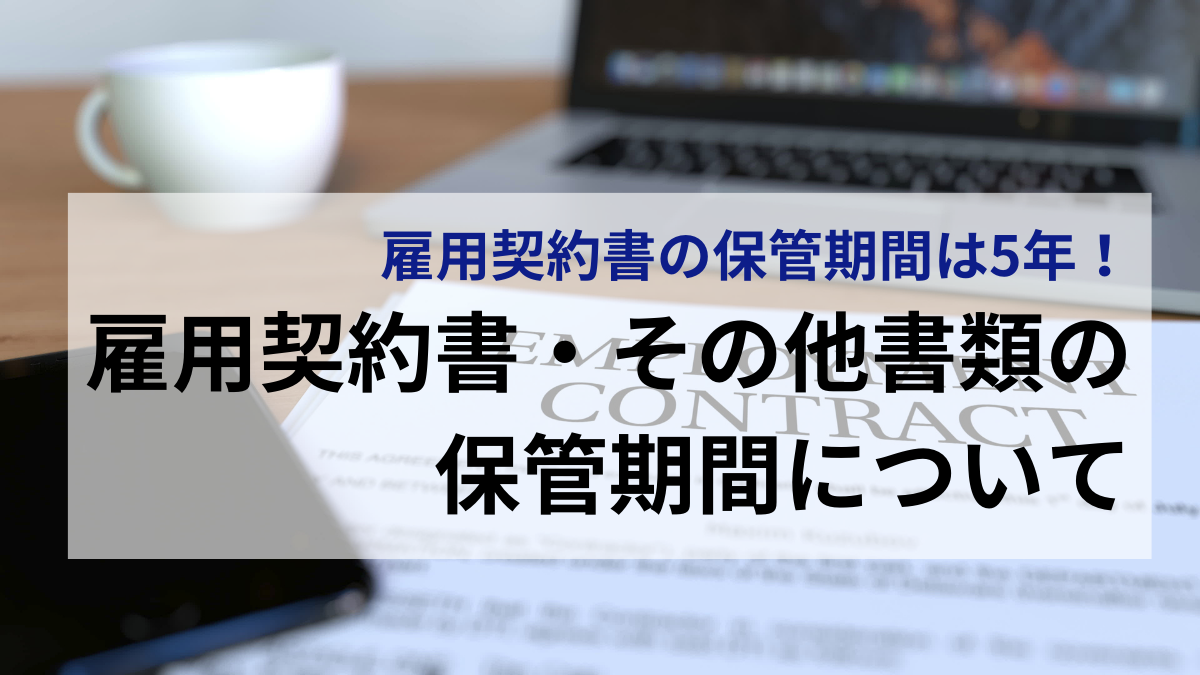
企業が労働者を雇うときは、双方が同意したうえで雇用契約書を発行します。労使間のトラブルを防止するためにも、雇用契約書には契約期間や就業場所などの条件を記載し、正しく交付しましょう。
また、雇用契約書は法律によって保管期間が決められているため、労働者が退職してもすぐに処分してはならないものです。今回は、雇用契約書とその他の書類もあわせて、保管期間について詳しく解説します。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用契約書の保管期間

労働基準法が改正され、2020年4月1日より雇用契約書の保管期間が5年に変わりました。改正前の保管期間は3年間でしたが、延長されたことにより長期間の保管が必要になったのです。
保管期間が5年になった理由は、同年に施行された民法改正が関係しています。民法改正によって、賃金の債権に関する消滅時効が2年から5年に延長されたので、労働基準法も合わせて変更されました。
賃金債権の消滅時効とは、たとえば未払いの残業代や賃金があっても、決められた期間を超えてしまうと、労働者の請求権が消滅してしまうものです。これまで2年と定められていた賃金債権の時効が5年に延長されたことに合わせて、労働基準法も同じように延長されました。
1-1. 保管期間に関する経過措置
雇用契約書の保管期間は5年に延長されましたが、実際は経過措置が講じられたため、当分の間は3年の保管で問題ありません。賃金債権の時効も当分の間は3年です。
保管期間が延長されることで企業側に負担がかかることが懸念され、経過措置が取られています。ただし、法律でよく使われる「当分の間」の期間は、明確に定められていません。多くの場合、次の改正まで現行の内容が続きますが、企業としては早めに準備を進めておくことが大切です。
なお、雇用契約書は従業員が退職した日から数えて3年間、保管する必要があります。
参考:民法の消滅時効と賃金|日本労働組合総連合会
参考:改正労働基準法等に関するQ&A|厚生労働省
2. 雇用契約書以外の書類の保管期間
法改正に伴い、雇用契約書だけでなく他の書類の保管期間も5年に変更されたので、把握しておきましょう。また、保管期間の年数が異なる書類もいくつかあるので紹介します。
2-1. 雇用契約書以外に5年の保管が必要な書類
保管期間が5年に延長されたのは雇用契約書だけではありません。労働基準法109条で定める書類は全て対象になります。以下は5年保管の対象となる主な書類です。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 雇入れに関する書類
- 解雇に関する書類
- 災害補償に関する書類
- 賃金に関する書類
- その他労働に関する書類
雇用契約書は「雇入れに関する書類」に分類されます。また、「その他労働に関する書類」のなかには、出勤簿やタイムカード、退職や休職に関連する書類などが含まれます。
雇用契約書と同じで、これらにも経過措置が適用されているので保管期間は当分の間3年です。
2-2. 2~3年間の保管義務がある書類
2年間保管しなければならない主な書類は以下の通りです。
- 健康保険に関する書類
- 厚生年金関連の書類
- 雇用保険に関する書類
健康保険に関する書類の保管期間は、健康保険法施行規則で定められており、「資格取得確認通知書」「資格喪失確認通知書」「被保険者標準報酬決定通知書」などの文書が該当します。
雇用保険に関する書類は2年間の保管義務ですが、被保険者に関する書類は4年間の保管が必要なので注意しましょう。雇用保険の被保険者に関する書類は、離職票や雇用保険被保険者資格取得確認通知書などが当てはまります。
3年間の保管義務がある書類としては、労災保険に関する書類や、労働保険の徴収・納付の書類が挙げられます。
これらは、労災保険法と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」で定められており、給付や徴収が完結した日から3年間書類を保管しなければなりません。
2-3. 7~10年間の保管義務がある書類
さらに長い期間、保管しなければならない書類も存在します。以下は7年間の保管が必要な書類です。
- 取引に関する帳簿
- 源泉徴収簿
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
取引に関する帳簿は、帳簿閉鎖日もしくは作成日や受理日の属する事業年度終了日の翌日から2カ月を経過した日を起算日として、7年間保管する必要があります。
また、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日が起算日になりますので、覚えておきましょう。
「株主総会の議事録」や「決算書類」は10年間保管する必要があり、これらは会社法で義務付けられています。
参考:人事労務関係書類保存期間一覧|日本人事労務コンサルタントグループ
参考:記録の保存期間|キノシタ社会保険労務士事務所
参考:労働保険・社会保険・人事労務 書類保存期間一覧|東京都新宿区の社会保険労務士法人リーガルネットワークス
3. 雇用契約書の正しい保管方法

保管期間が決められている書類を保管していない、もしくは期間内に処分してしまった場合、保存義務に違反するため労働基準法120条で定める罰則「30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。そのため、書類は正しい方法で適切に保管しましょう。
3-1. 電子化して場所を取らずに保管する
保管が必要な書類を電子保存することで、場所を取らず管理もしやすくなります。
ただし、書面で交付した契約書をスキャンしてパソコンに保存していた場合、コピーとして扱われることがあり、提示を求められる場面では原本が必要になりますので注意しましょう。
はじめから電子契約書で契約をしていた場合は、電子データが原本として認められます。
雇用契約書の電子化は保管に便利なだけでなく、印刷や郵送のコスト削減、やり取りの手間も省けるため、電子化する企業も増えているようです。
近年、電子帳簿保存法が改正され、保存に関するルールが緩和されたので、請求書や領収書であれば、税務署に申告しなくてもスキャン保存が可能になりました。スキャンした書類はすぐに破棄できます。
電子保存する際は、いつでも確認できるよう一元管理しておくと良いでしょう。
3-2. 書面の場合はわかりやすい方法で保管する
書面で保管をしている場合は、わかりやすい方法で保管することが重要です。保管が必要な書類は種類が多いので、種類別・年度別に分類しましょう。チェックしたいときに置き場所がわからないと、作業効率が低下してしまうため、整理整頓を心がけることが大切です。
分類した書類にはいつまで保管が必要なのかメモ書きを貼り付けておくと、いつ破棄するべき書類なのか把握しやすくなります。
また、「古い書類が取り出せない」という事態にならないよう、上に積み重ねて保管するのではなく、立てておくと良いでしょう。ファイルやフォルダに入れてまとめておくと、背表紙で確認できますのでおすすめです。
3-3. 保管期間が過ぎた書類は処分する
期限が過ぎた書類は処分しても問題ありません。
しかし、書類に書かれている情報は重要な個人情報なので、処分の際は専用業者に依頼したり、社内で適切に廃棄したりするなど、慎重におこなう必要があります。
古い書類をいつまでも保管しておくと、管理のためのコストが無駄にかかるだけではなく、場所を取るなどの問題が生じる可能性がありますので、溜め込まないようにしましょう。
4. 雇用契約書を電子化して保管するメリット

雇用契約書を電子化して保管すれば、ペーパーレス化を図れる、業務を効率化できるなどのメリットを得られます。以下、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
4-1. ペーパーレス化を図れる
ペーパーレス化を図れることは、雇用契約書を電子化する大きなメリットです。雇用契約書のデータを作成し、従業員へメールなどで送付すれば、わざわざ紙に印刷する必要がなくなります。印刷する手間や費用を削減できるのはもちろん、管理スペースの有効活用にもつながるでしょう。
環境保護の観点からも、社会のさまざまな場所でペーパーレス化が進んでいます。書類をデータ化することでコストを削減しつつ、環境に配慮すれば、企業のイメージアップを図ることも可能です。
4-2. 業務の効率化につながる
雇用契約書を電子化すれば、雇用条件の提示や契約手続きに関する業務を効率的に進められます。紙の書類でやり取りしようとすると、印刷や交付の作業にかなりの時間がかかってしまうでしょう。電子データであればメールなどで送付するだけでよいため、担当者の負担を軽減できます。
また、管理の手間を削減することも可能です。書類の整理や廃棄にかかる時間を省けるため、コア業務に集中でき、企業全体の生産性が向上するでしょう。
4-3. 契約手続きを素早くおこなえる
契約手続きを素早くおこなえることも、雇用契約書を電子化するメリットのひとつです。とくに一度に多くの従業員を採用する場合は、大量の雇用契約書を作成しなければなりません。紙の雇用契約書を作成しようとすると、作業の手間がかかって担当者の負担が増えたり、残業が発生したりする可能性もあります。
電子化によって採用プロセスを効率よく進め、スムーズに仕事を開始できるようにしましょう。
5. 雇用契約書の保管期間中は正しく保存しておこう

雇用契約書の保管期間は2020年の法改正によって、3年から5年に延長されましたが、現在は経過措置が取られているため当分の間は3年の保管義務となっています。
しかし、経過措置はいつまで続くのかわかりませんので、企業は今のうちから5年間保管できる体制を整えておいた方が良いでしょう。
雇用契約書の保管は法律で義務付けられているため、書面もしくは電子保存をして、いつでもチェックできるようにしておく必要があります。
書類は種類が多く、保管年数や関連法律も異なりますが、保管義務のある書類は正しく適切に保管しておきましょう。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









