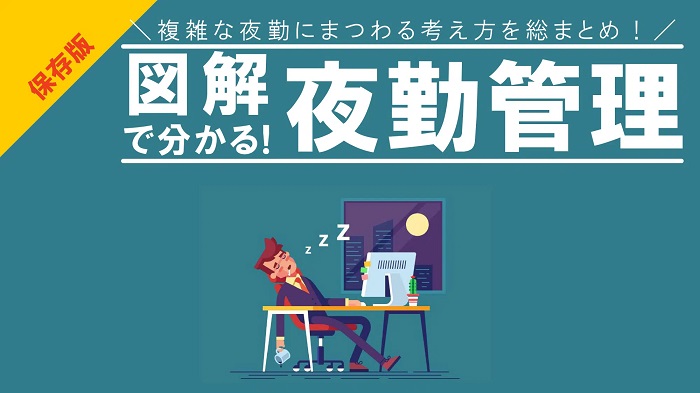夜勤手当とは、夜勤が発生した場合に支給される手当のことです。夜勤手当と深夜手当は労働基準法で定義されているかという違いがあります。正しくルールを定めずに給料を計算していると、違法になり罰則を受けるリスクがあります。この記事では、夜勤手当と深夜手当の違いを解説します。また、深夜手当の計算方法や、計算を効率化するためのツールも紹介します。
日勤とは異なる勤務形態である夜勤は、労働基準法で別にルールが設けられているため、「何が正しい夜勤の勤怠管理か理解できていない」という方もいらっしゃるでしょう。
そのような方に向け、当サイトでは夜勤時の休憩や休日の取らせ方、割増賃金の計算方法まで、労働基準法に則った夜勤の扱い方について解説した資料を無料で配布しております。
「法律に沿って正しい夜勤管理をしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 夜勤手当とは?

夜勤手当とは、夜勤をする労働者に支払われる手当のことです。夜勤手当と深夜手当は一見同じ手当に思えますが、法律で定義されているかなどにおいて違いがあります。ここでは、夜勤手当とは何か、深夜手当との違いを踏まえて詳しく紹介します。
1-1. 夜勤とは?
夜勤とは、原則22時から5時までの労働のことです。夜勤をおこなうことで、生活リズムが崩れ、健康に悪影響を及ぼすリスクもあります。そのため、通常の賃金に加えて、労働の負担の重さを考慮して、夜勤手当などの手当を支給する企業も多いです。
関連記事:夜勤とは何時から働いた場合のこと?労働基準法上の定義とは
1-2. 夜勤ができる従業員の条件
労働基準法第61条により、原則として18歳未満の従業員に夜勤をさせることはできません。ただし、交代制によって働く16歳以上の男性など、例外規定もあります。また、労働基準法第66条に則り、母子の健康上の理由で本人から申請があった妊産婦(妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性)に対しても、夜勤をさせることができません。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。(省略)
第六十六条 (省略)
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説
1-3. 夜勤手当と深夜手当の違い
夜勤手当と類似しているのが深夜手当です。どちらも似たような意味で使われますが、明確な違いがあります。夜勤手当は、夜間に働く人に支給する手当のことで、会社が任意で支給します。たとえば、看護師や介護職、建設業のように夜勤が前提となっているような職種において支給されるケースが多いようです。しかし、法律で定められていないため、必ず支給する必要はありません。また、「1カ月〇円」「夜勤1回につき〇円」のように、夜勤手当の金額も会社が自由に定められます。
一方、深夜手当とは、労働基準法第37条で定められた手当のことで、深夜労働をおこなった従業員に対して必ず支払うことが義務付けられています。深夜手当は、通常の賃金の25%以上とされています。たとえば、1時間の深夜労働があったら、1時間分の通常の賃金に25%以上の割増率を掛けて、深夜手当が計算されます。深夜手当の割増率は25%以上であれば、30%でも40%でも問題ありません。ただし、25%を下回ると違法になるので注意が必要です。このように、夜勤手当と深夜手当は意味が異なるため正しく定義を理解しておきましょう。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 (省略)
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
関連記事:深夜労働は何時から何時まで?深夜時間帯の割増賃金の計算方法も詳しく解説!
1-4. 夜勤手当を支給する場合は就業規則への記載が必要
夜勤手当は、深夜手当と違い、法律で定められていないので、支給しなくても問題ありません。しかし、夜勤手当を支給するのであれば、あらかじめ支給金額や支給方法などを就業規則で定めておく必要があります。労働基準法第89条に基づき、常時従業員数10人以上の企業は、賃金の定めを含めて就業規則を作成し、届け出る義務があります。
また、労働基準法第15条の労働条件の明示義務により、新しく雇用する従業員に対しては夜勤手当が支払われることについて、労働条件通知書などを通して事前に周知しておく必要もあります。このように、夜勤手当を支払う義務はありませんが、支給する場合はあらかじめ就業規則や労働条件通知書を通して従業員に正しく周知することが大切です。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(省略)
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(省略)
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
2. 深夜手当(深夜労働の割増賃金)の計算方法

夜勤手当は企業の裁量で自由に支給できます。しかし、深夜手当(深夜労働の割増賃金)は労働基準法で基準が定められているので、正しく計算しなければ違法になり、罰則が課せられる恐れもあります。なお、深夜手当を計算する際の基本的な計算式は、次の通りです。
深夜労働の割増率は、法律で2割5分以上と定められているので、それを下回らないよう注意が必要です。ここからは、時給制、日給制、月給制それぞれの場合の深夜手当の計算方法について紹介します。
2-1. 時給制の深夜手当の計算方法
ここでは、時給1,000円の労働者が18時〜23時の5時間勤務した場合を例に、深夜手当がいくらになるのかシミュレーションして紹介します。この場合、18時〜22時までの4時間は通常勤務、22時〜23時までの1時間が深夜労働に該当します。そのため、1時間分の深夜手当を支給しなければなりません。深夜手当の計算式は次の通りです。なお、割増率は25%で計算しています(以後、同様)。
つまり、深夜手当は250円になります。したがって、この場合の支払うべき総賃金は、5,250円(=4,000円+1,250円)となります。
2-2. 日給制の深夜手当の計算方法
ここでは、所定労働時間が18時〜22時で日給4,000円の労働者が18時〜23時の5時間勤務した場合を例に、深夜手当がいくらになるのかシミュレーションして紹介します。
まず1時間あたりの基礎賃金を計算する必要があります。この場合、1時間あたりの基礎賃金は1,000円( = 4,000円 ÷ 4時間)と求められます。深夜手当の計算式は次の通りです。
この場合も、深夜手当は250円になります。したがって、この場合の支払うべき総賃金は、5,250円(= 4,000円 + 1,250円)になります。
2-3. 月給制の深夜手当の計算方法
月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金を計算するのに、まず月平均所定労働時間を算出する必要があります。単純に月給を月の労働日数で割ってしまうと、祝日などの関係で営業日数が月によって異なり、月ごとに1時間あたりの基礎賃金が変わってしまう可能性があります。そのため、年間を通して同じ基礎賃金で割増計算できるように、月平均所定労働時間を次の計算式で算出します。
次に、月給を月平均所定労働時間で除すことで、月給制の場合の1時間あたりの基礎賃金を計算することができます。ただし、月額賃金から次のような手当は除外して計算しなければならない点に注意が必要です。
- 家族手当 (扶養人数に応じて支払うものに限る)
- 通勤手当 (通勤距離等に応じて支払うものに限る)
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当 (住宅に要する費用に応じて支払うものに限る)
- 臨時に支払われた賃金
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
ここからは、次のような労働者を想定して、深夜手当がいくらになるのかシミュレーションして紹介します。
- 月給:25万円
- 年間日数:365日
- 年間休日:110日
- 諸手当:なし
- 1日の所定労働時間:8時間
- その月の深夜労働時間数:10時間
このケースでは、その月に10時間分の深夜手当の支給が必要です。まず月平均所定労働時間は148.75時間と計算できます。これを基に、1時間あたりの基礎賃金を計算すると、1,680円(端数処理後)となります。
この場合の深夜手当は4,200円です。月給に深夜手当4,200円を加えて、その月の給与として支給する必要があります。
当サイトでは、深夜0時をまたいで働いた際の暦日の考え方、深夜労働時の割増賃金の適切な計算方法をわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。 労働基準法に沿った勤怠管理や深夜手当の考え方を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
3. 深夜手当と残業手当の関係

深夜労働だけ発生するのであれば、深夜手当を割増計算して支給すれば問題ありません。しかし、深夜労働と残業が重なるケースもあります。ここでは、深夜手当と残業手当の関係について詳しく紹介します。
3-1. 残業手当には3種類ある
残業が発生した場合、残業代(残業手当)を計算しなければなりません。残業手当は「法定内残業」「法定外残業(60時間以内)」「法定外残業(60時間超え)」の3種類があります。労働基準法第32条で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えない残業であれば、割増賃金の支給は不要です。
しかし、法定労働時間を超える労働は法定外残業に該当し、割増率25%以上を適用して時間外労働の割増賃金を支給しなければなりません。また、法定外残業が月60時間を超える場合、割増率50%以上を適用する必要があります。このように、残業手当は残業の種類によって計算が異なるので注意が必要です。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も
3-2. 深夜手当と残業手当が重なった場合の計算方法
深夜労働と残業が重なった場合、割増率を合算して割増賃金を支給する必要があります。したがって、深夜手当と残業手当が重なる場合の割増率は、次のようになります。
- 深夜労働と法定内残業:25%以上
- 深夜労働と法定外残業(60時間以内):50%以上
- 深夜労働と法定外残業(60時間超え):75%以上
(例)所定労働時間が9時~18時(休憩時間1時間)、時給1,000円の従業員を9時~23時で労働させた場合
|
時刻 |
割増率 |
計算式 |
給与 |
|
9:00~18:00 |
0% |
1,000 × 8 |
8,000円 |
|
18:00~22:00 |
25% |
1,000 × 4 × 1.25 |
5,000円 |
|
22:00~23:00 |
50% |
1,000 × 1 × 1.5 |
1,500円 |
|
【合計】14,500円 |
|||
このように、深夜労働と時間外労働が重複する場合、給与計算が複雑になるので注意が必要です。
関連記事:【図解】夜勤した従業員の休憩時間・休日・賃金の計算方法を分かりやすく解説
4. 深夜手当と休日手当の関係

深夜労働と休日出勤が重なるケースもあります。ここでは、深夜手当と休日手当の関係について詳しく紹介します。
4-1. 休日手当は法定休日に出勤する場合に支給が必要
休日手当とは、労働基準法第35条で定められた法定休日(週1日または4週4日)に労働が発生する場合に支給する手当のことです。休日労働に対しては35%以上の割増率を適用して、休日手当を支給しなければなりません。なお、法定休日の労働時間はすべて休日労働に含まれるので、時間外労働は発生しないことになります。つまり、休日労働と時間外労働が重なることはありません。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
4-2. 深夜手当と休日手当が重なった場合の計算方法
深夜労働と休日労働が重なった場合も、割増率を合算して割増賃金を計算する必要があります。深夜手当と休日手当が重なる場合の割増率は60%以上です。
(例)時給1,000円の従業員が法定休日に15時~23時で勤務した場合(18時~19時の1時間で休憩を取得)
|
時刻 |
割増率 |
計算式 |
給与 |
|
15:00~22:00 |
35% |
1,000 × 6 × 1.35 |
8,100円 |
|
22:00~23:00 |
60% |
1,000 × 1 × 1.6 |
1,600円 |
|
【合計】9,700円 |
|||
このように、夜勤(深夜労働)のみならず、時間外労働や休日労働にも当てはまる場合は、各種割増手当を加算して賃金を支給する必要があります。
4-3. 所定休日の出勤の場合は残業手当が発生する可能性がある
法定休日以外に所定休日を設けている企業も少なくないでしょう。たとえば、土日休みの場合、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日としている企業もあります。所定休日の出勤の場合、通常の労働日と同様の勤務として扱われます。休日労働に該当しないため、休日手当の支給は不要です。
ただし、所定休日の場合、残業手当が発生する可能性があります。また、所定休日に残業と深夜労働が重なった場合、割増率を合算して、割増賃金を支給しなければなりません。このように、所定休日の出勤の場合は、法定休日の出勤の場合と賃金の計算方法が変わるため注意が必要です。
関連記事:休日出勤して残業したらどうなる?残業代の計算方法と法定休日の割増賃金を解説
5. 深夜手当を計算する際の注意点

深夜手当の計算は法律で定められており、きちんと守らなければ違法になり、罰則が課せられる恐れもあります。ここでは、深夜手当を計算する際の注意点について詳しく紹介します。
5-1. 正社員でもアルバイトでも手当の支給対象となる
労働基準法はすべての労働者に適用されます。そのため、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、夜勤をさせた全従業員に深夜手当を支給しなければなりません。また、企業の裁量で夜勤手当を支給する場合も、同一賃金・同一労働の原則に則り、雇用形態で差別化してはならないので注意が必要です。
5-2. 管理職でも深夜手当の支給は必要
労働基準法第41条に該当する管理職の人は、労働時間や休憩時間、休日の規定が適用されなくなります。そのため、残業手当や休日手当は支給しなくても問題ありません。ただし、深夜労働の規定は適用されるので、深夜手当は必ず支給しなければなりません。また、管理監督者に対しても労働時間の把握義務はあるため、1分単位で正確に勤怠管理をおこないましょう。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
5-3. 深夜手当の端数処理にはルールがある
深夜手当を計算する際、1時間あたりの基礎賃金や、割増賃金の金額などに端数が生じることもあるかもしれません。そのような場合、切り捨てて処理すると、労働基準法の「全額払いの原則」に違反することになる可能性があります。従業員が不利にならないよう、切り上げて計算するようにしましょう。ただし、割増賃金の計算や1カ月の賃金計算において、端数を切り捨てても問題ないケースがあります。しかし、就業規則に記載が必要など、ルールが定められているので、端数処理をする際は気を付けましょう。
労働基準法上認められている端数処理方法は次のとおりです。
(1)割増賃金の計算
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。
(省略)
(3)1か月の賃金計算
D.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。
E.1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが出来る。
なお、E・Dの取り扱いをする場合は、その旨就業規則に定めることが必要です。
5-4. 固定残業代制における深夜手当の計算には注意が必要
固定残業代制(みなし残業代制)とは、基本給に加えて、あらかじめ一定の残業があるものとみなして残業代を支給する制度を指す言葉です。固定残業代に深夜手当を含めることもできますが、事前にその時間と金額を就業規則に明記しておく必要があります。また、みなし残業時間を超えて深夜残業があった場合、別途で残業手当や深夜手当の支給が必要になるので気を付けましょう。
関連記事:みなし残業と固定残業の間違いやすいポイントを徹底解説
5-5. 裁量労働制にも深夜労働は適用される
裁量労働制とは、業務の時間配分や手順、やり方を労働者の裁量に任せる制度のことです。たとえば、裁量労働制のみなし労働時間を8時間と設定している場合、労働時間が6時間であっても、10時間であっても、8時間として扱われることになります。そのため、原則として残業代は発生しません。
ただし、みなし労働時間が8時間を超える定めにした場合や、休日出勤が発生した場合などは、残業手当や休日手当が発生することになります。また、深夜労働が発生した場合は、深夜手当も上乗せして支払わなければならないので注意が必要です。
関連記事:裁量労働制は残業代が出ない?計算方法や休日出勤・深夜労働についてわかりやすく解説!
6. 深夜手当の計算に便利なツール

深夜手当の計算そのものは、それほど難しいものではありません。しかし、従業員によって夜勤の時間帯が異なったり、残業・休日と重なったりするケースがあるため計算ミスが生じやすく、計算対象となる従業員が多いほど業務の負担も大きくなります。ここでは、深夜手当の計算を効率化するための便利なツールを紹介します。
6-1. Web上の計算ツール
インターネット上には、1時間あたりの基礎賃金や夜勤の労働時間、割増率を入力するだけで、簡単に深夜手当を計算できるツールがあります。Web上の計算ツールは、無料で利用できるものも多く、素早く導入することが可能です。そのため、コストの負担なく、導入することができます。
ただし、従業員数が多い場合、入力に時間や手間がかかるので、かえって業務負担が大きくなる恐れもあります。従業員数が少なく、シンプルな勤怠制度を導入している場合、Web上の計算ツールを使用して深夜手当を計算してもよいかもしれません。
6-2. エクセルやスプレッドシート
Excelやスプレッドシートといった表計算ソフトを活用すれば、関数やマクロを用いて計算を自動化し、深夜手当の計算を効率化することができます。また、既に表計算ソフトを導入していればコストはかかりません。さらに、従業員が使い慣れているため、操作しやすいというメリットがあります。
ただし、Excelやスプレッドシートの場合、人の手で深夜労働の時間を入力しなければならず、手間がかかったり、人的ミスが発生したりする恐れもあります。また、関数・マクロにエラーが生じると、復旧に時間がかかるケースもあります。従業員数が少なく、コストの負担を減らして勤怠管理をしたい場合、まずExcelやスプレッドシートなどの表計算ソフトで深夜手当を計算してみてもよいかもしれません。
6-3. 勤怠管理システムや給与計算ソフト
勤怠管理や給与計算に課題を感じている場合、勤怠管理システムや給与計算ソフトといった専用のITツールの導入を検討してみるのも一つの手です。勤怠管理システムや給与計算ソフトを導入すれば、打刻・集計・給与計算を連携しておこなえるため、人的ミスを減らし、業務を効率化することができます。また、深夜手当の計算も自動化することが可能です。勤怠管理システムや給与計算ソフトにはあらゆる種類があるので、料金や機能、使いやすさなどを比較して、自社のニーズにあったツールを選定することが大切です。
7. 夜勤手当や深夜手当に関連するよくある質問

ここでは、夜勤手当や深夜手当に関連するよくある質問への回答を紹介します。
7-1. 夜勤手当や深夜手当を支給しない場合の罰則は?
夜勤手当の支給は法律で定められたものでないため、就業規則や雇用契約書・労働条件通知書などで労働者に明示していないのであれば、支払わなくても違法になりません。
一方、深夜手当の支給は労働基準法第37条で定められた義務です。従業員に夜勤をおこなわせたのに、深夜労働に対する割増賃金を支払わなかった場合、労働基準法第119条に基づき、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れもあるので注意しましょう。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第三十七条、(省略)の規定に違反した者
7-2. 夜勤手当は非課税?
夜勤手当は労働の対価に該当するため、所得税法上、非課税になりません。深夜手当も同様です。
しかし、宿直(夜間に勤務先で待機すること)や日直(日中に勤務先で待機すること)に対する手当であれば、勤務1回につき4,000円までを非課税とできる可能性があります。ただし、食事が支給される場合は、4,000円からその食事の価額を控除した残額までが非課税の対象です。このように、夜勤手当や深夜手当は「給与所得」として課税されますが、非課税になる手当もあるため、法律を基にきちんと確認しておきましょう。
(宿日直料)
28-1 宿直料又は日直料は給与等(法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。)のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。
7-3. 育休明けは夜勤を拒否できる?
育児休業から復帰した従業員がいきなり夜勤のある仕事に就くと、生活リズムが乱れ、体調を崩す恐れがあります。育児・介護休業法第19条により、小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てている労働者から請求があった場合、原則として、事業主は当該労働者に深夜労働をおこなわせることができません。ただし、事業に支障がある場合など、拒否できるケースもあるため、育児・介護休業法や就業規則などもきちんとチェックするようにしましょう。
第十九条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。(省略)
引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第19条一部抜粋|e-Gov
8. 夜勤手当と深夜手当の違いを押さえて正しく給与を支給しよう

夜勤手当は、企業の裁量で自由に支給するか決められます。ただし、夜勤手当を支給する場合、労働条件通知書・雇用契約書や就業規則に明記することが大切です。一方、深夜手当は、労働基準法で定められた手当であるため、深夜労働があった労働者に支給しないのは違法になります。深夜手当の計算方法は複雑になるケースもあるため、勤怠管理システムや給与計算ソフトの導入を検討してみるのもおすすめです。
日勤とは異なる勤務形態である夜勤は、労働基準法で別にルールが設けられているため、「何が正しい夜勤の勤怠管理か理解できていない」という方もいらっしゃるでしょう。
そのような方に向け、当サイトでは夜勤時の休憩や休日の取らせ方、割増賃金の計算方法まで、労働基準法に則った夜勤の扱い方について解説した資料を無料で配布しております。
「法律に沿って正しい夜勤管理をしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。