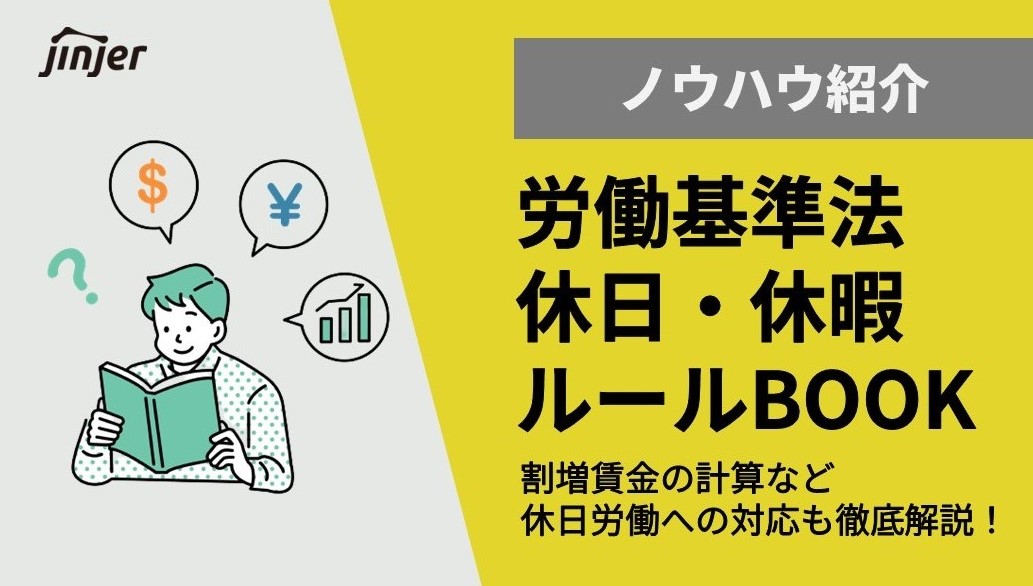休日出勤した従業員に代わりの休日を取得させるために「代休」を与えることがあります。代休は法律で定められたものでないため、必ずしも従業員に与える必要のある休日ではありません。
しかし、従業員の健康面を考慮して、休日出勤をさせた場合は代休を与えて取得させるよう労務管理をおこなうのが望ましいです。
今回は、代休と振替休日との違いを交えながら、休日出勤した従業員に代休を取得させる方法や注意点を解説します。
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
目次
1. 休日出勤の代休をなしにするのは違法?

法律上、企業が従業員に代休を取得させる義務は存在しません。代休の取り扱いは就業規則や労働契約に依存します。
そのため、企業は明確なルールを整備し、代休取得に関する方針を周知することが求められます。従業員にとって、制度が理解しやすいことが重要です。
2. 休日出勤の代休なしが違法になる場合

休日出勤に対して代休を与える義務はありませんが、場合によっては休日出勤後に代休を取得させないと違法になるケースもあります。詳しくみていきましょう。
2-1. 代休なしにより法定休日の条件を満たさない場合
法定休日は最低でも「1週に1日」もしくは「4週に4日」です。そのため、代休を取得させないことにより、この条件を満たさなくなる可能性があります。たとえば、1週間に1日の休日を設けている場合、その法定休日に出勤させると、1週間に1度も休日を取得しないことになるので違法です。この場合、労働基準法第119条により、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が課される恐れがあります。
なお、36協定を締結している場合はこの限りではありません。
2-2. 休日手当が支払われない場合
代休では本来休日であった日に出勤をし、その後に代わりの休日を決めます。そのため、法定休日に出勤させた場合に、休日労働に対する割増賃金を支払わないのは違法です。この場合も、労働基準法第119条により、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性があります。ただし、振替休日は事前に出勤日と休日を入れ替えているため、休日労働に対する割増賃金が支払われなくても違法にはなりません。
2-3. 就業規則に記載せずに代休を有給休暇に変更した場合
企業が就業規則に記載せずに、代休を有給休暇に変更することは、法的に問題があります。
これは労働者の権利を侵害する行為であり、違法性を伴います。有給休暇の取得を拒否し、強制的に代休を適用することも許されません。どちらの場合も、企業は慎重に対応する必要があります。
2-4. 代休取得の権利を明示している場合に拒否する
労働契約や就業規則に代休取得の権利が明示されている場合、従業員からの申請を拒否することはできません。
企業の人事担当者や現場の管理者は就業規則や労働契約をしっかりと確認し、従業員の権利を尊重した運用を心がける必要があります。
3. そもそも休日出勤とは
 休日出勤とは、法定休日もしくは所定休日(法定外休日)に出勤することを指します。法定休日とは、労働基準法第35条に定められた休日で、会社は必ず週に1回または4週に4回の休日を設けなければなりません。一方、所定休日(法定外休日)は会社が独自で定めた休日であり、法律により定められた休日ではありません。まずは、休日出勤には2種類があることを押さえておきましょう。
休日出勤とは、法定休日もしくは所定休日(法定外休日)に出勤することを指します。法定休日とは、労働基準法第35条に定められた休日で、会社は必ず週に1回または4週に4回の休日を設けなければなりません。一方、所定休日(法定外休日)は会社が独自で定めた休日であり、法律により定められた休日ではありません。まずは、休日出勤には2種類があることを押さえておきましょう。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
関連記事:休日出勤の定義|支給すべき賃金やルールについて詳しく解説
3-1. 休日出勤をした場合の残業や割増賃金の扱い
法定休日に出勤した場合は「休日労働」の扱いになるため、割増賃金の支払いが必要になります。ただし、法定休日に出勤した場合、時間外労働は適用されないので、残業代は生じません。
一方、所定休日に出勤した場合は、通常の労働日と同様に扱われます。そのため、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働くと、「時間外労働」の扱いになります。時間外労働が発生したら、割増賃金を支払う必要があります。
なお、法定休日でも所定休日でも、22時から5時までの間に労働した場合は「深夜労働」となり、割増賃金の支払いが発生します。各種割増率は次の表の通りです。
|
種類 |
割増率 |
|
時間外労働(月60時間以内) |
25%以上 |
|
時間外労働(月60時間超え) |
50%以上 |
|
休日労働 |
35%以上 |
|
深夜労働 |
25%以上 |
法定休日に夜勤をおこなった場合、休日労働と深夜労働が重なるため、60%以上の割増率を適用する必要があります。また、所定休日の深夜時間に残業をおこない、その月の残業時間が60時間を超える場合、75%以上の割増率を適用して、割増賃金を支払わなければなりません。
関連記事:休日出勤が残業扱いになる場合とは?計算方法とあわせて解説
3-2. 休日出勤をするには原則36協定の締結が必要
法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に労働させたりすることは、原則として認められていません。時間外労働や休日労働をおこなわせるには、36協定の締結が必要です。なお、36協定を結んだとしても、時間外労働や休日労働には上限があるので注意する必要があります。
以上から、休日出勤をさせるには、原則36協定の締結が必要です。ただし、所定休日に労働させる場合で、法定労働時間を超えないのであれば、36協定の締結は不要です。
このように、法定休日と所定休日で残業代や割増賃金、36協定の取り扱いが変わるので、きちんと理解を深めておくことが大切です。
関連記事:36協定の休日出勤に必要な届出と休日出勤の上限について詳しく解説
4. 労働基準法における代休とは

代休とは、休日出勤後、別の労働日に休みを取得させることをいいます。代休は労働基準法で定められている制度でないため、法定休日の要件を遵守していれば、休日出勤をした後に代休を与えなくても違法とはなりません。
関連記事:代休の定義とは?振休・有給の違いなど基本的なところを詳しく解説
4-1. 振替休日との違い
代休とは、休日出勤した後に、代わりとなる休日を別の労働日に取得させることをいいます。一方、振替休日とは、休日出勤する際に、事前に休日と別の労働日を入れ替えておくことをいいます。
つまり、代休が「事後」に休日を付与するのに対して、振替休日は「事前」に休日を付与するといった大きな違いがあります。代休と振替休日の違いをまとめると以下のようになります。
|
|
代休 |
振替休日 |
|
休日の決定タイミング |
休日出勤「後」 |
休日出勤「前」 |
|
割増賃金の支払い |
・休日労働:法定休日の場合に必要 ・時間外労働:法定外休日の場合に必要 |
・休日労働:不要 ・時間外労働:必要 |
なお、代休も振替休日も、法律で定められた用語ではないので注意が必要です。
4-2. 代休を与えないリスク
代休を与えない場合、法定休日や所定休日に出勤した分、人件費が増加します。また、代休を与えないことにより、従業員の健康状態の悪化や仕事に対するモチベーション低下などの悪影響を及ぼす恐れもあります。そのため、休日出勤があったら、代休を取得させるようにしましょう。
なお、法定休日に出勤させた場合や、所定休日に時間外労働をさせた場合、割増賃金を支払う必要があります。代休を取得させたとしても、割増賃金分の人件費の上昇は避けられないことを理解しておきましょう。
4-3. 代休の取得期限はある?
代休は法律に定められた休みではないため、付与自体が任意となっています。そのため、代休の取得期限は法律上で明確に定められていません。ただし、労働基準法第115条では、「災害補償その他の請求権」の時効は行使できるときから2年間と定められています。そのため、代休の取得期限は2年間だと考えられます。
ただし、代休の取得期限を2年とするのは、長期間に及んで従業員の代休管理をしなければならず、労務管理の負担が大きくなります。また、代休は、従業員の健康管理の観点から、休日出勤の直後に取得させるのが望ましいです。
以上から、代休の取得期限は、就業規則で定めるのが一般的です。会社が取得期限を自由に設定できますが、繁忙期なども考慮して1~2か月の期限を設けている会社が多いようです。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
関連記事:代休に取得期限はある?消滅時の対応や管理のポイントを解説
4-4. 休日出勤は代休で相殺できる?
休日出勤の中でも、所定休日に出勤させた場合、代休を取得させることでほかの労働日の労働義務を免除することができます。一方、法定休日に出勤させた場合は休日労働となり、代休を取得させたとしても休日労働分の割増賃金は相殺できません。割増賃金は労働者にとって負担の大きい労働に対して支払われる賃金であるため、代休を与えたとしてもその分の賃金は支払う義務があります。
関連記事:残業の相殺は違法?代休やボーナスとの相殺は可能か解説
5. 休日出勤後に代休を取得した場合の割増賃金の計算方法

休日出勤をして代休を取得した場合、休日出勤した分については割増賃金の支給が必要となることがあります。代休の割増賃金額については、休日出勤した日が「法定休日」または「法定外休日」かによって扱いが変わってきます。なお、割増賃金は次の式で計算することが可能です。
ここでは、休日出勤の後に代休を取得した場合の支払うべき割増賃金の計算方法について詳しく紹介します。
関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説
5-1. 法定休日に休日出勤した場合
法定休日に休日出勤した場合、後日代休を取得したとしても、「休日労働」に該当するため35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
- 法定休日(日曜日)に出勤後、次の火曜日に代休を取得
- 休日出勤(日曜日)の労働時間:10時間
- 1時間あたりの基礎賃金:2,000円
この場合、休日労働の割増賃金が発生します。割増賃金は7,000円(2,000円 × 10時間 × 0.35)となります。なお、1日の法定労働時間を超えて働いていますが、休日労働には時間外労働が適用されないので、残業代は生じません。火曜日に代休を取得しても、通常の労働日の賃金については控除できますが、休日出勤した際の割増賃金については控除できないので注意が必要です。
5-2. 法定外休日(所定休日)に休日出勤した場合
所定休日(法定外休日)は法律上の休日に該当しないため、休日労働に対する割増賃金の支給は不要です。しかし、法定労働時間の上限「1日8時間、週40時間」を超えている場合は、時間外労働の割増賃金を支払わなくてはいけません。
- 法定外休日(土曜日)に出勤後、次の水曜日に代休を取得
- 日曜日~金曜日までの労働時間の累計は48時間(日曜日を起算日とする)
- うち休日出勤時(土曜日)の労働時間:8時間
- 1時間あたりの基礎賃金:2,000円
土曜日は1日の法定労働時間を超えていませんが、週の法定労働時間を超えています。そのため、8時間分の時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。割増賃金は4,000円(= 2,000円 × 8時間 × 0.25)です。
なお、次の水曜日に代休を取得して賃金を相殺したとしても、時間外労働の割増分は残ります。法定外休日の労働の場合、起算日に注意が必要です。もしも木曜日を起算日としている場合、金曜日~水曜日の週の労働時間が40時間以内に収まっていれば、土曜日に時間外労働の割増賃金は発生しないことになります。
休日出勤が発生した際の割増賃金計算は、従業員が事前に振替休日を取得しているか、該当の週、該当日にその従業員が何時間勤務したのかなどの要素によって計算方法が変化します。なぜ割増率が変化するのかもっと詳しく知りたいという方に向けて、当サイトでは「休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」という無料のガイドブックをお配りしています。振替休日や代休など各種制度の相違点や、休日に関する法律の規制を細かく解説しているので、休日出勤に対する適切な対応を確認したいという方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードして、ご活用ください。
6. 代休を運用する際の注意点
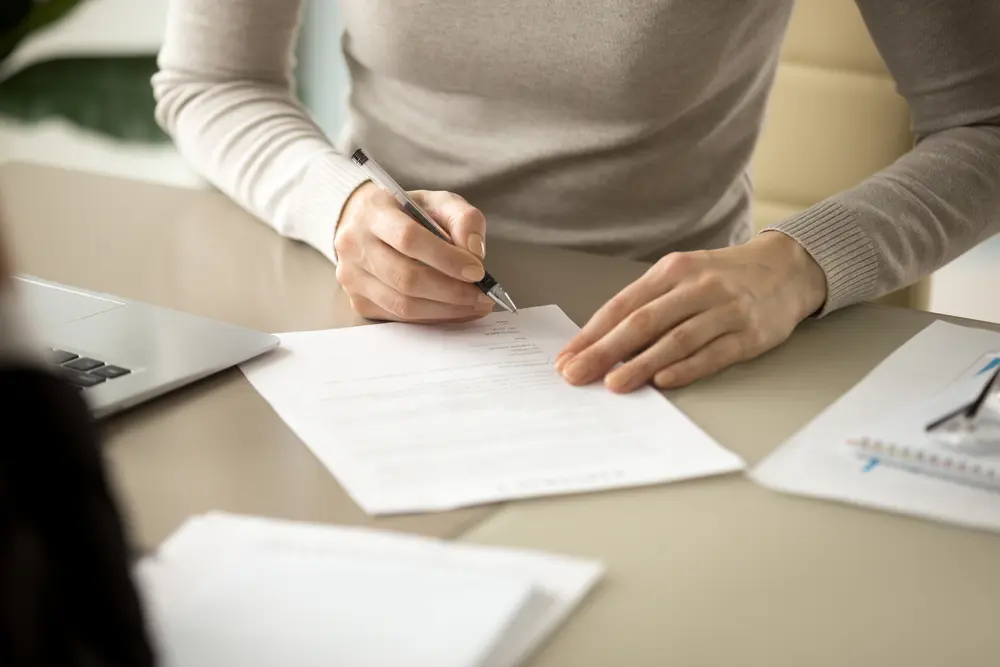
代休、振替休日は、たとえ人事担当者や労務担当者であっても混同しやすいものです。従業員においてはさらによく理解していないケースも珍しくありません。ここでは、トラブルを起こさずスムーズに休日出勤や代休を運用する際の注意点を紹介します。
6-1. 代休や代替休暇について就業規則に記載する
代休や振替休日の制度を円滑に運用するためには、就業規則や労働条件通知書・雇用契約書など、あらかじめ書面に決まりを明記しておくことが大切です。
代休や振替休日は、就業規則などに記載していなくても取得させることは可能です。しかし、代休・振替休日を取得すると賃金控除が発生するため、従業員から「代休を取りたくない」「振替休日の代わりに有給休暇を取得したい」といった申し出がある可能性もあります。このような場合でもスムーズに対応できるよう、細かく代休や振替休日のルールを定めておきましょう。
6-2. 休日出勤後の代わりの休日は必ず代休扱いにする
休日出勤が発生した後で代わりの休日を設定する場合は「代休」扱いとなります。また、法定休日の休日出勤に対しては、休日労働の割増賃金が発生します。
割増賃金を支払いたくないからといって本来代休であるはずの休日を振替休日扱いにすることは認められません。従業員から未払い賃金として請求を受ける可能性もあります。
納期が迫っているといった理由から、急遽休日出勤が必要となる場合、後日代休として休日をとることはやむを得ません。しかし、事前に休日出勤となることがわかっているのであれば、割増賃金を発生させないためにも、代休でなく、振替休日を取得させましょう。
6-3. 管理職には代休を付与しなくてもよい
労働基準法第41条により、管理監督者には休日に関する規定が適用されないので、代休を付与しなくても問題ありません。ただし、肩書が管理職であっても、労働基準法上の管理監督者に該当しないケースがあります。このような「名ばかり管理職」には、労働基準法の労働時間や休憩、休日が適用されるため、代休・代替休暇についても一般従業員と同様に適切に取得させる必要があります。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)
関連記事:労働基準法第41条第2号の「管理監督者」の意味や特徴を詳しく解説
6-4. 従業員に休日出勤を強制してはならない
休日出勤や残業は、会社が命じることは可能でも、従業員に強制することはできません。
同様に、代休の取得についても、従業員の意思が尊重されるべきです。もし従業員が割増賃金の支払いを希望する場合、その意向に応じて対応が求められます。
なお、拒否したことでペナルティを科すことは許されないため、企業は適切な運用を心がける必要があります。
7. 代休について正しく理解し従業員へ早めの取得を促そう

代休とは、休日出勤した後に、別の労働日に休日を入れ替えることです。代休の取得期限は会社が自由に決められるため、従業員への代休の取得を促す意味でも、早めに期限を設けておくと良いでしょう。業務量が多く代休を取得できない従業員には、半日や時間単位で取得を促すこともできます。
なお、代休を活用する場合、法定休日に出勤した日に対しては、休日労働の割増賃金を支払わなければなりません。前もって休日出勤が発生するとわかっているのであれば、代休ではなく、振替休日を取得させるようにしましょう。