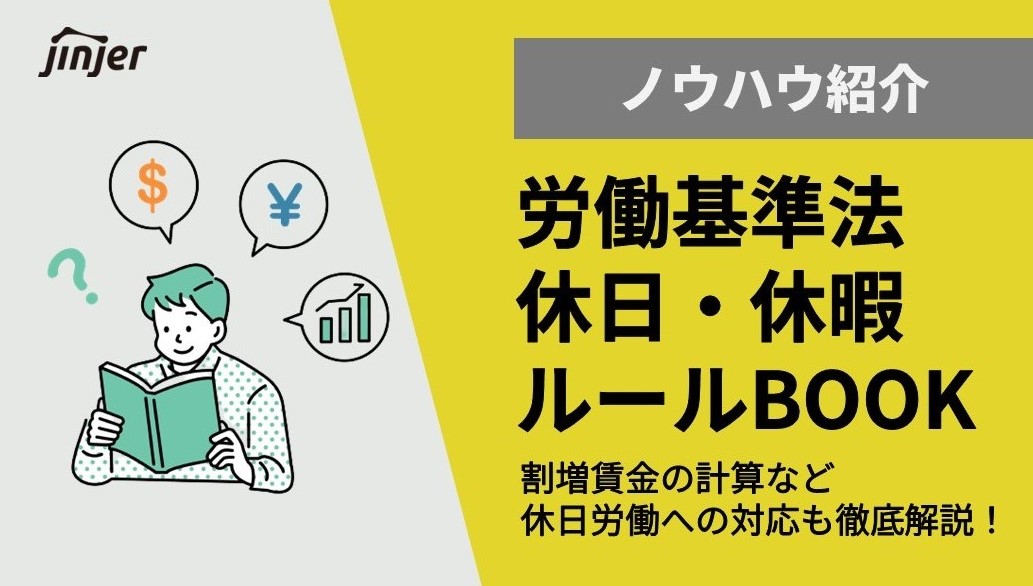本来の休日と出勤日を交換する形で取得する振替休日ですが、期限切れになった場合の対応を含め、休日を取得できる期限についてよく知らないという企業担当者も多いのではないでしょうか。今回は、振替休日と他の休みの違いについて確認しながら、振替休日を取得すべき期限について紹介します。また、振替休日の取得期限に関して、企業が注意しておきたい点についてもあわせて解説します。
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
目次
1. 振替休日の期限とは?

振替休日とは、法定休日・法定外休日といった休日に出勤をした場合に、代替として他の勤務日を休日とすることです。振替休日は、勤務日と休日が入れ替わっただけなので、出勤日の代わりの休みをあらかじめ指定して取得させなければなりません。ここでは、振替休日の定義を説明したうえで、振替休日の期限について詳しく紹介します。
1-1. 厚生労働省による振替休日の定義
振替休日は、労働基準法などの法律で定められた制度でないため、明確な定義があるわけではありません。しかし、厚生労働省により、振替休日の定義が明示されています。厚生労働省による振替休日の定義は次の通りです。
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
このように、振替休日とは、あらかじめ休日と定められている日を勤務日にし、その代わりに他の勤務日を休日とすることを意味します。法律で定められていないので、必ずしも振替休日の制度を設けなければならないわけではありません。しかし、振替休日を設定する場合、厚生労働省の定義に従って適切な仕組みを構築することが大切です。
関連記事:振替休日の基本的な部分を休日の定義や条件とあわせて詳しく紹介
1-2. 振替休日の期限は2年
振替休日は法律で定められていないので、明確な取得期限もありません。ただし、労働基準法第115条「時効」により、振替休日の期限は、振り替える労働日から「2年間」と考えられます。そのため、振替休日は振替日から2年以内に取得させるようにしましょう。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
1-3. 振替休日はできる限り早く取得させるのが望ましい
振替休日に明確な取得期限は設けられいませんが、労働基準法の時効の観点から2年で権利が喪失すると考えられます。しかし、振替休日の目的は、休日に勤務した労働者に休息を与えることです。そのため、振替休日は休日出勤日からできるだけ近い日程で取得させることが望ましいです。
2. 振替休日の付与に必要な3つの要件

振替休日の制度を設ける場合、期限のみを守ればよいわけではありません。ここでは、振替休日を正しく付与するための3つの要件について詳しく紹介します。
2-1. 就業規則に規定する
振替休日は法律で設けられた制度ではありません。そのため、振替休日を設けなくても違法にはなりません。しかし、振替休日を設計する場合、就業規則にその内容を明記する必要があります。なお、労働基準法第89条により、常時従業員数10人以上の企業は、休日や休暇の内容を含めた就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2-2. 出勤する休日と労働日をあらかじめ設定し、休日出勤日の前日までに連携する
振替休日は、休日出勤の前に、休みとする日を定めなければなりません。休日出勤後に指定して、代わりに休日を取得する場合、振替休日の定義を満たさなくなるので注意が必要です。振替休日を設ける場合、休日出勤の前日までに休日出勤の日と、その代わりの休みの日を明確にするよう制度を構築することが大切です。
2-3. 法定休日の要件を満たす
労働基準法第35条により、週に1日もしくは4週に4日の休日を必ず労働者に与えなければなりません。たとえば、1カ月に4日の休日を設定しており、そのうち1日を休日出勤した場合、その月の休日数は3日になってしまいます。もしも振替休日を次の月に取得する場合、労働基準法の法定休日のルールに違反することになります。そのため、法定休日の要件を満たしているかどうか確認したうえで、振替休日を付与するようにしましょう。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
関連記事:法定休日と法定外休日の違いとは?振替休日や代休との関係もわかりやすく解説!
3. 振替休日と代休の違い

振替休日と混同されやすい制度に「代休」があります。代休とは、休日に労働をおこなった後、その代わりに休みを取得させることを意味します。なお、代休も法律で定められた制度ではないため、必ず設ける必要はありません。ここでは、振替休日と代休の違いについて詳しく紹介します。
3-1. 休日決定のタイミングの違い
振替休日を設ける場合、出勤する休日の前日までに振替休日を取得させる日を決定し、従業員に予告しておく必要があります。一方、代休の場合は、休日出勤をした後に休日を定めます。そのため、急な休日出勤が決まった場合には、代休で対応することが一般的です。
なお、代休の取得期限も、労働基準法第115条の「時効」の観点から2年間とされています。しかし、振替休日と同様で、労働者に適切な休息を与えるためにも、休日出勤日と近い日程で代休を取得させることが推奨されます。
関連記事:振替休日と代休の違いとは?計算方法の違いや注意点を解説
3-2. 賃金の計算方法の違い
振替休日の場合は、出勤日と休日を入れ替えただけという考えになります。そのため、法定休日だった日に出勤した場合でも、割増賃金の計算・支給は不要です。一方、代休の場合には、休日労働をした代替として休みを取得させることになります。そのため、法定休日に出勤させた場合、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要です。
従業員を出勤させた場合、法定休日では35%以上、法定外休日であっても、法定労働時間を超過した分の労働時間に対しては、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。このように、割増賃金の支給の有無について、振替休日と代休には違いがあります。
代休付与での対応になった場合の運用ルールについて不安があるという方は、当サイトがお配りしている「休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」をご覧ください。このガイドブックでは労働基準法による休日の定義から振替休日、代休の細かな制度の違い、休日の管理方法についてもわかりやすく解説しています。休日出勤時の適切な対応を確認したい方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」を無料でダウンロードしてご活用ください。
4. 振替休日と有給休暇の違い
 振替休日ともう一つ混同されやすい制度に、年次有給休暇があります。有給休暇は、従業員のリフレッシュを目的とした休暇で、働いていなくても給与が発生します。ここでは、振替休日と有給休暇の違いについて詳しく紹介します。
振替休日ともう一つ混同されやすい制度に、年次有給休暇があります。有給休暇は、従業員のリフレッシュを目的とした休暇で、働いていなくても給与が発生します。ここでは、振替休日と有給休暇の違いについて詳しく紹介します。
4-1. 法律で定義されているかの違い
振替休日は法律で定義されていないので、必ずしも制度として設ける必要はありません。一方、有給休暇は労働基準法第39条により定められた制度なので、要件を満たした労働者に対して必ず休暇を付与しなければなりません。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
4-2. 給与の発生に関する違い
振替休日の場合、休日勤務日の給与は発生しますが、振替休日自体に給与が発生することはありません。一方、有給休暇を取得した場合、その日の勤務時間分の給与を受け取ることができます。振替休日を取得すると、賃金が減るという観点から、振替休日の代わりに年次有給休暇を取得したいと申し出る従業員もいます。このような場合、就業規則に明確な記載がなければ、企業側は有給休暇の申請を拒否できないので注意が必要です。
4-3. 休日の取得基準についての違い
振替休日は、休日の取得条件として、出勤した休日の前日までに振替日を決定しておかなければなりません。休日出勤後に休日を取得した場合、代休扱いとなるので注意が必要です。一方、有給休暇の場合は、一定の条件を満たしている場合のみ付与されるものとなります。付与の条件としては、以下の2つが挙げられます。
- 雇い入れ日から継続して6カ月間勤務した場合
- 労働日の出勤率が8割以上の場合
有給休暇付与の要件を満たしている場合、パート・アルバイトや契約社員などの雇用形態に関係なく、すべての従業員に有給休暇を付与しなければなりません。
関連記事:【図解】有給休暇の付与日数がひと目でわかる!付与要件や最大日数の求め方
5. 振替休日の期限に関して企業が注意すべき点

振替休日については取得期限に加えて、さまざまな細かなルールがあります。ここでは、振替休日の期限に関して企業が注意すべき点について詳しく紹介します。
5-1. 振替休日の期限をあらかじめ定めて就業規則に明示する
振替休日の制度を設ける場合には、あらかじめルールを決め、期限を定めておき、就業規則に記載することが大切です。振替休日を指定する際、ルール上は最長で2年の間で決めることができます。しかし、1年半などに設定すると、運用が煩雑になります。また、振替休日の期限をあらかじめ企業で定めておくことで、遠すぎる振替休日の取得を避けることにもつながります。自社の振替休日の取得期限を設定したら、従業員とのトラブルを避けるためにも、就業規則にきちんと明記しておくようにしましょう。
5-2. 業務量を調整する
休日出勤を依頼しなければならない理由を考えた際に、業務自体に問題がないかを確認しましょう。「1人に業務の負担が偏っている」「業務を円滑に回すための人材が不足している」「スキルが業務内容に追いついていない」といった場合、休日出勤と振替休日でその場をしのぐだけでなく、根本的な問題を解決する必要があります。また、休日出勤をしたものの、振替休日を取得することによる業務の滞りが生じないよう、従業員が振替休日を取得するための業務量の調整をおこなうことも大切です。
5-3. 週をまたぐ振替休日は割増賃金が発生する
労働基準法第37条により、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働をおこなった場合に、時間外の割増賃金を支払う必要があると定めています。月曜日から金曜日まで週40時間働いた後に、さらに労働日を設定した場合、労働時間は規定の週40時間を超過することになります。この超過した時間に対しては、時間外の割増賃金として25%以上の割増率が加算されます。このように、振替休日の取得が週をまたぐ場合、割増賃金が生じる可能性もあるので注意が必要です。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
5-4. 月をまたぐ振替休日は一旦給与を支払う
月をまたいで振替休日を取得させる場合、締め日よりも前に休日出勤をおこなった分に対しては給与を支払う必要があります。これは、労働基準法第24条に規定されている「賃金全額払いの原則」に基づくものです。労働した分の給料は、労働が発生した際に支払わなければなりません。振替休日が月をまたいだ場合、一般的に1日分労働日が多くなった月と1日分休日が多くなった月が発生します。労働日が多くなった月は1日増えた労働日分の賃金を加算して給与計算しなければなりません。休日分の給与については、改めて休日を取得した時点で控除をおこないます。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
関連記事:月またぎの振替休日を処理する手順と注意点を徹底解説
5-5. 労働基準法に違反しないように注意する
週や月をまたいでの振替休日の取得は労働基準法の法定休日や法定労働時間の規定に違反してしまう可能性があります。また、月をまたいでの振替休日の取得は給与計算のミスを招く原因にもなります。さらに、時間外労働や休日労働が発生する場合、36協定の締結と届出が必要になります。
法定労働時間や法定休日、割増賃金、36協定などの労働基準法の規定に違反すると、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則が科せられる恐れがあります。また、労働基準法に違反すると、厚生労働省のホームページなどに企業名が公表され、社会的信用を損なう可能性もあります。このようなペナルティを受けないよう、振替休日を設ける場合、法律を正しく理解し、適切に対応することが大切です。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
5-6. 再振替にする場合の対処法
振替休日に設定した日にやむを得ず仕事が入ってしまう可能性もあるかもしれません。このような場合、振替休日の再振替が可能です。ただし、労働者の心身の負担を考慮すると、なるべく避けるようにしましょう。また、再振替をおこなう場合、法定休日や賃金支払いの5原則などの法律に抵触しないよう注意が必要です。
6. 振替休日の期限に関連するよくある質問

ここでは、振替休日の期限に関連したよくある質問への回答を紹介します。
6-1. 半日や時間単位で振り替えることは可能?
振替休日を半日や時間単位で取得させることはできません。振替休日の休日というのは、暦日単位で付与するものなので、半日や数時間の場合、休日と認められません。そのため、有給休暇のように半日や時間単位で付与することはできません。独自に企業の就業規則などで「振替休日を半日や時間単位で取得できる」などと定めていても、無効となる可能性が高いので注意しましょう。
関連記事:振替休日の半日単位や時間単位での取得は可能?違法になる場合も解説!
6-2. 振替休日が期限切れになったらどうする?
振替休日が期限切れになってしまうケースもあるかもしれません。振替休日は法律で定められた制度でないため、就業規則の期限に従うのが一般的です。そのため、就業規則により振替休日が期限切れとなってしまったら、従業員は原則として振替休日を取得することができません。ただし、法定休日などの要件を満たさなくなった場合は、振替休日などの休日を取得させなければなりません。また、振替休日の目的に基づき、休日出勤日とできるだけ近い日程で振替休日を取得させるようにしましょう。
6-3. パート・アルバイトにも振替休日は適用される?
正社員だけでなく、パート・アルバイトや契約社員なども、労働者に該当します。そのため、法定休日や法定労働時間などの労働基準法がパート・アルバイトにも適用されます。もしも、パート・アルバイトとして働く人が休日出勤(法定休日)する場合、割増賃金が発生します。しかし、振替休日をパート・アルバイトにも適用できるよう制度を整備しておき、休日出勤の日と代わりの休みの日を入れ替えることで、休日労働に対する割増賃金の支給を減らし、人件費の抑制につなげることが可能です。
関連記事:休日出勤は残業扱いになる?計算方法や代休・振替休日の対応をわかりやすく解説!
7. 振替休日の取得期限を意識して長期化を避けよう

振替休日の取得期限については明確な基準はないものの労働基準法第115条に則り、最長でも2年までと考えられています。しかし、社内ルールでは、できれば2年よりも短い期限で設定するようにし、その点について就業規則などに明記しておいたほうがよいでしょう。可能な範囲で、入れ替えた勤務日の前後で振替休日を取得させれば、休日取得の長期化を避けることもできるようになります。従業員の健康や割増賃金などに大きな影響を与えるので、常に振替休日の取得期限については意識しながら運用をおこなっていくことをおすすめします。