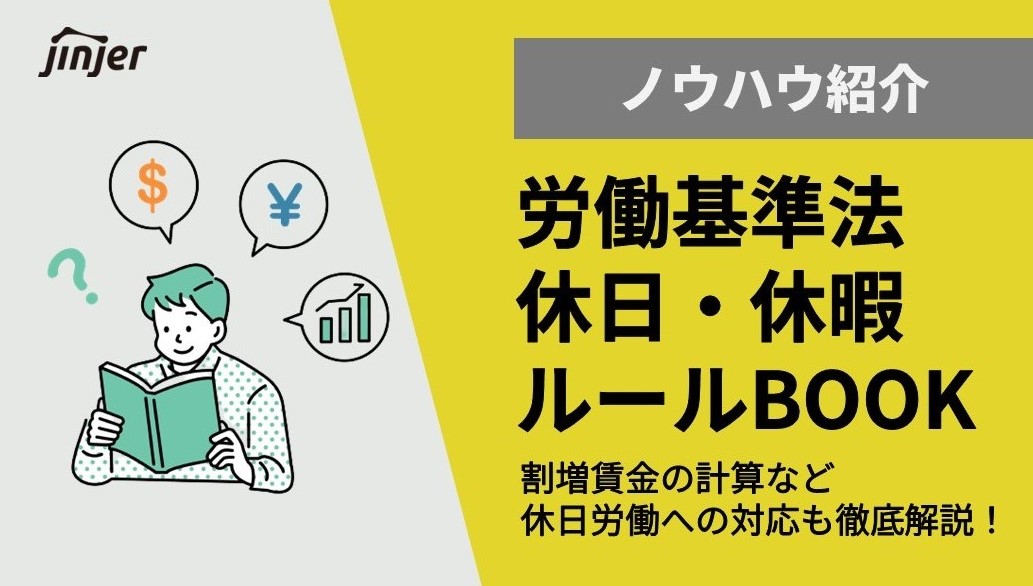類似した休みである「振替休日」と「代休」ですが、これら2つには休みを取得するタイミングや賃金計算の方法など、明確な違いがあります。
今回は、振替休日と代休の主な違いについて解説していきます。また、両者の賃金計算方法で大きく異なる点について取り上げ、賃金計算をする際の注意点についてもふれていきます。
【休日出勤の対応や振休代休の付与に不安のある方へ】
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
目次
1. 「振替休日」と「代休」の定義の違い

振替休日と代休の違いについて、順に確認していきましょう。
振替休日の定義は、前もって休日とされていた日を労働日とし、そのかわりにあらかじめ日時の違う他の労働日を休日とすることです。
一方、代休の定義は、休日出勤をおこなった後、そのかわりとして本来労働日であった日に休日を取得することです。
あらかじめ休日と労働日を交換した振替休日と、休日出勤が発生した後に休日を付与する代休は全くの別物です。また、定義以外にも割増賃金と取得条件などに違いがあります。
振替休日と代休を混同してしまった場合、割増賃金の計算を誤る可能性があるため、違いをしっかりと把握しておきましょう。
関連記事:振替休日の基本的な部分を休日の定義や条件とあわせて詳しく紹介
1-1. 「休日」と「休暇」、「法定休日」と「法定外休日」の違い
振替休日と代休の違いを正しく理解する上で重要となるのが、「休日」の考え方です。
振替休日や代休は、休日を変更することです。休日と似た意味を持つ言葉に「休暇」があります。
休日とは、もともと労働義務がない日を指します。一方の休暇は、本来は労働日に該当するものの、労働義務が免除される休みのことです。
休暇の具体例としては、年次有給休暇、夏季休暇、育児休暇などがあります。
また、「休日」には以下の2つの種類があります。
| 休日の種類 | 概要や注意点 |
| 法定休日 |
|
|
法定外休日 (所定休日) |
|
法定休日と法定外休日(所定休日)では、割増賃金(残業代)の割増率が異なります。詳しくは、後ほど解説します。
2. 「振替休日」と「代休」の休日を決めるタイミングの違い

振替休日か代休かを分けるポイントの1つに、休日を設定するタイミングがあります。
振替休日は、もともと休日と定められた日に出勤する代わりに、「あらかじめ」設定される別の休日のことです。これに対し代休は、もともと休日と定められた日に労働し、「その後」設定する別の休日のことです。
つまり、代わりとなる休日を設定するタイミングが事前の場合は「振替休日」、事後の場合は「代休」となります。
3. 「振替休日」と「代休」の割増賃金の違い
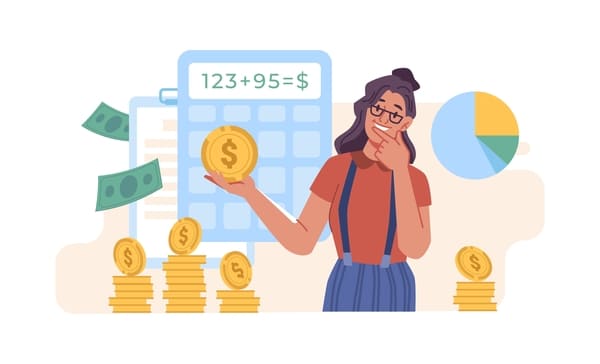
同じ1日の休みでも、振替休日か代休かで企業が支払うべき割増賃金に違いが生じます。本章では、それぞれに支払うべき割増賃金と割増率について解説します。
なお、割増賃金の規定は以下の表を参考にしてください。
| 残業の種類 | 割増率 | 残業が発生する条件 | |
| 時間外労働 | 1.25倍以上 | 1日8時間・週40時間のいずれかを超える労働が発生した場合(法定外休日の労働時間は含まれるが、法定休日の労働時間は含まれない) | 時間外労働が月60時間までの部分 |
| 1.5倍以上 | 時間外労働が月60時間を超えた部分 | ||
| 深夜労働 | 1.25倍以上 | 22時~翌5時の間の労働 | |
| 休日労働 | 1.35倍以上 | 法定休日の労働 | |
| 割増の対象となる労働が重複した場合 | 1.5倍以上 |
・時間外労働が0時間を超えて月60時間までの部分 ・深夜労働が重複する部分 |
|
| 1.75倍以上 |
・時間外労働が月60時間を超えた部分 ・深夜労働が重複する部分 |
||
| 1.6倍以上 | ・法定休日に深夜労働した部分 | ||
3-1. 振替休日の割増賃金
振替休日では休日と出勤日を入れ替えただけとなるため、原則として通常の給与分のみを賃金として支払います。法定休日と出勤日を交換し、もともと法定休日だった日に労働させたとしても、休日労働に対する割増賃金は発生しません。
ただし、入れ替えて出勤日となった日に時間外労働や深夜労働が発生した場合は、その分の割増賃金が必要となります。時間外労働と深夜労働それぞれの割増率は25%以上で、両者が同時に発生した場合には、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、同一週内に振替休日を設けず、翌週にまたがるようなケースでは、労働基準法上に規定されている週40時間を超える労働が発生する可能性があるため、割増賃金を支払わなければならない可能性も出てきます。
3-2. 代休の割増賃金
代休では、休日に出勤をしたあと代わりとして休日を取得するため、場合によって割増賃金の支払いが必要です。
休日出勤をした日が法定休日であった場合、35%以上の割増賃金が必要となります。休日出勤をした日が所定休日であった場合、1日8時間、週40時間を超えた部分から時間外労働に対する割増賃金が25%以上で必要となります。
また、法定休日・所定休日とも、労働が22時~5時に及んだ場合は深夜労働に対する割増賃金が25%以上で上乗せされるため、注意しましょう。
4. 「振替休日」と「代休」の取得条件の違い
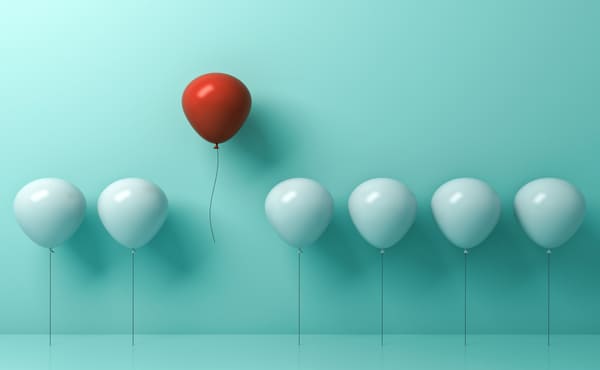
振替休日と代休を取得させる場合には、条件や決めておきたいルールが存在します。
条件を満たしていなければ振替休日を運用できない可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
4-1. 振替休日の取得条件
振替休日が社内で有効なルールとして認められる条件には、次の4つが挙げられます。
- 振替休日に関する事項が就業規則に規定されていること
- 休日出勤前日の勤務終了前までに従業員に振替日を予告していること
- 法令で定められている法定休日が確実に確保されていること
- 振替休日とする日を前もって指定すること
これらの点が明確にされていない状態で、振替休日のルールを運用しようとすると、振替休日が有効なものとして認められない可能性があります。この場合、代休として扱うことになるため注意しましょう。
4-2. 代休の取得条件
代休には振替休日のように絶対に定めなくてはならない規定や守らなくてはならない条件は特にありません。
ただし、従業員とのトラブルを避けるためにも、就業規則に代休について規定しておくことが望ましいでしょう。
代休を運用する際に決めておきたいルールは、次の3つが挙げられます。
- 代休の申請方法(申請書の提出方法など)
- 代休を取得する期限(休日出勤後、いつまでに代休を取得するか)
- 代休を取得する際の賃金(法定休日・所定休日に出勤した場合の割増賃金)
5. 「振替休日」と「代休」を取得させる際の注意点

振替休日や代休を取得させる際には注意すべき点があります。これらの点に気を付けなければ、違法運用になったり、労働者から「不当な扱いをした」とみなされたりするため、しっかりと確認しておきましょう。
5-1. 時間外労働を代休で相殺するのは違法
時間外労働分の割増賃金を支払わず、代休で相殺することは違法です。なぜなら、時間外労働は25%以上の割増賃金を支払うべき労働で、代休で相殺すると割増分の給与が未払いとなってしまうからです。
5-2. 従業員の許可なく欠勤を代休にはできない
従業員が休日出勤後に欠勤した場合、従業員の許可なく欠勤日を代休としてはいけません。
あくまでも従業員の同意があった場合のみ、欠勤日を代休とすることができます。
5-3. 振替休日と代休を付与するにはあらかじめ就業規則に定めておく必要がある
振替休日と代休を付与する際には、あらかじめ就業規則に明記しておくことが必須です。
制度を適切に運用するためには、その根拠を明確にしておく必要があります。
記載がないまま制度を導入すると、後々トラブルの原因となり、最悪の場合は振替認定が否定され、割増賃金の支払いを求められるリスクがあります。
制度を知らずに運用することのないよう、的確なルール作りを心掛けることが重要です。
5-4. 期限を守る
振替休日に明確な期限はありませんが、労働基準法により、権利の消滅時効である「2年」が適用されます。しかし、休日を2年後に設定するのは現実的ではありません。
振替休日は、同一賃金支払期間内で行なわれることが望ましいので、給料の締日よりも前に休日を取得できように設定しましょう。
就業規則などに、「振り替える日程は休日出勤から1か月以内」などのように、あらかじめ取得期限に関するルールを決めておくと運用や管理がスムーズになります。
5-5. 事後の休日は「代休」扱いとなる
これまでに解説した通り、振替休日は休日出勤の「前日」までに、従業員に休日・出勤日を伝えておく必要があります。
そのため、すでに休日出勤をしてしまった場合に、振替休日として扱うことはできません。この場合は「代休」として扱い、必要に応じて割増賃金を支払う必要があります。
コストなどを理由に、代休ではなく振替休日として扱いたいと考える企業も少なくないと思われますが、ルールを守って適切に制度を運用しましょう。
5-6. 有給休暇の取得希望がある場合はそちらを優先する
原則として、代休は取得しなければならない義務はありませんが、有給については従業員が望んだ日に取得させる義務があります。そのため、従業員から、有給取得の希望があった場合には、休日出勤をおこなった場合でも、有給を優先させなければなりません。
ただし、代休というのは休日に労働させた際に発生する休日です。そもそも法定休日に従業員を働かせる場合や時間外労働をさせる場合は36協定の締結が必要になります。このような振替休日や代休など休日に関する細かい規定は数多くあります。
すべてを調べて確認するのは手間がかかるため、当サイトでは休日や休暇についてまとめた無料のガイドブック「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」をお配りしています。
一度ダウンロードしていただくといつでも読み返すことができるので、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードして休日に関する各種対応の参考書代わりにご利用ください。
5-7. 振替休日が月をまたぐ場合には給与からの控除が必要
従業員に振替休日を取得させる場合、やむを得ず休日取得が翌月になってしまう、というケースもあります。
このような場合には、休日出勤をした月には1日分の給与を支給し、休日を取得した翌月の給与から1日分を控除する計算をしなければなりません。
給与は働いた分支給しなければならないので、振替休日と労働日が月をまたいだからといって労働分の給与を後ろ倒しにしたりすることはできません。
関連記事:月またぎの振替休日を処理する手順と注意点を徹底解説
6. 「振替休日」と「代休」で労働基準法違反になる事例

最後に、振替休日と代休でよくあるラトラブル事例を2つ紹介します。
6-1. 繁忙期などを理由に、振替となる休日を取得させない
振替休日を利用したくても、繁忙期などを理由に休日を設定できないケースも出てくるかもしれません。このような場合は、以下のいずれかの方法で対処しましょう。
- 休日の再設定をおこなう
- 一定期間を過ぎても休日が設定できない場合は、休日手当として支給する
一度設定した休日を、再度変更することに違法性はありません。ただし、就業規則などに明記しておく必要があります。
また、あらかじめルールとして決めていた期間内に休日を取得できない場合は、休日出勤分の給与を支払いましょう。
繁忙期を理由に、休日を取得させず休日手当も支払わないというのは法令違反となるので注意が必要です。また、この場合は休日分の割増賃金を支払うことも忘れないようにしましょう。
6-2. 振替勤務中の実働時間が8時間を超えたが割増賃金を支払わない
振替による勤務において、実働時間が1日8時間、もしく週40時間をを超えることもあるかもしれません。この場合は、振替出勤中であっても時間外労働が発生しているため、割増賃金を支払う必要があります。
「法定休日、所定休日問わず、1日の労働時間が8時間を超過、もしくは週労働時間が40時間を超過した場合、25%の割増賃金を支払う」というルールに則って振替勤務の割増賃金を支払うことを覚えておきましょう。
7. 振替休日と代休の違いを理解し、正しく運用しよう!

振替休日と代休の主な違いは、休みの取得タイミングと休日労働に対する割増賃金の支払いが必要かどうかです。
振替休日では、休日出勤の前日の勤務終了までに従業員に振替日を予告する必要がありますが、出勤日と休日を入れ替えただけという前提のため、原則として休日労働に対する割増賃金の支払いは不要です。
一方、代休では、休日出勤をおこなった後に、出勤の代替として休日を取得する形となり、休日に出勤した割増賃金の支払いが必要になります。
両者の違いを理解して、就業規則などにルールを明記しておきましょう。これにより、振替休日や代休にありがちな労使トラブルの発生を防ぎ、法令に基づいた適切な運用が可能となるでしょう。