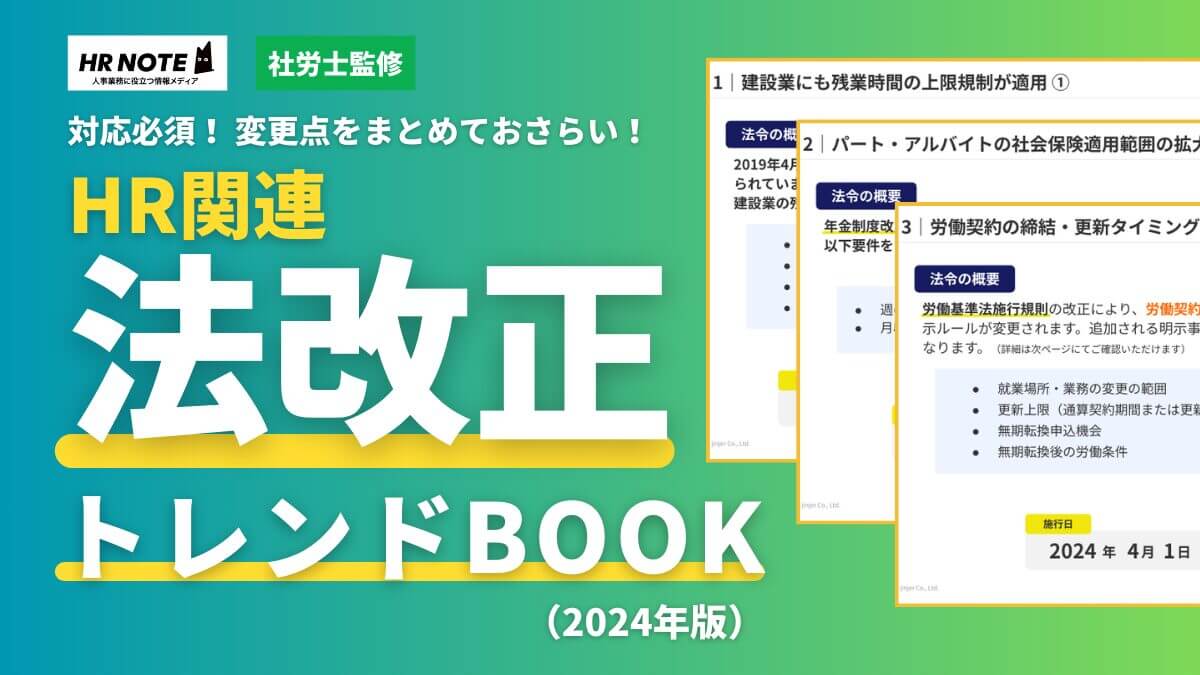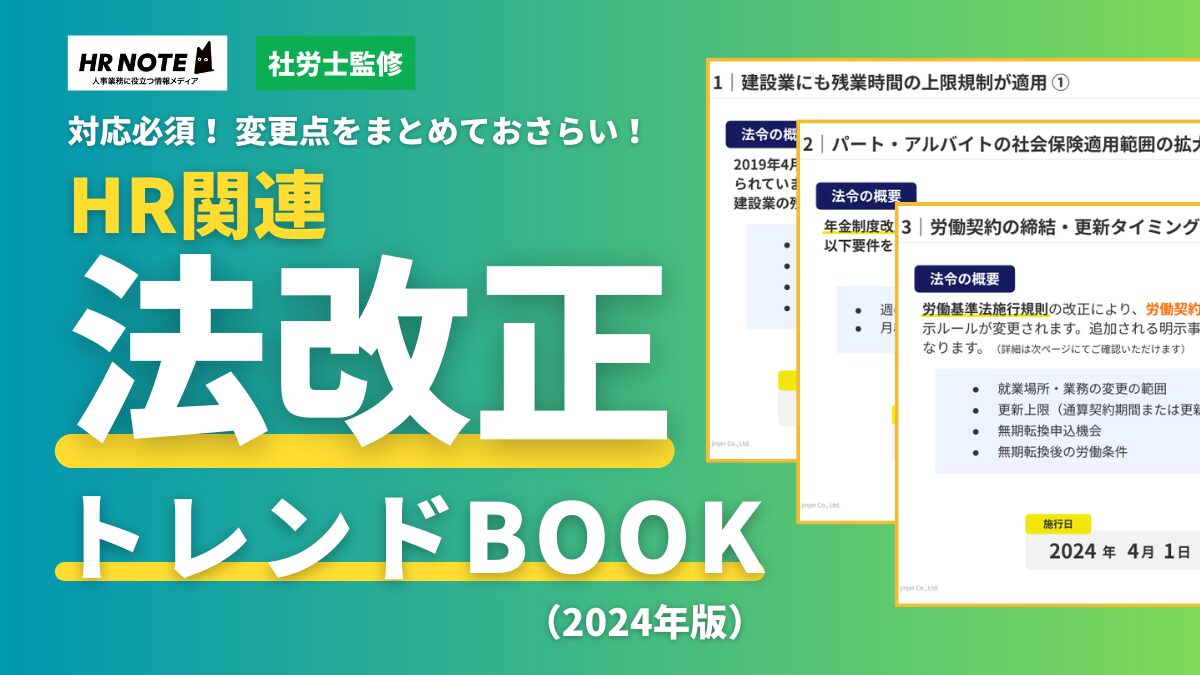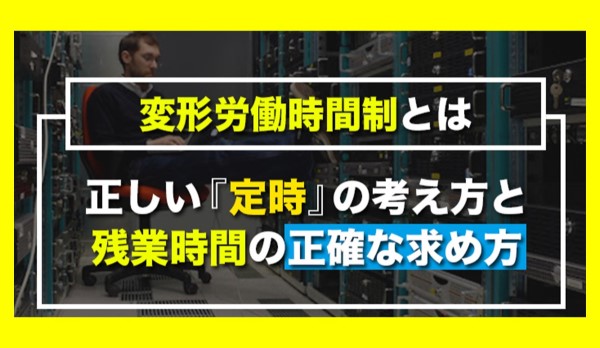
変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。
ただし、変形労働時間制の場合でも法律で規定された労働時間を超えた分は残業代として支払わなければなりません。
変形労働時間制は繁忙期や閑散期など、業務にかかる時間が月や週ごとにバラつきがある場合に労働時間を調整できることから、夏休みなどの長期休暇がある教職員などでも導入が検討されています。
教員に変形労働時間制を 自民党部会が提言
自民党の教育再生実行本部の部会は15日までに、教員の長時間労働を抑制するため、労働時間を年単位で管理する「変形労働時間制」の導入を盛り込んだ中間提言をまとめた。
労働基準法は労働時間の上限を原則として「1日8時間、週40時間」としており、教員も規制の対象。一方で、労基法は1カ月や1年といった一定期間の平均で労働時間を計算する変形労働時間制も認めている。
通常、労働時間は「1日8時間、1週40時間」とされ、これを超えれば時間外労働(残業)とになります。
一方、1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヶ月トータルで労働時間の調整ができていれば時間外労働にはならないのです。
変形労働時間制で働いていると「どこから残業代が発生するのか」と感じる方もいると思います。
今回は変形労働時間制での労働時間の考え方と長時間労働や未払い残業代などの対処方法についてご紹介します。
目次
【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版
2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。
2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。
人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。
- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい
- 社労士が監修した正確な情報を知りたい
- HR関連の法改正を把握しておきたい
という方はぜひご確認ください!
変形時間労働制とは

労働時間を月・年単位で計算する制度
冒頭でも説明した、変形労働制ですが、簡単に言うと、労働時間を1日単位ではなく、月・年単位で計算することです。
通常は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働は直ちに時間外労働(残業)となり、月から土曜日まで毎日8時間で働いたとすると、週48時間労働として8時間の残業が発生します。
繁忙期や閑散期で残業代を抑える効果がある
しかし、業種によっては隔週ごとに繁閑が発生する場合があり、第1週は48時間労働が必要であるが、第2週は32時間労働で足りるというケースもありえます。
このように、忙しさ・仕事量の違う、いわゆる繁忙期・閑散期のある業界・職種は、変形労働時間制を積極的に取り入れることで、残業代コストを抑制する傾向にあります。
変形労働時間制は期間ごとで2つに分けられる
変形労働時間制には、2つの種類があります。
と言っても、主にどの範囲の期間で労働時間を清算するかの違いになります。1ヶ月ごとに就労時間を設定する変形労働時間制(多くは1ヶ月単位の変形労働時間制)と、1ヶ月を超える期間で就労時間を設定する変形労働時間制(多くは1年単位の変形労働時間制)があります。
以下で詳しく解説していきます。
1ヶ月単位の変形労働時間制
変形労働時間制を導入している企業では、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している企業が多いでしょう。例えば、1ヶ月間を変形労働時間制の期限とすると、下の月ごとの法定労働時間以内で、就業時間を定めます。
|
28日 |
160.0時間 |
|
29日 |
165.7時間 |
|
30日 |
171.4時間 |
|
31日 |
177.1時間 |
そして、各日・週ごとに労働時間を振り分けていきます。例えば、月末に忙しくなるような会社の場合、以下のようになり、

合計176時間となり、月31日で177.1時間となっている法定時間以内なので問題ありません。就業規則には、
|
日 |
始業時間 |
就業時間 |
休憩時間 |
|
1日から24日まで 25日から月末まで |
午前10時 午前9時 |
午後6時 午後7時 |
正午から午後1時 上記に同じ |
といったように記載されているでしょう。
1年単位の変形労働時間制
一方、1年間の変形労働時間制は、1ヶ月以上1年未満で労働時間を設定する変形労働時間制です。
例えば、シーズンごとに繁忙期・閑散期があるような業態に適しています。例えば、繁忙期に就業時間を伸ばしたり、週6日間労働にしたりして対応します。
その分、閑散期の出勤日数や就労時間を減らすことで、年間の就業時間数が、年間の法定労働時間内に収まるようにします。年間での法定労働時間数は、以下のようになります。
|
365日 |
2085.7時間 |
|
366日(閏年) |
2091.4時間 |
1年単位の変形労働時間制の休日の考え方
もう一点、1年単位の変形労働時間制には、休日の取り方も関与してきます。極端な話、閑散期にまるまる休ませて、繁忙期に31日全部働かせる様なことがないような決まりです。
そのために以下の様な決まりが設けてあります。
|
1年あたりの労働日数 |
280日(年間休日85日) |
|
1日あたりの労働時間 |
10時間まで |
|
1週間あたりの労働時間 |
52時間まで |
|
原則連続で労働できる日数 |
連続6日 |
|
特定的に連続で労働できる日数 |
1週間に1日の休み(最大連続12日) |
これらを元に、会社ごとに就業時間が定められます。
変形労働時間制を導入できる基準
それでは、会社は簡単に変形労働時間制を導入できるのでしょうか。結論を言うと、1ヶ月単位の変形労働時間制は、簡単ですが、1年単位の変形労働時間制は、若干手間がかかります。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合
1ヶ月単位の変形労働制の導入は簡単です。所定労働時間が月の法定労働時間に収まるように(週の平均40時間以内)所定労働時間を設定して、就業規則に記載をすれば完了です。
労働基準監督署に提出する必要もありません。ただ、当該記載は、変形期間中の始業時刻、終業時刻、変形期間の開始日等が明示されるものである必要があります。
1年単位の変形労働時間制の場合
一方、1年単位の変形労働制は、1年間の各日の労働日について法定労働時間内に収まるように(週の平均40時間以内)所定労働時間を設定した上で、これについて労使協定(労働者の代表との協定)を結び、それを労働基準監督署に提出しなくてはなりません。
法定労働時間と変形労働時間制の考え方
それでは、変形労働時間制での残業の出し方はどうなっているのかを解説します。
法令に基づく計算方法は日、週、月毎に時間外労働の有無を確認する必要がありとかなり複雑です。
そのため、ここでは便宜的に一般企業が運用する残業の出し方について説明します。
(当該計算方法の場合、法定の方法よりも残業時間が増加するため、必ずしも全ての企業でこの計算に従った残業代請求が可能となるわけではない点をご留意ください。)
所定労働時間の繰り上げ・繰り下げはできない
まず、変形労働時間制と言っても、就業規則で定めた労働時間を変動することはできません。
例えば、7時間と所定労働時間で定められて日に、8時間働いてしまったからといって、「翌日の所定労働時間を1時間減らして残業していない」ということにはできません。
残業時間を計算する際は、就業規則と照らし合わせる
変形労働時間制は、日によって労働時間も変わることがあるので、複雑なように思えます。
変形労働制を導入するにあたって、必ず就業規則が作成されているはずなので、そちらを元に残業代を算出します。
簡単に言えば、7時間が所定労働時間の日に8時間働いたのであれば、1時間残業したことになりますし、10時間の所定労働時間の日に10時間働いても、残業をしていないことになります。
仮に所定労働時間以内に退勤したのであれば、早退扱いになります。
法定労働時間を超えていないかをチェック
そして、そもそもの会社で定められている所定労働時間が、法定時間を超えていないかをチェックしましょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合
週の労働時間の平均が40時間を超えていないかと、所定労働時間の月の合計が下記の数値を超えていないかをチェックして下さい。
|
28日 |
160.0時間 |
|
29日 |
165.7時間 |
|
30日 |
171.4時間 |
|
31日 |
177.1時間 |
1年単位の変形労働時間制
同じく週の平均労働時間が40時間を超えていないことと、年間合計の所定労働時間が下記の数値を超えていないかをチェックして下さい。
|
365日 |
2085.7時間 |
|
366日(閏年) |
2091.4時間 |
会社で決めてある、所定労働時間が法定労働時間を超えているようでしたら、その超えている分も残業とみなされます。
変形労働時間制に相似した2つの制度
同じく、1日8時間という法定労働時間の枠にとらわれない労働時間制の働き方があります。こちらは、上記の変形労働時間制と異なりますので、それぞれ簡単に説明し、詳しく記載したページヘのリンクを貼っています。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は始業時刻と終業時刻を労働者の裁量に委ねる労働時間制度であり、労働時間は月単位で計算します。月の労働時間が法定労働時間を超えれば残業代が発生する制度です。
裁量労働制
裁量労働制とは、労働時間を実労働時間で算定せず、一定時間とみなして運用する制度です。そのため、裁量労働制の下では実際には長時間の労働があったとしても、残業代は決められた範囲でしか発生しません。
変形労働時間制の問題点と対処法
変形労働時間制は適正な運営をされていれば、会社側は、業務量に応じて余計な残業代が生じるリスクを適法に回避することが出来ます。
労働者側も、仕事が少ない期間は、労働時間が少なくなり、メリハリの有る働き方も出来ます。
しかし、会社側は少し変則的な労働時間をあやふやにして運営しているケースが有ります。
所定労働時間があやふやにされる
例えば、1ヶ月変形労働時間制を取り入れている会社だとして、所定労働時間が6時間の日と10時間の日が設けられていたとします。
この場合、しっかり就業規則が作成されている必要性がありますが、それをあやふやにして、あたかも10時間労働が当たり前のようにして残業代を支払わないようなことがあり得ます。
また、6時間と設定されている日に8時間働かせて定時扱いにするような事があります。
上記のような恣意的な残業代のカットは違法であり、残業代は権利としてあるが未払いであるという状態です。このような場合は、一度弁護士に相談されてみてもいいかと思います。
残業代の請求方法に関して、詳しくは「未払い残業代のある人が知っておくべき残業代請求の全手順」をご覧ください。
就業規則が法定労働時間をオーバーしている
そもそもの就業規則での所定労働時間が法定労働時間をオーバーしている場合があります。この場合も、法定労働時間からオーバーしている時間分は、会社の基準では残業ではなくても、法律的に見れば残業になります。
就業規則を確認の上、その時間が法定時間を超えているようでしたら、会社に理由を聞いてみて、曖昧な返答しか返ってこなければ、就労時間をごまかしている可能性があります。
年間休日が異常に少ない場合(年間85日以下)もそれに当てはまります。
事実をまとめ、労働基準監督署や弁護士に相談されてみてください。労働問題を得意とする弁護士は「労働問題を得意とする弁護士一覧」から無料で相談できます。
まとめ
いかがでしょうか。業態によっては、土日出勤やシフト制、夜勤などのカレンダー通りに働けない業態もあります。
「うちの業界は、休みが少ないから。労働時間が長いから。」と当たり前のように思っていても、法的に守られている労働時間は存在します。
それを、変則的に変えることができる制度が、変形労働時間制ですが、定められた労働時間を超えれば、正規に残業代が支払われるべきです。
「当たり前」のように泣き寝入りするのではなく、なぜ自分の会社で長く働いても給料が変わらないのかのカラクリを自身でも探してみて下さい。
違法性が思い当たれば、弁護士に相談するようにしましょう。未払いだった残業代は返ってきます。
| 出典元一覧 |
梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
--------------------
▼無料ダウンロードはこちら▼
https://hrnote.jp/document/?did=148030