
従業員が退職する際には、退職者から提出してもらうもの、逆に会社側から退職者に渡さなければいけないものがあります。この記事では、会社側と退職者双方にとって後々のトラブルにならないために、退職手続きに必要となる書類や対応についてわかりやすく解説します。また、退職手続きのチェックリストも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 会社側の退職手続きのフロー
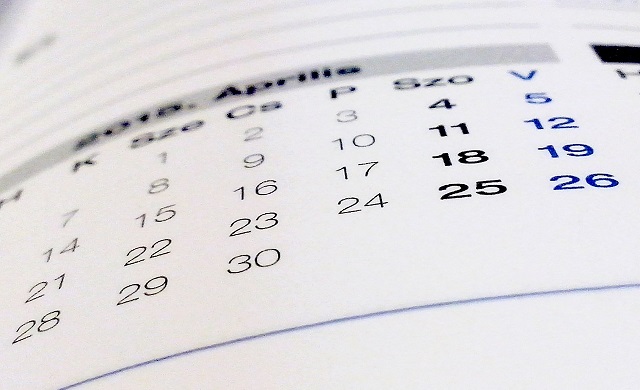
退職手続きに関して、会社側がいつまでに何をすべきかは、法律で定められいるものもあります。ここでは、会社側の退職手続きの流れについて詳しく紹介します。
1-1. 会社側の退職手続きは何日前から開始する?
会社側が退職手続きに関して時系列でやるべきことを説明すると、次のような流れになります。
- 退職日の2週間前以前
退職者からの退職意思の確認、退職届の受け取り。業務の引き継ぎ。 - 退職者の最終出勤日
社員証、名刺、その他貸与物の回収。預かっていれば雇用保険被保険者証、年金手帳
の返却。 - 退職日
健康保険証の回収。
- 退職日以後
雇用保険や健康保険、厚生年金保険に関する退職手続きをする。ハローワークへ行き離職票を発行してもらい、退職者に送付する。 - 最終の給与計算確定後
源泉徴収票の発行と送付。(給与明細に同封して送るとスムーズです。)
退職手続きに関して、期限が決まっているものもあります。退職手続きをスムーズにできるよう、会社側はいつまでに何をすべきか、事前に洗い出し、マニュアルとしてまとめておくことが推奨されます。
1-2. 14日以上前に退職届を受理する
まずは従業員の退職の意思を証拠として残すため、退職届を記載し、提出してもらいましょう。民法第627条により、正社員の場合、退職の意思を表示した日から14日(2週間)を経過することで、雇用契約は終了します。たとえば、従業員が退職しようとする日の3日前に退職届を提出した場合、会社側はそれを拒否し、退職届を提出した日から14日後の退職とすることが可能です。そのため、退職届は14日以上前に提出してもらいましょう。
なお、期間によって報酬の定めをしている場合や、パートやアルバイトなどの有期雇用契約の場合、退職届の提出期限が通常と変わる可能性があります。会社側と従業員の間でトラブルが生じないよう、退職届の提出に関する定めをあらかじめ就業規則に記載しておくことが大切です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
関連記事:退職届は何日前までに出すべき?民法や労働基準法の観点からわかりやすく解説!
1-3. 業務の引き継ぎを実施する
業務の引き継ぎに関して明確に定めた法律はありません。しかし、退職日まで従業員は労働者であり、就業規則や雇用契約で示されている義務を果たす必要があります。また、民法第1条や労働契約法第3条などには、労働者の義務が示されています。
もしも労働者が業務の引き続きを全くおこなわず、会社側に実害を与えた場合、会社側は従業員に対して損害賠償請求をできる可能性もあります。そのため、業務の引き継ぎの重要性を退職予定者に周知し、今後の円滑な組織運営のためにもきちんと業務の引き継ぎをしてもらいましょう。
(基本原則)
第一条 (省略)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。(省略)
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
1-4. 社員証・名刺・健康保険証などを回収する
従業員へ貸し出しているものは、退職日か最終出勤日までに回収しましょう。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 社員証
- 名刺
- パソコン
- スマートフォン
- タブレット
- 健康保険証
なお、従業員に扶養家族がいる場合は、全員分の健康保険証を回収しなければなりません。
1-5. 社会保険や税金の退職手続きをする
従業員が退職したら、社会保険や税金関係の手続きが必要です。これらの退職手続きを怠ると、退職者が転職した際に新しい社会保険に加入できないなど、トラブルが生じる恐れがあります。また、提出先や提出期限は、書類ごとに異なる場合もあるので、提出遅れが生じないよう事前に手続きのスケジュールを明確にしておきましょう。
1-6. 離職票や源泉徴収票を発行する
退職者の雇用保険被保険者離職票(離職票)はハローワークから会社に送付されます。そのため、離職票が会社に届いたら退職者に送付しましょう。また、最後の給与額が確定したら、源泉徴収票を発行します。源泉徴収票は、新しい職場で年末調整をしたり、確定申告をしたりする際に必要です。
2. 会社側がすべき具体的な退職手続き
 従業員が退職した後、会社側がすべき手続きはいくつかあります。これらの手続きが滞ってしまうと、「会社側が退職手続きをしてくれない」「退職手続きが遅い」といった従業員の不満につながります。ここでは、会社側が従業員の退職後にすべき具体的な手続きについて詳しく紹介します。
従業員が退職した後、会社側がすべき手続きはいくつかあります。これらの手続きが滞ってしまうと、「会社側が退職手続きをしてくれない」「退職手続きが遅い」といった従業員の不満につながります。ここでは、会社側が従業員の退職後にすべき具体的な手続きについて詳しく紹介します。
2-1. 雇用保険の資格喪失手続き
雇用保険に加入している従業員が退職したら、雇用保険の資格喪失手続きをおこなわなければなりません。雇用保険の資格喪失手続きが遅れると、失業手当の受け取りなどに支障を来す恐れがあるので注意が必要です。
雇用保険の資格喪失手続きをする際には、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、必要に応じて「離職証明書」を事業所を管轄する公共職業安定所長(ハローワーク)に、従業員の退職日の翌日から10日以内に提出する必要があります。また、離職票が会社に届いたら、速やかに退職者に送付しましょう。
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や記入例、添付書類、提出方法をわかりやすく解説!
2-2. 健康保険と厚生年金保険の資格喪失手続き
従業員が健康保険や厚生年金保険に加入している場合、これらの社会保険の資格喪失手続きも必要になります。なお、組合管掌健康保険(組合健保)と全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)のどちらの健康保険に加入しているかで、提出書類や提出先などの手続きの仕方が異なります。
協会けんぽに加入している場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から5日以内に日本年金機構に提出することで、健康保険と厚生年金保険の両方の資格喪失手続きを同時におこなうことができます。なお、被保険者資格喪失届を紙で提出する又は郵送する場合は、本人と被扶養者分の健康保険被保険者証を添付しなければなりません。電子申請で行う場合は保険証を別途郵送する必要があります。そのため、健康保険証を回収する際は、本人に加えて、その家族の分も提出してもらうようにしましょう。
一方、組合健保に加入している場合、期限までに健康保険被保険者資格喪失届は組合健保に、厚生年金保険被保険者資格喪失届は日本年金機構に提出することで、資格喪失手続きができます。この場合、厚生年金の資格喪失手続きに添付書類は不要です。ただし、健康保険被保険者資格喪失届の提出期限や提出先、添付書類は、加入している組合健保によって異なるので、事前にきちんと確認しておきましょう。
関連記事:社会保険の資格喪失届とは?書き方や注意点を詳しく解説
2-3. 住民税の手続き
会社側が給与から住民税を差し引く「特別徴収」を採用している場合、従業員が退職したら住民税に関する手続きも必要です。一方、従業員が自分で住民税を納める「一般徴収」を採用している場合、会社側の住民税に関する手続きはありません。住民税(特別徴収)の退職手続きは、退職者がすぐに転職しない場合と転職先が決まっている場合で異なります。
(1)退職後の転職先が決まっている場合
新たな就業先が「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を前の職場を退職した日の翌月10日までに所轄の市区町村に提出することで、引き続き特別徴収により住民税を納めることが可能です。このような場合、退職先の会社は異動届出書を退職者に交付し、退職者が転職先にこの書類を提出してもらう必要があります。
(2)退職後の転職先が決まっていない場合
基本的に従業員自身で住民税を納付してもらう必要があります。そのため、退職先の会社側が「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに退職した従業員の住所地の市区町村に提出しなければなりません。なお、退職する時期によっては、退職者に住民税の未徴収税額がある場合、会社側が給与や退職金から一括徴収しなければならないケースなどもあります。不明な点がある場合、最寄りの自治体に相談してみましょう。
2-4. 所得税の手続き
所得税法第226条により、従業員が退職した後、1カ月以内に退職者に対して給与所得の源泉徴収票を交付する必要があります。また、退職金を支給する場合は、同様に、退職後1カ月以内に退職所得の源泉徴収票を交付しなければなりません。なお、退職者が退職した年に転職した場合は、新たな就職先に給与所得の源泉徴収票を提出して、新たな就職先での源泉徴収額と合わせて年末調整をすることになるので忘れずに送付しましょう。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
関連記事:退職所得の源泉徴収票とは?書き方や提出期限、確定申告の必要性について解説!
2-5. 従業員持株会を導入している場合の手続き
従業員持株会とは、従業員が自社の株式を定期的に購入し、中長期的な資産形成をサポートする福利厚生制度の一つです。従業員が従業員持株会を利用している場合、退職に伴い、退会の手続きが必要になります。退会後は、「個人口座に預け入れる」「従業員持株会に清算してもらう」といった手続きが考えられます。
2-6. 外国人労働者が離職する場合の手続き
雇用保険の被保険者に該当しない外国人労働者が退職する場合、「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。提出期限は、退職後の翌月の末日までです。また、提出先は、所轄のハローワークになります。なお、ハローワークでは、外国人雇用状況届出書を基に、事業主に助言や指導をおこなったり、離職した外国人に再就職支援をおこなったりします。
3. 会社側から退職者へ渡す書類のチェックリスト
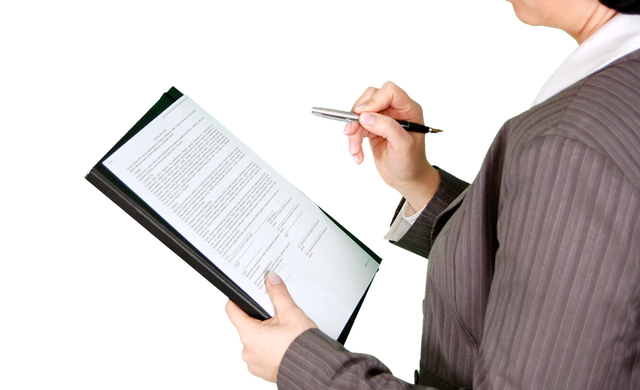
会社側から退職者へ渡す書類のチェックリストは、次の通りです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 退職証明書
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 源泉徴収票
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
ここでは、それぞれの書類について詳しく紹介します。
3-1. 離職票
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、退職者が失業手当の給付を受ける際に必要な書類です。離職票を発行するには、「雇用保険被保険者資格喪失届」に加えて「離職証明書」をハローワークに提出する必要があります。なお、次の職場が決まっている場合、離職票の発行は不要なため、事前に退職者に離職票の発行を希望するかどうかを確認しておきましょう。ただし、退職者が59歳以上の場合、高年齢雇用継続給付金の給付額を決めるために離職票を必ず交付しなければなりません。
関連記事:離職票の発行の流れとは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方、義務について解説!
3-2. 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険の加入状況を証明するための書類です。雇用保険被保険者証は重要な書類であるため、入社と同時に、会社側が預かるケースもよくあります。退職者が次の職場へ提出する場合や、教育訓練給付金の支給を受ける場合に必要となるので、会社で預かっている場合は退職する際に離職者に返却しましょう。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?発行方法や再発行のやり方、退職日・転職の際の手続きを紹介!
3-3. 退職証明書
退職証明書とは、会社側が発行する従業員の退職を証明するための書類です。労働基準法第22条により、退職者が請求する場合、会社側は退職証明書を必ず発行しなければなりません。退職者が離職後に、国民健康保険や国民年金保険に加入する場合、離職票だけでなく、退職証明書でも手続きができます。離職票の発行に時間がかかる場合などに、退職証明書は有効的なので、退職者から求められたら速やかに交付しましょう。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(省略)
3-4. 年金手帳
年金手帳とは、年金に関する情報を管理するための手帳を指します。年金手帳には基礎年金番号が記載されており、国民年金・厚生年金保険の手続きをする際に必要になります。年金手帳も、雇用保険被保険者証と同じく、会社側で預かっている場合、退職と同時に返却しましょう。
現在は年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に切り替わっています。なお、既に発行されている年金手帳はこれまで通り有効です。もしも基礎年金番号通知書を年金手帳の代わりに預かっている場合は、退職する際に基礎年金番号通知書を退職者に返却しましょう。
3-5. 源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、退職先が退職後1カ月以内に退職者に発行する必要があります。年の途中で退職し、再就職する場合、給与所得の源泉徴収票を転職先に提出することで、年末調整を受けることが可能です。
また、退職先は退職金を支給する場合、退職所得の源泉徴収票も交付しなければなりません。退職者は、転職先に退職所得の源泉徴収票を提出する必要はありません。ただし、確定申告をする場合、給与所得だけでなく、退職所得の源泉徴収票も必要になるので、適切に保管しておくよう退職者に伝えましょう。
3-6. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書は、住民税の手続きに必要な書類です。転職先が決まっていない場合、退職先が退職した従業員の住所地の自治体に提出するだけで問題ありません。一方、転職先が決まっていて、住民税の特別徴収を継続する場合、次の勤務先に提出する必要があります。そのため、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を発行し、必要事項を記載したら、退職者に交付し、転職先に届け出るよう伝えましょう。
当サイトでは、入社・退社時の社会保険手続きの内容や、担当者が気を付けておくべきポイントなどを解説した資料を無料で配布しております。退社時の社会保険の対応で不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
4. 会社側が退職者に提出してもらう書類のチェックリスト

会社側が退職者に必要書類を返却・交付するだけでなく、次のように退職者側から会社側に提出してもらう必要のある書類もあります。
- 退職届
- 健康保険証
- 名刺
- 会社の備品
- 書類やデータ
- 退職所得の受給に関する申告書
ここでは、それぞれの書類について詳しく紹介します。
4-1. 退職届
退職は、従業員からの口頭での意思表示でも成立します。しかし、口頭での意思表示のみで退職が決まってしまうと、後々「言った言わない」のトラブルに発展しやすくなるので、必ず退職届を作成し、提出してもらうようにしましょう。社内で決まった退職届のフォーマットが無い場合は、「退職の意思・退職の理由(一身上の都合など)・退職日・氏名」を記載して押印したものを提出してもらいましょう。
ただし、退職の理由が契約社員やパート・アルバイトなどの契約期間終了による雇止めの場合には、提出してもらう必要はありません。また、退職の理由が会社都合での解雇や懲戒解雇の場合は、逆に会社側から解雇通知書(解雇予告通知書)を退職者に渡す必要があります。なお、退職者から請求があった場合、解雇理由証明書の交付も必要です。
4-2. 健康保険証
社会保険の場合、従業員は会社を通じて健康保険に加入しています。つまり、会社を退職すると、現在所持している健康保険証は無効になります。そのため、従業員が退職する際に、健康保険証を返却してもらわなければなりません。また、従業員本人だけでなく、退職する従業員の家族全員分の健康保険証を返してもらう必要があるので注意が必要です。
4-3. 名刺
会社で作成した場合はもちろんのこと、自作した名刺であっても、退職すればその名刺は役割を終えます。会社名が入っているものなので返却対象となります。また、忘れがちなのが取引先からもらった名刺です。会社にとって重要な個人情報の一つであるため、必ず返却してもらうようにしましょう。
4-4. 会社の備品
会社に所有権がある物は必ず返してもらいましょう。社員証やパソコン、スマートフォン、制服、鍵など、会社によって貸与品や備品は異なります。退職者自身がもらったと勘違いしていることもあるので、会社側から返却物のリストを渡しておくと抜け漏れなくスムーズに対応することが可能です。
4-5. 書類やデータ
一見価値がないように見えても、「機密情報」に該当するものは数多くあります。たとえば、サンプル品や提案済の資料、過去のレポート、ボツになった開発データなどです。このような情報が退職者によって外部に漏れると、退職先が責任を負わなければならなくなる恐れがあります。会社から提供した書類やデータは、退職時に返却もしくは破棄するように指示しておきましょう。
4-6. 退職所得の受給に関する申告書
従業員が退職する場合に、退職金を支給する会社も少なくないでしょう。退職金は「退職所得」に該当し、通常の給与と異なる方法で税金が計算されます。退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を記載・提出してもらわない場合、退職金に対して一律20.42%の税率が掛けられて税金が算出されることになります。この場合、税金の納め過ぎとなり、還付を受けるため、後に確定申告が必要になる可能性があります。
退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらうことで、退職者の状況や退職金の金額に応じて適切な税率を計算して源泉徴収がされるようになります。このように、退職金を支給する場合、会社側は退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を交付し、実際に退職金を支払うまでに提出してもらうようにしましょう。
関連記事:退職金にかかる税金(所得税・住民税)の仕組みや計算方法をわかりやすく解説!
5. 会社側の退職手続きに関する注意点

退職手続きをおこなう際に会社側が注意しなければならない点はいくつかあります。ここでは、会社側の退職手続きに関する注意点について詳しく紹介します。
5-1. 返却必須の物は期限を定めてできるだけ手渡しする
必ず返却してほしいものは、できる限り手渡しで返却してもらうようにしましょう。しかし、従業員が残った有給休暇を消化している場合など、手渡しが難しいケースもあります。そのような場合に備えて、あらかじめ郵送による対応も検討しておくことが大切です。ただし、郵送だとタイムラグが生じ、返却が遅れて手続きが間に合わなくなる恐れもあるので注意が必要です。
5-2. 健康保険証は退職日に返却してもらう
健康保険証が使えるのは、退職日までです。退職日の翌日からその健康保険証は使用できなくなります。そのため、退職日より早く返却してもらうと、病院にかかったときに保険適用できなくなる可能性があります。
また、社会保険被保険者資格喪失届は、原則として資格喪失日から5日以内に健康保険証を添付して提出しなければなりません。そのため、健康保険証は退職した後すぐに回収する必要があります。従業員から「退職日に使うのでその後返したい」という申し出があった場合には、会社に持参するか、郵送で返却するのかなど取り決めをして必ず回収できるようにしておきましょう。
5-3. 個人情報は5年間保管する
従業員の個人情報が書かれた書類は、原則として退職日から5年間(当面の間は3年間)保管する必要があります。退職したからといって、すぐに破棄することはできません。
労働基準法109条により、労働者名簿や賃金台帳など、労働に関する重要な書類の保管期間は5年間と定められています。ただし、労働基準法第143条により、労働基準法第109条には経過措置が設けられており、保存期間は当面の間5年間でなく、3年間でも問題ありません。しかし、いつ経過措置が終了するのかは未定なので、可能な限り5年間保管しておくようにしましょう。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。(省略)
関連記事:労働基準法第109条の重要な書類の保存期間は何年?法改正や経過措置、違反した場合の罰則を解説!
5-4. 従業員の退職後の手続きを伝える
従業員の中には、退職後どのような手続きが必要になるのかわからない人も少なくないです。たとえば、次のような手続きについてあらかじめ周知しておくと、退職者はスムーズに手続きをすることができます。
- 国民年金保険への切り替え手続き
- 国民健康保険や健康保険任意継続制度などの健康保険に関する手続き
- 失業保険受け取りの手続き
- 年末調整や確定申告の手続き
- 住民税の支払い手続き
従業員が退職した後も、円満な関係を築けるように、退職後の手続きを丁寧に伝えましょう。
関連記事:年末調整とは?確定申告との違いや対象者、やり方や注意点などを徹底解説!
6. 会社側の退職手続きを効率化するポイント

従業員が退職する際、会社側はさまざまな手続きをおこなわなければならず、時間や手間がかかります。ここでは、退職手続きを効率化するポイントについて詳しく紹介します。
6-1. 労務管理システムを導入する
労務管理システムとは、入社・退職の手続きや、勤怠管理、給与計算、社会保険の手続きなどを効率よくおこなえるシステムです。労務管理システムに従業員のデータをあらかじめ登録しておけば、退職の際に会社側が準備しなければならない書類とToDoリストを自動で作成することができます。
また、労務管理システムでは、社会保険や雇用保険の資格喪失届、源泉徴収票の作成もシステム上でおこなえるため、退職手続きの業務量を大幅に削減することが可能です。手書きで作成する場合と比べて、期間や金額の計算などのミスを防ぐこともできます。さらに、法律の改正に伴って税率や保険料が変動した場合でも自動で対応できるため、法改正時の変更点を間違えるリスクもなくすことが可能です。
6-2. 電子申請を利用する
「雇用保険被保険者資格喪失届」や「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」などの退職手続きは、電子申請することもできます。電子申請であれば、24時間365日申請することが可能です。また、インターネット環境があれば場所を問わず作業できるので、業務の効率化も期待できます。なお、社会保険の電子申請が義務化されている会社もあるため注意が必要です。
関連記事:社会保険手続きの電子申請が義務化!やり方やメリット・デメリットを解説
6-3. 作業リストやスケジュール表を作成する
作業リストやスケジュール表を作成することも大切です。退職手続きのなかでは、さまざまな書類をスケジュール通りに作成しなければならないため、抜け漏れが生じたり、手順に悩んだりすることもよくあります。スムーズに作業を進めるためにもチェックリストを作成しておくとよいでしょう。会社側で確認するのはもちろん、従業員へも渡しておけばミスの防止につながります。
7. 会社側がすべき退社手続きを理解しておこう!

従業員が退職する場合、会社側はさまざまな書類を用意し、期限までに手続きをしなければなりません。手続きが遅れると、「新たな会社で社会保険に加入できない」「失業手当が受け取れない」といったトラブルを生む恐れがあります。あらかじめ退職手続きに必要な書類のチェックリストを作成し、マニュアルにまとめておくと、抜け漏れなくスムーズに手続きが可能です。また、労務管理システムや電子申請を新しく導入してみるのもおすすめです。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









