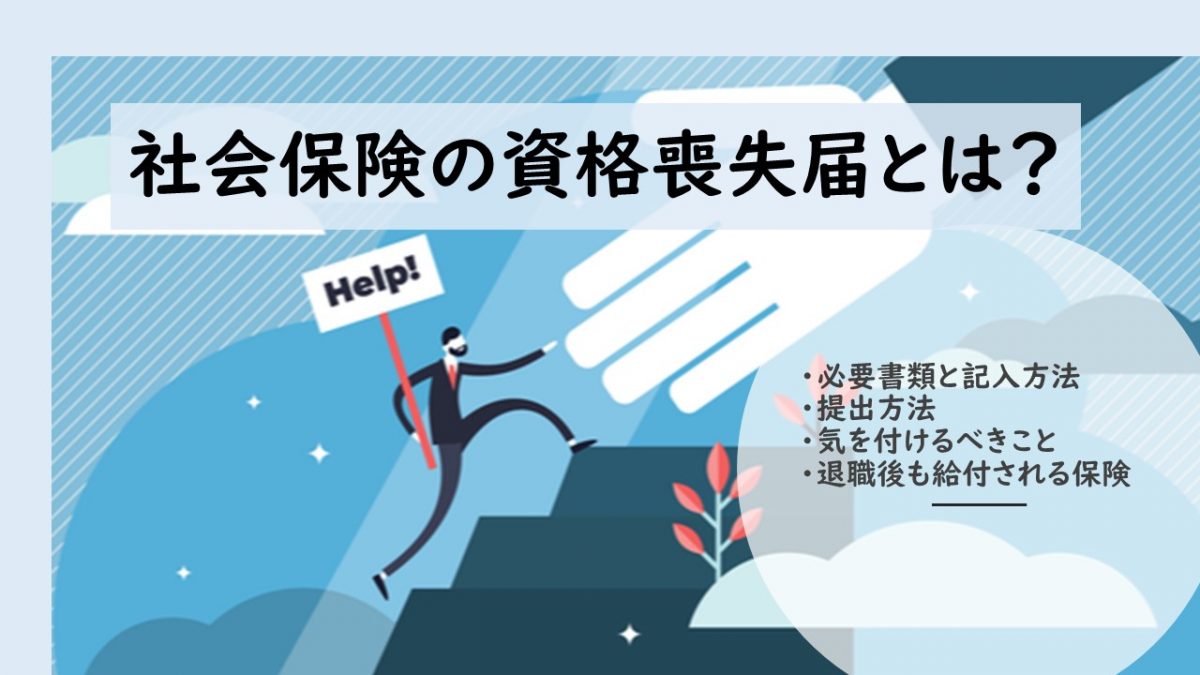
従業員が退職する際に必要な手続きのひとつとして、社会保険の資格喪失届の提出が挙げられます。
会社の経営者や事業主、人事担当者などは社会保険の資格喪失届の概要や手続きなどを理解しておくことが必要です。本記事では、従業員が離職する際に欠かせない、社会保険の資格喪失届について詳しく紹介します。
関連記事:社会保険喪失届とは?必要な場面や作成上の注意点を紹介
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険の資格喪失届とは?

社会保険の資格喪失届とは、従業員が解雇、退職、死亡などの理由により「健康保険」及び「厚生年金保険」の資格を喪失するときに、提出が必要になる書類です。
「資格喪失届」と呼ばれることも多いのですが、正式名称は「被保険者資格喪失届」となっています。
万が一、転職する従業員の資格喪失届の届け出が遅れてしまうと、転職先での健康保険証の交付が遅れるので、人事担当者は速やかに書類を作成して提出しなければなりません。
関連記事:社員が退職したときの社会保険手続きについて徹底解説
1-1. 社会保険の資格喪失届を提出する必要があるケース
以下のような事象が発生した場合は、社会保険の資格喪失届を提出しましょう。
従業員が退職したとき
当然ですが、従業員が退職したときは被保険者資格喪失届の提出が必要です。従業員に必要書類を提出してもらい、会社側が手続きをおこないます。
加入条件を満たさなくなったとき
社会保険には、労働時間や賃金などの加入条件が定められています。雇用形態が変更になったなどの理由で加入条件を満たさなくなった場合は、すぐに手続きを進めましょう。
資格喪失年齢になったとき
70〜75歳前後の従業員がいる場合は、年齢による資格喪失にも注意が必要です。厚生年金保険については70歳の誕生日の前日、健康保険については75歳の誕生日の当日に資格を失うため、それぞれ資格喪失の手続きをしなければなりません。
従業員が死亡したとき
従業員が死亡したときも社会保険の資格喪失届を提出する必要があります。本人はもちろん、扶養家族の健康保険証も回収するようにしましょう。
1-2. 社会保険の資格喪失届の提出期限・提出先
社会保険の資格喪失届は、資格を失う事象が発生した日から5日以内に提出しなければなりません。
協会けんぽの場合は、年金事務所にて手続きをおこないます。別の健康保険組合に加入している場合は、年金事務所と管轄の保健組合にて手続きを進めましょう。
1-3. 社会保険の資格喪失届は電子申請で提出可能
社会保険に関する手続きは、電子申請で進めることが可能です。年金事務所などへ出向く必要がなくなり、交通費や郵送費を削減できます。また、紙による申請より早く処理されることも大きなメリットです。
電子申請は、日本年金機構のホームページからおこないましょう。
参照:電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)|日本年金機構
1-4. 社会保険の資格喪失届の添付書類
資格喪失届を提出する際は、従業員本人と扶養者分の保険証を一緒に提出します。事前に従業員へ通知しておき、回収を忘れないようにしましょう。保険証を回収できない事情がある場合は、健康保険被保険者証回収不能届を添付します。
また、以下のものを交付している場合は回収のうえ、添付しなければなりません。
- 高齢受給者証
- 健康保険特定疾病療養受給者証
- 健康保険限度額適用
- 標準負担額減額認定証
1-5. 社会保険の資格喪失届のダウンロード方法
資格喪失届は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。PDF版とExcel版があるため、好きな様式をダウンロードして記入しましょう。
記入例も同時に記載されているので、記入方法がわからない担当者は、下記リンクを参考にしながら作成してみてください。
参照:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
1-6. 社会保険の資格喪失届の提出が遅れた場合の罰則
社会保険の資格喪失届の提出が遅れた場合でも、とくに罰則はありません。
ただし提出が遅れると、退職者が失業給付金を受け取れないなど、労使間のトラブルが発生する可能性もあるため、速やかに手続きを完了させましょう。
2. 社会保険の資格喪失届の書き方

従業員が退職する場合、健康保険と厚生年金保険の手続きが必要です。事業主は、資格喪失届を日本年金機構および加入している健康保険組合に提出をする必要があります。
また、資格喪失届の提出と同時に健康保険証の返却をおこなわなければならないので、退職の際に従業員から返却してもらうようにしましょう。ここでは、資格喪失届の基本的な書き方を紹介しますので、参考にしてください。
2-1. 提出者記入欄
所在地や名称など、事業所の基本情報を記入します。事業所整理記号と事業所番号は、新規適用時に付与された記号と番号を記入しましょう。
2-2. 被保険者整理番号
資格を取得したときに付与された被保険者整理番号を記入します。
2-3. 氏名・生年月日
氏名は、住民票に登録されている通りに記入する必要があります。フリガナはカタカナで記入しましょう。生年月日の年号は、該当する番号を〇で囲みます。
2-4. 個人番号(基礎年金番号)
個人番号は、本人確認をおこなったうえで記入しましょう。基礎年金番号を記入する際は、年金手帳などに記載されている10桁の番号を記入します。
2-5. 喪失年月日
下記の通り、喪失年月日を記入しましょう。
- 退職等による資格喪失:退職日の翌日・転勤の当日・雇用契約変更の当日
- 死亡による資格喪失:死亡日の翌日
- 75歳到達による健康保険の資格喪失:誕生日の当日
- 障害認定による健康保険の資格喪失:認定日の当日
2-6. 喪失(不該当)原因
退職や死亡など、該当する理由を◯で囲みましょう。
2-7. 保険証回収
保険証回収の項目には、添付する保険証の枚数を記入します。回収できなかった場合などは、「返不能」の部分に枚数を記入しましょう。
3. 社会保険の資格喪失届の提出方法

ここでは、社会保険の資格喪失届を提出するまでの流れを紹介します。
3-1. 社会保険の資格喪失届を作成する
日本年金機構や加入している健康保険組合の資格喪失届の記入書類を準備して、記入を進めていきます。
記入する内容としては、先ほど紹介した通り、事業所整理番号、被保険者整理番号、氏名、生年月日、基礎年金番号、資格喪失年月日、資格喪失理由、被保険者証回収区分などです。とくに数字は間違えやすいため、注意して記入しましょう。
3-2. 退職者から保険証を提出してもらう
社会保険の資格喪失届を提出する際には、被保険者証(保険証)の添付が必要なので、退職者に被保険者証の提出をしてもらいましょう。
協会けんぽの保険証であれば、その保険証と資格喪失届を事業所の管轄の年金事務所に提出し、健康保険組合に加入している事業所であれば、その保険証を健康保険組合に提出します。
何らかの理由で被保険者証を回収できない場合は、「健康被保険者証回収不能・紛失届」を別途作成して添付することが必要となります。
提出方法としては、各事務所の窓口での提出、電子申請のほか、郵送での提出も可能です。
資格喪失届は、従業員が退職をした翌日から5日以内に、年金事務所および事業所が加入している健康保険組合に提出ををしなければいけません。
3-3. 正副2部作成する
資格喪失届は必ず、正副2部作成して提出しましょう。窓口提出の場合は、その場でコピーをして処理をしてくれることもありますが、できるだけ窓口の負担を減らすよう心がけ、2部作成して提出するとよいでしょう。
また、急ぎの場合は窓口に直接提出することをおすすめします。郵送の場合、投函から会社控えの資格喪失届が戻ってくるまで1週間程度かかることがあります。
4. 社会保険の資格喪失届を提出する際に気を付けなければいけないこと

社会保険の資格喪失届を提出する際は、以下のような点に注意しましょう。
4-1. 提出期限に遅れないようにする
前述の通り、資格喪失届は基本退職日から5日以内に提出することになっているので、速やかに提出をしましょう。
また、健康保健証は被保険者資格喪失届に添付して提出するのが基本ですが、何らかの事由で、退職者から返却されない場合は、健康保険被保険者証回収不能・滅失届を提出すれば、健康保健証を添付しなくても大丈夫です。
4-2. 任意継続も可能
資格を喪失する対象の従業員が希望する場合は、健康保険に継続して加入することも可能です。
資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があり、(退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当する)資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すると、任意継続被保険者資格を取得できますので、被保険者から依頼があった場合は、この届出用紙も作成が必要となります。
当サイトでは、入社・退社時の社会保険の手続き内容や手続き時の気を付けるポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。
入社時の手続きに関しては、提出期限を過ぎると罰則が生じるものがあるので、手続きを漏れなく遅滞なく行いたいご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
5. 社会保険の資格喪失届の提出後にしなければならないこと

社会保険の資格喪失届の控えは、必ず一箇所に保管をするようにしましょう。労働基準監査局などの調査で提出を求められる場合があるからです。
また、社員名簿や社会保険台帳に退職日と退職事由を明記しておくことをおすすめします。当該従業員が、被保険者番号などを問い合わせてくる場合や、社会保険事務所などから問い合わせがある場合もあるので、簡単に調べられるようにしましょう。
5-1. 社会保険の資格喪失届を訂正したいときはどうする?
資格喪失届を提出した後に間違いに気付いた場合は、記載内容を訂正することが可能です。同じ書式を準備し、上部の「被保険者資格喪失届」と書かれている横に、赤字で「訂正届」と記載します。
訂正前の数字や文字を赤字で、正しい数字や文字は黒字で記入して再度提出しましょう。
6. 退職後も受けることができる保険給付とは

退職後は被保険者の資格を喪失します。しかし、一定の要件を満たす場合、受けられる保険給付もあります。人事担当者や経営者の方も知っておくことで、退職者が出た際にスムーズに対応できるでしょう。
以下、退職者が受けられる保険給付について説明します。
6-1. 傷病手当金
傷病手当金とは、私傷病により休業した際、健康保険による条件を満たした場合に支給される制度です。
- 疾病又は負傷のため療養中であること
- 労務に服することができないこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給)
- 報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給)
退職後は被保険者の資格を喪失しますが、次の一定の要件を満たす場合には、退職後も支給開始から1年6カ月を限度に支給されます。
- 資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
- 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること
6-2. 出産手当金
被保険者の資格を喪失する日の前日まで、継続して1年以上被保険者だった場合、資格喪失時に受けていた出産手当金を引き続き受け取ることができます。
出産前後合わせて原則98日間の範囲内で支給を受けることになっていますが、この期間からすでに支給を受けた場合、残りの期間の支給額を受けることが可能です。
6-3. 出産育児一時金
資格を喪失する日の前日まで、継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失日以降、6カ月以内に出産した場合に支給されます。(関係条文 健康保険法第106条)
参照:健康保険法|e-Gov
6-4. 埋葬料
被保険者が資格を喪失した後に死亡した場合、埋葬料または埋葬費が支給されます。
- 継続給付を受けている人が死亡したとき
- 継続給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡したとき
- 被保険者が資格を喪失して3カ月以内に死亡したとき
(関係条文 健康保険法第105条)
7. 社会保険の資格喪失届の書き方を覚えて正しく作成しよう!

今回は、社会保険の資格喪失届について解説しました。社会保険の資格喪失届は、従業員の退職の際に人事および総務が対応しなければいけない手続の1つです。
従業員が安心して仕事をするうえで社会保険は重要です。従業員が転職をする際などに資格喪失届の手続きをスムーズに進めることができないと、対象者の次の職場での社会保険の対応が遅れることもあります。
また、健康保険組合によっては手続方法などが少し異なる場合もありますので、各事業所ごとに加入をしている組合に直接問い合わせるなどして、正しい手続方法を確認したほうがよいでしょう。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









