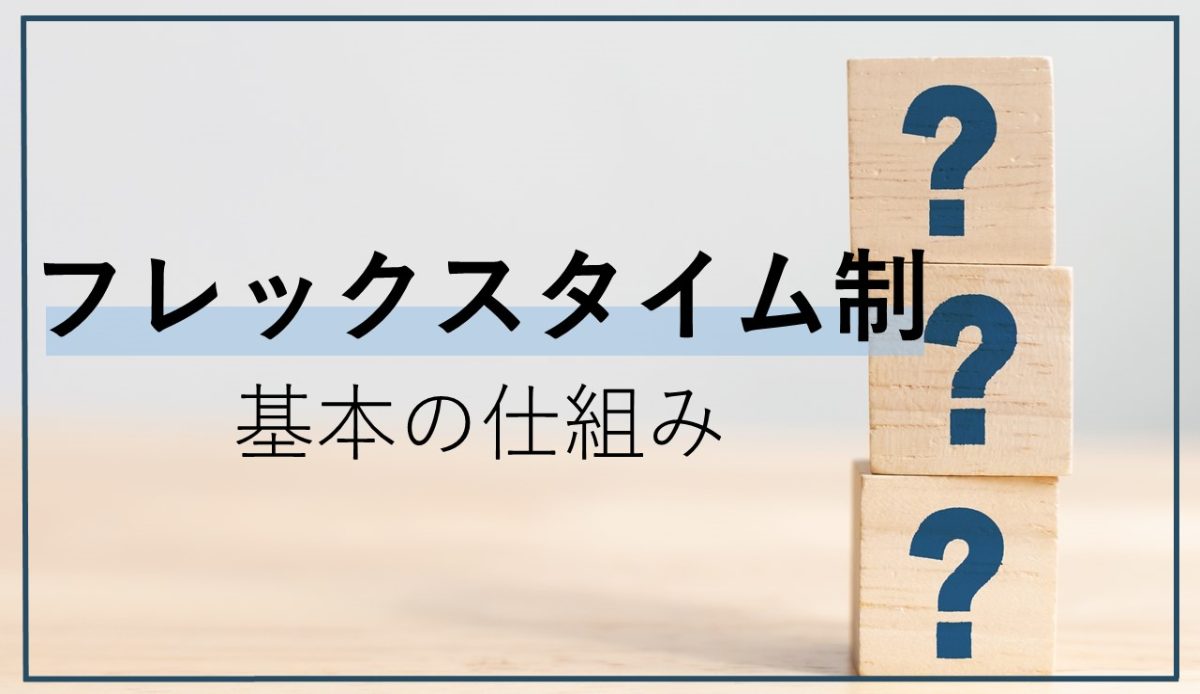
昨今働き方改革が官民で進められており、柔軟な働き方が実現できるフレックスタイム制度の導入を取り入れる企業が増えています。フレックスタイム制度は固定制と異なり、残業時間の捉え方や、導入にあたっていくつかの工程が必要になります。
フレックスタイム制度の適切な運用を始めるために、必要な基礎情報を労働基準法に基づいてわかりやすく解説します。
フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。
また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。
「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1.フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、近年になって耳にするようになった制度かと思われがちですが、実は1988年から日本国内での導入が始まっていました。しかし当時はワークライフバランスがそこまで重要視されていなかったため、今のような普及にはいたらなかったようです。
フレックスタイム制度が定時制と異なる点は、出退勤の時間を個人の裁量で柔軟に調整できる点です。
一定期間内(清算期間)の総労働時間をあらかじめ定めておき、その総労働時間を満たす範囲で労働者は出退勤の時間を自身で決めることができます。
ただし、出退勤の時間を自由に決めることができるとはいっても実際は24時間いつでも好きな時間に働けるわけではなく、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。
1-1. フレックスタイム制の目的
フレックスタイム制の目的は、従業員が自らの働き方を選択できるようにすることです。これにより、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなり、従業員の満足度向上が期待できます。
また、労働者は自分の生活スタイルに合わせて時間を配分できるため、充実感を持って働くことができます。
最終的には、ワーク・ライフ・バランスを実現し、より良い職場環境を築くことがこの制度の重要な目的と言えるでしょう。
2.フレックスタイム制の仕組み
 一般的にフレックスタイム制では、1日のうち必ずあらかじめ勤務しなければならない時間が決められている「コアタイム」と、いつでも出勤・退勤が自由な「フレキシブルタイム」で構成されています。
一般的にフレックスタイム制では、1日のうち必ずあらかじめ勤務しなければならない時間が決められている「コアタイム」と、いつでも出勤・退勤が自由な「フレキシブルタイム」で構成されています。
ただし、フレックスタイム制であるからといってコアタイムは必ず設けなければいけないものではなく、コタアイムなしのフレックスタイム制とすることも可能です。
2-1. フレックスタイム制の清算期間とは
フレックスタイム制では、最初に事業者と労働者代表が労使協定によって「清算期間」を設定します。清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働しなければならない時間を定める期間のことです。
コアタイムの有無に関わらず、労働者はこの清算期間の間に決められた総労働時間分働かなければなりません。また、事業者は1週間の労働時間が平均40時間になるかを確認し、所定労働時間に応じて時間外労働分の残業代などを計算します。
なお、清算期間の上限は3ヵ月となっており、従業員の都合に応じて労働時間を調整することができます。たとえば、家庭の事情で1ヵ月間は早く帰宅したいといった場合、3ヵ月の清算期間のうち1ヵ月分は労働期間を減らし、ほかの2ヵ月で労働時間を増やすといったことが可能です。
2-2.フレックス制の総労働時間とは
フレックス制において総労働時間は、労働契約上、労働者が清算期間内に労働すべき時間として定められる時間を指します。つまり、総労働時間は所定労働時間と同じ意味合いです。
総労働時間は、次のように法定労働時間の範囲内で設定することができます。また、法定労働時間の総枠は「(清算期間の暦日数÷7)×40時間(1週間の法定労働時間」で算出できます。
|
清算期間:1ヵ月単位 |
清算期間:2ヵ月単位 |
清算期間:3ヵ月単位 |
|||
|
清算期間の暦日数 |
法定労働時間の総枠 |
清算期間の暦日数 |
法定労働時間の総枠 |
清算期間の暦日数 |
法定労働時間の総枠 |
|
31日 |
177.1時間 |
62日 |
354.2時間 |
92日 |
525.7時間 |
|
30日 |
171.4時間 |
61日 |
348.5時間 |
91日 |
520.0時間 |
|
29日 |
165.7時間 |
60日 |
342.8時間 |
90日 |
514.2時間 |
|
28日 |
160.0時間 |
59日 |
337.1時間 |
89日 |
508.5時間 |
このように、フレックスタイム制では、清算期間と総労働時間によって多く枠を設定します。運用上注意したいのは、清算期間が1ヵ月を超えた場合でも、繁忙期などによる過度に偏った長時間労働はみとめられない点です。
1ヵ月以上清算期間がある場合は、清算期間内の労働時間が平均して週40時間以内であることが必要です。また、1ヵ月ごとの労働時間は週平均50時間を超えてはいけません。いずれの場合も、超過した労働時間については時間外労働としての割増賃金が発生します。
2-3. フレックスタイム制のコアタイムとは
『コアタイム』とは、その時間内は必ず勤務しなければならない時間帯のことです。従業員同士のコミュニケーションを円滑にするために設定されます。
例えば、コアタイムを10時から15時に設定して必ずオフィスに出勤することにすれば、その時間帯には社員全員が集まり会議や打ち合わせがしやすくなります。
よくある勘違いで多いのが「コアタイムの時間だけ働けばよいか」というものですが、もちろんそんなことはありません。
フレックスタイム制では一定期間の総労働時間が定められているので、コアタイムの時間のみ働いていると合計労働時間が定められた労働時間を下回り、労働時間が不足してしまいます。
企業によっては労働時間の不足分が給料から控除される可能性もあるので、その線引きをどうするのかを企業で考える必要があります。
2-4.フレックスタイム制におけるフレキシブルタイムとは
フレックスタイム制では、コアタイム以外にも「フレキシブルタイム」と呼ばれる時間帯もあります。フレキシブルタイムは、従業員が自由に出退勤の時間を決められる時間帯を意味します。
たとえば出勤時間が7時~11時まで、退勤時間が16時~21時までと設定されているのであれば、この時間帯であればいつでも出退勤が可能です。出退勤時間は固定する必要はありません。たとえば、7時に出勤をして16時に退勤をし、翌日は10時に出勤して19時に退勤することも可能です。
ただし、出退勤の時間を決める際は、清算期間内の所定労働時間を満たせるように考えながら調整する必要があります。
2-5.スーパーフレックスタイムとは
スーパーフレックス制とフレックスタイム制の一番の違いは、「コアタイムがあるか否か」です。
通常、フレックスタイム制には出勤を義務付けるコアタイムと、自由なフレキシブルタイムがありますが、スーパーフレックス制にはコアタイムが存在しません。そのため、スーパーフレックス制を採用している会社では、働く時間帯はほぼ完全に自由となります。
スーパーフレックスタイム制を導入する場合は、通常のフレックスタイム制以上に社内コミュニケーションに注意して環境を整備する必要があります。
ここまで、フレックスタイム制の仕組みやよくある疑問について解説してきましたが、当サイトでは、フレックスタイム制の基礎知識や残業代の考え方、導入手順などを図を用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。
この資料一つで制度の検討から導入まで対応できるため、フレックスタイム制を導入検討中のご担当者様は、こちらから「フレックスタイムを実現するための制度解説BOOK」をダウンロードしてご確認ください。
2-6.時差出勤制度との違い
フレックスタイム制度と似たものに時差出勤制度があります。一見似たような制度に見えますが、それぞれの制度は作られた背景が異なります。フレックスタイム制度が作られた背景は従業員の生産性を高めるためですが、時差出勤制度が作られた背景は通勤ラッシュを回避するためです。
時差出勤制度とフレックスタイム制度の大きな違いは、出退勤の自由度です。時差出勤は所定労働時間が8時間と定められている場合は、出勤時間を早めたり遅らせたりしても、1日のうち所定労働時間である8時間は働かなければいけません。
一方、フレックスタイム制度は出勤時間も退勤時間も自由に決めることができます。コアタイムが設けられている場合、コアタイムの時間帯のみ働く日があっても問題はありません。コアタイムが設けられていない場合は、出退勤の時間はより自由になります。
3.フレックスタイム制のメリット

「自由に出勤し、自分のタイミングで帰宅できる」という働き方は、従業員にとって非常に魅力的です。このような働きやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットをもたらします。以下に、フレックスタイム制の主なメリットを4つ挙げます。
3-1. 従業員のワークライフバランスを推進できる
フレキシブルタイムの間であれば自由に出勤退勤ができるので、急な用事が入ってしまって帰宅しなければいけない場合や、通勤ラッシュの時間帯をずらしての出勤などが可能になります。
子育てや介護をしている方にとっても、柔軟に働けることは魅力的に映ることでしょう。
従業員のワークライフバランスを重要視することができるので、働くことにストレスを感じる社員も大幅に減るのではないかと考えられます。
3-2. 無駄な残業を軽減できる
フレックスタイム制では、清算期間中の労働時間を労働者の采配で調整することができます。
そのため、残業が多い労働者の場合、もし1日で10時間以上働いたとしても、別の忙しくない日に労働時間を短く調整できるため、従業員の無駄な残業を減らせる可能性があります。
これにより従業員に支払う残業代をカットできれば、企業全体のコスト削減にも繋がります。
仕事量が少ない時期の労働時間を繁忙期に割り振るといった、メリハリのある働き方に変えることで、従業員のタイムマネジメント能力の向上も期待できるでしょう。
3-3. 優秀な人材が集まりやすい
多様な働き方が求められている現代において、フレックスタイム制を導入することは、企業の大きなアピールポイントとなります。特にワーク・ライフ・バランスを重視する求職者にとって、プライベートとの両立が容易になるこの制度は、大変魅力的です。人材獲得のための競争が激化する中、優秀な人材からの応募を集められる可能性が高まります。
3-4. 企業イメージの向上につながる
働き方にも多様性が求められている現代において、フレックスタイム制やテレワークを導入している企業は「時代の流れに柔軟に対応している」として高く評価されやすい傾向があります。
特に、子どもがいる共働き家庭や、親の介護をしなければならない人にとっては、業務内容と同じくらい勤務形態も重要視されるポイントです。フレックスタイム制を導入していれば、働きやすい会社として企業イメージが向上し、人材確保のしやすさにもつながることが考えられます。
4.フレックスタイム制のデメリット

従業員にも企業にも多くのメリットがあるフレックスタイム制ですが、導入するにはいくつかのデメリットも考えられます。フレックスタイム制を導入する際には、メリットだけではなくデメリットも踏まえた上で慎重に検討することが大切です。以下ではフレックスタイム制のデメリットを紹介します。
4-1. 勤務時間外に仕事の連絡がくる可能性がある
自分の働く時間を調整できたとしても、仕事で関わる人の勤務時間はコントロールできません。
そのため、フレックスタイム制を利用して早い時間に退勤したとしても、退勤後に取引先から電話やメールで従業員に連絡が来る可能性があります。
関係者のスケジュールを無視すると、業務に支障が出る可能性もあるため、仕事をスムーズに進められない可能性があることは注意しておく必要があります。
4-2. 出社時間がバラバラになる
出社時間がバラバラだと、緊急の案件に対応できないケースが出てきます。
そうなってしまうと取引先に多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。このような事態を避けるためには、コアタイムとフレキシブルタイムをきちんと設けて、必ず会社に出勤しなくてはいけない時間を設定したり、業務フローの見直しや人員配置について検討する必要があるでしょう。
また、コアタイムに遅刻をしてもその分の賃金をカットすることができないため、遅刻ペナルティを設けなければコアタイムの意味がなくなってしまう可能性があります。
4-3. 社内外のコミュニケーションがとりづらくなることがある
フレックスタイム制を導入した場合、メンバー全員がそろう時間が少なくなります。
そのため、急な会議や打ち合わせをしようと思っても、人が集まらない可能性があります。
コアタイムが長く設定されている場合はそれほど心配ありませんが、コアタイムが短い場合は、会議のスケジュール調整は早めにしておく必要があるでしょう。
オンライン会議ツールや社内チャットなどのコミュニケーションツールの活用も重要です。
4-4. 従業員の出退勤管理が大変
フレックスタイム制における労働時間の調整は、基本的に労働者に任せることになります。
自己管理がしっかりできていない場合、総勤務時間が不足しているという事態にもなりかねません。もしそのような事態になった場合は、給料から控除されたり、不足分を足した時間を次の清算期間の総労働時間として勤務したりする必要があります。
そうならないためには、企業が従業員一人ひとりの労働時間を把握しなければなりませんが、個別に出退勤を管理すると担当者の負担が増大します。そのため、フレックスタイム制に対応した勤怠管理システムの導入がおすすめです。
さらに、フレックスタイム制では、繁忙期になったとしても特定の時間帯に企業側から出勤命令を出すことはできません。したがって、フレックスタイム制を導入する際に、対象となる従業員が信頼できる人材なのかを見極める必要があります。
4-5. 光熱費が高くなる可能性がある
フレックスタイム制を導入した場合、従業員の出退勤時間の幅が広がるため、その分オフィスが稼働している時間が前後に伸び、光熱費が高くなる可能性があります。
対策としては、フレキシブルタイムの幅を長くしすぎないことや、人感センサーが搭載された照明やエアコンを導入するといったことが挙げられるでしょう。
フレキシブルタイムの幅が長すぎると、早朝や深夜に労働する従業員が増える可能性があり、労働者の健康面に悪影響を及ぼす可能性もあります。フレキシブルタイムは過度に長くしすぎないことも大切です。
5.フレックスタイム制を導入するためのフロー

フレックスタイム制度を導入・運用を開始するには、いくつか注意すべき点があります。ここからは、それぞれの手順と注意点を解説します。
5-1. 就業規則に定める
「始業・終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる」という旨を記載した就業規則、ないしはそれに準ずるものを作成する必要があります。またフレキシブルタイム・コアタイムを設ける場合も、就業規則にて定めることが求められます。
厚生労働省が提示している就業規則のひな形は、以下の通りです。
(適⽤労働者の範囲)
第○条 第○条の規定にかかわらず、営業部及び開発部に所属する従業員にフレックスタイム制を適⽤する。
(清算期間及び総労働時間)
第○条 清算期間は1箇⽉間とし、毎⽉1⽇を起算⽇とする。
② 清算期間中に労働すべき総労働時間は、154時間とする。
(標準労働時間)
第○条 標準となる1⽇の労働時間は、7時間とする。
(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)
第○条 フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の⾃主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。
② 午前10時から午後3時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属⻑の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
(その他)
第○条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。
5-2. 労使協定を締結する
清算期間は、3ヵ月以内で定める必要があり、1ヵ月を超過する場合は使用者と労働者との間で締結した労使協定を所轄労働基準監督署長へ届け出ることが必要となります。労使協定には、明記する必要がある項目が6つ(うち、2つは任意項目)存在します。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1⽇の労働時間
- コアタイム(※任意)
- フレキシブルタイム(※任意)
また、任意でコアタイムやフレキシブルタイムを追加して定めるケースが多いです。
5-3. 必要に応じて勤怠管理ツールを導入
フレックスタイム制度を導入した場合も、定時制と同様に、時間外労働手当や割増賃金は発生します。
しかし、出退勤のタイミングがバラバラであることや、清算期間中の実働労働時間が異なる可能性が出ることで、従業員の勤怠管理が複雑化するかもしれません。
そのため、従業員の勤怠情報をリアルタイムで確認できるクラウド形態のものや、給与計算をスムーズに連携できるシステムの導入などで、従業員の勤怠を正確に管理することが求められます。
6.フレックスタイム制を導入する際の注意点
 フレックスタイム制を導入する際には、特に以下の3つの点に注意が必要です。
フレックスタイム制を導入する際には、特に以下の3つの点に注意が必要です。
- 労使協定を締結する
- 就業規則の社内周知を徹底する
- 制度に応じた勤怠管理システムを導入する
スムーズにフレックスタイム制を導入するためにも、導入のフローに加えて注意点についてもあらかじめ理解しておきましょう。
6-1. 労使協定を締結する
フレックスタイム制を導入する際は、労使協定を締結する必要があります。労使協定では、とくに以下の6点について定めておく必要があります。
- 対象となる従業員の範囲
- 清算期間
- 清算期間に対する総労働時間(清算期間内の所定労働時間)
- 標準とする1日の労働時間
- コアタイム(任意)
- フレキシブルタイム(任意)
フレックスタイム制では、定められた時間内であれば労働時間を自由に選択できますが、清算期間が定められています。従業員は清算期間内で所定労働時間を満たせるよう注意しなければいけません。
6-2. 就業規則の社内周知を徹底する
フレックスタイム制を導入する際には、就業規則に始業時間および就業時間を労働者の決定に委ねる旨を定めておく必要があります。
また、フレックスタイム制について就業規則に定めた場合は、その内容を従業員に周知徹底する必要もあります。どれだけ詳細に規定を設けても、そのことが従業員にきちんと伝わっていなければ、規定に効力が生じません。
フレックスタイム制についての説明会を開催したり、パンフレットを配布するなどの対策をおこないましょう。
6-3. 制度に応じた勤怠管理システムを導入する
フレックスタイム制を導入すると、制度の性質上、どうしても従業員の出退勤の時間が不明確になり、把握しにくくなってしまいます。さらに、勤務時間が異なることで、従業員間の情報共有がしにくくなる可能性があります。
そのため、フレックスタイム制を導入する場合は、フレックスタイム制に対応した勤怠管理システムを導入し、勤怠管理を徹底することが大切です。また、従業員同士が連絡をとりやすいように、情報共有がスムーズになるシステムやツールの導入も検討する必要があるでしょう。
7.フレックスタイム制に関するよくある疑問8選

フレックスタイム制を導入した場合、「残業代は出るの?」「遅刻したらどうなるの?」といった疑問を抱える方も多いでしょう。
そこで、ここからは、フレックスタイム制に関してよくある疑問を8つピックアップし、お答えしていきます。
【疑問①】残業代は出るのか?
フレックスタイム制は基本的には総労働時間が基準であるため、1日のうちで勤務時間が8時間以上であったとしても、実働時間の合計が総労働時間を超えていなければ、残業扱いにはなりません。
例えば、ある日の労働時間が10時間だった場合を考えてみましょう。
通常の労働時間制の企業では2時間が時間外労働となりますが、フレックスタイム制を導入している企業では、清算期間内の総労働時間で計算するためこの限りではありません。 フレックスタイム制における時間外労働の取り扱いに関しては、清算期間の長さによって異なります。
清算期間が1ヵ月以内である場合は、清算期間内で法定労働時間を超過した労働があれば、時間外労働手当の支給が必要です。
清算期間が1ヵ月を超えており3ヵ月以内である場合は、以下の2点を超えた分が時間外労働に該当し、手当の支給が必要となります。
- 1ヵ月ごとに週平均の労働時間が50時間を超過した場合
- 清算期間を終えて法定労働時間総枠を超えた場合
また、1ヵ月単位での時間外労働が60時間を超過した場合には、割増率50%の割増賃金が必要です。
いずれの清算期間においても、時間外労働の発生が見込まれる場合には、定時制と同様であらかじめ36協定を締結する必要があります。
法定休日や深夜での労働などにも、それぞれ割増賃金が発生するということを覚えておきましょう。
【疑問②】労働時間に不足が発生した場合は?
フレックスタイム制の清算期間における実労働時間が不足している場合には、給与支払いにおいては2つの手段が存在します。
- 不足時間の賃金を控除する方法
- 賃金控除せず、不足時間を繰り越し、次の清算期間の総労働時間に合算する方法(ただし、加算後の労働時間は法定労働時間の総枠の範囲内である必要があります)
【疑問③】遅刻や早退の概念はあるのか?
フレキシブルタイムに関しては、遅刻も早退も存在しません。問題になるのはコアタイムのみとなります。
コアタイムは出社を義務付けている時間帯であるため、コアタイムに遅れれば遅刻、退勤すれば早退として扱われます。
ただし、コアタイム中に遅刻や早退が発生しても、清算期間(最大3ヵ月)の総労働時間を満たしている限りは、賃金を不足時間分カットすることが困難になります。そのため、コアタイムの遅刻や早退については、あらかじめ社内でルールを規定し就業規則に記載しておく必要があるでしょう。
【疑問④】有給休暇は取れるのか?
フレックスタイム制の場合も、通常通り有給休暇の取得が可能です。
取得の際は、その日に標準となる1日の労働時間を働いたものとして取り扱うことになるので、標準労働時間が8時間の場合は、フレックスタイム制であっても「8時間働いた」として有給休暇を取得できます。
【疑問⑤】フレキシブルタイム外で働く従業員がいた場合はどうなる?
フレキシブルタイムを設定している企業内にフレキシブルタイム外で働く社員がいる場合は、定時制での残業と同じく、企業ごとに管理をおこなうことが求められます。労働時間への加算や、適宜時間外手当を支払う必要があります。
逆に、コアタイム以外のフレキシブルタイムで労働に従事せずに業務に支障をきたした場合は、業務命令違反として懲戒処分の対象にもなりうるので注意しましょう。
管理者は従業員の労働状況をしっかりと把握し、適切な労働環境をつくることが大切です。
【疑問⑥】裁量労働制・変形時間労働制の違いは?
裁量労働制・変形時間労働制もフレックスタイム制度と同様、定時制と異なる勤務形態であるため、混同しやすいです。それぞれの制度の特徴は以下の通りです。
変形労働時間制とは、特定の週において法定労働時間を超えて働かせることが可能な制度です。1ヵ月の労働時間を平均し、週40時間を超えない場合のみ導入できます。閑散期は労働時間を減らし、繁忙期には労働時間を増やすといった効率的な働き方が実現できます。
裁量労働制とは、労働時間を従業員に完全にゆだねる制度です。外回り営業、研究職、企画職といった特定の職種のみが導入できます。自身で裁量を調整できたり時間を自由に使えることから、より高い成果をあげられることが期待できます。
フレックスタイム制は、所定労働時間が清算期間全体で決められているものです。1日の労働時間を従業員が調整できることで、柔軟な働き方が実現し、業務と生活の両立がしやすくなります。残業時間の削減や、生産性の向上が見込めるでしょう。
【疑問⑦】部署や個人単位での導入は可能か?
フレックスタイム制を、特定の部署や個人ごとに適用させることは可能です。また清算期間も労使協定に明記すれば、部署や個人によって異なる期間で設定しても問題ありません。
例えば、開発部門においてはプロジェクトによって忙しさが変わるため、フレックスタイム制を導入した際に特に柔軟さが求められるケースがあります。 一方で、コールセンターのように業務が一定で、勤怠が一律に求められる部署の場合には、定時勤務を基本としつつ、一部フレックスタイム制を導入するという形も考えられます。
このように、フレックスタイム制は部署や個人の業務特性に応じて、柔軟に運用することができるため、導入の際にはそれぞれのニーズを考慮し、最適な形での配慮が必要です。
しっかりとした運用体制と従業員への説明があれば、より効果的に働きやすい環境を提供できるでしょう。
【疑問⑧】フレックスタイム制導入に向いている業界・職種は?
大手企業から中小企業まで導入の動きが進んでいるフレックスタイム制度ですが、なかなか導入までいかない企業も多いはずです。
なぜフレックスタイム制が普及しないのか疑問に感じる方もいると思いますが、業務形態や職種によって、メリットを享受できる度合いが変動することが理由として挙げられます。
平成30年の厚生労働省の調査によると、業界別でのフレックスタイム制の導入率は、「電気・ガス・水道」が29.6%と最も高く、その後に情報通信業(24.0%)、専門・技術サービス業(14.1%)、製造業(13.8%)が多いことがうかがえます。一方で飲食業や宿泊業、医療福祉業などの接客を仕事とする業界や、建設業は依然として導入率が低い状況であることがわかります。[注1]
またフレックスタイム制に特に向いている職種は、個人の裁量で仕事を進められるという特徴があります。企画職や事務職、エンジニア、Webデザイナー、Webライターなどの職種が該当します。
8.フレックスタイム制の導入で働きやすさや生産性の向上を目指そう
 フレックスタイム制度について、基本的な知識を一通りご説明しました。普通の労働基準と異なっているため、勤怠の管理をしっかりしておかないと給与計算をする際に誤差が生じてしまう可能性があります。
フレックスタイム制度について、基本的な知識を一通りご説明しました。普通の労働基準と異なっているため、勤怠の管理をしっかりしておかないと給与計算をする際に誤差が生じてしまう可能性があります。
そのようなことにならないためにも、フレックスタイム制度に対しての理解を深めていきましょう。フレックスタイム制度を取り入れることで、職種によっては従業員の仕事に対する生産性や、企業の業績向上につながる可能性があるかもしれません。








