
フレックスタイム制には、従業員のライフワークバランスや生産性の向上といった効果が見込まれることから、導入を検討する企業が増えています。フレックスタイム制の導入・運用には、労使協定の締結や就業規則にまつわるルールの理解が不可欠です。
本記事では、フレックスタイム制を導入するにあたり、労使協定に組み込む必要がある事項、就業規則にまつわるルールや注意点をあわせて解説します。
フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。
また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。
「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. フレックスタイム制とは
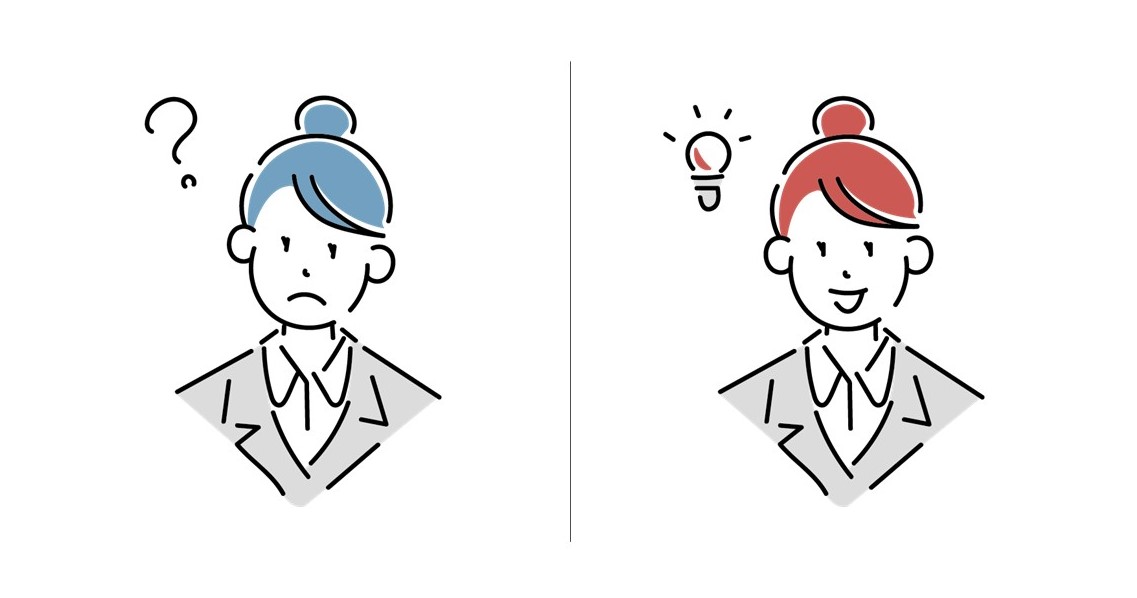
フレックスタイム制度とは、「最大期間を3ヵ月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で出退勤の時間を自分で決めることができる」制度です。
一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。
1-1. コアタイムとフレキシブルタイム
『コアタイム』とは、その時間内は必ず勤務しなければならない時間帯です。決まった時間に会議や打ち合わせなどをする場合に、フレックスタイムを理由に参加しないわけにはいきません。
たとえば、10時から15時と明確に時間を設定して、オフィスに出勤する時間をコアタイムとして設けます。定例の会議や打ち合わせがある場合は、コアタイム内に設定すると、もれなく参加できるようになります。
一方、『フレキシブルタイム』とは、コアタイム以外で、いつ出社または退社してもいい時間帯のことです。このコアタイムとフレキシブルタイムは、企業によって自由に時間帯を設定できるため、コアタイムが長さは会社によって異なります。
なお、『スーパーフレックス』『フルフレックス』と呼ばれる、コアタイムなしの働き方でも問題ありません。
ここで注意したいのは、コアタイムの時間だけ働いていればよいと考えてしまうことです。フレックスタイム制度は清算期間内の総労働時間が定められてるため、コアタイムしか稼動しない場合、合計労働時間が規定を下回り、労働時間が不足してしまいます。
労務担当者や現場の管理者は、従業員の労働時間が不足しないように管理することが求められます。
1-2. フレックスタイム制のメリット・デメリット
フレックスタイム制のメリットは以下の通りです。
- 時間外労働を削減できる
- 従業員の自主性を尊重しやすい
- ラッシュ時を回避した通勤ができる
一方、フレックスタイム制にはデメリットもあります。
- 繁忙期がある場合、出社・退社時刻を会社で指定できないため業務が回らないことがある
- 満18歳に満たない従業員には適用できない
フレックスタイム制を導入する際は、対象となる業種や従業員の選定に注意する必要があります。
これに加え、フレックスタイム制はワークライフバランスの向上にも寄与します。従業員が自身のライフスタイルに合わせて働く時間を選べることで、ストレスを軽減し、仕事への満足度が向上します。
ただし、この制度が効果的に機能するためには、企業の文化や業務特性に応じた適切な運用が求められます。例えば、チームでの協力が求められる業務では、コアタイムを設定することで、メンバー間のコミュニケーションを円滑に保つことが重要です。
フレックスタイム制の効果を最大限に引き出すためには、時間の管理だけでなく、労働者自身の自己管理能力も重要な要素となります。企業は従業員に対して、制度の活用方法やメリットをしっかりと理解させることも重要です。
▶コアタイムの意味や目的とは?フレックスタイム制の効果的な運用を解説!
2. フレックスタイム制の導入に必要な手続きとは?

フレックスタイム制度は、「清算期間(最大3ヵ月)を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内であれば、出退勤の時間を従業員に委ねる」という制度です。
このような就業形態を実現するために、次の2つの要件を満たす必要があります。
- フレックスタイムを導入する旨を就業規則等に規定する
- 具体的な事項に関して労使協定を締結する
では、次項以降でそれぞれについて詳しくみていきましょう。
Step1:就業規則等に規定する
就業規則あるいはこれに準ずるものには、「始業・終業時刻を労働者の自主決定に委ねること」を規定する必要があります。また、対象となる労働者の範囲や清算期間、清算期間における総労働時間に関しても、労働者の始業・終業時刻にかかわる事項であることから、就業規則等でも規定しなければなりません。
注意すべき点は、フレックスタイム制度において、始業時間だけあるいは終業時間のいずれか一方だけを労働者に委ねることは不適切であるという点です。必ず両方の時刻を労働者の決定に委ねなければなりません。
Step2:労使協定を締結する
労使協定は、事業場に過半数の労働者で組織された労働組合があればその組合と、そうした組合がない場合は過半数の労働者を代表した者と締結します。労使協定では、フレックスタイム制度の基本的な枠組みを5つの項目に設定しています。
労使協定を締結したら、所轄の労働基準監督署長に届け出を忘れずにおこなってください。届出の提出方法は、受付にて直接渡す方法と、郵送する方法の2種類が認められています。
労使協定の締結を届け出る際は、労使協定届(様式第3号の3)を用意し、労使協定の写しと共に届出をおこないましょう。
なお、法改正によって令和3年4月1日以降は使用者の押印または署名が不要になりました。e-Gov電子申請を通じたオンラインの手続きも可能です。
Step3:従業員へ周知する
企業は、就業規則を従業員に知らせる義務があります。フレックスタイム制の導入をおこなうにあたっても、従業員への周知を徹底しなければなりません。フレックスタイム制のルールや導入の意図を含めて伝え、社内への浸透を図りましょう。
周知方法に関しては、労働基準法106条の労働基準法施行規則第52条の2にて、以下の通りに定められています。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
引用:労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
このように、周知をおこなう際には労働者がいつでも情報を確認できる場所への掲示・交付が求められます。デジタルデータをアップロードした場合には、社外への持ち出しが発生しかねないため、コピーやダウンロードの制限を加えるなどの対策をすることをおすすめします。
【注意】フレックスタイム制において労使協定の届出が不要なケースとは
清算期間とは、厚生労働省によると「フレックスタイム制において、労働者が労働すべき時間を定める期間のこと」と定義されています。また清算期間の上限は、法改正により1ヵ月から3ヵ月に更新されました。
仮に清算期間を1ヵ月以内に定める場合は、労使協定の届出は不要です。
清算期間が1ヵ月を超える場合には、労使協定届を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。これに違反すると、罰則(30万円以下の罰金)が科せられる可能性があるので注意が必要です。
3. 【ひな形付き】フレックスタイム制において就業規則で定める必要がある項目
就業規則とは、使用者が従業員に対して求める規則であり、従業員はそれらを守る必要があります。フレックスタイム制においては、下記の情報を追加する必要があります。
3-1. 始業及び終業時刻の両方を労働者の決定に委ねること
フレックスタイム制を取り入れた際には、従業員には始業・終業時間の両方を、自主的に決定できる権利が与えられます。上記の旨を含めた厚生労働省が出す就業規則のひな形は、下記の通りです。
(適⽤労働者の範囲) 第○条 第○条の規定にかかわらず、営業部及び開発部に所属する従業員にフレックスタイム 制を適⽤する。
(清算期間及び総労働時間) 第○条 清算期間は1箇⽉間とし、毎⽉1⽇を起算⽇とする。 ② 清算期間中に労働すべき総労働時間は、154時間とする。
(標準労働時間) 第○条 標準となる1⽇の労働時間は、7時間とする。
(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム) 第○条 フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員 の⾃主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ね る時間帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ね る時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。 ② 午前10時から午後3時までの間
(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)につい ては、所属⻑の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
(その他) 第○条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。
4. 【ひな形付き】フレックスタイム制に関する労使協定で締結が必要な項目

労使協定を締結するためには、以下の通り労働組合か従業員代表者と書面による協定を取り交わす必要があります。
- 労働者の過半数で組織する労働組合
- その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
- その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
労働組合と使用者の間で締結し、組合員にのみ効力を及ぼす労働協約と呼ばれる協約もありますが、労働基準法第32条の3により、フレックスタイム制を導入する際は「労使協定」の締結が必要です。
フレックスタイム制度における労使協定の基本的な枠組みについて紹介します。
4-1. 対象となる労働者の範囲
フレックスタイム制度の対象となる労働者の範囲を明示します。全労働者、○○課に所属する者、本社の事務員など様々な範囲が考えられます。
▶フレックスタイム制が適している職種は?|メリット・デメリットもご紹介!
4-2. 清算期間
清算期間に関しては「期間の長さ」と「起算日」の両方を定めなければなりません。ゆえに、毎月1日から末日までの1ヵ月間などと定められることが一般的です。期間の長さは1ヵ月以内であればよいので、1週間単位など任意に定めることが可能です。
清算期間を決定する際には、企業の業務サイクルや状況を考慮することが重要です。例えば、業務が繁忙期を迎える月や四半期の最終月などに合わせて、運用しやすい期間を設定することで、労働時間の管理がスムーズになります。
また、清算期間が1ヵ月を超えた場合には、労使協定の届け出が必要となります。このため、期間を設定する際には、1ヵ月に留めることで届出の手続きを省略できる点も考慮すると良いでしょう。
▶フレックスタイム制の清算期間とは?最大3ヵ月に延長する際の注意点
4-3. 清算期間における総労働時間
定めた清算期間内に労働しなければならない時間を定めます。この時間を平均した1週間の労働時間は、法定労働時間と同じかそれより少なくなければならないことに注意してください。
法定労働時間は40時間/週の場合、清算期間における総労働時間は次の「法定労働時間の総枠」以下にする必要があります。清算期間における総労働時間を超えて労働した場合は、時間外労働として取り扱われます。
| 清算期間 | 法定労働時間の総枠 |
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
| 7日 | 40.0時間 |
労使協定においては大きく分けて、
①法定労働時間の総枠の範囲内で1ヵ月○○時間といった具合に一律に総労働時間を定める方法
②所定労働日を定めて所定労働日の労働時間を定める方法
があります。
現在は清算期間が最大3ヵ月まで可能なので、清算期間に合わせて都度計算をし直すようにしましょう。
▶フレックスタイム制で残業代は減るの?残業時間の算出方法を解説!
4-4. 標準となる1日の労働時間
一般的には定めた総労働時間を清算期間における所定労働日数で割ったものを記載します。
ここで設定された標準となる1日の労働時間は、賃金計算の基礎となる重要な要素です。
ただし、単に適切と思われる労働時間を記載するだけでも構いません。たとえば、「1日の労働時間は6.5時間とする」と具体的に明記することも可能です。
フレックスタイム制度の対象となる労働者が有給休暇を取得した場合、ここで定めた時間を労働したものとして取り扱われます。
このように、標準となる1日の労働時間の設定は、企業にとっても従業員にとっても、フレックスタイム制度を適切に運用するための重要な基準となります。
さらに、標準労働時間の設定により、労働者は自分の労働時間を理解し、管理することができるため、労働意欲の向上にも繋がります。
4-5. コアタイムとフレキシブルタイム※任意項目
コアタイムとは、従業員が必ず出勤している必要がある時間帯のことです。
この時間帯を明確に定めることで、チーム内でのコミュニケーションや業務の調整がしやすくなります。
コアタイムを設ける場合はその開始時刻と終了時刻を定める必要があります。
ただし、コアタイムの開始時刻から終了時刻までの時間数と清算期間として定めた「標準となる1日の労働時間」がほぼ一致するような場合は、フレックスタイム制度の趣旨から外れてしまうことに注意してください。
フレキシブルタイムは、従業員が自分の意思で始業および終業の時刻を決定できる時間帯です。
フレックスタイム制度の柔軟性を生かし、企業の特性に合ったコアタイムとフレキシブルタイムを適切に設定することが重要です。
さらに、コアタイムやフレキシブルタイムを活用することで、仕事の効率や生産性を高めることが期待されます。
なお、コアタイムとフレキシブルタイムはフレックスタイム制に関する労使協定を締結する上で必須の項目ではなく、任意でよいとされています。
4-6. フレックスタイム制における労使協定のひな形例
フレックスタイム制における労使協定のひな形例を紹介します。作成する際は、最新の法令に基づき、自社に合う内容に適宜変更しましょう。
○○○○株式会社○○○と過半数代表者○○○は、労働基準法第32条の3のフレックスタイム制について、次のとおり協定する。
(適用対象者)
第1条 対象者は営業部門の正社員とする。
(清算期間)
【清算期間を1ヵ月とする場合】
第2条 清算期間は、毎月1日から31日までの1ヵ月とする。 ただし、清算期間の途中から、フレックスの適用を受けることになった従業員については、フレックス適用日から、月の末日までを清算期間とする。
(清算期間における総所定労働時間)
【清算期間を1ヵ月とする場合】
第3条 清算期間における総所定労働時間(以下、「総所定時間」という。)は、当該清算期間の所定労働日数に7.5時間を乗じた時間数とする。
(標準となる1日の労働時間の長さ)
第4条 標準時間は、1日7.5時間とし、年次有給休暇を取得した日については7.5時間の労働があったものとして取り扱う。
(休憩)
第5条 休憩時間は、12時から13時までとする。
(コアタイム)
第6条 フレックスの適用対象者であっても、10時から15時までは、勤務しなければならないものとする。
(フレキシブルタイム)
第7条 フレックスの適用対象者が、選択により労働することができる時間帯は、次のとおりとする。
開始 7時から10時まで
終了 15時から19時まで
(時間外労働と賃金の控除)
第8条 第3条の契約時間を超えて労働した場合は、賃金規定の定めるところにより、時間外手当を支払う。この場合、法定労働時間を超えて労働した場合には、賃金規定の定めるところに従って、割増賃金を合わせて支払う。 第3条の契約時間に満たない場合は、その不足時間分を賃金規定の定めるところにより控除する。
(休日及び休日勤務)
第9条 休日は次のとおりとする。 ①土曜日 ②日曜日 ③国民の祝日 休日に労働を命ぜられた場合には、実労働時間に応じて賃金を支払う。 法定休日に労働した場合には、賃金規定の定めるところに従い、割増賃金を支払う。
(深夜労働)
第10条 深夜に労働することを命ぜられ、これをおこなった者に対しては、賃金規定の定めるところにより深夜割増手当を支払う。
(遅刻、早退、欠勤の取扱い)
第11条 遅刻、早退に関する就業規則の定めは、第6条のコアタイムの時間につき、これを適用する。 コアタイムの時間につきまったく勤務しなかった者については、就業規則の欠勤に関する扱いを適用する。ただし、その者がフレキシブルタイムに勤務した場合には、その時間に相当する賃金を支払う。
(フレックスタイムの適用解除)
第12条 毎月の総所定時間を下回る勤務がしばしば及ぶ者については、フレックスタイムの適用を解除し、通常勤務を命ずることがある。
(フレックス期間途中の異動等)
第13条 清算期間の途中で退職、解雇、異動等があり、フレックスの適用を受けなくなった場合の総所定時間は次のとおりとし、清算期間途中までの実労働時間がこれを超える場合は、超えた時間について時間外手当を支払い、不足がある場合については、賃金の控除は行わない。
この場合、法定労働時間を超えて労働した場合には、賃金規定の定めるところに従って、割増賃金を合わせて支払う。
総所定時間=フレックス適用期間中の所定労働日数×標準時間
(有効期間)
第14条 本協定は令和6年4月1日より1年間有効とする。ただし、有効期間満了の3ヵ月前までに労使のいずれかから書面による異議の申出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。
署名捺印
また、当サイトでは、本記事で解説したフレックスタイム制度に関する基礎知識や導入手順、メリット・デメリットを図を用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。
フレックスタイム制度は細かい考え方が複雑に絡み合っていますので、導入検討中だが制度の理解や運用方法について不安な点が残っているご担当者は、こちらから「フレックスタイムを実現するための制度解説BOOK」をダウンロードしてご確認ください。
5. フレックスタイム制の運用にあたり任意で定めておきたい事項
 労使協定に含む事項には、上記のフレキシブルタイムと同様、任意で定められる場合のある事項が複数存在します。
労使協定に含む事項には、上記のフレキシブルタイムと同様、任意で定められる場合のある事項が複数存在します。
5-1. 休憩時間
原則として、フレックスタイム制においても休憩時間は、6時間を超える労働には45分、8時間を超える労働には1時間を労働の途中で与える必要があります。また一斉に与え、自由に利用させなければなりません。しかしフレックスタイム制により、従業員一人一人の始業・終業時刻が異なってくる場合、休憩をとる時間も異なることが考えられます。
このため、各従業員が自分の勤務状況に応じて休憩を管理できるシステムを導入することが求められます。
例えば、就業規則内に「従業員は任意のタイミングで休憩を取得できるが、労働基準法に則った休憩時間を必ず確保すること」と明記し、労使協定を締結することで、各自の責任に基づく柔軟な働き方をサポートできます。
休憩を取得する時間をゆだねる場合は、その旨を就業規則に記載する必要が出ます。
さらに、定期的に従業員に対し、休憩の大切さや取得方法について研修や説明会を実施することで、労働環境全体の改善にも寄与することが期待できます。
5-2. フレックスタイム制の適用外時間帯
例えば、年末年始をはじめとする祝日でフレックスタイムを適用させない時間がある場合は、その旨を明記します。また深夜残業を防止したい場合は、フレキシブルタイムを設定して勤務ができないようにするとよいでしょう。
特に、午後22時から翌午前5時の時間帯については、全ての従業員が休息を取ることを優先するため、こちらを始業・就業時間から除外することが推奨されます。
このように、フレックスタイム制を運用する際には、適用外の時間帯を明確に設定することが、労働者の健康管理や業務の効率化に寄与します。
5-3. 超過時間・不足時間の取り扱い
残業が発生する企業の場合、清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過して労働した場合の取り扱いを明記しておくとよいです。
逆に実労働時間が総労働時間に至らなかった場合には、下記2パターンの対応があります。
- 不足分を次月の総労働時間に繰り越す
- 不足時間分を賃金から控除する
不足時間分を翌月の総労働時間に上積みさせることは、法定労働時間の範囲内である限りは、違法となりません。
▶フレックスタイム制で不足時間控除が適用される具体例で徹底解説
5-4. 休日の取り扱い
所定の曜日を休日にしたい場合は、休日の取り扱いを明記します。
また法定休日での出勤は、フレックスタイム制においても休日労働に対する割増賃金が求められるため、その旨を明記しておくとわかりやすいです。
そのため、休日のうちどれが所定休日で、どれが法定休日かを明確にしておくべきでしょう。
休日出勤が発生した場合の賃金についても、明確に取り決めておくことが望ましいでしょう。
たとえば、休日出勤をした場合の賃金は労働基準法に則り割増賃金を支払う、または振替休日を消化することを不要とするなどの具体的なルールを設けることで、従業員が安心して働ける環境を整えることが可能です。
休日出勤時の対応を事前に定めることで、労働者にとって公平な処遇が確保され、働きやすい職場環境の構築につながります。
5-5. 遅刻・早退・欠勤の取り扱い
フレックスタイム制では、本来、総労働時間を満たしていれば問題はありませんので、遅刻や早退などは発生しません。
しかし、コアタイムの遅刻・早退・欠勤を防止したい場合は、下記のように制裁やインセンティブを設け、労使協定を結ぶことで対策が可能です。
- 正当な理由なくコアタイムに欠勤した場合は減給の処分とする。
コアタイムの遅刻・早退・欠勤を賞与に反映させることで、従業員のモチベーションを高めることができます。
さらに、コアタイムに遅刻・早退・欠席がなかった場合、皆勤手当てを支給することで、誠実な出勤を促すインセンティブとなります。
フレックスタイム制導入により、秩序の乱れが懸念される場合は、事前に対策を取ることが重要です。
適切なルールを設けることで、従業員の勤務意欲を高めるだけでなく、企業全体の生産性向上にも寄与するでしょう。
▶フレックスタイム制における遅刻の考え方を控除やペナルティと合わせて解説
5-6. フレックスタイム制の解除条件
例えば、従業員が適切な時間管理をおこなえず、コアタイムへの遅刻や総労働時間の不足を繰り返す場合は、定時制に切り替えることも手段の一つです。解除する条件を定めて、事前に労使協定に定めておく必要があります。
具体例としては、コアタイムにおける遅刻が連続して3回発生した場合、フレックスタイム制の適用を解除し、通常勤務への移行を検討するという条件を設けることが考えられます。
このような解除条件をあらかじめ明確にすることで、従業員にも責任感が生まれ、自主的な時間管理を促すことが可能になります。
また、解除の際は従業員への事前通知を行い、状況に応じたフォローアップも重要です。これにより、適切な労働環境を維持しながら、フレックスタイム制度を円滑に運用できる体制を整えることが期待されます。
5-7. フレックスタイム制の有効期間
有効期間を定めておくメリットとしては、のちにフレックスタイム制を解約する際の工数が省けることです。定めない場合は、解約時に企業と従業員との合意を再度とる必要があるためです。
有効期限を一年に設定しても毎年新たに締結することは逆に手間になりかねないため、特定の期限までに解約の申し出がない場合は、自動更新をする旨を定めることを推奨します。
6. フレックスタイム制の運用における注意点
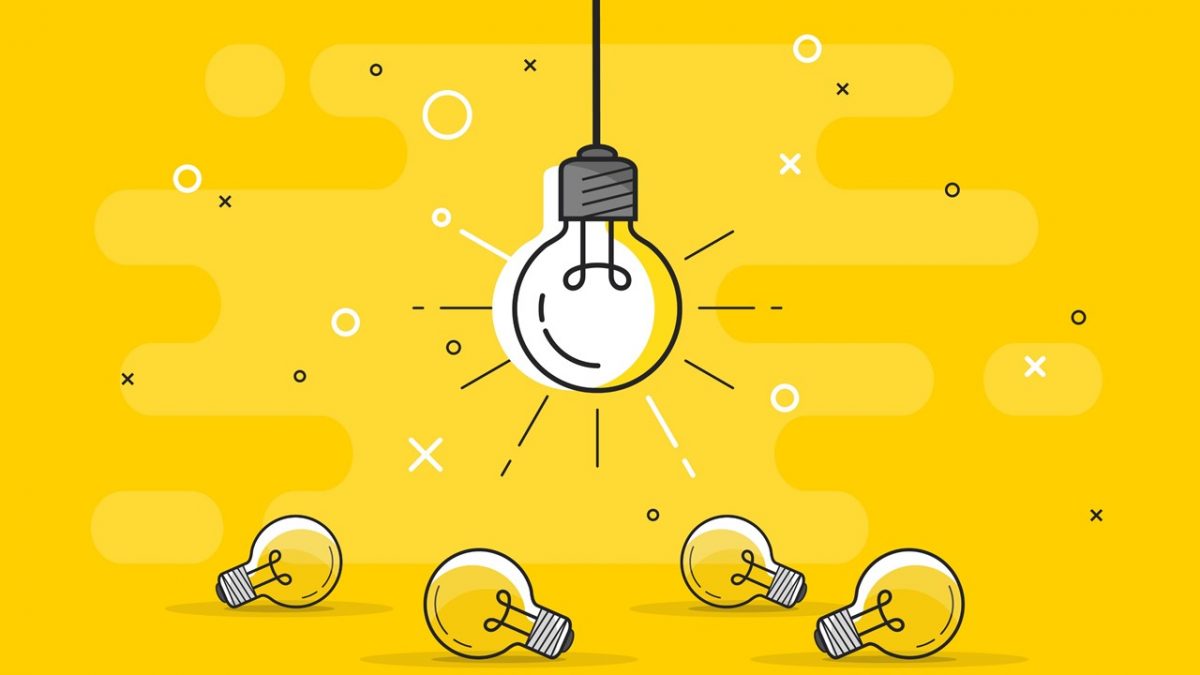
労働時間の自由度が高いフレックスタイム制ですが、正しいルールのもとで運用しなければ、労働基準法に違反してしまう恐れがあります。定時制とは異なる部分を理解し、注意しておくべきポイントを明確にしましょう。
6-1. 36協定の締結・届出と割増賃金の支払う必要があるケース
フレックスタイム制は始業・終業時間を従業員に委ねる制度ですが、定時制と同様、総労働時間が1日8時間、1週間で40時間を超える場合は、36協定の締結・届出をおこなう必要があります。同様に、休日労働が発生する場合も36協定の締結が必要です。時間外労働には25%、休日労働には35%の割増率で割増賃金が必要になるため、注意しましょう。
6-2. 労働時間に過不足が生じた場合の処理方法
フレックスタイム制において、労働時間の総枠に対して発生した不足分は、以下の二つの処理方法があります。
- 次月に繰り越す
- 不足分の給料をカットする
しかし、翌月に繰り越しをおこなう際には、総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうと労働基準法に違反してしまうため注意が必要です。
6-3. 遅刻や早退の管理について
遅刻や早退、欠勤などは設定したコアタイム内に労働できていない場合にカウントされます。
しかし、例えばコアタイム終了前に1時間の早退した社員がいた場合、1時間分の賃金をカット出来るとは限りません。別日に早退した時間分働き、清算期間における総労働時間が満たされている可能性があるためです。
不就労としてではなく、就業規則違反としてペナルティを課す場合は、労働基準法91条にある「1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えない、1賃金支払期に発生した減給の合計が給料総額の10分の1を超えない」を満たす必要があります。
6-4. 2023年4月1日以降の割増賃金の考え方
2023年4月1日以降は、大企業だけでなく中小企業も対象も月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。
清算期間が1ヵ月を超えるフレックスタイム制においては、1ヵ月ごとに以下のそれぞれを時間外労働としてカウントします。
- 週平均50時間を超えて労働した時間
- 清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(ただし、1でカウントした時間は除外する)
1、2で算定した時間外労働については、60時間までは25%以上、60時間を超えた時間については50%以上の割増率で計算して支給しましょう。
7. フレックスタイム制は労使協定を締結してから導入・運用しよう

フレックスタイム制は、始業・終業時刻を自身で自由に設定ができる便利な制度です。社内でスムーズに導入をするためには、労使協定の締結や就業規則をしっかりと定めることが重要です。
注意しておくべきポイントを理解し、社内に正しくフレックスタイム制を取り入れましょう。








