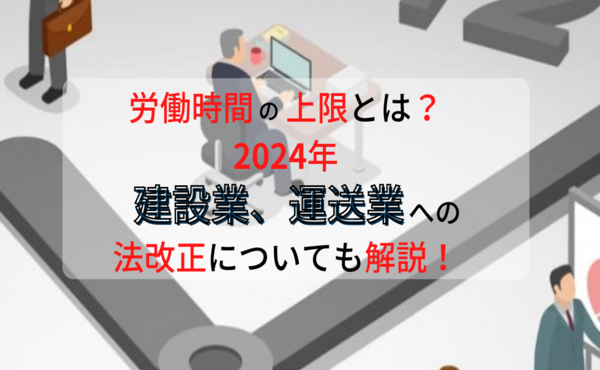 労働時間の上限について理解することは、従業員が健康に働ける労働環境を作るうえで非常に大切です。また、従業員ごとの労働時間を客観的に把握することは企業の義務であるため、しっかりと管理しましょう。
労働時間の上限について理解することは、従業員が健康に働ける労働環境を作るうえで非常に大切です。また、従業員ごとの労働時間を客観的に把握することは企業の義務であるため、しっかりと管理しましょう。
本記事では、労働時間の上限や36協定、2024年4月に適用された建設業や運送業に関する法改正まで、幅広く解説します。
関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!
この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。
そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。
法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。
働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひ「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 労働時間の上限とは?

労働時間・残業時間の上限や休憩時間に関するルールは、労働基準法によって明確に定められています。労働時間の上限について理解することは、労働基準法に違反してしまうリスクをなくすだけでなく、働きやすい労働環境づくりに不可欠です。
ここでは、労働基準法によって定められた労働時間の上限について解説します。
1-1. 労働時間とは?
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下にある時間」のことです。また、労働時間は「所定労働時間」と「法定労働時間」に分けられます。
所定労働時間とは、各企業の就業規則により定められた労働時間のことです。一方で、法定労働時間とは労働基準法によって定められた労働時間の上限のことを指します。
関連記事:「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いとは?定義や残業代計算について詳しく解説!
労働時間に含まれる時間
労働時間の定義に沿って考えると、以下のような時間も労働時間に含まれます。
- 指定された制服・作業着に着替える時間
- 電話番をしながら自席で休憩する時間
- 上司からの指示による掃除の時間
逆に、労働者が自由に行動できる休憩時間や移動時間は、労働時間には含まれません。基準をしっかりと理解したうえで、労働時間を管理しましょう。
1-2. 1日・1週間の労働時間の上限
労働基準法第32条により、法定労働時間は「1日8時間、週40時間」までと定められています。この法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合は、36協定を締結しなくてはなりません。
関連記事:労働時間の月あたりの上限とは?月平均労働時間や200時間労働の可否を解説
1-3. 1カ月の労働時間の上限
1カ月を4週と考えると、法定労働時間の上限は160時間(40時間 × 4週)です。36協定を結んだ場合、月の残業時間の上限は45時間であるため、総労働時間の上限は205時間(160時間 + 45時間)となります。
ただし、上限を超えなければ問題ないというわけではなく、従業員の健康や生活を守るため、できる限り残業を減らす努力をすることが大切です。
1-4. 1年の労働時間の上限
次に、1年間の労働時間の上限を考えてみましょう。365日から土日や年末年始休暇などの日数を引くと、約240日となります。よって、1年間における法定労働時間の上限の目安は、約1,920時間(8時間 × 約240日)です。
また、36協定を結んだ場合、年間の残業時間の上限は360時間であるため、総労働時間の上限の目安は約2,280時間(約1,920時間 + 360時間)となります。
1-5. 労働時間の上限に違反した場合の罰則は?
36協定を締結せずに法定労働時間を超えて働かせたり、36協定の時間外労働の上限を超えて働かせたりした場合、労働基準法第119条により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則が科される恐れがあるので注意が必要です。
2. 36協定を締結したときの労働時間の上限

企業と従業員の間で36協定を締結すると、「1日8時間、週40時間」を超える労働が可能になります。しかし、無制限に労働させられるというわけではなく、法定労働時間を超える時間外労働は「月45時間、年360時間まで」と定められているため注意しましょう。また、時間外労働には割増賃金が発生します。
なお、36協定はすべての従業員と締結できるわけではありません。以下に該当する従業員は時間外労働が認められていないため、36協定を締結することができません。
- 18歳未満の従業員:法定労働時間を超える労働・深夜労働・休日労働は原則禁止
- 妊産婦の従業員:妊娠中、または出産後1年未満の労働者は、法定労働時間を超える労働・深夜労働・休日労働は原則禁止(従業員からの請求があった場合)
- 育児・介護中の従業員:小学校就学前の子どもがいる場合や介護が必要な家族が居る従業員が対象。時間外労働の制限を請求された場合は、1カ月で24時間、1年で150時間を越える残業や深夜労働は原則禁止(正常な運営を妨げない場合などの条件付き)
また、管理監督者も36協定の対象外です。一定の地位や権限を持つ従業員は、経営者と一体的な立場であることや、地位にふさわしい賃金を支給されていることなどを理由に、労働時間の上限管理の対象には含まれません。
2-1. 特別条項付き36協定における労働時間の上限
36協定の「月45時間、年360時間」を超えて労働させる場合は、労使間で特別条項付き36協定を締結する必要があります。
以前はこの特別条項を締結さえしていれば、「月100時間未満、年720時間以内」などの上限を超えても罰則を受けることがなく、実質無制限に労働させることが可能でした。しかし、法改正により、時間外労働の上限を超えた場合には、懲役や罰金が科されることになりました。
特別条項付き36協定における時間外労働の条件は、下記の通りです。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 2~6カ月の時間外労働と休⽇労働の合計が、平均月80時間以内
- 月45時間以上の残業は、年に6回以上おこなってはいけない
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回まで
企業は、罰則が科されることを避けるために労働時間の上限を守るわけではありません。長時間労働による従業員の過労死を防いだり、心身の健康を維持したりするために上限を守るのです。このことをもう一度認識し、改めて労働時間の上限を厳守する取り組みをおこないましょう。
2-2. 2024年4月以降は建設業者なども上限規制の対象
一部の業種においては、2023年まで上限規制の猶予期間が設けられていましたが、2024年4月以降は36協定を締結した場合の上限規制が適用されます。具体的には、以下のような業種・職種が該当するため注意しましょう。
- 建設事業
- 自動⾞運転の業務
- 医師
- ⿅児島県および沖縄県の砂糖製造業
他の業種と同様に、上限を超えないように業務を調整していきましょう。
2-3. 36協定を締結しても労働時間を減らす努力は必要
36協定を締結したからといって、上限まで労働させてよいということにはなりません。36協定を締結しても、労働時間を法定内に収めるよう努めましょう。
2018年9月に、厚生労働省は「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」として、以下の8つの項目を取り上げています。
- 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる
- 労働者の安全に配慮する
- 時間外労働・休日労働を行う業務を明確にする
- 特別な事情以外で限度時間を超えない
- 短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない
- 休日労働をできる限り少なくする
- 労働者の健康・福祉を確保する
- 限度時間が適用除外されている業務でも健康・福祉を確保するよう努める
36協定は止むを得ず締結するものであるという認識をもち、本当に必要なときにだけ法定外の労働をおこなわせるようにしましょう。
関連記事:労働時間の1日の上限は8時間!労働基準法に基づく時間外労働の上限設定方法
3. 労働時間の上限規制が設けられている理由

労働時間の上限規制が設けられている理由としては、従業員の健康やワークライフバランスを維持することなどが挙げられます。それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
3-1. 健康を維持するため
従業員の健康を維持するためには、長時間労働を抑制し、適度に休息を取ってもらうことが大切です。過度な残業や休日出勤が続くと、肉体的にも精神的にも疲労が蓄積してしまいます。その結果、病気になったり、怪我をしたりする可能性も高まるでしょう。
また、長時間労働はモチベーションや集中力の低下にもつながります。効率よく働いてもらうためにも、労働時間の上限規制を守ることが重要です。
3-2. 多様な働き方を選択できるようにするため
従業員が多様な働き方を選択できるようにすることも、労働時間の上限規制が設けられている理由のひとつです。少子高齢化による労働力不足を補うためには、多様な人材に活躍してもらうことが欠かせません。
しかし、育児や介護などの事情で、労働時間が長すぎると働けないという従業員もいます。そこで、労働時間を抑制することで、多様な人材が働けるような環境をつくる必要があるのです。
3-3. ワークライフバランスを改善するため
ワークライフバランスを改善するためにも長時間労働を抑制することが必要です。仕事の時間だけではなく、プライベートの時間を確保しなければ、従業員の生活を充実させることはできません。
仕事とプライベートを両立できないことを理由に、転職を考える従業員もいます。労働時間をしっかりと管理し、過剰な時間外労働が発生していないかチェックしましょう。
4. 時間外労働の上限規制に関する法改正や注意点

労働力人口が減少するなかで、長時間労働の割合が高い水準で推移しており、労働者がプライベートの時間も確保しつつ、健康を保ちながら働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。
その課題を解決するために、労働基準法の見直しが度々おこなわれているため、しっかりと把握しておかなければなりません。ここでは、直近でおこなわれている労働基準法の改正について解説します。
4-1. 中小企業も時間外労働の上限規制が導入
前章で紹介した特別条項付き36協定の上限規制は、2019年4月から大企業にのみ適用されていましたが、2020年4月から中小企業にも適用されました。
なお、中小企業は、中小企業基本法により明確に定義されています。下記の資本金額もしくは出資総額、常時使用従業員数のどちらかの基準を満たす場合に、中小企業とみなされます。
|
業種 |
資本金額もしくは出資総額 |
常時使用従業員数 |
|
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
4-2. 時間外労働の割増率が変更
2010年4月より、月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に変更されています。
ただし、中小企業には猶予期間が設けられており、2023年3月までであれば、月60時間以上の残業に対しても割増率25%の適用で問題ありませんでした。しかし、2023年4月に猶予期間は終了したので、中小企業も月60時間以上の時間外労働には割増率50%を適用する必要があります。
長時間労働を抑制するために、今後も法律が改正される可能性があります。将来の法改正に備えるためにも、現行法における残業の上限時間や法改正による上限規制の内容をよく理解しておく必要があります。当サイトでは、残業の上限時間についてわかりやすくまとめた資料を無料でお配りしています。こちらからダウンロードすることができますので、残業に関する法改正の理解にお役立てください。
4-3. 労働時間に対する適切な休憩時間の付与も忘れずに!
労働時間の上限だけでなく、休憩時間の管理も重要です。休憩時間とは、使用者の指揮命令にない時間のことで、仕事から完全に離れて心身を休めることを目的としています。
労働基準法では、休憩時間を以下のように定めています。
- 1日の労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合:最低でも45分以上の休憩を付与
- 1日の労働時間が8時間を超える場合:最低でも60分以上の休憩を付与
この規定を守っていれば、付与の方法は企業ごとに決めることが可能です。たとえば、1日の労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合でも休憩時間を60分にする、60分の休憩時間を分割して付与するなどでも問題ありません。
たとえ、法定労働時間の上限を守っていても、休憩時間を適切に付与しなければ法令違反となります。正しい休憩時間が付与されているか、この機会に確認しておきましょう。
4-4. 着替えの時間も労働時間の上限に含まれる
労働時間の上限を考える際、以下のような時間も労働時間に含まれるので注意しましょう。
- 始業前の準備や掃除・片付けなどの時間
- 着用がルール化されている制服や作業着への着替えの時間
- 強制参加の社内研修の受講時間
- 使用者の指示による、業務に必要な学習をおこなった時間
これらも含めて、労働時間の上限が守られていることを確認しましょう。また、労働時間の上限以内であっても、上記の時間は給与の支給対象になります。法定外労働時間に該当する場合には、割増計算も必要になるので注意が必要です。
4-5. 特別な勤務形態の労働時間の上限
労働時間の上限は、基本的に「1日8時間、週40時間」で考えます。しかし、特別な勤務形態の場合には、上限の考え方が変わります。特別な勤務形態の労働時間の上限の考え方は以下の通りです。
|
勤務形態の種類 |
労働時間の上限の考え方 |
|
変形労働時間制 |
|
|
フレックスタイム制 |
|
|
裁量労働制 |
|
5. 建設業の労働時間の上限に関する法改正

前述の通り、2024年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます。特別条項付き36協定を締結しても、「月100時間未満、年間720時間以内」が上限となるため注意しましょう。
5-1. 適用除外のケース
建設業の特性上、上限規制が除外されることがあります。それは、災害復旧や復興事業に従事する場合です。
災害復旧や復興事業に従事する場合、時間外労働と休日労働の合計について、以下2つの上限規制が適用されなくなります。
- 月100時間未満
- 2~6カ月の月平均が80時間以内
ただし、「年720時間以内」という上限は適用されるため注意が必要です。また、時間外労働に関する上限は緩和されても、割増賃金は通常通り発生するので注意しましょう。
関連記事:2024年から建設業の労働時間に上限規制が適用!今から準備できる対応とは?
6. 運送業の労働時間の上限に関する規定と法改正

2024年4月から、運送業の時間外労働の上限は「年960時間まで」となりました。「1カ月の残業時間が45時間を超えるのは、1年につき6カ月まで」という条件は適用されないので注意する必要があります。
また、運送業に属するトラックドライバーは36協定でなく、厚生労働省が定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、改善基準)によって、労働時間の上限規制が定められています。ここでは、この改善基準について解説します。
関連記事:運送業の労働時間の上限とは?2024年問題や厚生労働省の規定を詳しく紹介
参考:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準|厚生労働省
6-1. 1日・1カ月ごとの「拘束時間」上限
「拘束時間」とは始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休息時間を合わせた時間のことです。この拘束時間は、原則として1カ月につき293時間までと定められていますが、労使協定を締結している場合は、拘束時間を最大360時間まで延長できます。(1年につき、6カ月まで)
ただし、1年間の合計拘束時間が3516時間(293時間×12カ月)以内でなければならないという条件があるので注意しましょう。
1日の最大拘束時間は原則13時間です。しかし、勤務中に8時間の休息時間を取れば、最大16時間まで拘束しても良いと定められています。ただし、15時間以上の拘束時間を取っていいのは1週間に2度までと定められているため注意が必要です。
6-2. 1日の最大運転時間と連続運転時間
1日の最大運転時間は2日平均で9時間が限度です。また、1週間の最大運転時間は2週間ごとの平均で44時間が限度となっています。
連続運転時間に関しては最大4時間と定められています。
なお、運転開始から4時間以内、4時間経過した直後に30分以上の休憩を取らせることが必要です。1度に30分の休憩を取れない場合は、1回の休憩(10分以上)を取得させ、合計で30分以上にしなければなりません。
関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き
7. その他の業種・勤務形態別の労働時間の上限とは

ここからは、建設業・運送業以外の業種、勤務形態別に労働時間の上限を解説します。
7-1. タクシードライバーの労働時間の上限
長時間労働と聞くと、タクシードライバーをイメージする人も少なくないでしょう。タクシードライバーも、運送業と同様、厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によって労働時間の上限が決まっています。
タクシードライバーの場合は、日勤か隔日勤務によって労働時間の上限が異なります。以下の比較表で確認してみてください。
|
|
日勤 |
隔日勤務 |
|
拘束時間 |
|
|
|
休憩時間 |
|
|
|
労働時間 |
|
|
タクシードライバーについても、2024年4月より労働時間の上限規制が適用されているので、きちんと確認しておくことが大切です。
7-2. ダブルワークの労働時間の上限
従業員がダブルワークをしている場合、労働時間の上限はどのように扱えばよいのでしょうか。結論を言うと、労働時間は通算して考えなくてはなりません。
この場合も、従業員は「1日8時間、週40時間」までしか働くことはできません。そのため、従業員にダブルワーク先での労働時間を申告してもらって労働時間を把握する必要があります。
平日5日の勤務で週40時間に到達しているにも関わらず、ダブルワークでさらに仕事をした場合は、法令違反になります。また、ダブルワークの分は法定外労働時間に該当するため注意が必要です。ただし、36協定を締結していれば、1カ月45時間、1年360時間を上限とする時間外労働が可能になります。
なお、個人事業主やフリーランスは労働基準法の適用外となるので、労働時間の上限は適用されません。しかし、長時間労働による健康被害を防ぐために、労働時間の管理はきちんとおこないましょう。
8. 労働時間の上限を超過しないための対策

労働時間の上限を超過する事でさまざまなリスクが発生します。たとえば、長時間労働による過労死や睡眠不足による労働災害、残業代を巡る法的トラブルなどが挙げられます。これらのリスクを減らすためにも、労働時間の上限を超過しないことが大切です。
ここでは、労働時間の上限を超過しないための対策を解説します。
8-1. 勤怠管理システムによる労働時間の把握
勤怠管理システムの導入により、適切な労働時間の把握や残業代計算を効率化できます。労働時間の把握、とくに残業代計算は非常に複雑で、どうしても多くの時間を割くことになるでしょう。
勤怠管理システムを使うことにより、複雑な残業代計算を効率化するだけでなく、法改正にも自動で対応できるため、労働時間を削減することにつながります。
また、労働時間の上限を超える、もしくはそれに迫る従業員をアラームで通知する機能を備えたシステムもあります。全従業員の勤怠状況をリアルタイムで確認できるため、労働時間の上限を超過して働く従業員を確実に減らすことが可能です。
関連記事:労働時間の計算方法を例を用いて解説!計算を効率化する方法も紹介
8-2. 業務環境の整備
従業員の現在置かれている労働環境を正しく把握し、労働環境を整えることも大切です。
実際に、従業員に業務量や時間外労働についてヒアリングすることで、業務量が明らかに多く時間外労働を余儀なくされている部署や、深刻な人員不足により業務時間中に業務を終わらせられていない部署などを明らかにすることができます。
従業員へのヒアリングで得た情報を踏まえて、業務効率化に向けて施策を立てることが重要です。
8-3. 代替休暇の付与
代替休暇とは、1カ月に60時間以上の時間外労働が発生した場合、割増賃金の代わりに有給休暇を与える制度です。代替休暇の時間数は以下の計算式で算出できます。
代替休暇の時間数 = ( 1カ月の時間外労働時間 – 60 ) × 換算率
※換算率 = 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率 – 代替休暇取得時に支払うべき割増賃金率
2023年4月からは中小企業も代替休暇制度を適用することができます。ただし、代替休暇には取得期限があるなど、注意点も多いためきちんと仕組みを理解しておくことが大切です。
8-4. 上司の意識改革
労働時間の上限を守るためには、上司の意識改革を図ることも必要です。過度な残業が発生するような業務配分をしたり、残業をしている従業員を評価したりするような状態では、長時間労働を抑制することはできません。
従業員が健康的に長く働けるよう、長時間労働を抑制する取り組みを率先しておこなうべきでしょう。従業員が休みやすいよう、上司が早めに帰宅したり、有給休暇を積極的に取得したりすることも大切です。
9. 適切な労働時間の管理をおこない、上限規制に適応しましょう

本記事では、労働時間の上限、36協定、建設業と運送業に関する法改正に関して解説しました。長時間労働が状態化すると、肉体的にも精神的にも疲労が蓄積し、モチベーションや集中力が低下してしまうでしょう。労働時間の上限を理解して遵守することは、働きやすい労働環境づくりだけでなく、従業員の健康を守ることにもつながります。
勤怠システムの導入や従業員へのヒアリングを通して、正しい労働時間を把握し、労働時間の上限を超えないように配慮しましょう。このような取り組みが結果として従業員の健康を守り、業務効率や業績の向上などにつながるに違いありません。
この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。
そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。
法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。
働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひ「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。









