
労働基準法では賃金について明確に定義されています。また、賃金の支払い原則や未払い賃金に関する請求権の時効、賃金台帳の保管期間などについても細かく定められています。この記事では、労働基準法の賃金の定義や支払い方法、違反した場合の罰則について解説します。また、賃金に関連した労働基準法の条文も詳しく紹介しています。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法の賃金とは?

労働者を雇用する場合、労働基準法に基づき正しく賃金を支払う必要があります。ここでは、労働基準法に基づく賃金の定義について詳しく紹介します。
1-1. 賃金の定義
賃金とは、労働基準法第11条に基づき、労働の対償として使用者から労働者に支払われるすべてのものを指します。給料や賞与、手当、報酬など、名称が違っていても、労働の対価として支払われていれば、賃金に該当します。つまり、毎月支払われる給料だけでなく、労働協約や就業規則、労働契約などで支給条件があらかじめ明らかになっているものは賃金と定義されます。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
1-2. 賃金に含まれない金銭
労働の対価として支払われたかどうか簡単に判断するのは難しいです。次の3つの要件いずれかに該当するものは、賃金に該当しないとされています。
|
条件 |
説明 |
具体例 |
|
任意的恩恵的給付 |
恩恵的に支払われる給付 |
など |
|
福利厚生給付 |
福利厚生としての給付 |
など |
|
企業設備・業務費 |
業務に必要となる企業施設や費用 |
など |
また、賃金は使用者が労働者に支払う金銭なので、従業員が客から直接受け取るチップなどは賃金に含まれません。なお、建前上、見舞金としていても、労働の対価として支払われているものと判断されれば、賃金に含めなければなりません。このように、使用者から労働者に支給する金銭などは、一つひとつ内容を確認し、賃金に含めるかどうか慎重に判断することが大切です。
1-3. 所得税法の賃金との違い
労働基準法に基づく賃金は、所得税法では給与に含まれるものとしています。また、労働基準法が労働者の保護を目的としているのに対し、所得税法は個人の所得への適正かつ公平な課税を目的としているため、取り扱いが異なる点にも注意が必要です。
たとえば、役員への報酬は労働基準法上の賃金に含まれませんが、所得税法上の給与として課税されることになります。このように、労働基準法と所得税法それぞれの賃金の定義を正しく理解し、適切に会計処理をおこなうことが大切です。
(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2. 労働基準法による賃金の支払い方法
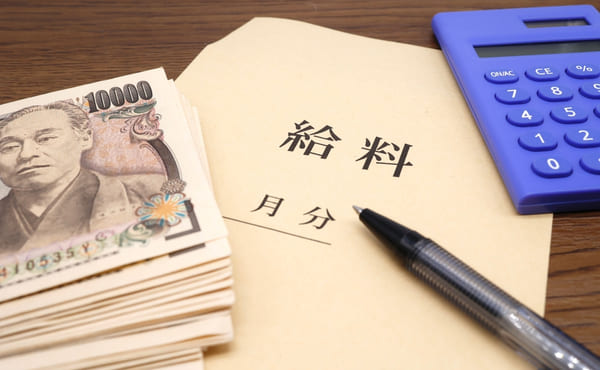
労働基準法第24条では、使用者が労働者に支払う賃金のルールを定めており、これを「賃金支払いの5原則」とよびます。ここでは、労働基準法で定められた5つの原則とその例外についてそれぞれ紹介します。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(省略)
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(省略)
2-1. 通貨払いの原則
賃金は、必ず通貨で支払われる必要があり、現物支給は禁止とされています。現物支給が禁止でなければ、定期券や自社の在庫商品などを給料代わりに渡す会社も出てきてしまうでしょう。それを防ぐため、賃金は日本の貨幣である日本銀行券で支払うことと決められているのです。
ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合は、通貨払いの原則の例外となります。また、労働者の同意を得て口座振込をしたり、退職手当を一定の要件を満たす小切手や郵便為替によって支払ったりすることは可能です。さらに、従業員の同意が得られれば、給与デジタル払いも認められています。
2-2. 全額払いの原則
賃金は原則、全額が支払われなければなりません。全額払いの原則を根拠に、賃金は1分単位で計算されなければならず、15分単位・30分単位で丸めることは原則として違法です。賃金が全額支払われなければ、労働者の生活は不安定になるでしょう。さらに、賃金の一部が支払われないせいで労働者が自由に退職できなくなるという問題もあります。そのため、会社の経営状況が厳しく全額払いが苦しい場合でも、分割払いをしてはいけないと決められています。
ただし、社会保険料や財形貯蓄金などを賃金から控除することは、法令に別段の定めがある場合であれば、全額払いの原則の例外となります。また、労使の自主的協定がある場合の親睦会費の控除なども、全額払いの原則の例外です。
関連記事:なぜ労働時間は1分単位で計算するのか?違法になる根拠や対策方法を解説!
2-3. 直接支払いの原則
賃金は、労働者に直接支払わなければならないと決められています。直接支払いの原則を定めることで、会社と労働者の間に第三者が入って賃金を搾取するような事態が起きるのを防いでいるのです。賃金を直接労働者本人に支払うのは、当たり前のことだと思われるかもしれません。しかし、高校生のアルバイト代が親の口座に振り込まれるなど、意外と直接支払いの原則が守られていない実態があります。
銀行口座を開設する手続きは、未成年者であっても親権者や法定代理人の手伝いがあれば可能です。さらに、口座の種類次第では未成年者本人だけで手続きができる場合もあります。口座開設が難しい場合は本人に給料の手渡しをすればよいので、本人以外に賃金を支払う正当な理由はほとんどありません。
ただし、労働者が入院などで欠勤しており、自分で給料を受け取れない場合に家族を使者として代わりに受け取らせることは可能です。また、賃金が国税徴収法や民事執行法に基づいて差し押さえられているケースでは、差し押さえた者に賃金を払っても労働基準法に違反しません。
2-4. 毎月払いの原則
賃金は、毎月1回以上支払われなければなりません。1カ月に2〜3回支払うケースは問題ありませんが、2カ月に1回などのケースは労働基準法違反になるので注意が必要です。ただし、退職金のように臨時に支払われる賃金や賞与など厚生労働省令によって定められている賃金の場合は、毎月払いの原則の例外となります。
2-5. 一定期日払いの原則
賃金は、毎月一定期日に支払わなければならないと労働基準法で定められています。賃金の支払い日を「毎月第4月曜日」などと決めてしまうと、月ごとに支払い日が変わってしまうので、避けなければなりません。毎月25日や毎月末日など、決められた日に賃金を支払うことで、労働者は光熱費の引き落としやローンの返済といった資金繰りの予定を立てやすくなります。ただし、毎月払いの原則と同様で、臨時に支払われる賃金や賞与などは一定期日に支払われなくても問題ありません。
関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介
3. 労働基準法の賃金に関係する条文

労働基準法には、さまざまな賃金に関係した条文があります。ここでは、労働基準法の賃金に関係する条文について詳しく紹介します。
3-1. 均等待遇(労基法第3条)
労働基準法第3条「均等待遇」に則り、国籍や信条、社会的身分を理由に、賃金を含む労働条件に関して差別的取り扱いをしてはいけません。たとえば、同じ仕事をしているのにもかかわらず、日本人労働者と外国人労働者で、賃金が変わるような制度を設計している場合、労働基準法違反になるので注意が必要です。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
3-2. 男女同一賃金の原則(労基法第4条)
労働基準法第4条「男女同一賃金の原則」により、女性だからという理由で賃金に関して差別的取り扱いをすることは認められていません。なお、女性を不利に扱う場合だけでなく、有利に扱う場合も、差別的取り扱いに含まれるので、正しく定義を押さえておきましょう。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
関連記事:労働基準法の第4条の意味や遵守するためのポイントを徹底解説
3-3. 平均賃金(労基法第12条)
休業手当や解雇予告手当、年次有給休暇手当などを算出するために、労働基準法第12条に基づき、平均賃金を計算する必要があります。平均賃金とは、直近3カ月に支払われた賃金の総額を、その間の総日数で除した賃金のことです。
平均賃金は、原則として、労働の対価として支払われたすべての賃金を含めて計算します。しかし、臨時に支払われる賃金(見舞金など)や、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・ボーナスなど)は、平均賃金の計算に含めないので注意しましょう。
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(省略)
関連記事:労働基準法の平均賃金とは?計算方法や端数処理、最低保障額をわかりやすく解説!
3-4. 労働条件の明示(労基法第15条)
労働基準法第15条に則り、使用者は労働契約を締結する際、労働者に労働条件通知書を交付し、賃金を含む労働条件を明示する義務があります。労働条件通知書だけでは、法律の要件を満たせても、労働者から労働条件に対して同意が得られたことを証明できないため、雇用契約書もあわせて交付するようにしましょう。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!
3-5. 非常時払(労基法第25条)
労働基準法第25条により、出産や病気、災害など非常事態があった場合に、労働者がその費用に充てるために事業主に請求をした場合、使用者は支払期日の前であっても、既に労働があった分に対しては賃金を支給しなければなりません。なお、非常時払いは、労働基準法施行規則第9条に基づき、労働者本人だけでなく、当該労働者の収入によって生計を維持する者に非常事態が起きた場合でも適用されます。
(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
3-6. 出来高払制の保障(労基法第27条)
出来高払制とは、労働者の成果や結果に応じて賃金が決まる制度のことです。労働基準法第27条に則り、出来高払制やその他の請負制で働く労働者であっても、労働時間に応じて一定以上の賃金を保障しなければなりません。そのため、完全出来高払制を採用している場合、労働基準法違反になるので注意が必要です。
(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
3-7. 最低賃金(労基法第28条)
労働基準法では最低賃金に関して、最低賃金法に従うと定義されています。最低賃金法第4条により、労働者には例外を除き、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。アルバイトやパート、派遣社員などの非正規社員であっても、最低賃金を下回る給料で働かせることはできません。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。2つ以上の最低賃金が適用される場合、最も高い最低賃金が採用されます。なお、最低賃金は、割増賃金や賞与、一部手当などを含めないで計算されるので注意しましょう。
(最低賃金)
第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。(省略)
関連記事:労働基準法における最低賃金とは?基準や罰則を徹底解説
3-8. 割増賃金(労基法第37条)
労働基準法第37条に則り、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働(時間外労働)や法定休日(週1日もしくは4週4日以上)の労働(休日労働)、深夜帯(原則22時~5時)の労働が生じた場合、それぞれ割増賃金を上乗せして賃金を支給する必要があります。なお、割増率は次の通りです。
- 時間外労働(月60時間以下):25%以上
- 時間外労働(月60時間超え):50%以上
- 休日労働:35%以上
- 深夜労働:25%以上
なお、時間外労働と深夜労働など、割増労働が重なった場合、それぞれの割増率を合算して割増賃金を計算することになります。また、時間外労働と休日労働をおこなわせる場合、労働基準法第36条に基づく36協定の締結・届出も必要なため留意しておきましょう。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
3-9. 就業規則(労基法第89条)
労働基準法第89条により、常時10人以上の従業員を雇用している使用者は、賃金の定めを含む就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。また、就業規則には、周知義務もあるため、きちんと労働基準法に基づき労働者に周知することが大切です。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(省略)
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4. 労働基準法の賃金に関する注意点やポイント

労働基準法の賃金の決定や計算、支払いには多くの気を付けるべき点があります。ここでは、労働基準法の賃金に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。
4-1. 同一労働同一賃金を遵守する
「同じ仕事をしているのであれば同一の水準の賃金が支給されるべき」という同一労働同一賃金の考え方が一般的になりつつあります。パートタイム労働法第8条でも、短時間労働者(パートやアルバイトなど)や有期雇用労働者(契約社員など)の賃金や手当といった待遇について、仕事の内容や配置の変更範囲などを総合的に考慮し、通常の労働者と比較して不合理な待遇差を設けることは認められていないため注意が必要です。
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
4-2. 賃金を正しく支払わなければ罰則がある
労働基準法には、懲役や罰金といった罰則規定も定められています。正しく賃金を計算し、支払わない場合、賃金支払いの5原則に違反することとなり、労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金のペナルティを受ける可能性があります。
また、最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、最低賃金法に基づき罰則が課せられる恐れもあります。さらに、法律違反による未払い賃金が労働者から請求されれば、使用者はこれに応じなければならないので注意が必要です。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第二十三条から第二十七条まで、(省略)の規定に違反した者
4-3. 賃金請求権の時効は5年に延長されている
労働基準法第115条に則り、賃金請求権の時効は、これを行使できる時から5年間とされています。2020年4月1日に施行された改正労働基準法では、2年から5年に消滅時効期間が延長されています。ただし、当面の間は経過措置により、5年間でなく、3年間が適用されるので注意しましょう。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間(省略)
○ 改正法の施行日以後、賃金請求権の消滅時効期間は、現行の2年から5年に延長されます。ただし、経過措置として、当分の間は3年が適用されます。
5. 労働基準法の賃金に関連したよくある質問

ここでは、労働基準法の賃金に関連したよくある質問への回答を紹介します。
5-1. 通勤手当は賃金に含まれる?
通勤手当も、労働の対価として支払われるため、労働基準法の賃金に該当します。ただし、業務で必要となる旅費を実費精算した場合、その金銭は賃金に該当しません。また、割増賃金の基礎となる賃金や、最低賃金など、通勤手当を含めないで計算するケースもあります。さらに、所得税については、一定限度額までであれば非課税扱いになるので注意しましょう。
通勤手当について
・通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されている。
関連記事:労働基準法には通勤手当の規定はある?距離の基準も解説
5-2. 賃金台帳の保管期間は?
労働基準法第108条に則り、使用者は賃金台帳を作成する義務があります。また、労働基準法第109条により、賃金台帳は5年間の保存が義務付けられています。ただし、労働基準法第109条には経過措置があり、当分の間は3年間の保存でも問題ありません。しかし、いつ経過措置が終了するかは未定なため、できる限り5年間保存しておくようにしましょう。なお、賃金台帳の保管期間の起算日は、最後の記入をした日であり、作成日ではないので注意が必要です。
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
関連記事:労働基準法第109条の重要な書類の保存期間は何年?法改正や経過措置、違反した場合の罰則を解説!
5-3. 賃金に端数が出た場合の処理方法は?
1カ月の賃金を計算してみた結果、100円未満の端数が生じた場合、50円未満切り捨て、50円以上切り上げをして支払うことが認められています。また、1,000円未満の端数が発生した場合、翌月に繰り越して支払うことも可能です。他にも、割増賃金を計算する場合、一定の端数処理が認められているので、きちんと確認しておきましょう。
- 1か⽉の賃⾦⽀払額(賃⾦の⼀部を控除して⽀払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が⽣じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
- 1か⽉の賃⾦⽀払額に⽣じた1,000円未満の端数を翌⽉の賃⾦⽀払日に繰り越して支払うこと。
関連記事:給与計算の端数処理(小数点以下)の方法とは?注意点も紹介
6. 労働基準法に基づき賃金を正しく支払おう!

労働基準法に基づく賃金とは、労働の対償として支払われるすべてのものと定義されています。そのため、給与だけでなく、手当や賞与なども、労働の対価として支給されているのであれば、賃金に含める必要があります。また、労働基準法では、賃金の支払い方法についても細かく規定されています。労働基準法に違反すると、罰金などの罰則が課せられる恐れもあるので、正しく賃金を計算し、労働者に支払うようにしましょう。
労働基準法総まとめBOOK









