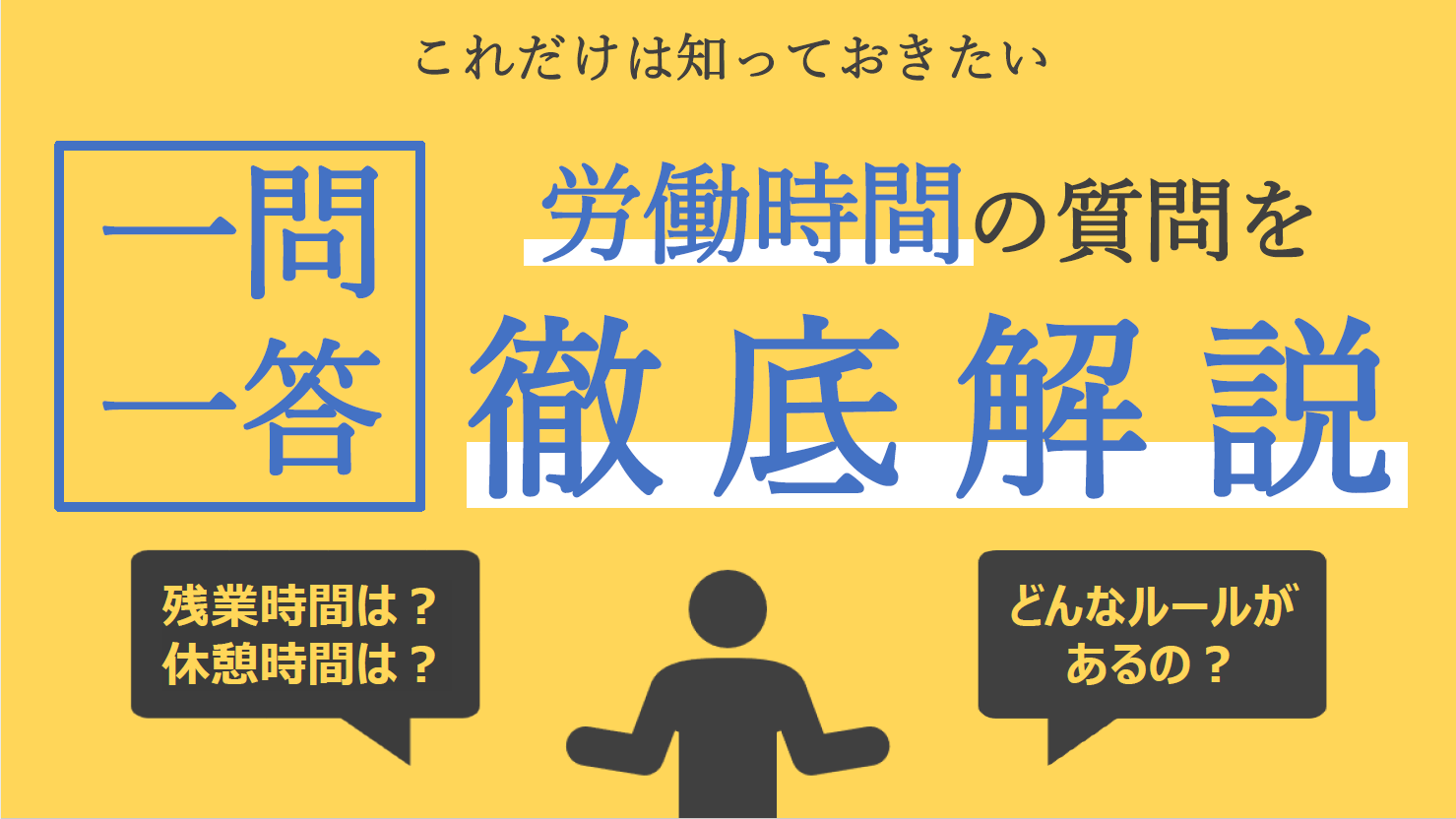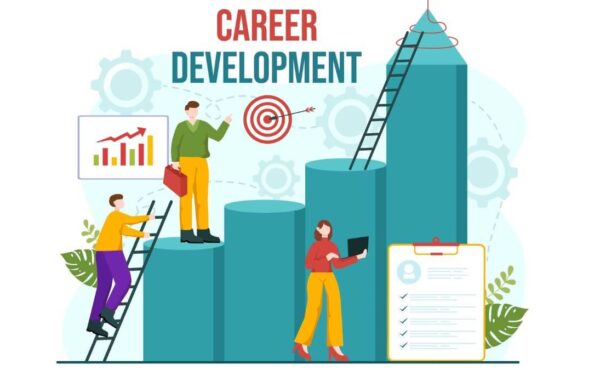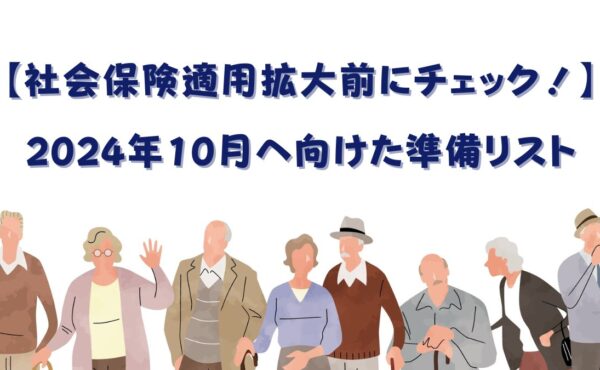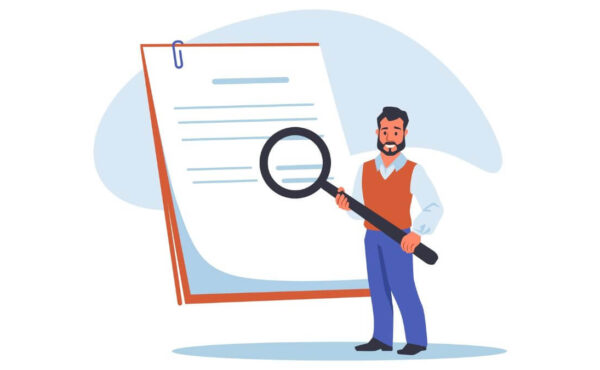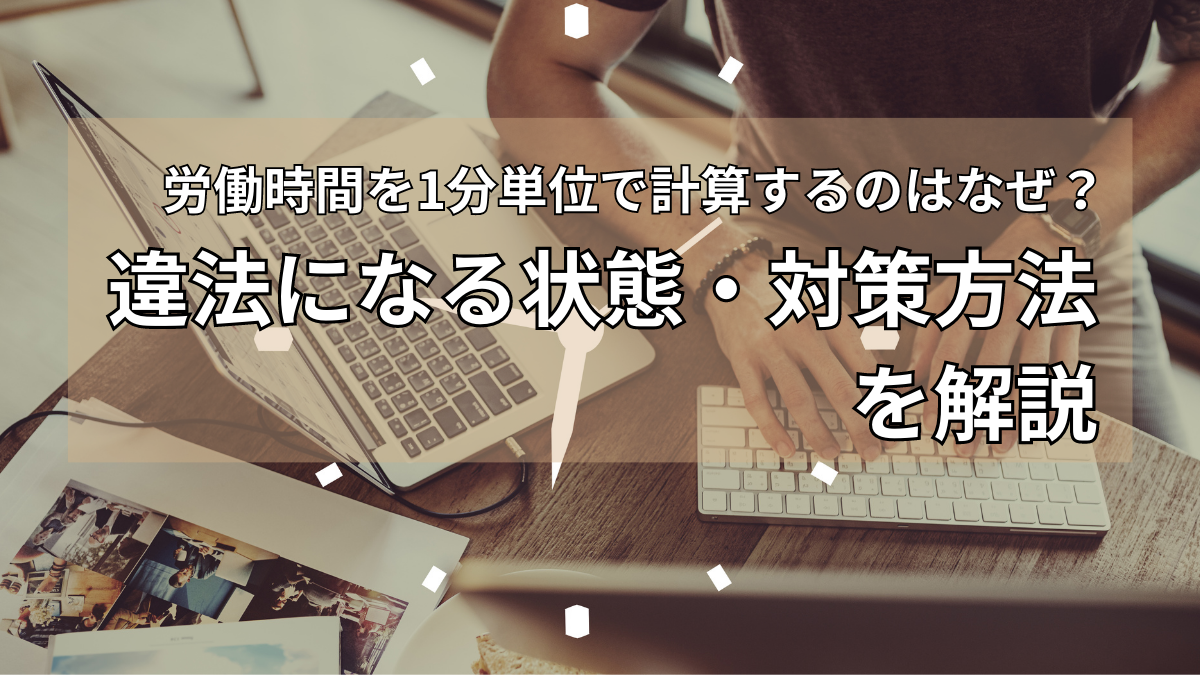
時間外労働を15分や30分単位に区切り、労働時間を切り捨てて賃金計算するのは、違法とされ、処罰される可能性があります。厚生労働省により、労働時間は原則1分単位で計算しなくてはいけないと定められているからです。
残業時間の取り扱いを誤ると罰則が科せられる可能性があるため、適切な労働時間管理をおこなう必要があります。そのため、労働時間の計算の考え方についてしっかり押さえておきましょう。
本記事では、労働時間を1分単位で計算する理由や、例外的に認められる端数処理、時間外労働手当の計算方法もあわせて解説します。
労働時間でよくある質問を徹底解説
この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。
ジンジャーは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をご参考にください。
目次
1. なぜ労働時間は1分単位で計算するのか?

労働時間を1分単位で計算する理由については、賃金計算と深い関係があります。
従業員へ労働の対価として支払う賃金は、原則「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなくてはならない」と労働基準法第24条第1項において定められています(賃金全額払いの原則)。
法律の条文内には「1分単位で計算しなくてはいけない」と明確には記載はされていません。
しかし、条文内にある「全額を支払う」が、たとえ労働時間が1分単位であっても、切り捨てることは認められないと解釈されるのです。
ただし、従業員にとって有利となる条件であれば、切り捨てや切り上げは認められます。
たとえば、出勤時間を切り捨てたり、退勤時間を切り上げたりすることは従業員にとって有利となるため、問題ありません。一方、出勤時間を切り上げたり、退勤時間を切り捨てたりすることは、支払われる給与が実労働時間分よりも短くなってしまうため、違法となる可能性が高いです。
2. 残業代の切り捨ては違法になる

残業時間を15分や30分単位で区切って、賃金計算している会社も少なくないでしょう。
15分未満や30分未満を不当に切り捨てて残業代を計算するのは、先述で解説した通り「賃金全額払い」の原則に反することになり、労働基準法第24条の違反となります。残業も労働時間であるため、1分単位で計算して賃金を全額支給しなければなりません。
ただし、15分を30分、30分を1時間といったように、時間を切り上げて賃金計算するのは、労働者にとって有利となりますので違法とはなりません。
2-1. 1か月単位で30分で区切る場合は例外として認められる
残業時間も原則としては1分単位で計算しなくてはなりません。
ただし、1か月の残業代を通算して計算している場合は、厚生労働省労働基準局による通達(昭和63年3月14日基発第150号)に基づいて、次の通り端数処理することができます。
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
つまり、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てして賃金計算をおこなって良いということになります。たとえば、1か月の残業時間の合計が20時間25分であった場合、30分未満の端数である25分は切り捨てして、20時間として賃金計算することができます。
ただし、切り捨てだけおこなうのは原則認められていないため、仮に1か月の残業時間の合計が20時間31分であった場合は、30分以上を切り上げて21時間としなくてはいけません。
2-2. 違反に対する罰則内容とは
不当に労働時間を切り捨ててしまった場合、賃金を全額支払うことができないため、賃金全額払いの原則を定めた労働基準法第24条の違反となります。
この場合、下記の罰則が下される可能性があります。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)第二十三条から第二十七条まで(省略)
使用者は労働者に不利益を被るような処理をおこなうことは許されず、実労働時間分の適切な賃金を支払う必要があります。
3. ノーワーク・ノーペイの原則とは

ノーワーク・ノーペイの原則とは、労働者が労働を提供していない場合は、使用者は労務を提供されていない部分について、賃金を支払わなくても良いということを意味しています。つまり、従業員が働いていない時間については、会社は賃金を支払う必要がないということです。
ノーワーク・ノーペイの原則については、次の民法第624条が根拠とされています。
民法第624条
労働者は、その約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
ノーワーク・ノーペイの原則が適用とされるケースには以下のものがあります。
- 遅刻
- 早退
- 欠勤
- 介護休業
- 産前産後休業
- 育児休暇・育児休業
- 自然災害等の不可抗力による休業
- 公民権行使の期間 など
上述のケースのような場合では、ノーワーク・ノーペイの原則によって1分単位で賃金カットすることができます。たとえば、所定労働時間が8時間である社員が5分の早退をした場合、7時間55分の賃金を支払えば良いとされます。
4. 時間外労働手当を計算する上での注意点

残業代を計算する際は、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、とくに注意すべき点を2つ紹介します。
4-1. 法定外残業の場合は割増率を乗じて計算する
残業には2種類があり、「法定外残業」と「法定内残業」があります。
法定外残業は、法定労働時間「1日8時間、週40時間」を超えて残業した時間のことです。法定外残業の場合は、次の割増率を乗じて割増賃金で支払わなくてはいけません。
- 1日8時間または週40時間を超える労働(時間外労働)…25%以上の割増賃金
- 22時~翌5時までの労働(深夜労働)…25%以上の割増賃金
- 法定休日の労働(休日労働)…35%以上の割増賃金
- 1か月に60時間を超える残業…50%以上の割増賃金
たとえば、9時〜18時(1時間休憩含む)勤務の社員が20時まで残業した場合、法定外残業は2時間であるため、2時間×1.25の割増賃金を支払わなくてはいけません。
また、23時まで残業した場合では法定外残業は5時間ですが、22時〜23時までの1時間は深夜手当の対象となるため、4時間×1.25,1時間×1.5の割増賃金となります。
一方、法定内残業は、法定労働時間内で行った残業になります。法定内残業の場合は、割増賃金を支払わなくても良く、通常賃金で問題ありません。
たとえば、9時~13時勤務のパートが15時まで残業したとしても、労働時間が6時間となり法定労働時間内におさまりますので、割増賃金の支払いは不要です。
4-2. 50銭未満と以上の処理
1時間当たりの割増賃金を計算した際に端数がでてしまった場合は、次のように処理することが認められています。
- 50銭以上1円未満は1円に切り上げ
- 50銭未満は切り捨て
たとえば、1時間あたりの割増賃金が1,100.4円の場合は、50銭未満の0.4円を切り捨てし1,100円とすることができます。逆に、1時間あたりの割増賃金が1,100.8円の場合は、50銭以上の0.8円を切り上げて1,101円とすることができます。
4-3. 1か月での賃金支払額は100円単位で四捨五入できる
もし1か月の賃金の合計額に100円未満の端数が生じた場合には、50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は切り上げする処理が認められます。
ただし本処理をおこなうには、就業規則にてあらかじめ記す必要があり、記載がない場合には認められません。
4-4. 1ヶ月の賃金支払額に1,000円未満の端数が生じた場合の繰越し
1か月の賃金支払いに、1,000円未満の端数が生じた場合は、もちろん切り捨ては認められません。ただし1,000円未満の端数を翌月の賃金支払い時に繰越すことは可能です。
翌月以降への繰越は認められておらず、こちらも繰越処理をおこなうためには就業規則への記載が必要となります。
5. 1分単位で正確に労働時間を管理するための対策
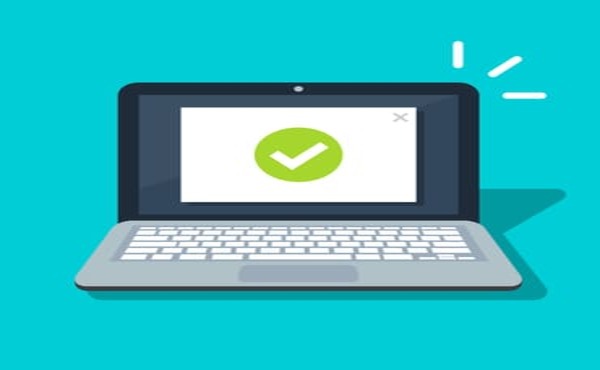
このように労働者の労働時間には、1分単位で賃金を支払うことが労働基準法により定められています。そして不当なまるめ処理や端数計算により労働者に不利益が被った場合には、罰則対象となる可能性があるため、企業では対策が不可欠です。
ここからは、1分単位で労働時間を管理するための対策方法を解説します。
5-1. タイムレコーダーはデスク付近に設置しよう
タイムカードにて勤怠管理をしている場合、従業員の打刻時間が実労働時間とズレてしまうこと、打刻漏れが頻繁に起きることにより労働時間が把握できない、などといった問題点が生じることがあります。
このような場合は、打刻機の場所が遠かったり、目につきにくい場所に置かれていることが多いです。
タイムレコーダーなどの打刻機は、目のつきやすいデスク付近に設置しましょう。
5-2. 1分単位で給与の自動計算までできる勤怠管理システムを導入する
従業員の打刻漏れの多さや、1分単位で正確な勤怠管理に課題を感じる場合は、勤怠管理システムを導入することが最も効果的です。またクラウド型のサービスであれば、労働基準法の改正にも自動で対応するため、給与計算で無自覚に法律を侵す心配もなくなります。
6. 労働時間は原則1分単位で計算!端数の切り捨てはNGなので要注意

労働時間は、労働基準法第24条の全額支払いの原則に従って、1分単位で計算するのが決まりとなっています。労働時間を切り捨てて計算するのは法律違反となり、罰則が科せられますので注意しましょう。
ただし、1か月で残業代を通算する場合はこの限りではありません。遅刻や早退など、従業員が労働に服していない時間については、ノーワーク・ノーペイの原則が適用され、賃金から控除することができます。
ただし、この場合も、1分単位で計算して労働時間から控除するのが決まりとなっています。
労働時間でよくある質問を徹底解説
この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。
ジンジャーは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をご参考にください。