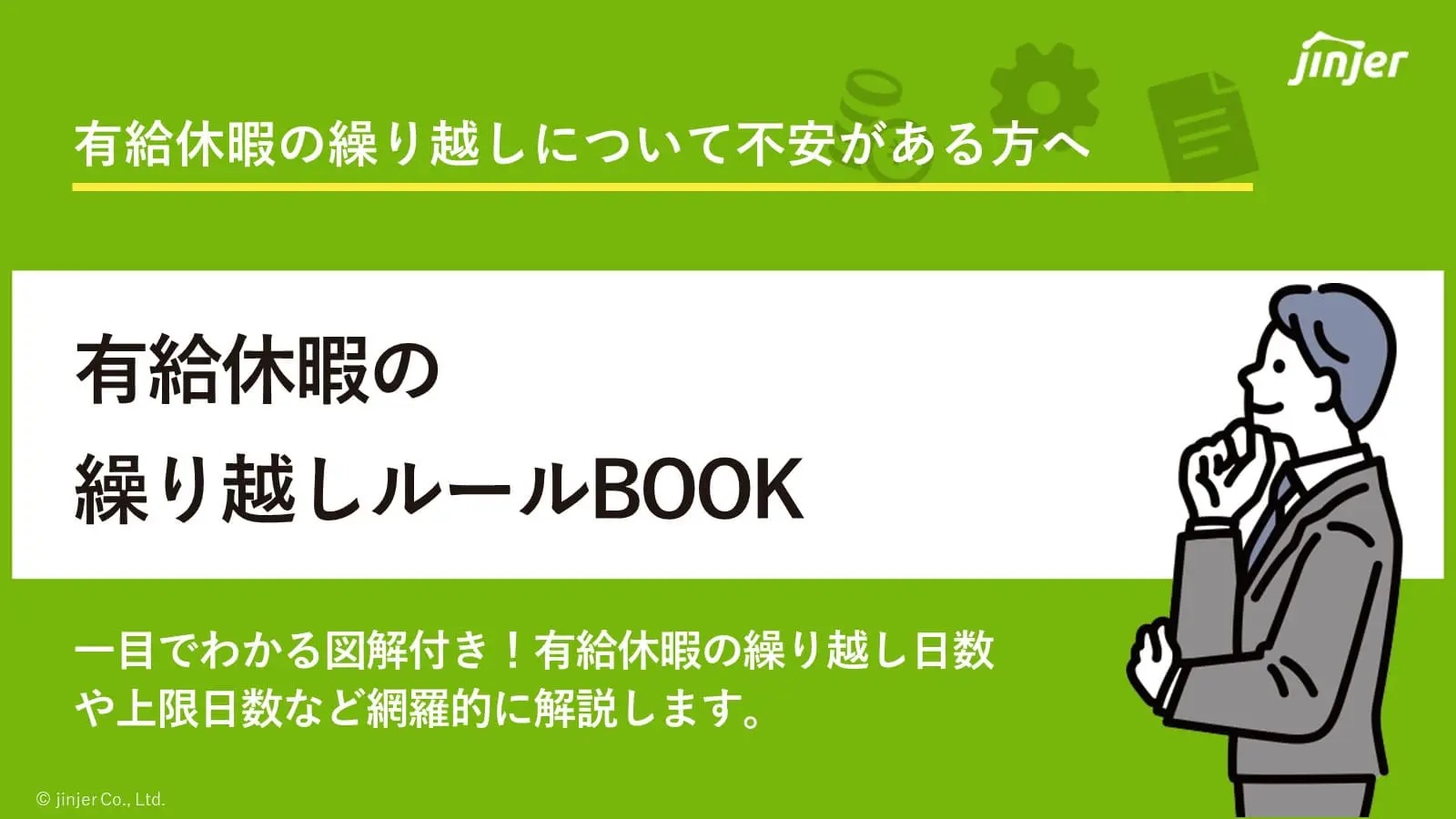年次有給休暇は、一定の基準を満たした全ての労働者に一定日数が付与されます。しかし、1年間で付与された全ての有給休暇を消化できないこともあるでしょう。
残った有給休暇は、翌年度に繰越することができます。この記事では有給休暇の繰越についてわかりやすく解説しますので、ぜひ理解を深めておきましょう。
関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説
「有給は何日まで繰り越せるの?」
「有給を保有できる日数は最大何日?」
「有給を消化しないとどうなるの?」
など有給の繰越に関して、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「一目でわかる図解付き!わかりやすい有給休暇の繰り越しルールBOOK」を無料配布しております。
本資料では有給の繰り越しの仕組みはもちろん、有給の最大保有日数や消滅してしまう時効など有給に関して網羅的に解説しております。また有給の繰り越しについてよくある質問とその答えもまとめているので、この資料一つで有給の繰り越しに関する疑問をすぐ解決できる大変わかりやすい資料になっております。
有給を正しく運用したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 労働基準法が定める有給休暇の付与条件や付与日数
 有給休暇の繰越について理解するためには、まず法律で定められている有給休暇の付与条件や日数を把握する必要があります。ここでは、有給休暇の付与条件や付与日数について解説します。
有給休暇の繰越について理解するためには、まず法律で定められている有給休暇の付与条件や日数を把握する必要があります。ここでは、有給休暇の付与条件や付与日数について解説します。
1-1. 法律で定められた有給休暇の付与条件
労働基準法で定められた有給休暇の付与条件は以下の通りです。
- 雇入れの日(採用日)から起算して労働者が6カ月継続して勤務している
- 全労働日の出勤率が8割以上
労働日とは、法定休日と所定休日を除いた日です。出勤率は「出勤日 ÷ 労働日」で算出し、業務で発生した怪我や病気を理由とする休業期間、育児・介護休業の期間は全て出勤日としてカウントします。
上記2つの付与条件を満たしていれば、正社員のみならず、パート・アルバイトなどの非正規雇用者にも有給休暇を付与しなければなりません。
参考:年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
1-2. 法律で定められた有給休暇の付与日数
労働基準法で定められたフルタイム労働者に対する有給休暇の付与日数は以下の通りです。
<フルタイム労働者の有給休暇の付与日数>
|
継続勤務年数 |
半年 |
1年半 |
2年半 |
3年半 |
4年半 |
5年半 |
6年半 |
|
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
なお、勤務年数6年半以上のフルタイム労働者には、1年ごとに20日の有給休暇が付与されます。
パート・アルバイトなどの短時間労働者は週所定労働日数に応じて、以下のように日数が比例付与されます。
<パート・アルバイトなどの短時間労働者の有給休暇の付与日数>
|
週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
継続勤続年数 |
|||||||
|
半年 |
1年半 |
2年半 |
3年半 |
4年半 |
5年半 |
6年半 |
|||
|
付与日数 |
4日 |
169日~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
|
3日 |
168日~121日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
|
|
2日 |
120日~73日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
|
|
1日 |
48日~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
|
使用者は最低限この日数を労働者に付与する義務があり、付与せずにいると労働基準法に違反することになります。罰則が与えられる恐れもあるため注意しましょう。
関連記事:【図解】有給休暇の付与日数と付与のポイントをわかりやすく解説!
1-3. 会社独自の有給休暇を設けることも可能
労働基準法はあくまで使用者が守るべき最低限の義務です。そのため、最低限の有給日数以上の休暇を会社独自で付与することには何の問題もありません。また、有給休暇の付与時期を早めることも可能です。
しかし、有給休暇を前倒して付与した場合、最初に有給休暇を付与した日が基準日となり、労働者が勤続した場合、1年ごとにその基準日に有給休暇を付与する必要があります。なお、1回目の有給休暇を付与した日のことを基準日といいます。
このように会社独自の有給休暇制度を設けることで、従業員のモチベーション向上が期待できるでしょう。 企業が独自に有給休暇を設けることは、特に競争が激しい業界では、従業員の確保や定着率向上に寄与する重要な要素となります。 ただし、独自の制度を導入する際には、必ず労働基準法の規定や労働者の権利を侵害しないように注意が必要です。
関連記事:【有給休暇】徹底ガイド!付与日数・年5日取得義務化・法律と罰則を解説
2. 有給休暇の繰越(繰り越し)とは
 有給休暇の繰越とは、付与された有給休暇を従業員が消化できなかった際に、翌年度に残日数を繰越することです。有給休暇には消滅時効(有効期限)があるため、繰り越す際には注意が必要です。
有給休暇の繰越とは、付与された有給休暇を従業員が消化できなかった際に、翌年度に残日数を繰越することです。有給休暇には消滅時効(有効期限)があるため、繰り越す際には注意が必要です。
ここでは、有給休暇の繰り越しについて詳しく紹介します。
2-1. 有給休暇の繰越は2年以内なら可能
有給休暇の有効期限は付与されてから2年間です。労働基準法第115条では、年次有給休暇の請求権は2年で消滅すると定められているため、2年以内であれば、有給休暇は繰越することが可能です。
たとえば、その年に15日の有給休暇が付与され、5日消化したとします。この場合、10日の有給休暇が翌年に繰り越されます。この10日の有給休暇を翌年消化しなければ、消滅してしまうので注意が必要です。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
関連記事:有給休暇の有効期限とは?基準日の統一や繰越のルールについて解説!
2-2. 有給休暇の繰越をしない場合は違法になる
有給休暇を繰越なしに定めると違法になります。
労働基準法で年次有給休暇の請求権が定められており、有給休暇を取得することは労働者の権利であるため、有給休暇を全て消化できなかった場合、残日数を翌年度に繰越さなければ違法となります。会社の就業規則に1年間で有給休暇が消滅するなどといった記載があったとしても、それは法律に反しているため、無効となります。
3. 有給休暇の繰越日数の上限について
 ここでは、有給休暇の繰越日数の上限について解説します。
ここでは、有給休暇の繰越日数の上限について解説します。
3-1. 有給休暇の繰越日数に上限はある?
有給休暇の繰越日数に上限はありません。付与されてから1年のうちに取得できなかった年次有給休暇は、全て翌年に繰り越すことができます。しかし、有給休暇には2年間の期限があるため、有給休暇を繰越できる日数は、その年に付与された有給休暇と同じ日数です。
勤続年数によって有給休暇の付与日数が異なるため、繰越日数の上限も異なります。
1年に付与される有給休暇日数は20日なので、繰越できる日数は最大で20日となります。
2年間の保有期限を過ぎた有給休暇は消滅してしまうため注意が必要です。繰越には期限があるので、企業は従業員が有給休暇をため過ぎていないか随時確認する必要があります。
3-2. 有給休暇の最大保有日数は?
法定通りに付与した場合、有給休暇の最大保有日数は35日です。
有給休暇を法定通りに付与した場合、1年につき最大で20日間付与できます。翌年に繰り越しをおこない、翌年も20日間を付与すれば、最大で40日間の有給休暇を保有できると考えられるかもしれません。しかし、法定の有給休暇取得義務によって、年間5日分の有給休暇は必ず取得する必要があります。
翌々年も20日間を付与すれば最大で60日間になるかというと、有給休暇には2年間の保有期限がありそれを超えたものは消滅するため、有給休暇の最大保有日数はやはり35日になります。
3-3. パート・アルバイトも有給休暇を繰越できる!
有給休暇が付与されているパートやアルバイト従業員も繰越が可能です。
パートやアルバイトは正社員や契約社員などのフルタイム労働者に比べ勤務日数・時間が少ないため、付与される有給休暇日数は少なくなります。しかし、付与日数以外のルールは同じなので、有給休暇を繰越することができます。
逆に、雇用形態の違いから繰越を認めない場合は違法となるので注意が必要です。
関連記事:パート・アルバイトに有給休暇を付与すべき?ルールをわかりやすく解説【事例付き】
4. 有給休暇繰越のわかりやすい計算方法 ~事例も紹介~
 有給休暇の繰越と消滅について、具体的な例を挙げてくわしく説明します。毎年20日間の有給休暇を付与されるケースを例に見てみましょう。
有給休暇の繰越と消滅について、具体的な例を挙げてくわしく説明します。毎年20日間の有給休暇を付与されるケースを例に見てみましょう。
関連記事:有給の消滅期限はいつ?計算方法や時効・買取をわかりやすく解説
4-1. 付与と繰越の例(1年目)
ある従業員に、今年度20日間の有給休暇が付与され、そのうち10日を取得したとします。前年に付与された有給休暇は前年のうちにすべて取得済みなので、消滅する有給休暇はありません。
この場合、新規に付与された20日から取得した10日を引くと、残りの有給休暇は10日となります。この10日は翌年度に繰越され、次年度の有給休暇と合算されることになります。
新規付与日数:20日
― 取得日数:10日
= 翌年度繰越日数:10日
4-2. 付与と繰越の例(2年目)
前年に未取得だった10日を繰り越し、当年度に新たに20日が付与されました。この場合の計算は以下の通りです。
+新規付与日数:20日
=合計30日
今年度の保有日数は、繰越と新規付与を合計すると30日になります。一般的には、前年度からの繰越日数から消化するため、この年には7日の有給休暇を取得したとすると、残りの有給は23日となります。
合計30日
― 取得日数:7日
=残日数:23日
ただし、残った3日は時効により消滅しますので、翌年度に繰り越せるのは20日になります。
このように、前年度からの繰越と新規付与の取り扱いは重要です。有給休暇は原則として古いものから消化されるため、特に、従業員には今年度付与分と前年度付与分を明確に分けて通知することが望まれます。
4-3. 付与と繰越の例(3年目)
3年目には、前年に繰り越された20日と新たに付与された20日、合わせて40日間の有給休暇が保有されている状態です。
+新規付与日数:20日
=合計40日
5. 有給休暇の繰越・付与に関する注意点

有給休暇の繰越をおこなう場合、注意点がいくつかあります。ここでは、有給休暇の繰越において押さえておきたいポイントを詳しく紹介します。
5-1. 繰越された有給と新規付与された有給で先に消化されるのは?
有給休暇は、原則として古いものから消化されます。そのため、繰越された有給と新規付与された有給とでは、繰越された有給から先に消化するのが基本です。
ただし、会社独自のルールで有給休暇は当年分から消化すると定められている場合は、この限りではありません。この場合は、新規付与された有給から消化することを、就業規則にきちんと明記する必要があります。
5-2. 有給休暇の買取はNG?
有給休暇は、労働者のリフレッシュのために設けられている制度です。そのため、有給休暇の買取は、原則として認められていません。しかし、下記の3つのケースの場合、労働者が不利とならないのので、有給休暇の買取が認められています。
- 法律で定められた日数を超える有給休暇
- 退職時に消化しきれていない有給休暇
- 消滅時効となった有給休暇
繰越された有給休暇が消化されないからといって、使用者が強制的に有給休暇を買い取るのはNGです。ただし、有効期限が切れてしまった有効休暇の買取は例外的に認められています。有給休暇の取得に関しては、労働者が不利益を被らないよう、適切な対応をとることが大切です。
関連記事:有給休暇の買取は違法?退職者の対応や計算方法、デメリットを解説!
5-3. 有給休暇の基準日は会社ごとに異なる
有給休暇の基準日は会社によって異なります。基準日とは、有給休暇を付与した日のことです。雇入れから6カ月経過したタイミングで最初の有給休暇が発生するため、その日を基準日とするのが基本ですが、従業員によって基準日が異なると管理が煩雑なってしまいます。
そこで従業員全員に対して2回目以降の付与日は統一するなど、基準日を前倒しているケースもあります。基準日の決め方によって、繰越や消滅のタイミングが異なるため注意しましょう。
5-4. 有給休暇の年5日の取得義務では繰り越し分から取得してよい?
年次有給休暇を取得する際は、原則として古いものから消化するので、繰越分から消化します。取得義務が定められている年5日の有給休暇には、繰越分の有給休暇についても含まれます。そのため、繰り越しされた有給休暇を5日消化することで、有給休暇の年5日取得義務化に対応することが可能です。
6. 有給休暇の繰越について企業がおこなうべき対応

有給休暇を正しく繰越するためには、従業員ごとの残日数をしっかりと管理し、繰越処理を忘れずにおこなうことが大切です。また、繰越をする前に取得を促すことも忘れないようにしましょう。
以下、有給休暇の繰越について企業がおこなうべき対応を紹介します。
6-1. 有給休暇の日数をしっかりと管理する
企業は、有給休暇の付与日数や取得日数、残日数などを従業員ごとに管理しなければなりません。繰越を正しくおこなうためには、その有給休暇が前年から繰越したものか、新たに付与したものかを把握しておくことも大切です。
従業員数が多い企業の場合、管理が複雑になり、ヒューマンエラーが発生する可能性もあるため、勤怠管理システムなどを導入して業務を効率化するとよいでしょう。
6-2. 繰越処理を忘れずにおこなう
消化しきれなかった有給休暇については、翌年への繰越処理をおこないましょう。正しく繰越処理をおこなわないと、法律に違反してしまいます。
基準日や消滅時効を確認したうえで、繰越処理を進めることが大切です。勤怠管理システムを活用すれば、有給休暇の付与や繰越を自動化できるため、手間を省きたい場合は導入を検討してみてください。
6-3. 有給休暇の取得を促す
有給休暇の繰越は可能ですが、できる限り消化させるようにしましょう。有給休暇は、従業員の心身の健康を維持するために重要です。
また、年10日以上の有給休暇が付与される従業員については、そのうち5日分を確実に取得させなければなりません。上司が率先して休むなど、有給休暇を取得しやすい環境を構築し、消化を促しましょう。
7. 有給休暇の繰越や計算を効率化するなら勤怠管理システムがおすすめ

紙やExcelで有給休暇の日数を管理している場合、年5日の有給休暇を取得していない従業員や、繰越された有給休暇の有効期限が切れてしまう従業員の管理が難しい場合もあります。有給休暇をきちんと管理できていないと、労働者の不満につながる可能性があります。場合によっては、労働基準法に違反して罰金や懲役といった罰則を受ける恐れがあるため注意しましょう。
有給休暇の管理を効率化したい場合、勤怠管理システムの導入がおすすめです。勤怠管理システムを活用すれば、従業員の情報を入力するだけで、自動で有給休暇の付与日数が計算されます。従業員が有給休暇を取得したら、自動で残日数や繰越日数も更新されるので、業務負担が減ります。また、法律の基準を満たしていない従業員にはアラート機能で有給休暇の取得を促すことも可能です。
このように、勤怠管理システムを活用すれば、有給休暇の管理を効率化することができます。複数のツールを比較して自社のニーズに合う勤怠管理システムを導入することが大切です。
関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介
8. 有給休暇の繰越や付与日数について理解しよう
 有給休暇は労働基準法によって労働者に認められた権利です。同時に使用者は労働者に有給休暇を付与する義務があります。使用者は、労働者の有給休暇の繰越や付与日数を正確に理解しておきましょう。
有給休暇は労働基準法によって労働者に認められた権利です。同時に使用者は労働者に有給休暇を付与する義務があります。使用者は、労働者の有給休暇の繰越や付与日数を正確に理解しておきましょう。
また2年以内であれば、有給休暇は繰り越すことができます。2年を超えてしまうと消滅するため、有給休暇は計画的に消化することが大切です。有給休暇の取得しやすさは、企業の労働環境を判断する重要な指標です。適切に有給休暇を管理し、従業員が有給休暇を取得しやすい労働環境を整えましょう。
「有給は何日まで繰り越せるの?」
「有給を保有できる日数は最大何日?」
「有給を消化しないとどうなるの?」
など有給の繰越に関して、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「一目でわかる図解付き!わかりやすい有給休暇の繰り越しルールBOOK」を無料配布しております。
本資料では有給の繰り越しの仕組みはもちろん、有給の最大保有日数や消滅してしまう時効など有給に関して網羅的に解説しております。また有給の繰り越しについてよくある質問とその答えもまとめているので、この資料一つで有給の繰り越しに関する疑問をすぐ解決できる大変わかりやすい資料になっております。
有給を正しく運用したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。