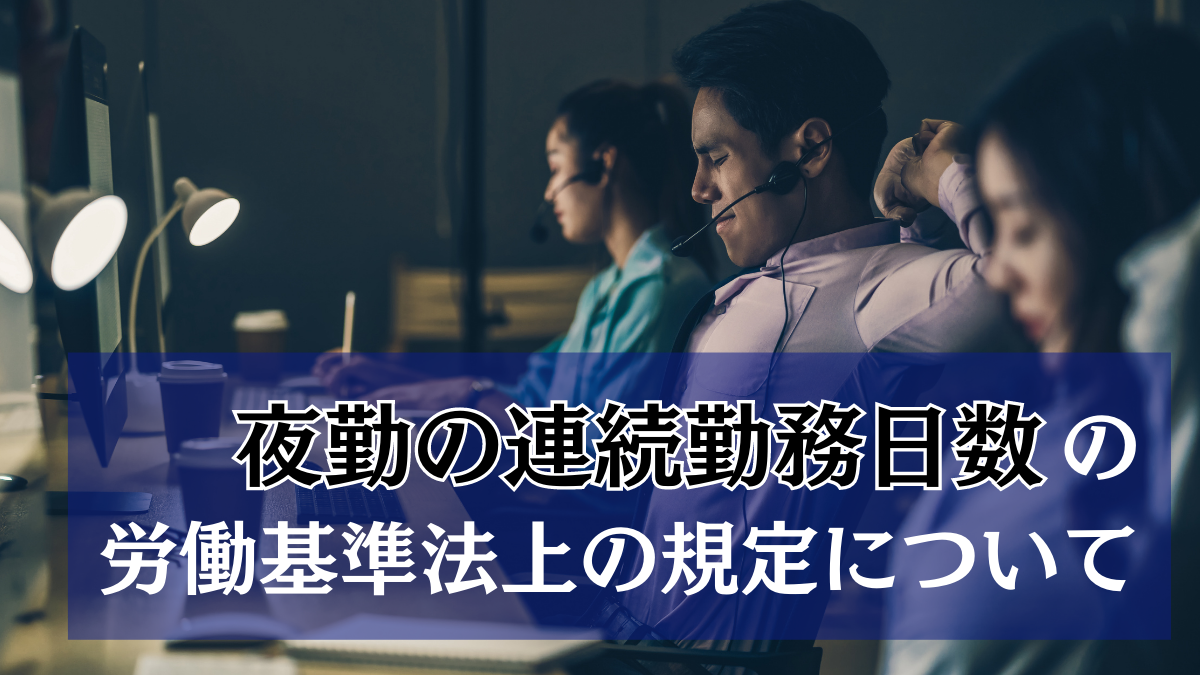
夜勤の連続勤務日数は労働基準法で明確に制限されているわけではありません。ただし、「夜勤からの日勤の場合」「日勤からの夜勤の場合」など、夜勤の連続勤務には注意点が多くあります。この記事では、法律上の夜勤の連続勤務における取り扱いについて解説します。また、夜勤の連続勤務は何回まで可能なのかも紹介します。
労働時間でよくある質問を徹底解説
この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。
ジンジャーは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
目次
1. 労働基準法上の夜勤からの連続勤務の取り扱い

夜勤をさせること自体は、労働基準法上、問題ありません。ただし、法律で定められた労働時間や休日のルールを守る必要があります。また、夜勤と日勤を含む連続勤務については、留意しておかなければならない点もあります。ここからは「夜勤から日勤への連続勤務の場合」「日勤から夜勤への連続勤務の場合」などのパターンを取り上げ、夜勤からの連続勤務の取り扱いについて詳しく解説します。
1-1. 夜勤とは?
夜勤とは、原則22時から翌日の5時までの深夜帯に勤務することです。夜勤の日数について法律による制限はありません。ただし、労働基準法第61条により、原則として18歳未満の労働者に夜勤をさせることはできません。また、労働基準法第66条により、妊産婦から請求があった場合、夜勤を免除しなければ違法になるので注意が必要です。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。(省略)
第六十六条 (省略)
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
1-2. 夜勤から日勤への連続勤務の場合
夜勤から連続してそのまま日勤をおこなう場合、労働基準法上、違法になりません。たとえば、月曜日の22時から火曜日の5時まで夜勤をおこない、5時間後、火曜日の10時から18時まで日勤をした日を考えてみましょう。
労働基準法では、深夜0時以降の夜勤をした場合、「始業時刻が属する日の労働」としての扱いになるため、あくまでも夜勤については月曜日の労働として扱われます。一方、火曜日の日勤については、火曜日の労働とみなされます。労働基準法第32条で定められる法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えていない限り、夜勤から日勤への連続勤務は違法になりません。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
1-3. 日勤から夜勤への連続勤務の場合
日勤での勤務をおこなった後、夜勤への連続勤務をおこなった場合、途中に休憩を取っていたとしても同じ暦日での勤務となります。そのため、法定労働時間を超えてしまう場合、違法になる可能性があります。このような場合、事前に36協定を締結しておく必要があります。
たとえば、月曜日の9時から17時で日勤をした従業員に、月曜日22時から火曜日の5時まで夜勤をさせた場合を考えてみましょう。夜勤の始業時間が月曜日のため、この夜勤は月曜日の勤務として扱う必要があります。法定労働時間を超えた労働になるため、36協定を結んでいない場合、労働基準法違反となり、罰則が課せられる恐れもあるので注意が必要です。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
1-4. 夜勤から夜勤への連続勤務の場合
夜勤明けの日に夜勤をおこなうのも、違法になりません。たとえば、22時から5時までの勤務を連続2日させたとしても、法定労働時間が守られているので、労働基準法に違反しません。ただし、労働基準法第35条により、1週間に1日または4週間に4日の法定休日を与えていなければ違法になるため注意が必要です。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
1-5. 労働基準法違反による罰則
法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日を付与していなかったりすると、労働基準法に違反することになります。労働基準法に基づき、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れがあります。また、厚生労働省サイトに労働基準法に違反した企業として会社名が公表されるリスクもあります。罰則を受けると、事業の存続が難しくなる可能性もあるので、法律に基づき、きちんと夜勤労働者の勤怠管理をおこないましょう。
2. 夜勤からの連続勤務が違法になるケース

法定労働時間や法定休日を守っていれば、夜勤の連続勤務をおこなわせても原則違法になりません。しかし、そのほかにも注意点は多くあります。ここでは、夜勤からの連続勤務が違法になるケースについて詳しく紹介します。
2-1. 割増賃金が正しく支払われていない場合
夜勤をさせる場合、労働基準法第37条に基づき深夜労働の割増賃金を支払う必要があります。また、法定労働時間を超えて残業させた場合や、法定休日に労働させた場合も、時間外労働や休日労働といった割増賃金が発生します。割増率は次の通りです。
|
項目 |
割増率 |
|
時間外労働(60時間以下) |
25%以上 |
|
時間外労働(60時間超え) |
50%以上 |
|
深夜労働 |
25%以上 |
|
休日労働 |
35%以上 |
|
深夜労働 + 時間外労働(60時間以下) |
50%以上 |
|
深夜労働 + 時間外労働(60時間超え) |
75%以上 |
|
深夜労働 + 休日労働 |
65%以上 |
残業時間が60時間を超える場合や、割増労働が重複する場合は、割増率が大きくなります。正しく割増賃金を計算していない場合、適切な賃金が従業員に支払われず、労働基準法違反になるので注意が必要です。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
2-2. 安全配慮義務に違反している場合
労働契約法第5条「安全配慮義務」により、企業は労働者が安全を確保しながら労働できるよう必要な配慮をおこなわなければなりません。安全配慮義務を怠ると、違法になるだけでなく、従業員から損害賠償を求められる恐れもあります。とくに夜勤での連続勤務が続いているような場合には、従業員の安全の確保が難しくなっている可能性もあります。早いうちに労働者が安心して働けるような環境を整備することが大切です。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
2-3. 法定休日を与えていない場合
夜勤で勤務させる場合でも、暦日単位(午前0時から午後12時まで)で休日を与える必要があります。そのため、夜勤明けの日を休日として取り扱うことはできません。従業員には、夜勤明けの日とは別の日を法定の休日として与える必要があります。休日の与え方が誤っている場合には、法令違反として罰則の対象となるため注意しましょう。
関連記事:夜勤明けの日は休み扱い?法律での休日の定義や注意点をわかりやすく解説
2-4. 36協定の違反をしている場合
法定労働時間を超えた労働(時間外労働)や法定休日の労働(休日労働)をさせる場合、事前に36協定を締結する必要があります。36協定を結ばず、時間外労働や休日労働をさせた場合は違法になります。
また、36協定には時間外労働や休日労働の上限も定められています。36協定を締結しても、原則として「月45時間・年360時間」を超えて労働させることはできません。ただし、臨時的な事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を結ぶことで、次のような範囲で、上限を延長させることができます。
- 時間外労働(休日労働含まない):年720時間以内
- 時間外労働(休日労働含む):月100時間未満、2〜6カ月平均80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられる回数:年6回まで
このように、36協定を締結したとしても、時間に関係なく働かせられるわけではありません。36協定を締結していても、その上限を超えて労働させたら違法になるので注意が必要です。
関連記事:36協定違反の罰則や罰則回避のポイントをわかりやすく解説
2-5. 休憩時間を正しく付与していない場合
労働基準法第34条により、夜勤の場合でも労働時間に応じて正しく休憩時間を与えなければなりません。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間の付与が必要です。
たとえば、夜勤から日勤(夜勤)への連続勤務の場合、夜勤をする日と、日勤(次の日の夜勤)をする日に区分して、労働時間に応じて休憩を付与する必要があります。一方、日勤から夜勤への連続勤務の場合、夜勤を深夜0時より前に開始していれば、同日勤務の扱いになるので、日勤と夜勤の労働時間を合算した数値を基に休憩時間を付与すれば問題ありません。
このように、労働基準法では休憩時間の付与義務が定められています。夜勤が関係する連続勤務の場合、休憩時間の管理が煩雑になる可能性もあります。正しく休憩時間を付与していなければ、労働基準法に違反することになり、ペナルティが課せられる恐れもあるので注意が必要です。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き
3. 夜勤からの連続勤務をさせるリスク

夜勤の連続勤務は、労働時間や休日、休憩の規定を守り、適切な割増賃金を支払っていれば法律上問題ありません。しかし、夜勤の連続勤務は健康上のリスクを高める恐れがあります。ここでは、夜勤が続くことによって考えられる健康リスクについて詳しく紹介します。
3-1. 夜勤が続くと体がだるくなりやすくなる
夜勤が続くことで、疲労が蓄積し、休みを取得しても思うように疲れがとれていない可能性があります。結果として、体にだるさを感じ、注意力が低下して労働災害につながるリスクもあります。また、勤務中の集中力が低下し、業務の生産性が下がってしまうこともあるかもしれません。
3-2. 昼夜逆転により自律神経が乱れやすくなる
夜勤の連続勤務で昼夜逆転の生活が続くことにより、生活リズムの乱れが発生しやすくなります。そのため、自律神経の乱れやホルモンバランスへの影響が心配されます。夜勤労働者のメンタル面が悪化するリスクもあります。
3-3. 睡眠時間や食生活の乱れによる病気のリスク
夜勤や日勤など、不規則な勤務をさせていると、十分な睡眠時間が確保できていない可能性があります。また、夜勤の連続勤務により、ストレスが蓄積することで、食生活の乱れも懸念されます。睡眠や食生活が乱れることで、病気へのリスクが一段と高まります。がんや心疾患、脳疾患などの可能性も大きくなります。
4. 夜勤労働者に対して企業が取るべき対策

夜勤の連続勤務にはさまざまなリスクがあります。夜勤が多く発生する業種の場合、健康リスクを避けるため事前に対策を講じておくことが大切です。ここでは、夜勤労働者に対して企業が取るべき対策について詳しく紹介します。
4-1. 健康診断の結果を活用する
健康上の問題を早期に発見するためにも、企業内でおこなっている定期的な健康診断の結果を十分に活用することが重要です。高血圧や糖尿病などが見つかった場合には、早期に産業医との面談を勧めるようにしましょう。また、夜勤労働者などの条件を満たす従業員には、年2回の健康診断を受けさせる義務があります。夜勤が多い従業員の健康を維持するため、正しく健康診断を実施し、健康を管理しましょう。
関連記事:夜勤労働者は2回の健康診断が必要!項目や対象者の基準も詳しく解説
4-2. 無理のないシフト管理を実施する
夜勤の連続勤務は、労働時間や休日などの規定を遵守し、割増賃金を適切に支払っていれば法的に問題ありません。しかし、夜勤が続くと、健康上のリスクが高まります。従業員の健康を維持するためにも、夜勤が連続しないよう配慮し、交代制を採用するなど、無理のないシフト管理をおこなうことが大切です。
4-3. 適切に休憩を付与する
労働基準法第34条に則り、夜勤労働者に対しても労働時間に応じて休憩時間を正しく付与する必要があります。労働基準法で定められている数値は最低基準のため、1時間30分など長めの休憩を付与することは問題ありません。ただし、次のような休憩付与のルールを守る必要があります。
- 休憩は労働時間の途中で与える(始業直後や終業直前の休憩付与は禁止)
- 休憩は一斉に与える(労使協定を結ぶことで一斉付与の原則を除外できる)
- 休憩時間は労働から解放されていなければならない
夜勤労働者に対して仮眠を与えているケースもあるかもしれません。仮眠時間は、手待ち時間とみなされ、自由が保障されていないため、休憩時間として認められない可能性もあります。仮眠時間を休憩時間とみなすのであれば、仮眠時の取り扱いをあらかじめ明確に定めておきましょう。なお、休憩時間は分割して与えても問題ありません。たとえば、1時間の休憩を付与しなければならない場合、「30分×2回」で休憩を与えても違法にはなりません。
(休憩)
第三十四条 使用者は、(省略)休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
関連記事:【図解】夜勤した従業員の休憩時間・休日・賃金の計算方法を分かりやすく解説
4-4. 勤務間インターバル制度を導入する
勤務間インターバル制度とは、従業員の健康を維持するため、勤務の終了から次の勤務までの間に一定の休息時間を設けなければならない制度のことです。一定の休息時間を設けることで、睡眠時間やプライベートの時間を確保でき、健康リスクを抑えて働いてもらうことが可能です。2019年以降、勤務間インターバル制度の導入は事業主の努力義務となっています。勤務間インターバル制度を導入しなくても罰されることはありませんが、従業員の健康を守るためにも、適切な休息を取れるような労働環境を整備しましょう。
4-5. 勤怠管理システムを導入する
夜勤の連続勤務をさせる場合、労働時間や休日の管理、割増賃金の計算などが煩雑になる可能性があります。タイムカードやExcelなどで労働時間を集計し、給与を計算している場合、間違った賃金を計算してしまい、違法になる恐れがあります。また、月末にまとめて集計作業をしていると、月の途中で労働時間や休日の規定に違反していても気づかない可能性があります。
このように、勤怠管理や給与計算に課題を感じている場合、勤怠管理システムの導入を検討してみるのも一つの手です。勤怠管理システムであれば、リアルタイムで労働時間を管理できるので、労働時間の上限を超えそうな従業員に対して、早い段階でアラートを出して注意を促すことができます。また、労働時間の集計から賃金の計算までを自動化できるため、人的ミスを防ぎながら、業務を効率化することが可能です。
5. 夜勤の連続勤務は何回まで?
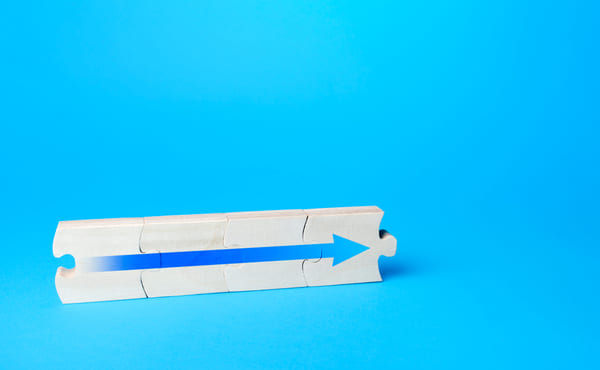
夜勤の連続勤務日数について、労働基準法上での明確な定めはありません。ただし、労働者に1週間に1日もしくは4週間に4日の法定休日を与えなくてはなりません。つまり、従業員に対して連続で夜勤を命じられる法律上の上限日数は、原則的な1週1日の休日であれば最大で12日間となります。
5-1. 変形休日制であれば夜勤の連続勤務日数を延長することも可能
変形休日制とは、4週間の間に4日以上の休日を与える制度のことです。労働基準法では1週間に1日の休日を原則としていますが、4週間に4日の休日を与えても問題ないため、変形休日制であれば、4週間の初日に休日を4日与えた後、残りの3週間は無休という連続勤務も可能です。
就業規則に変形休日制の起算日などを明記したうえで、制度を採用すれば法律上問題なく、13日以上の連続勤務をさせることができます。ただし、このような働き方は従業員の健康リスクを高めることになります。また、週の労働時間が40時間を超える可能性もあり、多くの割増賃金の発生も考えられるため注意が必要です。
6. 夜勤の連続勤務日数は労働基準法での定めはないがリスクへの配慮が必要

夜勤の連続勤務日数についての労働基準法上の規定はありませんが、従業員を連続して夜勤勤務させることで、健康リスクや法令違反へのリスクが高まります。また、正確な割増賃金の支払いがされていなかったり、36協定に違反していたりする場合、違法になる可能性もあります。夜勤の連続勤務をさせる場合、法律だけでなく、健康リスクも考慮して、労働環境を整備するようにしましょう。








