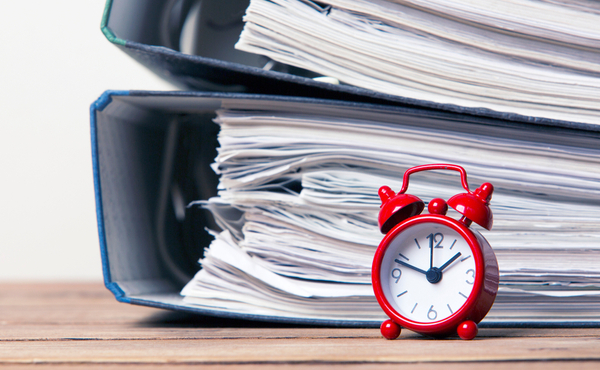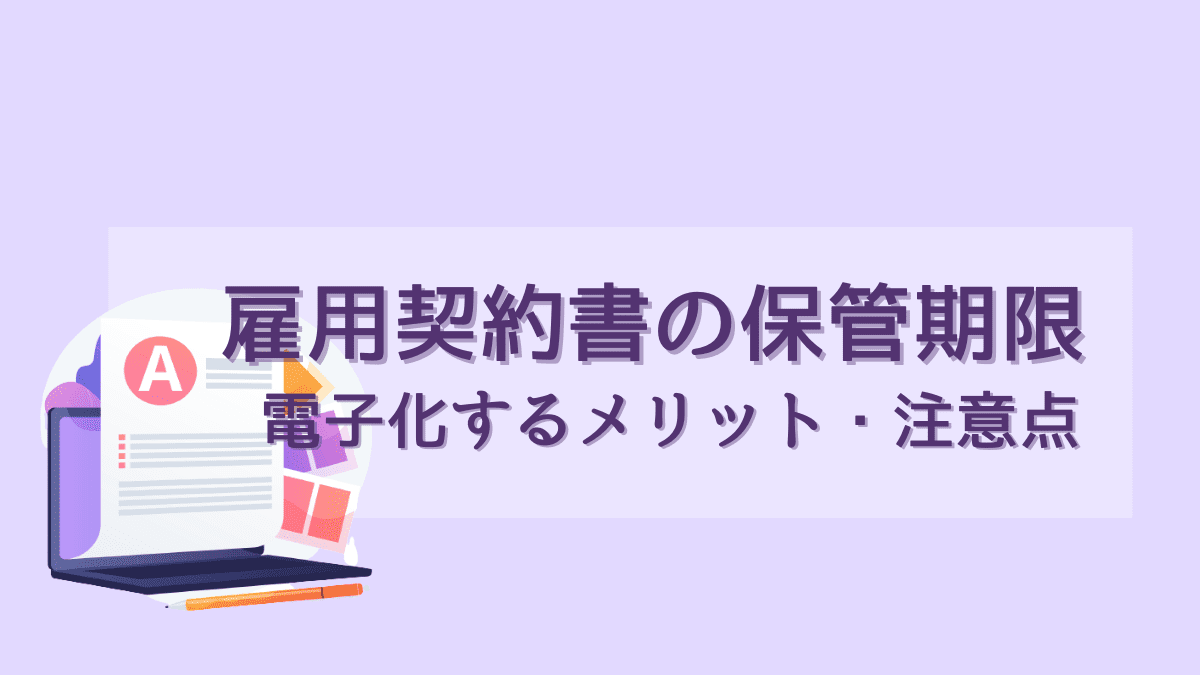
雇用契約書の保管期限は退職日から5年後です。しかし、雇用契約書の保管期間には経過措置があるなど、注意点も多くあります。この記事では、雇用契約書の保管期限やその起算日についてわかりやすく解説します。また、雇用契約書の保管方法や、電子化して管理する場合のメリット・デメリット、注意点についても紹介します。
労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。
当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 雇用契約書の保管期限の起算日はいつから?
雇用契約書を作成している場合、いつからいつまで保管すればよいかわからない人もいるかもしれません。ここでは、雇用契約書の保管期限やその起算日について詳しく紹介します。
1-1. 雇用契約書とは?
雇用契約書とは、使用者と労働者の間で取り決めた労働条件の内容を確認し、双方が合意したことを証明するための書類です。雇用契約書の交付は、法律で定められた義務ではありませんが、雇用に関するトラブルを防止するため作成することが推奨されています。
なお、雇用契約書と似た書類に「労働条件通知書」があります。労働条件通知書と雇用契約書の記載内容はほとんど同じです。しかし、労働条件通知書は、労働基準法第15条によって、交付しなければならないと決められています。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
関連記事:雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや雛形などの書き方について徹底解説
1-2. 雇用契約書の保管期間
雇用契約書の保管期間は、労働基準法第109条により5年間と定められています。なお、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿といった法定三帳簿も5年間保管する必要があります。
労働基準法の保管期間の規定に違反すると、万が一労働条件に関するトラブルがあったときに、会社側が不利になる恐れがあります。また、労働基準法第120条に則り、30万円以下の罰金の罰則を受けるリスクもあります。そのため、適切な方法での管理が求められます。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
第百二十条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第百九条までの規定に違反した者
関連記事:雇用契約書の保管期間は5年!経過措置の内容やほかの書類についても紹介
1-3. 雇用契約書の保管期間には経過措置あり
労働基準法第109条の保管期間に関する規定については、経過措置が設けられています。労働基準法第143条により、当面の間、保管期間は5年間でなく、3年間でも問題ありません。つまり、雇用契約書の保管期間は、現状経過措置によって3年間の保存が義務付けられています。しかし、経過措置がいつ終了するかは未定なため、できる限り5年間保管しておくことが推奨されます。
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。(省略)
1-4. 雇用契約書の保管期限の起算日は「退職した日」
雇用契約書の保管期限は理解していても、いつから保管期間を数えるべきか、起算日がわからないという人も少なくないでしょう。労働基準法施行規則第56条に則り、雇用契約書の保管期限の起算日は、従業員が退職(解雇)した日(死亡した日)になります。
そのため、雇用契約書の保管期限は、労働者が退職した日から5年後です。雇用契約書を作成した日や、雇用契約を締結した日が起算日にならないので注意が必要です。
第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
(省略)
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
(省略)
2. 雇用契約書の保管方法
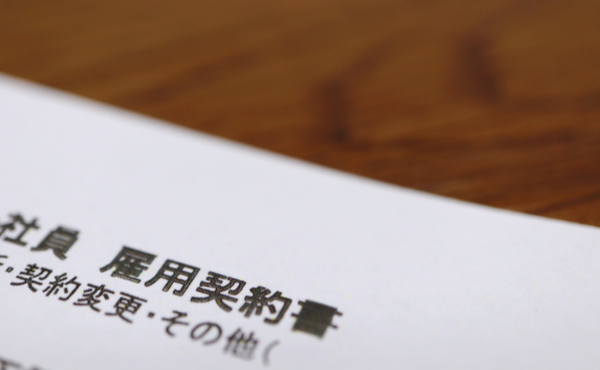
雇用契約書の保管方法には、大きく紙と電子データの2種類があります。ここでは、それぞれの保管方法について詳しく紹介します。
2-1. 紙で保管する
雇用契約書の一般的な管理方法として、契約書類を紙面に印刷し、台帳を作って管理、その後保管期限を待って破棄するという方法があります。すぐに必要な雇用契約書を取り出せるよう、年度別や雇用形態別などに仕分けして管理するようにしましょう。また、雇用契約書は社外秘の情報を含む重要な書類であるため、保管場所に鍵をかけるなど、セキュリティ対策に気を付ける必要があります。
2-2. 電子データで保管する
従来の紙媒体での管理方法では、期限が過ぎた契約書を保管したままにしているケースも多いです。また、保管スペースが必要になり、コストもかかります。このような課題を解消するため、紙と同等の効力を持つ、雇用契約書の電子化が注目されています。
雇用契約書は法律で定められた書類でないので、電子環境さえ整備すれば、従来から電子化して管理することができました。電子データで保管する場合も、アクセス権限を付与する、バックアップを取るなど、不正アクセスや改ざんなどのセキュリティ対策に気を付ける必要があります。
2-3. 電子データをプリントアウトして保管するのは違法?
雇用契約書を電子化し、電子契約した書類をプリントアウトして保管している人もいるかもしれません。電子帳簿保存法の改正により、2024年1月から契約書データを送付・受領した場合、電子データのまま保管することが義務付けられています。
そのため、電子データで送付した雇用契約書の控えは、電子データの状態で保管しなければなりません。なお、電子データで保管できていれば、セキュリティ対策のためなどで、プリントアウトすること自体は違法でありません。ただし、電子データを削除しないように気を付けましょう。
請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)が、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。引用:電子取引関係|国税庁
3. 雇用契約書を電子化して管理するメリット
 2019年4月から労働条件通知書の電子化が解禁されました。これにより、労働条件通知書や雇用契約書を電子化したいと考える企業も増えています。ここでは、雇用契約書を電子化するメリットについて詳しく紹介します。
2019年4月から労働条件通知書の電子化が解禁されました。これにより、労働条件通知書や雇用契約書を電子化したいと考える企業も増えています。ここでは、雇用契約書を電子化するメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 人材採用がスピーディーになる
雇用契約書を電子化することで、人材の募集から雇用契約の締結までの一連の流れをスピーディーに進めることができます。そのため、優秀な人材をいち早く採用したいという採用担当者の狙いにも合致したものとなります。
3-2. 契約更新時の業務効率がアップする
従業員の契約更新をする場合にも、電子化された雇用契約書を利用することで、効率アップが期待できます。従来の紙書類でおこなっていた印刷・押印作業の手間、また、手作業によるミスも削減できます。
3-3. 書類のコスト削減が可能となる
紙書類で保管する場合、印刷代や用紙代、郵送料などのコストが大きくかかります。また、保管する書類が多くなればなるほど、書類保管に要するスペース代もかかってきます。しかし、電子化して管理することにより、ここで挙げたコストに関してはすべて不要になります。
3-4. リモートワークが推進しやすくなる
書類の電子化をはかることで、従来必要とされた書類の押印作業が不要となり、リモートワークを推進しやすくなります。また、リモートワークを推進することで、全国各地からさまざまな人材を集めることが可能となり、結果的に優秀な人材と出会えるチャンスも広がります。
関連記事:雇用契約書の電子化は合法?メリットや導入方法、労働条件通知書との違いも解説
4. 雇用契約書を電子化して管理するデメリット
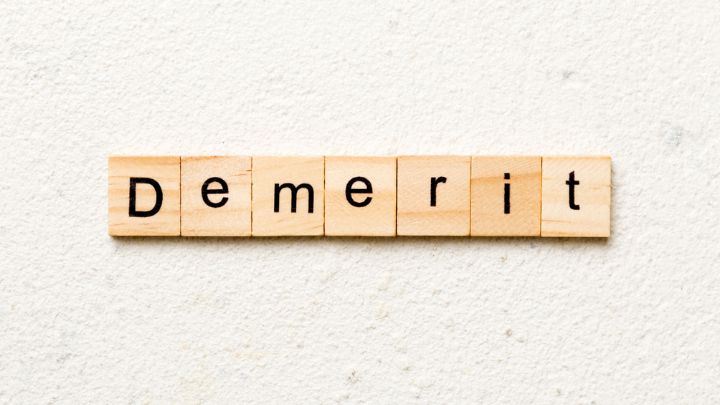
雇用契約書を電子化する場合、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、雇用契約書を電子化して管理するデメリットについて詳しく紹介します。
4-1. システムの導入・運用コストがかかる
雇用契約書を電子化する場合、法律の要件を満たすため、電子契約サービスや契約書管理システムなどの導入や運用が必要になります。初期費用や月額費用が大きい場合、経営を圧迫することになり、途中でシステムの導入や運用をやめることになる可能性もあります。雇用契約書を電子化する場合、あらかじめ予算を明確にし、料金や機能が自社のニーズにあったツールを導入することが大切です。
4-2. 労働者の同意を得る必要がある
紙の雇用契約書で労働契約を締結することに慣れている従業員にとっては、雇用契約書の電子化に対して抵抗を感じるかもしれません。また、新たに採用される労働者は、PC・スマホなどの端末やインターネット環境がなければ、雇用契約を締結できません。
このように、雇用契約書の電子化は、従業員に負担を強いる可能性があります。雇用契約書を電子化する目的やメリットを説明し、同意を得たうえで雇用契約書の電子化を進めましょう。
4-3. 操作ミスによるトラブル
雇用契約書を電子化すれば、ボタン一つで簡単に契約書の送付や雇用契約の締結などの手続きができるようになります。しかし、間違った人に雇用契約書を送付してしまったり、労働条件を確認していないにもかかわらず雇用契約に締結してしまったりするリスクも増加します。あらかじめ雇用契約書を電子化する場合のリスクを労働者に伝え、操作ミスによるトラブルが起きないように教育をおこなうことが大切です。
5. 雇用契約書を電子化する方法や流れ

雇用契約書を電子化するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、雇用契約書の電子化方法の流れを紹介します。
5-1. 雇用契約書の作成・交付に関する課題を洗い出す
まずは雇用契約書の作成・交付に関する自社の課題を洗い出しましょう。たとえば、「コストがかかる」「管理に時間や手間がかかる」などが挙げられます。課題を洗い出し、目的を明確にすることで、雇用契約書の電子化をスムーズに進めることができます。
5-2. 電子契約サービスを選定する
電子契約サービスとは、紙の契約書の代わりに、Web上で電子ファイルを利用して押印・署名をおこなうことで契約ができるサービスです。電子契約サービスには、さまざまな種類があります。料金や機能、サポート、セキュリティなどの観点から複数のツールを比較したうえで、自社のニーズにあった電子契約サービスを選定しましょう。
関連記事:電子契約サービス比較22選|選定ポイントや機能・コスト一覧表を紹介!
5-3. 社内ルールや業務フローを変更する
電子契約サービスを導入する場合、これまでの社内ルールや業務フローでは対応できない可能性があります。そのため、社内ルールや業務フローの見直しをおこない、必要に応じて変更しましょう。
5-4. 従業員や新たに採用する労働者に周知する
雇用契約書を電子化する環境が整備できたら、混乱を招かないためにも、システムの使い方や運用のフローをきちんと従業員に周知しましょう。また、雇用契約書を電子化して送付する場合、新たに採用される労働者に対しても、電子契約のやり方について適切に伝えることが大切です。
5-5. 雇用契約書を電子化して運用する
電子契約サービスの導入、社内ルール・業務フローの変更が実施できたら、実際に雇用契約書の電子化を始めてみましょう。定期的に見直しをおこない、課題があったら改善することで、施策の効果を高めることができます。
6. 雇用契約書を電子管理する際の注意点

ここでは、雇用契約書を電子化して管理する際の注意点について詳しく紹介します。
6-1. 電子帳簿保存法に注意する
電子化して雇用契約書をやり取りする場合、電子帳簿保存法の「真実性」「可視性」といった要件を満たす必要があります。電子帳簿保存法の要件を満たしてない状態で、雇用契約書を電子化すると、契約書としての効力が認められない恐れもあります。また、企業側だけでなく、従業員側にも電子帳簿保存法の注意点を周知することが大切です。
関連記事:電子帳簿保存法における要件は?具体的な保存方法も紹介
6-2. 雇用契約書は労働条件通知書と兼用できる
雇用契約書と労働条件通知書の目的や役割に違いはあれど、内容にほとんど変わりがないこともよくあります。雇用契約書は労働条件通知書と兼用して、「労働条件通知書兼雇用契約書」と1枚の書類にまとめて交付することも可能です。労働条件通知書兼雇用契約書を交付することで、事務手続きの負担を減らすことができます。ただし、労働条件通知書兼雇用契約書には、労働条件通知書の必須事項や雇用契約書に必要な署名・捺印欄を設けなければならないので注意が必要です。
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説
6-3. 雇用契約書の記載事項を正しく書き記す
雇用契約書は法律で交付が義務付けられたものでないので、明確な記載事項は決まっていません。一方、労働条件通知書は、労働基準法施行規則第5条で定められた次の記載事項を網羅して記載する必要があります。
【絶対的記載事項】
- 労働契約の期間
- 就業の場所と従事すべき業務の内容
- 始業・終業時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間
- 休日・休暇
- 交代制の有無とその内容
- 賃金の決定や計算、支払の方法
- 賃金の締切りと支払時期
- 退職(解雇を含む)
【相対的記載事項】
- 昇給
- 退職手当に関する具体的な定め
- 臨時的に支払われる賃金(賞与やボーナスなど)
- 最低賃金
- 労働者に負担させるべき食費や作業用品など
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償や業務外の傷病扶助
- 表彰や制裁
- 休職
【2024年4月から追加された事項】
- 就業場所の変更範囲
- 業務内容の変更範囲
- 更新上限の有無と内容(※有期労働契約のみ)
- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(※有期労働契約のみ)
絶対的記載事項は労働条件を明示する際、確実に記載しておかなければなりません。相対的記載事項は、その定めをしている場合に限り、必ず記載する必要があります。なお、相対的記載事項は書面でなく、口頭でもよいとされていますが、トラブルを招かないよう、書面に記載しておくことが推奨されます。
また、2024年4月から労働条件明示ルール改正により、記載事項が追加されています。労働条件通知書兼雇用契約書を交付する場合も、これらの事項を網羅して記載しなければなりません。このように、労働条件通知書や雇用契約書には記載事項のルールも定められているので、きちんと確認しておきましょう。
関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!
6-4. 雇用契約書の電子化要件に気を付ける
雇用契約書は法的に交付が義務付けられた書類でないため、明確な電子化要件は定められていません。一方、労働条件通知書には、労働基準法施行規則第5条に記載された電子化要件があり、次のいずれもの要件を満たさなければ、電子交付が認められません。
- 労働者が希望する場合のみ電子化が認められる
- プリントアウトが可能な方法で電子交付する
- 本人のみが閲覧できる状態で交付する
労働条件通知書だけでなく、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行する場合も、電子化要件を満たさなければならないので注意が必要です。
(省略)法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6-5. 管理監督者やパート・アルバイトでひな形を変える必要あり
雇用契約書は採用する従業員に応じて、ひな形・テンプレートを変えたうえで作成する必要があります。新しく雇用する従業員が「管理監督者」に該当する場合、労働基準法の労働時間や休憩、休日などの規定が適用されません。なお、「管理監督者」とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定義されています。管理監督者かどうかは、次のような事情を考慮したうえで判断されます。
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有しているこ
- 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
- 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
そのため、管理監督者向けの雇用契約書を作成する際は、上記の要件を満たすよう作成することが大切です。
また、正社員だけでなく、パート・アルバイトと雇用契約を結ぶ場合も、トラブルを未然に防ぐため、雇用契約書を交付することが望ましいです。なお、パート・アルバイトなどの短時間労働者や有期雇用労働者の場合、パートタイム労働法第6条に則り、次の記載事項も労働条件通知書や雇用契約書に含める必要があります。
- 昇給の有無
- 退職金の有無
- 賞与・ボーナスの有無
- 雇用管理の改善などに関する事項に関係した相談窓口
労働条件通知書のひな形は、厚生労働省「様式集」からダウンロードすることができます。労働条件通知書のテンプレートを活用し、自社のニーズにあわせてカスタマイズすることで、効率よく雇用契約書も作成することが可能です。
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
関連記事:雇用契約書の書き方とは?記載すべき事項やパート・アルバイトのケースも紹介
7. 雇用契約書を電子化する際のポイント

電子契約サービスを利用して、雇用契約書を電子化する場合、事前に検討しておきたい点がいくつかあります。ここでは、雇用契約書を電子化する際のポイントについて詳しく紹介します。
7-1. 契約書のどの段階までを電子化するかを決める
雇用契約書を電子化する場合、契約書のどの段階までを電子化するのか検討したうえで、サービスの導入を検討するとよいでしょう。電子化する目的やどの範囲まで電子化をおこなうか明確にして、サービスを導入すると、自社の目的に合った電子契約サービスを選択することができます。
7-2. どのレベルの電子契約サービスを利用するかを考える
自社で導入する電子契約サービスに対し、どのレベルまでの機能を求めるのか、あらかじめ決めておくのがおすすめです。電子契約サービスの中には、契約書の作成だけでなく、タスク管理やシステム連携などの機能、契約書のスキャン機能を備えているものもあります。電子契約サービスを選ぶ際には、必要なサービスが過不足なく提供されているものを選ぶようにしましょう。
7-3. サービスの本人確認方法を検討する
電子契約書で利用する本人確認の方法には、電子サインや電子証明書があります。電子サインと比較し、電子証明書のほうがより本人性の担保に有効という特徴があります。自社の認証ルールと照らし合わせたうえで、最適な方法を選択するようにしましょう。
7-4. 入社する人への周知方法を検討する
雇用契約書の電子化については、入社してくる人に対しても、あらかじめ周知しておきましょう。サービスの仕組みや操作のマニュアルなどを事前に用意しておくと、ITに苦手意識がある人でも、サービスを最大限に活用できるようになります。
7-5. 社内での電子契約に対する理解を深める
今いる従業員に対しても、電子契約サービスを利用した雇用契約書とすることで、業務効率の向上をはかれます。電子契約サービスについての理解を深めるため、積極的にサービスの利用方法に関する研修や説明会を開催してみるのも一つの手です。
8. 雇用契約書の保管ルールを守り適切な管理を!

雇用契約書の保管期限は、原則として従業員が退職した日(起算日)から5年後です。ただし、保管期間には経過措置が設けられており、当面の間は5年間でなく、3年間でもよいとされています。しかし、経過措置がいつ終わるかわからないため、可能な限り5年間保管しておくようにしましょう。また、雇用契約書は電子化して管理することもできます。雇用契約書を電子化する場合、電子帳簿保存法などの法律の要件を満たす必要があるため、この機会に電子契約サービスの導入も検討してみましょう。
労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。
当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。