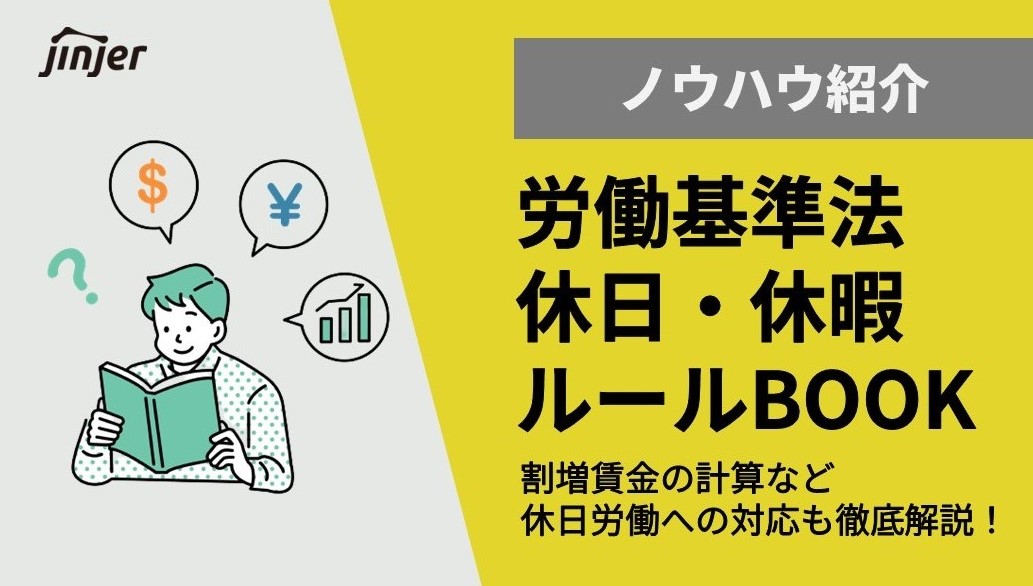法定休日に従業員を出勤させる場合には、あらかじめ上限を決めたうえで出勤させる必要があります。制限なく法定休日の出勤が続くと、法令違反につながる場合もあるため注意しましょう。
今回は、法定休日出勤の回数や出勤に関する決まり、法定休日に出勤させる場合の注意点について解説していきます。
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
目次
1. 法定休日とは?

法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、使用者が労働者に対して最低限与える義務がある休日のことです。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
同法に従い、週に1回、または4週に4回の休日を付与しなければなりません。適切な休日日数を付与できなかった場合、法律違反に該当し、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が下る可能性があります。以下、法定休日について詳しく解説します。
1-1. 休日には「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」が存在する
労働者に付与する休日には「法定休日」と「所定休日」の2種類があり、法律上の扱いが異なります。法定休日とは、先ほど紹介した通り、労働基準法で定められた労働者に最低限付与すべき休日のことを指します。
一方、所定休日とは、各企業が定める休日のことです。所定休日は法律により定められているものではないため、付与する日数などは企業の裁量に委ねられています。
たとえば、週休2日制で土日が休みの場合は、どちらか一方が法定休日となるでしょう。
関連記事:法定休日とは?法定外休日との違いや出勤した場合の割増賃金のルール
1-2. 法定休日は年間で最低何日与えるべき?
法律により定められている法定休日の付与日数は、週に1回、または4週に4回です。年間で換算すると1年は約52週となるため、法定休日を週に1回付与すると設定した場合、「52日」が年間最低付与日数になります。
ただし、1日8時間を所定労働時間とした場合、5日で法定労働時間(1日8時間、週40時間)の上限に達してしまうため、所定休日も追加で付与することが必要です。土曜日を所定休日、日曜日を法定休日として、週休2日制をとっている企業が多いのはこのためです。
この場合、付与すべき法定休日と所定休日を合計すると、最低105日の休日付与が必要となります。
関連記事:休日出勤の定義とは?割増賃金の計算方法や強制・拒否できるかどうかも解説!
2. 法定休日の出勤回数に上限はある?

法定休日の出勤回数や労働時間には上限があります。繁忙期など、どうしても従業員を法定休日に出勤させなければならないシーンはありますが、だからといって従業員を制限なく出勤させることはできません。
本章では、法定休日において出勤回数が制限される場合について、その理由とともに解説します。
2-1. 就業規則や36協定による法定休日の出勤制限
法定休日に出勤させる場合は、事前に労使間で36協定を締結することが必要です。また、36協定を締結する際は、休日労働させられる日数の上限を定めなければなりません。その内容は就業規則にも記載する必要があります。
定められた規定以上に法定休日の出勤をさせることはできません。もし出勤をさせた場合には、労働基準法違反となってしまいます。法定休日の出勤をさせなくて済むように、業務量を調整したり、生産性を上げる仕組みづくりをおこなったりしましょう。
2-2. 時間外労働の上限規制
法定休日の出勤回数が制限されるもう一つの根拠として、時間外労働の上限規制が挙げられます。労働基準法では、法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
法定労働時間を超過して労働させる場合、36協定を締結しなければなりません。36協定を締結した場合、月45時間・年360時間以内で時間外労働をさせることが可能となり、この上限は「一般条項」とよばれます。
また、臨時的な特別の事情で一般条項以上の時間労働させる必要がある場合には、特別条項付き36協定を結ぶ必要があります。特別条項付き36協定の上限は以下の通りです。
- 時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満
- 時間外労働+休日労働 ・・・2〜6ヵ月平均80時間以内
- 時間外労働・・・年720時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月まで
36協定の一般条項の上限に休日労働の労働時間に関する制限は含まれていませんが、特別条項付き36協定の場合は上限の一部に休日労働が含まれています。そのため、この上限を超過しないよう、法定休日の出勤回数を管理しなければなりません。
たとえば、すでに法定外残業の時間が月90時間を超えている状況で法定休日に2回出勤した場合、1日8時間とすると以下の計算式になり、特別条項の上限である月100時間未満を超過してしまいます。
上限を超えないようにするためには、休日に出勤する回数を制限するなどの対策を検討しましょう。
3. 法定休日の出勤に関する決まり

従業員を法定休日に出勤させなければならなくなった場合、次に挙げる2つの決まりを守らなければなりません。
3-1. 36協定の締結と届出
従業員に法定休日の出勤を求める場合、あらかじめ36協定を締結して届出が済んでいる必要があります。
36協定は労働基準法第36条に基づく規定であり、労使間で話し合ったあとで協定を結びます。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
36協定を締結することなく、法定休日に従業員を出勤させることは法令違反です。場合によっては、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される場合もあるので注意しましょう(労働基準法第119条)。
また、36協定を締結しているだけでなく、労働基準監督署長への届出までをおこなっておかなければなりません。
届出をしていない状態で法定休日に出勤をさせた場合も36協定違反となり、使用者に対して懲役や罰金の罰則が科される可能性があるので、忘れずに届出をおこないましょう。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
3-2. 振替休日の指定
法定休日の出勤が多い場合には、36協定で規定されている時間外労働や休日労働の上限を超える可能性が高くなります。
時間外労働や休日労働の上限を超えそうなことがあらかじめ予想される場合には、振替休日の指定を検討しておくのがおすすめです。
振替休日とは、休日出勤する前にあらかじめ振り替える休日を指定しておき、休日と労働日を入れ替える制度のことです。この場合、労働日と休日を入れ替えたと考えるので、休日労働をしたとはみなされません。
ただ、一点注意すべきなのは振替休日の指定は、必ず休日の出勤前におこなわなければならないという条件があることです。
休日出勤後に休日を付与した場合には、代休扱いとなり、法定休日に出勤させた場合は休日労働とされます。結果として、時間外労働や休日労働の時間数が上限を超え、法令違反につながってしまうので注意しましょう。
関連記事:法定休日に出勤させたら振替休日を付与できる?付与条件や代休との違い
4. 法定休日に対する振替休日を有効にする条件
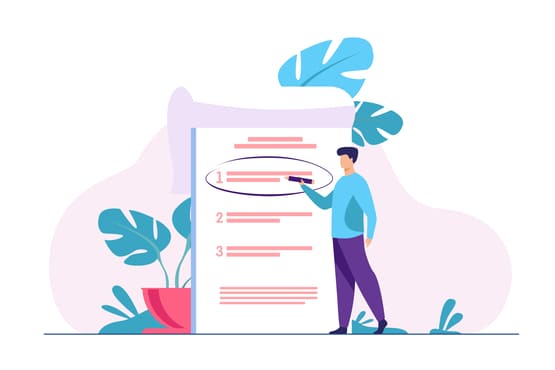
法定休日に出勤する場合、前もって振替休日の指定を検討することを推奨しましたが、振替休日を有効にするためには、いくつかの条件があります。
ここでは、振替休日を有効にする条件を4つ紹介しておきます。
4-1. 振替休日に関する就業規則への記載
就業規則へ記載しておかなければ、振替休日の制度を利用することはできません。休日に出勤した分について、休日を別の日に振り替える可能性や振替の方法などについて明記しておく必要があります。従業員への周知も忘れないようにしましょう。
4-2. 従業員に対する前日の勤務終了までの予告
休日に出勤させ、振替休日を利用する場合には、休日の前日の勤務終了までに従業員に対して振替休日の予告をしておく必要があります。
振替休日の予告をしないまま法定休日に出勤させた場合には、振替休日の制度は利用できず、代休で対応しなければなりません。振替休日でなく代休を取得する場合、賃金計算などの対応が異なるので注意が必要です。
関連記事:代休とは?振替休日との違いや労働基準法上の定義、取得期限を解説
4-3. 振替休日とする日の指定
休日に出勤する場合の振替休日をいつ与えるかについては、あらかじめその日付を明確にしておく必要があります。
振替日がはっきりしない場合、振替休日として認められないので、前もって振替休日の日付を決めたうえで休日出勤をさせるようにしましょう。
4-4. 労働基準法に定められた休日の確保
労働基準法において、従業員には1週間に1日もしくは4週間で4日の法定休日を与えるよう定められています。
36協定を締結していない場合、法定休日の要件を満たさない状態で従業員に振替休日を取得させようとしても、法令違反となるため注意しましょう。
関連記事:振替休日とは?労働基準法の定義や代休との違い、取得期限を解説
5. 法定休日の出勤回数に関する注意点

従業員を法定休日に出勤させる場合には、次の6点に注意しましょう。
5-1. 法定休日の出勤回数上限は慎重に決める
法定休日の出勤回数については、あらかじめ従業員に明示しておく必要があります。36協定で出勤回数の上限について決めたうえで、就業規則には休日労働のルールについて明記しておくことが大切です。
出勤回数の上限を決める際は、従業員を縛る内容にならないよう、ある程度余裕をもたせるなど、慎重に対応することが大切です。
5-2. 法定休日に出勤させる場合、割増賃金の支払いが必要
休日労働は労働者にとって負担が大きいため、法定休日に出勤させる場合、休日労働の割増賃金の支払いが必要です。休日労働に対する賃金の割増率は35%以上と定められているので、法定休日に出勤させた場合は正しく割増賃金を支払いましょう。
関連記事:法定休日と所定休日の違いは?割増賃金のルールや注意点を解説
5-3. 法定休日出勤の回数が多いと企業の社会的信用を下げる原因になりうる
休日労働や時間外労働が多いと、法律を守っていたとしても企業の印象は悪くなってしまいます。法律に違反していたり従業員との間でのトラブルが発覚したりすると、さらに悪い印象が強くなるため注意が必要です。
その結果、取引先と思うようなやりとりができなくなる、優秀な人材が集まりにくくなる、離職率が高くなるといった原因にもなります。
働き方改革が進み、良好な職場関係を作る努力が企業に求められています。時間外労働、休日労働が多すぎる場合は業務を見直す、人員を増やすなどの対策も必要です。
5-4. 法定休日の出勤回数を可能な限りおさえる
法定休日の出勤回数を増やしすぎると、従業員の負担が大きくなるため注意しましょう。原則、法令違反をせず、36協定で締結した内容を守っていれば、従業員を法定休日に出勤させることが可能です。
しかし、従業員側の立場からみると、休日出勤の頻度が多くなることにより、休日の予定を立てられず、常に頭から仕事が離れない状況が続きます。結果として、従業員のモチベーション低下にもつながりかねません。
また、休日出勤の回数を減らすことで、割増賃金の支払いの必要もなくなるので、企業側にとってもメリットがあるといえます。
5-5. 所定休日の出勤回数を分けてカウントする
法定休日と所定休日の出勤回数は、別々にカウントしなければなりません。所定休日における出勤回数を除外して、法定休日の出勤回数が上限を超えないように管理しましょう。
また、所定休日の労働は通常の出勤日と同じ扱いとみなされ、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働に対しては、時間外労働の割増賃金の支払いが必要になるので注意が必要です。
関連記事:所定休日の割増賃金とは?法定休日や割増賃金の計算方法も詳しく紹介
5-6. 正確な勤怠管理を心がける
法定休日の出勤回数に限りませんが、従業員の勤怠状況は正確に管理しなければなりません。勤怠管理を怠ると、知らないうちに長時間労働が発生したり、割増賃金の支給を忘れたりしてしまいます。また、法定労働時間を超過してしまうケースもあるでしょう。
法定休日の出勤回数や労働時間の管理を効率化するためには、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。勤怠情報を自動で集計できるため、担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
休日出勤をさせた場合の適切な対応をもっと詳しく知りたいという方に向けて、当サイトでは「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」をお配りしています。
休日と休暇の定義の違いや、混同しやすい代休と振休の要件など、休日・休暇の基本的な情報をこれ一冊でご確認頂けます。休日出勤に対する法律に則った対応を確認したい方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードして、ご活用ください。
6. 法定休日出勤の回数をしっかりと把握して法律違反を避けよう!

今回は、法定休日に出勤をする場合の出勤回数の制限や出勤についてのルール、また、法定休日に出勤させる場合の注意点などを解説しました。従業員に法定休日の出勤をさせる場合には、上限を考えた対応が必要です。その理由として、労働基準法で定められている時間外労働の上限規制や就業規則・36協定による法定休日の出勤制限が挙げられます。
また、法定休日の出勤については、ルールを守ったうえでの出勤が必要となるので、あらかじめ確認をしておくと安心です。労働基準法はもちろん、就業規則や36協定を十分理解して、法令違反を指摘されることのないようにあらかじめ対策をとりましょう。
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。