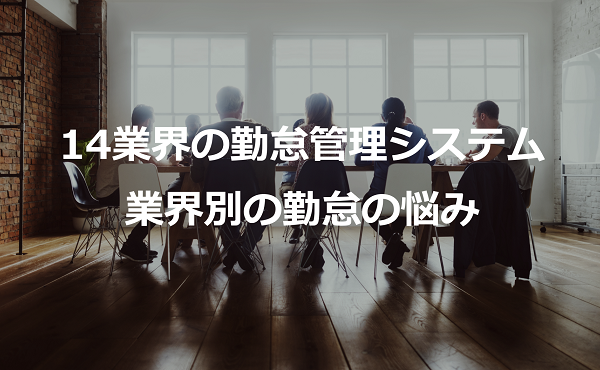
2019年4月に働き方改革法が施行され、自社の労働状況や勤怠管理を見つめ直そうとしている企業も多いのではないでしょうか。すべての業界に共通している課題もあれば、特定の業界に存在する課題もあります。
それに合わせて、特定の業界に特化した勤怠管理システムを提供しているサービスも多く存在しています。
本記事では、業界を問わず共通している勤怠の課題、特定の業界ならではの課題、各業界に特化した勤怠管理システムを紹介します。
数多くある勤怠管理システムの中から、自社に見合うシステムを探す際、何を基準にして選べばいいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
そのような方のために今回、社労士監修のもと、「勤怠管理システムの比較表」をご用意いたしました。資料には以下のことがまとめられています。
・勤怠管理システムの5つの選定ポイント
・社労士のお客様のシステム導入失敗談
・法対応の観点において、システム選定で注意すべきこと
お客様の声をもとに作成した、比較表も付属しています。これから勤怠管理システムの導入を検討されている方はぜひご活用ください。
目次
1. 勤怠管理の課題を解決できるシステム
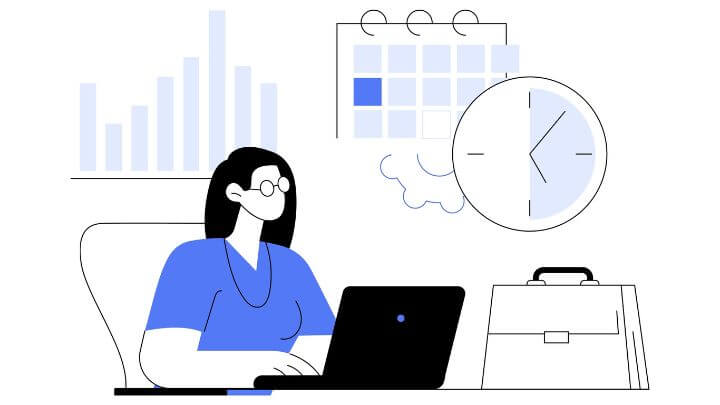
勤怠管理システムとは、従業員ごとの出勤時刻・退勤時刻を記録して、労働時間を客観的に把握できるシステムのことです。残業時間を自動的に算出したり、給与計算システムと連携できたりするものも存在します。勤怠に関する業務のほとんどを自動化できるため、人事担当者の負担を大きく軽減できるでしょう。
以下、業界ごとにおすすめの勤怠管理システムを紹介していますので、導入を検討している場合はぜひ参考にしてください。
1-1. 勤怠管理の必要性
適切な勤怠管理をおこなうことは、労働基準法によって定められた企業の義務です。企業は、従業員ごとの労働時間を正確に把握して、残業手当を支払ったり、有給休暇を付与したりしなければなりません。勤怠管理を怠ると、罰則が科せられる可能性もあるため注意しましょう。
また、従業員に対して正しい賃金を支払うためにも勤怠管理は重要です。残業時間や休日出勤時間をしっかりと把握して、割増賃金を含めた正しい賃金を支給しましょう。
2. すべての業界に共通する勤怠管理の課題

ここでは、勤怠管理に関するよくある課題を紹介します。
2-1. 集計業務に工数がかかっている
タイムカードで勤怠管理をしている場合、月末にタイムカードを集計しExcelに入力、そしてそのExcelを確認しながら給与計算をおこなわなければいけません。
拠点が複数あると、タイムカードを収集する作業にも時間がかかります。タイムカードの記載にミスがあれば、従業員に確認しなければいけないので、さらに時間がかかるでしょう。また、拠点によってシフトルールが違うのであれば、そのシフトルールごとに休憩時間の集計や給与計算をおこなう必要があります。
また、多様な職種の従業員が在籍している企業であれば、職種ごとに働く時間や、時給が異なるので、勤怠管理も給与計算も大変です。
2-2. 従業員ごとの正確な労働時間の把握が難しい
タイムカードで勤怠管理をしている場合、従業員の労働時間を確認したいとき、各拠点からタイムカードを回収しなければいけません。そのため、リアルタイムで労働時間を確認することが難しいです。働き方改革法が2019年4月から施行され、従業員の正確な残業時間をリアルタイムで把握することは重要です。
また、打刻漏れがあったとき、その従業員に連絡して打刻の修正をしてもらう必要があります。しかし、従業員は打刻した時間を忘れているケースも多く、正確な勤怠管理ができません。
2-3. 申請業務が面倒
打刻修正や残業申請を紙でおこなう場合は、従業員が申請書に記入し、それをどの上長から承認をもらえばいいのか確認し、その上長のところに直接持っていくことが必要です。
従業員は申請フローが複雑かつ、時間がかかってしまうことで、申請が面倒だと感じてしまいます。そのため、申請業務をおこなわずに、管理者が実際の労働時間を正確に管理することができないケースもあります。
2-4. シフト作成が面倒
シフトを作成するときは、従業員のスキル・希望・人員配置・出勤日数など、さまざまなことを加味してシフトを作成する必要があります。しかし、最適なシフトを作るには時間がかかります。人事担当者(管理者)は、シフト作成以外にも仕事があるので、シフト作成に時間をかけすぎるわけにはいきません。
また、2019年4月から施行された「働き方改革法」によって、退勤時間と翌日の出勤時間の間には、インターバルをあけることを推奨されています。シフト作成するときは、意識しないといけないことがたくさんあり、人だけで対応するのが難しいです。
2-5. 給与計算が面倒
アルバイトを多く雇っている企業であれば、従業員ごとに時給が異なるでしょう。その場合、給与計算するときに、従業員ごとに時給を変えないといけないので大変です。また、シフトルールが異なる店舗であれば、店舗ごとに異なる休憩時間や勤務時間などを給与計算時に考慮しないといけないので、ミスが多くなってしまいます。
給与は従業員にとって重要なものなので、ミスは許されません。そのため、確認作業も必要になってきます。確認作業の工数も入れると、給与計算は担当者にとってかなりの工数になるでしょう。
2-6. 法改正への対応が面倒
勤怠管理に関する法改正がおこなわれると、社内における勤怠管理方法を変更しなければなりません。紙やExcelで勤怠管理をおこなっている場合、書式や関数を変更するなど、対応に追われるケースもあるでしょう。
クラウド型の勤怠管理システムを利用すれば、法改正に合わせて自動でアップデートされるため、対応の手間はかかりません。法改正は随時おこなわれるため、人事担当者の負担を減らすためにも勤怠管理システムの導入を検討しましょう。
2-7. 有給休暇の管理が面倒
有給休暇を正しく管理できないことも勤怠管理における課題のひとつです。有給休暇は、継続勤務年数や所定労働日数に応じて正しく付与しなければなりません。また、1年で10日以上の有給休暇が付与される従業員については、5日以上取得させることが義務化されています。
アナログで勤怠管理をおこなっていると、付与日数を間違えたり、取得させるのを忘れたりするケースもあるでしょう。有給休暇を効率よく管理するためにも、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
3. 業界ごとに異なる勤怠管理の課題

ここでは、業界・職種ごとに異なる勤怠管理の課題について解説します。
3-1. 建設業の勤怠管理の課題
建設関連の会社は、複数の現場を抱えていることが多く、その現場ごとにタイムカード機を設置するのは現実的ではありません。そのため、日報で出勤時間と退勤時間を報告するケースが多いのではないでしょうか。
日報で勤怠管理をおこなうと、正確な出勤時間・退勤時間・残業時間がわからなかったり、休憩時間が把握できなかったりします。また、工期が短く設定されていたり、天候の関係で予定より進捗が遅れていたりすると、長時間労働になる傾向があります。
人手不足である建設業界では、正確な労働時間を把握し、業務を調整をしなければ、離職率が高まってしまうでしょう。
【関連記事】建設業向け勤怠管理システム比較9選|出勤簿|労働時間管理|日報管理
3-2. 病院の勤怠管理の課題
病院には医師や看護師などのさまざまな職種、早番や夜勤などさまざまな勤務形態があります。多様な職種や勤務形態があるため、打刻方法も状況に合わせて対応しなければいけません。職種や勤務形態に分けて集計しなければいけないので、多大な工数がかかります。
また、打刻漏れが見つかり、申請をあげてもらうにも、部門ごとで申請のあげ方が異なるケースもあるので大変です。
【関連記事】病院向け勤怠管理システム比較9選|出勤管理|看護勤務対応|医療クラウド
3-3. 介護業の勤怠管理の課題
介護業では、介護施設で働く人もいれば、ホームヘルパーとして訪問介護をおこなう人もいます。介護施設で働く人はタイムカードで勤怠を管理していることが多く、先ほど伝えた通り、集計作業に工数がかかります。
ホームヘルパーは日報で出退勤の管理をおこなっていることが多く、月末にまとめて回収している企業も多いです。その場合、出勤するたびに日報に出勤時間と退勤時間を記載しているわけではなく、月末にまとめて記載している従業員もいるでしょう。このような方法では、正確な勤怠管理はできませんし、リアルタイムでの勤怠管理が難しいです。
【関連記事】介護業向け勤怠管理システム比較10選|ヘルパーに対応|シフト管理
3-4. 営業職の勤怠管理の課題
営業職は、朝や夜に商談が入ることも多々あります。そのため、直行直帰するケースが多いでしょう。
直行(直帰)をおこなう場合には、事前に直行(直帰)申請書を書き、提出する必要があります。月に数回であればいいですが、週の過半数が直行直帰の場合、申請書を作成することに多くの工数がかかります。
また、承認する側も、毎月大量の申請書を確認する工数がかかります。
【関連記事】営業職向け勤怠管理システム比較8選|直行直帰に対応|タイムカード
3-5. 派遣元企業の勤怠管理の課題
派遣元企業は月末になると、「派遣社員が提出したタイムシートに間違いがないか」「未申請の残業をおこなっていないか」の確認作業をおこなう必要があります。また、タイムシートにミスがあった場合、タイムシートを差し戻して、修正してもらい、それを改めて確認しなければいけません。
また、派遣社員の勤務時間については派遣先が管理するため、派遣元が派遣社員の勤務時間や残業実績をリアルタイムで把握できません。
【関連記事】派遣会社向け勤怠管理システム比較10選|シフト管理|派遣社員対応|クラウド
3-6. 飲食業の勤怠管理の課題
複数の店舗を運営している飲食業の企業であれば、勤怠の集計業務が大変です。タイムカードで勤怠管理している場合、複数の店舗からタイムカードを集めないといけません。店舗ごとにシフトルールが違うケースもあるので、休憩時間や勤務時間の集計でミスをしてしまうことも多いでしょう。
また、シフト管理も煩雑です。急遽欠員が出た場合、その欠員を補うために、他店舗から応援を要請する必要があります。しかし、「どの店舗の、どの従業員が出勤できるか」が紙のシフト表ではひと目でわからないため、その確認に時間がかかってしまいます。
【関連記事】飲食店向け勤怠管理システムを徹底解説|多店舗展開やシフト管理にも対応
3-7. コールセンターの勤怠管理の課題
コールセンターは、多くの従業員を雇用しています。雇用形態は、アルバイト・契約社員・派遣社員などさまざまです。また、早朝や深夜に働く従業員もいるため、勤怠データの集計に時間がかかります。
さらに雇用形態ごとに給与計算を分けないといけないため、工数もかかります。管理が複雑になり、ヒューマンエラーが起こりやすいでしょう。
【関連記事】コールセンター向け勤怠管理システム比較8選|シフト管理・シフト作成
3-8. 警備業の勤怠管理の課題
警備業の打刻方法は電話連絡を使うケースが多いです。各警備員が上番、下番時に所属している会社に電話で連絡をします。
この電話連絡の時刻はほかの警備員と重なることが多く、電話連絡が管制室に集中します。そのため、従業員の「電話がなかなかつながらない」「上番の連絡ができないから、仕事を始めることができない」といった不満につながります。
また、管制側は電話対応だけではなく、勤怠情報をパソコンに入力したり、紙に書き控えたりといった作業が発生します。ほかにも、現場にたどり着けない従業員の対応をおこなうこともあるので、出退勤のピーク時はとても忙しくなるでしょう。
【関連記事】警備業向け勤怠管理システム比較9選|シフト管理|管制業務|上版下番報告
3-9. 保育園の勤怠管理の課題
保育業界では、規定の時間より長く働かされることが多いにも関わらず残業代が発生しないケースが多いようです。そのため、保育士の仕事は残業が多いうえに、給料が少ないので、離職につながってしまいます。
そうならないためにも、正確な残業時間の把握が重要になってきます。しかし、残業時間を正確に把握しようと思うと、系列保育園へのヘルプ業務も含めて、タイムカードの集計をおこなわなければいけません。労働時間の管理という点では、残業時間の上限が決まっているので、その上限を超えないように注意が必要です。毎日のリアルタイムな残業時間の把握が必要なので、集計作業が大幅に増えてしまいます。
【関連記事】保育園の勤怠管理システム比較8選|パート・正社員対応|シフト管理
3-10. 美容室の勤怠管理の課題
美容室は、曜日や時間帯によってお客様の数が大きく異なります。平日の昼間はお客様が少ないですが、週末はお客様が多いなど、忙しさに合わせて配置するスタッフの数やスキルを調整する必要があります。このようなスタッフの配置を手書きで管理するとなると、非常に大変な作業になります。
また、他店舗への応援が必要となるケースもあるでしょう。そのため、複数の店舗でバランスよくシフトを作成する必要があります。
【関連記事】美容室向け勤怠管理システムまとめ|勤怠・シフト作成業務を削減
3-11. 清掃業の勤怠管理の課題
清掃業の従業員は1日に複数の現場をまわることが多いので、その管理はさらに大変になります。出退勤だけではなく、1つの現場が終われば、完了の連絡がきて、次の現場に到着すれば仕事を開始する連絡がきます。
これらをすべて管理者が対応しなければいけないので相当な工数になります。また正規雇用者と非正規雇用者の雇用条件の違いを考慮するのも大変です。
契約によっては、移動時間が給与の対象になる場合もあれば、給与対象にならず、清掃をしている時間のみが給与対象になる場合もあります。移動にかかる交通費の計算も必要です。
【関連記事】清掃業向け勤怠管理システムまとめ|出退勤の連絡や正確な勤怠管理
3-12. 製造業・工場の勤怠管理の課題
製造業においては、数多くの工程に対してさまざまな職種の正社員・パートスタッフが関係します。そのなかで「どの工程で」「誰が」「何時間」関わったかを正確に把握しなければ、勤務時間や給与を算出することができません。
しかし、工場の場合、3交代などの時間交代制度をとり、さらに職種が細かく分かれていると、工数管理部分と勤怠管理の連携がおろそかになります。その結果、工数管理と勤怠管理をそれぞれ独立して管理したうえで組み合わせをおこなうため、管理が煩雑です。
【関連記事】製造業向け勤怠管理システム比較5選|工場の勤怠管理対応|工数管理
3-13. 運送業の勤怠管理の課題
運送業において、ドライバーの存在は欠かせません。短距離輸送で日帰り勤務の場合は、事業所でタイムカードを切るだけなので単純です。しかし、長距離輸送の場合、事業所に24時間以上戻らないことも多く、出退勤の手続きをおこなうことが難しくなります。
また労働時間の報告も本人の自己申告のため、正確な勤務時間を把握することは困難といえるでしょう。
【関連記事】運送業向け勤怠管理システム比較5選|夜間のドライバーの勤怠管理まで
3-14. 小売業の勤怠管理の課題
一般的に、店舗ごとに勤怠のデータを管理して、最終的に本部で集計するという管理方法が多いでしょう。ところが、シフトを埋めるためには、複数の店舗を掛け持ちする社員も必要になります。
勤怠管理の担当者にとっては、複数の店舗を見比べて集計するのは負担が重く、ミスが発生する可能性も高くなるのではないでしょうか。
【関連記事】小売業・サービス業向け勤怠管理システム比較|中抜け対応|就業管理の課題
4. 勤怠管理の課題を解決するポイント

勤怠管理の課題を解決するためには、以下のようなポイントを意識しましょう。
4-1. 勤怠管理に関するルールを見直す
勤怠管理に関するルールは、必要に応じて見直さなければなりません。社内で働き方改革などを進めている場合は、とくに注意が必要です。
たとえば、テレワークを導入することになった場合は、始業時刻や終業時刻を報告してもらうルールを新設する必要があるでしょう。正しく勤怠を把握できるよう、随時ルールを見直して、就業規則に記載しておくことが大切です。
4-2. 勤怠管理をアウトソーシングする
社内で勤怠管理をおこなうのが難しい場合は、アウトソーシングを検討しましょう。アウトソーシングとは、社内でおこなっていた業務の一部を外部の業者へ委託することです。
アウトソーシングすることで従業員の負担が減るだけではなく、他の重要な業務に集中できるようになります。新しく従業員を雇うより、コストを抑えながら業務効率化を実現できるでしょう。
4-3. 勤怠管理システムを導入する
勤怠管理の課題を解決するなら、便利なシステムを導入するのがおすすめです。勤怠管理システムを導入すれば、従業員ごとの労働時間や残業時間、有給休暇の取得日数などを一元管理できます。
勤怠状況をリアルタイムで把握できるため、残業が多すぎる場合に業務を調整したり、休暇の取得を促したりすることが可能です。さまざまな勤怠管理システムが存在するため、業種や職種などに合わせて最適なものを選びましょう。
5. システムを活用して勤怠管理の課題を解決しよう!

今回は、勤怠管理に関する課題や解決策を紹介しました。勤怠管理の課題を解決して業務効率化を図りたい場合は、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。システムを活用して勤怠に関する情報を一元管理し、担当者の負担を減らしましょう。
ただし、勤怠管理システムを導入するときは、自社が抱えている課題に合ったものを選ぶ必要があります。自社にどのような勤怠管理の課題があり、その課題を解決するにはどのような機能があればよいのか、しっかりと検討したうえで導入を進めましょう。







