
労働基準法には法定休日の定めがあるため、年間休日の最低ラインが決められます。原則として、年間休日は105日以上設けなければなりません。この記事では、労働基準法に基づく年間休日の考え方についてわかりやすく解説します。また、年間休日の数え方や、年間休日と有給の関係性など、年間休日の規定に関する注意点やポイントも紹介します。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法に基づく年間休日の最低ラインは105日?

労働基準法には休日に関して細かく規定がされています。労働基準法の法定休日と法定労働時間に基づくと、フルタイム労働者に対する原則的な年間休日の最低ラインは105日です。ここでは、労働基準法に基づく年間休日の最低ラインの考え方についてわかりやすく解説します。
1-1. 休日と休暇の違い
休日とは、会社の就業規則などに基づき、既に労働義務が免除されている日を指します。一方、休暇とは、本来働く義務があるけれど、申請によって労働義務が免除される日のことです。このように、休日と休暇は似た意味を持ちますが、違いがあるのできちんと押さえておきましょう。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類について詳しく解説
1-2. 法定休日とは?
労働基準法第35条に則り、原則として、毎週1日以上の休日を付与する必要があります。この休日のことを、法定休日とよびます。なお、4週4日以上の休日を与えることでも、法定休日の要件を満たすことが可能です。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
1-3. 休日の数え方
休日は、原則として、午前0時~午後12時までの24時間の暦日単位で付与しなければなりません。つまり、残業などにより、午前0時を超えて働くことになった場合、その日を休日としていても、休日を付与したことになりません。なお、交代制を採用している場合、一定の要件を満たせば、暦日でなく、継続して24時間の休む時間を与えれば、休日と認められることもあります(昭和63年3月14日付け基発1450号)。
休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことになりません。
引用:休憩・休日|厚生労働省
1-4. 年間休日の最低ラインは52日
最低でも週1日もしくは4週4日の法定休日を付与しなければなりません。1年間は約52週間(365日 ÷ 7日 = 52.14週)であるため、年間休日の最低ラインは52日と計算できます。つまり、年間休日が52日よりも少ない場合、原則として、労働基準法違反になるため注意が必要です。
1-5. 法定休日だけでは105日に達しない
労働基準法では、休日だけでなく、労働時間の定めもあります。労働時間第32条により、原則として、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせることはできません。法定労働時間に基づき、1日8時間働く場合、週に5日勤務すると上限40時間に達します。
1年52週と考えれば、260日(52週 × 5日)勤務することになり、休日は最低でも105日(365日 – 260日)が必要です。フルタイム労働者に対しては、法定休日のみでは、労働時間の条件を満たせません。そのため、法定休日に加えて、所定休日(法定外休日)も設定し、年間休日を105日以上にすることが求められます。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
2. 労働基準法に基づく年間休日の最低ライン105日の例外
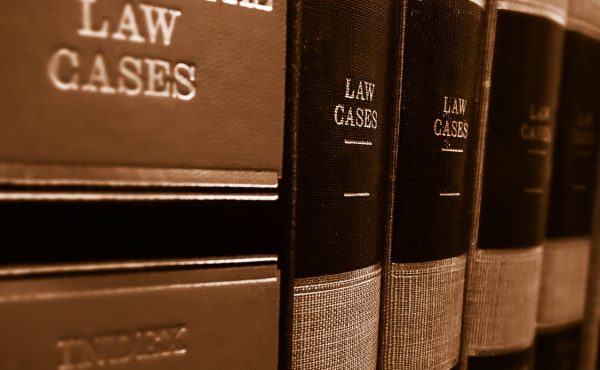
法定労働時間と法定休日の観点から、原則として、年間休日は105日以上付与する必要があります。しかし、年間休日が105日未満でも問題ないケースがあります。ここでは、労働基準法に基づく年間休日の最低ライン105日の例外について紹介します。
2-1. 労働時間が1日8時間以下と短い
年間休日が最低でも105日必要になるのは、1日の労働時間が8時間で週40時間勤務している場合です。一方、1日6時間の労働であれば、週に6日勤務しても36時間で週の上限にも達しません。そのため、パートやアルバイトなど、通常の従業員よりも短い時間で働く労働者の場合、年間休日は105日の最低ライン未満でも問題ない可能性があります。
2-2. 36協定を締結・届出している
突発的な業務の発生などで、残業や休日出勤をしなければならず、法定労働時間や法定休日の条件を満たせないケースもあるかもしれません。このような場合、事前に労働基準法第36条に基づく36協定を締結し、届出をすることで、時間外労働や休日労働が可能になります。
36協定を締結・届出すれば、月45時間・年360時間が残業時間の上限になるため、年間休日が105日を下回っても違法とはなりません。ただし、36協定に記載した条件が適用されるので、「法定休日の労働は1カ月1回まで」とした場合、月に2回以上休日労働をさせると違法になるので注意が必要です。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
2-3. 有給を年間休日に組み込む
年次有給休暇(有給)とは、労働基準法第39条の条件を満たした労働者が申請することで、給与をもらいながらも労働義務が免除される休暇を指します。年間休日には有給を含みませんが、有給を年間休日に盛り込んで計算することは問題がないとされています。そのため、年間休日を100日に設定し、残り5日を有給の消化にあてることで、年間105日の休日を設けられます。
労働基準法が改正されたことで、2019年4月1日より有給が年10日以上の従業員は、1年で5日消化することが義務化されました。そのため、年間休日105日に足りない5日分を有給にあてることになるのです。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(省略)
関連記事:有給休暇の計算方法は?日数・賃金の計算方法を詳しく解説
2-4. 変形労働時間制を採用している
変形労働時間制とは、月や年単位で労働時間を調整することで、1日10時勤務や週45時間勤務など、一時的に法定労働時間を超えられる働き方を指します。変形労働時間制を採用している場合、年間休日の最低ライン105日を下回っても問題ないことがあります。また、フレックスタイム制や裁量労働制といった働き方を導入している場合も、年間休日の最低ライン105日が適用されない可能性もあるので、正しく制度の仕組みを理解しておきましょう。
関連記事:変形労働時間制とは?残業の考え方や導入方法、注意点をわかりやすく解説
3. 労働基準法に基づく年間休日に関する注意点

労働基準法に基づく年間休日には、いくつか押さえておきたい気を付けるべき点があります。ここでは、労働基準法に基づく年間休日に関する注意点について詳しく紹介します。
3-1. 法定休日と所定休日の労働に対しては割増賃金を支給する
36協定を締結すれば、時間外労働や休日労働が可能になります。ただし、法定休日に働かせる場合や、所定休日に時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払いが必要になります。時間外労働と休日労働の割増率は、それぞれ次の通りです。
- 時間外労働(月60時間以下):25%以上
- 時間外労働(月60時間超え):50%以上
- 休日労働:35%以上
なお、法定休日の労働に時間外労働が適用されることはありません。たとえば、法定休日に9時間働いた場合、9時間分の休日労働の割増賃金を支給することになります。ただし、時間外労働と深夜労働、休日労働と深夜労働は重複するケースがあるので注意しましょう。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
3-2. 就業規則に休日を明記する
労働基準法第89条に則り、常時10人以上の労働者を雇用している会社は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則には、休日の内容を含める必要があります。いつを休日とするのかなど、細かく休日のルールを設定しておくことで、労働者とのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
3-3. 管理監督者には年間休日の制限が適用されない
労働基準法第41条に基づき、管理監督者に該当する労働者は、労働時間や休日の規定が適用されないため、年間休日の制限もありません。そのため、管理監督者は、休日の規定に関係なく、自由に休み、働くことができます。ただし、相応しい権限や賃金が与えられていない場合、管理監督者とみなされず、通常の従業員と同様の年間休日を与えなければ違法になるので注意しましょう。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 (省略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 (省略)
関連記事:労働基準法第41条第2号の「管理監督者」の意味や特徴を詳しく解説
3-4. 労働基準法に違反すると罰則が課せられる
労働基準法には罰則規定もあります。労働者に正しく年間休日を与えず、法定休日の規定に違反すると、労働基準法第119条に則り、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります。また、労働基準法に違反した企業として、厚生労働省のホームページなどに会社名が公表され、社会的信用を損なうリスクもあるので気を付けましょう。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第三十五条、(省略)の規定に違反した者
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
3-5. 高度プロフェッショナル制度の年間休日は104日以上
労働基準法第41条の2に基づく高度プロフェッショナル制度を導入する場合、当該制度を採用する労働者に対しては、労働時間や休日、休憩、割増賃金といった規定が適用されなくなります。しかし、104日以上の年間休日および4週4日以上の休日を与えることが義務付けられています。高度プロフェッショナル制度を導入する場合、その他にも、さまざまな要件があるためきちんと確認しておくようにしましょう。
第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。
(省略)
四 対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。(省略)
引用:労働基準法第41条の2一部抜粋|e-Gov
4. 労働基準法に基づく年間休日を守るためのポイント
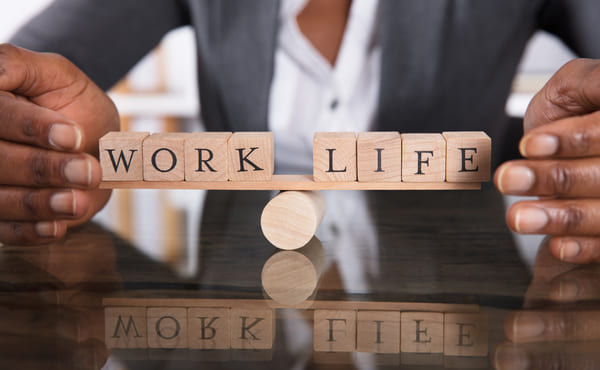
年間休日を正しく遵守しなければ、労働基準法により懲役や罰金などの罰則が課せられる恐れがあります。ここでは、労働基準法に基づく年間休日を守るためのポイントについて詳しく紹介します。
4-1. 年間105日は休日数が少ない
週休2日制にすれば、年間休日の最低ラインをクリアすることができます。この場合、夏季休業や年末年始休暇、国民の祝日、ゴールデンウイークなどは考慮していません。そのため、一般的には休日は少ない傾向にあるといえるでしょう。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、令和4年1年間の年間休日総数の企業平均は110.7日となっており、105日よりも多い結果でした。労働者1人あたりの平均では115.6日で、さらに多い結果となっています。昨今はワークライフバランスの充実を求める従業員、求職者も多い傾向にあるため、年間休日を増やすことは企業イメージの向上につながります。
4-2. 独自の休暇制度を導入する
年間休日を増やす方法として、年末年始や祝日を休みに設定するだけでなく、独自の休暇制度を導入する方法もあります。たとえば、リフレッシュ休暇が挙げられます。リフレッシュ休暇とは、従業員の希望するタイミングに一定期間休暇を取得できる制度です。
繁忙期がバラバラで、夏季休暇や冬季休暇を設けるのが難しい場合、リフレッシュ休暇を導入してみるのも一つの手です。また、結婚や葬儀などに休みを取得できる慶弔休暇や、誕生日や記念日に休みを取れるアニバーサリー休暇など、従業員のニーズにあわせて独自の休暇制度の導入を検討してみましょう。
4-3. 振替休日や代休を活用する
仕事には急なトラブルが付き物であり、どうしても残業や休日出勤をしなければならないケースはよくあります。法律の要件を満たしていても、法定外労働が多くなれば、従業員の健康が悪化するリスクを高めます。そこで、休日出勤の代わりに休みを取得できる、振替休日や代休を設けることも推奨されます。
振替休日とは、休日出勤が発生する前に、休日と勤務日を入れ替えておく制度のことです。一方、代休とは、休日出勤が発生した後に、代わりに休みが取得できる制度を指します。振替休日と代休は違う制度であり、どちらを採用するかで割増賃金の計算方法などにも影響が出るため注意しましょう。
関連記事:代休の定義とは?振休・有給との違いや月またぎが発生するケースについて解説!
5. 労働基準法の年間休日に関連するよくある質問

ここでは、労働基準法の年間休日に関連するよくある質問への回答を紹介します。
5-1. 週の起算日は日曜日?
法定休日の計算をする場合、週の起算日の考え方が重要になります。就業規則に明記すれば、その日を週の起算日とすることが可能です。たとえば、月曜日を週の起算日とする場合、月曜日から日曜日までの間に、1日以上の休日を与えれば、法定休日の条件を満たすことができます。
なお、週の起算日は指定しなくても問題ありません。しかし、その場合、自動的に日曜日が週の起算日となります。労使間でトラブルを招かないよう、週の起算日や休日の数え方などは、就業規則にきちんと記載し、従業員に正しく周知しておくことが大切です。
5-2. 休日の買取はできる?
法定休日は、法律で定められた休日であり、休日を付与できないからといって買い取ることはできません。ただし、年次有給休暇であれば、退職時に有給が残っている場合などに限り買取が可能です。また、労働基準法第37条に基づき、一定の要件を満たせば、時間外労働(月60時間超え)の割増賃金を支払う代わりに、代替休暇を与えることもできます。
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
関連記事:有給休暇の買取は違法?退職時の対処や買取の計算について解説
5-3. 副業やダブルワークをしている場合の年間休日のルールは?
労働基準法第38条に則り、副業やダブルワークをしている場合、労働時間は通算して考える必要があります。しかし、休日の合算に関しては定められていません。そのため、A社とB社でダブルワークしている場合、A社とB社それぞれが法定休日をきちんと与えていれば違法になりません。つまり、労働者は、A社が法定休日と設定している日に、B社で働くことも可能です。
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
6. 労働基準法に基づく最低ライン以上の年間休日を付与しよう!

労働基準法に基づき、原則として、最低でも105日以上の年間休日を設ける必要があります。ただし、労働時間が短い場合や、36協定を結んでいる場合などは、年間休日が105日を下回っても問題ない可能性があります。しかし、年間休日が少ないことは、従業員満足度の低下につながりやすいです。「年末年始を休日に設定してみる」「リフレッシュ休暇を設けてみる」など、労働者が働きやすい環境を整備するため、年間休日を増やせるよう努力しましょう。
労働基準法総まとめBOOK









