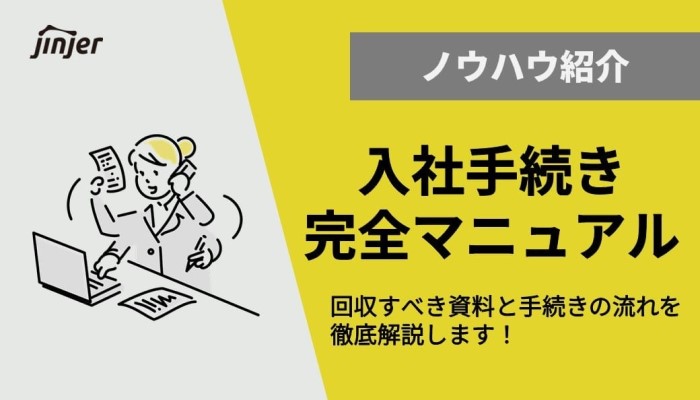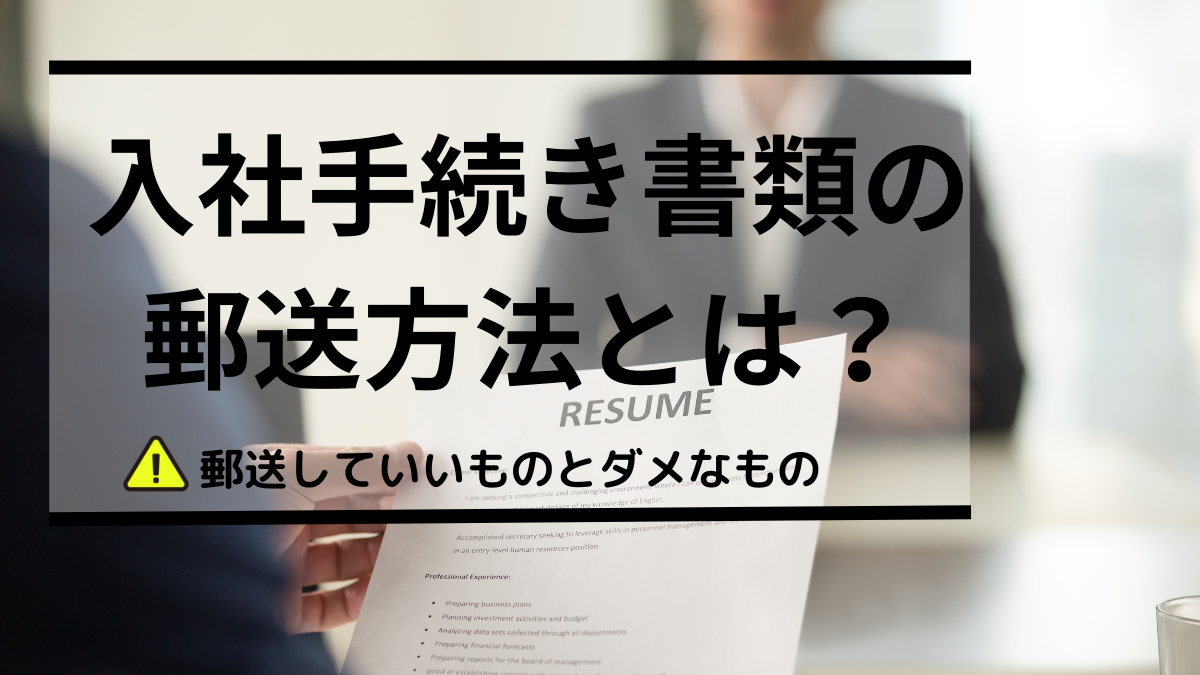
入社手続きを滞りなく進めるためにも、手続きに必要な書類を内定者へ確実に受け渡しすることが重要です。また、入社手続き書類の中には個人情報も含まれることから、郵送で送る場合にはいくつか注意しておくべき点があります。本記事では、入社手続き書類の中で郵送できる書類や、その郵送方法、添え状の書き方についてわかりやすく解説します。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きを行いたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
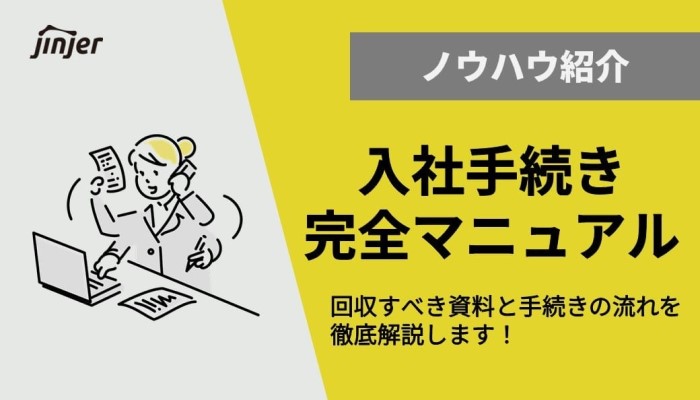

目次
1. 入社手続きの書類は郵送できる?

入社手続きの書類を郵送することはできます。入社手続きの書類を郵送することで、さまざまなメリットが得られます。しかし、注意点もあります。ここでは、入社手続きの書類を郵送するメリットと注意点それぞれについて詳しく紹介します。
1-1. 入社手続きの書類を郵送するメリット
入社手続きの書類を郵送することで、直接手渡しする必要がないため、遠方に住んでいる人に対しても効率よく届けることができます。会社側の担当者はオフィスで、労働者は自宅で書類の作成業務ができるため、手続きの負担を減らすことにもつながります。また、郵送手段は複数あり、追跡可能な方法を選べば、紛失などのリスクを減らすことも可能です。
1-2. 入社手続きの書類を郵送する注意点
入社手続きの書類を郵送する場合、直接手渡しする場合と比べると、紛失のリスクがあります。そのため、社外秘の情報を含む場合や個人情報を含む場合、手渡しで渡すことが推奨されます。また、郵送には紙代や印刷代に加えて、封筒代や切手代などの郵送費用がかかります。膨大な人数に対して郵送する場合、コストの負担が大きくなる恐れもあります。
さらに、郵送の場合、タイムラグが生じることで、実際に手元に届くまで時間を要する可能性があります。入社手続きの書類のなかには、期限が定められており、素早く手続きしなければならないものもあります。このように、入社手続きの書類の郵送にはメリットだけでなく、デメリットもあります。そのため、郵送に向いている書類とそうでない書類に区分して、最適な手段を選び、手続きをすることが大切です。
関連記事:【完全版】入社手続きマニュアル!手順や必要書類、注意点を徹底解説!
2. 入社手続きの書類で郵送できる書類

入社手続きの書類のうち、再発行もできるような書類の場合、郵送しても問題ないでしょう。ここでは、入社手続きの書類で問題なく郵送できる書類について詳しく紹介します。
2-1. 内定通知書
内定通知書とは、企業が応募者に対し採用の承諾をしたことを知らせるための書面です。書面の様式は企業によって異なりますが、記載されている内容は一般的に次の通りです。
- 応募へのお礼
- 採用内定の通知
- 入社予定日
- 提出書類の案内と提出期限
- 問い合わせ先 など
法的に書面を発行する義務はないため、企業によっては口頭やメールなどで済ませるところもあります。ただし、応募者とのトラブル防止や安心感を与えるといった意味合いから、内定通知書を書面で発行するのが一般的であり、郵送して交付するのも一つの手です。
2-2. 内定承諾書
内定承諾書とは、応募者が企業に対して内定を承諾する旨を知らせるための書類です。企業によって「入社承諾書」や「入社宣誓書」など呼び方が異なることもあります。内定承諾書の記載事項については主に次の内容が記載されます。
- 内定を承諾する旨
- 内定に関する誓約事項
- 内定の取消事由に該当する場合異議を唱えない旨
- 応募者の署名・捺印欄 など
内定承諾書も法律で義務付けられた書類でないので、郵送で送付しても問題ないでしょう。内定承諾書には、応募者の署名・捺印欄を設けて郵送します。応募者には、内定承諾書に署名・捺印のうえ、返信用の封筒に同封し、返信してもらうよう、送付状や添え状などにも明記しておきましょう。
2-3. 労働条件通知書・雇用契約書
労働条件通知書とは、賃金や労働時間、勤務場所、業務内容など労働条件に関する事項が記載された法律で交付が義務付けられた書面です。一方、雇用契約書とは、労使双方が労働条件に合意したことを証明するための契約書です。
労働条件通知書や雇用契約書は重要な書類ですが、労働開始前に送付し、雇用契約を結べばよいため、時間的に余裕があることから、郵送で手続きするケースもよくあります。しかし、社外秘の情報が含まれることから、郵送で送付する場合、追跡可能な方法で送ることが大切です。また、労働条件通知書や雇用契約書は電子化もできるので、要件を満たせるのであれば電子交付することも検討しましょう。
関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!
3. 入社手続きの書類で郵送を控えるべき書類

入社手続きの書類の中には、「紛失したら大きなトラブルを生む」「手続きまでに時間的な余裕がない」といった書類もあります。このような書類の場合は、郵送を控えるべきといえます。あくまでも郵送を控えるべきであって、絶対に郵送できないわけではないので注意が必要です。ここからは、入社手続きの書類で郵送を控えるべき書類について詳しく紹介します。
3-1. 給与振込先口座情報
給与の振込を銀行口座でおこなっている企業も少なくないでしょう。銀行振込をするには、あらかじめ労働者の同意を得たうえで、振込先情報を提示してもらう必要があります。通帳やキャッシュカードのコピーを提出してもらう場合、紛失すると、悪用されるリスクもあります。そのため、直接手渡しで提出してもらうことが推奨されます。
3-2. 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、被保険者番号が記載された雇用保険の加入状況を証明するための書類です。過去に雇用保険に加入したことがある労働者の場合、雇用保険被保険者証を提出してもらう必要があります。
雇用保険の入社手続きをする場合は、雇用保険被保険者証を基に、雇用保険被保険者資格取得届を作成し、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。スピーディーに手続きしなければならないことに加え、雇用保険被保険者証を紛失すると再発行に時間や手間がかかることから、郵送でなく、手渡しで提出してもらうようにしましょう。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?発行方法や再発行のやり方、退職日・転職の際の手続きを紹介!
3-3. 年金手帳・基礎年金番号通知書
年金手帳とは、年金加入記録を証明するために用いられる書類です。現在では年金手帳が廃止されたため、年金手帳でなく、基礎年金番号通知書を保有している人もいます。
社会保険(厚生年金保険)の手続きをするには、年金手帳や基礎年金番号通知書に記載されている基礎年金番号が必要です。また、基礎年金番号を記載した被保険者資格取得届を入社した日から5日以内に提出しなければなりません。紛失などのトラブルを防ぎ、スムーズに手続きをするためにも、年金手帳や基礎年金番号通知書は手渡しで提出してもらうのが望ましいです。
3-4. 健康保険被扶養者異動届(第3号被保険者関係届)
健康保険被扶養者異動届(第3号被保険者関係届)とは、家族を被扶養者にする場合などに提出が必要になる書類です。被扶養者の手続きをするには、事実が発生した日(入社日など)から5日以内に健康保険被扶養者異動届(第3号被保険者関係届)を日本年金機構や健康保険組合に届け出る必要があります。
このように、健康保険被扶養者異動届(第3号被保険者関係届)の手続きは速やかにおこなわなければなりません。また、添付書類が必要になることもあります。そのため、郵送でなく、手渡しで提出してもらうことが推奨されます。
関連記事:国民年金第3号被保険者関係届とは?電子申請の方法や記入例・添付書類も解説!
3-5. 扶養控除等申告書
扶養控除等(異動)申告書とは、年末調整を受ける際に扶養控除などの適用を受けるために必要な書類です。扶養控除等申告書には、労働者とその家族の個人情報が記載されます。なお、扶養控除等申告書は、その年の最初に給与を受け取る日のまでに提出してもらいますが、通常は入社時に提出してもらいます。なぜなら給与計算をする時に扶養控除申告書の情報に基づいて行うためです。個人情報を保護するためにも、郵送でなく、手渡しで提出してもらうようにしましょう。
3-6. 前職の源泉徴収票
前職の源泉徴収票は、その年に転職した場合、転職先で年末調整を受けるために必要となります。転職先に提出する前職の源泉徴収票は原本である必要があります。紛失した場合のリスクも考え、郵送でなく、直接手渡しで提出してもらうのが望ましいです。
関連記事:年末調整にマイナンバーは必要か?記入を拒否された場合についても解説!
3-7. マイナンバー
会社側は労働者の社会保険や税金に関する手続きのため、マイナンバーの情報が必要です。そのため、入社手続きの書類の一つとして、マイナンバーの情報を提供してもらう必要があります。マイナンバーは重要な個人情報であるので、郵送でなく、手渡しで提出してもらうことが推奨されます。なお、マイナンバーの情報提供を拒否する労働者に対して、強制はできないことを押さえておきましょう。
郵送できる書類とそうでない書類を判断するためにも、入社手続きにはどのような書類がどのタイミングで必要になるか把握しておきましょう。当サイトでは、入社手続きに必要な書類と入社手続きの手順をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。入社手続きの手順に不安がある方は、こちらのフォームから資料をダウンロードしてご確認ください。
4. 入社手続きの書類を郵送する方法

入社手続きの書類は、企業や内定者にとって重要な書類であるため、確実に受け渡しができるようにしなくてはいけません。ここでは、入社手続きの書類を郵送する方法について詳しく紹介します。
4-1. 封筒はA4サイズが便利
入社手続きの書類は、A4サイズの用紙で作成されるのが一般的です。書類を送付する際は、折り目をつけないようにするため、A4サイズの封筒を用意して送付しましょう。封筒を作成する際に注意したいポイントは次のとおりです。
- 宛名は縦書きで記載。宛先の住所・氏名を間違えないよう十分注意する
- 他の書類と区別がつくよう表面の左下に「入社書類一式在中」と赤字で記載
- 裏面に差出人の住所・会社・部署名等を記載する。
(会社名・住所が印字された封筒を使用する場合は裏面の記載は不要) - 切手を貼付する際は、料金が不足しないよう気を付ける
また、雨に濡れて書類が汚れてしまわないよう、透明のクリアファイルに書類を入れて送付するようにしましょう。
4-2. 返信用の封筒を同封
内定承諾書など一部返信が必要となる書類もあるため、切手を貼った返信用封筒も同封します。返信用の封筒を同封することは、相手の手間を省くだけでなく、誤送付を防ぐ効果もあります。
返信用の封筒を作成する際に、表面の宛名の敬称を何と入れるべきか悩むところですが、部署名または担当者名に続けて「行(いき)」と入れるのが一般的です。裏面には何も記載せずに同封します。送り状には、同封の返信用封筒で書類の返信を依頼する旨の一文を忘れずに入れておきましょう。
4-3. 追跡サービスが利用できる形式で発送する
入社手続きの書類は重要な書類であるため、配達されたかどうかを確認できる追跡サービスが利用できる方法で送ることが望ましいです。たとえば、簡易書留や一般書留、特定記録郵便、レターパックなどが挙げられます。それぞれの特徴は次の通りです。
・一般書留
引受から配達までの過程が記録されます。破損や紛失時には実損額が賠償されます。
・簡易書留
引受と配達のみ記録。破損や紛失時には5万円まで賠償されます。郵便料金は一般書留と比べて割安です。
・特定記録郵便
引受のみが記録されます。郵便受けに配達されたかどうかWEB上で確認することができます。郵便料金にプラス210円で利用することが可能です。
・レターパック
A4サイズ4㎏までであれば、全国一律料金で配達してもらえるサービスです。レターパックプラスは対面にて配達、郵便料金は600円です。一方、レターパックライトは郵便受けに投函となり、郵便料金は430円です。いずれも、配達状況をWEB上で確認することができます。なお、レターパックを利用するには、専用の封筒を購入する必要があります。
内定通知書など、入社手続きの書類の中には信書も含まれます。信書に該当する場合、宅急便やメール便などの方法で送ることはできないので注意しましょう。
4-4. 入社手続きの書類を郵送する際に添え状は必要?
入社手続きの書類を郵送する際は、添え状をつけるのが一般的です。添え状は、いつ・誰が・どのような書類を送付したか知らせるだけでなく、会社と内定者のコミュニケーションを図る役割もあります。丁寧でわかりやすい文面であれば、内定者の会社に対する信頼感は高まります。添え状には、次のような項目を記載します。
- 送付年月日
- 宛名
- 差出人
- 頭語と結語
- 挨拶文
- 記書き
- 送付内容・部数
送付内容は、内定者が迷わないように返信が必要なのか、自宅で保管するものなのか、入社日当日に持参するものなのかなどを明記しておきましょう。返信が必要な書類は、記入例なども同封し、期日も明らかにしたうえで送付します。また、問い合わせ先となる担当者の氏名も記載しましょう。入社手続きでは、内定者が安心して手続きを進められるよう配慮することが大切です。
関連記事:入社手続きに必要な書類一覧!手続きの流れやメール・添え状などのルールを紹介
5. 入社手続きの書類を送付する方法
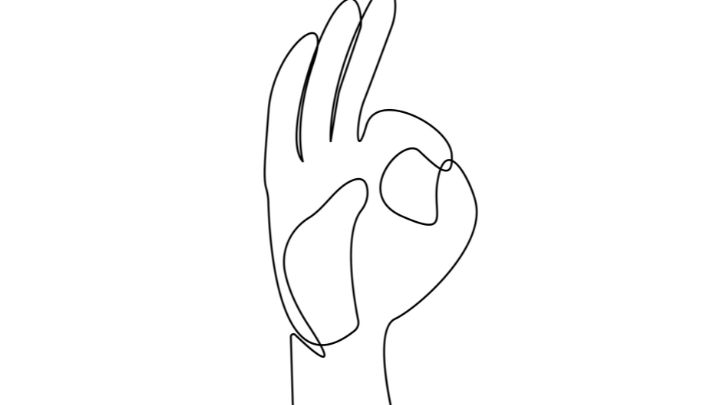
入社手続きの書類を送付する方法には、郵送以外にも、「直接手渡しする」「メールやシステム上で送る」といったやり方があります。ここでは、それぞれの方法のメリットや注意点について詳しく紹介します。
5-1. 直接手渡しする
入社手続きの書類を直接手渡しする場合、確実に受け渡しができるので、郵送途中などに紛失したり、電子上で不正アクセスを受けたりするリスクを減らすことができます。また、受け取ったらすぐに手続きができるので、タイムラグが生じません。書類に不備があったとしても、その場で指摘や修正もできるため、期限が近い書類は手渡しすることが推奨されます。
ただし、直接手渡しで入社手続きの書類を提出するには、労働者がオフィスまで足を運ぶなど、時間がかかります。また、会社の担当者と労働者のスケジュールを調整しなければならず、手間もかかります。遠方に住んでいる労働者の場合や、スケジュール調整が難しい場合は、郵送やメールなどでやり取りするのがおすすめです。
5-2. メールやシステム上で送付する
昨今ではIT技術の進歩やクラウドサービスの登場により、メールやシステムを使って入社手続きの書類を電子化して送付することもできるようになっています。メールやシステム上で入社手続きの書類を送付すれば、紙代や印刷代、郵送費用などのコストを削減することが可能です。また、書類の管理もシステム上でおこなえるので、物理的な保管スペースを減らし、検索機能などを活用して効率よく入社手続きの書類を管理することができます。さらに、遠方に住んでいる場合や、リモートワークで働いている場合にも、柔軟に対応することが可能です。
ただし、メールやシステムを利用して入社手続きの書類を送付する場合、PCやスマホなどのデバイスやネットワーク環境の整備が不可欠で、ITツールに不慣れな労働者にとっては使いにくく、ストレスに感じる可能性もあります。また、セキュリティ対策を徹底しなければ、不正アクセスや改ざんなどのリスクもあります。このように、入社手続きの書類の電子化は確かに便利ですが、必要に応じて手渡しや郵送にも対応できるようにすることが大切です。
6. 入社手続きの書類の郵送に関するよくある質問

ここでは、入社手続きの書類の郵送に関するよくある質問への回答を紹介します。
6-1. 入社手続きの書類が返送されたら?
内定者から入社手続きの書類が返送されてきたら、書類ごとにチェックします。内定承諾書や雇用契約書は、内定者の署名・捺印があることを確認してからファイリングしましょう。また、返送された書類には、内定者からの添え状が同封されているかもしれません。添え状と、同封された書類が一致しているかを確認してください。返信された書類に不備がなければ、会社のルールに従って外部に漏れないよう正しく保管することが大切です。
6-2. 入社手続きの書類の押印の種類に指定はある?
入社手続きの書類への押印は、実印でなく、認印でも問題ありません。しかし、信頼性や確実性を担保するため、身元保証書など実印が求められるケースもあります。その場合、実印で押印した書類に加えて、印鑑証明書も送付してもらうようにしましょう。実印でなければならない場合、間違って認印で押印しないよう、送付状や添え状などにもその旨を記載しておくことが大切です。
7. 入社手続き書類を郵送する際は送り方や書類の種類に注意!

入社手続きの書類は郵送で送付することができます。しかし、遅延や紛失のリスクもあるので、重要な書類は直接手渡しすることが推奨されます。また、確実に書類が届いたかどうか把握できるようにするため、追跡可能な郵送方法を採用することが大切です。スピーディーに入社手続きをするために、クラウドサービスを導入するなどして、入社書類の電子化を進めてみるのもおすすめです。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きを行いたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。