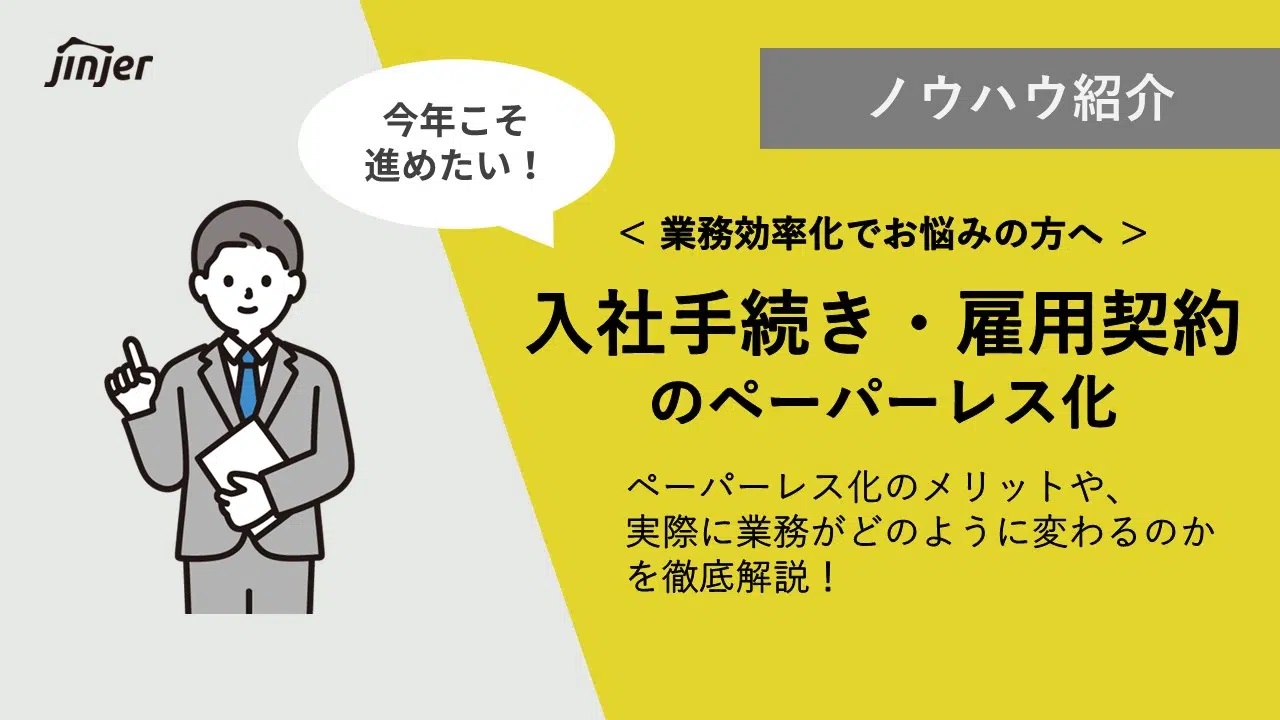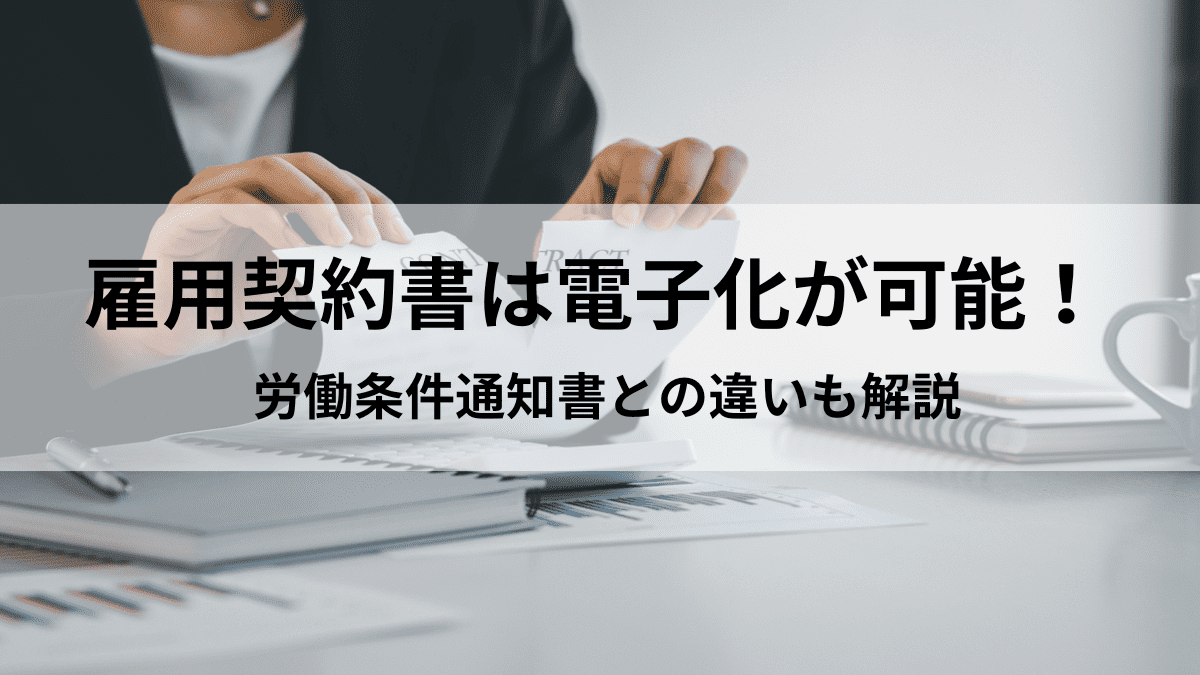
2019年4月1日から労働条件通知書の電子化が解禁されたことで、採用活動のオンライン化が進んでいます。この記事では、雇用契約書は電子化できるかどうかや、その要件をわかりやすく解説します。また、雇用契約書を電子化するメリット・デメリットやその方法・手順、電子契約システムの選び方についても紹介します。
「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理業務を楽にしたいが、どうしたらいいかわからない…」
とお困りの方におすすめなのが、入社手続き・雇用契約の電子化です。入社手続き・雇用契約を電子化すると、入社手続きを郵送ではなくシステム上で行えるため、差戻や修正書類の回収にかかる時間や工数を削減することができます。
「便利なのはわかったけど、どうやって電子化すればいいか分からない」という方に向けて、
当サイトでは雇用契約・入社手続きを電子化する方法や、電子化によって入社手続き業務がどのように効率化されるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 雇用契約書は電子化できる?

2019年4月1日から労働条件通知書の電子化が解禁されました。雇用契約書も電子化できるのか気になる人は少なくないでしょう。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書の違いを説明したうえで、雇用契約書は電子化できるのかどうか詳しく紹介します。
1-1. 雇用契約書とは?
雇用契約書とは、民法第623条に基づき、雇用者と労働者の間で取り交わす契約書のことです。雇用契約書の交付は法律で義務付けられているわけではありません。そのため、雇用契約は、口頭での契約でも成立します。しかし、口頭の場合、後で「言った、言っていない」と労使間でトラブルに発展する恐れがあります。このような事態を未然に防ぐためにも、労働条件に同意したことを書面に証拠として残せるよう雇用契約書がよく用いられます。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。引用:民法623条|e-Gov
関連記事:雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや雛形などの書き方について徹底解説
1-2. 雇用契約書と労働条件通知書との違い
労働条件通知書とは、会社側が新たに採用した従業員に対して労働条件を明示するために用いられる書類を指します。労働基準法第15条「労働条件の明示義務」により、雇用契約書と異なり、労働条件通知書の交付は法律で定められています。
なお、労働条件通知書だけでは、労働条件を明示できても、同意が得られたことを証明するのが難しいです。労使間で合意があったことを証明するため、雇用契約書が使用されます。このように、雇用契約書と労働条件通知書は、記載事項や内容が似ていますが、使用される目的に違いがあります。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説
1-3. 雇用契約書は電子化できる!
労働契約法第4条によって雇用契約書は「できる限り書面により確認するもの」と定められていますが、そもそも雇用契約書には書面交付義務がなく、かつてより電子化してデータで提供しても何ら問題ありませんでした。
これまで労働条件通知書は書面での交付が義務付けられていました。そのため、労働条件通知書は紙で、雇用契約書は電子データで提供することが面倒なため、電子化が進まない現状もありました。しかし、2019年4月1日から労働条件通知書の書面交付義務が緩和され、次の要件すべてを満たせば、労働条件通知書も電子化して交付することができるようになりました。
- 労働者の同意があること
- 労働者本人のみを対象とした手段で送信すること(電子メールなど)
- プリントアウト可能な状態にすること
これにより、労働条件通知書と雇用契約書の両方を電子化して提供できるようになり、より雇用契約書の電子化が進むようになっています。
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条 (省略)
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説
1-4. 【補足】雇用契約と労働契約の違い
雇用契約と似ている言葉として労働契約という言葉もあります。この2つは、定義している法律に違いがあります。雇用契約は民法で、労働契約は労働契約法で定義されている言葉ですが、意味に関してはほぼ同義として捉えて問題ないでしょう。
関連記事:労働契約とは?雇用契約との違いや締結・更新・変更時における解説
2. 雇用契約書の電子化の要件
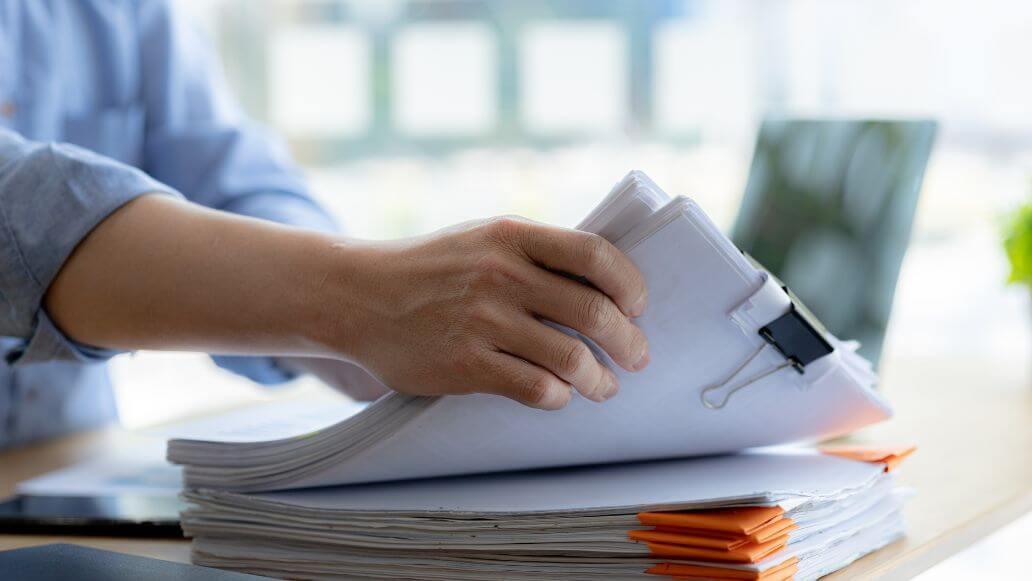
雇用契約書を電子化する場合、電子帳簿保存法の「電子取引データ」の要件を満たす必要があります。ここでは、雇用契約書を電子化するための要件について詳しく紹介します。
2-1. 真実性の要件
真実性の要件とは、電子データが正確かつ完全に記録され、改ざん・紛失を防止するための要件のことです。雇用契約書を電子化できたとしても、改ざんされたことを見破れなければ、簡単に改変されトラブルを招くことになってしまいます。電子帳簿保存法の真実性の要件を満たすためには、次のいずれかの条件を満たすことが必要とされています。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領
- 速やかにタイムスタンプを付与
- データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないス
テムを利用- 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け
なお、受領した電子データは、原則としてそのまま保存しなければなりません。しかし、電子データで保存できていれば、書面に出力し、管理しても問題ないとされています。
2-2. 可視性の要件
可視性の要件とは、保存されている電子データの書類を必要に応じてすぐに検索・表示できるようにするための要件を指します。たとえ雇用契約書を電子化し、信頼性が担保されていても、必要なときに出力できなければ、証拠として機能しません。電子帳簿保存法の可視性の要件を満たすには、次のような措置が必要とされています。
- 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。)
- 見読可能装置の備付け等
- 検索機能の確保
参考:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。|国税庁
なお、バックアップは要件とされていませんが、経年劣化などのリスクを考え、電子データのバックアップを保存しておくことも推奨されています。
2-3. 雇用契約書の保管期間を守る
労働基準法第109条により、雇用契約書は当該労働者が退職した日(死亡した日)を起算日として5年間保管しなければなりません。これは紙だけでなく、電子化された雇用契約書も同様です。そのため、雇用契約書を電子化する場合、長期間にわたってシステムやサーバー上に保管できるような体制を構築する必要があります。
なお、経過措置により、当面の間は5年間でなく、3年間の保存期間でも問題ないとされています。しかし、経過措置はいつ終了するのか未定なため、可能な限り5年間保管しておくようにしましょう。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
関連記事:雇用契約書の保管期間は5年!経過措置の内容やほかの書類についても紹介
3. 雇用契約書を電子化するメリット

雇用契約書を電子化することで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、雇用契約書を電子化するメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 生産性が向上する
紙の雇用契約書を使用している場合、送付や返送に手間がかかり、実際に契約が締結するまでに時間を要するケースがあります。雇用契約書を電子化すれば、メールなどで簡単に送付・返送できるので、スピーディーに雇用契約を締結することが可能です。このように、雇用契約書を電子化することで、契約業務の生産性の向上が期待できます。
3-2. コストを削減できる
紙の雇用契約書を使って雇用契約を締結する場合、印刷代や郵送代などのコストがかかります。雇用契約書を電子化すれば、これらのコストを削減することが可能です。また、雇用契約書を書面で保管する必要がないため、書類を入れるキャビネットなどのオフィス用品の購入費用も削減することができます。
3-3. 雇用契約書の管理を効率化できる
紙媒体の雇用契約書を使用している場合、雇用契約を締結した後、その契約書をファイルなどに入れて管理する必要があります。従業員数が多い企業の場合、必要な雇用契約書を探そうとする際に、時間や手間がかかる可能性もあります。
雇用契約書を電子化すれば、電子データを使ってシステム上で雇用契約書を管理することが可能です。また、従業員ごとに契約日や契約ステータスを管理できるため、検索機能を活用して、素早く見つけたい雇用契約書を探し出すことができます。
3-4. リモートワークに対応できる
紙の雇用契約書を利用する場合、印刷・押印・署名・郵送などの手続きのために、担当者はオフィスへの出社が求められます。雇用契約書を電子化することで、雇用契約に関する手続きをすべてシステム上でおこなうことができるようになります。そのため、雇用契約の締結のためだけに、わざわざ出社する必要がなくなり、リモートワークを推進することが可能です。
3-5. コンプライアンスを強化できる
紙の雇用契約書を使用している場合、紛失・盗難のリスクがあります。また、誰が閲覧したかなどを管理できないため、不正が発生したときの対応に遅れが生じる恐れもあります。
雇用契約書を電子化すれば、システム上で管理できるので、バックアップ体制を強化することで、紛失や盗難といったセキュリティリスクを減らすことが可能です。また、閲覧した場合や、改変した場合、その記録がログとして残るため、不正が起こったときでも素早く対応することができます。
4. 雇用契約書を電子化するデメリット
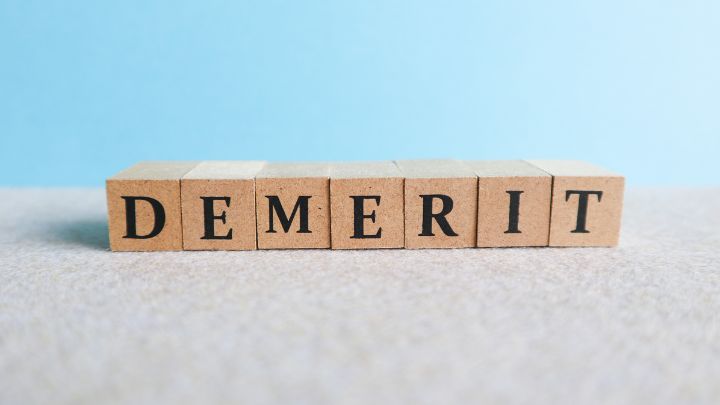
雇用契約書の電子化には、メリットだけでなくデメリットもあります。ここでは、雇用契約書を電子化するデメリットについて詳しく紹介します。
4-1. 導入・運用コストがかかる
雇用契約書を電子化するには、契約フローの見直しやシステムの導入・運用など、一定のコストがかかります。とくに小規模事業者など、雇用契約書を取り扱う機会が少ない場合、雇用契約書の電子化がコストに見合わない可能性もあります。あらかじめ目的を明確にし、費用対効果を検証したうえで、雇用契約書の電子化を進めましょう。
4-2. 相手の理解や同意が必要
紙での雇用契約が当たり前だと思っている従業員にとっては、雇用契約書の電子化に対して不満を感じる可能性があります。また、パソコンやスマートフォンなどの端末や、ネットワーク環境を整備していない労働者の場合、雇用契約の締結が難しくなる恐れもあります。雇用契約書を電子化する場合、事前に従業員の環境をヒアリングし、電子化しても問題ないか事前に理解や同意を得ることが大切です。
4-3. 操作ミスのリスク
雇用契約書を電子化すれば、簡単に書類をシステム上でやり取りすることができるようになります。しかし、操作ミスにより、間違った人に雇用契約書を送信したり、誤って契約ボタンをクリックしたりするリスクも発生しやすくなります。
あらかじめ想定されるトラブルを洗い出し、対応策を検討しておくことで、問題が生じても柔軟に対応することが可能です。また、雇用契約書を電子化するにあたって、従業員に対してセキュリティ教育を実施するのも一つの手です。
5. 雇用契約書を電子化する方法

先程の解説の通り、雇用契約書は必ずしも交付しなくてはならない書類ではありません。しかし、労使トラブルを防ぐために取り交わすのが一般的で、労働条件通知書とセットで作成するケースもあります。ここでは、雇用契約の手続きを電子化する方法について詳しく紹介します。
5-1. 「雇用契約書」と「労働条件通知書」をそれぞれ電子化する
雇用契約書だけでなく、労働条件通知書も電子化できるようになったため、それぞれの書類を別々に作成し、電子化して労働者に送付する方法があります。労働条件通知書と雇用契約書の目的にあわせて契約フローや内容を変えることで、自社のニーズにあわせて雇用契約の手続きを電子化することが可能です。
また、新たに採用される労働者にとっても、それぞれの書類が別々で送られてくるので、混乱しにくくなります。ただし、労働条件通知書と雇用契約書それぞれ別々で電子化する場合、書類の送付や保管といった事務負担が大きくなるので注意が必要です。
5-2. 「労働条件通知書兼雇用契約書」を電子化する
雇用契約書と労働条件通知書は、「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚の書類にまとめることもできます。内容が変わらないのであれば、労働条件通知書兼雇用契約書を電子化して送付・保管することで、事務負担を減らすことが可能です。
ただし、それぞれの書類の目的が伝わりにくくなる恐れもあるため、事前に自社の従業員や新たに採用する労働者に対して、労働条件通知書兼雇用契約書の目的や意味をきちんと周知しておきましょう。
5-3. 「労働条件通知書」のみを電子化する
雇用契約書の交付は法律で定められているわけではないため、雇用契約書は作成せず、労働条件通知書のみ電子化して送付する方法もあります。しかし、雇用契約書を交付しない場合、労働者が労働条件に同意した証拠が残らず、トラブルの原因になりかねません。そのため、雇用契約書も電子化して交付することが推奨されます。
6. 雇用契約書を電子化する際の注意点

雇用契約書を電子化する際にはいくつかの気を付けるべきポイントがあります。ここでは、雇用契約書を電子化する際の注意点について詳しく紹介します。
6-1. 電子帳簿保存法に対応できるように準備をする
雇用契約書に限らず、さまざまな書類を電子化して管理する場合、電子帳簿保存法を遵守することが求められます。電子帳簿保存法に対応しない電子データは、証拠として認められず、トラブルが起きた場合に不利益を被る恐れがあります。また、労働基準法などの法律の要件を満たさないこととなれば、懲役や罰金などの罰則が課せられる可能性もあります。そのため、雇用契約書を電子化する場合、電子帳簿保存法をきちんと理解し、それに対応したシステムを整備することが大切です。
6-2. 改ざんされないような体制を構築する
雇用契約書は、労働条件に関して労使双方が合意した証拠になります。もしも書き換えが起これば、契約書として機能せず、労使間でのトラブルに発展する恐れがあります。そのため、雇用契約書を電子化する場合、アクセス権限を適切に付与したり、監視機能を強化したりするなど、簡単に改ざんされないような体制を構築することが大切です。
6-3. 労働者側が雇用契約書をチェックしているか確認する
雇用契約書を電子化して送付しても、労働者が押印・署名し、労働条件に同意してもらわなければ、雇用契約は成立しません。たとえば、メールで雇用契約書を送付した場合、メールフィルター機能により正しく受信できず、内容を確認できていないケースもあります。
このような事態が生じないよう、雇用契約書を電子化して送付する場合、事前にメールフィルター機能を解除してもらうなど、手続きの注意点を伝えておくことが大切です。また、電子契約システムを導入して、雇用契約書の手続きフローを可視化し、なかなか労働者の同意が得られない場合、催促をおこなうのも一つの手です。
7. 雇用契約書を電子化する手順
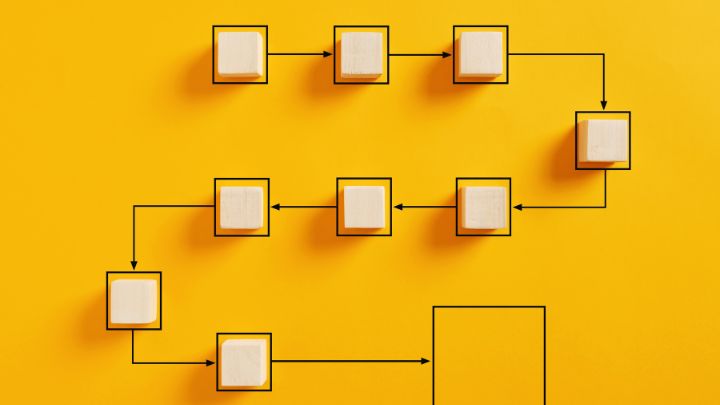
雇用契約書の電子化にはメリット・デメリットがあり、正しく電子化環境を整備しなければ、トラブルを招く可能性があります。ここでは、雇用契約書を電子化する手順について詳しく紹介します。
7-1. 現状を把握して課題を洗い出す
まずは現状の雇用契約の手続きを確認し、どのような課題があるのか確認しましょう。現状で問題なければ、雇用契約書を電子化しなくても問題ない可能性があります。問題点が明らかになれば、それに対するアプローチも具体化されやすくなります。
7-2. 雇用契約書の電子化手段を決める
雇用契約書を電子化する場合、労働条件通知書と雇用契約書別々で電子化するのか、労働条件通知書兼雇用契約書として電子化するのか、その方法を決めます。また、電子化手段には、次のような方法が考えられます。
- 雇用契約書をPDF化し、電子メールで送付する
- デジタル署名サービスを利用する
- クラウドサービスを契約する
いずれもメリット・デメリットがあるため、自社のニーズにあわせて最適な手段を選択することが大切です。
7-3. ITツールの無料トライアルを利用する
雇用契約書を電子化するにあたって、電子契約サービスやワークフローシステム、契約書管理ツールなど、ITツールが役立ちます。必要なITツールは、組織の規模や業務状況などによって異なります。まずはITツールの無料トライアルを積極的に活用してみましょう。無料トライアルであれば、自社のニーズにあわなければ、コストがかからず解約できるためリスクを抑えることができます。
7-4. 導入するシステムを決定する
無料トライアルを利用して複数のツールを比較したら、実際に導入するシステムを決定しましょう。ITツールを導入するにあたり、実際に運用できるまでに要する期間もチェックしておくことが大切です。
7-5. 雇用契約書の作成から交付までのフローを整備する
導入するITツールが決まったら、実際に雇用契約書を電子化する場合の作成から交付までのフローを整備しましょう。申請・承認の手続き方法や、雇用契約書の保管方法などを具体的に定め、ルール化してマニュアルにまとめておくと、スムーズに雇用契約書の電子化を進めることができます。
7-6. 従業員に周知する
雇用契約書を電子化するための手続きが整備できたら、従業員に周知しましょう。研修・セミナーなどを用意して、雇用契約書を電子化する目的やメリット、注意点などを事前に伝えておくことで、トラブルを未然に防ぎ、効果が得られやすくなります。
7-7. 実際に雇用契約書を電子化する
従業員に周知ができたら、雇用契約書の電子化の運用を開始します。運用を始めると、問題が発生することもあります。定期的にルールを見直し、改善をおこなうことで、効果的に雇用契約書の電子化を導入・運用することができるようになります。
8. 雇用契約書の電子化に活用すべきツールの選び方

実際に雇用契約を電子化する手段としては、電子契約サービスがおすすめです。電子契約サービスを利用すれば雇用契約書の電子化はもちろん、契約の締結からその後の保管までの全てに対応することができます。ここでは、電子契約サービスの選び方について詳しく紹介します。
8-1. 料金プラン
電子契約サービスを導入するには、導入コストがかかります。長く運用する場合、運用費用に注意しなければ、途中で契約をやめることになり、コストの無駄遣いになる恐れがあります。そのため、自社の従業員数や契約書数にあった料金プランを提供している電子契約サービスを選ぶことが大切です。
8-2. 機能
電子契約サービスには、さまざまな機能が搭載されています。どのような機能が必要か明確にしたうえで、過不足のない機能が搭載されたシステムを選ぶことが大切です。とくに、契約書の信頼性に関わる電子署名の種類には注意が必要です。また、後から機能を追加したり、変更したりできるか、拡張性もチェックしておくことが重要です。
8-3. 使いやすさ
電子契約サービスの操作が難しい場合、社内に定着せず、雇用契約書の電子化が進まない可能性があります。そのため、直感的に操作できる使いやすい電子契約サービスを選定することが大切です。また、外国人労働者を雇用する場合は、多言語に対応しているシステムを選ぶことも重要です。
8-4. 外部連携
電子契約サービスには、外部連携機能が搭載されていることもあります。外部連携機能を活用すれば、電子契約サービスと既存のサービスを紐づけて、データ入力・出力などを自動化し、業務を効率化することが可能です。ただし、外部連携できるサービスは限定されていることもあります。そのため、既存の契約書作成ツールや文書管理サービスなどと連携できるかチェックすることが大切です。
8-5. サポート体制
電子契約サービスを導入する場合、初期設定につまずき、実際に運用するまでに時間がかかってしまう可能性があります。また、運用している最中にトラブルが生じることもよくあります。サポート体制が充実している電子契約サービスを選べば、素早く問題を解決することが可能です。どのようなサポートが必要かを考え、自社のニーズにあったサポート体制を提供しているサービスを選びましょう。
関連記事:電子契約システムの導入メリットとは?注意点・代表的なサービスも紹介
9. 電子契約サービスで契約業務の工数削減を実現しよう!
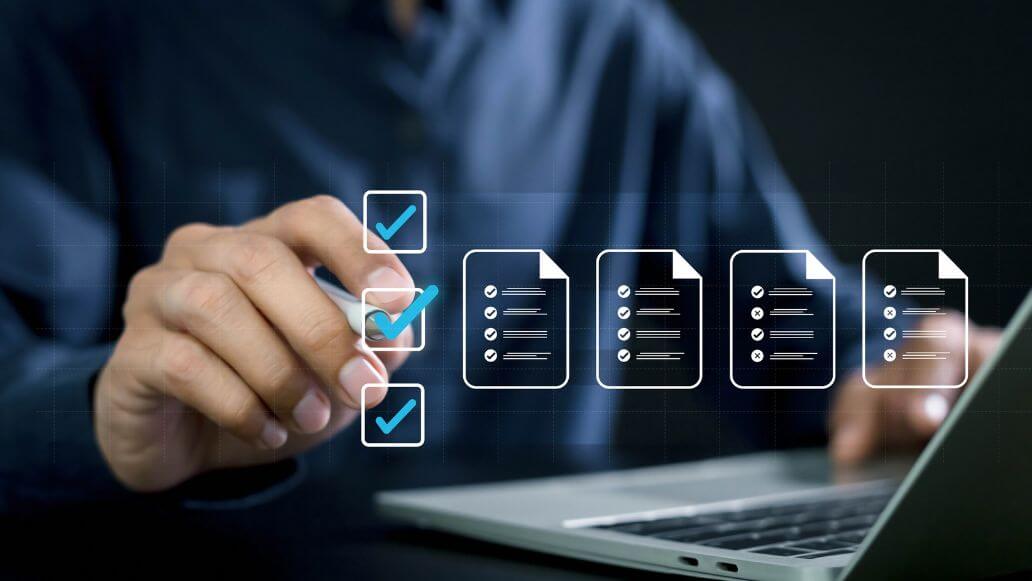 現在では雇用契約書だけでなく、労働条件通知書も電子化することができるようになっています。雇用契約書や労働条件通知書を電子化することで、雇用契約に関する業務を効率化することが可能です。雇用契約の手続きを電子化するにあたり、電子帳簿保存法を遵守したり、セキュリティ体制を整備したりするため、電子契約サービスの導入がおすすめです。
現在では雇用契約書だけでなく、労働条件通知書も電子化することができるようになっています。雇用契約書や労働条件通知書を電子化することで、雇用契約に関する業務を効率化することが可能です。雇用契約の手続きを電子化するにあたり、電子帳簿保存法を遵守したり、セキュリティ体制を整備したりするため、電子契約サービスの導入がおすすめです。
「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理業務を楽にしたいが、どうしたらいいかわからない…」
とお困りの方におすすめなのが、入社手続き・雇用契約の電子化です。入社手続き・雇用契約を電子化すると、入社手続きを郵送ではなくシステム上で行えるため、差戻や修正書類の回収にかかる時間や工数を削減することができます。
「便利なのはわかったけど、どうやって電子化すればいいか分からない」という方に向けて、
当サイトでは雇用契約・入社手続きを電子化する方法や、電子化によって入社手続き業務がどのように効率化されるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。