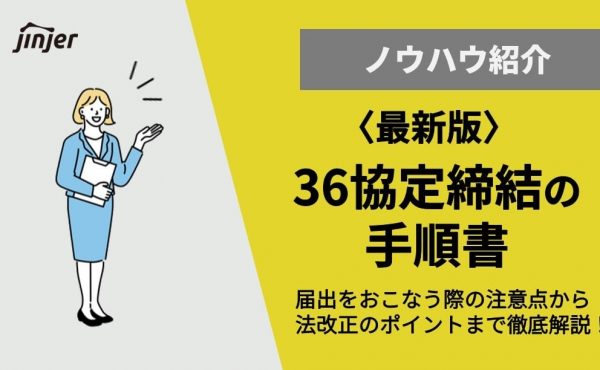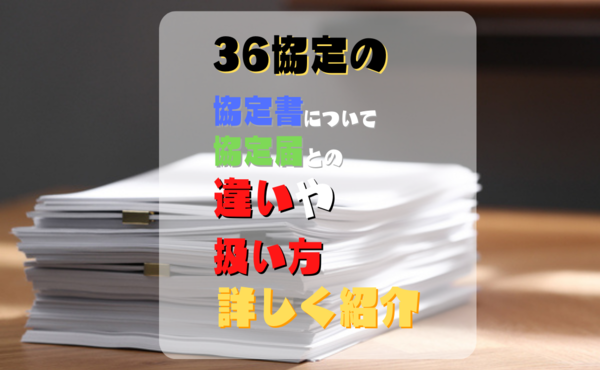
36協定を締結すると、時間外労働や休日労働が認められるようになります。36協定を結ぶ際は、協定書の作成や押印・署名が不可欠です。ただし、協定届のように、提出は不要です。この記事では、36協定の協定書とは何か、協定届との違いを踏まえてわかりやすく解説します。また、協定書と協定届を兼ねる場合の取り扱いについても紹介します。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 36協定の協定書とは?

36協定の協定書(36協定書)とは、36協定を結ぶ際に労使間の合意の証拠となる書類のことです。ここでは、36協定の定義や締結方法を説明したうえで、36協定書の必要性について詳しく紹介します。
1-1. 36協定とは?
36協定とは、時間外労働や休日労働が発生する場合に締結する労使間の協定のことです。労働基準法第36条に基づく協定であることから、「36(サブロク)協定」と呼ばれます。なお、時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働を意味し、休日労働とは、法定休日(週1日もしくは4週4日)に生じる労働を意味します。36協定を締結することで、時間外労働や休日労働が可能となります。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
1-2. 36協定の締結方法
36協定は、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合と締結をおこないます。該当する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者と36協定を結ぶことになります。36協定は、企業単位でなく、事業場単位で締結しなければなりません。また、36協定の締結をしても、届出をしなければ、36協定の効力は生じないので注意が必要です。
1-3. 36協定には協定書が必須!
労働基準法第36条に定められている通り、36協定は「書面」により締結をおこなう必要があります。この書面のことを「36協定書」といいます。36協定書は、使用者と労働者代表の双方が合意したことを証明する書類になります。
36協定書を用いず、36協定を結んだ場合、後に労使間でトラブルが生じる可能性があります。また、36協定が無効になる恐れもあるので、必ず36協定書を用いて36協定を結ぶようにしましょう。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
2. 36協定に記載すべき事項
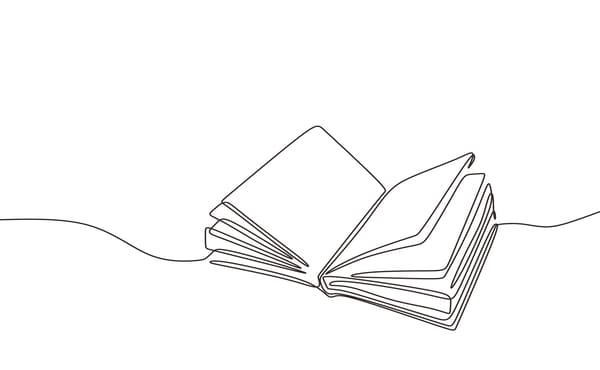 労働基準法第36条に基づき、36協定書に記載すべき事項は主に次の5つがあります。
労働基準法第36条に基づき、36協定書に記載すべき事項は主に次の5つがあります。
- 時間外労働や休日労働をさせる労働者
- 時間外労働や休日労働をさせる期間(対象期間)
- 時間外労働や休日労働をさせる条件
- 時間外労働や休日労働をさせる上限(1日、1ヵ月、1年それぞれ)
- 時間外労働や休日労働を適したものにするための事項
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
これら事項が正しく記載されていない場合、36協定が無効になる恐れもあるので、正しく36協定書のフォーマットを作成しておくことが大切です。ここからは、36協定書に記載すべきそれぞれ内容を詳しく紹介します。
2-1. 時間外労働や休日労働をさせる労働者
まずは、時間外労働や休日労働をさせる対象となる労働者についてです。業務の種類や労働者の数を明記します。記載する業務の種類については、設計や検査、経理事務といったようにその範囲を細分化することが必要です。
2-2. 時間外労働や休日労働をさせる期間(対象期間)
36協定を締結したとしても、原則として「月45時間・年360時間」の上限を超えて労働させることはできません。1ヵ月、1年がいつから始まるか明確にするため、36協定の起算日を明確にし、時間外労働や休日労働をさせる期間を特定する必要があります。なお、1年間の上限を定めなければならないため、対象期間は1年間が原則です。
関連記事:36協定の起算日はいつ?有効期間や給与締め日との関係性、変更できるかどうかも解説!
2-3. 時間外労働や休日労働をさせる条件
本来、法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に働かせたりすることは認められていません。36協定を締結・届出したからといって、どのような場合でも時間外労働や休日労働をさせられるわけではなく、例外を認めるための正式な理由が必要です。時期によって仕事数が大幅に前後するような業種であれば、「急な受注や納期の変更に対応するため」といった理由が必要になります。
なお、36協定の時間外労働の上限「月45時間・年360時間」をどうしても超えてしまうケースがあるかもしれません。そのような場合、特別条項付き36協定を締結・届出することで、臨時的な事情がある場合に限り、上限を延長させることができます。ただし、この場合も無制限に時間外労働や休日労働ができるわけではありません。なぜ36協定の上限を超えなければならないのか、臨時的な事情をきちんと36協定書に記載しておくようにしましょう。
関連記事:36協定の特別条項とは?新様式の記載例や上限を超えた場合の罰則を解説
2-4. 時間外労働や休日労働をさせる上限(1日、1ヵ月、1年それぞれ)
時間外労働や休日労働のできる上限は、36協定を締結する際に、労使間で合意に至った時間・日数となります。ただし、36協定には時間外労働や休日労働の上限が設けられているので、それを超えた上限を設定することは認められません。
36協定を結ぶ際には、1日、1ヵ月、1年それぞれの時間外労働の上限を定める必要があります。また、休日労働ができる日数も定めなければなりません。このように、時間外労働や休日労働をさせる上限も、36協定書に明確に記載することが大切です。
関連記事:36協定の休日出勤に必要な届出とは?上限回数や代休・振替休日との関係性も解説!
2-5. 時間外労働や休日労働を適したものにするための事項
労働基準法施行規則第17条に基づき、36協定書には次の「厚生労働省で定める事項」を明記する必要があります。
- 36協定の有効期間
- 36協定の対象期間の起算日
- 特別条項に係る要件を満たすこと
- 一般条項の上限を超えて働かせる場合の条件
- 一般条項の上限を超えた労働者に対する健康および福祉を確保するための措置
- 一般条項の上限を超えた場合に適用される割増賃金率
- 一般条項の上限を超えて働かせる場合の手続き
36協定書には、有効期間を定めなければなりません。対象期間が1年であることや、上限の見直しは定期的にすべきであることから、有効期間も1年間とすることが望ましいとされています。
有効期間を過ぎると、36協定も無効になります。そのため、有効期限が切れる前に、再び36協定を締結し、再度届出をおこなうことが大切です。なお、「4.」~「7.」の項目については、特別条項の定めをしない場合、記載しなくても問題ありません。
3. 36協定書と36協定届の違い

36協定の協定書と協定届について、内容の違いはほとんどありません。しかし、目的や提出の必要性などに違いがあります。ここでは、36協定書と36協定届の違いについて詳しく紹介します。
3-1. 作成の目的
36協定書と36協定届は内容がほとんど同じになるケースもあります。しかし、それぞれの書類を作成する目的が異なります。労働基準法第36条に基づき、36協定を書面で締結するために作成するのが協定書です。一方、36協定届は、使用者と労働者側で締結した協定を、管轄の労働基準監督署に提出するために作成するものです。
つまり、労働基準法第36条の規定を満たすために作成するのが「36協定書」です。そして、36協定の効力を生じさせるために作成するのが「36協定届」です。このように、36協定書と36協定届は作成する目的に違いがあります。
3-2. 押印・署名の有無
36協定書の場合、使用者と労働者側で合意したうえで締結したことを証明するため、前者と後者の双方の押印や署名が必要です。一方、36協定届の場合、以前までは押印・署名が必要でした。しかし、2021年4月から36協定届が新様式になり、押印・署名が不要になりました。36協定届の用紙は、厚生労働省や労働基準監督署のホームページから入手することが可能です。すでに押印・署名欄は削除されているため、押印や署名を設けたい場合、自社で記入欄を設ける必要があります。
関連記事:36協定の押印・署名が廃止に?不要になった背景や注意点を解説!
3-3. 提出の必要性
36協定書は、労働基準法により作成が義務付けられていますが提出不要です。一方、36協定届は作成するだけでは意味がありません。36協定届を所轄の労働基準監督署に届け出て受理されることで、36協定は効力を持ちます。このように、36協定書と36協定届は提出の必要性も異なるので注意が必要です。
3-4. 【ポイント】36協定書と36協定届は兼ねることができる
36協定書は36協定届と兼用することが可能です。また、36協定書を作成する際、36協定届のフォーマットを用いることができます。ただし、36協定書と36協定届を兼ねる場合、36協定届にも労使間で合意したことの証明となる押印・署名が必要になるため注意が必要です。
昨今の働き方改革関連法を受けて、他にも36協定で改定された箇所があります。刷新された36協定書の様式や特別条項の上限規制を、詳しくご存じでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、法改正後の36協定の解説から、締結までの手順をわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。法改正に対応して適切に36協定の届出をしたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
4. 36協定書を作成する流れ

36協定書を作成しない場合、従業員に時間外労働や休日労働をさせることはできません。残業や休日出勤が発生するのであれば、36協定書の作成は必須ともいえます。ここでは、36協定書を作成する流れについて詳しく紹介します。
4-1. 36協定書の原案を企業側が作成しておく
36協定を結ぶ際、労使で話し合うことが不可欠です。しかし、36協定書の必要事項については、法律で定められています。そのため、事前に36協定書のひな形・テンプレートを作成しておき、原案も作っておくと、スムーズに36協定の締結ができます。
4-2. 労働者側の代表者を選出する
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)、過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と締結する必要があります。過半数組合は、すべての労働者(パート・アルバイトなども含む)の過半数で組織されていなければなりません。
また、過半数代表者は、労働者の過半数を代表しなければならず、投票・挙手など民主的な方法で選ばれる必要があります。会社側が一方的に指名した場合には、過半数代表者と認められません。なお、管理監督者は、過半数代表になれないため注意が必要です。労働者側の代表者が正しく選出されていない場合、36協定を締結し、届出をしても、当該36協定は無効になる恐れもあるので気を付けましょう。
関連記事:36協定における労働者代表の選出方法とは?管理職や出向者の取り扱いも解説!
4-3. 36協定の内容について双方で話し合い押印・署名をする
正しく労働者側の代表者を選出できたら、当該労働者代表と話し合い、36協定の内容を細かく定めましょう。36協定の内容がまとまったら、その内容を36協定書に記載し、最後に労使双方の押印・署名をすることが大切です。
5. 36協定書の書き方のコツ

36協定書に関しては、特別に指定されている用紙やフォーマットがあるわけではありません。法律で定められた記載事項について抜けや漏れがなく記載されていれば、自社独自の様式を用いても問題ありません。
しかし、36協定書をゼロから作成しようとする場合、ハードルが高く、時間や手間がかかります。36協定書のひな形やテンプレートはインターネット上で取得できるので、それを活用し、自社の仕様にあわせてカスタマイズするのがおすすめです。
先述した通り、36協定書と36協定届は兼用できます。そのため、厚生労働省が提供する36協定届のサンプルを用いるのも一つの手です。また、記載例を参考にすれば、抜けや漏れなくスムーズに36協定書・36協定届を作成することができます。36協定届のひな形は、以下からダウンロードできるので、ぜひ参考にしてみてください。
【36協定届のフォーマット】
・時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項):様式第9号
・時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項):様式第9号の2
6. 36協定書の作成・提出に関する注意点

36協定書の作成や提出にはさまざまな気を付けるべき点があります。ここでは、36協定書の作成・提出に関する注意点について詳しく紹介します。
6-1. 36協定書の内容は従業員に周知しなければならない
36協定書は、協定届のように提出は不要です。しかし、労働基準法第106条「周知義務」にあるように、36協定の内容についていつでも確認できるよう、見やすい場所に掲示したり、備え付けたりして、従業員に周知する義務があります。36協定書の内容がきちんと周知されていない場合、36協定が無効になったり、労働基準法違反により罰則が課せられたりする恐れもあります。36協定を結んだら、その内容を適切に周知するようにしましょう。
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)、第三十六条第一項、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
6-2. 36協定書を作成しても届出なければ違法になる
36協定書を作成しても、36協定届を所轄の労働基準監督署に提出しなければ、36協定の効力は生じません。36協定届を提出せず、時間外労働や休日労働をさせた場合、労働基準法に則り、懲役や罰金といったペナルティが課せられる可能性もあります。36協定書は提出不要ですが、36協定届は必ず期限までに提出しなければならないので注意が必要です。
関連記事:36協定届の提出期限とは?有効期間や提出忘れ時の罰則についても解説!
6-3. 36協定書は適切な期間の保管が必要
36協定書や、36協定届の控えは、労働関係に関する重要な書類に該当します。そのため、労働基準法第109条により5年間の保存が義務付けられています。なお、労働基準法第109条には経過措置が設けられており、当面の間は3年間の保管でも問題ありません。ただし、いつ経過措置が終了するかはわからないため、可能であれば5年間保存しておくことが推奨されます。36協定書の保管期間の起算日は「その完結した日」になります。36協定書の作成日からではないので注意が必要です。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
7. 36協定を締結する際は協定書と協定届を正しく作成しよう!

36協定の協定書とは、使用者と労働者側の双方が合意した証となる書類のことです。協定書は協定届のように提出不要です。ただし、押印・署名が必要になるなどの注意点もあります。とくに、36協定書と36協定届を兼ねる場合は気を付けて作成や提出をおこなうことが大切です。36協定書と36協定届の違いを理解し、それぞれについて正しく扱うようにしましょう。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。