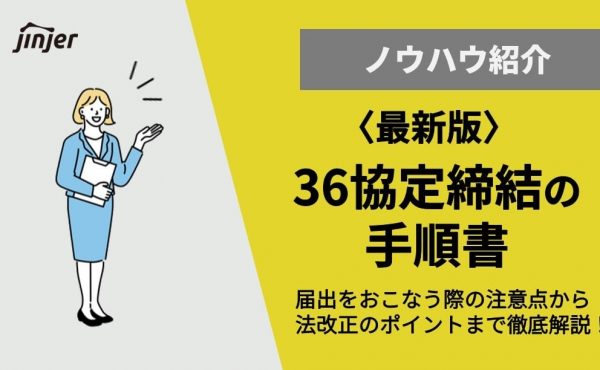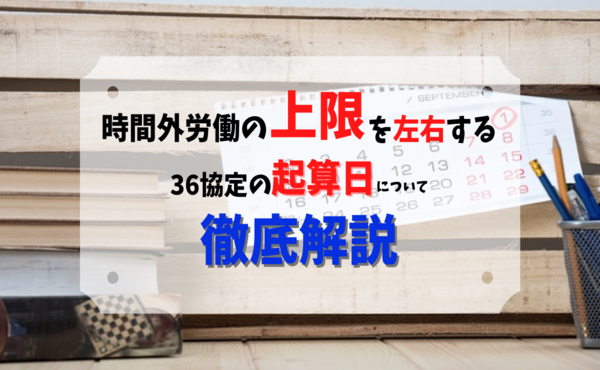
日本の労働基準法では、法定労働時間が定められており、この時間を超えて労働を命じる場合は36協定の届出を提出する必要があります。この36協定には、さまざまな取り決めがあるため、知らないままでいると法令違反をしてしまうかもしれません。
本記事では、時間外労働の上限を左右する36協定の起算日について徹底的に解説します。
関連記事:36協定について、わかりやすく解説!|特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 36協定の起算日とは

36協定における起算日とは、「36協定が適用され始める日のこと」を指します。36協定では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間、1年360時間と定めています。いつから制度が適用されたかによって1年で360時間以内におさめられるかが変わり、その基準となる開始日が36協定の起算日です。
36協定のなかでは、法定労働時間を定めているだけでなく、届出を提出することでこの時間を超えて働くことを認めるルールが設けられています。こういった制度の有効期間の1日目が36協定の起算日です。
もし、5月1日が起算日なのであれば、36協定に基づいて法定労働時間を超えたり休日に出勤したりして労働できるのは5月1日からとなります。
1-1. 起算日は36協定届に記載する必要がある
36協定の届出には、起算日について記入する項目が設けられています。届出を作成する際に決定した起算日を正確に記載しましょう。起算日を決めるルールはとくに設けられていないため、企業側で決定できます。
ただし、起算日が中途半端な日付だと業務を複雑化させる恐れがあるため、企業では賃金の計算期間の起算日と合わせているケースが多いです。
また、起算日を変えることは原則として認められません。雇う側と労働者との間で話し合ったうえで適切な起算日を決めることが大切です。
1-2. 36協定の有効期限についても要注意
加えて、36協定については有効期限についても注意しなければいけません。その対象期間は1年としているため、期限が近づいた際は過ぎてしまう前に再度届出を提出する必要があります。こういった点を踏まえても、わかりやすいように年月日で管理することが推奨されます。
このように36協定を締結・継続するためには、起算日をはじめとする手続きを正確におこなう必要があります。しかし具体的な提出方法や上限規制に対応する方法がわからず不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 当サイトでは、36協定の概要や提出方法を順を追ってわかりやすく解説した無料で配布しております。 36協定自体や届出の方法を確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
2. 派遣社員の36協定の起算日は?

派遣社員についても、法定労働時間を超えて労働をおこないたいのであれば、36協定の届出を提出する必要があります。ただし、派遣社員についてはその企業に所属する正社員とは扱いが異なるため注意しましょう。
2-1. 36協定の締結は派遣元とおこなう
派遣社員の36協定の届出の提出は、派遣先ではなく、派遣元の使用者がおこないます。つまり、派遣先の事業や業務を踏まえたうえで、派遣元が36協定の届出を提出しなければいけません。
派遣社員に適用される起算日は受け入れた日ではなく、派遣元と結んでいる36協定に記載された起算日ですので、十分に注意しましょう。
36協定の届出の様式は、派遣先となる企業の規模や事業・業務の内容に合わせて最適なものを選ぶ必要があります。派遣元はこういった点を踏まえて36協定の届出を用意することが大切です。
また、年次有給休暇の管理については派遣元のルールに基づいておこなう必要があるので、こちらも一緒にチェックしましょう。
関連記事:派遣社員に対して適用される36協定について残業時間や上限を正しくチェック
2-2. ただし、使用者は派遣先になる
派遣社員の36協定は派遣元と結ぶものですが、使用者は派遣先になります。36協定違反が発覚した場合、違反責任を負うことになるのは使用者です。使用者である派遣先が時間外労働を命じていない場合でも、使用者として罰せられることもあります。
派遣社員を受け入れる企業の多くで、タイムシートや勤怠管理システムを導入しているのは、こうした理由により勤怠管理を客観的におこなうことが必要だからです。
3. 36協定の起算日と有効期間・対象期間の違い
36協定には起算日のほか、有効期間と対象期間の2つがあります。混同されやすい部分ですが、有効期間や対象期間は別のものですので注意が必要です。
| 用語 | 概要 |
| 有効期間 | 締結した36協定が効果を持つ期間 |
| 対象期間 | 実際に時間外労働を命じられる期間 |
有効期間は、36協定の内容が効果を有している期間のことを示します。あくまでも有効な期間というだけで、有効期間いっぱいまで時間外労働を命じられるわけではありません。
実際に時間外労働を命じられる期間は、対象期間です。有効期間内の対象期間であれば、36協定に則った時間外労働を命じることができます。
3-1. 36協定の有効期間は1~3年の間で決める
36協定の効果がある有効期間は、最短で1年、最長で3年の間で決められます。1年よりも短い期間や、3年以上の期間を設定しても、原則として届出は認められません。
1~3年の期間内であれば企業独自の期間を決定できますが、36協定は1年に1度の見直しと届出が推奨されています。そのため、有効期間も1年とすることが一般的です。
3-2. 対象期間は1年間と定められている
36協定の対象期間は、例外なく1年間と定められています。これは36協定の内容を1年に1度は見直し、労働基準監督署長に再届出をすることが推奨されているからです。
時間外労働時間や休日出勤の日数は、有効期間ではなく、こちらの対象期間で計算します。
4. 36協定の起算日の変更は可能?

36協定の起算日は、基本的に有効期間中での変更ができません。設定する際は自由に決められますが、一度適用されてしまうとなかなか変更ができないルールとなっています。
これは、起算日を変えたいのであれば、今適用されている36協定を破棄する必要があるためです。改めて締結する際、前のものを引き継ぐことはできないため、変更前の36協定はもともとなかったものとして扱われてしまいます。
変更が簡単に認められてしまうと、1年における時間外労働の限度を正しく決めて制度を適用することが難しくなってしまいます。よって、36協定の起算日は変更が原則できないのです。
4-1. 36協定の起算日を変更できるケース
基本的には36協定の起算日は変更できませんが、例外として認められるケースがあります。それは、事業所を複数持っている企業が全社で36協定の対象期間を統一させたい場合です。このようなケースに限って、破棄と再締結が認められます。
しかし、このように破棄と再締結が認められる場合でも、最初に設定した起算日に基づいた対象期間に従って、法定労働時間を超えて労働ができる月数を引き続き守らなければいけません。
5. 36協定の起算日を決めるときのポイント

最後に、36協定の起算日を決めるときのポイントを確認しておきましょう。
5-1. 36協定の起算日は企業が自由に決められる
36協定の起算日は、企業側が自由に決められます。しかし前述の通り、決めてからの変更は容易ではありません。安易に起算日を決めてしまうと、あとから不都合に感じられる場面が出てきてしまう可能性があります。そのため、36協定の起算日は慎重に決めなければいけません。
5-2. 賃金支払いの起算日と合わせるのがおすすめ
36協定の起算日を決める際は、賃金の支払いに関する起算日と合わせたほうが管理が簡単になります。その理由の1つとして、以下のようなケースを想定してみましょう。
ある従業員を1カ月の間に法定労働時間を60時間超えて働かせたとします。法定労働時間が1カ月の間で60時間を超えていると、雇っている側は割増金額を支払わなければいけません。これは、労働基準法で定められている義務の1つです。
給与の支払日は企業によってそれぞれ決められています。割増金額を給与に適用する際、月々の時間外労働時間を算出して台帳にまとめておくことが必要です。
もし、36協定の起算日と賃金の支払いに関する起算日が異なっている場合、給与を支払うその期間においては60時間を超えてはいないものの、36協定の起算日に基づくと超えてしまっているというケースが発生するかもしれません。
このことから、36協定の起算日と賃金の支払いに関する起算日を統一させておくことで、管理が簡単になるメリットがあるのです。
6. 36協定の起算日は慎重に決定しよう!

36協定の有効期間は1カ月となっています。有効期間が切れてしまう前に再度届出を提出しなければ、制度が適用されていない期間が生まれてしまうかもしれません。この間に時間外労働や休日出勤をしてしまうと、労働基準法に違反してしまうことになります。
また、1カ月あたりに60時間を超えて時間外労働をする場合、割増金額を支払う義務が発生しますが、これについての管理も36協定の起算日に影響してきます。36協定の起算日は、管理しやすいようにほかの起算日と合わせて管理しておくとよいでしょう。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。