
現在日本は、高齢者の全人口を占める割合が世界でもトップクラスとなっており、医療費は年々高騰しています。健康保険料が高くなることで、負担を感じている事業所も多いでしょう。
そのため、社会保険の対象外である非正規雇用で労働力を賄っている企業も増加してきました。今回は、社会保険の加入を選択できる任意適用事業所とはどのようなものなのか、手続き方法などを詳しく解説します。
関連記事:社会保険の種類ごとの特徴や加入条件をわかりやすく解説
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険の任意適用事業所とは?強制適用事業所との違いを紹介

社会保険の適用事業所は、強制適用事業所と任意適用事業所の2つに分けられます。ここでは、2つの違いについて確認しておきましょう。
1-1. 強制適用事業所
強制適用事業所とは、社会保険への加入が強制される事業所のことです。株式会社などの法人化している事業所は、従業員の人数に関係なく強制適用事業所となります。また、農林水産業など一部の事業を除き、常に5人以上の従業員を雇用している個人事業主も強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。
強制適用事業所において以下のような従業員を雇用する場合は、社会保険に加入させる必要があります。
- フルタイムで働く従業員
- 週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムで働く人の4分の3以上の従業員
また、パートやアルバイトなどの短時間勤務の従業員については、以下の条件を満たす場合に社会保険に加入させなければなりません。
- 従業員数51人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
なお、以前は「従業員数101人以上」という基準がありましたが、2024年10月に社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51人以上の企業で働くパートやアルバイトも加入対象となりました。
1-2. 任意適用事業所
任意適用事業所とは、法律上は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務がないものの、事業主の申請と従業員の過半数の同意により、加入することが可能な事業所です。たとえば、美容院や会計事務所など、一部の個人事業主が該当します。任意適用の認可を受けて加入した場合は、強制適用事業所と同様に、一定の条件を満たす従業員全員を社会保険に加入させる必要があります。
2. 任意適用事業所として社会保険に加入すべき?

前述の通り、強制適用事業所の条件に該当しない場合、法律上は社会保険に加入する義務はなく、無理に社会保険に加入する必要はありません。社会保険に加入しなければ、事業主は保険料を折半して支払う必要がないので、出費を抑えられるなどのメリットがあります。
しかしその場合、従業員は国民健康保険や国民年金に原則として加入しなければなりません。従業員の負担が多くなり、福利厚生が充実していないということで、人材を確保しにくいというデメリットが生じます。
今後もさらなる事業展開をしていこうとする企業なら、社員の補充が必要となってくるでしょう。求職者は保険料を安く抑えられるような職場、すなわち福利厚生が充実しているところを探すのではないでしょうか。社会保険を適用している事業所へ、求職者が流れてしまうことも増えるかもしれません。
事業主が負担すべき社会保険料を抑えたい場合は、業種別で結成されている健康保険組合に加入するとよいでしょう。協会けんぽに加入するケースが多いものの、業種別の組合の場合だと協会けんぽよりも保険料を抑えられる可能性があり、結果として事業主の負担軽減につながることもあります。
したがって、将来性を考える場合には、強制適用事業所の条件にあてはまらない場合でも、任意適用事業所として社会保険に加入する方が望ましいでしょう。
関連記事:社会保険の加入条件は?保険の種類ごとに条件を詳しく紹介
3. 任意適用事業所として社会保険に加入するための手続き
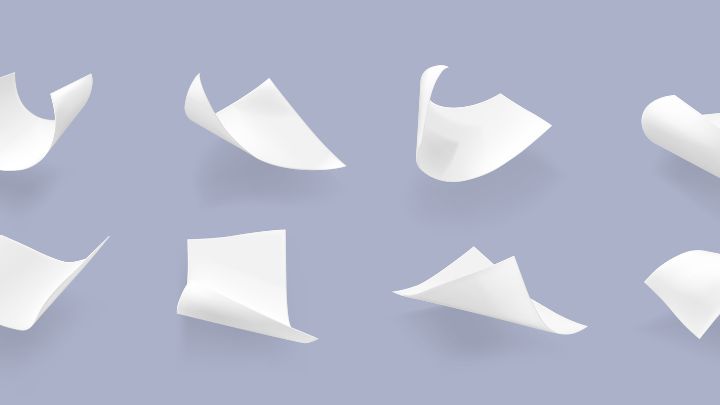
任意適用事業所として社会保険に加入するためには、まず従業員の意見を聞かなければなりません。従業員全体の半数以上の同意を得られたら年金事務所に申請の手続きをおこなうことができ、そのうえで厚生労働大臣の認可を得られれば加入できます。
任意適用を受ける際は、事業所を管轄している年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」を提出しなければなりません。事業所の名称や所在地などを正しく記入し、提出しましょう。
3-1. 任意適用申請書の書式
任意適用申請書の書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。以下のような項目を記入して提出しましょう。
- 事業所所在地
- 事業所名称
- 事業主氏名
- 事業主住所
- 給与計算の締切日
- 給与支払日
3-2. 添付書類
任意適用申請書と一緒に、以下の書類を提出する必要があります。
- 任意適用同意書
- 事業主世帯全員の住民票原本
- 公租公課の領収書(原則1年分)
任意適用同意書とは、従業員の半数以上の同意を得たことを証明する書類です。住民票原本は、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを準備しましょう。公租公課の領収書は、コピーでも問題ありません。
任意適用同意書の書き方
任意適用同意書の書式も、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。以下のような内容を記載して提出しましょう。
- 事業所の名所
- 事業所の所在地
- 使用される者の数
- 同意する者の氏名
- 同意する者の生年月日
- 同意する者の住所
3-3. 申請方法
申請方法としては、窓口への持参、郵送、電子申請があります。電子申請であれば、わざわざ窓口へ出向く必要がなくなるため、手間や交通費・郵送費用を削減できます。24時間365日いつでも申請できるので、スムーズに手続きを進められるでしょう。
関連記事:社会保険の手続きにはどのような種類がある?従業員の加入要件についても解説!
4. 任意適用事業所として社会保険に加入するメリット

任意適用事業所として社会保険に加入することで、以下のようなメリットが得られます。
4-1. 健康保険に加入するメリット
社会保険適用事業所でない職場で働くと、従業員は健康保険に加入できず、基本的に国民健康保険に加入することになります。国民健康保険には扶養という概念がないため、家族単位での加入ができません。そのため、個人単位で保険料が計算されることになり、特に家族が多い場合には経済的負担が大きくなることもあります。
一方、任意適用事業所として社会保険に加入すれば、従業員は健康保険に加入でき、一定の条件を満たす家族は扶養に入ることが可能です。パート・アルバイトなどでも一定以上の所得がある場合を除き、家族全体が扶養家族として健康保険に加入できます。さらに、従業員は保険料を事業主と折半することになるため、負担が少なくなります。
従業員にとってのメリットが大きくなれば、企業の魅力向上につながるため、人材確保もしやすくなるでしょう。
4-2. 厚生年金に加入するメリット
厚生年金に加入すると、国民年金のみよりも将来受け取れる年金を増やすことができます。さらに、一定の条件を満たす配偶者は保険料を納付しなくても、国民年金第3号被保険者として国民年金の恩恵を受けることが可能です。
また万が一、被保険者が亡くなってしまった場合、配偶者や子などは遺族厚生年金を受け取れる可能性もあり、国民年金よりも保障の範囲が広くなります。
4-3. 労災保険に加入するメリット
社会保険に加入していない場合、従業員が不幸にも勤務時間や通勤しているときに重大な事故に巻き込まれた際には、使用者責任として事業主が治療費や賃金などを支払わなければなりません。しかし労災保険に加入していると費用の全額を国が肩代わりしてくれるので事業主の負担が減ります。
このように、各種社会保険に加入するメリットは多く、採用においてもプラスに働く可能性があります。
ただし、従業員を社会保険に入れる際の手続き(資格取得届の提出)は従業員分の書類を集める必要があるため工数が多く、さらに提出期限が決められているため注意が必要です。
当サイトでは、上述した社会保険手続きの内容や、手続きの際に気を付けるポイントなどを解説した資料を無料で配布しております。社会保険手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
5. 任意適用事業所として社会保険に加入するときの注意点

任意適用事業所として社会保険に加入すれば多くのメリットが得られますが、注意点もあります。ここでは、任意適用事業所として社会保険に加入する際の気を付けるべき点について詳しく紹介します。
5-1. 全従業員が加入することになる
社会保険は事業所単位で加入する制度であるため、加入要件を満たす従業員全員が加入の対象となり、特定の従業員だけを除外することはできません。
任意適用事業所として社会保険に加入するには、被保険者となるべき従業員の半数以上の同意が必要ですが、手続きが完了すれば、同意していなかった従業員も加入対象になります。そのため、社会保険のメリットや負担の仕組みについて事前に丁寧な説明をおこない、理解を得ることが重要です。
5-2. 簡単に脱退することができない
任意適用事業所として社会保険に加入した場合、簡単に脱退することはできません。脱退することは可能ですが、加入時の過半数同意よりも条件が厳しくなっています。
具体的には、従業員(被保険者)の4分の3以上の同意を得てから、手続きを進めなければなりません。また、任意適用の取消が認可されれば、脱退に同意しなかった人も、社会保険被保険者としての資格を喪失することになり、従業員の不満につながる恐れもあるので、慎重に対応しましょう。
参照:任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき|日本年金機構
6. 任意適用事業所として社会保険への加入を検討しよう!

今回は、任意適用事業所の概要や、社会保険に加入するメリットを紹介しました。強制適用事業所の条件に該当しない場合、社会保険に加入する義務はありませんが、任意適用事業所として社会保険に加入することでさまざまなメリットを得られます。今後従業員を増やすことを考えているなら、任意適用事業所として社会保険への加入を考えてみるとよいでしょう。
従業員の半数以上の同意があれば、任意適用事業所として社会保険への加入申請ができます。申請には、任意適用同意書、事業主世帯全員の住民票原本、公租公課の領収書などの添付書類も必要です。優秀な人材を確保するためにも、手続きの準備を進めましょう。
>>編集部オススメの記事はこちら<<
▶【社会保険】手続きで迷わない手順マニュアル!
「社会保険」を手続きする流れについて、わかりやすくご紹介します。
▶『社会保険』に含まれる「健康保険・厚生年金」を徹底解説!
社会保険の中の「健康保険」と「厚生年金保険」についてご紹介します。
▶『社会保険』に含まれる「労働保険」を徹底解説!
社会保険に含まれる「労働保険」についてご紹介します。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









