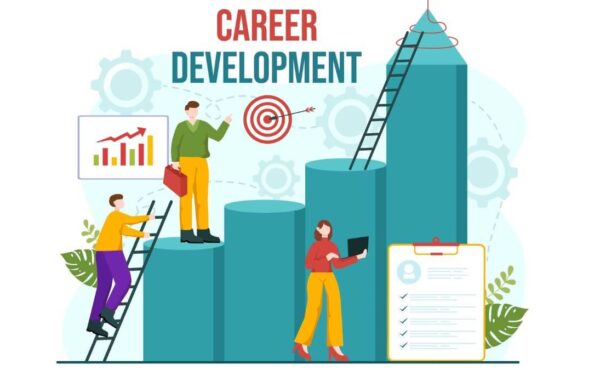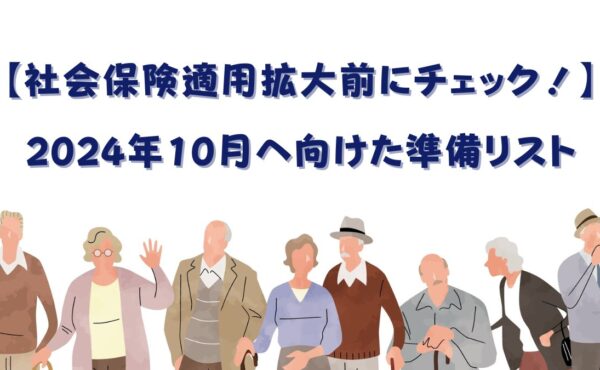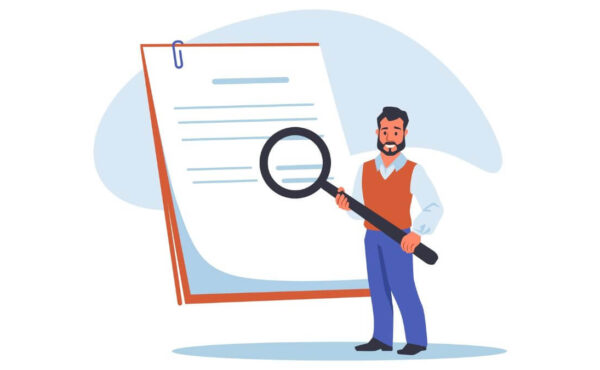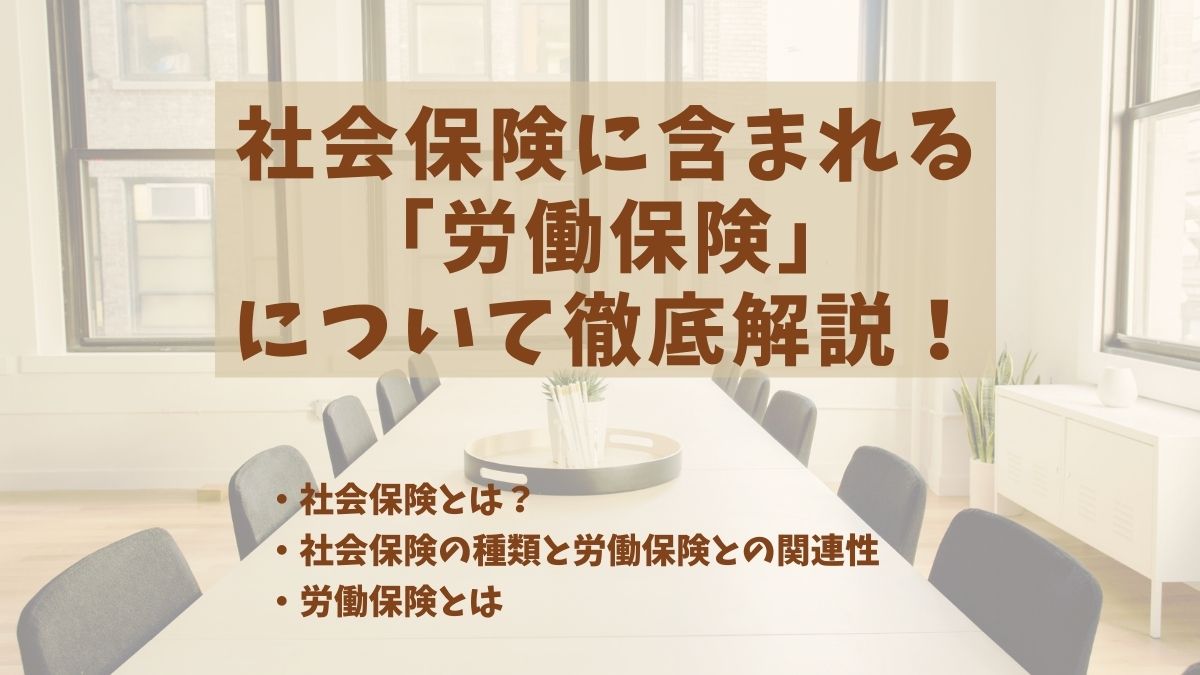
社員が入社したとき、退社するとき、労災が起こったときなどに、どのような保険がどのように適用されるか、しっかりと理解していない担当者は意外に多いかもしれません。
出勤・退勤時に起こる事故や、過労からくる病気など、昨今はイレギュラーな事件がいつ発生してもおかしくないので、保険に関する早急な対応が担当者に求められています。
そこでこの記事では「社会保険」に含まれる「労働保険」にフォーカスを当てて徹底解説していきます。労働保険について理解を深めたい人は、ぜひチェックしてください。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 労働保険とは?
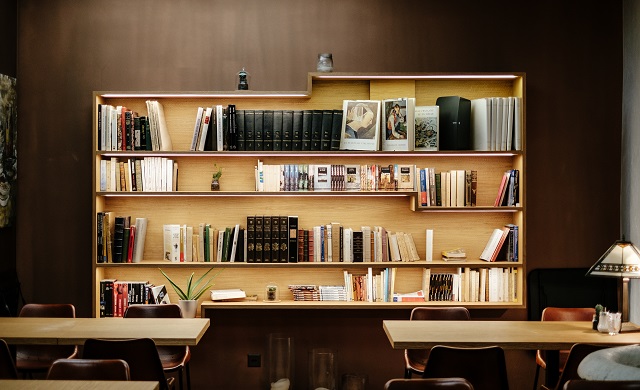
労働保険とは、労働者の雇用の安定や生活の保護を目的として、国が運営している社会保険制度のひとつです。労働保険には労災保険と雇用保険の2つが含まれており、労働者を1人でも雇用している場合は加入しなければなりません。
労災保険については、正社員はもちろん、パートやアルバイトなどの短時間労働者も加入対象となります。雇用保険については、労働時間など一定の条件を満たす労働者が加入対象となります。
1-1. そもそも社会保険とは?
日本国憲法第25条の生存権には、「健康で文化的な最低限度の生活」を国民に対して保障すること、つまり社会保障が定められています。
社会保障は、国民が生活をするうえで直面するであろうリスクに備えて事前に保険に加入し、国民の生活を保障する制度です。
このような社会保障制度は、社会保険、公衆衛生、社会福祉、公的扶助の4つの柱で構成されています。運営主体は国、または地方公共団体であり、保険対象者は強制加入が原則とされています。
1-2. 社会保険の種類

社会保険には、以下のような種類があります。
また、広い意味で言われる「広義の社会保険」と、狭い意味で言われる「狭義の社会保険」の2つが存在します。「広義の社会保険」とは、労働保険と社会保険の2つを合わせたものです。「狭義の社会保険」は健康保険、厚生年金、介護保険を指します。使われる場面によって意味合いが異なるため注意しましょう。
2. 労働保険の種類

労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の2つで構成されています。労働基準法をベースに、労働者をサポートし、生活を保障する目的でつくられました。
労災保険と雇用保険では、加入対象や保険料などが異なります。ここでは、労災保険と雇用保険の特徴について詳しく解説しますのでチェックしておきましょう。
関連記事:労働保険とは|労災保険と雇用保険の制度概要と仕組み・加入手続きを詳しく解説
2-1. 労災保険(労働者災害補償保険)について
労災保険とは、仕事が原因で怪我をしたり病気になったりした際に、労働者本人やその家族を保護するための保険です。労災保険に加入することで、働けなくなったときの休業給付や、病院で治療を受けるときの療養給付などを受けられます。
労災保険の加入対象
労災保険は、労働者が個人で加入するものではなく、法人、個人事業主など雇用者側が加入することによって、すべての労働者に対して適用される保険です。ここでの労働者には、正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態に関わらず、すべての人が含まれます。
労災保険の保険料
労災保険の保険料は、雇用者側の全額負担となっているので、労働者側は保険料を支払う必要はありません。したがって、雇用者が労働者の賃金から労災保険料を天引きする行為は違法です。また、労働者が業務中に事故にあった場合は、病院からの診断書や請求書、必要な書類を労働監督基準署に提出する必要があります。
2-2. 雇用保険について
雇用保険とは、労働者が仕事を失ったときや介護・育児のために休業したときに、一定の給付を受けられる制度です。雇用の安定を目的としており、教育訓練を受けた場合にも給付を受けられます。保険適用時に給付される金額や期間については、会社在籍時の給料、在籍期間、失業した理由などによって異なります。
加入対象や保険料は以下の通りです。
雇用保険の加入対象
雇用保険の加入対象には正社員だけではなく、所定労働時間が週20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みのあるパートやアルバイトなども含まれます。[注1]
要件を満たす場合は、日雇労働者や季節労働者も加入対象となるため忘れずに手続きをおこないましょう。
[注1]厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
雇用保険の保険料
雇用保険の保険料は、労働者と会社の双方が支払うことになっており、毎月の負担は1,000円前後です。雇用保険料率は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建築の事業の3つで分けられており、年度ごとに改定されます。最新の保険料率は厚生労働省が公開しているためチェックしておきましょう。[注2]
もし従業員を各種社会保険に加入させることを決めているのであれば、それぞれの提出期限を守って対応しなければなりません。
各種社会保険の提出期限の違いや本記事でも触れた社会保険料の種類に関しては、当サイトで無料配布しております「社会保険手続きの教科書」で分かりやすく解説しておりますので、社会保険の理解について不安な点があるご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!
3. 労働保険に加入するための手続き
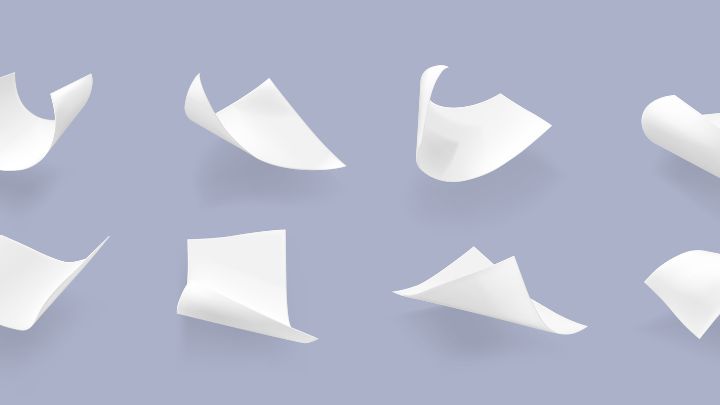
ここでは、労働保険に加入するための手続きについて解説します。
3-1. 労災保険に加入するための手続き
労災保険に加入するために提出すべき書類は以下の通りです。
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書
上記の書類を準備して、所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
保険関係が成立した日の次の日から10日以内に提出しなければなりません。概算保険料申告書は、保険関係が成立した日の次の日から50日以内でよいのですが、忘れないようまとめて提出するのがおすすめです。
3-2. 雇用保険に加入するための手続き
雇用保険の対象となる労働者を採用した場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までにハローワークへ提出する必要があります。
手続きが完了すると「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」が交付されるため、忘れずに労働者本人へ渡しましょう。
また、初めて労働者を雇用する場合は、以下の書類を提出しなければなりません。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 保険関係設立届
- 概算保険料申告書
4. 労働者を守るために労働保険の加入手続きを進めよう!

今回は、社会保険に含まれる労働保険について詳しく説明しました。労災保険や雇用保険は、労働者やその家族の生活を守るための重要な制度です。病気や怪我、失業などの際に必要な給付を受けられるよう、しっかりと手続きをおこないましょう。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。